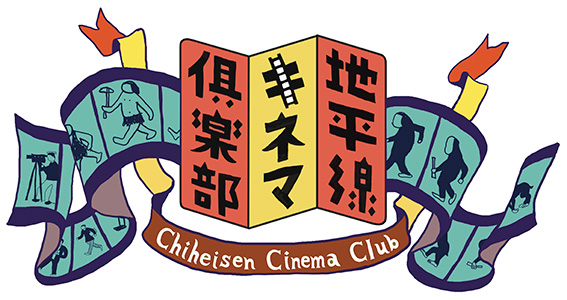★地平線通信541号(2024年5月15日発行)より転載(筆者:笹谷遼平)
■去る3月30日は私にとってはじめての地平線報告会でした。高沢進吾さんの35年間アラスカに通われたお話で、「刺激的」という軽はずみな言葉では到底集約できない熱量と情報量で、私はひたすらに畏敬の思いばかりを抱きました。なかでもオムツ交換やトイレの介助をしていた子供が今は立派な大人になっているとのお話に、生活の機微、そして35年の重さを感じずにはいられませんでした。何故そのような熱量を保てるのかという問いに、高沢さんは簡潔に「面白いから。行くたびに発見があるから」と返答されました。その颯爽とした言葉とともに、飛行機に乗ってこの場からアラスカに出発してしまうのではないかと、そんな絵さえ想起させられました。同時に、主語が「自分」ではなくなったときに、弱くなるものは確かにあると、一人納得しました。思えば、主語が自分のままもの作りを続けることが、一番難しいのかもしれません。映画の場合は観てくださる人がいてようやく完成するものだと思っているので、自分が作りたいものと人が観たいもの、そのバランスの取り方にいつも悩まされています。
◆2011年の東日本大震災と原発事故より以前、私はサブカルチャーを追いかけては映像作品を作っていました。秘宝館、蝋人形職人、道祖神のお面のドキュメンタリーなど、今書いていても「?」と思うモチーフばかり追いかけていましたが、私としてはサービス精神というか、エンタメを提供しているつもりでした。すでに優れた作品が世に沢山あるのだから、私はカウンターカルチャーを走るんだと格好をつけていた時期でもあります。そんなとき3.11がありました。遅すぎるかもしれませんが、25歳の私は、目の前の世界と土台の世界が砂上の楼閣だったと、いかに今まで飼い慣らされていたのかを、大いに思い知りました。同時に、このまま消費社会に乗っかったままでいいのかという危機感がつのり、人から評価されなくてもいいから主語が自分の作品を作りたい、真正面から映画と取っ組みあいたい、命(自然)に触れたい、私はそのような思いに駆られたのでした。そこで1トン近い大きい馬が1トンほどの重いソリをひき競走する「ばんえい競馬」という生々しく力強いモチーフに出会いました。

◆2013年2月20日の夜明け前、私は北海道帯広競馬場(ばんえい競馬)の練習場に立っていました。マイナス25度。マフラーで口元を隠すと息でまつ毛が凍り、目が開かなくなってしまいます。すべてが凍るなか、ソリをひいた馬と人が行き交い、馬の汗や息の熱が煙のように立ちのぼり、朝日が透けて輝く神秘的な当地の「当たり前」の光景に、都会人の私は言葉を失いました。それが映画『馬ありて』の、はじめての撮影でした。
◆ドキュメンタリー映画には大きく二つのパターンがあると思っています。一つ目は、対象を映画の枠に収め構成する方法(歴史上の人物を対象にしたテレビ番組を思い浮かべていただくとわかりやすいかもしれません)、二つ目は、先天的に映画に適した対象(人)が映画のなかで花開く方法です(映画『ゆきゆきて神軍』などはその極致です)。拙作『馬ありて』はそのどちらでもないように思います。馬と人の営みと、主語を自分に、ということだけをブラさずに、あとは感覚のまま美しいと思うもの、裸でゴロリと寝そべっているような「当たり前」の現実を切り取ることに、私は腐心しました。対象もばんえい競馬から北日本に広がり、伐採した木を馬と運ぶ「馬搬(ばはん)」、馬を売買し生計を立てる「馬喰(ばくろう)」、馬への信仰を起源とした「オシラサマ」などを撮らせていただき、馬を通して自然と人間の関係を考えました。

◆特に馬搬は、山の斜面に丸太がゴロゴロと転がり、一歩間違えると大事故に繋がってしまう大変危険な現場でした。馬搬の親方・見方さんは手綱一本と声だけで馬とコミュニケーションをとり、木を運んでいきます。ときには怒号が飛び交い、見方さんは馬をいさめました。他人から見ると厳しく映るかもしれません。しかし彼と馬の関係は、かわいい家族だというただ平和なものだけではなく、人間と馬の命懸けの真剣勝負のうえに仕事や生活が成り立っているという、とても身体的な関係でした。実際、見方さんは馬搬の仕事中に何頭もの馬を事故で亡くしています。そこにあるのはキレイ事や西欧的倫理ではなく、「自然のなかで生きるために生きる」ということだったのではないか、そんな風に思っています。
◆京都の郊外、向日市の新興住宅地で生まれ育った私は、都会人の部類に属すると思います。自然に対する身体能力を養わず、資本主義社会が提供する娯楽と情報を食べて生きてきました。『馬ありて』という映画は、どうしようもない現代人の自分の更生と学びの旅でもありました。馬ではなく牛歩ですが、これからもその旅を続けていきたいです。では6月1日、地平線キネマ倶楽部にて。お待ちしております。[笹谷遼平]