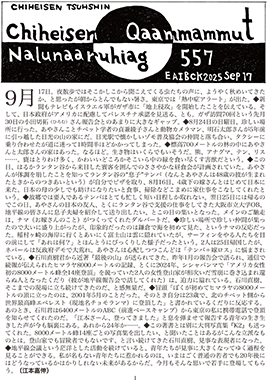
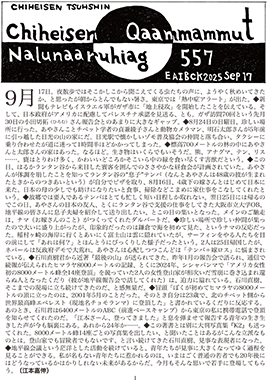
9月17日。夜散歩ではそこかしこから聞こえてくる虫たちの声に、ようやく秋めいてきたか、と思ったが朝からとんでもない暑さ。東京では「熱中症アラート」が出た。
◆新聞もテレビもイスラエル軍がガザ市に「地上侵攻」を開始したことを伝えている。そして、日本政府がアメリカに配慮してパレスチナ承認を見送る、とも。ガザ訪問70回という先月30日の小田切拓(ひろむ)さん報告会とのあまりに大きなギャップ。
◆8月24日の日曜日、珍しい場所に行った。「あやさん」ことチベット学者の貞兼綾子さんと動物カメラマン、明石太郎さんが5年前に引っ越した日光の山の家にだ。日光駅で懐かしいゾモ普及協会の仲間と落ち合い、タクシーに乗り合わせたが道に迷って1時間半ほどかかってしまった。
◆標高700メートルの林の中にあやさんと太郎さんの家はあった。なるほど。生き物はいくらでもいそうだ。熊、アナグマ、テン、リス……。鹿はとりわけ多く、かわいいどころかそこいら中の緑を食い尽くす害獣だという。
◆この日、はるかランタン谷から来日した賓客を囲んでのささやかな昼食会が計画されていた。あやさんが体調を崩したことを知ってランタン谷の“息子”テンバ(なんとあやさんは48歳の彼が生まれたときからのつきあいという)が自分でビザを取り、8月16日、4歳下の嫁さんとはじめて日本に来た。日本の母の少しでも助けになりたいと食事、掃除などこまめに家仕事をこなしてくれたという。
◆故郷では要人であるテンバはとても忙しく短い日程しか取れない。翌日25日には帰るのでこの日、あやさんの日本の友人、とくにランタン谷で支援の仕事をしてきた大阪市立大学OB、地平線の皆さんに息子夫婦を紹介して送り出したい、とこの日の集いとなった。メインのご馳走は、ナマ(お嫁さんのこと)がつくってくれたダルバートだ。
◆珍しい場所で珍しい仲間が集ったので大いに盛り上がったが、印象的だったのは鎌倉で海を初めて見た、というナマの反応だった。稲村ヶ崎の海岸に行くとあいにく富士山は雲に隠れていたが、サーフィンをやる人たちを目の前にして「あれは何?」とほんとうにびっくりした様子だったという。2人は25日帰国したが、ネパールは反政府デモで大荒れ。あやさんは心配しつつこんどは「テンバ+嫁ロス」に悩まされている。
◆石川直樹君から近著『最後の山』が送られてきた。昨年1月の報告会で語られ、通信で続報が伝えられたヒマラヤ8000メートルの記録、とくに2024年、シシャパンマで「「アメリカ女性初の8000メートル峰全14座登頂」を競っていた2人の女性登山家が相次いだ雪崩に巻き込まれ還らぬ人となったくだり(彼が地平線報告会で話してくれた)は、迫力に溢れている。石川直樹、そこまでの現場に立ち続けてきたのだ、と感無量だ。
◆冒頭「ぼくが初めてヒマラヤの8000メートルの頂に立ったのは、2001年5月のことだった。そのとき自分は23歳で、北のチベット側から世界最高峰エベレスト(現地名チョモランマ)に登頂した」と書かれているくだりに反応する。あのとき、石川君は6400メートルのABC(前進ベースキャンプ)から東京の私に携帯電話で登頂を知らせてくれたのだ。「江本さーん、登ってきました」と息を弾ませて報告する青年の生き生きした声が今も脳裏にある。あれから24年か……。
◆この著書とは別に大判写真集『K2』も送ってくれた。8000メートル峰14座ごとの写真集を出したい、と聞いたことはあるがこんな立派なものとは。登山家でも冒険者でもないです、と言い続けてきた石川直樹、見事な表現者になった。
◆地平線会議という茫洋とした活動を続けていると、青年たちが見事に大きくなってゆく過程を見ることができる。私が名もない青年たちに惹かれるのは、いまはごく普通の若者でも20年後にはどうなっているかはかりしれない未来があるからだ。今月もそんな思いで若手に登場してもらう。[江本嘉伸]
今月は報告会レポート延期します
今月の「報告会レポート」ですが、事情あって来月以降に延期します。内容が非常に微妙で十分ではないレポートのまま掲載するわけにはいかない、という判断ですのでどうかご了解ください。[E]
■このごろ、日々の暮らしのなかで、ひんぱんにガザのことが頭に浮かぶようになっている。食事をすれば「こんなの食べられないだろうな」と思ったり、シャワーやトイレでも「水さえ自由に使えないんだよな」と。自分が傍観者であるだけでなく、加害者の側に組み込まれているのではと思うと、申し訳ない気持ちでいっぱいになる。
◆小田切さんに、ガザはイスラエルにとって“打ち出の小づち”になっていると聞いて、パレスチナ支援のNGOに寄付している友人にそれを話してみた。支援さえも占領と破壊を下支えする構造の一部になってしまうと。破壊すると国際社会から援助が入って復興、また破壊してと繰り返しながらイスラエルはむしろ得していると。友人は「じゃあ、どうしたらいいんだろうね」と困った顔でつぶやいた。まさにそれ、私も困っている。答えが出ない。でも考えるのをやめたら終わりだ。この不条理な現実を問い続けること。それは私たちが今できる抵抗なのだから。[高世仁(今回の報告会にて小田切さんと対談)]
■8月30日の報告会では、参加者に噛みついてくれるように依頼し、こちらも敢えて辛辣な表現を交えながら返答した。なぜそんなやり方をしたのか。その理由は、パレスチナ問題をいくらか知っている人ほど、通説以外を受け入れようとしないからだ。特に問題なのは「イスラエル人にも良い人がいて、彼らを支えることこそが、平和への第一歩になる」という考え方だ。
◆シオニズムとは、「パレスチナ」の地のすべてを領有し、その人口のすべてをユダヤ教徒にすることを目標とする考え方だ。シオニスト左派の語る「平和」も、その延長線上にある。「パレスチナ」の殆どを領有し、パレスチナ人は最小面積の中か、海外に放逐するのが彼らの方針だ。
◆考えてもみて欲しい。ホロコーストによる彼らの犠牲に対する責任がパレスチナ人にはないことは容易に理解できるはずだ。今回でいえば、10.7以降、イスラエル領内に入って軍事力を行使したガザ地区住民が皆無といえること、ガザには戦車も戦闘機もないこと。日本を含む国際社会こそが、ガザ地区を大きな収容所にしていることも。
◆人類史の汚点とさえいえそうな現状だからこそ、重要なのは「解決とは何か」を考えることだ。事態の構造を理解し、正確な数字を把握する。関係する国、機関が何をしているのか、本来何をすべきなのかを整理する。そして処方箋を作り、それに基づき行動するしかない。
◆闇雲に「イスラエルを批判」し「ガザ地区住民のために寄付」しても、平和にはならない。往々にして、事実は通説とは異なるものだ。意図的に作り上げられるものでもある。パレスチナ問題については、まずは通説を忘れて欲しい。
◆そこでフリーランスにできることといえば、事実をこれでもかと積み上げること。心の中に杭を打ち込むことくらいしかない。だから今回も、「嫌ーな話」にしようとした。
◆時代が、大きく変わろうとしている。パレスチナは、その最先端事例ではないか。9月9日に、イスラエルがカタールを空爆した。その前日にエルサレムでパレスチナ人が、ユダヤ教徒を銃撃した。個人的には、後者の方を注視している。この続きは、また、「嫌な話」をする会で。[小田切拓]
■このたび、拙著『シリアの家族』が、「第23回開高健ノンフィクション賞」を受賞させていただくこととなりました。身に余る光栄です。『シリアの家族』は、2011年以降、内戦状態となったシリアやその周辺国などを舞台に、人々がどのように故郷での暮らしを失い、異郷に生きてきたのか。難民になるということ、故郷を失うということがどういうことなのかを描いた作品です。それは同時に、シリア難民の一人である夫を持つ私自身の、セルフドキュメンタリーでもあります。
◆この作品は、私の人生のなかでも二度と出会えないだろう、特別な一冊だと感じています。アサド政権下、まだ小さな二人の子供たちをトルコに残し、危険を覚悟し、単独で夫の故郷パルミラへと向かった2022年の取材。また、妻の立場としては非常に傷ついたものの、表現者の立場からはワクワクしてしまった第二夫人騒動。何より、一生に一度経験できるかどうかというシリアの政権崩壊を目の当たりにし、夫とともに取材できた巡り合わせを、まるで夢を見ていたかのように思い返すのです。(第二夫人騒動については繰り返されるかもしれませんが)まさに一生のうち、たった一度経験できるかどうか、といえる瞬間をいくつも経験し、それらを作品中にしっかりと落とし込むことができました。
◆その執筆には4年ほどかかりましたが、特に記憶に残っているのはコロナ禍の日々です。2020年以降の新型コロナの流行時は、仕事もなくなり、貯金も尽き、さらに夫は働いておらず、保育園にも子供を預けられませんでした。そんななか、2人の小さな子供を電動自転車の前と後ろに乗せ、Uber Eatsの配達員をし、日々の生活費を稼ぎながらこの原稿を書きました。
◆常に綱渡りのような経済状態のなか、幼い子供を抱え、執筆とはまったく別の収入で家計を支えねばならない私にとっては、書き続けることこそが最も困難なことでした。ですので、開高賞受賞という連絡をいただいたときは、なんて素晴らしいことが起きたのだろう!と感銘を受けつつ、それ以上に、この作品を世に送り出せることが、自分にとって最も素晴らしいことなのだと、感慨深いものがありました。「良いノンフィクションとは、どれだけ自分の内面をさらけ出すことができるかだ」と教えてくださったのは江本さんです。また良い作品とは、その作品を通して書き手が変化を経験するものだ、とも教えていただきました。
◆その言葉を、私はこの作品を描くにあたり常に意識していました。思えば、実は前作の『人間の土地へ』(集英社インターナショナル)でも開高賞に応募し(2017年)、最終作品にはノミネートされたものの、受賞を逃したことがありました。四谷の荒木町のマンションにあった江本さんの家で受賞の知らせを(お掃除をしながら)待たせていただいたのですが、その際、良きノンフィクションとは何かを教えていただいた記憶が蘇ります。
◆当時、江本さんの家では飼い犬の麦丸がまだ生きており、長男のサーメルは床を這って、人間モップ状態になっていたのでした。あれから7年。子供たちは成長し、私もまた、シリア難民の取材をなんとか続けてきました。そして、世界情勢の変化の中でシリアのアサド政権が崩壊するという時代の激動とともに、私自身の人生の激動も、この本に詰め込みました。
◆作品を描きながら気づいたのは、登場人物たちが、私とシリアとを繋ぎ、フォトグラファーとしての道や、アサド政権崩壊後まで続く取材へと導いてくれたのだ、ということです。その中には、すでにこの世を去った人物も少なくありません。しかし作品を綴ることで、私は彼らに何度も出会い、その存在を感じることができました。
◆これまで不安定な経済状況のなか、情熱をもって取り組んできたシリア難民の取材。それをひとつの作品として世に送り出すことができること。そして栄誉ある賞として評価いただいたことを、ただただ嬉しく思います。いつも私の活動を応援くださる地平線の皆様、本当にどうもありがとうございます。この受賞を今後の活動の糧とし、これからもシリアの人々の生き様を淡々と見つめていきます。
◆『シリアの家族』の発売日は11月26日の予定です。ぜひ手に取っていただけましたら幸いです。そしてこの本を通し、多くの方が、新しいシリアと繋がっていくことを願っています。[小松由佳]
■2005年、ロスアンジェルスからニューヨークまでランニングで横断した。5400キロの間、一歩も抜けていないと言い切れたとき、マイイベントは気持ちよく終わった。時間が流れ、心の奥底に微かな火がともった。それが何かには気づいていた。北米ランの続きがやりたいのだ。
◆3月31日に退職して4月10日に日本を離れる。今回の旅は20年前の北米ランと今とが一本の線で繋がっていく形にしたい。日本から太平洋を越えて北米。北米から大西洋を越え、ユーラシア大陸最西端のポルトガルのロカ岬から再スタートする。できればそのまま日本までランニングで帰ってくる。
◆旅の準備を始めて驚いたのが、ヨーロッパまでの東回りの航空券の値段だった。近所の旅行会社で聞くと、なんと80万円!。いくら航空券が値上がりしたとはいえ、それはないだろ。面白いのは需要の多い西回りルートなら13万円で買える。要は「一本の線」のこだわりを捨てれば安く行けるが、そこは譲れない。何か策はないかと、かつてNYに住んでいた仲間に相談すると、格安航空券の組み合わせ方法を教えてくれる。パソコンと格闘し手に入れたチケットは、成田〜ホノルル〜NY〜リスボン。これで11万円なり。その仲間から、ハーレムの格安宿情報も入る。この時点で旅の質が変わってしまっていると痛感する。すべてがネットなのだ。苦手なネットとなんとしてもお友達にならねばなるまい。
◆今回の計画だが、やってみたいことが6つあった。NYで英語で講演をしてみる。昔働いていた弁当屋の現状を見る。初めて大西洋を越える。ユーラシア大陸最西端のロカ岬に立つ。巡礼路ポルトガルの道で聖地サンチャゴ・デ・コンポスティーラまで歩く。地の果て、フィステーラに行く。フィステーラはロカ岬からは1000キロほど。全体の計画の中では一部に過ぎない。だが、その先は遠すぎて、何も見えなかった。もともと今にしか生きていない感じがあり、遠くを見るのは苦手だ。無駄なく行動するには計画を分析して細分化していくほうが効率的だ。とはいえ見えないものは見えないし、やりたいのはプロジェクトではなく旅である。スケジュール化して達成する形ではなく、気分で形が変化していく自由さが欲しい。
◆いよいよ走り旅の再開。リスボンの空港に着いたら、最初に携帯をネットに繋げ、とアドバイスを受けていたが、いきなり躓く。空港内の書店でリスボンの地図を購入して、予約している宿を目指す。自分の走り旅の物差しは20年前の北米横断。たった数キロ歩いただけで、その物差しが使えないのがわかる。理由は地形が複雑、坂が多い、道が垂直に交わらない。確認しないと進めない状況がやたらと多い。これでは紙地図がないと、まるでわからない。20年前、北米横断ランでロスを出発したとき、目指す町は北北東だから……、って感じで進んでいた。今思えばウソだろって思う。ともかくSIMである。宿に着き、宿の近くの携帯ショップでSIMを手に入れる。これで現在地と地図を確認できるはずだ。
◆リスボンについて3日目。最初の目的地のロカ岬に向かう。距離は50キロ。50なら一日で行けそうな気がする。もっと情報が欲しくて調べると、岬の周辺には宿がない。おまけに天気予報は強風、雷雨。情報を集めれば集めるほど不安が増してくる。初日から野宿はイヤなので目的地は35キロ先の観光地シントラとする。北米では平均50キロペースだった。あれから20年が過ぎ、現在61歳。どの程度自分が衰えているかは行動してみないとわからない。
◆スマートウオッチをランニングにセットして走り……出せない。歩くのも厳しい坂道が続く。雨が降り出しレインコートを着る。すぐに雨が上がる。脱ぐ。また雨がくる。分岐が現れ、立ち止まって携帯で道を確認する。5分後、また判断に迷う道が現れる。「走る」など、とてもできない。Googleナビが不自然な細い道を示す。逆らいたくなるが、そもそも画面が指す北と感覚の「北」とが違う方向だ。
◆それでもリスボンからロカ岬まで往復100キロを歩くと、少し自信がついた。こうやって積み重ねていけばいつかはたどり着けるのだ。それは今まで何度も経験している。さてプレランニングは終わり。いよいよ巡礼路である。巡礼路に入って2日目。道端で休憩していると昨夜の巡礼宿にいた3人が声をかけてくれた。イギリス人とアメリカ人とオーストリア人。それぞれが一人旅の巡礼者だった。その夜の宿も決まっていなかったので彼らについていく。心から助かった、と思えた。団体行動が苦手なので一人で旅してきたが、このチームは不思議なほどうまくいって楽しい日々だった。歩くペースの違いからチームは解散したが、オーストリアのローレンスとは、以後何度も会い、今でも連絡がつく。
◆チームが解散したあとは一人で黙々と歩き続け、1000キロでついに「地の果て」フィステーラに着いた。ここが巡礼路の完全な終点で、その先には海しかない。来たかった場所は聖地サンチャゴではなくここだと思った。大西洋を見下ろす崖に腰を下ろし大きくため息をつく。全身の力が抜け立ち上がれなくなった。出発時にあげた6つの夢は、たった1か月ですべてかなってしまった。夢が現実となった今、これから何を目標にして進めばいいのかわからなくなってしまった。
◆ここから先は次のステージとなる。巡礼路の終点で巡礼路の物語は終わる。これ以上続けることは掟破りの異端となる。でも地の果ては僕にとっては通過点だ。これからはただ一人、道を逆行する。もう同じ道にいても違う存在だ。それから1800キロ。何万人もの巡礼者とすれ違った。一日中挨拶し続け、一日中「どこにいくのだ」「サンチャゴはあっちだ」と言われ続ける。巡礼者の共通の話題は、「どこから来た?」「何キロ歩いた?」だ。毎日繰り返されるその話題は人種も年齢も性別も越える。そしてシンプルに距離が長いほうが尊敬される。1000キロを超えたあたりから、僕はほぼ無敗となった。
◆7月6日。4本の巡礼路をつないでフランスのルピュイに到達する。EUに滞在できる90日ギリギリ。距離はロカ岬から2800キロ。ここでフィステーラに着いたときと同じように、また燃え尽きてしまった。ともかく早くEUの外にでないといけない。どこを次の起点にするかは重要なポイントだ。にもかかわらず考えることそのものがイヤで、セルビアのベオグラードに逃げる。そこに岡村隆さんの訃報が飛び込んできた。ベオグラードについても、何もやる気にならず、ドナウ川をただ眺めていた。体も疲れているが、心も疲れている。もう回復を待つしかない。フランスとセルビアはまったく違う世界で順応するのにも時間が必要だった。
◆ベオグラードのドミトリーは同室で、ロシア人とウクライナ人の若者が仲良く遊んでいた。角ばって古ぼけた町には、うっすらとアジアが混じっている。少し気持ちが回復してくると景色も見え始め、刺激に満ちた国にいるとエネルギーも充電されてきた。これからのことを考えると、出来るだけEU圏に近い西の端からスタートするほうが、次に来るときに抜けた区間を埋めやすい。それはボスニアのバニャルカと決め、バスで移動する。
◆バスの窓から景色を観察していると絶望的な気分になった。路肩がまったくない道を高速並みのスピードで車が走っている。実際、ボスニア、セルビアは厳しかった。路肩のない国道を避けて山に入るとGoogleマップは動作せずに山奥に放置される。山にはクマもいるし、地雷原も残っていた。巡礼路を歩いていたときは厳しいと思った。だが巡礼路を出るともっと厳しい。巡礼路はさまざまな力で守られていると感じる。ボスニアである日、右目の中に何かデキモノがあるのに気づいた。これは日本に帰って検査したいが、こんな中途半端な状態では帰れない。
◆ボスニア人、セルビア人は会ってみると驚くほど親日で優しく、嫌な思いをしたことは一度もない。道端の人はすべて応援してくれ、何度もいきなり食べ物をもらったりもした。ボスニア、セルビアでの歩きは800キロ。セルビアの先はブルガリア、ルーマニア、ギリシャと、EU諸国が立ちはだかり、どこにも抜けられない。次の手はイスタンブールに飛ぶしかないのだが、北マケドニアに興味がわきバスでセルビアから移動。首都のスコピエからイスタンブールに飛ぶ。そこからギリシャ国境に近いエデェルネにバスで移動。イスタンブールまで350キロを歩いた。
◆イスタンブールからさらにトルコの東側を歩き、10月10日に再び、フランスかセルビアに戻るつもりだった。しばらく気持ちがそっちに向くのを待っていたが、ボスボラス海峡より東のトルコがいつまでたっても心に浮かんでこない。自分の中で消化しきれない旅が、先の道を阻んでいる。同時にすべて自分で決断できる自由にも疲れてしまった。ずっと気になっていた眼のこともあり、一度日本に帰ろうという気持ちになった。
◆この5か月で、ポルトガルのロカ岬からイスタンブールまで歩いた距離は約4000キロ。その中で走れたのは10キロほどだ。走るつもりで始めた旅だが、歩いているうちに、もうどっちでもよくなった。自分の本『ロスからニューヨーク走り旅』を読み直すと、同じことが書かれている。歩くと時間がかかり過ぎるから「走る」と。自分にとって大事なのは何かに夢中になっている時間で、「何か」は別になんでもよいのだと思う。
◆一応の目標であったイスタンブールには着いた。着きはしたが、こんな中途半端な状態で終わるわけにはいかない。途中の空白エリアであるフランスのルピュイからボスニアのバニャルカまで1500キロと、セルビアのニーシからトルコのエデェルネまでの500キロは近いうちに埋めて、一本の線を伸ばしていきたいと思っている。[新しく「歩き旅人」の看板もあげた、坪井伸吾]
■「アフリカ開発会議(TICAD)」は1993年に始まり今回で9回目を数える国際会議。この会議が始まったきっかけは、1989年に就任した南アフリカ共和国のデ・クラーク大統領がアパルトヘイト撤廃に向けた改革を打ち出し、1990年には黒人解放運動指導者のネルソン・マンデラを釈放したことにあるそう。思い返せば1989年はベルリンの壁が崩壊して冷戦が終結し、世界史の大きな転換点となった年でした。そうした新たな事態のなかで、日本はアフリカとどのようにかかわるべきか、アフリカ諸国に対して積極的にかかわっていく姿勢を示そうと、第1回目のTICADが企画されたのでした。そして、2003年の第3回TICADからは、緒方貞子JICA理事長主導で「人間の安全保障」が基調テーマになり「一人一人が、一人一人を幸せにする国際協力」が打ち出されました。
◆私たちが初めてTICADにかかわったのは2013年。アフリカをテーマにした日本主導の国際会議と知って、「参加させてください」と外務省を訪れたところ、なんと漁業や水産セクターはまったく議題に入っていない。スタートから20年間、漁業は一度も議題にのぼらず、食料といえば農業だけとのこと。海に囲まれたアフリカの会議なのに、魚が好きな国民が多いのに、なぜ漁業がテーマにのぼらないのですかと聞けば、「これまで言いだす人がいなかったから」。
◆驚きながらも、文句より実践と考え直し、サイドイベントの枠組みで自主シンポジウムを企画。そして様々な苦労の末にセネガル、ギニア、コートジボワールから漁村女性を招いてTICADデビューを果たしました。当初、テーマは海賊問題や水産資源の持続的利用にしようかと考えましたが、やはり女性たちの交流が大切、海を越えて浜の女性たちが交流し励ましあおうと決めました。
◆宮城や茨城、千葉、神奈川の浜から横浜に集まってもらい、アフリカ女性と一緒に市内の小学校を訪問して「おさかな授業」を開いたり、おしゃべりしたり。アフリカのかあさんたちは、羽田空港に裸足で降り立つワイルドな人もいたけれど、皆さんとってもチャーミング。その一方、シンポジウムでは「アフリカの漁業は全域で行われている基幹産業なのよ」と堂々とスピーチするし、時には厳しい顔で「アフリカ水産セクターの女性は漁師がとった魚の加工から販売のすべてを担っている。なのに社会的な地位は低く、まったく評価されていない。みんな貧しく、文字を知らないまま大人になっている。この現状を変えたくてここに来た」と力強く話すアフリカのかあさん。その勢いと明るさは見ている人の心にしっかりと響き、NHKの国際放送に出演することにもなりました。
◆2019年に同様のシンポジウム開催、そして今年8月もシンポジウムを開催しようと企画を始めて驚いたのは、日本政府の立ち位置、考え方がすっかり変わってしまったことでした。「一人一人が……」だったはずが、日本企業にどんどん進出してもらいましょう、というビジネス会議が今回のメインテーマ。変わったのは日本だけではなく、アフリカ側が「もっともっと豊かになりたい」「協力や援助ではなく、共にビジネスをしよう」となってきた、という事情もある。英仏の姿が薄まる一方、ロシアや中国やトルコがアフリカに経済進出していることも大きな変化。
◆そんななかで、今年も私たちは「もっと浜の女性たちが正しく評価されるようになってほしい」「アフリカの水産セクターを支える女性たちに光を」と訴えるシンポジウムを開催しました。国際NGOのお金をかけたシンポジウムや派手なパフォーマンスに比べて、まったく地味な活動であるけれども、すしざんまいの木村清社長から応援メッセージが届いた! また、こどもプロジェクト応援団の小泉進次郎氏が農水大臣の立場で駆けつけてくれたことは、今回の大きなインパクト。ありがたいことでした。[佐藤安紀子]
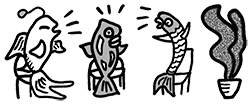
イラスト ねこ
■それは下痢から始まった。いきなり尾籠な話で申し訳ないが、8月、アフリカのカメルーンに入国して一週間。チャンという街に滞在し、気候にも慣れてきた時期に少し便が緩くなった。辛いものを食べたり、酒を飲みすぎた時にそうなることはある。チャンの食事はしばしば辛いのだ。腹痛もないし、その日は普通に街を歩き回ってスケッチをした。
◆翌日の朝、便は水の様な状態に。痛みはない。肛門括約筋がなんとも頼りないので、少し散歩してはホテルで休む。夕方帰ってきたマキちゃんが「マラリアになるとピー(下痢)になるんだよね〜」と冗談めかして言う。彼女はアフリカ通い30年でマラリア経験7〜8回という猛者だ。確かに首都ヤウンデでは蚊に刺された。でも標高の高いここチャンでは蚊はほとんどいない。それに潜伏期間は二週間くらいと思い込んでいた。「ま、食欲もあるし、疲れじゃない?」
◆夜8時ごろ、突然猛烈な寒気に襲われる。体が震え、歯がガチガチと鳴る。足先が氷の様に冷たく感じ、毛布を2枚かけても寒い。マラリアの症状は「おこりのような寒気」と聞いたことがある。これがそれか、と冷静に観察する自分がいた。おこりは数分続き、震えがおさまると熱が出た。体温計で38度くらいまで確認したが、その後は寝たのでよく覚えていない。眠りは浅く、うなされていたそうだ。
◆翌朝8時、ホテルオーナーのツァモさんが信頼している医者が部屋に来てくれた。濃紺のスーツにネクタイ姿のすらっとした体型。ツンと先とがりの革靴がおしゃれだ。それが49歳10人の子持ちのミシェル先生だった。まず電池式の血圧計で血圧を測り、次いで血を一滴とって検査。血中酸素濃度も大丈夫。糖も出ていないと言われる。カメルーンでは高血圧や糖尿病が多く、まずはそのチェックをするそうだ。その後問診があり、下痢の対処として点滴を受ける。リンゲル液を入れたボトルは、ベッド上方のランプから紐で吊る。持参した洗濯物干し用の紐を僕が自分でランプに結んだ。熱は下がっていて、普通に起き上がれる。体調は悪くないのだ。午後1時。血液検査の結果、マラリアと判明。マラリア治療に切り替わる。先生は僕の血液型がB型と知って「これはいい血液型だ」と絶賛する。血液型を褒められたのは初めてだ。
◆カメルーンでは、治療にあたってまず薬局で薬を買う。病院勤務医のミシェル先生も同じだ。前金を払って買ってきてもらった薬は抗マラリア薬artesunate。時間を空けて3回にわたり静注する。その日の夕方、1回目の注射。右手の甲に刺した針に注射器を繋いで何本か打つが、どれかの薬がめちゃくちゃ痛かった。血管の枝が一本一本わかるくらいの薬液の侵入感。あまりに痛いので、以降2回は点滴にしてもらうことに。
◆翌日は朝7時に2度目の点滴。午後4時に3度目の予定。合間は一人で街に出る。まだ便はゆるいが体調は悪くなく、チャンを取り巻くちょっとした丘に登り、街を見下ろす場所で風景をスケッチした。宿に戻り、最後の点滴のはずが、時短なのか、またもや注射。痛かったが、案外あっさりと治療終了。予後の飲み薬を色々と処方される。
◆アフリカに行くにあたり、一番の心配はマラリアだった。予防薬も数種類あるが、副反応があると聞き、飲んでいない。外出時は長ズボンに靴下、運動靴を履き、虫除けスプレーも使う。宿でも寝る前にスプレーをかけていたのだが、それでも少しは刺される。これまでは罹患しなかったが、今回、熱帯地方の洗礼を受けたというわけか。幸い軽症だったので、現地の行動にも大きな障りはなく、後遺症もない。ちなみに僕よりも10日ほど長く現地に滞在したマキちゃんは、僕の帰国後に発症したが、熱も出なかったそうだ。というわけで、この夏、アフリカのまた一側面を見る体験だった。できればもうかかりたくないけど。[長野亮之介]
■北大探検部の赤嶺直弥です。地平線会議を探検部の先輩に教えてもらってから早いもので4年ほどになりますが、8月に初めて報告会に顔を出しました。地平線の本丸へ乗り込むまでの紀行文を書かせてもらいます。所属している学会が8月末に湘南であるということで、これは併せて報告会に行けるのではと思ってから幾月。帰りの飛行機をうんと遅くして、報告会に参加できると相成りました。
◆本題に入る前に少々寄り道の話を。会場のキャンパスから数駅行ったところが荻田泰永さんの冒険研究所書店の最寄駅でした。ぜひ行っておかねばと、学会発表が無事終わった開放感の中で訪れました。折悪く荻田さんはご不在でしたが、書棚の隅から隅まで物色し、財布の紐を緩くしました。行きの時点で学会用のスーツやらポスターやらでパンパンだったザックがはち切れんばかりですが、価値ある重さに満足しています。
◆パレスチナに日本で一番詳しいとも称されるジャーナリストの小田切拓さん。江本さんをして今回は珍しいタイプと言わしめるほど、なかなかに強烈な報告会でした。内容を簡略化してわかった気にさせるよりも、とにかく聴衆に強い印象を残すために意図的にそうしたと仰っていました。
◆先輩諸氏から怒られそうですが、私はあるときから政治や国際問題を一歩引いて見るようにしてきました。理系の研究者を志すことを現実的に意識しだしたころからです。大袈裟にいえば自分の人生の使い方を考えたときに、自分一人の力で如何ともし難いことに頭を悩ませるよりも、自分にできる範囲で人類の未来に貢献することに力を注ぐべきだと考えたからです。そんなこともあってパレスチナ問題にあまり関心を持っていなかった私は基礎知識すらもままならず、少々難解な報告会となりました。
◆しかし個人がどれだけ無関心に振舞ったとしても、日本政府は国際政治に関与しています。具体的な行動はなかなか難しくとも、迷いながらも絶えず考え続けることが、か弱くとも一票を投じている一国民としての責務なのだと考えさせられました。報告会の中で小田切さんから放たれた数々の鋭い言葉は、世間知らずの若輩者の心に深く突き刺さり、強い印象を残したと報告させていただきます。
◆報告会の後は「新北京」での打ち上げにもお邪魔しました。飛行機のこともあって短い滞在でしたが、噂に聞いていた餃子をはじめ美味しい料理の数々と温かく迎えてくださった皆様のおかげで楽しい時間となりました。改めてありがとうございました。来年の北海道地平線に向けて、江本さんからいくつか宿題もいただきました。ビールと餃子をご馳走していただき、段々と後に引けなくなってまいりました。北海道の仲間たちとしっかり相談したいと思います。まずは秋の北海道でお待ちしております。
◆この原稿はなるべく熱いうちにと、札幌への帰路で書き上げました。ほろ酔い状態での乱文でお目汚し失礼しました。ではまた。[北大探検部 赤嶺直弥]

■先月の通信でお知らせして以降、通信費(1年2000円です)を払ってくださったのは以下の方々です。万一記載漏れがありましたら必ず江本宛メールください。通信費を振り込む際、通信のどの原稿が面白かったかや、ご自身の近況などを添えてくださると嬉しいです(メールアドレス、住所は最終ページにあります)。
森美南子 宮内純 飯野昭司(10000円) 田島裕志(4000円 2年分です) 永田真知子 世古成子 石塚徳子
■酷暑お見舞い申し上げます。先日9月4日〜6日、沖縄は旧盆を迎え、いつもはシーンとしているここ浜比嘉島の村内はにぎやかでした。普段は空家で人けのない家には明かりがつき老若男女集まってご馳走を囲み仏壇には飾り物供え物がたくさん。そんな中、お盆最終日はウークイといってご先祖様があの世に帰る日、エイサーを踊って送り出します。
◆島に住む、または島出身の青年たちによるエイサー。比嘉のエイサーは伝統があり、昔全島エイサーコンクール(昔はコンクール形式だったらしい。今は祭りとなって順位付けはなし)で連続優勝した実績を持ちます。一時は過疎化で衰退、存続の危機もあったと聞きました。17年くらい前、私が島に来たころには踊り手もじかた(三線弾き)も高齢化、それでもなんとかつないでおりました。
◆近年の比嘉エイサーは、20代〜30代が中心になり10代もいて、約1か月前から練習を重ね、じかたも若手が頑張っています。ウークイの夜と翌日のワカレアシビの一斉演舞には島内外からたくさんの見物人が来ていました。YouTubeにもあがってるみたいなので「比嘉エイサー」で検索してみてください。
◆お盆が過ぎたら心なしか風が秋めいたような気がします。内地は今年は相当ヤバい暑さと聞いてます。浜比嘉島は最高気温はせいぜい33度、日陰に入れば涼しいので、ぜひ夏は沖縄に避暑に来てください。[浜比嘉島 外間晴美]
p.s. 来年秋の北海道大集会、いいなあ! 比嘉で織物をしている渡辺智子ちゃんとも話していたのですが、日程の都合が付けばぜひ行きたいなあ! 20代の頃125ccのオフロードバイクにテントを積んで北海道を走り回ったのを思い出します。日程決まったらぜひ教えてくださいね!
■2026年初秋に予定している北海道での地平線会議を成功させるため、1万円カンパを募っています。北海道地平線を青年達が集う場にしたい、というのが世話人達の希望です。交通費、宿泊代など原則参加者自身の自己負担としますが、それ以外に相当な出費が見込まれます。たとえば事前に何度かスタッフが現地入りして当日の進行、宿泊のことなど打ち合わせ(たとえばこの10月末の3日間、4人が現地入りする予定です)しますが、その際の補助などにあてたいです。どうか趣旨お汲み取りの上、北海道上陸作戦にご協力ください。[江本嘉伸]
賀曽利隆 梶光一 内山邦昭 新垣亜美 高世泉 横山喜久 藤木安子 市岡康子 佐藤安紀子 本所稚佳江 山川陽一 野地耕治 澤柿教伸(2口)神尾眞智子 村上あつし 櫻井悦子 長谷川昌美 豊田和司 江本嘉伸 新堂睦子 落合大祐 池田祐司 北川文夫 石井洋子 三好直子 瀧本千穂子・豊岡裕 石原卓也 広田凱子 神谷夏実 宮本千晴 渡辺哲 水嶋由里江 松尾清晴 埜口保男(5口) 田中雄次郎 岸本佳則 ささきようこ 三井ひろたか 山本牧 岡村まこと 金子浩 平本達彦・規子 渡辺やすえ 久保田賢次 滝村英之 長塚進吉 長野めぐみ 北村節子 森美南子 飯野昭司
★1万円カンパの振り込み口座は以下の通りです。報告会会場でも受け付けています。
みずほ銀行四谷支店/普通 2181225/地平線会議 代表世話人 江本嘉伸
■地平線通信556号(2025年8月号)はさる8月20日、印刷し発送しました。今号は岡村隆追悼号のかたちになりました。汗をかいてくれた方々は、以下の皆さんです。江本は日本記者クラブでの映画試写会『壁の外側と内側 パレスチナ・イスラエル取材記』に参加したあと、出来上がった通信を受け取るため、新宿郵便局で車谷さん、白根さん、長岡さんの3人と落ち合い、ずしりとした通信の束を受け取りました。皆さん、ありがとうございました。
車谷建太・伊藤里香・高世泉・中嶋敦子・長岡のり子・白根全・渡辺京子・落合大祐
■8月23日から9月6日まで、北海道大学環境科学院の実習でスイスに行ってきました。スイスアルプスの氷河を巡り、実際に氷河上を歩いたり氷河が生んだ地形を観察したりして、自然界における氷河の役割について学びます。今年はプログラムが学外に開かれ、多様な専門分野の大学院生8名と教員2名で、2週間をともに過ごしました。
◆新千歳空港を発ち香港まで6時間。乗り継いでスイス・チューリッヒ空港まで12時間。長旅でしたが、スイスの街に降り立つとその疲れが吹っ飛びました。青というより緑に近い鮮やかな色の湖、綺麗に刈り揃えられた芝に、煙突付き木造住宅がポツポツ。家の窓辺には赤い花が植えられ、あちこちでスイス国旗がはためいていました。私がスイスを訪れるのは2度目です。7歳のときに家族と来たことがありますが、当時の記憶はほとんど残っていません。ただ、スイスの国民的飲料「リベラ」とクロワッサンを口にしたときは不思議と懐かしさがあり、当時の思い出がよみがえってくる感覚がありました。味覚や嗅覚が覚えてくれていた記憶が、脳にフラッシュバックする感じ、たまに経験します。ここ数か月慣れない土地で研究に悩む日々を送っていた私にとっては、目に飛び込んでくるもの肌で感じるものすべてが新鮮で、刺激的で、開放的でした。
◆2週間でウンターグリンデルワルト氷河、アレッチ氷河、ローヌ氷河、ゴルナー氷河の4つの氷河を観察しました。そのうちローヌ氷河の上を歩きましたが、表面は黒くジャリジャリしていて、氷河が運んだ土砂や石がごろごろ転がっています。日常的に見る透明で滑らかな「氷」のイメージとは違っていました。氷河上を歩ける日がくるとは夢にも思っていなかったので、この感動をかみ締めながらクレバスに落ちないようゆっくり歩を進めました。
◆ローヌ氷河ではGPS観測、気象観測、水文観測を実施しました。現地での観測、データの解析、結果報告までの自然科学研究の一連の流れを経験したのは、社会学を学んできた私にとって初めてのことでした。私以外の学生は氷河、岩石、アイスコア、海洋物理、植生を専門とするいわゆる「理系」で、専用のプログラムを使いこなして数値化されたデータをあっという間にグラフ化してくれました。私はそれを眺めることしかできず、スキル不足で役に立つ作業ができないもどかしさを感じました。
◆その一方で、自然を相手に研究観測を行う楽しさを知れたことは、私にとって大きな収穫でした。氷河の融け水が流れる川の流量を調べるために、水深・流速を測り、観測データを計算しグラフ化しました。流量の時間変動を表すグラフを作成し、スイス連邦環境庁のデータと比較したところ、多少の違いはあれ同じような動きを示し、類似した変動であることを確認できました。手作業、アナログ、目分量なところがあり本当に正しいデータが取れるの?と疑問でしたが、実際には自分たちの計測・計算が間違っていなかったことが示され、さらに精度の高い観測を実施するためにどうすれば良いか、僅かな差が生じた原因は何かという議論にまで発展させることができ驚きました。
◆見た目ではわからない物体や現象が、数値、グラフに置き換わり、それを徹底的に観察・考察することで見えてくるものがあること、川ひとつ取っても氷河に関する様々な現象との関係性を考慮する必要があることを学びました。こうした気づきを得られたことで、氷河を見る目が随分変わりましたし、何より研究の喜びを改めて味わえたことが嬉しかったです。
◆法政大学社会学部から北海道大学に進学し、理系研究所に研究席を置かせてもらうと、今まで普通にできていたはずの相談、議論がうまくいかず戸惑うことが多いです。「もっとサイエンスをして」と言われたこともあり反論できず、文系の強みって何なんだろう、と思い悩んでしまうこともありました。ですが、今回の実習を通して「研究の楽しさ」を再確認できたことは本当によかったと思っています。疑問を追求する楽しみを知っていることは、辛くても研究を続けようとする原動力になるかもしれないからです。私は自然現象というよりは人間社会を対象にしていますが、違うものを見ていても喜びは同じなのだなと思いました。
◆今は、科学技術コミュニケーションという考え方に興味を持っています。専門家と市民が双方向に関わり、科学の意義や社会課題を共有し、協働を通じて知識や価値の創造に貢献する活動を指します。科学技術コミュニケーターは、科学技術に関することがらについて、異なる価値観を持つ人びとをつなげる入り口の役割を担います。人文社会系でありながら自然科学系の研究所に身を置いている、この環境をプラスに変え、文理という隔たりを小さくする努力をしてみたいと考えています。[北海道大学環境科学院修士課程1年 杉田友華]

■バフッ、ムニュ、ゴッ、ドス! それらを足して割ったような音が、あたまから離れない。素手で人の顔を殴る、生々しい音。この夏モンゴルにいた私は、人が人を殴る光景を、ほとんど毎日のように目撃していた。
◆たとえば大草原で開催された音楽フェスティバルに出かけたとき。深夜、仲間の1人が顔を傷だらけにして、テントへ戻ってきた。酔った若い3人組に、いきなり殴られたらしい。翌朝は、けたたましい男女の叫び声で目が覚めた。テントのファスナーをそっと半開きにして外をのぞくと、草の上で取っ組みあいながら殴りあうカップルを発見(しかも知人だった)。ウランバートルに戻れば、路上で2人の運転手が口論になって、車から降りるなり殴りあいが始まった(後ろはもちろん大渋滞)。ようやく滞在先のアパートに帰りつくと、こんどは階下で若者たちが殴りあっていた。
◆拳が顔にめりこむのを目の前で見るたび、最初はショックで、自分が殴られたわけでもないのに妙にぐったりしてしまった。けれど、あまりに日常茶飯事すぎて、次第に驚くことすらなくなっていった。
◆それから東京の暮らしに戻って、ちょうど1か月。こんな大きな街にいるのに、殴る人を一度も見ていない! というか、これまでの人生を通しても、日本の路上で殴りあいを見た記憶がほとんどなく、そのことにあらためて驚いている。心穏やかでいられてありがたい反面、ふと思う。日本人は(そして私自身も)、怒りをどこへ向けているんだろう? SNSで? 日記で? あるいは、抑えこんでいるのか。そもそも、環境がよくて怒る理由がないのだろうか?
◆モンゴル人は、愛情も怒りもストレートに出す傾向がある。そして彼らは(とくにウランバートルの都会人は)総じて陽気だけれど、苛立ちも強い。社会的背景も大きいかもしれない。1990年代はじめ、社会主義が崩壊して市場経済に突入したとき、大人たちは自分でビジネスを始めなければならず、必死にもがき苦労した。酒に逃げ、ストレスから子どもに暴力をふるう親もいた。その時代に子どもだった人は、現在30〜40歳前後になっている。年齢的には大人でも、一部の人は心の奥に今なお、愛情に飢えた子ども時代の自分を抱えたまま、苦しんでいるように見えることがある。
◆私は若いころ、プロボクシング観戦に夢中だった。聖地・後楽園に住み、あらゆるタイトルマッチに通い、全力の殴りあいを散々見たものの、不思議と後味の悪いパンチは一度もなかった。ではなぜモンゴルの路上で見た殴りあいは、こんなにも記憶にこびりついて離れないのか? 拳にこめられた感情がむきだしだったからだろうか。
◆こうも頻繁に殴りあいが起きる国の、その異常さを思いながら、静かな日本というこの国にもまた、音にならない苛立ちや、別の不穏さが潜んでいるような気がしてくる。日本では、私が知らないだけで、別のかたちの拳が存在しているのだろうか。
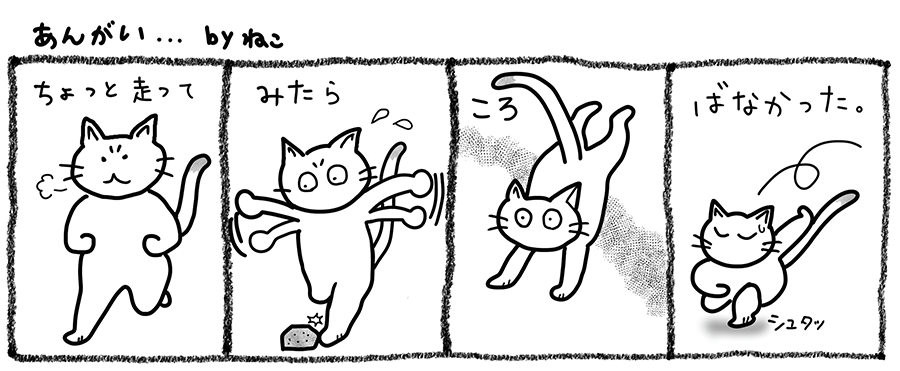
《画像をクリックすると拡大表示します》
■2025年8月11日、山の日。今年の第9回「山の日」全国大会が福井で開催された。山の日全国大会は、山に親しむ機会を得てその恩恵に感謝する日として、毎年各都道府県の持ち回りで各種イベントや講演会が開催される。今年は地元、福井での開催だったのだ。その11日、会場で主催者ブースに立つことになった。きっかけは7月中旬の沢登りだった。
◆勤務先のメガネ会社を半ば強引に説得し少なくない費用をかけて製品化した登山用サングラスは自分なりに会心の出来だった。しかし初夏を迎えても目的とした登山用品店への販売が少しも進まない日々が続いていた。そもそも懇意にしている登山用品店もなく、畑違いの登山・アウトドア業界への販売ルートもない。会社としてもどう売り出していくかも手探り状態の初モノだった。
◆そんなとき、見かねた登山仲間が沢登りの現場で、突然、福井県山岳連盟の関係者を引き合わせてくれたのだ。仲間からそのサングラスの説明をすると、その方の回答は「せっかくだから山の日の開催会場でサングラスを並べて全国に紹介しようよ」だった。言われた瞬間、「えっ、そんなこと開催2週間前に勝手に決めていいの? 自分は県の山の会に所属してないけど後で問題にならないか?」との考えが頭をよぎった。でも幸運の女神には前髪しかない。迷っている場合ではない。返事は「ぜひ、お願いします」だった。かくして、8月11日の山の日は、急遽、山の日全国大会の主催者ブースに立つことになった(後で知ったのだが、この人こそ山岳連盟の理事長だった)。
◆山の日の展示に向けて、バタバタした日々が続いた。サングラスを展示するディスプレイを作り、説明用のPOP(ミニポスター)を作り、展示レイアウトを考えてと時間に追われた。当日の会場では専用テーブルを設置させてもらい新しく発売した登山用サングラスを立ち寄る人ごとに説明・紹介していった。ブース内の連盟の人たちも、展示用のサングラスを持って急にブースに割り込んできた名も知らぬ珍客に「この人だれ?」と、最初は様子見だったと思う。当日は福井県を中心に全国各地の来場者や周囲のブース出展者、山の日アンバサダーの仲川希良さんらから直接サングラスの感想を聞け、好意的な反応があり製品の方向性は間違ってなかったのだと自信を取り戻す機会となった。
◆ 私はメガネの産地福井でメガネの企画販売会社に勤めている。 勤め先の売上の9割以上を占めるのは、メガネ店へのメガネフレームの販売だ。登山用サングラスは、自社でいつか作りたいと思っていた。メガネとスポーツ向けのサングラスは似て非なるものだ。業界的には業種や製造工場も異なるのだが仕事で登山と関われるサングラス作りに挑戦したく、登山メーカーや釣具メーカー向けにサングラスを提案し、裏方として企画・製造してきた。5年前からは縁あって某鉄道会社の運転士が掛けるサングラスのフレーム部分の供給を担うようになった。その状況でどうしても後回しにせざるを得なかったのが長年温めていた、自らが本当に欲しいと思える登山用サングラスだ。
◆お客様の製品を裏方として製造する中では、店頭の販売価格に直結するコストは大事な事項だ。でもそんな中で「コストがかさむけど、この構造があれば面白い」「あと30円かければ(誰も気づかないかもしれないけど)長期使用後でも品質が安定する」などいくつもの想いが堆積していた。その想いを実現するには、売れないリスクがあっても自分で作るしかない。今回発売したサングラスは、ハードな山でも日射しをしっかり防ぐ構造と、街中で掛けられるデザイン性の良さの両立を目指した。一般的に、ブランドもののサングラスの主流は欧米だ。瞳の色が薄く眩しさを感じやすい欧米人に合わせて「濃い色」のレンズを採用したサングラスが多い。でも日本人を含めたアジア人は瞳の色は黒や茶系だ。眩しさに比較的強いため、もう少し「薄い色」のレンズで充分だ。そのほうが山では使いやすい。日中だけでなく薄暗いシーンでも着用できるからだ。そんな今までの気付きを盛り込んだ製品に仕上げた。
◆話を戻すと、開発したサングラスをどう販売していくのかという営業面が大きな課題としてずっと残り続けていた。裏方として製造していることはあっても、何のつながりもない登山・アウトドア業界にサングラスをどう売り込めば拡がるのか。良い製品を作ったという自負はあったものの認知されない日々が半年近く続いた。そんな中、偶然にも別の製品で問い合わせのメールをいただいた北海道の登山用品店にこのサングラスの話をすると、取り扱いに手を挙げてくれた。熱量あるスタッフの方々で、我々の会社が驚くくらい多く販売いただいた。そんな1本の蜘蛛の糸をつかむような状態から一歩を踏み出した。最近になり登山用品の大手卸問屋がこのサングラスを取り扱いたいと言ってくれ、この会社を起点に少しずつ全国各地の登山用品店にこのサングラスが並び始めた。ようやくスタート地点に立てたところだと思う。
◆趣味のことに会社のお金を使わせてもらっているという負い目もあり、日常業務をきちんと終えてからこのサングラスに取り掛かると決めており日々の時間配分にはまだまだ課題が多い。要領が良くなく、コダワリも強いため時間がかかる。そこに出張も重なるため週の半分以上は10時過ぎの帰宅となる日々だ。しばらくはこの状態が続くだろう。でもやっていて愉しい。楽しさでなく、愉しさ。静かな満足というのだろうか。
◆ここに来るまでに、ウェブサイト用のサングラスの感想文章を引き受けてくださった小松由佳さん、ポーチに印刷する手書きイラストを提供いただいた緒方敏明さん、山での着用モデルを引き受けてくれた福井の山仲間達と、一人一人に感謝の想いだ。ECサイトのオープン日には落合大祐さんからサプライズで注文をいただいた。改めて皆様に御礼申し上げます。
◆想い始めたときから十年近くの時を経て自分が本当に欲しいと思える登山用のサングラスをようやく製品化できた。流行りのタイパという概念からすると、しなくてよい苦労もたくさんし続けてきていると思う。挑戦するだけでなく、「継続」していくことが何より大事だ。私なりに継続して頑張っていこうと思う。まだまだ道のりは長い。ふぅ……。今回のサングラスは「サングラス Niho」で検索すると出てきます。[福井市 山から遠ざかり気味の塚本昌晃]
■8月中旬に家族でマレーシア・ボルネオ島サバ州に1週間ほど滞在した。第1目的は東南アジア最高峰のキナバル山(4095m)の登頂。富士山よりちょっと高いだけで、それに「初心者にも優しい」などのネット情報もあり、まあ大丈夫だろうと臨んだらとんでもなくきつい山だった。入山するには、まずキナバル自然公園(標高約1800m)で登山届を出すと同時に、山頂までの往復を同行ガイドを雇うこと。と書いても、じつは、キナバル山は観光客にも人気の山で、自然公園に散在する宿も、富士山で言えば8合目くらいにある6軒のロッジへの予約も個人では取れない。なので、ここはその枠を押さえている旅行会社に一切合財を頼んだ。
◆自然公園での宿は快適。温水シャワーも出るし、ウォーターサーバーも備えている。食事は徒歩数分の場所にある大きめな施設でのバイキングだが、どれも美味しい。で、一泊して、いよいよ翌日に自然公園の事務所でまずは入山証(首からぶら下げる)をもらい、車で10分ほどの移動で登山口(ティンポホン・ゲート)に到着。ここで入山届を出してから登山が始まる。
◆ネット情報では「階段が整備されている」と書いているが、半分ウソ。普通に石や岩がゴロゴロしていて、なかなか歩きづらい。ガイドのアプソンさんは20年もガイドを続け、週2回はキナバル山に登っている。つまり今まで2000回以上も登った。格好もじつに軽装で、靴だってスニーカーだ。
◆周りのガイドを見ても、なかには踵を固定するだけのサンダル履きもいる。だが歩くのは抜群にうまい。絶対に疲れない。途中、高山病なのかポーターに背負われて下りてくる登山者を何人も見たが、そのポーターだってスニーカーで濡れた岩の上を当たり前に下っている。その逆にロッジに物資を運びあげるポーター(歩荷)も驚異的な量の荷物を運びあげている。やはりスニーカーで。
◆私はサバ州の隣のサラワク州での滞在が長いが、森の中では小学生の女の子がサンダルですいすい歩いているのを何度も見ている。「おそらくは」と思いアプソンさんに尋ねた。「あなたも含め、ガイドの皆さんは先住民族なのでは?」「そうです。私の村は自然公園から車で15分だけ行ったところ。同じ村からも何人もここで働いていますよ」。だがその雇用形態はいわば日雇いに近く、20年働いても、退職後に年金の支給はないとのことだった。
◆途中、数か所にトイレがあるが、すべて水洗でとても清潔。ゆっくりペースで標高3263mのロッジ「ラバンラタ」に着いたのは7時間後。キナバル山の登山管理はじつにシステマチックで、かつ登山者の快適な過ごし方をよく考えている。ロッジにしても、温水こそ出ないものの水シャワーは使えて、ウォーターサーバーも設置され、ここでもバイキング形式の料理を楽しむことができる(入山証の提示が必要)。
◆部屋は2段ベッドが3つの6人部屋で、時間制限はあるが壁のコンセントから充電もできる。こうやってゆとりをもって過ごせるのも、自然公園がキナバル山への入山者を1日165人と制限しているからだ。山のオーバーツーリズムを避けるこのシステムには見習うものがある。
◆朝(いや真夜中か)の1時半に起床。2人の子どもは高山病でロッジで待機することになり、私と連れ合いとで2時に出発。というのは、富士山ならば、8合目以降もいくつもの山小屋があるが、キナバル山では山頂まで途中のチェックポイントを除けば一切の施設がない。つまり、一気に800m以上を上って下りてこなければならない。
◆ヘッドランプをつけても、周囲の状況はまったくわからず、ただガイドについていく。そして5時半に山頂に着いて、6時のご来光を待ってすぐに下山した。明るくなって初めてわかったが、これは舗装道路かと思うような灰色で平坦な岩場が続き、キナバル山が広大な花崗岩の山と実感した。
◆8時少し前にロッジに到着。だが、このとき、私は脚の力を使い果たしてしまった。しかし、自然公園の事務所から州都コタキナバル行きの車に15時には乗らねばならない。なのでガイドの「9時半にはここを出ましょう」に従うしかないのだが、そこからがとてつもなく苦行だった。今回の山行での失敗は登山用のウォーキングスティックを持ってこなかったこと。そこで、下山時にロッジでウォーキングスティックを買って、なんとかかんとか歩いたが、一歩を下ろすたびに腿に痛みが走る。
◆帰り道、ガイドのアプソンさんに尋ねたところ、ガイドは約260人いるそうだ。「その中で最高齢は何歳ですか?」「74歳です。今も現役でまだまだ元気」と話していたら、その数十分後、アプソンさんが「いました、いました。74歳のガイドです」と下から上ってくるガイドを紹介してくれた。もう35年ほどガイドをしているようで、何気に日本語もうまい。別れ際に「さようなら。気をつけてくださーい」と手を振って、重い荷物を背負いながらも軽々と山道を登っていった。すげーなあ。
◆下山後の公園事務所では、アプソンさんの証明により、登山者にはカラーの登山証明書が名前入りで発行された。とはいえ、登山のきつさから、登山後の3日間くらいは階段の上り下りに苦労した。困ったのが高校生の娘が今回登れなかったことで「もう一回来たい」と言い始めていることだ。え〜、オレ、また登んの。考えただけでげんなりするが、アプソンさんのように軽々と上る姿を見てしまったら、やはり訓練次第かなと思う。ちょっと頑張るか。[樫田秀樹]
■お会いしたことはないものの、岡村隆さんの最期には「生き切った」という言葉がふさわしいと感じました。周囲から見れば突然の幕引きだったかもしれませんが、地平線会議を通じた先輩と皆さまの強い絆を感じています。
◆報告は、父の他界を受けて転職2年目の畑と地域のことです。昨年の5〜6月は鳥よけネットを柱から手作りで、35a(3500平米)分の広さを設置したのは相当の作業でした。今年はネットを張るだけ♡と楽観視していたら、雨が多く気温が高いため、草の伸びが早すぎる! 集落での共同作業は6月第一週の日曜日と決まっていて、その前に刈るべき畔と放棄地の雑草はすでに腰丈になっているではありませんか! 急いで自分の圃場をハンマーナイフモアと丸刃草刈り機で刈り進め、気づけば汗だく、草まみれになっていました。日本の自然暮らしはとにかく草との戦いです。
◆ちなみに、私は水着の短パンとラッシュガードに直接草刈エプロンを着用し、草刈りの後はエプロンを外して、透明な川にざぶん。暑い草刈りから冷たい川への入水はサウナと同じで、清流と7種の川魚との一体感に虜になってしまいます。外気温が33度を超えても2時間程はお肌サラサラで、体が「整う」状態が続くのですから。
◆話は戻り、集落の共同草刈の目的は、水路の維持と農村景観の維持の二つが主です。各世帯から一人が参加。男仕事という暗黙の了解がありますが、私は紅一点で参加しています。子ども時代からおてんばで知られていたこともあり?、ここ3年の連続参加で馴染んできたと勝手に思っていますが、まだ気は遣われているかもしれません。
◆各家に草刈場所が分担され、終わった者は遅れている所に駆けつけて一斉に終了。顔見知りばかりの集落で、午前一杯の作業後にはビール1缶とつまみに菓子パンが配られ、神社の石段に腰かけて役員と集落管理の相談事が交わされる「直会」のような時間も設けられます。
◆水路の掃除も共同作業で、全国の各地と同じく田植え前の4月の連休の頭と決まっています。集落には碁盤の目のように水路が張り巡らされており、1年分のたまった土砂を、上流から住民が代わる代わる水路に入って、スコップや鋤簾ですくい上げていきます。すくった土砂は道路の反対側に運ぶなどして水路に入らないよう、後始末もまた力仕事です。水をたっぷり吸った土砂はとにかく重く、腰にずっしりと負担がかかります。もし1年でも休んだら、次の年にはもうできる気がしない……、そんな思いがよぎります。この作業には80歳にもなる高齢男性も加わって、各戸代表により維持されていますが、年々リタイヤも目立ちます。この作業の後も直会的な時間がありますが、単身移住者や戸に属する女性でさえ、様子を直接知る機会は少ないと思います。
◆集落は標高800m以上、冬はマイナス16度を記録することもあり、米の栽培には不向き。それでも必要に迫られ、戦後祖父たちが背後の山の裏から手掘りで水を引いて水田開発したと聞いています。生きていれば97歳の祖父は当時高校生で、男子高校生が全員動員されたそうです。冷涼のためあきたこまちか在来種を栽培しても、美味しい米は採れないとぼやく声もありました。
◆その後、農地改革で圃場と水路は整えられ、機械化による現代農業が進んだ代わりに、おびただしいヒキガエルやホタルの群れは消えました。令和では一部の田んぼだけが残り、半数は飛騨牛を育てる牧草地へと変化しました。しかし、30年前に父がブルーベリーを水田転用地で始めたころには、「(神聖な)田んぼに何を植えとるんじゃ」との苦言もあったとか。人々の理解と納得には、長い時間が必要なのだろうと思います。
◆先日、『里山資本主義』の著者・藻谷浩介氏の講演会に参加しました。「千年後には何が残るか」との問いに、「寺社、水路、田畑」の答え。アジアでは米が主食であり、稲作には水路と水平の圃場は欠かせません。一朝一夕にはできない圃場を、代々脈々と農民が営繕し、引き継いできた歴史があります。田んぼを守る掛け声にはこうした背景があります。私は長野県の中山間地直接支払制度懇談会委員としてこの課題に向き合っていますが、担い手不足の根本は「住む人の存在」が鍵だと思っています。
◆そんな水田転換地で進める30年程度の歴史のブルーベリー栽培も、野生生物との攻防が絶えません。鳩、スズメは隙あらばネット内に入り、果実をついばんではどこかへ逃げていく。先日は網にかかった鳩に気づかず、夜に獣が網を破って侵入、翌朝にハトの無残な死骸が残されていました。そんなある日の日暮れ、母が「また3羽かかってる!」と出かけて行ったまま帰らないので見に行くと、足を絡めた生きた鳩があちこちでもがいています。「そこまでして実を食べたいのね」。
◆一羽の足の網を外すのに20分ずつ奮闘し、羽が抜けて飛べなくても、目を合わせれば必死に逃げようとします。辺りは闇に包まれ、地面にいては獣にやられるため巨木の枝の股にそっと置いたのは、同じ生き物としてのせめてもの憐れみです。「何とか生き延びておいで」。翌朝にハトらはいなくなり、安否は不明。そして新たに、ブルーベリー圃場の脇にはトウモロコシの食痕が捨てられ、犬サイズの紫の糞が点々と落ちているのです。「はて、こんどは何者の襲来か?」。農地は食に執着する様々な命たちが交錯する、場所です。[中澤朋代]
岡村隆さんが急逝して早いもので2か月半近くが過ぎた。地平線会議でのお付き合いだけではなく、私はオシゴトのほうでも岡村さんと深く関わってきたので、心にぽっかりと開いた穴はなかなかふさがりそうもない。私にとって岡村さんは「頼りになる兄貴」で、岡村さんに相談できる、後ろで見守っていてくれるという安心感は何ものにも代えがたいものだった。
◆1988年に、私は岡村さんを取材してインタビュー原稿を書いている。子ども向け雑誌に「地球たんけんシリーズ」と題して、江本嘉伸・賀曽利隆・岡村隆・惠谷治・向後元彦・向後紀代美の各氏を紹介した。私が岡村さんについて少々知ったかぶりができるのも、このときの取材メモが残っているからだ。このままこのメモを埋もれさせてしまうのは惜しいので、地平線通信の誌面を借りて、個人的な思い出を交えながら岡村さんの歩んだ道の一端を紹介してみたい。
【観文研との出会い】——私が岡村さんをナマで初めて「見た」のは、秋葉原の日本観光文化研究所(観文研)だった。おそらく1978年の初め頃で、玉子色(と記憶している)のスーツを着て宮本千晴さんにペコペコと頭を下げているのがあの岡村隆だと知って驚いた。私の中学時代からの洞窟探検仲間だったK君が法政の探検部に入部したのだが、OBになっても部を支配する「オカムライズム」に馴染めず、同期らを何人も引き連れて探検部を割って出てしまった。このときK君から聞かされた岡村さんへの辛辣な批判から、「探検部に君臨するとっても偉そうにしている大先輩」という人物像が刷り込まれていた。
◆ところがそんな大物が、千晴さんの前でへいこらしている(まだこの頃は千晴さんのすごさをよく知らなかった)。これはのちに酔っぱらった岡村さんから何度も聞かされたことだが、岡村さんは千晴さんにはまったく頭が上がらないのだ。先月の地平線通信で千晴さん自身が書いているように、法政の探検部として送り出したモルディブやスリランカの報告書を観文研がシリーズで出版してくれた。とくに、普通なら印刷会社が担当する写真の製版作業(網伏せ)を、写真の腕のある千晴さんがすべて自分でやってくれたおかげで印刷費が抑えられ、出版が可能になった。このことに、何度頭を下げても足りないくらいの恩義を感じているという。報告書の制作中に千晴さんがふともらした「岡村よ、これは一生かけてやらねばならない仕事だぞ」というひとことが、岡村さんの人生を決定づけた。
◆1977年、29歳で探検部の4年後輩である節子さんと結婚した岡村さんは、翌年からトラベルジャーナル社という旅行情報を扱う小出版社に7年半勤務する。スーツ姿で観文研に現れたこのときは、就職(観文研からの卒業?)の挨拶のためにやってきたのだ。これで金の苦労もなくなるな、などとみんなから声をかけられて照れくさそうにしていたのが印象に残っている。
◆大学3年目の1969年にモルディブに長期滞在したあと、岡村さんが5年生になったときに、杉並区に探検部の拠点となる部屋を借りた。そこへやってきたのが向後元彦さんで、話が弾み、「君、明日から来なさい」と言われて観文研に出入りするようになる。「観文研の三馬鹿タカシ」の一人である立命館の森本孝さんもそうだったが、探検部の部室に向後さんが現れて「獲物」を一本釣りする狙いだった。このとき不在で向後さんと話ができなければ、その後の二人のタカシの人生も、また観文研自身の歩みも違っていたのかもしれない。
【スリランカ遠征へ】——1972年に大学を卒業したあと、岡村さんは観文研の「AMKAS探検学校」の「リーダー」としてアフガニスタンを訪れる。もともと岡村さんはヘディンやスタインに並々ならぬ思い入れがあり、中央アジアの探検に憧れていた。仏教にも詳しく、モルディブでイスラームにも触れている。ヘディンらが歩いたトルキスタンの一角をなすアフガンの旅は、心が躍るものだった。しかし中央アジアの探検は、すでに先人たちがやり尽くしている。当時は日中国交正常化の直前で、肝心の中国領トルキスタンには入れない。ちょっとした旅はできても、未知の空白を埋めていくような正統的な探検にはとうていならず、満足のいく成果はあげられないだろう。だったら、ジャングルに眠っている仏教遺跡を探し当てるほうが、よっぽど探検らしい行為じゃないか。そんな思いから、1973年と75年のスリランカ遠征へと向かうことになる。
◆73年の遠征資金は、主に観文研での資料整理のアルバイトと肉体労働で稼ぎ、75年は、上智大学探検部のOBグループが当時請け負っていた『週刊朝日』のレイアウトを担当して金を用意した。発行部数が桁違いの一流週刊誌のレイアウトを手かけた経験は岡村さんの自信となり、大きな誇りとなったようだ。
◆存在さえ忘れ去られた遺跡を探すためにはまず開拓村を訪れ、そこでガイドやポーターを雇ってジャングルに分け入っていく。40度を超す気温のなかでトゲだらけの薮をかき分けて進むのは、とんでもない苦行だった。見通しが利かないために方向を見失いやすく、常に磁石をにらみながら歩数計で距離を割り出して作図していくことになる。象をはじめとする野生動物にも気をつけなければならない。そんな苦労の果てに、2000年の時を経て崩れ果て、風化した仏教遺跡にようやく到達できるのだ。100近い遺跡を確認し、そのうちの40か所はまったく知られていない新発見の遺跡だった。
◆ひとつの遺跡から次の遺跡へと、未知の領域をつぶしつつ踏査路を伸ばし続けていく。まさに「遺跡を追い詰めていく」という形容がぴったりの行為だと感じていた。つまりこれは、岡村さんが憧れてやまない正統的な地理的探検のスタイルである。政府考古局との約束で、遺跡の位置を記載して簡単な測量と写真撮影をするだけ。発掘は絶対にやらない。その成果は考古局の登録台帳に記載され、専門家による将来の本格的な発掘調査を待つことになる。まったくのボランティアとして遺跡の位置確認・発見に協力するだけとも言えるが、自分たちの力をわきまえ、得られる成果を着実にものにしていくことに、岡村さんは大きな満足感を味わっていたようだ。
◆二度目のスリランカ遠征から帰ったのち、岡村さんは何をしたらいいのかわからなくなっていたという。就職する気はさらさらない。でも、妹さんの結婚式に無職のまま出席するのはさすがにまずいと思い、週刊つりニュース社に3か月勤めたが続かず、晴海埠頭で倉庫仲仕のバイトをしたりもした。ある日、新聞の求人欄でトラベルジャーナルが整理記者を募集しているのが目に留まり、気楽に活字の周辺にいられるのならと思って就職した。すぐに取材記者として原稿を書くようになり、やがて月刊誌のデスクとなる。仲間たちに酒を飲ませたり、後輩に仕事を振ったりできたのがうれしかったという。
【地平線会議創設からモルディブ再訪へ】——こうしてサラリーマン編集者として歩み始めるうちに、1978年12月に法政大学で開催された学生探検会議にOBとして参加した岡村さんは、翌年8月の地平線会議創設に加わった。当初の地平線会議は、毎月の地平線通信(当時は葉書)の発行、地平線報告会の開催、年報『地平線から』の編集・発行が三本柱だったが、年報に載せる情報の提供を広く呼びかけるために、岡村さんはスポーツ雑誌『Number』の創刊準備号から地平線会議のコーナーを確保して、さまざまな記事を載せた。ささやかな行動やイベントが、岡村さんの筆によって立派で誇らしいものに見えてくるのには驚かされたものだ。82年にはトラベルジャーナル新書を立ち上げ、惠谷治さんの『国境の世界』や伊藤幸司さんの『旅の目カメラの眼』など、ユニークな旅の本のシリーズを提供していった。
◆1982年12月2日の朝日新聞夕刊に、ヘイエルダールがモルディブの無人島で謎のピラミッド状の遺跡を発見したというニュースが大きく載っていて、岡村さんは我が目を疑った。出土した石片などから、この遺跡は古代インダス文明の影響を受けた「太陽神殿」なのだと推測されているという。思わず「それは違う!」と心の中で叫んでいた。
◆モルディブにはスリランカと同じように仏教が伝わった時代があり、50年前にベルというイギリス人が幾つか仏教遺跡を発掘していた。それを知らないヘイエルダールが、仏教寺院特有の仏舎利塔を太陽神殿と見誤ったのではないか。そもそもヘイエルダールの太陽神殿伝播説そのものが学問的に証明されていない、うさん臭いものだ。でたらめな学説を放置していたら、それがそのまま定説になってしまう心配がある。モルディブと仏教遺跡の両方を知る者は、自分しかいない。そんな思いから83年の9月、とりあえず2週間の休暇を会社に申請してモルディブへと旅立った。
◆この旅の模様をつづったのが、『モルディブ漂流』(筑摩書房 1986)である。14年ぶりに訪れた島の変貌ぶりや懐かしい家族たちとの感動的な再会シーンも印象深いが、航海に出るといきなりいきいきとしてくる岡村さんの姿が手に取るようにわかって面白い。そして魔の海峡を越えてたどり着いたガン島で、ヘイエルダールが見た遺跡に到着した。最初は「なんだ、やっぱり仏舎利塔じゃないか」と思ったのに、スリランカのものとは違って四方に階段があり、傘蓋と思われる石片もぜんぜん似ていない。モルディブにヒンドゥー教が伝播していたという説もあり、自分が知らない謎の遺跡の前に立っているように思えて、混乱したまま旅を終えることになった。
◆帰国後、古代南アジア史を専攻する立教大学の小西正捷教授に写真を見てもらうと、やはり遺跡は仏教寺院で、石片もネパールなどに多いタイプの傘蓋だと即座に判明した。謎が解けたのはうれしかったが、子どものころに憧れたヘイエルダールの誤りを証明してしまって、複雑な心境になったという。
◆『モルディブ漂流』は優れた紀行文であり、テレビの「太陽神殿」取材チームとしてモルディブに送り込まれた植村直己さんとの競いあいや帰国時の邂逅シーンなど、ちょっとハラハラ、しみじみさせられるところもあって面白く読めるが、特筆しておきたいのは岡村さんの文章力である。「島々がゆらめいていた。」と冒頭の1行をいきなり書き始めるのは、高校時代から文学に親しんできた岡村さんにしかできない芸当だろう。なぜ14年もモルディブに行けなかったのかという逡巡も、深く胸を打つ。……今回もここで紙数が尽きた。モルディブから帰国後の岡村さんや私とのオシゴトの話は、次の機会としたい。[丸山純]
■今月のフロント原稿は南インドに出張している落合大祐さんが見てくれている。レイアウト担当の新垣亜美さんを校正仕事で助けてくれている武田力さんは青森県三沢で本業をこなしながらの作業だ。
◆私がよく引用させてもらう朝日や読売などの新聞、そしてNHKはじめとするテレビ媒体は「オールドメディア」としてしばしばネット民に笑いものにされている。まあ、笑わば笑え、私自身はどうしても活字人間の立場を放棄できない。
◆しかし、この2人やモンゴル・日本を軽やかに往復している大西夏奈子さんなどを見ていると地平線会議も相当変貌しているのだな、と痛感する。
◆今号は、丸山純さんの岡村隆追悼が読ませた。丸山君、岡村隆のこと、もっと書いてね。[江本嘉伸]
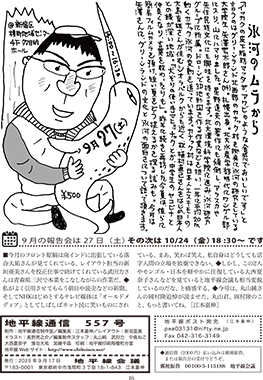 |
氷河のムラから
「イッカクの皮下脂肪マッタが、アワビのような食感でおいしいです」と言うのはグリーンランド北西部のカナック村を拠点に氷河の研究をしている大学院生、矢澤宏太郎さん(24)。札幌出身。北大水産学部時代にワンゲル部に入り、山にハマりました。星野道夫の著作にも傾倒し、アラスカや先住民族文化にも興味を持ちます。 北大環境科学院に進み、氷河研究グループに所属。ドローンで3D地形図を作る作業などを担い、一年に平均20m動くカナック氷河の変動を追っています。カナック村は日本人エスキモーの大島育雄さんが住むシオラパルクからも近く、故・植村直己さんをはじめ、日本人との縁が深い地域。 「犬ぞりの使い手マヒュッチャクとか、中学生のヤコビナと仲良くなり、言葉を教わったりも」。昨年に続き再訪した今夏は、彼らに簡易フィルムカメラを預け、短い夏をどう捉えるかを探る試みも。 今月は矢澤さんに、グリーンランドの文化と氷河の面白さについて語って頂きます。 |
地平線通信 557号
制作:地平線通信制作室/編集長:江本嘉伸/レイアウト:新垣亜美/イラスト:長野亮之介/編集制作スタッフ:丸山純 武田力 中島ねこ 大西夏奈子 落合大祐 加藤千晶
印刷:地平線印刷局榎町分室
地平線Webサイト:http://www.chiheisen.net/
発行:2025年9月17日 地平線会議
〒183-0001 東京都府中市浅間町3-18-1-843 江本嘉伸 方
地平線ポスト宛先(江本嘉伸)
pea03131@nifty.ne.jp
Fax 042-316-3149
◆通信費(2000円)払い込みは郵便振替、または報告会の受付でどうぞ。
郵便振替 00100-5-115188/加入者名 地平線会議
|
|
|
|
|
|