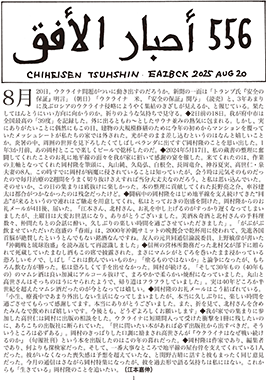
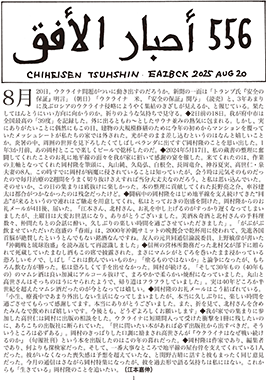
8月20日。ウクライナ問題がついに動き出すのだろうか。新聞の一面は「トランプ氏『安全の保証』明言」(朝日)「ウクライナ 米、『安全の保証』関与」(読売)と、3年あまりに及ぶロシアのウクライナ侵略にようやく集結のきざしが見えるか、と報じている。果たしてほんとうにいい方向に向かうのか。祈りのような気持ちで見守る。
◆2日前の18日。我が府中市は全国最高の「39度」を記録した。外に出るともわ〜としたサウナ並みの熱気に包まれる。しかし、実にありがたいことに偶然にもこの日、建物の大規模修繕のために今年の初めからマンションを覆っていたメッシュシートが私たちの家では外された。光がそのまま差し込むというのはなんと嬉しいことか。炎暑の中、周囲の世界を見下ろしたくてしばしベランダに出てすぐ岡村隆のことを思い出した。1年3か月前、あの岡村とここで楽しくビールで乾杯したのだ。
◆2024年5月17日、私の蔵書の整理に奮闘してくれたことのお礼に地平線の面々を我が家に招いて感謝の宴を催した。来てくれたのは、作業の主軸となってくれた岡村隆を筆頭に、丸山純、久島弘、白根全、長岡竜介、神谷夏実、高世仁・泉夫妻の8人。この時すでに 岡村が病魔に侵されていることは知っていたが、会う時は元気そのものだったので毎月治療の2週間をうまく切り抜けさえすれば当分大丈夫なのだろう、と私は思い込んでいた。そのせいか、この日の集まりは底抜けに楽しかった。本の整理に貢献してくれた長野亮之介、車谷建太は都合がつかなかったのは残念だったけど。
◆闘病中の岡村隆をはじめ地平線を支え続けてきた“同志”が来るというので連れはご馳走を用意してくれ、私はとっておきの泡盛を開けた。岡村隆からのお礼メールが4日後、届いた。「江本さん、北村さん、お礼を申し上げるのがすっかり遅くなってしまいましたが、土曜日は大変お世話になり、ありがとうございました。美酒&奇酒と北村さんの手料理数々、仲間たちとの会話に酔い、久しぶりの楽しい時間を過ごさせていただきました」。「がぶがぶ飲ませていただいた泡盛の『春雨』は、2000年沖縄サミットの晩餐会で乾杯用に使われて、先進各国首脳が絶賛したというとんでもない銘酒なんですね。友人の元共同通信論説委員、上野敏彦が書いた『沖縄戦と琉球泡盛』を読み返して再認識しました」
◆信州の営林所勤務だった北村父が部下に贈られて死蔵していたまむし酒もこの席で披露された。まさにマムシがとぐろを巻いたまま浸かっている恐ろしいモノで、しばし「これは飲んでいいものか」「塗るものではないか」と論争になったが、もちろん飲む方が勝った。私は恐ろしくて手を出せなかった。岡村が続ける。「そして30年もの(40年もの)のマムシ酒は良い加減にアルコール抜けて、まろやかで柔らかい焼酎になっていました。丸山と高世さんはそっちのほうにヤられたようで、帰り道はフラフラしていました」。実は40年どころか半世紀を超えたマムシ酒だったのが今となっては嬉しい。
◆岡村隆のお礼メールはこう結ばれている。「小生、療養中であまり外出しない生活になってしまいましたが、本当に久しぶりに、楽しい時間を過ごさせてもらって感謝してます。本当にありがとうございました。また、折を見て、北村さんを含めたみんなで飲めれば嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いします」
◆我が家での集まりに参加した高世仁は岡村に出版の相談をした。ウクライナに短期間入って受けた衝撃を1冊に残したいのに、あちこちの出版社に断られていた。「世に問いたい本があれば必ず出版社から出すべきだ。そういうところは必ずある」。岡村のきっぱりした口調に励まされ高世さんが『ウクライナはなぜ戦い続けるのか』(旬報社刊)という本を出版したのはこの年の暮れだった。
◆岡村隆は作家であり、編集者であり、何よりも探検家だった。そして、一番大事なところで地平線の屋台骨を支えてくれている1人だった。彼がいなくなった喪失感は予想を超えていたな、と関野吉晴に話すと彼もまったく同じ意見だった。今月の通信はさながら岡村特集になったが、彼を過去形で語る気持ちは私にはない。これからも「生きている」岡村隆のことを追いたい。[江本嘉伸]
■報告会の冒頭、江本さんから7月9日に亡くなった岡村隆さんを追悼するお話があった。私は法政大学の大先輩の岡村さんとは500回記念大集会で少しお話しただけであったが、そのときの岡村さんの穏やかにほほ笑む顔が忘れられない。40秒ほどの黙とうを全員でした後、江本さんは岡村さんの著書『モルディブ漂流』を紹介され、「この名著を文庫本のかたちで再刊できないか」出版元に働きかけていると伝えた。
◆本題の山田淳報告会にはいる。1979年神戸生まれ、地平線会議と同い年。7大陸最高峰登頂を当時の記録最年少の23歳でやり遂げる直前の2001年の7月「7S's トレンド化計画」のタイトルで261回目の地平線報告会を、株式会社フィールド&マウンテンを立ち上げた2010年9月には「Tシャツ、ジーンズ山ノボラーの福音」と銘打って(いずれも長野亮之介さんの命名)、377回の報告者として登壇している。恐れ多くも今回レポートを任された私は山田さんの自信に溢れた話し方とその視野の広い内容に吸い寄せられてしまった。
◆15年ぶり3回目の登場となる山田さん。今回は冒険や何かの成功とは一線を置き、今社会で何が起きていて自分には何ができてそのためにこれから何をしていきたいのか、という社会全体の展望を語る、地平線会議のなかでも画期的な内容であった。それもあって、今回のレポート担当の私がプレッシャーを持ったのはやむをえない……。山田さんのお話は登山をする人だけに限らず、日本の観光業や将来を考える多くの人にとって、刺激を感じる内容だったのではないか。7大陸最高峰、いわゆるセブンサミッツのことや起業にいたるまでの経緯については、過去のレポートを読んでいただきたい。ちなみに過去の報告会に彼は浴衣姿とスーツ姿で登場しているが、今回は普通のアウトドアマン、しいて言えば登山ガイドをやっているように見えなくもない格好で、見た目にとくにこだわりを持っているようには思えなかった。46歳になった彼はただ、圧倒的情熱を携えた語りのそれだけで独特な雰囲気があった。
◆当時最年少23歳でセブンサミッツをやったあと、4、5年間富士山でガイド活動をする。その後大学を卒業し、マッキンゼー社に入り3年働いた。毎日朝9時から翌朝5時まで働き、ものを考える余裕はなかったが仕事は充実して楽しかった。視野を広げたいと思い海外勤務にも出たが、2009年日本に戻ってきたそのころ、北海道のトムラウシ山で大きな遭難が起きる。この事故をきっかけに彼は「違う、自分は今見ているこういう遭難を防ぐために生きるんだ」と我にかえった。そして、ニュースを見た翌日に会社を辞めると伝えた。12月までは辞めさせてもらえなかったが、辞めたその翌年2010年2月にフィールド&マウンテンを起業した。
◆ちなみにその当時は江本さんが『岳人』に連載していたコラムでこの新しい事業のことを紹介し、それをきっかけに、377回目の地平線報告会にも呼ばれたのである。今回の報告会は、実は山田さんにとって富士山が開いている最繁忙期。その中でほんとうに偶然山田さんの予定が空いていた7月26日に、江本さんから頼まれ、引き受けたという。さすが江本さんの嗅覚は鋭い。ドンピシャに山田さんの唯一空いている週末を指定してきたので、これは断れなかったという。オンラインでの打ち合わせも、韓国に飛ぶ直前の羽田空港で対応したという。そんな慌ただしい中であったが、江本さんの方はお構いなしといった風であったとか。
◆トムラウシの事故でガイドと旅行会社の関係や、お客さんとガイドの責任の持ち方とか、構造的な問題があると山田さんは感じた。しかし、具体的に何が自分にできるのか分からない。自分がやりたいことをまず文字にしてみようと思って考えたテーマが、「登山人口の増加」「安全登山の推進」の2つだった。登山人口が増えると事故が増え、事故が増えると登山人口は減る、という波を2000年ごろから繰り返しているこの業界で、安全化を考えながら安定的に登山人口を増やしたいと考えた。
◆アクセルとブレーキのような関係のこの2つのテーマは、創業から15年ずっと変わっていない。現在、社員30人とパート100人の企業になったが、15年経営してきてわかったのは、創業者と会社は別物であり、会社の存在意義を代弁するのが自分の立場だということ。登山人口の増加のため・安全のためどうするかは、山田さん自身が考えるのではなくて、社員みんなが考える、そういう場を作るのが、自身の役目でもある——。地平線という場でまさに経営者だから言えることを述べる山田さんがかっこよかった。
◆「山に人が溢れている、危険な外国人が増えている、初心者ばかりで事故が増えている」とマスコミのネガティブ情報が流れる中、山に行く人は減ってしまう。その中で勘違いしている人が多いと山田さんは指摘した(山好きの私自身もまさにネガティブな思い込みもあったのだからその指摘に少しドキッとした)。しかし、山小屋は詰め込み主義をやめて定員制となったし、寝床も1人ひとり仕切りができて寝る環境は良くなった。そして最近の富士山の登山者数はコロナ前より少ないままだから、環境は明らかによくなっているはずだという。フレキシブルな働き方ができていないおかげで、登山客は土日祝日に集中し、どうしても混んでいるイメージを持ってしまうが、平日は逆にがらんどうなんてこともある。
◆インバウンドについても、日本に近い韓国の人と、遠いヨーロッパの人たちでは、お金の使い方やモチベーションが違う。何度も来ることができる人もいれば、一生に一度だけという人もいる。それを一言インバウンドという言葉でまとめることはできない。そもそも日本国内でもお客さんの考え方は異なって、たとえば、福岡の方は、日本アルプスなどは一生に一度の経験かもしれないが、東京のお客さんからすると何度も行けてレベルアップなども図れる。
◆言ってしまえばお客さんの扱い方が異なり、違う商品・違う売り方・違う請求の仕方があるという。そんな中で、世界中に、この日本の素晴らしい自然をどうやって一番価値高い状態で売ることができるのかを考えたい。受け身になるのではなく、誰かが仕掛けて安定的に増やすことをやらないといけない。みんなが好きな自然や山に行くために、その障壁をなくしたい。安定的な登山人口の増加と、安全のための知識・正しい情報を広げたい。そこで3つのキー、「道具・情報・きっかけ」という要点で、それぞれ事業を展開した。
◆まず、道具は「やまどうぐレンタル屋」というレンタル事業。富士山の去年の登山者数は約20万人だがそのうち4万人が山田さんの会社のお客さんという。ゲートが新たに設置されたことと4千円の入山料が設定されたことで登山者は減ったが、それでも突発的に富士山に来る人はいる(新型コロナ前には歌舞伎町で一晩飲んでその翌朝に富士山に来る人もいたそうだ)。そんな人たちには、例えば新宿で装備がそろえば安全に近づくことになる。
◆危ない人を止めるのは行政の役割であって、山田さんたちがやることは、危ない人を危なくないようにすることだ。学生登山にもレンタル付きでガイドする。中学生に侘び寂びの世界は早く、登山は厳しいと山田さんも感じるようだが、息の長い話、大人になったときに、また山に戻ってきてほしいという考え方で、12歳の子の10年後の登山人口を「買いに行っている気で」やっていると言う。
◆2つ目は、『山歩みち』というハンドサイズのフリーペーパー作り。フリーの小冊子にした理由は、雑誌を買わない時代になったのとハンドバッグに入る小さいサイズだと持っていきやすいから。そこに山の情報、安全の情報・知識を詰め込んでいる。これは富士山でレンタルしたお客さんにも配っていて、そこに載っている情報をもとに、富士山の次の山に行ってほしいと考えているためである。なので、情報の次にきっかけを作る。
◆3つ目のきっかけは、「Yamakara」という登山ツアー事業。2015年から始めたこの事業は、特に日本人向けだが、今は年間で一万人ぐらいの参加者がいる(今回の報告会の会場にもツアーに参加したお客さんが来ていた。お客さんというか、むしろ彼や彼の会社のファンといってもいいかもしれない)。1人増えたらクチコミでまた1人増える。3回以上山に行ったら、そのあとも続く。ただ安いというだけではなく、レンタルもつけるというようにして、きっかけはうまく作ることが重要だと言う。ツアーにはみんなレンタルを付けることで、ツアーをきっかけに縦走やテント泊、冬山登山を始めましたというお客さんもいる。
◆彼は「ビジネスプレゼンみたいになってますけど」と冗談も言いながら、グラフのついたスライドをいくつか見せて説明してくれた。富士山の登山者数は、2017年は28万人いたが、コロナ禍の2020年にゼロに。その後、回復したが、2024年は20万人。コロナ前にはまったくとどかずにそのまま低空飛行しているなか、インバウンドの登山者は2024年6万人で全体の約3割。コロナ前は1割程度であったのが、今は日本人の割合が減り、つまりコロナ前と比べると富士山に登る日本人は激減した。そんななかで、山田さんの会社のレンタルのお客さんは、2015年に2万8千人ほどだったが2023年は4万人。インバウンドのお客さんが増えてきている今、さらに右肩上がりだ。これをまわすためにレンタル道具も増やす必要がある。現在ザックの在庫が1万個、靴は毎年3千足くらい新たに購入して1万2千足ある。
◆2010年に立ち上げて最初にやったのがレンタル屋さんだったが、当初は短年で見ると利益が減ってしまう販売店からメーカーに「レンタル屋には卸すな」という大号令がかかって、逆風が起きたとか。すると東京中の販売店から吸い上げなくてはいけないという状況になり、2012年からは学生バイトにお金を持たせて神田中からザックや靴を買ってきてもらうということまでした。しかし、コロナ前後からはみんな直接やりとりをしてくれるようになり、今は落ち着いた状況になった。ツアーの現状は、2024年7月で750人だったのが今年は1200人に増えて、ざっくり1.8倍から2倍ぐらいの変化で伸びてきている。売り上げも拡大し、登山ツアー会社の中では2、3番目ぐらいの規模になった。
◆そんな今、彼がやろうとしていることは登山ガイドの正社員化。彼は、経産省が出しているデータをもとにして、人口減、低収入、若者の転職率の低さなど、日本社会の問題にまで話を広げて語ってくれた。ガイドという仕事はフリーランスが多く、収入が安定しないため将来ビジョンが描きにくい。登山ツアーはお客さんの年齢層が高く案内する側の方が若いという中、人口変動をもろにくらう業界になっているので、キーパーソンであるガイドの地位向上・定職化を図り、教育もしてガイド自体のクオリティをあげるという仕組みを作るようにしている。
◆たとえば富士山の仕事は7、8月だけだが、それ以外のシーズンは他の地域(海外も)組み合わせ1年を通じて仕事のある状態に安定させる。日本の若者は、他の国と比べても圧倒的に転職率が低い。最初は新しいことをやろうと意気込んで就職するが、そこで安定してしまって、その先は新しいことに挑戦しようとしない。そのため、登山ガイドも新卒や第二新卒で捕まえに行くしかないと考えている。なので、山田さんの社員は最近30人と増えてきたが、新入社員はほぼ20代だという。自然好きな若い人たちに入ってきてもらってここでガイド業をスタートさせている。
◆山田さんは、アウトドアや会社だけではなく、日本の将来についてもポジティブに考えている。ここで出てくるのがAIやロボット。サービス業や観光業は、AIが出てくれば出てくるほど、人間が勝つからである。レンタルの梱包や登山ツアーの企画はロボットがやってくれる。でも現場は、最後はやはり絶対に人間だ。だから、相対的に言うと、この先とてつもなく強い業界になる。
◆インターネットが出てきたときと同じようにAIやロボットの登場で世の中は、ぐるっと変わる業界とそうでない業界があり、そのどっちかになるという。Yamakaraではツアーをエンジニアでもある山田さんが作った自社のシステムで作成している。たとえば、ツアーで一人キャンセルが出たとき、その埋め合わせはシステムが自動でやりくりしてくれる。そうやって、人の手をかけるべきところとそうでないところできれいに切り分けた上で、生身の人間であるガイドが、企画担当が、旅行屋さんが、本当に専念すべきところに専念する。
◆言葉の壁もシステムがやってくれるからそれほど大きくはない。そうは言ってもスペイン語ができるようになった山田さんは今、韓国語と中国語を勉強している。最後共感することはやはり人間にしかできないから。日本の登山人口は600万人。人口の5%ほどだ。韓国10%、アメリカ18%に比べて低い。山田さんが今やりたいことは、日本の津々浦々の人たちが山に行ける状態を作りたいということだ。そのためのアイデアが実践されている。たとえばYamakaraの福岡の方たち向けの名古屋発着ツアーでは名古屋までの飛行機は指定したものを「自分で」取ってもらう。名古屋発着にすると新幹線でも帰りやすいからだ。遠かったイメージが、飛行機を使うと近くなる。同じようなことを韓国、香港、台湾の人たちにもやりたい、と話す。
◆アジア全体までは、自分の代で行けるかな、できれば東南アジアまで伸ばしたいが、ヨーロッパまではちょっと自分の人生的に、次の代に任せることになるかな、なんて、山田さんの夢は先を見据えてどこまでも大きい。そして、彼は「富士山」のクォリティを上げる必要があると強調した。富士山の次の山にも行ってもらうためにも、世界を相手にしているという意識を持ってしかるべきだと。民間企業のトップとしてやれることは、できるだけお客さんの方を向いた仕事をして、それでしっかり利益が上がる形を取って、社員に還元していくことであるという。
◆山好きを増やすことをしたいという思いは中学生のころから夢にあったといい、それを今かなえている事実が本当に凄い。安曇野に住む私が今回報告会レポートを依頼され、東京行きを決断したのは、山田さんがやっていることは私にとても大事なことだと考えたからだ。私は大学を出て4年間やってきた林業をこの冬に一度辞めてもっと広く山の世界に関わっていくために動こうと思っている。その私に山田さんの話は本当に刺激的だった。何よりもその視野の広さ! 彼が社会に働きかけようとしていることは、山に関わらない人間にとっても、大きな希望になるのではないか。彼の動向をこれからも追っていきたい[長野県安曇野市 林業4年目 小口寿子]
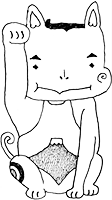
イラスト 長野亮之介
■江本さん、地平線の皆様、先日はホントにありがとうございました! 「この日しかない」ってドンピシャで僕の唯一空いてた週末を引き当てる江本さんの嗅覚、マジで凄すぎです!
◆10年以上ぶりだったけど、地平線会議の温かい雰囲気に包まれて、昔を思い出して懐かしかったし楽しかった。地平線のコミュニティの変わらない魅力に触れることができて、本当に嬉しかったです。あの場にまた立てたことに心から感謝しています。
◆今回、これまで社内だけで話してきた事業の展望や、社会に対する想いを改めて皆さんの前で話す機会をいただいて、自分の中でも頭の中がすごく整理できた気がします。今の日本の観光業って、インバウンドで活況を呈しているように見えるけど、まさに岐路に立っていると思うんです。だからこそ、浮足立たずに、落ち着いて本質的な価値を提供することが大事だと思っています。
◆結局のところ、事業を動かすのは人だから、関わってくれる人を増やして、みんなが一緒に成長できる環境を作っていくのが一番重要なんだと再確認しました。特に、ガイドは現場の要だと思うし、思いたい。彼らが誇りを持って働けるようにしていくことが、日本の山やアウトドア観光業の未来を作っていくことにつながると信じています。
◆世界に誇れる日本の山、そしてアウトドア観光業を、僕も少しでも関わって作っていきたい。そんな想いを強く抱くことができた、本当に貴重な機会でした。
◆ちなみにこの感想文、全部AIに書かせました(笑)。すごい時代になりましたね。[山田淳]
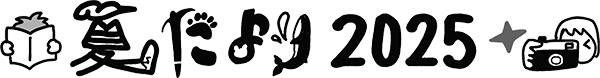
■8月9日、セルビア第三の都市ニシュ。ブルガリアまで100キロ地点にいます。4月19日にユーラシア大陸最西端のポルトガルのロカ岬をスタート。ポルトガル、スペイン、フランスと、巡礼路を4本繋いで歩く(2800キロ)。そのへんでシェンゲン協定の90日で時間切れに。4月の通信にここまでは書いていて、やってみたら、その通りだった。そこからEUの外に出ないといけないので、ボスニアに。
◆巡礼路を出ると、巡礼路がいかに守られた道であったのかが身にしみる。ブルガリアも入れないので、ここからイスタンブールに飛んで、どう動くか考えます。今、歩行距離は3500キロです。元気です。[坪井伸吾]
■今年の夏は、6月の北海道西興部の「夏至カブ」イベント参加(+観光)から始まった。旭川で気温は30℃。旭山動物園の羆は元気に檻の中を動き回っていた。暑い日に登山すれば羆は活動してないから大丈夫!という勝手な思い込みは打ち砕かれた。西興部でウエンシリ岳に日帰り登山したが、羆とニアミスした。私達夫婦の少し先行のカップルが、獣臭と大きな足音、そして鼻息も聞いたそうだ。ドキドキドキ……。
◆7月は八ヶ岳の天狗岳登頂後に黒百合ヒュッテ泊、長岡ご夫妻の演奏でアンデスの世界にトリップ。白馬岳の大雪渓も初体験。8月は、早池峰山、西丹沢の沢登り、北アの双六岳と、登山三昧の夏は続く……。[古山もんがぁ〜里美]
■今夏から会社業務の一環で、「公益財団法人・知床自然アカデミー」のオンライン講座を受講しています。企業のサステナブル活動で今回受講することになり、先日オンラインで釧路湿原のタンチョウについて講義を受けました。この知床自然アカデミーは地平線でもお馴染みの梶光一さんが代表理事をされています。そのことをホームページで知り、自分の価値観のルーツに近づけたようで嬉しく思いました。
◆快適さも不快さも受け入れて、自然の中で活動することは自分の価値観の土台です。今はオンライン講義ですが、いつか出張で知床に行けたらと。明日からは子どもたちを連れて広島に帰省します。太陽の日差しが突き刺さる猛暑ですが、子と一緒に瀬戸内の海で泳ぐのが楽しみです。[山本豊人]
■5月の地平線報告会で、エベレスト日本女子登山隊の思い出をお話させていただきました。見渡せば、ドクターを除く隊員14人のうちすでに7人が物故者。私はなんだか「過去を語る語り部」おばあさんになった気分でした。そんな中、登頂50年を機に、田部井家の家族物語を題材にした映画がつくられ(主役はなんと吉永小百合さん!)、私の旧著「ピッケルと口紅」が映画の参考資料になった縁で、文庫化されたのです(山と溪谷社刊 税込1210円)。
◆今月18日には書店に並ぶとのこと。よかったら読んでください。「昔読んだよ」という方、新たに書き加えた「少し長いあとがき」もあります。彼女の七大陸達成後、田部井さんと私、二人の山好きオンナが老いていくという、ちょっと黄昏色の物語。でも、私には印象的な夕焼けでもあるのです。これをばねに、今は日本女性登山史を書いています。今年中に仕上がるのかしら?[北村節子]
■今、カメルーンの首都ヤウンデにいます。ここは比較的通信状況がいいため、メールも送受信できます。明日移動する予定のチャンでは通信はかなり不如意になると思います。それで今のうちにと、メールしました。
◆こちらの8月は雨季のはずなんですが、今のところまだあまり雨が多くないようです。毎朝どんよりとした曇り空ですが、降りそうで降らない。降り出すとすごいそうですが、この2日、まだシャワー程度の雨しか経験してません。
◆3月の乾季にきたときはとにかく埃っぽくて、植物も赤土を被り、緑が見えにくい状況でした。雨の季節になって一変しているかと思いきや、例年より雨が少ない上、ここヤウンデは一応都市なので、風景はあまり変り映えしません。気温は25度ほどで、夜は肌寒いくらい。ヤウンデは標高730mですが、チャンはさらに標高が高く(1400mくらい)、もっと涼しいようです。なんだか、アフリカに避暑に来たような感じです。[長野亮之介 8月14日]
■デナリで35年気象観測をしていた大蔵喜福さんと奥様、1989年に遭難された小松幸三さんの奥様らが先日、タルキートナ倉庫の片付けを兼ねて来アラスカした。私はチリから急遽帰国、直会をする機会を得た。加えて、今年はビリーこと児玉壮太君率いる第2次デナリ隊発足で女性4人を含む9人の若者たちが登頂し、測器回収もできた。ビリーは登頂だけではなく、人類がまだ知らないデータを取ろうという意欲がある若者だ。
◆体力は若いとき、精神力は歳とってからと思っていたけど、どちらも若いときが一番だとやっと気づいた今日この頃、自己管理能力が遥かに劣って思うように体力調整が進まない! あと4か月で前人未到の穴掘りが出来るのか? これからが正念どころ。[吉川謙二]
■6月、三重で開催する自分の写真展の準備をしている途中、帯状疱疹がやってきました。その3日後に小さな写真賞の受賞通知がきました。そのとき、帯状疱疹があまりに痛く、お断りしようかと一瞬思ったのですが辞退はややこしい。日本医学ジャーナリスト協会というのがあります。そこで「離島医療」をテーマにシンポジウムをしていただけることがやや決まり、チャンスです。離島医療の課題を知って欲しい。その前から沖縄の医師が書く島の医療の日常を本にするサポートをしていました。
◆私は5年前に心臓に突然死の波が出ています。それから5年生き延びたのです。それより後に病気になった岡村隆さんの方が先に逝ってしまうなんて……と薬の副作用もあって、心のなかは混乱し、ふらつきから道をまっすぐ歩けない日々が続きました。薬の量が減って、少し正常な判断力を取り戻しました。今まで、仕事の量に押しつぶされていました。限界を自覚し、クリアーな生をまっとうしたいと願い、500グラムの軽量ライカで日々、今までとは違う感覚で娘・夏帆の写真を撮っています。[河田真智子]
■先日、アラスカより帰国しました。猟が始まる直前の3月にキャプテンの奥さんが亡くなるという、思いもよらない出来事から始まった今年のクジラ猟は、到着前に13頭もクジラを捕獲。そのうち2頭は我々のクルーによるものでした。町に着いた翌日に最後の1頭がとれ、4月中にクジラ猟は終了。相当暇になるかと思いきや、肉の処理や雑事がたくさんあり、例年以上に忙しい。
◆今年は4月の頭から北風が吹き続け、猟場となる町の南の氷は、はるか沖合に吹き流され、4月から広々とした海面が見えているという、いつにない異様な光景。氷がないけれど、気温は低く寒い春。その後、6月中旬になって、ようやく南風が吹いて氷が戻ってきて、7月上旬に町を離れるまで、海には氷があるという、まるで90年代のような状態(地元の人談)になっていました。南風とはいえ、氷の海を越えてくるので、冷たい風です。
◆帰る直前に岡村隆さんの訃報。前回、地平線報告会で猟の話をした際には「用事があって行けなかった。次回は是非」とコメントをFacebookでいただいていたのでまたお話しできると思っていたのに、残念でなりません。涼しいところから戻り、暑さと時差ボケでぐったりしていますが、会社にも復帰するので、そろそろ動かないと。北海道で40度になるなど、おかしな気候がつづきますが、お気をつけてお過ごしください。[高沢進吾]
■北海道大学修士2年の矢澤と申します。現在グリーンランド北西部カナックへ移動中です。修士論文とArCS-3の調査の一環で滞在しますが、私の計画について簡単に説明させていただきます。まず氷河観測についてです。今年はカナック氷河とボードイン氷河の2つの氷河での観測を予定しています。
◆カナック氷河では、2012年から10年以上にわたってモニタリング観測が行われており、私はドローンを使って測量します。この観測は、衛星画像からでは見えない標高変化や氷流動を広範囲で測定でき、氷河変動への理解に役立ちます。ボードイン氷河でも同様にドローンを用いた測量を行います。こちらの氷河は海洋に流れ込む氷河で、カービングと呼ばれる氷が切り離される現象による氷損失を定量化したいと考えています。
◆次に文化的調査について。使い捨てフィルムカメラを現地住民に配って、夏のカナックでお気に入りのものを撮ってきてもらいたいと思っています。写真から小さな空間で生活している先住民の夏の楽しみが見えてくると嬉しいです。また、雪や氷の表現、言葉について興味があります。アラスカやアイスランドでは生活に根ざした雪の名称が細かくついていると聞いたことがあります。グリーンランドは口伝えの文化であったため、書き記されているものは多くありません。そこで、雪や氷に関わる言語を、コミュニケーションの中で現地住民から引き出せたらいいと思っています。
◆氷河と文化の大まかな計画です。特に文化の方はどこまでできるかわかりませんが、有意義な滞在にしたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします[北海道大学 矢澤宏太郎 7月22日]
■2026年初秋に予定している北海道での地平線会議を成功させるため、1万円カンパを募っています。北海道地平線を青年達が集う場にしたい、というのが世話人達の希望です。交通費、宿泊代など原則参加者自身の自己負担としますが、それ以外に相当な出費が見込まれます。趣旨お汲み取りの上、北海道上陸作戦にご協力ください。[江本嘉伸]
賀曽利隆 梶光一 内山邦昭 新垣亜美 高世泉 横山喜久 藤木安子 市岡康子 佐藤安紀子 本所稚佳江 山川陽一 野地耕治 澤柿教伸(2口)神尾眞智子 村上あつし 櫻井悦子 長谷川昌美 豊田和司 江本嘉伸 新堂睦子 落合大祐 池田祐司 北川文夫 石井洋子 三好直子 瀧本千穂子・豊岡裕 石原卓也 広田凱子 神谷夏実 宮本千晴 渡辺哲 水嶋由里江 松尾清晴 埜口保男(5口)
今月分 田中雄次郎 岸本佳則 ささきようこ 三井ひろたか 山本牧 岡村まこと 金子浩 平本達彦・規子 渡辺やすえ 久保田賢次 滝村英之 長塚進吉 長野めぐみ 北村節子
★1万円カンパの振り込み口座は以下の通りです。報告会会場でも受け付けています。
みずほ銀行四谷支店/普通 2181225/地平線会議 代表世話人 江本嘉伸

■7月半ば、アルハンガイ県の大草原でおこなわれる「ARA(アラ)」という音楽フェスティバルを訪れた。ロックやヒップホップなどのライブが、なんと1カ月も続く。友人たちと私はARAで2泊してウランバートルへ戻る予定だった……が、だれかが「モンゴル北西端のオブス県へ行こう」と急に言い出し、私も着の身着のままで道連れに。1,000kmの道のりを中古プリウスで爆走してオブス県に入ると、越えても越えても山があらわれる! 岩だらけの坂道にぶつかるたび、何度も車を降りて後ろから「1、2、3!」と人力で押すことを繰り返し、40〜50の山を越えて(ゼーゼー)、ようやくヒャルガス村に着いた。
◆村では、女の子たちがお化粧して浮き足立っていた。今晩から、村の学校の創立100周年記念祭がはじまるという。やがて昭和っぽい音楽が聴こえてきて、ちいさな広場で青空ディスコがスタート。民族衣装のデールを着たおじいさんが、腰をかがめたゴーゴーダンスではじけていた。
◆翌日、友人のバイト先の後輩の実家だという遊牧民宅を訪問。村から離れた山の上にあり、人工の音が何もない。聴こえてくるのは、ンモーーーという牛の低いダミ声、ブルッという馬の荒い鼻息、メエエという子羊の頼りない声ばかり。そういえばあるホーミー奏者が、「子どものとき、ひまだから家畜の声を真似しているうちに、喉の筋肉が鍛えられてホーミー歌手になった」と話していたのを思い出す。
◆ここのゲルに暮らす遊牧民のお父さんとお母さんは、100周年を迎えた学校の同級生として出会った。もう35年のつきあいで、互いを思いやる仲の良さが素敵。突然やって来た私たちのために、お父さんは大事な羊を一頭ほふり、野生のタルバガン(シベリアンマーモット)も捌いてくれた。夫婦ともジョークが好きで、家事の手を忙しく動かしながら笑い話がとまらない。モンゴル人は総じて冗談が好きだけれど、仕事も生活も家族で支えあう遊牧民にとって、「楽しく会話する」ことは円滑に生きるための生命線なのだろうと思った。翌朝ここを離れるとき、お母さんが手縫いの青色のベストを私にプレゼントしてくれ、何も与えられなかった私たちのためになぜここまで?という驚きとともに、お別れした。
◆さらに北上し、私たちは巨大なオブス湖に到着してキャンプした。対岸はロシアのトゥバ共和国。最果てにある湖は人の気配がなく、白い鳥がやたら元気に飛び回る。グワッグワッという奇妙なうるさい鳴き声に、こわいほどの強い意志を感じ、人間のいない土地だと鳥はこんなに活き活きするものなのかと、覗いてはいけない世界を見てしまった気がした。
■先月の通信でお知らせして以降、通信費(1年2000円です)を払ってくださったのは以下の方々です。万一記載漏れがありましたら必ず江本宛メールください。通信費を振り込む際、通信のどの原稿が面白かったかや、ご自身の近況などを添えてくださると嬉しいです(メールアドレス、住所は最終ページにあります)。
橋口優 永井マス子 金子浩 高橋千鶴子 市村やいこ ささきようこ 相田忠男 津川芳己 下司啓太 氏名不詳氏
■小松由佳さんのあらたな作品『シリアの家族』(仮題)の開高健ノンフィクション賞受賞が決まりました。ほんとうに素晴らしい!! まだ原稿の段階ですが、一気に本としての刊行は進むでしょう。
◆正式な授賞式は11月21日、帝国ホテルで集英社4賞の贈賞式として行われる予定です。この賞は、原稿段階での審査というやり方なので集英社インターナショナルによると本としての発売予定は、11月26日を目指しているとのことです。その段階で是非あらためて報告会を開き、お祝いをしたい、と考えています。[E]
■今や渋谷スクランブル交差点は、世界中から最先端没落先進国のお気軽ニポンへ、円安グルメおもてなしを求めて押し寄せるインバウンド訪日客の聖地。俗っぽい観光名所のNYタイムズ・スクエアやロンドンのピカデリーサーカス、パリのシャンゼリゼ大通りに劣るとも勝らないセルフィー名所となっている。この空間の上空に、その昔ロープウェイが行き交っていたことを知る人は少ない。「ひばり号」という12人乗りの子ども専用ゴンドラで、旧東横百貨店本館から忠犬ハチ公銅像をかすめて、向かい側の玉電ビルを結ぶ全長75メートル、秒速0.5メートルの空中散歩が楽しめた。当年99歳を迎える渋谷ジモティーの母は、1951(昭和26)年から2年間だけ運行されていたこのひばり号の目撃者である。
◆詳細は『渋谷上空のロープウェイ——幻の「ひばり号」と「屋上遊園地」の知られざる歴史』(夫馬信一著・柏書房刊)にゆずるとして、渋谷駅から青山通りを直進した表参道界隈の山の手一帯が、一面の焼け野原になったことを知る人はさらに少ない。東京大空襲といえば80年前の3月10日未明、帝都トキオの下町一帯が325機の戦略爆撃機B-29による空襲で焼き尽くされ、10万人もの戦災死者の出た夜が記憶に刻まれている。
◆が、ニポン本土に対する空襲は前年6月の北九州から本格化し、終戦の詔勅が出される敗戦当日まで、全国の大中小都市は絶え間なく爆撃に晒された。ご丁寧なことに、終戦当日未明の玉音放送12時間前に大阪砲兵工廠はじめ、熊谷や伊勢崎、岩国ほか全国6都市が爆撃され、わずか半日違いで約2000人が帰らぬ人となった。
◆人口密集地域に於ける非戦闘員への無差別爆撃は明らかに戦争犯罪だが、フランコ将軍によるスペイン内戦時のゲルニカに始まり、ナチス・ドイツのロンドン大空襲、連合国によるドレスデンやフランクフルト空襲、大ニポン皇軍による重慶や上海への絨毯爆撃など、最大被害をもたらす効果的な作戦となった。軍事施設や軍需工場を精密爆撃で叩くより、広く一般市民に被害を与え戦意喪失させるのには有効だった。
◆5月25日未明の山の手大空襲は3月10日を上回る470機のB-29が3300トンもの焼夷弾を投下、渋谷から青山、赤坂界隈は火の海となった。畏れ多くも皇居内の明治宮殿まで焼け落ちたその晩、青山通りと表参道の交差点、旧安田銀行(現みずほ銀行)の角で、私が会ったことのない母方の祖母、つまり母の母は戦災死した。一晩で3600人を超えた犠牲者の中の一人だった。わずかに焼け残った写真と、母の話からかろうじて想像するには、静かで控えめな女性だったようだ。朧げにしか浮かんではこないが、やさしそうな祖母と一度は話してみたかった。
◆世界のトップブランドのフラッグショップが立ち並ぶオサレな表参道だが、青山通り交差点の両側に立つ大灯篭は、台座の一部が欠け落ち、ところどころ黒く変色したその夜の痕跡が今も刻まれている。近隣では表参道交番の後ろ角で今も営業する1891年創業の山陽堂書店と、向かいの安田銀行だけが石造りの建物だった。かろうじて山陽堂に逃げ込んだ100名ほどを除き、青山墓地や明治神宮の杜に避難しようとした地元住民は、火炎に焼かれ火だるまとなった。翌朝、安田銀行前の通りは、2階まで積み重なる焼死体で埋め尽くされていたという。
◆茅ヶ崎に疎開していた母は帝都壊滅被害甚大の報を聞き、東海道線も止まり両親の安否も不明な中、歩いて渋谷を目指した。飲まず食わずで歩き続けること3日、多摩川の橋も通行不能で、かろうじて残っていた小田急線の鉄橋を歯を食いしばり四つん這いで渡った。玉川通り(国道246号)を三軒茶屋から三宿に差し掛かったあたりからは、粉塵と悪臭に息もできない状態となる。ようやく道玄坂上に着いて目にしたのは、焼け野原に神宮外苑の絵画館と国会議事堂だけが残る凄惨な光景だった。
◆瓦礫の山をよけながら宮益坂を上り、青山学院に近い実家にたどり着いたちょうどその時、戸板に載せられた炭の塊のようなものが運び込まれてきた。表参道の角で見つかった母の焼死体だった。「見るなっ!」という父の怒鳴り声が響いたが、声も涙も出なかったという。どんな気持ちで茅ヶ崎から歩き続けたのか、その心中を思うとただ胸が詰まる。
◆毎年5月25日には、犠牲者を供養する追悼法要が近隣の古刹善光寺別院で今も営まれている。その日、ご近所の行きつけ老舗カフェJ-Cookでランチなんぞいただいていて、ふと思い出した。以前から気になっていて、戦後80年を迎える今年がラスト・チャンスになるかも知れない。善光寺でご遺族に混じって法要に参列、ご焼香を済ませたあと、表参道に立てられた追悼碑「和をのぞむ」前に移動。節目の年に取材も多く、行き交うインバウド観光客はふしぎそうに眺めている。
◆テレビ番組のインタビューに答える戦災体験者に直撃、当夜の状況を確認したかったのは、地下鉄銀座線が開通営業していたにもかかわらず、なぜ構内に避難できなかったかという長年の疑問だ。真珠湾奇襲攻撃の前月、帝国議会で「空襲時に地下鉄構内や施設に避難することはまかりならん」という政府方針が示された。空襲時には身を挺して消火に努めるのが国民の義務で、駅にいた人々は追い出された。避難するのは非国民という訳だが、実際の現場ではどうだったのか、これまで2、3回参加した法要ですれ違った記憶がある、常連の地元住民ご老人にうかがってみた。
◆当時14歳の軍国少年は、自宅があった骨董通りから避難しようとしたが、四方八方が燃え盛る火の壁のようだったそうだ。青山墓地を目指したご尊父とは現ヨックモック前ではぐれ、翌日すぐそばでご遺体が見つかったとのこと。地下鉄に逃げ込むなどとは、考えもしなかったという。東京大空襲のあとに発出された「中央防空計画」では、軍事最優先で聖戦遂行の妨げとなる避難行為はご法度、つまり帝国臣民の命は後回しにされていた。「生きて虜囚の辱めを受けず」と降伏を禁じ玉砕自決を強いた軍人に対する戦陣訓より先に、招集された訳でもない臣民は空襲から逃げずに立ち向かうよう命じられていた。
◆英独空軍のバトル・オブ・ブリテンが展開される中、1940年に始まるロンドン大空襲「ザ・ブリッツ」では、市民17万人が80駅に避難。構内には医薬品から2段ベッドまで用意されていた。激しい空襲から市民を守るために公共施設が積極的に活用され、犠牲者の軽減に貢献した。実際モスクワや平壌などの大深度地下鉄は核攻撃にも耐えられる構造だし、現にウクライナでは空襲警報のたびに防空壕として利用されている。キーフの地下鉄アーセナルヤナ駅は世界最深の地下105.5メートルで、イランの地下核施設を爆撃した最新のバンカーバスター弾GBU-57ミサイル(地下到達深度60メートル)でも余裕の深さだ。80年前の帝国臣民は避難すれば助かる施設がありながら、江戸時代と大差ないバケツリレーとモップのような火たたきで焼夷弾火災と闘うことを強いられた。
◆そもそも、本土空襲に向け開発された焼夷弾は正確には集束油脂焼夷爆弾、つまりクラスター・ナパーム爆弾だ。ガソリン放火の威力は京アニ事件などでも明らかだが、ガソリン原料のナフサとパーム油を混ぜゼリー状の「ナパーム」にして建造物や人体への粘着性を高め、さらにマグネシウムや燐を加えて水では消火不能にしたものがその正体。地上から600メートル上空で親爆弾が開裂し、38発の子爆弾が飛び散る構造で、紙と木で作られた日本の住宅をいかに効率よく燃やすか、ユタ州の砂漠に日本村を建設して燃焼実験が行われた。「火事と喧嘩は江戸の花」と詠われた江戸時代の大火から関東大震災まで、歴史上の記録を調査し、高射砲や迎撃戦闘機の攻撃を避ける夜間低空侵入戦法を採用。春一番のような強風が吹く夜を狙った。
◆焦土作戦を指揮したのはカーティス・ルメイ司令官で、当時の新聞では「鬼畜ルメイ」とか「皆殺しルメイ」と報じられていた。朝鮮戦争やキューバ危機、ベトナム戦争でも核兵器の使用を唱えた危ないヤツだったが、1964年12月7日ニポン国政府は彼に勲一等旭日大綬章なる最高位の勲章を授与した。航空自衛隊創設育成に多大なる貢献あり、と推薦したのは某・子鼠新次郎の祖父だが、裏で手を回していたのは某・大勲位中曽根と元大本営参謀で参議院議員の某・源田実だったそうな。さすがに、畏れ多くも国体護持のシンボルであらせられた昭和天皇は、慣例の勲章親授を避けたという。
◆空襲という視点から戦争の実態を描いた『日本列島 空襲の記録』(平塚柾緒編・講談社学術文庫)によれば、制海権を失った時点で生産力が激減し、戦争遂行は不可能になっていた。空襲による戦意喪失で、本土決戦など続けられる状態ではなく、要するに最初から企画ミスだったということだ。国家生存のためには滅亡も辞さないという過ち!
◆推計310万人と言われるニポンの戦争犠牲者だが、亜細亜太平洋全体では2000万から3000万ぐらいの人々が亡くなったとされる。それは単に数字ではなく一人一人の思いや記憶と物語があり、同時に現在進行形で戦争継続中の今日を問いかけてくる。ガザで飢える子どもも、ウクライナで闘う兵士も、その陰に忘れ去られているスーダンやエチオピアの内戦に逃げ惑う難民も、一個人として自分の眼前に思い描くことが出来るだろうか。AIとドローンによって戦争の形態が激変した昨今、さらに重い問いが突き付けられる。
◆ちなみに父一人娘一人で終戦を迎えた母は戦後クリスチャンになり、赤坂霊南坂教会幼稚園の教員を務めた。まだ闇市のようだった渋谷駅前で、冒頭のひばり号乗り場に並ぶ子どもたちの歓声を耳にし、ようやく戦争が終わり自分は生きていることが実感できたという。大東亜聖戦敗北と無条件降伏から80年を数える猛暑熱暑酷暑の夏、余計なおせっかいで一文を記す。[Zzz-Z@カーニバル評論家]
■岡村隆が逝った。あたかも目の前で突然雪庇を踏み抜いて雪壁に消えていったかのように。その短い墜落の間に、岡村隆は死を受け入れ、生を幸せと感謝と総括して逝った。うらやましいほどに見事だ。墜落の時間は短い。その短かさの中では耐えがたい痛みや息のできない恐怖も二の次になり、意識は事態と己が人生の本質を冷静に直観していた。そうであったと願いたい。そんなことを思うのもご本人の簡潔ながら率直な病状・闘病報告と関野医師の的確な補足解説があったおかげで、岡村の覚悟を皆で察していたからだ。ありがとう。
◆岡村はその諸活動を含めて岡村隆なのだが、時とともに、特にスリランカと本格的に取り組み始めてからは、わたしにはその仕事の成果よりも彼の気高さと知性と愛情のある人格全体への信頼感が増し、居てくれるだけでよい仲間、という存在になっていた。
◆友がまた一人去った。といってもわたしは岡村君とそんなに親しくしていたわけではない。観文研(近畿日本ツーリスト株式会社内の半独立部門)で出会ったときから10歳近く歳が上だ。当時観文研には向後元彦がいてAMKAS(あるくみるきく動アメーバー集団)という活動拠点を作っていた。向後はツーリストの馬場勇副社長と意気投合し、その求めを受けて探検を志す若者たちのネットワークづくりと活動の方法を模索していた。
◆最初の成果が平靖夫(法政大探検部創設者)や森本孝(立命館探検部)他諸大学の探検部系の若者たちと白馬岳山麓の法政大学山荘で開いた「たんけん会議」だ。60人ほどが集まりテーマを分けて3日間夜を徹して議論したと聞く。向後は企業につながる立場での拠点として観文研にAMKASなる場をつくり、会議の提言に沿ったいくつものプロジェクトをスタートさせる。岡村も先輩の平とともに同時代の探検的活動データーベースづくり(こうした作業モデルが後に森田靖郎や白根全による『地平線から』に展開した)を観文研のアルバイトという形で進める一方、「AMKASレポート」の一冊として『イスラーム世界のふたつの割礼』(法大探検部調査隊と早大探検部調査隊の共著)、『戦後学生探検活動史』(平靖夫との共著)を出した。さらに『セイロン島の密林遺跡一』『セイロン島の密林遺跡二』を出す。
◆しかしここで岡村の観文研での出番は終わる。向後も食わねばならず、観文研を去ったからだ。向後抜きでは金のかかる仕事はつづけられない。岡村のやっている探検の意義は素人のわたしにもわかり、『密林遺跡二』は無理矢理出せた。が、『密林遺跡三』は出せなかった。報告書は次の資金集めには最強の武器になる。それができないとすれば、せめて写真を見せられないか。わたしは白黒写真なら自宅で処理できたから、岡村が持ち帰ったフィルムを現像し、プリントし、また写真の濃淡を70線ほどの網点の大小に変換した網点写真の形でも焼いて渡した。それなら安価な軽印刷でも写真が使える。岡村に報いてできたのはそこまでだった。
◆それから岡村との縁は「学生探検会議」を経て「地平線会議」の発足の場に移る。江本家が膝を曲げて座ることしかできないほどにすしづめだったのを思い出す。メンバーや形の決まった組織ではなく、ひとつの渦のような場であること、やるべきだと思うことはそう思った者が世話人となってやるが、基本的に自前でやることなどが決まっていった。では名前をどうするか。いろいろ出たが、名前は内容を縛る。岡村が「地平線」と言った。わたしも脳裏に浮かんでいた言葉だったので推し、みなもすっと受け入れた。その後は自分の身にもいろいろあったし日本にいなかった時期もあるので、遠目にしか岡村を知らない。
◆だが今の目で見て、それから何年間かの食うことにからんだ岡村の模索は彼に必要な基礎訓練をすべて与えたのかと思う。さらに時が経ち、街道憲久が経営に苦しんでいた東海教育研究所の社長を引き受け、岡村を月刊誌『望星』の編集長に迎える。街道は東海大極地研究会の仲間たちとわたしをカナダ北極圏に誘い出し、ろくになすすべもなかった秋冬を共にもがいた男だ。『望星』は意志のある雑誌になり、教えられ考えさせられる内容が増えた。ただ遠くから見ているわたしの目には少し固い気がした。編集の価値観が少し観念的で生真面目すぎないかと。でも実際はこの時期岡村は猛勉強を続けていたのだと思う。観念を超え、思想にしていったのだと。いつしかわが妻も愛読者になっていた。
◆その成長を支えたのは『望星』での苦闘の他に2008年頃だったか岡村が発足させると案内をくれた「南アジア遺跡探検調査会」の運営と実践が大きかったのだろうと思う。わたしも一灯を献じ、一度研究会を聞きにいった。語り手は静かで、若い参加者はみな真面目だった。わたしは相変わらず遠くから見ていただけだが、岡村のやろうとしていることの広さと誠実さを実感し、納得した。しかし時間は必要で、花開いたのは岡村が『望星』から離れた後だろう。探検の現場に立つ実感と喜び、失望、次々に立ちはだかる難題と克服、後輩たちの訓練、そして責任。肉体と現場がすべての観念的なものを超えさせてしまったように見え、嬉しかった。安心して信頼できた。
◆事実、福田晴子の労作『宮本常一の旅学』の刊行前、わたしの心の老いがなによりの障害になっていたとき、声をかけた訳でもないのに、わたしの知らないところで、黙って進行に必要な評価と判断や著者への励ましをしてくれていたのは森本孝と岡村隆だった。岡村は優しくて気高くて、誠実な大人になっていた。わたしは岡村とそんなに親しくしていたわけではない。だが間違いなく仲間であり、友であった。
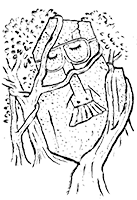
イラスト 長野亮之介
■今も、「おー、セキノよー!」と、声を掛けられるような、ほぼ1か月過ぎたが、岡村隆さんが生きているような感覚がまだ続いている。あまりにも急な死だったからだろう。
◆亡くなる4日前に留守番電話が入っていた。腹を括ったお別れの電話だった。そこには死期が迫っている報告連絡なのに、岡村さんらしい気高さがあった。岡村さんは仁徳があり、人付き合いも幅広かった。その多くの人に、じっくりと直接に別れの言葉を告げたかったのだろう。あまりにも急でそれは叶わなかったが、私には言葉を残してくれていた。岡村隆が私の留守電に残した最後のメッセージを地平線の皆さんにお伝えする。
◆「もしもーし、岡村隆です。とうとう白血病になってしまった。もうそろそろ明日、明後日という、今日明日かなということになってしまいました。九州で木の伐採などの疲れたせいではないとドクターから言われました。まあ来るべきときが来たということかな。いよいよという感じになりました。色々と若いころからお世話になりました。俺もなんか関野みたいにずっとやっていきたかったのだけど、途中で、老齢での引退と、なってしまったんだけども、ここまでやってこれたことで良しとするしかないかなあと思ってます」
◆骨髄異形成症候群の予後は決してよくない。平均5年くらいだが、10年以上元気でいる人もいる。それが2年で重症化してしまった。私だったら、不意の死の訪れに狼狽あるいは発狂してるかもしれないが、岡村さんは「ここまでやってこれたことで良しとするしかないかなあと思ってます」という。すでに現状を受け入れていた。家族、ドクターには、積極的な延命措置をとらないと告げていた。
◆身体では、とんでもないことが起こっていた。造血器官である骨髄の中で正常な白血球、赤血球、血小板がまともに作られない状態になっていた。鬼っ子ともいうべき何も役に立たない芽球細胞が、12万、最後は20万と増えていったのだ。身体は酸欠になり、免疫力は減退、出血しやすく止まりにくい状態になっていたはずだ。モルヒネ、睡眠剤を使わなければ耐えられない状態になっていった。
◆岡村さんとはもう56年の付き合いになる。10代からの付き合いだ。一橋大学に入学後すぐに探検部を創った。先輩がいないので、社会人山岳会に入ると共に、早稲田大学、上智大学、法政大学探検部の部室にお邪魔して、活動内容を聞いた。法政大学の部室にお邪魔したときに出会ったのが最初だった。その後、時々部室にお邪魔するようになった。そのとき、岡村さんは、独立直後で鎖国状態のモルディブに行く準備をしていた。その後、特例で入国、日本人初の長期滞在者となり、半年間の民俗調査ののち、ライフワークともいうべきスリランカの密林遺跡探検に転じたのだ。準備で忙しい中、親身にアドバイスをいただいた。その後も平靖夫さんが音頭をとって行われたたんけん会議、観文研、その後地平線会議などで頻繁にお会いするようになった。
◆さらに岡村さんと距離が縮まったのは1991年、私が20年間の南米の旅が終わって、新しい旅を始めようとしたときだ。そのころ最も信頼していた上智大学の探検部OB野地耕治さんに新しいプラン(グレートジャーニー)の概要を説明した。野地さんはすぐに昔からの仲間に電話をかけた。そしてすぐに野地さんの事務所崑崙企画に集まった。惠谷治早稲田大学、岡村隆法政大学、街道憲久東海大学、坂野皓早稲田大学の4人だ。野地さんは少し先輩だか、4人はほぼ同年代だ。
◆この5人でグレートジャニー応援団が結成され、惠谷が応援団長、野地さんが事務局長になった。揃いもそろって金はないが、油の乗り切ったフリーのジャーナリスト、ライター、映像ディレクター、編集者だ。「今までは、ライバルとして、火花を散らし刺激しあってきたが、この計画は関野にしかできない計画なので、みんなで応援しようじゃないか」ということになつた。
◆アフリカにゴールしてからも、岡村さんは今までに4冊の対談集を編集、出版してくれた。最初は(1)長倉洋海、次に(2)池澤夏樹、椎名誠、河合雅雄ほか16人との対談、(3)船戸与一、藤原新也、山折哲夫他7人との対談。最後に(4)山極寿一との対談。対談相手はすべて私が決めたが、(2)と(4)以外はほとんどの対談に立ち会ってくれた。編集では山川徹、丸山純にも手伝ってもらったが、アンカーとして、やはり岡村さん自身がまとめてくれた。
◆岡村さんに一番心配をかけたのは、2008年から2011年の海のグレートジャーニーだ。このときはモルディブ探検などで海に強い岡村さんに応援団長になってもらった。船作りに一年、インドネシア〜沖縄までの航海に3年かかった。危険だったのはマレーシアとフィリピンに囲まれたスールー海だ。穏やかな海だが、海賊およびアルカィーダと繋がるイスラム過激派アブサヤフが跋扈していた。資金源が誘拐ビジネスなのだ。危険地帯を安全に通る秘訣は目立たず、迅速にだ。しかしヨットと違い、風上には走れないし、スピードもでない。自分で作った手づくりカヌーなので目立つ。そこを通過するまで、岡村さんはどこにも行かずに、何かあればいつでも出動できるように待機してくれたのだ。3年がかりの航海だったが、幸い無事に通りぬけることができた。
◆岡村さんが厄介な病魔の診断がつく前後に対談をしている。まず2023年6月、私が代表をしている地球永住計画の対談シリーズ「現代の冒険者たち」で、スリランカ遺跡探検50年史をたっぷりと話してもらった。岡村さんと同じ地平線会議の創設メンバー江本嘉伸さん、宮本千晴さん、向後元彦さんほか地平線会議の現役メンバーも来てくれた。
◆診断がついて間もなく、2023年11月23日に新宿歴史博物館講堂で開かれた『つなぐ 地平線500!』の中のメインプログラムとして「関野吉晴×岡村隆対談」があった。これが岡村隆さんとの最後の対談になった。6月は私が聞き役、このときは主に岡村さんが聞き役になった。
◆地平線会議の実行部隊は江本嘉伸黄門の助さん角さん役の長野亮之介、丸山純や白根全以下私たちより少し若い世代だが、参謀役として宮本千晴さん、三輪主彦さんそして岡村隆さんがいる。彼がいなくなると、江本さんにとっても、地平線会議にとってもポッカリと大きな穴が空いた感じになってしまった。
◆私は地平線会議に特殊な雰囲気を感じていた。お金をもらって受ける原稿依頼を断ることはあっても、地平線通信の原稿はお金をくれないのに一生懸命書いてしまう。報告会も、いくら多忙でも、江本さんに頼まれると断れない。メディアでは、有名だけど語ることは薄っぺらい人がよく出ている。一方で、地平線通信の書き手や報告者は地味だが内容が濃い。地平線会議は共感してもらえると嬉しい人がたくさんいる場所だ。
◆50年間調査を続けてきたスリランカの遺跡調査も継続する気満々だった。お互い50年以上現役で、さらに続けていくつもりだった。岡村さんは、「俺たちは同志だからな」と言っていた。写真家の星野道夫さんにも、カムチャツカで亡くなる直前、「同志と思ってますから」と言われたことがある。お互い1歳か2歳の子を持ち、似たフィールドで行動していたせいだ。
◆この人だけには褒めてもらいたいと言う同志が消えていくのは寂しいが、その志は生きている。私は彼の視線を感じながら生涯現役で生きていきたい。
■惜別、岡村隆君、九州の小林から上京した少年は探検部に憧れて法政大学に入学しました。当時の探検部は、気球で世界旅行の夢を育んだ、創成期でありました。君はモルディブを目指す海彦、僕はモンゴルを目指した山彦でした。三宅島での歓迎合宿の洗礼、日高の登山、海山空に、日毎広がる身体知。やんちゃだったね、岡村君。
◆神宮球場の六大学戦、外野席に旗めく幟旗の応援は探検部の独壇場だった。早法戦の夜は、新宿の早稲田の野外舞台に上り「都の西北」を歌った僕達。早慶戦では銀座ライオンで「若き血」を唄い、ビールで六大学を謳歌した。歌が上手い岡村君は、歌詞も暗譜しているので、誰にも尻尾は掴まれない。この異能でバンカラな外交精神が、後の「地平線会議」で開花します。
◆愛唱歌「人を恋うる歌」では教授を喜ばせ、後にパートナーも射止めます。唄は、テレビっ子の君たちとラジオ派の僕たち世代を結ぶ、探検造山運動。君はまた、中野の下宿を探検舎と称し、学内外の仲間の拠り所を創成しました。田舎風情の九州男児の都会に根付くエネルギーが熱すぎる振舞いです。好奇心と行動で解決する、探検に必須の戦略的能力の片鱗を垣間見ました。
◆大学に長年居ると自ら何かしら学びを深めたくなるものです。日本文学科の君は文に拘り、剣としての筆で文字を捉え、一方で口舌は自由奔放でした。心身の二刀流は他人の文章を編集する仕事ができる素養につながりました。血気と学びが、岡村君の生涯を培う土台を作り上げたのだと思います。やがて節子さんも大学を卒業、岡村隆の生涯を支える伴侶となりました。
◆ 僕は日本観光文化研究所(観文研)の協力を得て、法大白馬山荘で「たんけん会議」を開催しました。生涯の友人関野吉晴さんが一橋大学の探検部で、お医者さんになる前です。僕はそのころ、法政に相応しい探検部の姿を模索して各地に人を訪ねました。姫路に京大探検部の安成哲三さん、北海道に草鹿平三郎さんを訪ねました。早稲田では、二名良日さん、原田健司さん等が部室にたむろしていました。早大文学部の授業もまじめに出席して、教授にばれた思い出があります。
◆探検の面白さを個人の興味に閉じ込めておくのは勿体ないと思いました。たんけん会議は情報と人が集まるバザール「探検の市場」を目指しました。互いを知る機会が、活動を臨界に導き、大学間の交流に発展するのです。大学探検史をまとめるにあたり、観文研に彼を紹介しました。宮本千晴さんに編集職人の道へ仕立てられたその後の彼は皆様ご承知です。これらを契機に全国に探検部が創設され、探検活動が飛躍的に増大します。また大学探検部とOBに加え、さまざまな人によるユニークな探検や冒険が百花繚乱する時代となり、みなさんご存知の地平線会議が始まりました。
◆岡村君は利他の境地で、人を育てる仕事に邁進する時間を悟りました。植村直己さんにある、誠実・愚直・利他など、冒険の倫理を継承した君。受賞では語られない「冒険の倫理」は、植村直己から手渡された宝物です。植村直己さんとのアナログな出会いを経験した、君に相応しい受賞です。岡村隆は自分のできることを精一杯尽くして、覚悟の人生を終えました。夫々の縁で結ばれた岡村隆の世界は、これからも皆さんと共にあります。
◆翻って僕は、前だけを見て進むことしかできない不器用な性格の動物です。文章も作者の肉体の一部と思う僕は、残酷な編集という仕事はできません。自分の心の発達を学び、人と繋がる手立てを今も模索している毎日です。自分の無知と人類の無知は等価値ではありません。しかし未知なるものを探り当てる行動は、同時に自ずと無知なる自己を見つけて、これを育てます。
◆私は法政大学探検部を創設しましたが、統治はしません。法政大学探検部は、各自創部のDNAを有する、自身の創始者であります。冒険者は常にパイオニアであれ。未知を探り、怖れをもって既知とする。君は創部の精神を、探検の本質と関わり、見事に体現してくれました。君が残したことはなんだろう。業績であろうか。それだけではありません。君が拓いた世界の向こうに広がる、新たな未知ではないだろうか。
◆僕は平泉から天竺に繋がる仏教とスリランカの関わりを無邪気に尋ねた。わかっていることは、わからないことだらけだという、君の言に納得した。かつて、フランス郵船(M.M)で海路を辿った我等、そこは仏教伝来の道。回教の前に仏教や、ヒンズー教があり、さらにその昔の多層文明に繋がる。マルコ・ポーロも辿った海のシルクロード、出会ったスリランカの世界。
◆君は韋駄天のごとく、我らを追い抜いて、逝ってしまいました。君の脚なら、ヒンズーの神、スカンドに会えるかもしれない。此岸の僕は、虚な腹が、副菜にクサヤを添えたカレーを求めている。鰹のカレーも、カラスミも、インド洋の味覚です。酒田のしょっつるはナンプラー、君の命日は「カレー忌」でどうだろう。岡村隆くん。君は一人じゃない、道標として、人々の記憶に残る君です。ありがとう。
■岡村隆さんは、僕にとっては常に「頼もしいアニキ」という存在でした。価値観がはっきりしていて、歯に衣着せずものを言ってくれる「フーテンの寅さん」のようなヒトです。
◆地平線会議では初期のころに「地平線から」という年報を発行していました。その編集ミーティングでは、岡村さんは声が大きくて押し出しが強いので、発言が際立ちました。でも押し付けがましくはなく、人の意見は尊重する。頭のいい人だな〜と思いました。印象的だったのは大集会イベント時の活躍です。盟友の惠谷治さんとのコンビで何度かオークションの仕切りをやっていただきました。地声が大きくて勢いもあり、決断が早い。お二人のコンビネーションの妙もあり、不動の立ち位置でした。
◆岡村さんが編集長をされていた「望星」という雑誌でのお付き合いもあります。僕は前任の街道憲久編集長のころから望星で仕事をさせていただいてました。岡村さんが後を継がれてから、表紙の絵を描かせていただくことに。地平線通信に描いている似顔絵を評して「オマエの絵には毒がある」と言われていました。「批評性がある」という意味だったかと思います。僕自身にはそんな意図はないのですが、ベテラン編集者であり、作家である岡村さんからそう言われると、そういう面もあるのかな……と少し嬉しかった。
◆望星の表紙では、毎月の特集テーマを絵にしていました。たとえば「怒りの効用」とか、「心の旅路」など、抽象的な「お題」も多い。具体的な絵にどう落とし込むか、無い知恵を絞ります。岡村さんはそういうとき、「こんなのはどうかな?」とアイデアを添えてくれました。ありがたいけど、あえて岡村案とは違う絵を描くと、「そうきたか〜」と感心してくれるのが嬉しい。いつもうまく行くとは限らなかったが、それが制作の密かなモチベーションにもなっていました。
◆25年ほど前、西武文理大学というできて間もない大学で、年に半期だけですが4年間非常勤講師をやりました。岡村さんが講師を推薦する立場にあった一人で、地平線会議のメンツなどから何名かを抜擢。その中になぜか僕も含まれていました。与えられたテーマは「エコツーリズム」です。それまで僕は、江本嘉伸さんに誘われて長期にわたりモンゴルでコックをしたり、NPO「砂漠に緑を」の向後元彦さんとベトナム、ミャンマー、エクアドルなどを訪れたり、長野県のNPO「地球クラブ」に協力してタイに行くなど、たまたまそれらしい活動に関わってはいましたが、所詮はただの野次馬です。
◆「それでいいから、まあやってみろ」と言われてお受けしました。最初の授業のとき、緊張しすぎて途中で頭が真っ白に。終了後にはとにかく甘いものが食べたくなって、帰りの駅でダンキンドーナツを貪り食った記憶があります。学生たちに何を伝えられたのかわかりませんが、僕の人生ではとても大きな蓄積になっています。
◆地平線通信では、岡村さんの似顔絵は何度も描きました。報告会登壇者常連の10数名の顔は、僕の中ではキャラクターとして定着しており、岡村さんもその一人です。2018年11月の報告会「”大発見”への一里塚」の際には、ゾウに乗った岡村さんの絵を描きました。しばらくして「気に入ったので、カラーで描いてくれよ」と言われ、二つ返事でお引き受けしたのです。A4ほどの小さな絵ですが、時たまお会いすると「あの絵は玄関に飾ってあるぜ」とおっしゃいました。岡村さんの葬儀の際、その絵が会場に飾られていました。久々に絵と再会してみて、この絵を描いてよかったと思いました。
◆岡村さんにはたくさんの恩義があり、何も返せていませんが、あの絵が最後まで岡村さんの身近にあったことがせめてもの自分への慰めです。岡村さん、あの絵には毒ではなく、畏敬の念しか盛っていないですよ。合掌。
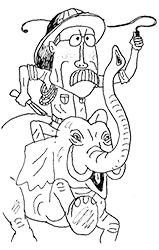
■5月末、2023年スリランカ隊の報告書作成が佳境を迎え、長めに話し合ったNPO南アジア遺跡探検調査会の集まりの後。飯田橋で少しだけ飲んだ夜が岡村さんと直接話せた最後の機会だった。暑かったからかいつもの焼酎ではなくビールを多めに頼んでいた。私が春先から成田空港滑走路延長に伴う住民移転を取材・撮影していると話を向けたところ、岡村さんはかつて三里塚闘争を間近で取材し、もみ合う人々に分け入って写真を撮ったエピソードを得意げにしてくれた。2年前に闘病生活となった当初と比べるとずいぶん元気になったように見えた。当たり前にまた飲みに行けると思っていた。
◆岡村さんが病気を発症し、遠征隊の参加を断念した23年のあの夏。密林にこそいなかったが、総隊長としてLINEの隊員チャットでいつもとほとんど変わらない岡村節を発揮していた。病床から居ても立ってもいられなかったのだろう。全権を境雅仁隊長に委ねると言っておきながら、現場に居るのと変わりないくらい口出ししていた。仲間内では冗談交じりに「奥さんにSNS取り上げてもらおう」と話していたほどだ。ただ、無理を押して助言してくれているのもまた、皆がわかっていた。
◆報告書作成の会議には3回に一回ぐらい、体の調子の良いときに参加されていた。闘病生活は精神的にもきついのだろう。この2年は話すたびに「これが最後になるかもしれん」とこぼしていた。最初こそ身構えていたが、時々顔を出されている様子から、数年が経つ中で元気にされているなと内心安心していたのだ。だから容態が急変したと岡村さんが短い投稿をしてから数日、NPOの、特に私世代の若いOB連中の反応はちょっと鈍かった。関野吉晴さんの投稿で詳しい病状を知った8日にはすでに家族以外は面会謝絶。慌ててこれが最後になることを念頭にメールを一通送った。亡くなる前日だったのでご本人が見ることはできなかっただろう。遠慮してすぐに電話をしなかったことを後悔している。
◆僅かなバツの悪さもあり、葬儀の撮影係をOB会と妻節子さんから持ちかけられたときには二つ返事でやらせていただいた。葬儀の二日間はじっくり遺影を見る間もなく撮影に追われた。あっという間に迎えた告別式。部の先輩でもある高山文彦さんが式辞で「貴方に褒められたい一心でやってきたのですよ」と仰っていた。大先輩と比べるのもおこがましいが、私は最前列でカメラを構えていることも忘れ涙を耐えられなかった。
◆19歳のときに法大探検部の1回生としてNPOの2010年スリランカ隊に参加した。最年少で唯一の法大生だった。だから当時62歳だった岡村さんからは「学生に不始末があったらお前を最初に怒るぞ」と言い含められ、宣言通り密林のド真ん中で大いに怒鳴り散らされた。日々密林探検のイロハを教わり、ともに川に入って1日の汗を流した。帰国してからも「そんな無知蒙昧でジャーナリストになれるか」と読むべき本を説いて下さり(そういえば、最初に紹介されたのはまさに式辞に登場した吉田敏浩さんの『森の回廊』と高山さんの『火花』でした)、また大人としての振る舞いを教わった。探検部では未確認生物調査に憧れて入部した私は「そんなオカルト趣味でなく本流の探検を志せ」と言われ続けたが、まったく譲らなかったのでいつしか諦めてくれた。最終的には南米ベネズエラの巨大猿伝説調査の計画をまともに仕上げるまで何かと助言いただいた。
◆新聞社に入ってからはいい仕事ができれば報告し、袋小路に佇んだときには「あの人なら何と言うかな」と頭に岡村さんの姿をよぎらせる。そんな人生の指標にしていた先輩だった。2年前はスリランカこそ一緒に行けなかったが、病気を発症する直前のあの人を沢登りに連れて行くという数年来の約束を果たせた。私たち世代のOBや学生と一緒にタマネギを切り、スリランカカレーを作って食べた夜は随分楽しそうだった。初めて会う現役生に焚き火を囲んで探検の意義を説く姿には自分が大学生だったころを重ねた。いくつになっても学生に全力で対峙してくれる希有な先輩だった。
◆今年、4年間の大阪勤務を経て東京に戻ってきた。まだ沢山のことを教わり、職業人としてあの人に認めてもらいたいと思っていた。それはもう叶わない。奇しくも探検部の現役指導やNPOには顔を出しやすくなった。大きく空いたあの人の穴を埋められるとは思わないが、岡村さんが愛した空間が少しでも長続きし飛躍できるよう微力を尽くしたい。本当にお世話になりました。
◆最後に、葬儀のアルバム作成にあたっては、地平線通信の発送日にお邪魔して地平線参列者の特定作業を手伝っていただきました。お陰様で一方的に知っている方が大分増えました。助けてくれた皆さんありがとうございました。
■ぼくは、「岡村さんの他界」が、まだ、ショックです。悲しく つらいです。大人になってから、出会った人間関係で……、こんなに 「苦しい気持ち」になるなんて。
◆「地平線会議」って、みんなが真剣に対峙して。すごく たのしくて すごく おもしろくて すごく ゆたかなきもちに なる……。
◆けど、それだけに……、というか、「お別れ」は、すごく かなしい……、身体のどこかに おおきな穴が空いたような感じ。いつまでも 想い考えている自分です
◆ぼくは こういう 悲しい 苦しい 辛い……、とかは、とても「たいせつなこと」なのだと 想います
◆岡村さん ありがとうございます[緒方敏明]
■岡村隆さんが亡くなりました。つい先日、『地平線通信』の4月号で、東京と故郷の小林(宮崎)、それとコロンボ(スリランカ)での「三拠点生活」を読ませてもらったばかりなのでショックです。うまく病気と共生しているとばかり思っていました。
◆岡村さんとは宮本常一先生が所長をされていた日本観光文化研究所(観文研)の同志です。岡村さんと森本孝さん、それと賀曽利隆の3人は「観文研の3バカタカシ」と呼ばれていました。ほぼ同年代の我ら3人は、若さとパワーを武器にして、それを誇らしくも思っていました。「観文研の3悪筆タカシ」と呼ばれることもありました。その観文研は1989年3月31日に閉鎖されました。2022年2月24日には森本さんが亡くなり、岡村隆さん、山田高司さん、賀曽利隆の3人で「地平線会議の3バカタカシ」として再登場したばかりでした。
◆山田高司さん、残された我ら「地平線会議の2バカタカシ」で、岡村さんの分も頑張って生き抜いていきましょう。「タカシ」のしぶとさを岡村さんに見てもらいましょう。岡村隆さんのご冥福を心より祈っております。[賀曽利隆]
■地平線通信555号(2025年7月号)は、さる7月16日、印刷、封入し、発送しました。今回は法政大探検部OBの毎日新聞カメラマン、滝川大貴さんが初めて参加してくれました。岡村隆の後輩としてご家族の依頼により、このたびの岡村の通夜、告別式で写真を撮っていた青年で、撮影した人々の中で誰が地平線関係者であるか確認するため参加してくれ、今月号にも原稿を書いてくれています。江本は今回も間に合わずまっすぐ「新北京」に直行させてもらいました。作業に参加してくれたのは、以下の皆さんです。ありがとうございました。
車谷建太 中畑朋子 伊藤里香 長岡竜介 高世泉 中嶋敦子 渡辺京子 白根全 滝川大貴 落合大祐 武田力 江本嘉伸
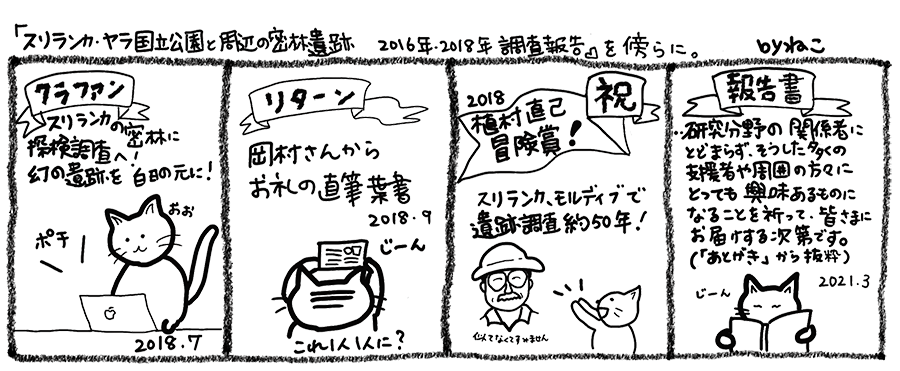
《画像をクリックすると拡大表示します》
■伊沢正名さんの新しい著書『うんこになって考える』(農文協 2000円+税)が出版された。「糞土師・伊沢正名が、人としてのさいごに語る 死と生の哲学」と帯にあるように糞土師人生の集大成。これまでの著書以上に「死」を意識した伊沢さんの単刀直入の遺言である。
◆推薦者のドクトル関野吉晴は「この本は、自らうんこになって書き進めるという世界初の偉業を成し遂げた、糞土思想の究極の決定版だ。そしてうんこになった伊沢正名師を土中に埋葬して、しあわせな死を成就してもらいたい」と書くが、実は本の目指すものは伊沢さんの「死」をどのように誰が見届けるか、にかかっている。本人は死期を悟れば「プープランド」という自分の土地にを掘り、自力で横たわるのでそのまま埋葬してほしい、と書き残しているのだ。
◆うーむ。ついにそういう人が現れたのか。伊沢さん、応援団はかなりいるらしい。すごい本が出たものである。[江本嘉伸]
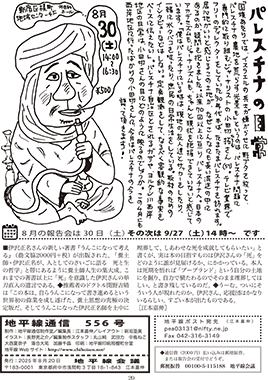 |
パレスチナの日常
「国境あたりでは、イスラエルの兵士が嫌がらせに野ブタを放って、パレスチナの農地を荒らす光景も」というのは、パレスチナ問題に専門的に取り組む、ジャーナリストの小田切拓(ひろむ)さん(57)。テレビ業界でフリーのディレクターをしていた'90年代半ば、たまたまパレスチナを訪れます。居心地がいいと感じるこの土地が、なぜこんなにも長い混迷の中にあるのか、疑問を抱きました。 以来70回以上に亘りパレスチナへ。日本のアカデミズムも、ジャーナリズムも、ちゃんと現状を把握できていないと感じています。「僕はパレスチナにいる時は、現地の友人たちとサッカーをしたり、一緒に水タバコを吸ったり、庶民の日常生活をしている。取材のためのインタビューなどはしない。定点観測をして、なるべく客観的な事実をベースに伝えたい」。 パレスチナ自治区とされるガザや、ヨルダン川西岸地区の日常は、小田切さんの目にどのように映るのでしょうか。この4月にも西岸地区に行ったばかりの小田切さんに、今月はパレスチナの今を語って頂きます! |
地平線通信 556号
制作:地平線通信制作室/編集長:江本嘉伸/レイアウト:新垣亜美/イラスト:長野亮之介/編集制作スタッフ:丸山純 武田力 中島ねこ 大西夏奈子 落合大祐 加藤千晶
印刷:地平線印刷局榎町分室
地平線Webサイト:http://www.chiheisen.net/
発行:2025年8月20日 地平線会議
〒183-0001 東京都府中市浅間町3-18-1-843 江本嘉伸 方
地平線ポスト宛先(江本嘉伸)
pea03131@nifty.ne.jp
Fax 042-316-3149
◆通信費(2000円)払い込みは郵便振替、または報告会の受付でどうぞ。
郵便振替 00100-5-115188/加入者名 地平線会議
|
|
|
|
|
|