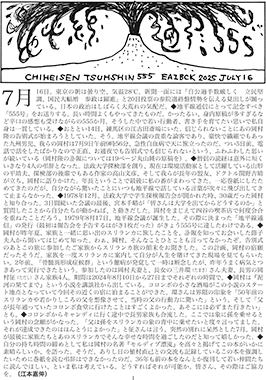
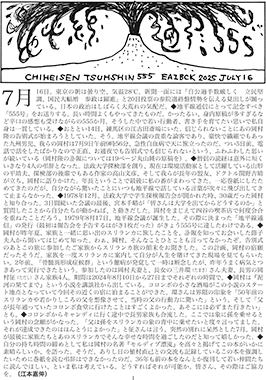
7月16日。東京の朝は曇り空、気温28℃。新聞一面には「自公過半数厳しく 立民堅調、国民大幅増 参政は躍進」と20日投票の参院選終盤情勢が踊っている。日本の政治はしばらく大荒れの気配だ。
◆地平線通信にとって記念すべき「555号」をお送りする。長い時間よくもやってきたものだ。かったるい、身内原稿が多すぎるなど辛口の感想も受けながらの555か月。そうした中で若い書き手、行動者を育てたい思いは私自身は一貫している。
◆おととい14日、練馬区の江古田斎場にいた。信じられないことにあの岡村隆の告別式が始まろうとしていた。そう。地平線会議の貴重な論客であり、豪快で繊細でもあった九州男児、我らの岡村は7月9日午前9時56分、急性白血病で天に旅立ったのだ。つい5日前、電話で話をしたばかりなので正直、お通夜でも告別式でも信じられないという、ふわふわした思いが続いている(岡村隆の訃報については19ページ丸山純の原稿を)。
◆僧侶の読経は意外に短くいきなり4人の弔辞となった。法政大学探検部を創り、現在は環境活動家として活躍している山形の平靖夫、探検部の後輩でもある作家の高山文彦、そして我らが長年の盟友、ドクトル関野吉晴が立ち、岡村に語りかけた。年長ということで最後に私の番がまわってきた。一応巻紙にしたためてきたのだが、自分ながら驚いたことにいつも地平線で話している言葉が次々に飛び出してきて止まらなかった。
◆1978年12月、法政大学で学生探検報告会が開かれた時、30歳だった岡村と知り合った。3日間続いた会議の最後、宮本千晴が「皆さんは大学を出てからどうするのか」と質問したことから自分たちが動かねば、と動きだした。岡村をまじえて四谷の喫茶店で何度会合を重ねたことだろう、1979年8月17日、地平線会議が誕生した。その際に決まった「地平線通信」の発行(最初は報告会を予告するはがき1枚だった)がきょう555号に達したわけである。
◆私は訃報を知ってお会いした節子夫人から昨年夏、岡村が家族と一緒に思い出のスリランカに旅したことをはじめて知った。わぁ、岡村、そんなことひとことも言ってなかったぞ。告別式のあとこの旅に参加したご家族からスリランカ旅の顛末をお聞きした。この計画、岡村の宿願だったそうだ。家族を一度スリランカに案内して自分が人生を賭けてきた現場を見てもらいたい。2年前、「骨髄異形成症候群」という難病が発覚して一時は断念したが、昨年うまく病気とつきあって実行できたという。参加したのは岡村夫妻と、長女の三井環(たまき)さん夫妻、長男の岡村征(ただし)さん家族4人。期間は2024年8月10日から27日までそれぞれの時間で。
◆岡村は『泥河の果てまで』という小説を講談社から出している。コロンボの小さな酒場がこの小説のスタート地点となっていて今回その近くの宿に泊まることができた。環さんは界隈の印象を「50年前のスリランカや若かりしころの父を想像させて、当時の父の行動力に驚いた」という。そして「父が長年通っていたコロンボ食堂に行けたことはすごくよかった。あそこには必ずまた行きたい」とも。
◆コロンボからキャンディに行く途中で長男家族も合流した。ここでは象に孫を乗せるという岡村の念願がかなった。「父は孫をスリランカの象の背中に乗せたいと度々言ってました。それが達成できたのはほんとうによかった」と征さんは言う。突然の別れに呆然とした7月。岡村が最後に家族たちとあのスリランカでそんな幸せな時間を過ごしたのだと知って嬉しかった。
◆自分の持ち時間の締めとして私は岡村の名著『モルディブ漂流』を高々と掲げてこの本がいかに素晴らしいか、を語った。そうだ。ありし日の植村直己との交流も記録しているこの本を強調したいために巻紙を読む弔辞はできなかったのだ。36年も前の本をなんとか復刊して若い仲間たちに読んでほしい、といま私は考えている。どうすればそれが可能か。皆さん、その際はご協力を。[江本嘉伸]
■今回の報告者は江本さんが「怪物」と称するほど、20代から勢力的に国内外をバイクで走り続けている鉄人「賀曽利隆」さんです。地平線会議の創設メンバーでもある賀曽利さんですが、報告者としては今回で何と16回目の登場となります。
◆レポートを担当しました私、福島県いわき市の渡辺哲にとって報告会へはコロナ前の2019年1月以来の参加となりました。報告会といえば必ず走って参加することにしているので今回も仕事を終えた金曜日の夕刻に福島県いわき市の自宅を出発し、国道6号線をひたすら南下して翌朝6時前に茨城県の東海駅に到着しました。先ずはランで気合いと気持ちを整えて、会場に向かいました。
◆報告会の冒頭、江本さんから「地平線では若者の発掘に力を入れているがシニアも凄い、その代表格が賀曽利隆さんです」と紹介されました。現在までのバイクでの総走行距離は約188万km。とてつもない距離を走破しながら、常に旅の記録を取り続けることで、それに裏打ちされた膨大な知識は聞いている人を圧倒するほどの迫力です。今までの旅のメモ帳は何と240冊にもなるそうです。
◆この日の第一声は「地平線で20代のころの話はしたことなかったので、今日はとても高揚している!」。早速20歳で飛び出したアフリカ大陸一周の話から始まりました。「広いな〜」、高校3年生の夏休みに千葉県の外房海岸に行く途中の車窓から広がる田園風景を見た時に賀曽利さんが発したこの一言がその後の運命を大きく変えた、すべての原点がこの一言にある、と回想されています。「アフリカなんてこんな広さなんかじゃないぞ!」と後に一緒にアフリカを旅する友人の前野幹夫さんの言葉が続きます。これがきっかけとなり一気にアフリカの雄大な大自然の風景が頭の中を巡り始めました。こんな狭い日本を飛びだして広い国々を旅したいと、沸々と気持ちに火が付き、「よし、アフリカへ行こう!」とすぐさま友人4人と具体的計画の立案に取りかかりました。
◆今回は会場に賀曽利さんと一緒にアフリカを旅したその前野幹夫さんが来られていました。前野さんにマイクが向けられると、「お前とは何十年も会ってなくとも、昨日会ったみたいだよ」と挨拶され、お2人の間柄を感じます。賀曽利さんも前野さんのことを「戦友」と呼んでいたほど、当時の凄まじい状況をくぐり抜けてこられたのですからね。
◆何故、アフリカへ行きたかったのか。それを賀曽利さんは「猛烈な反発心」という。大学受験を控え、敷かれたレールをただ進んでいくだけでいいのか、何かしたいのではないか、そんな「見えてしまった明日、見えてしまった自分」がアフリカへと駆り立てたのだと。大学受験には失敗してしまいましたが、「浪人はしない」と決めていたため、すぐさま資金稼ぎの仕事に没頭します。「すべて自分たちの手で準備し、必ずアフリカへ行く」という強い意志が1日20時間という過酷な労働を支え、2年間で100万円の資金を貯めました。
◆「生涯旅人」としてスタートの日となる1968年4月12日、横浜港から出港の日を迎えました。「やればできるのだ」と大きな自信を手に入れた賀曽利さんは、出発まで漕ぎつけた喜びに打ち震え、出航した船の甲板で、一升瓶をラッパ飲みしながら前野さんと祝杯を上げたそうです。この時の自信こそが「200万kmを目指す男」の礎となった、とのことです。
◆約40日の船旅を経てモザンビークのロレンソマルケスに降り立ち、いよいよアフリカの大地を走り出しました。食費を最小限に切り詰め、全泊野宿という超貧乏旅行でしたが、現地の人の優しさに触れながら旅を続けている途中で最大の危機に直面します。エジプトのベニスエフから古代遺跡の残るファイユームへ向かう途中で道に迷い、住民に道を尋ねようとした途端に、「イスラエル、イスラエル」と叫びだし暴徒化した群衆に襲われてしまったのです。殴られ蹴られ引きずり回されて、もう死を覚悟したそうです。そんな危機を地元の民兵により助け出され、どうにか難を逃れました。
◆アフリカに旅立つ前は腕や足の1本位は無くす覚悟でしたが、いざ死に直面すると、生きたい、死にたくないと生への気持ちを強烈に感じたそうです。その後も様々な危機を乗り越え、旅をスタートしてから1年を過ぎようとしたジブラルタル海峡を渡る前日に賀曽利さんは前野さんへ打ち明けます。「もう一度アフリカに戻りたい」と。この1年でアフリカに魅かれた思いを抑えることはできませんでした。その申し出を前野さんは淡々と受け止めたそうです。
◆そして二人はスペインで別れ、その後前野さんはイスタンブールから西アジアを横断し、インドのボンベイから日本へ戻りました。当初の計画通りのルート通り旅を終えたのです。賀曽利さんは西アフリカ経由で南下し、スタート地点のモザンビークのロレンソマルケスに戻り1969年12月に日本に帰りました。
◆続いて1971年8月に世界一周に旅立ちます。この旅もアフリカを中心とし、それもサハラ縦断をメインに据えての旅でした。タイのバンコクからスタートし、パキスタンのカラチでバイクを引き取り西アジアを横断〜アラビア半島を横断〜メッカ巡礼、そしてアフリカ大陸に入り西アフリカのラゴスからサハラ砂漠縦断を開始しました。地中海のアルジェまで約5000kmのルートのうち、途中の約1000kmは無給油地帯なので、サハラ砂漠を走るトラックを見つけ出しガソリンを積んでもらう作戦で、どうにかサハラ砂漠を縦断しました。その後は更にヒッチハイクでサハラ砂漠を縦断し、その後カナダに渡り、北米の全49州をバイクで走り1972年9月に日本へ戻りました。
◆20代最後は六大陸周遊(1973年8月)です。この旅はヒッチハイクをメインにして、バイクは現地でレンタルするスタイルを取りました。バイクを大陸から大陸へ輸送するには時間もお金もかかるためです。今回もタイのバンコクからスタートし、オーストラリアはヒッチハイクとバイクで回り、トータル2周しました。モーリシャス島〜マダガスカル〜南アフリカに入り、バイクを借りて南アフリカを走り、更にヒッチハイクでも回りました。ヨーロッパから北米そして南米コロンビアのカリまで来たところで、夜間野宿している際に何と盗難に遭ってしまいました。カメラや写真メモ帳等盗まれてしまい、ショックで気持ちを立ち直すことができず、残念ながら南米一周を断念し1974年11月に帰国しました。
◆ここまでの前半戦を怒涛のごとく話し続けた賀曽利さん。まるで先週旅をされてきたのかのような勢いで現地の地名や回ったルート、訪れた時期等を正確に記憶されています。若かりし日の賀曽利さんをが思い浮かべ、引き込まれた前半戦でした。
◆後半は30代の旅からスタートです。20代のほとんどは海外を走っていた賀曽利さんですが、30代に入り強烈な虚脱感に襲われたそうです。それこそ命懸けで走ってきた世界に対して、今まで自分のやってきたことは何だったのかと。そこで目が向いたのが日本です。峠や温泉といったテーマを持つことで日本を見て回ろうと決心し、30歳にして初めて日本一周に旅立ちます(1978年8月)。
◆そして1980年2月には鈴木忠男さん、風間深志さんと共にアフリカ大陸の最高峰「キリマンジャロ」にバイクで挑むチャレンジが続きます。出発の直前、当時の読売新聞(夕刊)の一面にこの冒険行について掲載された新聞記事のコピーが会場内に回覧されました。これは当時江本さんが書かれた記事です。
◆その後は1982年12月に風間深志さんと共に日本人初のパリ・ダカールラリーに参戦しました。このレースでは賀曽利さんは夜間に立木に激突し、大怪我を負い無念のリタイヤとなりました。その怪我の回復後に遂に南米一周を完遂させました(1984年10月)。
◆そして40代に突入した際に急激な体の衰え気力の萎えを感じるようになりました。賀曽利さん自身、かつては「サハラの狼」といわれていたのが「牙を無くした狼」になってしまった、と揶揄されていました。そこでこの局面を乗り越えるには、今まで最も情熱を注いできたサハラしかない、とサハラ砂漠縦断を決意し1987年11月に挑みました。40リットルの特注ビックタンクを搭載したSX200Rでサハラ砂漠往復縦断を成し遂げて、新たに力を取り戻すことができたそうです。
◆ただ、帰国後に更なる試練が賀曽利さんに襲い掛かります。40代編日本一周に旅立つ直前に何と左の肺に腫瘍が有る事が発覚しました。ただお医者さんの許可を得つつ旅を続行し、世界一周〜サハリン〜インドシナ一周〜オーストラリア2周を成し遂げます。痛みがなかったことをいいことに逃げ回っていましたが、いよいよ腫瘍が肥大化していたために、遂に腫瘍を摘出する手術を受けることになりました。40代の大半は常に肺の腫瘍のことが頭にあり、肺癌で自分は50歳までは生きられない、と覚悟して尻に火が着いた感じで「生き急いだ年代だった」と振り返ります。
◆更に50歳となった1997年12月には、またしても病魔が賀曽利さんを襲います。こんどは脈拍が途切れ途切れになる不整脈が続き、しばらくの休養を余儀なくされました。体調が戻っても「心臓をやられてしまった」と思うと、出歩こうという気もまったく起きずに、「このまま一生バイクに乗れないのでは」とさえ思ったそうです。当時江本さんからも、「1年間はおとなしくしていなさい」、と忠告を受けたそうです。そんな危機を救ってくれたのも実はバイクでした。
◆出発を1年遅らせた50代編日本一周(1999年4月)の途中で、何と奇跡が起こったのです。お医者さんからはこの不整脈とは一生つきあっていくことになる、と忠告されていたのですが、日本橋を出発してから13日目に何と脈が正常に戻ったのです。それ以降現在まで不整脈も一切なくなりました。常々バイクは「最高の健康機器」と宣言し、それを体現している賀曽利さんですが、正に説得力がありすぎるエピソードですね。
◆また温泉巡り日本一周(2006年11月〜2007年10月)では何と3063の温泉に入りまくり、これはギネスの世界記録に認定されました。真冬の信州でも温泉に入り続け、一日で10〜20湯の温泉に入る過酷な旅でしたが、これによって血管まで鍛えられたと力説されています。
◆還暦を迎えても何のその、60代編の日本一周(2008年10月)では厳冬期の北海道をアドレス125で走破し、更に海外ツアーも勢力的に走り続けました。そしてついに70代に突入です。70代編日本一周ではVストローム250というバイクで5年半で23万kmを走破しました。これまで1台のバイクで20万kmを走ったのは、初めてでした。
◆そして報告会の終盤では日本観光文化研究所の話題も出ました。宮本常一先生が所長を務められていた通称「観文研」。長らく賀曽利さんは所員として活動されていました。宮本常一先生が1981年に逝去され、1989年に観文研は閉所となりましたが、「先輩方からの教えがもの凄く生きている、ほんとうに観文研時代の経験は貴重だった」と振り返ります。
◆各年代を乗り越えるたびに病気や老いや様々な障害を乗り越えてきたなか、「70代への壁を乗り越えるのが今までで一番楽だった」と言います。まだまだ走るパワーは留まることなく、今年10月にはアフリカ縦断の旅を控えている賀曽利さん。いよいよバイクでの通算走行距離200万km到達まであと12万km余りまで迫って参りました。
◆もしや2年後の80代編日本一周中にその瞬間が訪れるのかと、密かに私も今からその瞬間を楽しみにしています。この先もどうぞお気を付けて、バイクで走り続けて下さいね。全国のカソリファンを代表してこれからもしぶとく背中を追って行きますよ。賀曽利さん、また焚き火キャンプやりましょう。次回は夜中に薪がなくならないよう、大量に準備しておきますので!![福島県いわき市 渡辺哲]
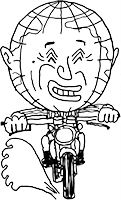
イラスト 長野亮之介
■今回の地平線会議での報告会は自分にとっては16回目になりますが、すごく期待したのは我が旅人生の原点をみなさんにお伝えできるということでした。1回目は1982年2月のことで、「パリ・ダカール・ラリー」を一緒に走った風間深志さんとの報告会でした。このとき、ぼくは34歳になっていました。それ以降の報告会では南米一周、サハラ砂漠往復縦断、インドシナ一周……というように、その時々の行動を報告させてもらいました。
◆我が旅人生の原点というのは1968年まで遡ります。20歳の旅立ちです。友人の前野幹夫君と横浜港からオランダ船の「ルイス号」に乗船。2台のバイクを積んでアフリカ大陸を目指したのです。1年をかけての「アフリカ大陸縦断」が2年あまりの「アフリカ大陸一周」になりましたが、22歳になって日本に戻ってきたとき、ぼくは生涯をかけて世界を旅しようと心に決めたのです。「22歳の決心」どおりに、「世界一周」(1971年〜72年)、「六大陸周遊」(1973年〜74年)とたてつづけに世界を駆けまわりました。
◆今回の報告会でうれしかったのは、「アフリカ大陸縦断」を共にした前野君が来てくれたことです。我々は17歳の夏の日、外房の鵜原海岸でキャンプしたのですが、その鵜原に向かう外房線の車中で「アフリカに行こう!」という話になったのです。横山久夫君、新田泰久君をまじえての4人組。結局、アフリカに旅立ったのは前野君とカソリの2人でした。横山君、新田君はすでに他界しましたが、今でもなにかというと2人を偲んでいます。
◆今回の報告会でうれしかったことのその2は、江本嘉伸さんの書いてくださった新聞記事を見つけ出したことです。報告会の事前の準備で資料を探している最中にみつけました。1979年11月17日付けの読売新聞の夕刊です。社会面一面をぶち抜くようにして、「冒険ライダー三人男」、「アフリカの最高峰キリマンジャロ」、「オートバイで登っちゃおう」……の大見出しが躍っています。賀曽利隆、鈴木忠男、風間深志3人のバイクでのキリマンジャロ挑戦を江本さんが記事にしてくれたのです。その記事のコピーをみなさんに見てもらいました。
◆80歳を過ぎた鈴木さんは今でもバリバリの現役ライダーだし、風間さんは1万人以上ものライダーを能登の千里浜に集める「SSTR」の主催者だし、賀曽利は生涯200万キロまであと12万キロ、あれから45年たっても変わらずに元気な「冒険ライダー三人男」だと江本さんにお伝えしました。
◆今回の報告会では賀曽利隆の40回に及ぶ「海外ツーリング」の一覧と、全部で12回になる年代編、テーマ編の「日本一周」の一覧をみなさんに見ていただきました。この一覧は受付で1枚づつ取ってもらいましたが、じつはみなさんに一番、見てもらいたかった「カソリの世界地図」があったのです。1968年〜69年の「アフリカ大陸一周」から2024年の「台湾周遊」までのすべての我が旅のルートを色分けして示した手作りの世界地図なのです。それをどこかの時点で回して見てもらおうとしたのですが、すっかり忘れてしまいました。残念無念。
◆でも限られた時間内で60年近い「カソリ旅」を話すことができ、最後に2026年の北海道・西興部村で予定されている地平線会議に「必ず行きますよ!」までを話せたのはほんとうによかったと思っています。[賀曽利隆]
■先月の通信でお知らせして以降、通信費(1年2000円です)を払ってくださったのは以下の方々です。万一記載漏れがありましたら必ず江本宛メールください。通信費を振り込む際、通信のどの原稿が面白かったかや、ご自身の近況などを添えてくださると嬉しいです(メールアドレス、住所は最終ページにあります)。
豊田和司(3000円 江本様ごぶさた致しております。通信費とカンパです。娘が酪農学園大学の卒業生でこれもなにかの御縁と思い別途1万円カンパに協力させていただきました) 中村易世(4000円 団塊の時の流れは2倍速。1年とばしていたようです) 水落公明(3000円 毎月“地平線通信”をお送り頂きありがとうございます。引き続きよろしくお願い致します。最近は近場の旅を細々と続けております……) 佐藤日出夫(10000円) 新保一晃(10000円 5年分) 菅野智仁 桃井和馬(10000円 岡村隆のお通夜の会場で)
■死にたいと思いながらひたすら一人で山のことを考えていたころの、自分の気持ちと山との向き合い方を忘れないでいたい。……山との向き合い方は人それぞれといえど、私のそれはどこかひねくれているだろうか。
◆大学を出てから年齢も出身も勤めも多種多様な人たちと山に登る機会が増えて、最近そのように少し感じるようになった。いろんな人と出会って山に登る、山に登っていろんな人と出会う。それは面白くて刺激的である一方で、山に関わる人間にも本当にいろんな人がいるんだと感じる機会になった。そして、そもそも私は、ただそこに在るだけで安心できる場所を求めて山に惹かれた人間であるので、できれば安心できる人と山に行きたいという欲が出てきた。それは、安全で成功的な登山ができるという意味の安心ではなく、安らぎや穏やかさ、存在としての安心感だ。
◆そんな安心感のある人と、私は昨年出会った。仕事でも山でも人としても尊敬するその方と、私はいわゆる「カップル」で登山をする機会が増え、この出会いは私の人生史上、最高峰に登ったも同然のことのようにさえ感じた。人が嫌いで家族さえも信じられなかった私が、生きるのに必要な山を追い求めていく中で出会った人。結婚とか男女のあれこれとか、人とお付き合いするなんて絶対にありえないと思っていた私が、相方と出会った……この事実を表に出すと何か壊れてしまうのではないかと恐れもあり、秘密にしておきたい気もする。しかし、こんなふうに山と向き合っている人間もいるのだということを誰かに知っていてほしいとも、思う。自惚れでもなく純粋に。
◆もっといろんな山に挑戦したいと思いつつも行動できずにいる私は、ただの言い訳かもしれないが、そもそも安心のために山にいたいのだから、挑戦するにも安心できる人とがいい。人を選んでいるのだから、とても自己中的だ。その貪欲さのおかげで、見える山の景色は限られているかもしれない。
◆先月の地平線通信を読み、私が2024年のボリビア旅で出会った、現地の女性登山隊を思い出した(一緒に写ってもらった写真は、LINEのプロフィールの背景にしている)。ひらひらしたスカートを履く現地の先住民族の女性たちチョリータは、アイゼンとヘルメットを身につけピッケルを持って雪壁を登攀訓練をしていた。2025年エベレスト登頂を目指しているとのことだったが、今年調べてみても最新の情報がわからない。かっこよくてかわいいBolivia’s cholita climbersに、幸運がありますように。[小口寿子 26歳になりました]
■アイスランドへの出国が8月に迫り、最近はもっぱら準備をしている。昨年の滞在では4回しかできなかった登山だが、今回はもう少し足を延ばすつもりだ。
◆アイスランドの山といえば、動的であるとともに静的である。プレートが生まれる海嶺が地上に突き出している島なので、島の中央部を走る変動帯では活火山が頻繁に噴火している。まさに生きる大地だ。しかし中央帯から沿岸部に向かうと、地質は過去にさかのぼっていく。過去の溶岩は固く地表を覆い、そのうえに苔が絨毯のように広がっている。苔がそこまで成長するのにおおよそ100年かかるそうだ。
◆背の高い木々はほとんどない。地元九州の山々ではシカやイノシシ、土壌の分解者たちを身近に感じられるが、アイスランドの山にはそういった賑わいがなく、生き物を寄せ付けない毅然とした態度が感じられた。そういった意味で、アイスランドでは地球環境のダイナミズムの一端を経験できる。何もなければ2年間行かせてもらうのだから、どんどん入っていきたいと思う。[安平ゆう]
8月の地平線通信で恒例の「夏だより」を特集します。1人300字以内で。短いので挨拶めいた文章は不要です。ただ事実を書いてほしい。締め切りは8月10日とします。パソコンを持たない方はハガキで江本宛に送ってください。[E]

■「モンゴルってこんなに人がいたの!? みんなどこに隠れていたの?」と思わず友人に聞いてしまったほど、7月11日のナーダムスタジアム(の外)は人、人、人だらけだった。新宿駅みたいだ。人混みに慣れていないモンゴル人は、互いにすれ違うときの避け方がわからないのか、ぶつかりまくるので身体が痛い(笑)。モンゴルの友人が渋谷のスクランブル交差点を上から眺めたとき、「なぜぶつからないの……!」と衝撃を受けた気持ちがわかる。
◆さて、集まってきた人びとは、全員がスタジアムに入るわけではない。家族やカップルでお揃いのデザインのデール(民族衣装)を着て、行列に並んで買った「ナーダムホーショール」と呼ばれる円形の揚げ餃子を食べ、スタジアムの周りをぐるぐる歩いて、お祭り気分を味わいたいのだという。芝生があれば(まるで果てしない草原であるかのように)寝転がってのびのび。一瞬で過ぎ去る夏の輝きを味わうのだ。
◆ナーダムはモンゴルの国民的祭典だ。子どもの競馬、大人の相撲、弓競技がおこなわれ、チャンピオンは英雄になる。競技に先駆け、11日の昼からスタジアムで開会式が開催された。強烈な太陽が照りつけるなか、スタジアム全体がどこか浮き足立って見えたのは、気のせいではないと思う。正面の観客席に、天皇陛下と皇后陛下が国賓として座っていらっしゃるのだ。その後ろには、デールを着た元横綱白鵬関の姿も。音楽や踊りなどの派手でにぎやかなセレモニーが始まった。
◆両陛下の下方には、記者やカメラマンがずらり並び、私もそのなかにいた。モンゴルの国会で撮影を担当する友人が、プレスパスを入手してくれたのだ。日本の大手メディアがモンゴルに関してこれほど逐一報道したことも珍しいが、モンゴルのメディアでも天皇皇后両陛下のご動向がつねに流れ、モンゴル人もそわそわしながら続報を待っている感じだった。SNSで「モンゴルをたくさん助けてくれて、日本ありがとう」と書く人もいた。
◆天皇陛下が日本式の教育を実践する学校を訪問されたときは、小学生の男の子が「ナルト天皇陛下」とご挨拶してしまい(アニメの「ナルト」がモンゴルでも大人気)、陛下が大笑いされながら「ナルヒトです」とおっしゃる微笑ましい場面もあった。天皇陛下はモンゴルで終始大歓迎を受けられ、尊敬されていて、陛下も雅子さまも笑顔がこぼれる瞬間が多く、私は心の底から嬉しかった。
◆もうひとつ感激したのは、両陛下が慰霊をされたために、日本のメディアでモンゴル抑留に関する報道がいくつも出たこと。元モンゴル大使の花田麿公さんが膨大な時間と熱量と労力を注ぎ取り組んでこられた問題であり、毎日新聞には花田さんのインタビューも掲載された。このことも本当に嬉しかった。
◆私は12日に一度帰国し、15日からことし4度目のモンゴルに来ている。地平線会議に出会っていなければ、そして岡村隆さんなど生涯現役の先輩方の生き様を通信や報告会で拝見していなければ、こんなふうに自分は生きていない。
■地平線通信554号(2025年6月号)はさる6月18日に印刷、製本し新宿局に預けました。この日はいつもの印刷局長、車谷建太さんが親孝行のロサンゼルス行き(通信のフロントで書いたように、あの大谷翔平選手の投手登板に居合わせた)で不在のため、かねて建太さんから手ほどきを受けていた中畑朋子さんが長岡竜介さんの助けを得て見事に代役を果たしてくれました。通信の印刷は、何よりも大事な作業です。ほんとうにありがたかった。
◆実は江本の事前告知がおざなりだったせいで(というより一度もメールではお知らせしなかった)集まってくれたのはわずか6人でしたが、そこはベテラン揃い。1人が広いテーブルを独占して作業できたため、少人数の割にはスピーディーに進んだようです。江本は18ページを作れた安心のため1時間眠るつもりで横になっていましたがなんと2時間も寝過ごしてしまい、結局間に合わず、皆さんが予約してくれた早稲田駅に近いレストランに直接駆けつけました。ここはいつもの中華とは違って家庭料理の雰囲気でハンバーグ定食、美味しかった。たまには小人数の作業も悪くないね。集まってくれたのは、以下の皆さんです。ありがとうございました。
中畑朋子 長岡竜介 伊藤里香 中嶋敦子 高世泉 久島弘 江本嘉伸
■こんにちは。2025年春、北大に進学し、5月からは探検部員として大学生活をスタートしました、青木銀(ぎん)と申します。18歳です。地平線通信に投稿するのは初めてです。今回は自己紹介がてらに、北大に来た理由、探検部に入った目的、地平線会議を知った経緯などをお話しできればと思います。地平線会議の皆さまからしたらちっぽけな拙い文章かもしれませんが、付き合ってもらえたら幸いです。まずは、北大に来た理由から。
◆北大に来たのは、南極に行くためです。南極に出会ったのは高1の終わりでした。家でごろごろしながらSNSを脳死でスクロールしていたとき、たまたま南極観測隊を映した動画を見かけ、これを機に自分の将来設計が次々に固まっていきました。南極のその雄大さと、画面越しに広がるまったく体験したことのない世界、そこで日々研究、またはそれをサポートしている観測隊という存在は、自分の世界を大きく広げてくれました。こんなことを知ってしまっては自分も南極に行くほかない。どうせなら人生のほとんどをかけてみたいと思い、南極を目指し始めます。
◆私の通っていた高校の生徒のほとんどは付属の大学に進学するため、大学受験を経験しません。こんな学校からなぜそこまでして北大を目指すのかといろんな人に聞かれましたが、そんなことを言われても、それくらい南極に行きたいんだとしか言いようがありません。南極に一番近そうな大学がたまたま北大だっただけだと。受験勉強は自分の世界を大きく広げてくれました。参考書、紙一枚とペン一本でここまで楽しめるのかと、ここで学ぶことの面白さを知ります。
◆北大入学が南極までの第一歩だと感じ、2年弱を受験勉強に捧げ、やっとのことで北大に来ることができました。はじめの一歩、無事達成。北大に来て早3か月。様々なものに出会い、自分の世界がどんどん広がっていきます。世界を大幅に広げてくれたものの一つが探検部です。私が探検部に入った目的は学ぶことです。様々な地形を行き、雪を踏みしめ、歩き方を学ぶ。または、道具の使い方を学ぶ。そして、知的好奇心にかられ、人の寄り付かない僻地に行く人たちがどんな人たちなのかを学ぶ。これらはすべて南極で役立つ学びだと感じ、入部を決めました。
◆探検部のみんなは自分の知らない世界をたくさん知っています。毎週火曜、部会に参加するたびにすごいところに来たなと圧倒されます。先日、北大探検部5年目の赤嶺直弥さんの運転する車に揺られ、低温研所属の杉田友華さん、そのほか探検部員とともにちえん荘に行ってきました。ちえん荘で五十嵐さんに紹介され、地平線会議を知りました。冒険家や探検家、世界を舞台に活動する人たちの有志によって成り立つ、知る人ぞ知るネットワーク。地平線会議という存在に唖然としてしまいました。こんなのを知ってしまったら、また世界が広がる。
◆ちえん荘で世界を広げてくれたのは他にも。畑を営む山川さんが持つ世界観からはとんでもない衝撃を受けました。ちえん荘を通して出会った方々から受けた刺激は自分にとってとても重要なものになると思います。ちえん荘に行った2日間を思い返すと、入部してまだ2か月しかたっていないのにもかかわらず、探検部に入ってよかったと感じます。北大に来てよかったし、なにより2年前南極に出会って本当によかった。
◆もちろん南極に行くことが一番の目的ですが、それまでの道中がこんなにも魅力的で面白いとは。うれしい誤算でした。今、自分の世界はどんどん広がっていきます。そのたびに自分がいかに未熟でちっぽけな存在かを思い知らされる。ただそれと同時に、南極に行くことを掲げた当初はずいぶん長く見えた道のりも今ではそう長くはないのかもとも思う。とにかく、世界は広い。そうわかっていても、それを凌駕するほど世界は広いのだと思います。自分はこれからもたくさんのことを学び、世界をもっと広げていきたいと思います。
◆最後に来年秋、地平線会議が北海道にも来ることについてもお話しさせてください。もうすでに視察もなされ、北海道地平線の第一歩を踏み出したとお聞きしました。地平線会議を知ってまだ日が浅いですが、地平線の皆さまに直接お会いできることを楽しみにしています。北大探検部の仲間とともに、ぜひ参加させていただきます。[北大探検部 青木銀]
★「ちえん荘」とは
ちえん荘は行き過ぎた効率、スピード社会に嫌気がさして「俺たちは遅れて行こう。遅延してなんぼ」と言ったのがはじまり。ヤマ仕事で使う「チェンソー」をかけた表現でもあります。ほかにも「知恵を使って生きる」とか「地縁」という表現も仄めかしていますが自由に解釈してほしい、との立場から平仮名で「ちえん荘」としました。2021年9月発足です。構成員は百姓 、 樵 、 大工、牛飼、家具職人、素浪人などです。
■江本さん、お久しぶりです。私はこれまで2年と少しの間、「椅子張り職人」という、椅子の座面部分に布や革を張ったり、ソファのカバー部分を縫製して仕上げたりするという、世間にはあまり知られていない仕事の修行をしてきました。北海道旭川市内にある、親方夫婦二人で営む小さな工房で修行の日々を送っていましたが、つい先日、6月30日をもって仕事を辞めました。これからは、「工房はち」という屋号で、自分の道を歩み始めます。
◆「ちえん荘」で生活を共にしてきた五十嵐が、昨年林業事業体として独立。同じくちえん荘の同居人だった山川佑司(地平線通信にも何度か寄稿しています)は、多品種の有機無農薬野菜を育てる農園での修行を昨年終えました。今年の春から独立して自分で畑を始め、朝から晩まで一人で野菜たちと対峙しています。これらのことが私の「早く自分で動き始めたい」気持ちにいくらか拍車をかけたような気もします。
◆今年に入ってから、「決められた時間に決められた場所に行って与えられた仕事をこなす毎日を、あと数か月続けたら、私は堕落するだろう」という危機感が募っていて。先月五十嵐に仕事を辞めたい旨を相談したところ、「それなら今すぐ辞めたほうがいいよ」と言ってくれました。「我々には、周りの目を気にして現状に耐え忍んでいる時間の余裕はないんだから、やりたいことやったほうがいい」と。その言葉に背中を押されてすぐさま決断し、1か月後には退職。「すべては自分次第」の広大な景色が目の前に広がった今、ワクワクが止まりません。
◆まずは、「ちえん荘」の移転準備をしたい。先月号に五十嵐が書いていましたが、縁あって私の地元である「南富良野町」というド田舎の、森の中にある古びた大きな丸太小屋を一軒、譲り受けることができたのです。江本さんにも昨年訪れてもらった、あの家です。雨漏りによる壁の腐れや、イタチならゆうに出入りできそうな屋根裏の大きな穴、組んである丸太と丸太の間に分厚く積もった埃……。快適に住めるようにするには、本腰を入れて修繕に取り組む必要があります。一度野生動物たちの手に渡ったこの大きな建物を、我々の居住空間にできるのか……? そして、この夏には沢から水を引いて「水道」設備を整えたり、今は野糞するしかないので冬に向けてトイレ環境を整えたり……。電気は当分いらないと思っていますが、「ちえん荘南富良野店」開店に向けてやりたいことは山盛りです。
◆私自身のこれからについては、正直まだはっきりとはわかりません。やりたいことは色々あって、それは学んできた「椅子張り」の技術を使って、一般のお宅で大切に使われてきた椅子やソファの布・革を新しいものに取り替える「張り替え」という仕事や、椅子張りの作業中に大量に捨てられる布のハギレを使ってバッグや小さな入れ物を作ること。それから、五十嵐が来年にも迎えようとしている「ばん馬」が使えるような馬具の作り方を学ぶこと(椅子張り職人の起源は馬具屋だと言われています)。とにかく、大好きな手仕事を中心とした暮らしを、コツコツと作り上げたいです。
◆「北海道地平線」も、動き出していますね。昨年秋に江本さんがちえん荘に来てくれて、一緒に北海道を車でまわったとき、「これから、皆をやる気にさせていくのが私の仕事」と言っていたのが思い出されます。その後何度か、北海道地平線のことで「あなたにも動いてもらいたい」と電話をかけていただき、私のやる気スイッチにも、火が灯されました。「江本さんに声をかけてもらったからには、動いてみたいな」と思わせるその人間力、今更ながら、じわじわとすごさがわかってきました。仕事を辞めて思い切り伸び伸びと動ける今、北海道地平線の準備に関われることがうれしいです。自分なりに、動いてみたいと思います。これから、よろしくお願いします。[ちえん荘住人「工房はち」 笠原初菜 7月4日]
■西興部村猟区管理協会の伊吾田順平と申します。西興部村では、エゾシカを地域の自然資源として位置づけ、2004年から全村を鳥獣保護管理法に基づく「猟区」に設定して野生動物を管理しています。猟区とは、入猟者数・入猟日・捕獲対象鳥獣の種類・捕獲数などについて管理者が独自の管理をすることができるエリアのことです。西興部村は北海道東北部、オホーツク海から25km内陸に位置した、人口約950人の山村です(私が移住した2005年は1,200人ほどでした)。
◆基幹産業は酪農と林業で、全面積30,812haのうち、89%を森林が、5%を農地が占めています。農業はすべて専業の酪農です。急激に減少する人口を背景に村では移住定住対策として様々な取り組みを行っています。一戸建て新築住居への補助として200万円+子供の数×50万円。色彩統一事業として村の指定のカラーにすると屋根と壁で最大75万円。エンゼル祝い金として出産への支援、さらに今年度からは大学奨学金制度が新設され、給付型として月最大3万円、貸与型として大学卒業後、詳細は省きますが村に帰ってきて就職すれば借りていた奨学金の返済の半分まで補助対象となるなど、他にも様々な制度があります。
◆西興部村では村外ハンターは地元ハンターのガイドがなければ狩猟を行うことができません。それにより安全かつ効率的にシカを捕獲することができます。また、解体もガイドが率先して行うので、ハンターはシカさえ獲れれば、解体ができなくても美味しくて衛生的なシカ肉が自宅に届くようになっています。
◆私は主にそのハンティングガイドを生業としています。また、ハンターの高齢化や減少が深刻となっていますが、西興部ではハンター育成事業も行っており、新人ハンターセミナーや大学生実習、エゾシカの魅力を広く発信するために狩猟見学をメインとして村の自然を体験するエゾシカエコツアーなどを行っています。西興部での生活はとても豊かで、通年シカを獲ることができます。獲れたシカはすべて解体して、日本全国にいる知人と物々交換でシカ肉を送っています。シカ肉は食料品やお酒など様々なものに変わり、お米はほとんど買ったことがなく、最大で60kg程のたくわえがありました。
◆シカ肉以外でも山の恵も豊かで春は山菜、夏はヤマベを釣り、秋にはキノコを採って、毎日のように、今日も食材は買ってないねって話しています。[西興部村猟区管理協会事務局長 伊吾田順平]
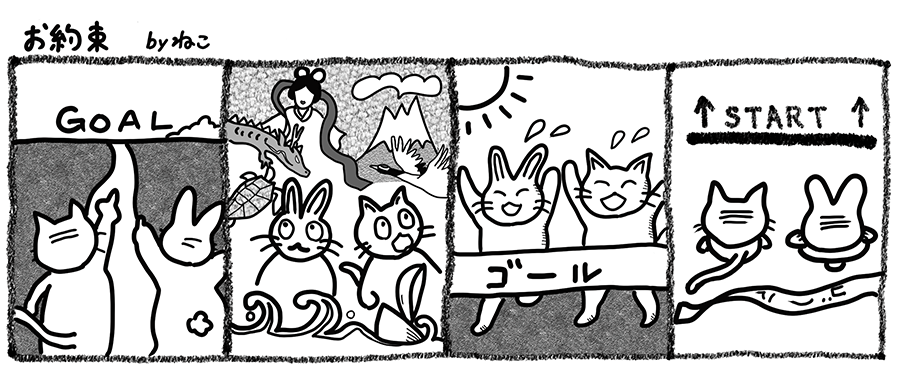
《画像をクリックすると拡大表示します》
■今年の私たち夫婦のGWは、天売島と焼尻島をメインとした北海道旅でしたが、西興部村のゲストハウスGA.KOPPER(ガコッパー)にも泊まりました。オーナーの浅野和さんとは、海外ツーリング仲間という元々の知り合いで、私たちにとっては友達に会いに行く、という感覚です。今までも何回か泊まりに行っています。
◆そして、6月もGA.KOPPER主催の「夏至カブ」(簡単に言えば、6月21日の夏至に、ホンダのバイク「カブ」で走る、というイベント)に参加するため、またまた西興部に行ってきました。イベントはもちろん楽しかったですが、GA.KOPPERの居心地は、いつ行ってもいいのです。素泊まりもできますが、ぜひ食事付の宿泊をお勧めします。
◆日本酒は杜氏経験のある浅野さんが日本各地のこだわりのお酒を揃えています。猟師の顔を持つ浅野さんが捕った熊や鹿の料理が出ることも。奥様が作る料理はどれもおいしく、盛り付けもおしゃれ! 本好きの浅野さんはたくさん本を揃えていて、音楽・楽器にも興味が深く、熊皮を素材にした手作りの太鼓があったり、ドラムセットもあったり、室内で色々楽しめます。
◆裏庭には、アイヌの仲間の協力で設計から2年がかりで今年5月に完成した、アイヌの住居チセがあったり、焚火もできますよ〜! 早春に落合大祐さんが行ったとき《注》はたまたま休館だったとのことですが、冬も営業してます。宿のすぐ前にバス停あり。GA.KOPPER宿泊を目的とした冬の北海道もいいかも……。来年地平線会議in西興部とのことですが、それとは関係なく、ぜひGA.KOPPER体験をしてみてください![古山もんがぁ〜里美]
《注》北海道での地平線会議イベント開催のリサーチを兼ねて、今年3月16日に落合が西興部を訪問。浅野さんとタイミング合わず、宿泊は叶わなかったが、伊吾田宏正さんと「GA.KOPPER」を訪ね、西興部で開催する場合の協力を浅野さんに依頼した。[落合記]
■2026年初秋に予定している北海道での地平線会議を成功させるため、先月から久々に1万円カンパを募っています。北海道地平線を青年たちが集う場にしたい、というのが世話人たちの希望です。交通費、宿泊代など原則参加者自身の自己負担としますが、それ以外に相当な出費が見込まれます。趣旨お汲み取りの上、北海道上陸作戦にご協力ください。協力いただいたカンパの使用については地平線通信でお知らせします。[江本嘉伸]
賀曽利隆 梶光一 内山邦昭 新垣亜美 高世泉 横山喜久 藤木安子 市岡康子 佐藤安紀子 本所稚佳江 山川陽一 野地耕治 澤柿教伸(2口)神尾眞智子 村上あつし 櫻井悦子 長谷川昌美 豊田和司 江本嘉伸 新堂睦子 落合大祐 池田祐司 北川文夫 石井洋子 三好直子 瀧本千穂子・豊岡裕 石原卓也 広田凱子 神谷夏実 宮本千晴 渡辺哲 水嶋由里江 松尾清晴
★1万円カンパの振り込み口座は以下の通りです。報告会会場でも受け付けています。
みずほ銀行四谷支店 / 普通 2181225 / 地平線会議 代表世話人 江本嘉伸
AM10時 ザック背負って学校へ。個人装備は米(5升 約2貫)も入れて5貫とチョット。野菜仕入れたり 石油買いに行ったり。パッキング 大きな圧力釜やザイルや野菜や肉やお菓子なんかを超特大のリュックに詰め込みます。膨れてゆくリュックをはらはらしながら見ている。12貫とチョット。
PM5時半 部室を出発 駒込までの道程でツカレル。上野。ホームにザックを置いて夕飯を食いに。駅のそばの食堂 冷やしソバ40円也。仲々おいしかった。ランチ60円也。まあ、安くて結構です。それから明朝のためにパンを40円買いました。何もはいっていない、おいしいミルクパン。ピッケルの紐が100円。ホームに見送りの人がずいぶん来ていてウィスキー1本やカルピスやお菓子を差し入れてくださる。お菓子は次の朝までに食べてしまったが、安いお菓子でネ、女子部の人たちがくれたのだそうです。
21:15 急行「北陸」ゴトリ、ゴトン、ゴトン……ガー。夜汽車ーー。外が真っ暗だという事はやっぱりつまらない。時々電燈、誘虫灯の光に、広い畑の一部が浮かびあがる。涼しすぎる風。ねむくなり、またねむらなきゃいけないと思い、目をつぶる。目をあける。クツもクツ下も脱いで裸足。鈴木、鴻農の両氏は座席の下にもぐりこんでねむる。寺本軍曹と江本さんは上で横になる。うつらうつら スース ゴトン、ゴトン。何度も目をあけてまた閉じて知らない駅にとまって走る。白んでくると、空が白んでくると もう朝です。日本海が見えた。静かな冷たい海。剱岳が見えた。雪渓がはっきりと見えている。大きい山たちがいる。魚津なんて所へ来るとじき降りるわけ。クツを履いて支度。富山 富山
AM6時50分 富山駅着 駅の冷たい水で洗面。きのう買ってきたパンを食べる。皆で食べる。
7時31分 富山発の電車。まったくすばらしい混み方でね。ザックの背中につけておいた麦ワラ帽子、グシャグシャなっちゃった。
8時45分 千寿原着。アイス最中なるものを10円で買って食べた。うまくない。氷のものは食べぬほうがいい。ここでちょっとブラブラして1時間半ほど。ケーブルカーに乗って美女平へ。
11時30分過ぎ バス1時間で弥陀ヶ原1930メートルへ。
PM1時10分 雨が降り始めて心細い。涼しく気持ちいいサ、と元気を出します。バスの中へ入り込んで昼食。カタパン4個、チーズ。十分の昼食と思った。
1時50分 出発。小雨の中、僕はトップ寺本氏のすぐ後について歩く。道は広く傾斜も緩いが雨でぬかって歩きにくい。矢村氏の足遅く、うしろで怒鳴る声。
2時35分 美松荘とかで小休止。歩き続ける。登りが急になって道はドロンこで狭い。ペシャッ! と膝をついて倒れたりしている。ズボンは真っ黒け。俺は歩き方がまずい。矢村氏遅れる。怒鳴り声 ファイト、ファイト! と言う。矢村一時グロッキー。天狗小屋前で甘納豆。午後5時頃。
7時 室堂キャンプ場着。嬉しかったね。へバッて動きがにぶい。鴻農、吉田が炊当(炊事当番のこと)になってミソ汁をつくる。ミソ汁のあたたかさ、うまさ。ミルクパンを食う。
10時20分 就寝。夜半、時に雨激し。
6時40分 起床。霧雨
8時 朝飯 玉ねぎ、油揚げの味噌汁 ヒダラ 朝飯後 霧晴れ素晴らしい青がのぞく。快適な気分。そこで僕は俺はどうせじきへばるんだから……、と嬉しい気分を強いて押さえる。男らしくない振る舞いである。出発後数分、矢村動かなくなる。弱気。俺だってヘタヘタになってへばりそうだが、まさか途中で帰るわけにはいかないじゃないか絶対に。続けるべし。続けるべし。結局、荷を軽くしてもらって矢村歩き出す。1時間のロス。地獄谷へ下る。硫黄のあの匂い。しばらくして水が見える。冷たい川の流れ。浅いが急な流れ。頭を水につっこんでいてメガネ流れ去る。もってかれた俺のメガネ。メガネなんかいらん。山は大きいぞ!と心に叫ぶ。渡渉。冷たくジーンとして痛い、が、快適。ここで昼食 カンパン6個。ジャム レモンパウダー。カンパンは山岳部特製のやつ、マーガリンがたっぷりで栄養価が高い。レモンパウダーは美味しいね。さて、登り。別山乗越の急な登り。荷は全然軽くなってない。あえぎあえぎ登る。だんだん足が重くなってくる。一歩をやっとこさで踏み出す。鴻農も遅れる。昼に飲んだ水がみんな皮膚から流れ出す。クタクタになって劔御前小屋に着く。早くテントに入りたいと思う。すぐ出発。下りである。ガタガタしながらも一所懸命歩く。雪を下りつつ眼前前劔の下に黄、緑、赤、橙、白……と多彩のテントを見る。ホッとするが、足は全くガクガク。鴻農つまずいて倒れること2度、足首を捻挫。キャンプ地に着くが、この夜のことメモしてなく、疲労していたためか記憶もない。
5時30分 起床。炊当。
7時朝食 飯 キャベツと豆腐の味噌汁 たくあん。鴻農捻挫のためテント動かぬこととする。
8時15分頃 鴻農テントキーパー 他は全員サブザックを背負って出発。平蔵の雪渓をつめる。雪渓登りなんとかいける。矢村が四六時中遅れ、しごかれている。俺は快適な気分とピッチでトップを追う。時に滑るがたいしたことはない。矢村、何度も滑っている。ラストの急な傾斜を掛け声かけながら登りきる。上にいた人たちが「えらい気合いがかかってましたなぁ、見てるだけで腹がしまりましたよ」などと声をかける。矢村をはさんだ一行を待って昼飯にする。カタパン6個。マーガリン 粉末ジュース。ジュースに雪をいれると実に美味しい。昼食は連日本当に楽しみである。滑落止めの練習をするため雪渓をちょっと降りる。途中岩のそばをトラバースする時、前を歩いていた横澤氏急に雪もろとも5、6メートル下に転落。薄雪を踏んだため。一瞬、愕然とするが元気な「畜生!」の声を聞いて一安心。傷らしい傷もせずに這い上がってきた。しかし、雪は怖い。下にザイルを張って滑落止めの練習。全然ヘタ。吉田のやるのは見事だ。チクショウと思うがどうしても腕が伸びちまってズルズル流される。ヤッケを着ているが早くもビッショリになる。何回も下までころがりそのたびにまた休む間もなく上へのぼる。矢村はうまくなった。俺はまだだめだ。ひざで止まっている。ズルズルともっていかれる。言われることはよくわかるのにやってみると相変わらずだ。段々エネルギーが消耗してくる。つかれが著しい。時間もなくなってグリセード練習にうつる。これができないときょうは帰れないと言う。必死になる。しかし、ヘタだ。すぐ転ぶ。足が伸びきって腰が曲がっちまって膝にバネがない。雪のかたまりに出会うとズデーンといく。ほんとによくすっ倒れる。適当なところでいよいよ下り。倒れては起き、起きてはつまづき、もう惰性で進んでいるようなものだ。フラフラしながら下る。下りに1時間かかったろう。下へ着いた時は疲労と寒さで気力全くなく、グロッキー。歯がガキガキとなる。途中で皆はマキ取りに。しかし、俺はそんな気力なくマキをもたされて先に帰る。星氏がしごき役。フラフラする僕を怒鳴り、ピッケルで尻をつく。ぼんやり一歩一歩足を出す。のろのろ歩いてキャンプにいつか着く。ヘタヘタ、テントに倒れ込む。さむい。服を替える。皆も1人2人と帰って来て、やがて飯。チクショウと唇かんで外に出る。カレー汁をかまどの火のそばですすりながらの夕食。実にうまい。ありがたいナと思う。元気も出てくる。言葉もでてくる。
9時 キャンプ出発。矢村また出発渋る。結局出発後数分には矢村テントへ戻り、9人のパーティーとなる。鴻農テントキーパー。平蔵谷の出合から源次郎尾根取り付き。俺は殊にはじめのうちモタモタして怖がってのろいピッチ。段々慣れてくると楽しくもなってきた。
PM1:50 ミルクパン、マーガリン、ジュース(雪入れて)、アンズの昼食。2峰の下り、25メートルの懸垂。ザイルをつけてもらったが、楽しいものだった。40分ぐらいで剱岳(3003メートル)頂上に立つ。すばらしい展望である。ここで甘納豆を食い、写真を撮る。僕はカンパンを拾って食べました。長次郎の雪渓をくだる。グリセードは相変わらずダメでころんだりすべったりをくり返している。でも、きのうより疲労も少なく気持ちも実に良い。少し雲が多くなってきた。焚き木を集めて横澤氏、小苅さんと帰る。この日何を食ったか忘れた。
炊当。6時起床。小雨。霧一面にかかり、劔全く見えず。焚き木に火つかず、ラジウスを使う。ガンダ飯。高圧ガマにまだ不慣れなせいかーー。ノリの佃煮 ラッキョウ。大根、豆腐の味噌汁 午前中ウタイマクッテイル
PM1時スギ ミルクパン マーガリン コンビーフ ホットミルクで昼食 食い物は唯一の楽しみだ。昼食後 ボンヤリ テントの中近所で歌う声しきり ハーモニカの音 時々 風でテントはためく ボンヤリしている 何か食べたい 下界のこと 家のこと 時に ものすごく侘しい。ハーモニカの音がきこえる。一日 停滞。
夜半から早朝にかけて雨。朝飯 ミソ汁(ジャガイモ、タマネギ) ノリ コブの佃煮 霧晴れて、劔眼前にそびえる。
9時過ぎパッキングにかかる。矢村帰りたい一念。怒鳴られたり、こづかれたり。でも帰る訳にはいかない。
10時半頃出発。矢村渋々歩き出す。急な雪渓の下り 荷があるので不安。しかし、アイゼンはつけない。3、4回滑ってその都度起き上がって12時45分、平蔵出合で遅れた一行を待つ。雨、降りはじむ。強くなる。ビニールを着るが、ちょっと寒い。
1時 雨の中、立ちながらミルクパン、グレープジュース(雨でみるみる水増しされちゃってうすい。まずい。捨てた。)の昼食。しばらくして雨も上がり、一気に真砂沢まで。ここを定着地とする。
長次郎谷へ向かう。全員。雪渓を半ばつめた頃、雨降り始め次第に強くなる。グリセードで引き返す。ほうほうのていでテントへ。雨ますます強く、豪雨。テントに浸水。高所からの水が流れ集まって一時奔流の中のテントと化す。吉田、裸で奮闘。皆、大笑い。しかし、夕刻晴れてくる。気持ちの良い雨上がりである。
全員早起き。矢村をテントキーパーとして7時30分 出発。二股への細い道を上り下りしながら1時間ほど。三の窓がこよなく蒼い空の中に我らを見下ろす。快晴。三の窓の雪渓 ーー上部はなかなか急ーー をつめる。ここで昼食。ミルクパン、マーガリン、ジュース。昼食後、江本、鴻農、小苅米、横澤、寺本の5人はジャンダルム2峰をAクラックから取り付く。寺本氏がトップ、ザイル2本を使って次々によじ登る。僕にとってははじめての岩場である。小さなガレで足すべらしてヒヤッとしてもどことなく楽しい。鴻農はずいぶん身軽く気持ちよく登ってゆく。2峰てっぺん、チンネのでっかい壁がおおいかぶさる。そろそろ夕刻時だというのに下の方のテラスには数パーティーが待っている。上の人もほとんど動かない。ハーケンの音だけがこだまする。こちらから小苅さんなどチンネのテラスに呼びかける。東工大の人らしい。向こうも声を返してくる。一番最後に鈴木、吉田の組がつく。アメをなめる。三の窓の雪渓。この上に東工大のテントがある。グリセード降下。二股のキャンプ地に東工大の本拠があってそこで休憩。小豆を煮て干したようなやつをもらって食う。アルコール分が入っているのか、そんな味がする。適当にバテながら真砂のテントへ。上級部員の松本、松永の両氏が出迎えてくれる。きょう合宿に合流したわけだ。矢村はいない。つまり“脱走”である。オレの腕時計 ーー朝預けておいたのだがーー もっていきやがった。新人はこれで3人となる。夜、ハヤシライスをすすりながらおいしく食う。
炊当。8時30分 長次郎谷めざして出発。出発時から膝がガクガクする。不安である。雪渓に入ってからも膝の痛みはひどい。とくに左足キリキリと痛む。半ば過ぎた頃、右の稜線目指して、つまり八峰上半をやるため江本、鴻農、吉田、松永、松本の5人は行動。残り6人は六峰Aフェースに取り付く。僕は足の痛みに泣き言を言いながらのろのろとついて行く。快適な道であるのに……。足の痛みさえなければと思う。イタくないのだと言い聞かせるが、キリキリとくいこむような本当に辛い。口惜しい。バカヤロウと、四六時中、心で叫んでいる。吉田、松本、江本の3人は池の谷乗越の雪渓から下りる。 鴻農、松永の2人は劔頂上へ。グリセード降下中、Aフェースの者に呼びとめられ、下のはい松おおわれた広いテラスに2、3時間。上で6人悪戦苦闘しているのにウトウト昼寝。いい気なもんだ。夜 ジャガイモ、タマネギ、ニンジンの天ぷら。(グンソウが揚げた)天ぷらはうまい。
きょうは、縦走へ移る第1日。別山平まで行けば良いのでゆっくりである。しかし、足のイタミが気がかりだ。
10時30分ごろ、テント担いで出発。歩き出してすぐ左ひざのイタミ、又ひどくなる。左腕のしびれがきょうは激しい。ザックの重みに左腕はダランと垂れ下がってツメタクなる。自分の腕のような気がしない。実に苦しむ。距離も大してなく、じっくり歩いていればすぐ着いてしまうような所なのにこの日ばかりは参った。ゆっくり歩いてもっぱらひとりしごかれて午後別山平着。女子部がテントを張っていた。時間が早いのでそばの雪渓でグリセード練習。これが最後の練習なのにやっぱり倒れてしまう。焚き木をとって帰営。夜 飯うまし。けんちん汁スープ 味噌とピーマンの煮たの。ーー 3年部員が作った。女子部と合流して夜、汁粉をつくる。
7時過ぎ出発。はじめの1ピッチ左腕のしびれ激しく難行。矢村脱走以来僕がどうも弱い。連日しごかれ役が続く。フーフー言って別山乗越へ。ホッとする。腕はしびれるが、足は続きそうである。別山、真砂岳、雄山を次々越える。このあたり団体や何かで実に人出が多い。一の越の小屋のそばで昼食。カタパン6 マーガリン、レモンパウダー。
浄土、ザラ峠を経てPM5時 五色ケ原に到着。ザラ峠にかかる少し前、雪渓に続く大きな斜面を鴻農足踏みはずしてころがり一瞬ヒヤッとする。運よく岩でとまったが足の運びは慎重でなければならない、と教えられる。ザラ峠や一の越の下りなどダラダラの長いガレ場下りに悩まされる。登りに比べ足の疲労も大きいようだ。夜 カレー汁 キャベツ、キュウリ、ソーセージで野菜サラダ。福神漬。ご馳走である。
女子部に1名故障者が出てわれらはここに一日停滞することとなる。上天気 きれいな花、石 鳥の声 のんびり 目の前に山々 あっちの方へ行く…… 草原に寝転んで書く ころがっている僕の下駄 草はやわらかい。静かにねかせてくれる。全然センチメンタリストになってしまう。丘の上からひとりで眺めた山々の夕暮れは 感無量 美しかった。
炊当。3時起床。マキの燃えつきすこぶるよく4時には朝食となる。うすあかり 朝明け。ジャガイモ 玉ネギ 麩の味噌汁 梅干し
6時出発 はじめ軽快な丘の散歩道 左腕のしびれも大した事なく気強し 日が高くなる。暑さが増す。汗はぜんぶ流れる。途中でカルピスを飲んでおいしい。
10時ちょっと過ぎ、スゴ乗越 カンパン6個 ジャム オレンジジュースで昼食先輩の持ってきた朝飯のノコリをイチゴジャムとミソで食う 登りを2ピッチでがんばり、薬師岳肩の辺に着きキャンプ。
2時前 すぐさまカマド作りから夕飯にとりかかる。途中で拾ってきた鯨のベーコンにジャガイモ、ニンジン、タマネギを刻んで茶飯 とってもうまい。紅茶をガブガブ飲む。ここからの夕焼けはいい、と聞かされていた。真っ赤な夕日の沈みゆく美しさを 皆立って眺めている。
5時15分ごろ ダイコンの味噌汁とアジのつくだ煮で食べる。質素だ。それでもうまい。今朝も茶の葉は入らず湯を飲む。
6時15分ごろ出発 薬師への長いダラダラ登りにうんざり。岩がゴロゴロの道。
9:00ごろ 2926メートルの薬師岳てっぺん 1ピッチ50分ぐらい下って、きれいな野原で昼食とする。ミルクパン8個 チーズ レモンパウダー1時間以上ここでボンヤリ(ねちゃった。スースー)さて、軽快な下り道を続ける。じきにゆるやかな登りとなり、太郎兵衛小屋が見えはじめる。のどかな美しい草原である。小屋から5、6分、テント場に着く。マキとりに草原のはずれまで行ってみる。そよ風。ウグイスの声。花タチの品のよい美しさ。清々しさ。けして折るまいと思う。荷はずいぶん軽くなったし、道もすばらしい。快適な山行と言おう。それにしても連日実に良い天気だ。
炊当 4時起床。ヒダラ ジャガイモ 麩の味噌汁
6時30分出発 黒部五郎の急なガレ登り。思った以上に苦しむ。それまでの道が平坦すぎたためか。てっぺんを下って雪解けの豊かな清流。その傍で昼食。カタパン7個、チョコリー、マーガリン、レモンパウダー 新人3人の写真をとってもらったり、実にいい休みでした。さらにくだって行く。冷たく澄んだ流れにちょいちょいぶつかるのに休みどころではない。うらめしい気持で歩く。やがて広い野原に出る。そこに水はない。小休止。三俣蓮華への登り、聞きしにまさるイヤな所。急な傾斜 枝にかじりつき、ザック ぶっつけながらのぼる。強烈なヤブ。ひどい所だ。上に出て甘納豆を食った時のうまさ。
3時頃、三俣蓮華の腹につきキャンプ。夕飯2升炊く。豆腐 ジャガイモのスープ。キャベツ ソーセージ、マヨネーズでサラダ。ピーマンのみそ煮。うまいうまい、と言いながら食う。相変わらず美しい日没である。
5時30分ごろ ジャガイモとお麩がほんの少しの味噌汁とヒダラで朝飯
7時スギ出発
8時30分 三俣蓮華小屋の前にザックをおろす。ここから1時まで行動が許される。新人3人とMr.軍曹の4人は雲の平へ。爺沢の水! イワナがすばしこく眼をかすめる。清々しい。冷たい。ピッチの早い登りとなる。僕は終始遅れる。時間があまりない。雲の平はどうってことなかった。反対側が素晴らしいのだそうだ。しかし、槍ヶ岳を中心にした山塊の全貌をはじめて眼前にする。堂々たる山容
1時過ぎ 駆け足下りで小屋前へ戻る。カンパンとジャム、ジュースで昼食 休む間もなく2時前には双六へ出発、すぐ登りとなる。登って歩いて下って4時過ぎ双六池着。途中アルプス銀座連なる槍、穂高の長い連峰に終始見とれる。夜は思わぬ拾い物でご馳走でした。カレー汁(ジャガイモ、タマネギ、ソーセージ、コンビーフ)みりん干し、キャベツ、ソーセージ、マカロニのバター炒め
炊当 槍への長い登りを開始 途中で誰かが拾った新聞で山中の活躍やミス・ユニバースのことなど知る。ゆかいな気がする。槍直下のガラ登り、へばりながら楽し。てっぺんは満員。眺めはいい。吉田は相変わらずモクひろいを稼いでいる。てっぺんから肩までおりたとき飲んだ雪を溶かしたジュースはうまかった。くだり。だらだらとガラガラとザーザーと。足が痛みだす。白出までの長い道。つらかった道。左足がひきつるようなイタミ。くだり歩行のまずさか。くだりを徹底的に嫌う。途中、穂高滝谷の出合を通る。見上げるとこわいような感じである。やっと出た白出沢はテント張れずこんもり林の中に背中の痛いシートを敷く。ソーセージ ジャガイモ、玉ねぎで茶飯。ソーセージ、ジャガイモ、玉ねぎ、春雨、長ねぎでおつゆ 寝苦しい夜である。
5時過ぎ あたりに鳥の声をききながら朝食 ゆるやかな林の道をゆっくり登る。やがて沢。左腕利かず、スタンスふるえ、ホールド探せず怒鳴られ通し どうもよくない。途中に小さいがすごい滝あり。感嘆。雪渓の途中、2、3度滑る。左肘に裂傷 血が出ただけのこと。合宿ラストの登り。横沢さんのトップ。声出しながら頑張って登りきる。
PM1:10 涸沢岳。鴻農と奥穂の頂上へ。てっぺんはガスって展望ゼロだった。涸沢の下り、雪渓でまたまた滑る。雪の上に立てば必ず滑ってしまう。どうしたのか。慎重のつもりなのに。俺が下手で雪渓下れず、皆も土の上をくだる。涸沢はテントでいっぱい。雨降りはじむ。一時非常に強し。うたれながら歩く。疲れてはいるがいい雨である。いよいよラストの歩きか、と思いながら黙って歩く。横尾。のんびりした平らな、きれいな所。人間も多い。夜 ウィスキーを小さなカップに一杯ずつ飲む。せんべいがある。チャーハン、スープ。皆丸くなって話しながら食う。寝たのは11時近く。
鴻農に起こされる。4時過ぎ、2人で最後の飯炊き。
横沢さん、5時30分頃、帰京第1号。パッキングしてさよならして、我ら2人、7時少し前に出発。荷の軽いことったら!(5貫、20キロぐらい) 梓川の流れに沿って平坦快適な道。
徳沢 8時前 ここで25円奮発 キャラメルを買う。はじめて使う金、なんともなく嬉しい。徳本峠の登り。快適ゆるいピッチで11時頃か頂上をきわめる。穂高の姿がすばらしい。カンパン、レモンパウダーで昼食。「ジャム、パクってくるんだったな」九大山岳部の人とカンパンを交換、飯盒の冷や飯をもらう。スープの素(チューブ)をかけて食べる。うまい。ご飯はうまい。
12時下り開始。コンディションは上々とは言えないが、道はきわめてラク。渓流づたいにながあい島々宿までの乱歩がはじまる。
18歳の夏山日記後記
■夏山の季節だ。大きな山、小さな山の違いはあれど皆さん、あちこちに出かけると思う。80年を超える私の人生を振り返って一番大事な時間は、実は18歳の初めての夏山合宿だったのでは、と最近しみじみ考える。横浜の海辺に育った私は山といえば丹沢しか知らないやわな少年だった。大学に入って初夏のある日入部を決意。先輩に言われて登山靴(7000円のを3回分割払いで)、超特大キスリング、進駐軍放出の寝袋(これはアメ横で)を買い、初めて山岳部の夏山合宿に参加した。◆本来なら4月の谷川岳で雪渓の登降を学び、6月の三つ峠で岩登りの基礎を叩き込まれてから長期の夏山に向かうのだが、遅れて入部した私はその過程がなく、いきなり長い、重い夏山につっこんだ。覚悟はしていたが、聞きしにまさった。そして、もちろん、山々は美しく、険しいが優しかった。この貴重な時間を記録しておこう、と小さなメモ帳に日々の行動を書きつけた。
◆下山して最初にやったのは、重いザックで麻痺し、だらんとぶら下がったままの左腕を上げ下げするトレーニングだった。今思い出してもぞっとする左腕の麻痺。お湯の中だとよく動いたので銭湯によく通った。そして、忘れないうちに、とメモ帳の記録を3Bの鉛筆で大学ノートに書き写した。ノートのタイトルを「登ったり降ったりのメモ」とした。それを大切に保管し、以来誰にも見せないまま今日まできた。
◆近年、若い人たちに地平線会議の心をいかに伝えられるかを、私は自分の使命と考えるようになった。そして、18歳の夏山日記が青年たちが何か考えるきっかけになるかもしれない、と気がつき、大学ノートの文字をパソコンに打ち込んだ。自分で書いたものなのに読みながら面白かった。地平線通信の貴重なページを借りるに値すると考え、今号でお伝えした。
◆なお、合宿から“脱走”した矢村は山岳部に戻ることはなくのちに仲間とワンゲル部をつくった。山岳部はとうに消滅したが、ワンゲル部はいまも存続している。外語山岳部は当時かなり先鋭的なクライミングを目指していたからか、同期の他の新人2人もやがて退部してしまい、はじめの4人の中で結局ひ弱だった私だけが残った。山岳部がくれる喜びを感じる度合いが少し強かったせいだと思う。[江本嘉伸]
■7月4日の午前11時51分、岡村隆さんはFacebookにこう書き込んだ。「白血病に進んでしまった。バタバタの最中ですが、皆さまこれまで本当にありがとうございました。お一人お一人にお礼申し上げます」。私はもう何年もFacebookを覗いていなかったので、岡村さんを継いで月刊『望星』の編集長をつとめている石井靖彦さんから電話でこれを知らされたのだが、思わず「えっ」と大声を出して、道行く大勢の人たちから注目を浴びてしまった。
◆帰宅して4年ぶりにFacebookにログインしてみると、すでに40件近いコメントが並んでいる。なかには弔辞のような文章もあったが、水泳の池江璃花子選手の例も頭にあって、あまり深刻には受け止めていなかった。しかもすぐ下には6月29日付けで、宮崎の実家に帰って草刈りや木々の伐採に明け暮れながら、田舎暮らしを楽しんだことが写真入りで軽妙につづられている。「お別れ」が近いなんて、信じられない。
◆岡村さんからは、いまの病気(骨髄異形成症候群)は白血病の前段階で、進行を食い止めるために月に7日通院して注射を受けていると聞いていた。注射中と直後の1週間ほどはシンドイが、あとの2週間はなんとか普通に過ごせる。調子のいい日は軽く晩酌もするし、昔の仲間と痛飲することもあったようだ。地平線通信4月号に掲載された「『老後』『病後』の計画修正」には、病気とうまく付き合いながらマイペースで生きていこうという、静かな決意がうかがえる。
◆ところが、あのFacebookの書き込みは最後の力を振り絞った挨拶だったようで、容体はどんどん悪化していき、7月9日の朝9時56分に息を引き取った。関野吉晴さんによると、白血病のなかでもきわめて悪性度の高いもので、主治医も驚くほど急速に進行してしまったそうだ。享年76歳。あまりにも早すぎる。病気というより、事故でいきなり岡村さんが連れ去られたような気がしてならない。最期はモルヒネで激痛を抑えていたそうだが、苦しむ期間が長くなかったのをせめてもの救いと思いたい。
◆岡村さんは1948年、霧島山の麓にある宮崎県小林市で生まれた。米どころだが畜産も盛んで、小学生のときは家の牛の世話を受け持ちながら、野山を駆け巡っていたという。『宝島』や『ロビンソン・クルーソー』を野外遊びのテキストにし、トム・ソーヤー流の探検ごっこに夢中になったが、中学2年で読んだヘイエルダールの『コン・ティキ号探検記』でホンモノの探検を知り、大きな衝撃を受ける。
◆高校時代は文学に親しんだが、法政大学の探検部がモルディブに遠征隊を出すという記事を受験雑誌で読み、文学部日本文学科(というより探検部)に進学。2年生となった1969年にモルディブへと出かけた。独立直後の鎖国政策のせいで入国許可がなかなか出なかったが、スリランカ(当時はセイロン)のコロンボにある大使館に3か月通い詰めると、ある日突然許可が下りた。
◆3名の探検部員はさっそく首都のあるマーレ島に渡って文化人類学的なフィールドワークを始めたが、1か月もすると、学問では島の人たちのほんとうの心の中はわからないのではないかと思えてきて、調査を放りだしてしまった。その後は漁師の家に世話になって、海で泳いだり釣りをしたり、帆船で島めぐりに出かけたりと気ままに半年間過ごす。島の娘さんといい雰囲気になったが、20歳の若さで人生を決めてしまいたくないという気持ちが強く、逃げるように島を離れた。
◆この遠征でスリランカ滞在中に、数多くの仏教遺跡が密林に埋もれたままになっていることを知った岡村さんは、以後スリランカ政府考古局などと連携しながら、法政大学探検部として7次にわたる遠征隊を派遣。2008年に「NPO法人南アジア遺跡探検調査会(SARERS)」を立ち上げてからは、他大学の探検部員や研究者たちも巻き込みながら、遺跡探査を続けた。この功績に対して、2018年の植村直己冒険賞が贈られている。
◆大学卒業後、小さな出版社でサラリーマンをしていた岡村さんは、かつて憧れたヘイエルダールがモルディブで「太陽神殿」を発見したというニュースを知るが、違う、それは仏舎利塔だと確信し、1983年に14年ぶりにモルディブを訪れた。この旅は『モルディブ漂流』(筑摩書房)という文学の香り高い名著となって結実する。
◆これを機に出版社を辞めた岡村さんは、編集プロダクション「見聞録」を立ち上げ、作家として小説を書き、月刊『望星』(東海教育研究所)の編集長として多くの書き手を育てながら単行本を送りだしていくことになる。……と、ここまでで字数が尽きた。岡村さんの人生に決定的な影響を与えた日本観光文化研究所とのかかわりや私との個人的なエピソードなどは、稿を改めたい。[丸山純]
■記念すべき「555号」は思いがけず岡村隆の訃報を伝える号となった。彼についてはいろいろな人の感慨があると思う。夏だよりとは別に8月号であらためて特集のようなかたちを考えている。
◆岡村隆といえば惠谷治だ。惠谷が逝ってしまったときの岡村の弔辞は切々と心をうつものだった。確かこの通信に全文掲載させてもらったな。もう逝って7年にもなるが、今回惠谷夫人とも久々にお会いしてとても懐かしかった。別れは再会の場でもある。
◆66年も前の夏山日記をついにお見せしてしまった。内容からいって自分以外には読ませられないと思い続けていたが、あの時代、あるいは私の貧しき青春を知ってもらうにはいい潮時だったかも。ご寛恕のほどを。[江本嘉伸]
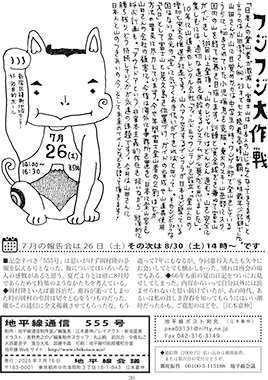 |
フジフジ大作戦
「日本人の登山者が激減し、富士山は日本人の山じゃなくなってきてます」と言うのは山田淳(あつし)さん(46)。23才で七大陸最高峰制覇。当時最年少記録でした。 山田さんが山に目覚めたのは中学生の時。ワンゲル部で登山をしているうちに、悩まされていた小児喘息を克服。東大のスキー山岳部に入り、国内の山を経て世界を目指します。 訓練と資金稼ぎを兼ねて富士山ガイドをし、300回以上登頂。「山のレジャー化はどんどん進む。山を安全に楽しむには、適切な道具を供給するシステムが必要だと思いました」 '10年に山道具のレンタル会社「フィールド&マウンテン」を設立。「登山人口の増加と安全の推進が社是です。山へアクセスするインフラが日本ほど整っている国はない。足元の「宝」に気づくお手伝いができればと思って」。 そのシンボリックな「入口」として富士山と屋久島を位置づけ、ガイドの育成や山道具使用方法の普及に尽力しています。今や年間富士登山者の2割ほどが山田さんの会社の顧客に。今後は海外に事務所を置き、日本に登山客を呼ぶ計画も。「アウトドアという、非資本主義的存在を扱いながら、経済的に勝ち残り、どう持続していくかが永遠の課題です」。 今月は山田さんに、日本人と山のつきあいの今、そして未来のイメージなどを語って頂きます! |
地平線通信 555号
制作:地平線通信制作室/編集長:江本嘉伸/レイアウト:新垣亜美/イラスト:長野亮之介/編集制作スタッフ:丸山純 武田力 中島ねこ 大西夏奈子 落合大祐 加藤千晶
印刷:地平線印刷局榎町分室
地平線Webサイト:http://www.chiheisen.net/
発行:2025年7月16日 地平線会議
〒183-0001 東京都府中市浅間町3-18-1-843 江本嘉伸 方
地平線ポスト宛先(江本嘉伸)
pea03131@nifty.ne.jp
Fax 042-316-3149
◆通信費(2000円)払い込みは郵便振替、または報告会の受付でどうぞ。
郵便振替 00100-5-115188/加入者名 地平線会議
|
|
|
|
|
|