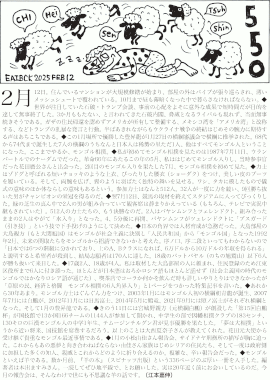
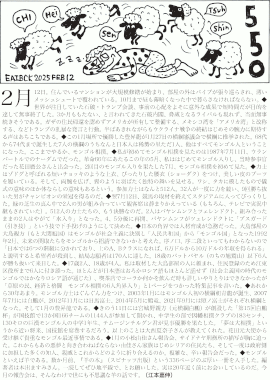
2月12日。住んでいるマンションが大規模修繕が始まり、部屋の外はパイプが張り巡らされ、薄いメッシュシュートで覆われている。10月まで昼も薄暗くなった中で暮らさなければならない。
◆世界が注目していた石破・トランプ会談、事前の心配をよそに意外な成果で短時間だが目的を達して無事終了した。3か月ももたない、と言われてきた石破内閣、脅威となるライバルも現れず、当面無事続きそうである。ガザの住民帰還を認めずアメリカが所有して整備する、メキシコ湾を「アメリカ湾」と改称する、などトランプの乱暴な発言と行動。半ばあきれながらもウクライナ戦争の終結はじめその腕力に期待する声はあちこちである。
◆この1月場所で優勝した豊昇龍が1月27日の横綱審議会で横綱に推挙された。68代から74代まで誕生した7人の横綱のうちなんと日本人は稀勢の里ただ1人、他はすべてモンゴル人ということになった。ここまでやるか、モンゴル相撲。
◆私が初めてモンゴル相撲を見たのは1987年7月11日、ウランバートルでのナーダムでだった。革命66年にあたるこの年の5月、私ははじめてモンゴル入りし、当時参事官だった花田麿公さんと出会った。2回目のモンゴル入りを果たした7月、モンゴル相撲を初めて見た。
◆力士はゾドグと呼ばれる短いチョッキのような上衣、ぴったりした腰衣(ショーダク)をつけ、美しい皮のブーツを履いている。そして、両腕を広げ、翼のように羽ばたく独特の舞いを見せる。ワシ、タカに模したもので儀式の意味のほか体ならしの意味もあるという。参加力士はなんと512人。32人が一度に力を競い、9回勝ち抜いた男がチャンピオンの栄冠を得るのだ。
◆翌7月12日、競馬の取材を終えてスタジアムに入ってびっくりした。緑の芝生の真ん中で2人の男が組み合っていて観客席は静まりかえっている(もちろん、テレビで実況中継もされていた)。512人の力士たちの、もう決勝なのだ。2人はバヤンムンフとツェレンドクト。組み合ったままの2人はやがて「水入り」となった。4、5分後に再開、バヤンムンフがツェレンドクトに「ブスガード(引き技)」という技で下手投げのようにして決めた。
◆日本の角界では人材育成が急務だった。大島部屋の大島親方(もと大関旭国)はモンゴルが社会主義に決別し「人民共和国」から「モンゴル国」となった1992年2月、未来の関取たちをモンゴルから招請できないかと考えた。序ノ口、序二段といってもわからないので「日本では6つの階級に分かれており、上のA、Bクラスになれば、6万ドルから10万ドルの年収を得られる」と説明すると希望者が殺到し、結局志願者は170人に達した。18歳のバットバヤル(のちの旭鷲山)以下6人が勝ち抜いて来日した。
◆17歳2人、18歳が4人。私は取材した大島部屋の人に頼まれ、住民登録のため江東区役所まで6人に付き添った。ほとんどが日本語はおろかロシア語もほとんど話せず(社会主義国の時代のモンゴルではかなりロシア語が通じた)、喫茶店でコーラか何かを飲んだ時も詳しいやりとりはできなかったが「草原の民、経済と格闘 モンゴル相撲の6人角界入り」と1ページをつかった特集記事を書いた。
◆あれから30年あまり。モンゴル力士はぐんぐん力をつけ、2003年1月にはモンゴル人初の横綱朝青龍が誕生、2007年7月には白鵬が、2012年11月には日馬富士、2014年5月に鶴竜、2021年9月には照ノ富士がそれぞれ横綱となった。そして1月の豊昇龍である。
◆きのう11日には宮城野親方(元横綱白鵬)が創設した「第15回白鵬杯」が国技館で13か国166チームの1144人が参加して開かれ、中学生の部で因幡相撲クラブの183センチ、130キロの巨漢モンゴル人の中学1年生、テムージンチルグン君が見事優勝を果たした。「夢は大相撲」というから近い将来、国技館を席巻するだろう。以上のことは大西夏奈子さんが教えてくれた。花田元大使から受け継ぐ貴重なモンゴル最近事情である。
◆1月の小松由佳さん報告会、サイドナヤ刑務所の描写が胸に迫った。これからもあの悪夢と向き合わねばならない由佳さん家族はじめシリアの住民たち、そして一度は政府側に加担した多くの知人、親戚とこれからどのように折り合えるのか。複雑な、辛い報告会だった。
◆モンゴルといえば羊である。数か月前、『羊の本』(スピナッツ出版)という336ページのぶ厚い一冊を入手した。編著者は本出ますみさん。一読してぜひ地平線で、とお願いした。実は20年近く前にお会いしているのだ。今月の報告会は、そんなわけで世にも不思議な羊の話です。[江本嘉伸]
■2025年初、数えて513回目となる今回の地平線報告会に登場してくれたのは、元日にシリアから帰国したばかりのフォトジャーナリスト、小松由佳さんだ。彼女は2008年以降、砂漠に生きる人々の暮らしを記録するためにシリアを訪れ、それを写真家として記録してきた。昨年12月8日にアサド政権が崩壊したことは記憶に新しいが、政権崩壊から1週間と経たないタイミングでシリア現地を訪れたという貴重なレポートを、地平線報告会という場でお話しいただいた。
◆由佳さんが取材のために日本を発ったのは12月7日。当初はシリア人難民の移住先での暮らしぶりを取材するつもりで、イギリス、フランス、ドイツで取材の予定を組んでいたものの、飛行機の乗り継ぎのために韓国にいたタイミングでアサド政権が崩壊間近というニュースが飛び込む。反体制派がダマスカスの1キロ手前まで来ていて、24時間以内に確実にアサド政権が崩壊するだろうという報道が出始めていたのだった。
◆そこから15時間のフライトを経て、ロンドンの空港に到着したのが12月8日の現地時間午後4時半、シリア時間昼12時。スマートフォンに電源を入れた途端にアサド政権崩壊というニュースが入ってきた。53年間にわたって独裁を続けた政権が崩壊するという歴史の重みをそのときに感じ、今すぐにでもシリアに行きたいという衝動に襲われた由佳さんだが、それでも気持ちを抑えて予定していたロンドンでの取材を始めた。
◆しかしイギリスに来て3日目、フェイスブックで見たあるコメントをきっかけに由佳さんは考えを変えることになる。「シリアに行きたいけれどヨーロッパで難民取材をしなければ」という由佳さんの投稿に対して、「一生に一度の機会かもしれないから見逃さない方がいい」とコメントをしてくれた人がいたのだ。しかし、8歳の長男を連れてきていたため、今シリアに行くことで息子の身に危険が及ぶリスクが拭えない。しかし今行かなければ、時代の転換点に立ち会えなかったことを一生後悔することになる。
◆それでもやはり今シリアに行くのであれば、由佳さんにとって外せない条件が一つあった。それは、シリア人の夫ラドワンさんも取材に同行してもらうということだった。生活を切り詰めてシリアへの取材費を捻出している由佳さんにとって重要なのは、コストに見合う価値のある取材ができるかどうかという一点に掛かっていた。ただ単にアサド政権崩壊後のシリアをレポートするだけであれば、大手メディアの報道に任せればいい。もし夫が同行してくれるならば、13年ぶりに祖国の地を踏む難民という当事者の視点で取材することができると思ったからだ。
◆夫のラドワンさんは13年前に徴兵により政府軍兵士となったが、同胞に銃を向けることを拒否して軍を脱走している。アサド政権下では、脱走兵は死罪となるため、二度と祖国に戻れないことを覚悟した上で脱走し、難民となったのだ。
◆シリア行きを決めた3日後、12月16日に夫のラドワンさんとレバノンの首都ベイルートで合流し、長男も含め3人でシリアに向かった。ベイルートから車で1時間ほどで国境に到着したが、アサド政権崩壊によりパスポートさえあればもはや誰でもシリアに入国できるのだという。由佳さんは2年前の2022年にシリアで取材を行った際はビザ取得が非常に困難だったため、これだけでもかなり大きな変化だ。
◆国境を越えてダマスカス市内に入ると、街中にも政権崩壊による変化が多くみられた。アサド政権下においてはいたるところで飾られていたアサド大統領のポスターも路上に廃棄され、今では反体制派の国旗が街中にあふれている。放置されたたくさんの軍事車両がホムスの方を向いており、最後の激しい戦闘が反体制派と政府との間で行われたことを物語っていた。こうした戦車や軍事施設はアサド政権下では撮影厳禁だったが、今では記念撮影をしたり、戦車に登っている人までいる有様だ。
◆不安に感じた由佳さんがシリア人に確認すると「アサド政権が崩壊した今、これはもう私たちのものだから大丈夫」とのこと。アサド政権の旗は燃やされ、反体制派のヒーローがプリントされたTシャツを売っていて、それを着て歩く人々がダマスカス市内には溢れていた。治安は良く、数日前まで滞在していたイギリスよりも安全だと思えるほどだった。こんなに短期間で時代が大きく動いたことに由佳さん自身も非常に驚いたが、それは現地のシリア人も同じだったようだ。街でインタビューしたシリア人たちも歴史の激動を目の当たりにして、とても信じられない思いだと語っていた。
◆シリアに入って2日目、由佳さんには必ず行くと決めていた場所があった。それが、夫のラドワンさんの兄であるサーメルお兄さんが収容されているというサイドナヤ刑務所だ。サーメルお兄さんは、由佳さんがシリアで何度も取材を重ねてきた大家族、アブデュルラティーフ家の六男で、冗談が好きでいつも陽気なお兄さんだった。アラブの春がシリアに飛び火した2011年頃、反体制派の若者たちと共に「シリアに自由を!」と叫んで投獄され、それ以降行方知れずになっていたのだ。
◆実はシリアに入る前にサイドナヤ刑務所の名簿を確認していて、サーメルお兄さんが2013年10月30日に亡くなっていることはすでにわかっていた。それでも、サーメルお兄さんがどんな場所でどんな時間を過ごしたのかを知るため、サイドナヤ刑務所に向かった。ダマスカスからサイドナヤ刑務所までは車で1時間、タクシーでの往復料金は150ドル。シリア人の平均月収は40ドルであることを鑑みれば、かなり高額だ。サイドナヤ刑務所にはすでに多くの人が集まっており、行方不明者を探しに来た人々、ジャーナリスト、ユーチューバー、あるいはピクニック気分で来ている人たちもいた。
◆由佳さんたちは、刑務所の中に入っていく。中は真っ暗でほとんど何も見えなかったが、その中の一室に、激しい異臭が漂う部屋があった。地面にはドロドロした液体が溜まっており、由佳さんは撮影のために部屋の奥にまで入っていったが、3メートルほど進んだところでドロドロの液体に足を取られて進めなくなった。その場にいたシリア人たちによれば、なんと人体の一部が腐敗したものだという。その部屋には、囚人の遺体をカットするための大型の機械があり、そこで処理された人体から流れ出たものが液体状となり腐敗した。それが、「ドロドロ」の正体だった。“人体の腐敗臭”を初めて嗅いだ由佳さんは絶句し、息子に「これはなんの匂い?」と聞かれても答えることができなかった。
◆サイドナヤ刑務所は、非常に劣悪な環境だったことが知られている。ここに送られた囚人はまず最初に、半地下の雑居房に収容される。その3メートル×4メートルほどの空間の中に10~20人もが収容され、真っ暗で灯りもなく、非常に寒く、食事も一日あたり、3人で1枚のパンを分け合うだけである。それだけでも地獄だが、毎日ひどい拷問が行われる。元囚人によれば、サイドナヤ刑務所での最大の死因は、看守たちによる撲殺だったという。最初に収監される地下の雑居房では次々と囚人が死亡していき、生き残った者だけが、2階以上にある雑居房に送られる。しかしそこでも、囚人たちは飢餓と恐怖と暴力に直面し続ける。サイドナヤ刑務所は、「人間虐殺の場」と呼ばれてきた。ここに送られた囚人の75パーセントが生きては帰れないと言われ、幸運にも釈放された人々も、その半数が精神に異常をきたしているとされる。アサド政権下、このサイドナヤ刑務所をはじめ、シリア各地の収容所に送られた市民たち約10万人が、今も行方不明になっている。
◆後日、サイドナヤ刑務所から生還したという2人の元囚人にインタビューする機会を得た。由佳さんは彼らに「どのようにサイドナヤ刑務所を生き延びたのか、囚人たちの生死を分けたのはなんだったのか」と尋ねた。彼らによれば、まず痩せていたり、身体が頑丈ではない者が先に亡くなっていったという。激しい拷問を毎日受けるため、どんなに精神が強くとも、拷問に耐えうる頑丈な身体でなければ生き残れなかった。また、“物事を深く考える人”は、人よりも早く精神に異常をきたして亡くなっていった。教養のある人ほど、この環境の不条理さに耐えられず、精神に異常をきたす確率が高かったらしい。そして精神に異常をきたしてから亡くなるまで、そう時間がかからないのだという。サイドナヤ刑務所では、そうやって亡くなった囚人を見せしめのため、雑居房にしばらく放置していた。そうやって放置された死体を見ながら、だんだん何も感じなくなり、そこで生きのびるため、人間らしい感情を失っていかなければならなかったという。由佳さんは衝撃のあまり、インタビューの途中で涙を流す2人の写真を撮影し忘れた。取材中に撮影し忘れたのは初めての経験だったという。
◆サイドナヤ刑務所での取材を終え、ダマスカスに戻ってからシリア中部のホムスという街に移動した。ここはシリア第3の大都市で、経済の中心地、交易の拠点でもあり民主化運動が盛んだった街の1つだ。ここで、由佳さんの友人であるシリア人女性とその家族に会うことになった。彼女はもともとパルミラで養鶏場を運営していたのだが、空爆で街が破壊されて生業を失い、今は最低限の生活を送っているのだという。
◆電気も1日30分しか使うことができず、燃料を買うお金がないため厳冬期でも防寒具を着込むことで凌いでいるそうだ。今でも生活は貧しいが、アサド政権が崩壊してからは政府に脅かされることもなく、自由を謳歌していると彼女は語った。そして物価にも変化があった。アサド政権下では政府系の企業が間に入って手数料をせしめていたことで食料品の価格が高騰していたようだが、今では目に見えて物価が下がったのだという。
◆ただ、彼女にとっての最大の懸念点は、アサド政権下で政府の協力者として働いていた息子が反体制派に逮捕されるのではということだ。息子もそれを恐れていて、今はずっと家に引きこもっているのだという。当時、政府系の仕事は給与が良かったこともあり、生活のためにその仕事をせざるを得ないという事情があった。しかし、そのような人々の働きによって、アサド政権下では多くの人々が殺され、大切な人を失う苦しみを味わうことになった。彼らが反体制派の裁きを受けるかもしれないということに対してどう思うか、由佳さんが夫のラドワンさんに聞くと「それも彼の選択だ」とのこと。政権崩壊後の今、シリアの人々は微妙な立場に置かれているのだ。
◆その後、夫ラドワンさんの故郷であるシリア中部のオアシス都市・パルミラへ向かった。パルミラに向かう道中、夫のラドワンさんは「今改めて振り返って、アサド政権に屈しなかった自分の選択を誇りに思う」と話した。ラドワンさんはもう二度とシリアに戻れないことも覚悟の上で、それでも民衆を弾圧することを拒否して脱走兵となった。それによって、13年間シリアに帰ることができなかったが、今は自分自身に対して誇らしい気持ちで故郷に帰ることができる。だから自分の判断は間違っていなかったし、そういう判断ができた自分に対して誇りを感じると語っていた。
◆2年前にも由佳さんはパルミラを取材していたが、そのときには親族の家に軟禁状態で、ほとんど身動きが取れなかったのだという。それに比べて今ではまったくの自由で、こうなるのであれば2年前に無理して取材しなくても良かったのではと思ってしまうくらいに拍子抜けした。
◆夫の親族の家で、由佳さんとラドワンさんを迎えるためのパーティが開かれた。たくさんの料理が準備されたが、予定よりも多くの人が集まったことで、料理は男たちに食べ尽くされてしまった。たくさんあったはずの料理のうち、由佳さんの食べる分はほとんど残されていなかったことをラドワンさんに愚痴ったとき、「女だから仕方ないよ」と言われ、由佳さんは、夫の考え方がイスラムの伝統的なものに回帰しつつあることに気づいた。
◆由佳さんが夫と共にシリアの土地を踏んで思ったのは「夫はいつかシリアに帰るのかもしれない」ということだ。シリア行きを提案したとき、ラドワンさんは、13年ぶりに故郷に戻れることを喜ぶ一方で、「空爆でボロボロになったシリアを見たら、過去の美しいシリアの記憶が失われてしまう」と危惧していた。しかし、今回の帰郷によって考えが変わったのだという。ラドワンさんは、いつかシリアに戻って生活する未来を考えているようだった。いつかそうなるかもしれないとは思っていたけど、その日が決して遠くないかもしれないということを由佳さんは悟った。アサド政権崩壊という歴史の大きな転換点に立ち会うとともに、由佳さん自身の家族としても変化の予兆を感じさせたシリア取材であった。
◆私が初めてシリアのことを知ったのは、2010年に見たNHKの旅行番組だった。古都アレッポのマーケットはとても賑やかで、鮮やかな色彩に溢れる異国情緒が漂う美しい街だった。大学受験で1日中勉強浸けだった当時の私にはとても眩しく映り、大学生になったらいつか訪れたいと思っていた。しかしその翌年、私が晴れて大学に入学したころにアラブの春が勃発し、シリア内戦へと突入。淡い憧れを持っていた異国の地が、もう絶対に訪れることができない場所になってしまっていたのだ。
◆今回レポートを書くにあたり、由佳さんが2020年に執筆された『人間の土地へ』(集英社インターナショナル)を拝読した。家族を愛し、砂漠を駆け回って自由に暮らすシリア人の生活が由佳さんの視点から瑞々しく描かれ、ノンフィクションでありながら文学のような繊細さが漂う美しい作品だった。ラドワンさんをはじめとして難民たちが祖国を離れた13年間はあまりにも長く、戦争で大切な人を亡くした悲しみは消えない。美しかったシリアの街は傷つき、シリア人同士の分断も残っている。それでも、止まった時間が再び動き出したことを祝福したい。シリア人の家族と暮らし、当事者として独自の視点でシリアを取材し続ける由佳さんの今後の報告から目が離せない。[貴家蓉子]
■2024年12月8日夜、取材先のロンドンの空港に到着した私は、スマートフォンに流れる報道に目を疑った。半世紀にわたって独裁を維持したシリアのアサド政権が、崩壊したというのだ。これは大変なことが起きた、というのが正直な思いだった。
◆シリアでは2011年以降内戦状態が続き、空爆や戦闘などによって50万人以上が死亡、500万人が難民となり、国内では720万人が避難生活を送っていた。こうした中での政権崩壊は、内戦の終結とともに、国外に逃れた多くの難民が故郷に帰還できる可能性を示すものだった。これまで難民の取材を行ってきた私は、このシリアの歴史的展開に興奮した。
◆今すぐ、シリアに向かいたい。しかし懸念は、8歳の長男を連れていたことだ。政権崩壊後、シリア国内の軍事施設を標的にしたイスラエルの空爆も数多く、混乱状態のシリアに子連れで入ることは躊躇された。その打開策ということもあり、夫も同行することになった。
◆シリア中部パルミラ出身の夫は、2011年に徴兵された。しかし同年、国内で民主化運動が拡大し、政府の立場から市民を弾圧する任務を負うことになる。悩んだ夫は、2012年に軍を脱走してヨルダンに向かい、難民となることを選んだ。そのため政権が倒れない限りは、二度とシリアに戻れない身となっていた。しかし政権崩壊により、その軛がなくなったのだった。
◆2024年12月16日、政権崩壊から8日目のシリアに、夫と息子と共に入国を果たした。夫にとっては13年ぶりの祖国だ。これまでアサド政権の恐怖支配の下、市民は厳しい言論統制を受けてきた。しかし今回目にしたのは、抑圧からの解放に歓喜し、自由に思いを語り合う人々の姿だった。かつて権威の象徴としてあらゆる場に掲げられていたアサド前大統領の写真は路上に捨てられ、街中には、政権を打倒した反体制派の国旗が、人々の大きな期待とともに掲げられていた。
◆二週間の取材期間、夫の故郷パルミラにも立ち寄った。タクシーの車窓にパルミラの街が近づくと、夫は、自分が誇らしい、と話した。市民の弾圧行為に加担しないことを決め、国を離れ難民になったこの13年間は、簡単な道ではなかった。しかし今、自分の決断に誇りを持って故郷に帰ることができる、と。しかしそうした夫の前に現れたのは、空爆によって市街地の8割が破壊され、瓦礫となった故郷だった。「とても嬉しくて、とても悲しい」。故郷に帰ってきた喜びと、故郷の悲惨な現実への悲しみに、夫は立ち尽くした。
◆家や街は再建できても、亡くなった人々はもう戻ってこない、と夫は言う。2012年に政治犯として逮捕され、刑務所での死亡が確認された夫の兄サーメルや、2021年にトルコで難民として亡くなった父親もその一人だ。今後シリアに平和がもたらされても、以前と同じ日常を送ることはもはやできないという。14年間の内戦によって人々が失ったものには、二度と手にすることができないものも多いのだ。
◆シリアでは今日も、破綻した経済と崩壊したインフラのなかで、国民の9割が貧困ライン以下の生活を送っている。空爆で破壊され、瓦礫と化した多くの街をいかに再建するのか。国内に存在する多様な宗派がいかに手を取り合い、ひとつのシリアを目指していけるのか。
◆半世紀にわたって続いた独裁政権と、14年にわたる内戦。それらが残した負の遺産と向き合いながら、シリアの人々は今、困難な再生の道を、希望と共に歩もうとしている。[小松由佳]
追記 今回、政権崩壊後のシリアに立つことができた幸運に、心から感謝しております。そして、突然の取材地変更について、多くの皆様に取材カンパをいただき、応援いただきました。おかげさまで一生忘れられないだろう取材となりました。皆様、本当にどうもありがとうございました。これからも、シリアの人々が、故郷とどのように繋がりながら生きていくのかを取材していきます。

イラスト 長野亮之介
■シリア政権が崩壊して間もないこのタイミングで、まさにその現場に入った小松由佳さんの話を聞く機会に恵まれた。小松さんの報告会が終わり、私たちは歴史から何を学び、何を活かすことができなかったのかと今も考えさせられている。10年以上の長きにわたるシリア内戦では、政権に不満を抱く自国民への徹底的な弾圧、監視と密告、それに伴う人々の分断が続いた。特に衝撃的だったのはナチス・ドイツのアウシュヴィッツ強制収容所以上に非人道的と言われるサイドナヤ刑務所を訪問した際の描写だ。サーメル兄も収容されたこの刑務所では拷問、処刑、餓死などのおぞましい所業で10万5000人以上が死亡したとされる。この現代になぜこれほど大規模かつ非人道的行為が続き、そしてシリア政権崩壊まで根本的解決を得なかったのだろうか。この現実の前には、どんな国際的な枠組みも薄っぺらく感じられてしまう。政府と反政府、そして宗教や民族間の対立と分断が続いたシリアから考えさせられることは多い。
◆一方で、前向きな気持ちにさせられたのはアサド政権崩壊後のシリアの新指導者、ジャウラニ氏による「今までのこと(旧政権協力者の処分)は水に流そう。これからシリアが目指したいのはこれまでのような対立でなく復興だ」との訴えだ。人々が様々な立場で長年争い続け、分断のしこりが残るシリア。夫のシリアを想う気持ち。懐かしき人々とシリアで直接再会できる喜び。アサド政権崩壊直後の激動のシリアへ夫のラドワン、お子さんと共に入国され、無数のシリアスな状況を見たにもかかわらず、小松さんは俯瞰した冷静な視点と温かな眼差しを持っていた。それ故、語る言葉は一言一句に深い意味を持っていた。報告会中の小松さんに会場の誰も割って入ることなどできなかったのではないだろうか。一歩深く、さらに一歩深くと話をされ、真摯に、そして覚悟を持って生きている小松さんの姿勢が伝わってきた報告会だった。[福井から駆けつけた 塚本昌晃]
■「隊長でなければまた行きたいですね」。2017年5月の報告会で、南極にまた行きたいかとの問いかけに、確かこう答えたように思う。2015年11月から2017年3月まで第57次南極地域観測隊に参加して帰国した直後のことで、偽りのない気持ちだった。
◆2008年に第50次南極地域観測隊、帰国後半年を置いて2010年に52次隊に野外観測支援担当隊員として参加した。52次隊から帰国後の2012年4月に国立極地研究所の職員となったのは50歳のとき。定年までの10年間は南極観測に関わって観測隊をきちんとサポートしようと考えた。
◆2015年に出発した57次隊で越冬隊長を務めたが、自ら望んで観測隊に応募した50次隊と52次隊とは違って、半ば業務命令に近いもの。とはいえ、また南極に行けるという楽しみと隊の責任者としてどこまでできるかという自分へのチャレンジという気持ちもあって引き受けることにした。
◆そして定年まであと1年、フリーになったらまたネパールに行きたいなと考えていた矢先、64次隊の越冬隊長として2022年から南極に行ってもらえないかというオファーがきた。様々な職業の人が集まり、生まれも育ちもバラバラで、価値観も異なる約30人の異年齢集団を閉鎖環境の中で率いるのは結構大変で、57次隊では自分の未熟さを痛感することも多々あり、そんな経験が冒頭の言葉となって表れたのだと思う。
◆もう南極は充分、次の道を歩こうと思っていたので、越冬隊長は引き受けられないと何度か断ったが、きちんと給料を払ってくれるならということで最終的にはオファーを受けることにした。過去、定年後の人物を隊長として送り出したことはなく、再任用職員として引き受けてしまうと給料が半分以下になって責任だけを押し付けられかねないということと、もし今後同様の事案が発生した場合の悪しき前例とならないために、極地研の上層部と条件闘争を繰り返し、納得できる条件が整ったというのが引き受けた背景にある。かくして史上最年長越冬隊長が出来上がった。
◆隊員は通常オーストラリアまで飛行機で移動して南極観測船「しらせ」に乗り込むが、出発した2022年11月はまだコロナ禍が収束しておらず、日本から昭和基地までの全行程を「しらせ」で行くという異例の出発となった。12月に昭和基地に到着し、忙しい夏期間を終え、地平線会議常連の澤柿教伸さん(法政大学教授)率いる63次隊と越冬交代を行ない、1年間の越冬生活が始まった。
◆過去にいくつかの報告があるので、越冬生活の詳細についてはここでは述べないが、64次隊は総じて落ち着いた隊だったと感じている。28人の越冬隊員の中には越冬経験豊富な者が何人かいて、経験に基づく彼らのアドバイスが隊の中で生かされていたし、初めて観測隊に参加した隊員も主体的に動く者が多く、全体としてまとまりのある隊だった。
◆また私自身は一度隊長を経験していたということもあり、前回よりは気持ちに余裕を持てていたように思う。さらに、前回から7つ年齢を重ねて、例えば20代の若い隊員は我が子よりも若くなったことなどもあって、私自身の物事に対する許容範囲が広がったことも気持ちの余裕に繋がったのではないかと思っている。
◆「全員が笑顔で家族のもとに帰る」。これは、出発前から越冬期間を通じて折に触れて私が隊員に対して言い続けて来た、越冬隊員としての最終目標だが、2024年3月21日に成田空港に降り立ち、出迎えの家族、友人、職場の同僚などと笑顔で語り合う隊員の姿を見て、やっと肩の荷を下ろすことができた。
◆南極から戻って残務処理を終えた6月、私は極地研を退職して念願のフリーランスになった。64次隊出発前、帰国後は長期間ネパールを歩こうと思っていると話していたら、思いのほか同行を希望する友人がいて、昨秋3か月間のネパールの山旅に出かけた。
◆東ネパールの2か月間は総勢6人(途中から3人)で歩き、ランタン谷の2週間はチームを再編成して3人で歩いた。16年ぶりのネパールの変化、辺境の東ネパールの刺激的な山歩き、2015年の大震災後初めて訪れたランタン村の変貌ぶりと村人の逞しさに触れるなど、充実した旅となった。紙幅の都合で詳細を語れないが、作成した報告書(下記リンク)と最近始めたnoteに掲載する紀行文を良かったらお読み戴ければと思う。[樋口和生]
グレートヒマラヤトレイル東ネパールトレッキング報告書
https://sites.google.com/view/antarcticwind
noteを始めました。ときどき覗いてみてください
https://note.com/kzhiguchi
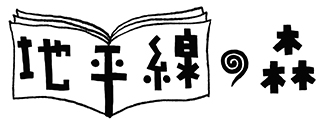
■1月に出版した新刊『酒を主食とする人々』(本の雑誌社)は予想外の出来事が重なった結果生まれた。発端は2019年に書店で砂野唯『酒を食べる—エチオピア・デラシャを事例として』(昭和堂)という本を発見したこと。これが驚くべき本だった。エチオピア南部に住むデラシャという民族は栄養のほとんどをソルガム(イネ科の穀物で和名はコーリャン、タカキビなど)由来の酒から摂取しているというのだ。アルコール度数3~4%の酒を大人は一人一日平均5リットルも飲み、子供も12、13歳ぐらいから普通に飲み始めるとか。
◆頭がくらくらしそうだ。私は日本人としては(あるいは世界的にも)最も多くの風変わりな食生活や食べ物に遭遇してきた人間の一人だと思うが、朝から晩まで酒を飲み続ける民族などこれまで見聞きしたことがない。信じがたいのだが、著者の砂野さんは京都大学で博士号を取得したれっきとした生態人類学者である。本書もデータがびっしりと記されている。事実だと信じざるをえない。
◆しかし……と、疑問がもくもくと湧き出てくる。酒ばかり飲んでデラシャの人たちは仕事をしているのだろうか? だいたい健康状態はどうなのか。未成年や高齢者や病人はどうなのか。とくに気になるのは妊婦。でもそれについてはこの本には何も書かれていない。
◆いやあ、ここに行ってみたい!と思ったものだ。しかしそれは叶わぬ夢だった。なぜなら、すでに優秀な研究者が調査を行い、一冊の本を書いているからだ。私が今更行っても後追いにしかならない。もちろん、仕事と関係なく旅行で行ってもいいわけだが、エチオピア南部は昔からの伝統を残した風変わりな少数民族がひしめくエリア。ここはエチオピア政府が半ば「保護区」のように扱っており、旅行者が自由に訪れることが難しいと聞いていた。莫大な入域料や撮影料をとられるという。
◆そのようなわけで諦めていたところ、TBSの番組「クレイジージャーニー」のスタッフから「高野さん、番組の企画としてどこかに行かないですか?」と声がかかった。ふつうは断るところ、「デラシャなら行きたい」と答えていた。ただ期待はしていなかった。デラシャは酒を主食とするという極めて珍しくて、ある意味ではテレビ向きの民族である。きっとすでにどこかの番組で取材されているだろうと思った。また、エチオピアは内戦が激しく、テレビ取材の許可が下りないんじゃないかとも推測した。私は「辺境のプロ」なのでいろいろなことが予想できてしまうのだ。
◆結果から言えば、私の二つの予想はことごとく外れた。驚いたことに、日本のテレビ局でデラシャを本格的に取り上げた番組はまだなかった。NHKが「食の起源」というシリーズを制作したとき、5分ほどデラシャを紹介したのみ。さらにエチオピア政府の許可も取れるという。辺境のプロの予想は誠に当てにならない。かくして、あれよあれよという間に、私は行くはずのない旅に出かけることになった。
◆行ってみれば、それは──たった2週間なのに──波瀾万丈の旅になった。だいたい、出発予定日に飛行機に乗れなかったばかりか、私が突然倒れて救急搬送されるというアクシデントが起きた。体調が回復しないまま現地へ行くと、そこでまた予想外のハプニングやアクシデントが連発。酒飲み民族の実態にも驚くばかりだった。私も通算10日ほど酒ばかり飲む生活を体験したら、自分の体が激変した。
◆実に濃い旅になったのだ。ただ、これを旅行記として出版するつもりはなかった。テレビ番組で放映するのだからそれで十分だと考えていた。しかし、ここでも「辺境のプロ」である私の読みは甘かった。クレイジージャーニーではなんと肝心のデラシャについて、ほとんど映像を流さなかったのだ!! そこにはテレビという媒体がもつ本質的な問題があった。しかし、勿体ない。なにしろ、すごく面白かったのだから。
◆というわけで、急遽予定を変更し、書かないはずの旅行記を書いてしまった。さらっと書きたかったけれど、私にはそんな高度な技術はなく、綿密にきっちりと書いてしまった。こんな本が売れるはずはないと思うけれど、なにしろ今回は予定外のことばかり。もしかしたら、売れるはずがないのに売れてしまうんじゃないかと期待してしまうのだが、辺境のプロの予想は当たった試しがないので、戦々恐々と状況を見守っている。[高野秀行]
■1月にモンゴルへ行ってきました。今回はドキュメンタリー番組の撮影チームと一緒で、私はコーディネーターという仕事をはじめて担当しました(バタバタしすぎてサイフと家の鍵を現地に置き忘れて帰国しました)。滞在中はマイナス20度までしか下がらず、今年は暖冬だそうです。ウランバートルの冬の風物詩となっている大気汚染のせいで、街の空気はうすらスモーキー。そんななかでもスフバートル広場には、透明な氷で巨大滑り台や馬群やゲルの彫刻がつくられ、親子連れやカップルが深夜まで遊んでいました。
◆昼になるとその広場に市民が集まり、「政府は辞職せよ!」と抗議デモを開始。別の日には「ウランを掘るな!」というデモも。フランスとモンゴルがゴビ地方のウラン鉱山の共同開発契約を結んだためで、今後30年間でウラン計9万トンを採掘する計画があるようです。
◆最近私は年3回のペースでモンゴルへ通っています。日本に情報があまりないモンゴルについてもっと知りたい、見聞きしたことを日本の皆さんにもお伝えしたいと、派遣社員をやめてフリーライターになったのが2013年。それから10年経ち、モンゴルでの活動に少しずつ手応えを感じられるようになって、2023年に法人化しました。ビザが出せるようになったので、モンゴルから人気ロックバンドを招いて東京でライブを開いたり、モンゴルの写真家や画家の本を日本の印刷技術でつくったり、日本で映画を撮影するプロジェクトにも関わっています。
◆一昨年から準備を進めてきた日本モンゴル映画祭も、3月22日~28日に新宿のK’s cinemaでようやく開催が決まりました。ふだん日本で見る機会の少ないモンゴル映画を集めて連日上映します。新宿のあとは横浜、名古屋、大阪など各地へもキャラバンする予定です。ぜひ皆さま、モンゴル映画を見にきてください!(先月の地平線報告会では受付に告知のポストカードを置かせていただき、どうもありがとうございました)。
◆映画祭の運営になぜ関わることになったかというと、柳楽優弥さん主演でモンゴルが舞台の映画『ターコイズの空の下で』のプロデューサーから提案されたのがきっかけでした。宣伝や配給の専門家たちと実行委員会をつくり、毎週Zoomで打ち合わせしながら超手弁当で準備しています。上映したい作品の制作者と条件を交渉したり、紹介文を作成したり、慣れないことばかりです。まだごく小さな映画祭ですが、モンゴル映画が日本の劇場で正式に配給されることにつながれば本望です。
◆映画祭のラインナップにどうしても入れたかった作品がいくつかあります。そのうち1本は、シャーマンの役目を背負う高校生の青年がある少女と恋に落ち、自分の生き方について葛藤する『シティ・オブ・ウインド』。別の1本は、アルコールに溺れて働かない母親の代わりに、寒く貧しいゲル地区で幼い弟と妹の面倒をみながら、進学の夢をあきらめきれない少年の物語『冬眠さえできれば』。
◆現代モンゴルのリアルな一面を見せてくれるこの2本には共通点があり、前者は2023年のヴェネツィア国際映画祭オリゾンティ部門で最優秀男優賞を、後者は同年のカンヌ国際映画祭公式部門にモンゴルの長編映画として初ノミネートされ、ともに世界でも日本の大きな映画祭でも高評価を得たものの、日本で配給されていません。さらにどちらも、チャーミングでかっこいい30代の女性が脚本と監督を務めています。
◆人口わずか350万人のモンゴルは、1990年頃に民主化されてから、政治汚職や経済格差などの社会問題が国民を悩ませてきました。自力で発展しようとすると隣国のロシアと中国からギロリと睨まれ……。爆発しそうなやりきれない思いを、映画や音楽などの芸術作品で表現する個性的な若者がどんどん生まれています。
◆人口の少ないこの国から、大相撲の横綱もまた誕生しました。照ノ富士関の引退と同時に、25歳の豊昇龍関が横綱に昇進したことはモンゴルでもニュースになり、相撲界の世代交代を象徴する出来事でした。2月11日には、今年は中止になるかと噂されていた白鵬杯の開催が決定。世界15の国と地域から1100人の子ども力士が横綱の地位を競うと同時に、日本の高校や相撲部屋からのスカウトを期待します。
◆天皇皇后両陛下が7月にモンゴルを訪問されるという報道も出ました。元在モンゴル日本国大使の花田麿公さんが長年尽力されてきた、日本人抑留者の慰霊もされるようでとても嬉しいです。その時期、私もモンゴルにいたいです。[大西夏奈子]
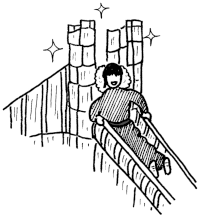
イラスト ねこ
■2025年1月28日、鳥海山の麓、秋田県にかほ市にて「阿部雅龍君をしのぶ集い」が行われ、200人ほどの人々が会場で阿部さんの功績をしのびました。私もパネラーの一人として参加させていただきました(主催は、南極探検隊長白瀬矗顕彰会と、NPO法人白瀬南極探検100周年記念会)。
◆南極冒険家として活動し、2023年11月から、白瀬ルートでの南極点踏破を目指していた阿部雅龍とは、同郷で同い年。阿部さんとは、フィールドは違えど、強い信念を持ち、自分が信じた道をひたすら進んでいくだけ、という感覚を共有しているように(勝手ながら)感じていました。
◆小学生時代から、秋田県出身の南極探検家、白瀬矗に憧れ、白瀬ルートによる南極点踏破を夢に見ていた阿部さん。着実に夢へのステップを踏み、ようやくその挑戦を目前に控えた2023年8月、無情にも脳腫瘍という病魔が彼を襲いました。その試練をも彼は、「南極よりも困難な冒険に行ってくる。そして必ず帰ってくる」と話していましたが、2024年3月27日に帰らぬ人となりました。あれから一年近く。突然の彼の旅立ちに、今も心にポッカリと穴が空いたようです。
◆「しのぶ集い」ではまず始めに、阿部さんが〝師匠〟として尊敬していた冒険家、大場満郎氏による講演が行われ、その後、阿部さんと親交があった元南極観測隊員の小森智秀さん、阿部さんの活動を記録してきた写真家の高橋こうたさん、そして〝師匠〟の大場さんと私の、4人によるパネルトークが行われました。
◆阿部雅龍は不思議な人で、彼がこの世から去ってもなお、彼が見せてくれた真っ直ぐな生きる姿勢や熱い心が、すぐそこにあるように感じられるのです。そしていつも、彼は語りかけているように思うのです。〝今、この瞬間を、ちゃんと生きているか!〟と。実は、昨年12月のシリア取材の際も、子連れで混乱のシリアに入ることに最後の最後まで悩みました。その時、阿部さんだったらどうするだろうか、ということも考えました。
◆「『いつか』はこない。『いつか』じゃなくて、やれるのは常に『今』しかないんだ」。生前彼の口から聞いた、その言葉が甦ってきました。そして私は、シリアへと向かうことになるわけです。私は今も、彼が残してくれたものを受け取り続けているように感じています。それは、南極冒険家として自分の道を切り拓き、ひたむきに突き進もうとした熱い生き様であり、強い信念、そして沢山の人を愛し、愛された彼の温かな人間性であるように思います。
◆最後に、犬ぞりの犬たちを連れて笑う植村直己さんの笑顔と、阿部雅龍の笑顔がそっくりだと思いました。二人とも、未知の世界を舞台に、唯一無二の自分の道を開拓し続けた〝人生の冒険家〟でした。阿部さん。限られた人生の中で、あなたと出会えたことに感謝。あなたの熱い心に触れさせてもらったことに感謝。あなたが与えてくれた沢山のことを胸に、しっかりと生きていきます! あなたを忘れないよ。[小松由佳]
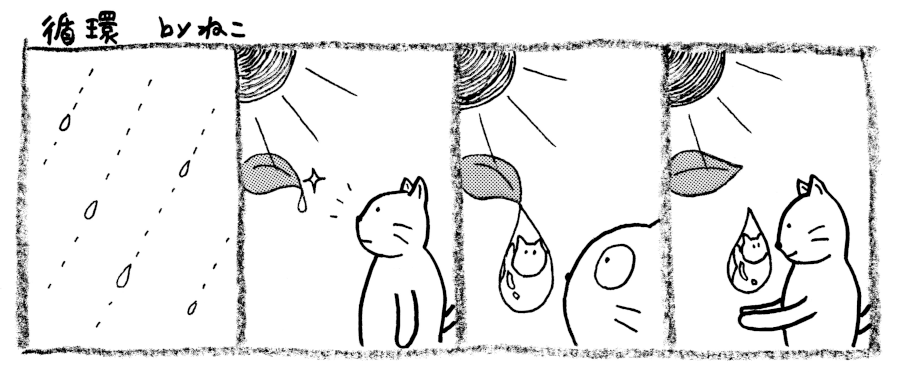
《画像をクリックすると拡大表示します》
■大隅半島を自転車で周った後、根占から山川へフェリーで渡る。今回の旅の終点は野元甚蔵さんの眠る納骨堂とした。甚蔵さんは2009年5月と2010年5月の報告者。2015年1月に97歳で亡くなった。港からの長い長い坂を上がり、岬の納骨堂に着いて、線香を灯した。海の向こうに佐多岬が見えるいい場所だ。
◆野元さんの娘さん2人、蓉子さんと菊子さんが開いたカフェ「紫苑」は近くの丘の上にある。晩年の甚蔵さんと共に過ごしたおばあちゃん犬のさくらが出迎えてくれて、ランチをご馳走になる。きょうは野元家風チキン南蛮だった。
◆蓉子さんが高校生のころ、米国の大学から大きな録音機を携えてやってきた学者の思い出を聞いた。通訳を介して、甚蔵さんのチベット体験を一問一答。でも肝心な点は「そこは話せない」と頑として譲らない。翌日すごすご帰る米国人の学者と、通学の列車内でたまたま一緒になり、父の無礼を詫びた。「野元さんは外人さんと知り合いだ」という噂が学校中に駆け巡ったそうだ。
◆しかし話題は父、甚蔵さんより、先に亡くなった母上の思い出話が圧倒的に多い。女子師範を出て教員をしていたころは美人教師と大人気。書も着付けも多芸で、いろんなことを知っている。夜空の星の中から人工衛星を見つけたこともあった。甚蔵さんが沈黙を破って『チベット潜行1939』を書き上げたのは、記録をせっせと清書した奥様の功績でもある。
◆夕方、種子島から打ち上げられるH3ロケットを一緒に見に行った。佐多岬の向こうにオレンジの炎が見えた後、しゅるしゅると煙の尾を引いてロケットが大気圏外に飛び立って行った。甚蔵さんも自宅のテラスからロケットの打ち上げを何度も見ていたそうだ。かつて内蒙古の夜空を見上げていた野元青年は、GPSで旅ができる時代など思いもよらなかったに違いない。[落合大祐]
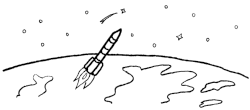
■先月の通信でお知らせして以降、通信費(1年2000円です)を払ってくださったのは以下の方々です。万一記載漏れがありましたら必ず江本宛メールください。通信費を振り込む際、通信のどの原稿が面白かったかや、ご自身の近況などを添えてくださると嬉しいです。通信の感想を書くことは地平線会議の活動を支援してくれることでもあり、お金以上に私たちの励みになることをご理解ください(江本のメールアドレス、住所は最終ページにあります)。
宮寺修一(10000円 通信費として) 樋口和生(10000円 近況は今月の通信に書かせてもらいました) 川本正道(10000円 地平線通信いつもありがとうございます) 福原安栄(3000円 本年度会費+αとして送金いたします。拙歌を一首。十四座登頂を遂げ 生還の稿にやすらぐ 地平線通信) 奥田啓司(2025年通信費 今年で20年目位でしょうか) 菊池民恵(10000円 「エモの目」は昭和が漂っており楽しませていただきました。発送の中止をお願い致します) 阿佐昭子(6000円 地平線の皆さま!このところずっと参加できず残念無念が続いています。通信費がいつから未納か失念いたしまして、今年とさかのぼって2年分振込みます。本年も冒険者のごとく楽しく過ごしましょう!) 佐野悦子(10000円) 平本達彦 高野久恵(5000円 長らくご無沙汰しています。此方での暮らしも20年余り、旅に出かけることは殆どなくなりましたが、好奇心だけはもち続けています。家と親戚、地域のあれこれで動き回る日々はもう暫く続きそうです。昼夜の寒暖差も激しい時期です。どうぞご自愛くださいますように。佐渡ヶ島から 1984年12月、62回報告会「台湾、ヤミ族とのふれあい」報告者。このときの予告はがき通信で長野亮之介が「画伯」として衝撃デビューした) 斎藤孝昭(15000円 1万円は通信費に、5千円はカンパです。1月の小松由佳さんのシリア緊急報告は衝撃でした。突然のアサド政権崩壊後のシリアの現在を明瞭な言葉で語ってくれました。サイドナヤ刑務所での身の毛もよだつ拷問の痕跡、夫の故郷パルミラに行く途中、反政府軍兵士たちの中に友人を見つけて生きて再会を喜ぶ夫。「誇りに思う」という言葉の意味。心を掻きむしられました) 中橋蓉子・野元菊子(20000円 昨年末、2人してインフルエンザ感染して、2週間近く辛い思いをしました。治りが遅いのは歳のせい?! わが家の娘トイプードルのさくらは15歳7か月。寒さ、気温の変化にだいぶ弱っていて、食、動きに二人で一喜一憂しています。通信費の¥10000は、カンパです。いつもありがとうございます) 菅原茂(10000円 通信費3年分+カンパ) 樫田秀樹 渡辺久樹・京子 波多腰純也 塚田恭子(10000円 数号前に、坪井伸吾さんが数年分の通信費を江本さんに手渡した顛末を読んで、あ、わたしも!という5年分です) 土谷千恵子
■「江本さん、すっかりご無沙汰しております。今徳島から横浜の実家に帰省中です。もしタイミングが合えばぜひお会いしたいです。1歳の娘も一緒です」。今回は急遽決めた帰省で、娘を両親や姪っ子たちと会わせるのがメインだったので、ほとんど誰にも連絡していなかった。そんな中、江本さんに数年ぶりに連絡したのは、会いたい人には会えるときに会っておかないと、と思ったから。そして散々お世話になっておきながらずっと連絡できていなかったことが気がかりだったから。
◆地平線のみなさま、大変長らくご無沙汰しております。一体何から話せばいいのだろう。最後に地平線通信に寄稿したのは2021年の10月。その後ショッキングな出来事があって、気持ち的にかなり落ち込み、ほとんど誰とも連絡をとらず、ひたすら自分と向き合った数か月。
◆そんなときに声をかけてくれたのが徳島の友人だった。「とりあえず住むところはうちにしばらくおったらええし、うちのぶどう畑で働いたらええけん。まやたろにぴったりの空き家もあるけん」。そんな彼女の誘いに乗って、気付けば徳島に来て間もなく3年になる。その間に築100年の古民家を借り、子猫(その友人のところで産まれた)を飼いはじめ、今の夫と出会い、気付けば母になっていた。最近は徳島西部(祖谷のかずら橋や脇町のうだつの町並みなど)を中心にインバウンドのガイドをしたり、都会から来た修学旅行生の受け入れ(田舎暮らし体験)をしたりしている。
◆それまでずっと根無し草で風来坊だったわたしにとって、3年も同じ場所にとどまるということは異例の事態だ。最近はむしろちょっと買い物に町に出る(うちは山の上なので、車で15分ほど下る)のも億劫なほど、すっかり出不精になってしまった。今は不思議なくらい、どこにも行きたくない。今回の帰省も直前まで迷ったし、以前なら会いたい人に片っ端から連絡をして、会いに行っていたのだけど、今回は結局ほとんど家から出なかった。
◆徳島に帰る前日、ようやく江本さんと連絡がついた。「明日14時に阿佐ヶ谷のカフェに写真展を見に行きます」とのこと。その時間ならなんとか飛行機の時間に間に合いそう。こればかりは迷わず行くことにした。阿佐ヶ谷駅から迷いに迷ってようやくたどり着いたカフェ、ひねもすのたりでは白根全さんプロデュースによるペルー先住民の写真家、マルティン・チャンビの写真展が開かれていた。
◆お店に入るや否や、江本さんやお連れ合いの北村節子さん、全さんにもお会いでき、娘も会わせることができて、感無量。そしてチャンビの写真も本当に素晴らしかった。銀塩でモノクロというのも相まって、独特の雰囲気を醸し出すポートレート。100年前のものとはいえ、クスコやプーノの写真からはあのとき自転車で走ったアンデスの風が感じられるようだった。「フィルムとデジタルでは1枚にかける本気度が違う」という全さんの言葉通り、一枚一枚に魂がこもっていた。
◆「本来なら俺に合わせる顔がないくらいなんだけど……。次の通信は頼むよ」と江本さんにクギを刺され、再び地平線に戻ってくることができました。感謝。次はリアルでまたみなさまにお会いしたいです。
◆飛行機の時間が迫ってきた。後ろ髪引かれながらも別れを告げ、阿佐ヶ谷から東京駅へ。そして成田空港行きのバスに乗り込んだ。バスの車窓からはビルに反射した夕日がキラキラと輝き、振り向くとちょうど日が沈もうとしていた。茜色に染まる荒川を眺め、たまには東京も悪くないな、と思った。
◆今年は娘を連れてどこか海外に行こう。ひとりのときとはまた違う世界が広がっているだろう。[桜井麻耶 旧姓青木]
■昨日はありがとうございました。久々に元気な江本さんや他の皆さんにお目にかかれて幸せな、また刺激的な時でした。この数十年封印してきた、人間とはどうしてこんなにも良くも悪しくも変化できるのか? 自分なりにどんな行動をすることで、自分も周りの人もそして巡り巡ってより多くの人が、穏やかで少しの幸福を分かち合って過ごせるようになるのかをアグレッシブに追求していきたいという思いを蘇らせていただきました。
◆もう少し動き出すには時間とスタートするための反発力が必要かとは感じています。焦らずでもスピードを上げてエネルギーを溜める活動を始めようと思えたひとときになりました。また参加させていただきます。よろしくお願いします。[報告会翌日に 水野麻子 「麻子のカメさん旅」(1996年3月29日)報告者]
■12日間に渡って阿佐ヶ谷のカフェ「ひねもすのたり」で開催したマルティン・チャンビ写真展には、200名以上の方々が足を運んでくださいました。1月の地平線通信に掲載した檄文を目にして、チリのドキュメンタリー映画『私の想う国』を見てから、チャンビ写真の目撃者となってくださった方々も多かったようです。この場をお借りして、感謝の一言をお伝えしたく存じます。
◆ガラス乾板に刻まれた美しい諧調、奥行きの深い圧倒的な構図、完璧としか言いようのない光の捉え方、どれを取っても卓越した作品性は語り尽くせず、その表現は「魔術的リアリズム」の一言に尽きる、と毎日のように繰り返し説明しました。が、そこで気付いたのは、やや思考停止気味に使い回している「魔術的」と「リアリズム」の意味です。あり得ない現実、と言ってしまえば狭すぎ、空想や誇張が入り込む演出された世界はその写真表現とは程遠い。むしろその視線の重さが、魔術に思えてしまうのでしょうか。あらためて、謎が謎を生む展示になったように思います。
◆てなわけで、これよりカーニバルの混沌に突入、南米仏領ギアナはカイエンヌの祝祭が手招きをしておるぞ! では、さらば![Zzz-全@カーニバル評論家]
◆有隣堂へ行った。新築だけあって実に立派である。大勢の人が来ていた。新築という言葉がでてきたが此の頃建つ家はほとんどが近代的であり、明るい。もちろん一般家庭においてもだ。反面、住居難で頭を悩ませている家庭は数限りなくある。新築する人達と住居難をなげく人たちの金銭上のへだたりが非常に大きいのだ。これが資本主義である。だからと言ってソ連のような共に産する主義を受け入れることは今のところありそうにない。僕としては資本主義の方がよい。しかしながらこれは僕の私欲邪念から生じたことであって政治的なものには一つも関連していない(あたりまえだ)。まわりが低くて己が出る、という欲意《ママ》の語が僕をめぐる。人の欲目は大きくて 馬鹿なことのみ 多かりき一凡人
◆久しぶりで皆先に寝てしまった。11時半、静寂を味わう。星を見るため外へでてみたら全くこの上もなく真っ暗だった。先刻まできれいに輝いていた星もほとんど見えなかった。それに外は非常に寒く、僕をそれほど長く置いておかなかった。
◆「はばたき」《通っていた大鳥中学の校友誌》巻頭言を今年から生徒が書くことになった。で、文芸部員からとるらしいので正直なところ野心満々である。やはりいちばんはじめに自分の名が載ると嬉しい。そして、その可能性は十分にある。もっとも全校生から募っても同じ気持ちだろう。
■地平線通信549号の発送作業は、印刷機故障のハプニングで一瞬緊張しましたが、通信を印刷する間だけ印刷機が動いてくれて、いつもより少し遅い19時には終わりました。北京が閉店してしまったので作業終了後の懇談場所は、北京の上の階にある居酒屋「舟形や」をテスト。最近アルコールを飲まない人が多いので、ちょっと場違いな雰囲気もありましたが、話に花が咲いてそれなりの成果でした。集まってくれたのは以下の皆さんです。ありがとうございました。最後の1人はフロント原稿を書き終えて安心し、1時間だけのつもりが3時間も爆睡してしまい、「舟形や」直行でした。
車谷建太 中畑朋子 久島弘 伊藤里香 高世泉 落合大祐 渡辺京子 秋葉純子 武田力 白根全 江本嘉伸
■2月3日、長逗留した山仕事の現場から引き揚げて、仲間が待つ共同生活家屋に帰宅した。昨年11月から約3か月、道内某所の馬搬現場で働かせてもらい、馬搬の見習いをさせてもらっていた。昨年度に続き、2度目となる冬山馬搬だ。
◆樹齢80年近い天然林で間伐した木を、親方の飼育する輓馬2頭で林道まで搬出する。木材を生産する工程のなかで「薮出し」と呼ばれる作業が、馬の主な役割だ。将来、大径木になってもらう樹木の成長を阻害する隣接木をチェンソーで伐倒し、居残ってもらう木々を傷つけないように一本ずつ搬出する。トラック出現以前に、土ソリに山盛りにした大量の木材を運んだ「クラシック馬搬」とは違い、丁寧さや繊細さを売りにして、残す森に価値をつけるのが、「現代馬搬」の大きな特徴だと解釈している。馬の役割を、かつての《馬=重機/大型トラック》から《馬=高性能ウインチ》への変化とみるとわかりやすい。
◆馬と搬出した木は、形や太さに応じて鋸断され、旭川の銘木市で取引される家具材や、近隣で消費される薪材・バイオマス燃料材に振り分けて積み上げてられていく。たとえば末口(丸太の小口の細いほう)直径が20cm以上で、通直、無節であれば、2.5mに伐って用材に。節だらけで、曲がりが強い、などの欠点があれば、2.4mに伐って薪材にする。
◆匂いのない冬山に、飛ばす切り粉の香しいこと。ミズナラを伐ってはウイスキーの酔い心地を脳が瞬間思い出し、コブシやホオを伐っては華の香りに少し先の春を想う。丸太を切り落とす間、ほんの数十秒の贅沢なひと時。丸太の集材や巻き立ては、グラップルフォワーダーやトラクターが牽引するグラップルが担う。重機の利用を完全否定するわけではなく、適材適所で馬を活用することで、親方の馬搬現場は成り立っている。人と馬と重機の協働で生産した丸太の量は一冬で大型トラック数台分にもなる。
◆親方の指示に従って、少しずつ木を伐りすすめ、枝を払っては、幹だけになった丸太を運び出す。樹種や太さによって変わる重さに応じて、数~数十メートルに丸太を切り落としておき、林内に馬方と馬を迎え入れる。ワイヤーロープで、丸太と馬を結びつける。馬が牽引する「ドッコイ」と呼ばれる馬具が、その結節点を担う。
◆ワイヤーをスムーズに装着すること、馬たちが戻ってくる前に次の丸太を用意しておくこと、あたりに散らばる枝や土にうずもれた枯れ木が支障にならないように小さく切っておくこと。単純な仕事ばかりだが、焦らずに、馬(馬方)を待たせずに、一定のペースで準備を整えておくのは案外難しい。丸太が地面にぴったりついていたりすると、ワイヤーをねじ込む隙間がない。地面に跪いて、呻きながらワイヤーを抜き差ししている間に、林道から帰ってきた馬が「もたもたすんな」とばかりに鼻息を荒げているのを見上げるのもしばしばだった。
◆それでもスムーズに輓馬2頭が滞りなく動き続けると、林の中に入り組むように倒れていた丸太はみるみるうちに林道に消えていく。すこし伐って、運んで、運んで。場所を移してすこし伐って、運んで、運んで、を繰り返す。
◆一度に全域の伐倒を済ませてしまわないのは、馬が運びやすい段取りを計算してのこと。十数メートル以内の狭い区域の中でも、倒す木の順番を考えて、馬を止めずに動かし続けられるような段取りをする。枝ぶりが大きく、枝払いしたあとの「ボサ(山に残される枝や梢の部分)」が散らかるような大木は、ほかの木を運び終わってから、最後に伐る。かかり木になったとしても、馬が引っ張りやすい方向に(安全な処理に時間がかかるかかり木も、大抵は馬で引っ張り落とせてしまうのは、馬搬の便利なところである)かかり木をつくる。「とにかく馬が苦労しないように」と親方はよく口にする。
◆大きな木を倒せば、それなりに危険も伴う。一度だけ、斜面の上方向に倒した樹高20mほどのシナの大木が、倒れきるまでに上に生える木に跳ね返されるようにして、2mほど後ろに「ずっ」とずれ落ちてきたことがあった。伐倒の基本通りに斜め後方に退避していたために横目で見過ごすだけに終わったが、以前林業の先輩が話していた死亡事故がこれと同じ状況だったことが思い出され、血の気が引いた。
◆大きな馬で大きな丸太を引きずり歩く馬搬も、まったく安全な仕事とはいえない。数メートルの短い丸太を1本で運べば丸太は左右に暴れることがあるし、10メートル近い丸太を運びだそうとすれば、進路が大きくカーブするのに伴い丸太が周囲をなぎ倒すように振り回されることもある。
◆運ぶ丸太がそのへんの枝をひっかけながらグングン進み、それに応じて枝もグングンしなり、限界値で開放された枝がフルスイング、足払いをくらいそうになることもある(だから、進路の枝を小さく切っておくことが重要なのだ)。笹薮の先を行く馬と、引きずられる丸太の間で足場を選びつつ、馬と自分の安全を確保しながら不安定な重量物を運ぶ。馬を両手の手綱で御しながら、すり抜ける木々の幹に丸太が傷をつけないよう目配りも忘れてはいけない。
◆自分が馬方をさせてもらっているときのこと。林道へ馬が出た先に丸太が堆積していて、牽引している丸太がそれを引っ掛けて動かしてしまうことがあった。二股に分かれた樹木の大枝を、馬が引く丸太が引っかけるようにして引っ張ると、「あっ」と思ったときにはもう片方の枝が自分の股下で跳ね上がり、そのまま向こうへ自分ごと引きずっていきそうになっていたのだ。「うあっ!」と声を出して被災の覚悟をした瞬間、運よく馬が止まってくれたことで、それ以上枝が自分を持ち上げることはなかった。現場をよく見ると、すぐ先でほかの丸太がつっかえ棒となって、どちらにしても二股枝の浮き上がりは止まってくれていたようだったが、一歩間違えれば、股を割かれるかたちで丸太の中を引き回されるところだった。
◆そのときのルートの出口は、林道と林の境界に段差があり、馬の後ろからでは先が見えない斜面になっていたために、搬出先の林道の様子がわからなかったのだ。それでも、林道に転がっている丸太の状態を予測する・記憶しておくとか、見えないなら一度止まって出口を確認してから馬を行かせるとか、できることはいくらでもあった。経験の浅さは勿論のこと、自分の手抜かりを突き付けられる一件だった。
◆親方がいる林内に馬と共に戻り、先の一件を打ち明け、しばし反省会。改善策が出そろったあと、親方は「いい経験したね」と。こういうとき、親方は決して頭ごなしに怒鳴ったり、起きたことを咎めたりしない。ただ、印象に残る一言で、私の心にクサビを打ってくれる。事あるごとにそのクサビを見つめなおしては、次に気をつけるべきことや反省点を肝に銘じては、あくる日の山に臨んだ。
◆初心者由来のヒヤリハットが連日続いた、とある昼休み、親方にこんなことを尋ねてみた。「やっぱり、山仕事とか馬仕事とかって、大小無数のヒヤリハットを超えることでしかベテラン選手にはなれないんですかね」。危険防止策を徹底し、リスクを低減した先にも、常に一様でない山や馬を相手にすれば、予測不能で偶発的な危険は拭い去れない。少しずつヒヤリハットを積み重ねていくなかで、危険に対する触覚が鋭敏になって、危険を予知・回避しやすくなり、長く現役でいられるのではないか。そういう意味で聞きましたと、慌てて付け加えた。
◆親方は、そうかもね。といったあと、馬の達人でも指が無かったり(馬を棒に結びつけるときに、馬が頭を力強く振って、指が綱に締められて取れてしまう)、暴走した馬に引きずられて亡くなったりすることがあるもんね、という話を淡々としてくれた。そしてその語りがまた、私の中にクサビとして打ち込まれ、馬を係留するたびに私の指を緊張させた。
◆馬とともに、山で仕事をすること。環境に優しいとか、森が綺麗になるとか、肉になるはずだった引退馬(輓馬の場合はばんえい競馬)が第二の人生を歩めるとか、馬と人が働く姿が美しいとか。昭和に消えた馬搬が、令和に注目されるとき、大抵はそういう文句がついて回る。私自身、以前の地平線通信に馬搬の利点、のようなものを並べて書いた。馬搬は魅力的で、美しい。けれど、林業馬搬は危険と隣り合わせの仕事であることに間違いなく、3K労働にほかならないというのもまた事実だと実感している。
◆明るく、朗らかなイメージが付与されがちな馬搬の現場には、冷や汗や脂汗や切り傷や打ち身やヒヤリハットがそこらじゅうに転がっている(ただし親方はといえば、いつも涼しい顔して馬搬しているのだが)。人だけでなく、先頭きって重荷に喘ぐ馬にしたってそうなのだ。彼らはいつも、大きな躰を汗で湿らせて、下手くそな私の荒い手綱に応じてくれる。ただし時には、無視され、頑として動かず、逃げられたりもする。私も、申し訳ないと思いながら、大声で馬を急き立て、逃げようとする尻を手綱で囲い、嫌がる馬を必死で林内に追い返す。
◆時々、馬が少し後ろを振り返り、恨めしそうな目でこちらを見つめてくることがある。自分が馬でもこんなペーペーに追われるのは嫌だよ、と同情せざるを得ない。一方で、そんな身分で現場に置いてもらっている以上、こっちも仕事をしなくちゃならないのも事実。心の中で馬に許しを請いながら、手綱を打ってハミを張る。心も体も、ゆるくない瞬間がやはりある。
◆ときに、噛まれ、踏まれ、蹴られたりもしながら馬と森に通わせてもらった日々は、飛ぶように過ぎた。これまで、いつも塞ぎ込みがちで苦手だった北海道の冬は、気が付けば冬至を過ぎていた。また1年後、親方の馬たちとともに、この山に帰ってきたいと、家に帰ったその日からもう思っている。私も早く馬方になりたい。
◆普段大げさに馬をかわいがらない親方が、時折みせる労いがある。馬運車に馬を納め、扉を閉める前に、愛馬のお尻を軽く、ポンポンと叩くのだ。重労働だった日ほど、それを拝めるチャンスがある。それを見るたび、私にはない、馬とのつながりが親方との間に見える気がして、少し羨ましい気持ちがする。馬搬という世界の入口に立たせてもらったばかりで、わからないことだらけの仕事だが、やめられないという気持ちがあることだけは、わかっているつもりだ。(ちえん荘住人)
◆1月14日の読売新聞夕刊に大きくモンゴルから相撲のため来日した30数年前の6人の若者の写真が掲載されたのでびっくりした。私ではなく写真部員が撮ったものなので文句をつけるつもりはないが、取材内容も当時の私の記事(1992年2月26日付け)をなぞったものなのでおいおい、と思ったのだ。
◆現役でもないのに、と言われそうだが、書き手の私にはひとこと断ってほしかっただけなのだ。私も新聞の仕事でモンゴル取材をしていたので活用されるのに反対するわけはない。在籍する友人を通じてやんわり伝え、一応返信はいただいたが。
◆羊をめぐる冒険、面白そうですよ。2月21日は是非![江本嘉伸]
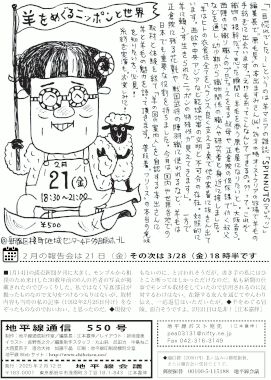 |
羊をめぐるニッポンと世界
「一目惚れでした〜」というのは羊マニアの雑誌「SPINNUTS(スピナッツ)」編集長で“原毛屋”の本出ますみさん(66)。24才の時オーストラリアの牧場で羊毛の手紡ぎに出会います。「え!? 毛糸ってこんなんしてできるのォ??って。これぞ織物の根幹だって思った瞬間に、羊毛を商う原毛屋になりたいと。 大阪育ち。西陣の染め織り職人のプロデュースをする叔母や、正倉院の保存課で働く叔父などを通し、幼少期から織物関係の職人や研究者と身近に接しました。「羊はヒトの衣食住全てをバランス良く支える点で他の家畜に抜きん出ています。西欧や中央アジアなど乾燥地帯の文明と不可分の存在。対照的に羊に頼らず生きられたニッポンの特殊性が見えてきます」。一方で正倉院に残る花氈や、戦国武将の陣羽織に使われるなど、羊毛は日本でも重要な役割を持ちました。 今月は国内や世界各地での取材と体験を経て「羊の国の案内人」を自認する本出さんに、羊と羊毛の魅力を語って頂きます。普段着“フリース”の本当の意味を知りたい方、必見! 糸紡ぎ実演も。お楽しみに! |
地平線通信 550号
制作:地平線通信制作室/編集長:江本嘉伸/レイアウト:新垣亜美/イラスト:長野亮之介/編集制作スタッフ:丸山純 武田力 中島ねこ 大西夏奈子 落合大祐 加藤千晶
印刷:地平線印刷局榎町分室
地平線Webサイト:http://www.chiheisen.net/
発行:2025年2月12日 地平線会議
〒183-0001 東京都府中市浅間町3-18-1-843 江本嘉伸 方
地平線ポスト宛先(江本嘉伸)
pea03131@nifty.ne.jp
Fax 042-316-3149
◆通信費(2000円)払い込みは郵便振替、または報告会の受付でどうぞ。
郵便振替 00100-5-115188/加入者名 地平線会議
|
|
|
|
|
|