

11月21日。朝の雨がやみ、陽がさしてきた。新聞、テレビは政治資金問題の手抜かりから辞任に追い込まれた寺田稔総務大臣の件を繰り返し伝えている。今月だけで3人目の大臣の辞任なのだ。
◆10月末、沢木耕太郎さんから、完成したばかりの『天路の旅人』(新潮社)を贈っていただいた。沢木さんが情報員としてチベット、モンゴルを歩き通した西川一三(にしかわ・かずみ)さんの豪放な生涯について書かれていることは、通信7月号のこの欄に書いた。西川さんの旅を克明に追った574ページ(沢木さんにとっても最長の作品だそうだ)の力作がついに完成したのである。
◆エベレストに初めてチベット側から登り(1980年)、チベット横断100日(1982年)などの取材を重ねる中で、明治から大正、昭和にかけてチベットに分け入った日本人が何人もいたことに強く惹かれた。30年前、月刊誌『山と溪谷』に2年3か月連載した後にまとめた『西蔵漂泊 チベットに魅せられた十人の日本人』という本は、その10人のドキュメントである。
◆明治時代の河口慧海、能海寛、寺本婉雅、成田安輝、大正時代の矢島保治郎、青木文教、多田等観、2度目の河口慧海、昭和時代の野元甚蔵、木村肥佐生、西川一三。仏教の原典を求めて、情報員として、冒険旅行者として、と立場はいろいろだったが、誰よりも強烈だったのが西川さんである。
◆初めてお会いしたのは盛岡駅前の居酒屋だった。当時西川さんは「姫髪」という小さな理美容用品卸業をやっておられた。「いま、馬油というのが売れるんですよ」と言っていた。いまは店はないと思うが『チベットと日本の百年』(新宿書房)という本の104ページに1990年当時私が撮った「姫髪」の前に立つ西川さんの貴重な写真がある。可能なら図書館などで探して見てほしい。
◆1年364日は仕事をし、休むのは元日1日だけ、という西川さん。会うのは午後5時以降、駅近くの居酒屋だったが、ほとんどつまみも取らず美味しそうに日本酒をやる。沢木さんの本を読んでいてほぼ同じスタイルの取材らしかったことがわかり、なんだかとても懐かしくなった。何度も盛岡に通ううち、はじめ2合だった酒は少しずつ増えお2人は「4合」が普通になったらしい。せいぜい2合だった私にはかなわない出会いだ。
◆夕方開始が定番の地平線報告会には出てこられなかったが西川さんは1994年の『西蔵漂泊』の出版記念パーティー、2001年12月15日、東京青山の「東京ウィメンズプラザ」でやった「チベットと日本の百年」という催しにはそれぞれ鹿児島の野元甚蔵さんとともに出てくださった。モンベルの会報「OUTWARD」で私と対談するため辰野勇さんと盛岡に行ったこともある。
◆青山の会場は、230人の席数に対して500人以上が詰めかけぎっしりすし詰めという盛況ぶりで主催したこちらが驚いた。あらゆるものが効率主義で進められる時代、破天荒な旅でも、けしてそのことをひけらかさない、自分を変えない生き方に共感し、ひとめ本人たちを見ておきたい、という、“ファン”が多かったのであろう。
◆興和義塾という若者たちの養成機関を出て8年もの長い期間、情報員として満州、チベット、モンゴルなど「西北」を旅して西川さんは、1950年にインドから送還された後、外務省に出頭した。国家を背負っての旅だったから報告を、という気持だったが「もういい、もういい」と取り合ってもらえなかった。怒りにまかせて川崎駅前の興和義塾の同期生、内川源司の部屋に住み着き、3年間ひたすら「西北体験」を綴った。「リンゴ箱にかじりついて一心不乱に原稿を書くその背中から光がさしていた」と内川は後に私に語っている。旅を書くのにここまでする人がいるのだ、と私もある意味ショックであった。
◆3年がかりで書いた3200枚の原稿を当時ベストセラー作りの名手とされていた光文社の神吉晴夫のところに持って行ったところ「長すぎる。300枚にできないか」と言われ西川さんは怒り心頭に達した。「あなたを出版界を代表する人と見て来たのに読みもしないでなんだ!」結局芙蓉書房から上巻、下巻、別巻の3部作から成る西川一三さんの唯一の著書『秘境西域八年の潜行』が出たのは1967年になってからである。
◆沢木さんは、西川一三という人間にクライマー、山野井泰史にもつながる人間の純粋さ、行動の美しさを見たのだろう、と思う。それが見事に結実した。ひと息に読むのに相当な体力と知識がいる西川一三の原作に較べ沢木さんの新著は断然読みやすい。本人とのインタビューを重ね、ご家族はじめ西川を知る人々に話を聞き確認しながら書いてくれているのである意味原作以上に信用ができるのである。山野井泰史の『凍』を書いた作家ならではの仕上げ方だ。
◆西川一三さんのことを多くの若者に知ってほしく是非一読を、とすすめておく。何よりも人間の生き方を考えさせられる一書なのだ。[江本嘉伸]
■コロナが日本に入ってきて3年になろうとしています。胃ろうによって栄養を摂り、気管切開をして首に穴をあけて呼吸をしている娘の夏帆を自宅で育て35年になりました。感染すると生きられる可能性は低いだろうという医師のアドバイスもあり、通所デイサービスを通算1年8か月休ませて過ごしました。そんな中で2020年夏には、私自身の心臓の定期チェックで「突然死の波が出ている」と診断され、ICDという超小型除細動器を胸に埋め込み、血管経由で心臓のなかに電線を埋め込む手術をしました。「最終武器だけれど」と、医師に言われました。ICDは心臓発作を防御はできず、意識を失ってから、電気ショックを与え、蘇生させるというものです。駅などにあるAEDと同じものを体内に携帯します。最も不便なことは、リュックを背負えなくなったこと、飛行場の搭乗ゲートを通過すると気絶するとのこと。旅に出て路上でバタンと倒れて死ぬ、のは、気持ちの憧れではありますが、現実はまわりに多大な迷惑をかけます。特に小さな島で倒れたら遺体搬送も大変です。
◆自宅にいることが多くなり、写真整理を始めました。自分自身が医療の渦中に入ったこともあり、懸案であった「医療と夏帆」をテーマにした写真をまとめられないか。自分が「死」を意識した今ならばできるかもしれない、と思いました。そんなときに三重に住む写真家・松原豊さんから、自分がやっているギャラリーで「写真展をやりませんか?」というお誘いがありました。「コロナ禍なので、河田さんが三重に来られなくても展示します」という30点程度の写真展です。
◆もし夏帆が小さな島で生まれていたら、夏帆は生きてはいなかったでしょう。東京で高度医療を受けてこその35年間という年月があります。コロナ禍で医療従事者たちは疲弊していました。さらに、医療従事者の子どもは感染を恐れられ、保育園でも預かってもらいにくい状態になっていました。
◆自分にできることは、夏帆が関わってきた医療を紹介することで、医療への感謝を伝えることではないか、と思いました。会場に行けないかもしれないので、写真展図録として写文集『医療への信頼』を作りました。診察室の医師、検査の様子や、嚥下指導、手術のあとの医師のさっぱりとした顔、気管切開直後の首の孔の診察の緊迫感、などなど医療の素顔をとらえた写真です。これらの写真は今後ほとんど撮れない写真になりました。今、多くの病院で撮影は禁止されています。
◆写真展は、今年7月沖縄の八重山・鳩間島の小中学校で開催し、現在、琉球大学附属図書館本館と医学部別館で開催されています。11月30日まで一般の方にもご覧いただけます。主治医に心配されながら、この2か所の写真展でトークをしてきました。自分の島旅を振り返りますと、力になってくれた島の人たちへの感謝の気持ちでいっぱいです。[河田真智子]
日時:2022年10月19日(水)〜11月30日(水)
場所:附属図書館本館2階ラーニング・コモンズ
医学部分館1階ロビー
企画:琉球大学附属図書館、gallery0369
写真・テキスト:河田真智子(島旅作家・写真家)
展示写真制作:写真弘社
展示構成:松原豊(写真家/gallery0369)
琉球大学付属図書館 特設サイト https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/info/10031/
購入ご希望の方は、河田真智子さんへでお申し込みください。
■極地研の樋口です。64次隊の越冬を控え、このたび立川の住居を引き上げました。出発前の隔離を行なって、11月11日に青海埠頭からしらせで出航します。昭和基地に着くまではメールでのやり取りが難しくなります。向こうに着いたら澤柿教伸さんと引き継ぎ後、2月1日に越冬交代を行なって1年間の越冬生活に入る予定です。2024年3月下旬まで留守にしますが、再会を楽しみにしています。お元気でお過ごしください。[樋口和生]
■高校生活も折り返し地点となった。3年生の先輩は大学も決まり始め、我々も受験生になる準備を始めたところである。2学期は学校行事などが多く濃い毎日が続いている。
◆2学期に入ってすぐに修学旅行があり、広島と大阪を訪れた。広島では原爆ドームを訪れ、広島平和記念資料館にて戦争の恐ろしさを学んだ。そこに並ぶ展示品の一つ一つはどれも戦争の恐ろしさを物語っていた。8時15分で止まった時計や黒焦げになった服やお弁当箱を見て胸が苦しくなった。自分が見ることができたのは、戦争の歴史のごく一部でしかない。二度とこのような悲劇を繰り返さないために、自分たちのような若い世代はもっと社会に目を向けなければならないと思う。そして戦争や核兵器の悲惨さを学ぶ必要があると思った。
◆原爆ドームは4度の保存工事により今も残されているが、戦後原爆ドームの保存に賛成する人たちばかりではなかった。原爆ドームは被爆の悲惨な記憶に繋がることから、取り壊しを望む声もあった。しかし、原爆ドームは絶対にこの世に残しておかなければならないものだと思う。被爆した当時の姿であり続けることに価値がある。私たちは実際に体験した方に話を聞くか、今残っている資料を見ることでしか歴史を学ぶことはできない。時間が経てば、直接話を聞くことはできなくなってしまう。だからこそ原爆ドームを残しておくことに意味があるのだ。また、実際に被爆者の方のお話を聞く機会もあった。当時の状況や感情が伝わってきた。人生初の修学旅行ではとても貴重な体験ができた。
◆10月4日、学校へ行く支度をしていたときだった。Jアラートが発令され、北朝鮮のミサイル発射を受け神津島にも避難を促す村内放送が流れた。ミサイル攻撃に対して、いったいどこに避難せよというのか。伊豆諸島や小笠原諸島は誤作動だったようだが、今までにない音の大きさで鳴った警報音は恐怖そのものだった。寮内だけでなく、村全体があの瞬間混乱していたと思う。
◆広島で戦争について学んできたこともあり、北朝鮮に対する怒りの感情が生まれた。なぜ戦争のきっかけになるようなことをするのか理解できなかった。今年は北朝鮮が発射したミサイルはすでに記録的な水準に達している。これは軍事力増強に対する北朝鮮の確固たる意志を示すとともに、国際的な制裁がほとんど効果を発揮していないといえると思う。
◆ミサイル一発には数百万〜数千万ドルという莫大な費用がかかる。この短期間で80発以上もミサイルを発射している北朝鮮だが、決して裕福な国ではない。にもかかわらずミサイルの開発や配備のハードルがここまで低いのはなぜなのか疑問に思った。北朝鮮のミサイル開発のための材料にどれほどの備蓄があるのかはわからないが、それだけで補えるほどの量ではない。外国から必要な物資を調達する能力があるのは間違いないだろうと思う。
◆少し調べてみたのだが、韓国政府が北朝鮮の宇宙ロケットの断片を解析したところ、部品にイギリス、スイス、アメリカ、中国、旧ソ連から入手したと思われるものが使われていたらしい。北朝鮮は様々な原料を海外に依存していることが分かる。これはミサイル、すなわち戦争を起こすきっかけに多くの国が関与していることを示す。
◆武器を持つことは争いを生むとわかっていながら作り続ける人間は愚かだ。どれだけ私達が呼びかけても今後完全になくなることはないと思う。世界のすべての人が戦争について学ぶべきだ。正しく学び正しく伝えることができれば、あの悲惨な光景をもう一度見ることはない。一人でも多くの人に伝えられるように、二度と戦争を繰り返さないために、まずは自分がこの問題について学び、沢山の人に伝えることができたらと思っている。
◆そして今年も文化祭の季節がやってきた。10月29、30日の2日間にわたり有観客での開催ができたので、とても賑やかな文化祭となった。クラス企画ではお化け屋敷を行った。お客さんのほとんどが島の子ども達なのだが、毎年の文化祭を本当に楽しみにしているという。10時半入場開始なのに9時から子ども達が押しかけて、校長先生がずっと相手をしていたと聞いた。内地では一学校行事としての位置付けの文化祭だが、神津島では村にはなくてはならない文化祭である。これもまた島ならではだと感じた。
◆11月9日、村を挙げての総合防災訓練を実施した。南海トラフ地震による津波を想定した訓練で、今年の夏に完成した津波タワーへの避難や、診療所でのトリアージ訓練等を行った。この防災訓練自体は有意義なものだったと思うのだが、東京都や自衛隊、警視庁、東京消防庁のほか、なぜか米軍までもが参加した。物資輸送や上空からの情報収集を目的としてオスプレイも飛んできた。話によると米軍は島の精米所で精米作業の体験をしていたとのことだったが、なんのためだったのかはいまだに不明である。軍事訓練的な要素があったのかは定かではないが、少なくともアメリカが島嶼部に干渉してきたことに変わりはない。これからの社会がどうなっていくのか不安であると同時に、自分が今後どの様なことを学びながら生きていかなければならないのか改めて考える良い機会となった。
◆最後に島ヘイセンvol.8でお伝えしていた防災士資格試験は無事に合格通知をいただいたので、ここに報告する。[神津高校2年 長岡祥太郎]
■みなさん、こんにちは。11月1日夜デリに到着、3日午後ディマプールに到着。今は6日お昼すぎです。この一週間、毎日がどんなふうだったかを全部シェアしたくなるくらいに、3年ぶりのインドは強烈です。この国の底力であろう市井の人々の逞しさにいちいち感服しています。
◆デリでの入国は拍子抜けするほど呆気なくすみました。審査の窓口がズラ〜と並んでいますが、こっちへ、あっちへ、と指示する人はおらず、「よくわかんないけど、まあこの列に並べばいいか……」と思った矢先、一番端の窓口で暇そうに座っているオフィサーが手招きしました。「私?」とジェスチャーで聞くと大きく頷くので、張ってあるベルトを潜り抜けそそくさとその窓口へ。したがって待ち時間ゼロ。搭乗券(もう用済みと思って仕舞い込んでいたのを、あたふたと手荷物をかき回して取り出す羽目に)とパスポートを提示してから、顔写真と指紋を撮られておしまい。なんの質問もありませんでした。
◆デリの気候は快適ですが、悪名高い大気汚染は相変わらず、というか数日前のディワリの花火でさらにひどかったのかも知れません。修道院でまず「あ、なんか懐かしい匂いだ」と思ったのは石鹸でした。それから翌朝5時すぎ(?)に聞こえたアザーンの響き。
◆3日11時すぎの直行便でディマプールへ。デリ空港でのチェックインカウンターからセキュリティーを済ませるまではうかうかしているとドンドン横入りされるので、はっきりと退けなければなりませんでした。「ウエルカム・トゥー・インディア」です。空港内でひっきりなしに流れる「マスク着用をお願いします」というアナウンスは、しっかりと無視されていました。途中、飛行機の左側からは、綺麗に雪化粧したヒマラヤ山脈(たぶんコルコタ経由だと拝めない)が遠くに見えました。3時間弱で到着。ディマプール空港は石垣空港くらいでしょうか。預かり荷物を引き取るところに、外国人に登録を求めるブースがありました。滞在先と滞在期間と目的を聞かれましたが、ここも何事もなく通過。よかった! 私、表向きはあくまでも、友人であるシスターたちを訪問するツーリストなのです。
◆3年前に置いていったものは修道服を含め、みんなカビ臭くなってました。時差は3時間半しかないので、もういつもの時間に目が覚めます。いろんな変化に目を白黒させながら活動を開始しました。
◆『いのち綾なす』の製作にも大いなる貢献をしてくれたアンガミ・ナガのゴッドフリー神父さんの銀祝に出席すべく、先週月曜日の夜にナガランド州はヴィセウェマ村に向かい、真夜中に到着しました。翌朝は暗いうちから準備のために様々な人が三々五々訪れてきます。「日本から来たシスター」と紹介され、丁重に挨拶していただきました。でも起きたばかりで修道服を着ていなかったので、初めてお目にかかった人からはちょっと胡散臭そうな視線も感じなくもありませんでしたが、白い修道服に着替えて出直すと「あら〜、シスター! ようこそ!」と大きな笑顔に。私が同一人物とわかって、その人もそして私も苦笑してしまいました。
◆二日後の銀祝はそれはそれはスケールの大きな式典で、改めてアンガミ・ナガの優れた民族性に圧倒されました。ちなみに豚肉だけでも1000キロが用意されたそうです。準備期間中は数え切れないお手伝いの人たちに三度のまかないを提供していましたから、お米の量は計り知れないものだったでしょう。引き出物は大型懐中電灯とかナガ・ショールとかジャケットとか。
◆ちょっとした「祭典」とも呼べるような式だったのは、これはゴッドフリー神父さん個人の銀祝だけでなく、ヴィセウェマ村という共同体の存在をも祝うイベントだからです。踊りにしても歌にしても、先住民族の文化の特徴に“コミューナル”(日本語ではどう表現したらいいのでしょうね)であることが挙げられると思うのですが、さもありなん、です。
◆また今回は幸いなことに『いのち綾なす』をナガの人々にお披露目する機会ともなりました。「アメリカでは換算レートに関係なく$30としているなら、そのままインドルピーにしてRs.2500(はっきり言って、とても高い)でいいと思う」とゴッドフリー神父さん。この日はお祝いだからRs.2000(それでも高い)としたのですが、二人の方が即お求めくださって大感激。こういうところにもナガの人々の資質と財のあり様が現れているかも知れません。いずれにしても今回は国内便の重量制限(15kg+手荷物7kg)のため限られた部数しか持ってこれなかったので、今後徐々に紹介していくつもりです。
◆このような喜び溢れる中、非常に悲しい知らせが届きました。メガラヤ州・ガロヒルズはラジャバラで私たちの大事なシスター・ニルマラが突然、天に召されたというのです。シスター・ニルマラは一冊目の写真集『行雲流水』に何度か登場する、ラジャバラ・ミッションにはなくてはならない存在です。そのシスターがあっという間に逝ってしまいました。享年75歳。心臓マヒでした。
◆ラジャバラの修道院には訃報を聞いたと、直ちに、至る所から、クリスチャン、ムスリム、ヒンドゥー、アミニストと、あらゆる人々が集まってきたそうです。翌日にはご遺体が救急車でMMS・インド北東部管区の本部があるアッサム州・スンダリに運ばれてきました。私も銀祝式があったその日の夜行で向かいました。シスターにしてみれば、最後の最後までミッションを生き抜くことができたのは大きなお恵みだったでしょうが、残された私たちはとにかく信じられないという気持ちばかり。今後どうしたらいいのかすっかり途方に暮れました。けれども、“Our life in mission goes on.”です。どうぞこれからも私たちがしっかりと使命を果たしていけますようお祈りください。[延江由美子]
◆皆さんはきっと、インドのコロナ感染状況は一体どうなっているのか気になっておられることでしょう。私が感じる限り、今となっては去年の惨状を想像することは難しいです。街中も市場も乗り物も人でごった返しているのですが、ほとんどの人はマスクなし(とは言うものの、マスクをしている人を必ず見かけます)。親しい間ではハグするし、頬っぺたで挨拶したりもします。握手も以前と同じです。昨日教会で行われた結婚式の披露宴では、いつものように手でいただきましたが食べ終わってから手を洗っていなかったことに気がつきました。インドに来てからあちらこちらに出向き、人と会い、食事を共にしていますが、2週間を過ぎてもいたって元気。このまま無事に過ごせることを願い祈っています。
◆学校は今年の1月から通常通りの授業になりましたが、ロックダウンの間はすべてオンライン授業でした。そのためナガランドでは、なんとタブレットが在庫切れになったとか。そして、タブレットを手にした学童や生徒たち、とりわけ女の子たちは韓流ドラマにハマったそうです!
◆ナガランドに戻った翌日、ペラペラのナイロン生地でできた修道服をアイロンがけしようとしていきなり焦がしてしまい、行きつけの裁縫師(アッサム州出身のアディバシ女性)に持って行きました。仕事場にハングル文字が書かれた紙箱があったので聞くと、16歳になる娘さんがすっかり韓流のファンになりスクリーンを見ながら書いたとのこと。もう一つ例を挙げると、表情に乏しい子だなあと思っていた私たちの志願者(西ベンガル出身のアディバシ女子)が、かの結婚式の写真を見て「わ〜〜! コリアンドラマみたい〜〜」といつになく興奮気味。韓国おそるべし、ですかね。
■福岡では、紅葉も終わりつつあり、夏が確かな足音とともに過ぎ去ったのだと肌身に感じます。今、大学の文系学部が集まるイーストゾーンのベンチに座り、大理石の冷たさを感じながらキーボードをたたいているところです。高台にあるこの場所は夕暮れが美しく、片手で足りるくらいの学生がよく語らっています。今となっては日常的なこの光景が、私はとてもうれしいです。
◆また朝ランニングをしていると、鼻を通る空気のにおいに、雪山が近づいている、という気持ちが起こります。今年度も私の所属する九大山岳部は厳冬期と春に、合宿を行う予定です。このままどこに行くのかを書きたいところですが、つい昨日(11月14日)の夜、九大山岳会のOBの方と検討会を開き、計画の修正を提案され、この冬に目指す山を決められずにいます。
◆現役部員全体の体力、経験値の少なさ、行動計画の甘さをご指摘いただいたのです。当初は厳冬期の五竜岳(遠見尾根からのルート)を、大学の冬季休業期間をめいっぱい使い、予備日を含め12月28日〜1月3日にかけて目指す予定でした。爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳、八ヶ岳など、雪の経験も積むことができ、ピークも目指すことができるような、ほかの山域も検討してはどうか。厳冬期の合宿を年末ではなく2月に行い、もっとじっくり時間をとって山に登ってほしい、など様々な意見をいただきました。コロナの影響もあり、日本アルプスでの合宿経験が少なく、部員全体の実力は例年に比べると強くはない、というのが現状です。悔しさもあります。
◆また今回の冬山の検討に加えて、九大山岳部の1年間の山行スケジュールや山域を見直すべきなのではないか、という話にもなっています。前回の投稿で少し報告させていただいた夏合宿での成果の少なさや、近年の剱岳周辺の雪渓の状態の変化、そしてその状態を判断できない現役の実力不足も、背景にあります。大きくいえば、これまで踏襲されてきた九大山岳部の山行スタイル、技術伝承のあり方が問われているのだと思います。
◆私自身は今年度で現役を引退し、自分の進路を考えなければなりません。今考えているのは、来年度1年間、大学を休学し、やりたいことをやってみよう、ということです。それはおおまかに、山小屋で働くこと、研究を進めること、ヒマラヤに行くことです。目的としては、山小屋で働き、山での生活、登山を取り巻く人、環境について知りたい。そしてそこで得た賃金でヒマラヤに行きたい(関心があるのは人と環境の関係です)。そして残りの期間で、再来年度の留学期間を確保するために、集中して卒業論文を執筆したい。
◆今私の頭の9割は雪山と来年度やりたいことでいっぱいです。どれだけ実現するかわかりませんが、走りながら考えたいです。これからも地平線の刺激を待ち、受け取りながら、自分と世界について考え行動してみようと思います。[九大山岳部3年 安平ゆう]
追記:18日、冬は八ヶ岳の天狗岳にしようと決まり、五竜は2月に持ち越しとなりました。山頂を踏むことは大事ですが、1年生の雪上訓練など部員の実力強化が目的です。
■「キッチン川小屋」などと勝手に名乗り、週末や休暇休日を使って南会津の渓谷と県道を挟んだ細長い林に建てた小屋でスイッチライフを実践している。会津の隠れ家のキッチンで作りたいものを作り、食べたいものを食べる、適度な運動に過大な食欲は我が小屋のモットーなのだ。
◆きっかけは学生時代、秋の連休を利用して友人と開通したばかりの山道を檜枝岐から奥只見銀山湖に向かい、山の錦が映し出された湖面にカヌーを浮かべ、掌状に広がった深いワンドの奥にある沢の出会いにカヌーを置き、さらに踏み跡をたどって花崗岩のスラブに囲まれた小さな池にベースを置いてボルダーリングを楽しんだ。
◆往路は夜行だったから見えなかった景色は復路には錦に染まった深山のくねくねとした道を堪能しながら御池から檜枝岐そして舘岩と辿って帰路についた。社会人になってからも秋だけでなく雪で閉ざされていない春も夏も通った。何回も通ううちに檜枝岐から見る伊南川やそこに合流する舘岩川の流れにカヤックを浮かべてみたい衝動に駆られたのだった。
◆まだ一番下の子が3歳になる少し前、南会津の舘岩村にプライベートでキャンプができる、それこそ猫の額位の土地を所有したいと思った。なにせ4人も子供がいるとどこに行ってもお金がかかる。管理されたキャンプ場は、それこそキャンプブームの真っただ中、有名なキャンプ場ではテントの張綱がお互い交差する難民キャンプの様相なのだ。また子供の誰かがお稽古事やら病気になることを考えると宿をとって旅行や行楽地に行くことはなかなかできない。当時は別荘を持つなんてお金持ちの道楽のような気がしていたけれど、とにかく小さくても我が家族と仲間くらいの人数が楽しめる自然の中のスペースがほしいと思った。
◆今は町村合併で南会津町となっているが、当時はまだ南会津郡舘岩村の中心を流れる舘岩川の支流の西根川という渓流を見下ろす川沿いの細長い林に理想の場所を見つけた。土地の横にさらに細い流れが浅く削った谷が流れている。車を止めることができる小さなスペースと枝沢に沿って下る踏み跡があり、降りきったところが浅いプールになっているのが気に入った。下の沢はイワナ釣りのメッカ西根川だ。水量が多ければ西根川から舘岩川を経由して伊南川の川下りが楽しめる。雪代時期にはわざわざ東京から激流カヤックを目指してくるコースだ。山スキーを楽しむのも会津駒ケ岳の登山口まで約30分で到着する。
◆ここが気に入った。私だけでない、ちょうど上の子が9才、年子の8才、6才と3才の4人、土地を見に行ったときに皆で川まで下りて水遊びができて大喜びだ。一発で決まった。
◆あれからすでに30年、家族や山仲間、川仲間、地元の知り合い、学生時代の仲間から地平線の仲間たちがいったいのべ人数にしたら何人この小屋に泊まってワイワイと歓談したことだろう。今では半地元民だ。キノコ採りに行って家で食べきれなければ近所のお店に持って行き手作りの漬物と物々交換したり、時にはジビエ肉をいただいたりする。
◆しかし約30年の間に周りの環境もだいぶ変わってしまった。東日本大震災で放射能の風評被害が出た年の7月末に豪雨災害で会津各地に土石流が発生、我が小屋の横を流れる水場にしている小渓に土石流が発生して小屋の一歩手前まで土砂に埋まってしまった。当然水場は崩壊、砂防堤が完成する2016年まで近所の湧水を利用していた。やっと落ち着いたと思ったらコロナだ。外出制限は村の観光需要に打撃を与えた。
◆ここ木賊には源泉かけ流しの渓谷の脇の露点風呂と引き湯を再度ボイラーで沸かす公共風呂広瀬の湯がある。広瀬の湯は管理に費用がかかり観光客の入湯税に頼ることが不可能となり閉鎖してしまった。地元では旅館業が成り立たなくなり、今は営業しているのは3軒のみだ。内風呂がない人はここが頼りだったから、お年寄りは人の少ない日中に露天風呂に入りにきたりして何とか生活しているような状態だ。
◆このところ毎年の様に起こる豪雨は、木賊温泉の横を流れる西根川上流の田代山の沢の斜面を崩壊して、毎年の様に土石流が発生し木賊温泉に観光客を呼び込む露点風呂は何回も小屋が流されたり埋まったりしている。木賊の露天風呂は土地の人とこの露天風呂のファンの皆で死守している。昨年も皆で埋まった露天風呂の掘り出しを行なった。
◆崩れた山肌からの山砂は雨のたびに渓谷の川床を埋めてしまい、我が小屋の下の淵は、昔は泳げる深さがあったが、この夏の渇水期には長靴の踝位の深さで対岸に渡れる、イワナ釣りのメッカの面影は今やなくなってしまった。
◆Go To なんちゃらの恩恵がある観光地には人が集中するけども、インフラが整備されて道がよくなり過ぎた分、ただ通過する部落となってしまい、枝道の奥に入ったこの木賊部落は観光シーズンには夜中でも走っていた車はほとんどなくなった。我々にとっては静かに過ごせる反面、村の将来が気になるこの頃です。[河村安彦]
■今年3月に喜界島を離れ、家族で埼玉県入間市に越してきて半年強になります。初めは人、モノの多さに驚き、人との繋りが島に比べて希薄(ただ知り合いがいなかった)なことに寂しさを感じましたが、少し車で走れば秩父があり、周辺も大きな公園が多く思いのほか自然が近く、のんびり子育てできる心地よい場所でした。また、地域も暖かい人が多く外で遊んでいるとよく声をかけてもらえます。
◆さて、入間での生活に慣れてきたころ、喜界島へ越す前に勤めていた会社に復職することになりました。心の準備はできていたものの、以前の仕事は出張でほとんど家に居ない、定時で帰った記憶のない働き方をしており、元の部署でどんな働きかたになるのか、と不安が大きな中での復職でした。
◆子どもから離れることに抵抗がありつつ、しかし、いざ働きにでると「母」ではなく「個人」として認められることは大事な時間だと感じています。一方、一緒に過ごす時間が極端に減るので、やはり遠方出張は控えたいのが本音です。幸い、子どもは保育園を楽しんでいて入所した園には広い園庭があり、その奥に森と呼ばれる場所とアスレチックのような遊具がたくさんあるので、毎日砂まみれの服と共に帰宅します。
◆夫と協力してやりくりし、子どもも生まれてからずっと病気知らずで過ごし、順調!?っと思った矢先、13日夜から発熱しました。疲れが出たのでしょうか。これから、いろんなイベントが起こるのでしょうね。先輩お母さん、お父さん方が乗り越えてきた道をポジティブに過ごしたいです。イライラしてしまうこともありますが……。[日置梓]
こころがはだかの
ひとのことばは
ひとのこころを
はだかにする
かくごをきめた
ひとのことばは
ひとのこころを
うつ
たいせつなひとの
いたみにそいねして
こちばをつむぐよりほかに
いきるみちはない
つむぐことばに
こころをこめるよりほかに
ソウルメイトに
であうすべはない
風光る死ぬまでことばをつむぐひと [豊田和司]
『急に具合が悪くなる』/宮野真生子・磯野真穂 著/晶文社/2019年(哲学者・宮野真生子と人類学者・磯野満穂の往復書簡)
■11月6日、板橋区の植村冒険館の30周年記念講演会があった。日本には実は植村直己冒険館は2つある。1992年に植村さんが住んでいた板橋区に開館した今回の植村冒険館と、故郷である豊岡市に1994年に開館した植村直己冒険館で、これまでは地平線会議は豊岡冒険館との付き合いが長い。しかし、先月の通信で「地平線会議との出会いは百科事典でした」と板橋冒険館学芸員の内藤智子さんが書いているように、板橋ともそれなりのお付き合いをしてきた。今回の催しは、昨年9月、新たに「板橋区立植村記念加賀スポーツセンター」内に冒険館が改装新規オープンしたのを機に荻田泰永さんが特別講演し、生前の植村さんを知るかつての仲間たちが冒険者の思い出を語り合った。
◆詳細を伝えるスペースはないので参加した植村直己冒険賞受賞者、岡村隆さんがFacebookに記したひとこと感想を本人の許しを得て紹介させていただく。
−−−−−−
◆行ってよかった。荻田くんの講演は話が進むほどに熱と深みが増し、聴衆に伝わるのが感じられた。自身の書店開業や読書という営みに絡めての「探検とは知的情熱の肉体的表現である」(チェリー・ガラードの言葉)の解説は秀逸で、探検部学生など若い人たちに聞かせたかった。その後のトークショーの各氏の話も面白かったが、大谷映芳さんの話はもう少し聞きたかったかな。それはともかく、しばらくぶりの仲間や旧知の方々と会えたのは嬉しかったし、このところの出不精を反省するいい機会にもなりました。イベントに感謝! そして、こうしたご縁の大元となった植村直己さんに感謝!
■地平線通信522号(2022年10月号)は10月24日に印刷・封入作業を終え、同夜発送しました。10月号も多くの人が書いてくれ、20ページの厚さに。巻頭の小松由佳さんはじめ書き手の皆さんにお礼を申し上げます。はじめて月曜日印刷にしてみたのでほぼ全員が週内に受け取れた、と推測しています(それでも遅く届いた方は、ひとことメールください。何日で届くのか調べているので)。先月も精鋭たちが頑張ってくれ、私が着いたときは、ほぼ作業は終わっていました。ほんとうに、ありがたいです。作業に馳せ参じてくれたのは、以下の皆さんです。
車谷建太 伊藤里香 白根全 落合大祐 高世泉 新垣亜美 江本嘉伸
◆早めに終えたので全員でいつもの「北京」に行き、餃子ほかを味わいました。皆さん、ありがとうございました。
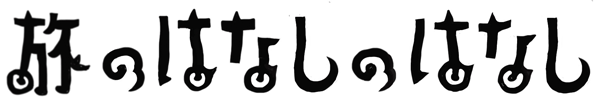
■衝撃の事実から入る。和歌山県民にはザジズゼゾの音がない。ザジズゼゾはすべてダヂヅデドとなる。そして僕は今でもザ行が言えない。普段気づかれないのは、ザ行の音がある単語を同義語に置き換えているからだ。受験英語では「R」と「L」の発音が正確に求められる。ところが海外で話すと不思議となんとかなる。会話は文なので、一つぐらい音がヘンでも流れから意味が分かる。ザ行も同じなのだ。
◆ザ行もダ行もダ行で話していたのに僕は京都の大学に行くまで気付かなかった。異変に気付いた瞬間は覚えている。ある日、ビリヤード屋のママと話していたら、クルーザーという言葉が通じなかったのだ。「んん? クルーダー? クルーザーですよね?」と話がおかしくなった。その後も似た事件が続き、何かがおかしい、と、気づいた。夏休みに和歌山に戻り高校の同級生に会うと、ソイツは「えっ、お前もか」と言う。「名古屋もや」「なんで?」となり、東京に行ったヤツも呼びだし、やっと全員その恐るべき真実に目覚めたのだった。
◆それから努力して無い音を手に入れようとしたが、まず違いを聞き分けるのが困難だった。なんとかしようとして進化したのはごまかし方だ。相手に「ん?」という表情が出たら、すかさず逸らす技術は身についた。しかし講演会で話しだすと、また困った。アフリカの地名はザ行音が多いのだ。ザイール、ザンジバル、タンザニア、ザンビア。地名は置き換えができず、しかもそんな地名まで知っている人は、かならず訂正してくる。関西人が中途半端な関西弁が許せないように、愛着や思い入れのある言葉に厳しいのは当然だと思う。悔しいのは僕は「知らない」わけでも「間違っている」わけでもない。「言えない」のだ。
◆ザ行を意識しだすと、誤りなく使えていた単語も不安になってきた。ダルエスサラーム。間違っていない……。本当に? ザルエスじゃないよな? なぜ僕は19歳まで気づかなかったの? ていうか和歌山県民はどうやって日常会話で違和感なく使い分けてるの? うおおお、わからねぇ。理屈はいい。ともかくなんとかせねばなるまい。
◆タンザニアをバイクで旅しているときに撮った、象が道を横切る写真がある。アフリカの話にはベストな写真なのだが、問題は「象」だ。単語は短ければ短いほど厳しい。象(ドウ)なんて最悪だ。これはキリン飛び出し注意の道路標識と合わせ技で解決した。まずキリン注意の写真を出し、次に象の写真を出す。「ほら、こんなこともあるんですよ」と言えば「象(ドウ)」と言わずに切り抜けられる。地名、国名、は、もともとの活舌の悪さを利用して、さらに活舌を悪くしてごまかした。
◆ある日、閃いた。自虐ネタから講演会を始めてみたらどうだろう? 前振りとして和歌山弁の話から入り、笑いをとってしまえば、お客さんが勝手に単語を変換してくれるはず。素晴らしいアイデアではないか! これは試してみたら、うまくいかなかった。ネタとしては悪くないはずなのに、思ったよりウケないのだ。「笑い」は奥が深く、演技力がないと印象には残らないらしい。講演会の途中で「ダンビア(ザンビア)」と言うと、やっぱり「ん?」て、顔が見える。前振りなんてすでに忘れられている。
◆ダメだ、これは! 考え方が根本から間違っている。ごまかすのではなくて、正確に話すのだ。もうこの際「話す」ことそのものを勉強し直しだ。そう決めて町の「話し方講座」に通うことにした。「実はザ行が話せません。講演会しなければいけないので、まいっています」と正直に告白すると、クラス全員が、この人をなんとかしてあげないといけない、という雰囲気になった。先生だけでなく先輩生徒さんからも「表情が乏しいです」「もっと口角をあげて」「はっきりと発音しましょう」などなど厳しく指導していただく。しかし明るく、楽しく、お客さんに元気を与える話し方となると、もはや技術ではなく性格を変えないといけない。とうとう先生も「坪井さんには坪井さんの味があり、それでいいと思います」という結論になり、当初の目的だったザ行も身につかずに終わる。
◆話し方講座は無駄だったのか、いやそうでもない。生徒さんの学びたい理由には想像を超えるものがあり面白かったし、先生は今でも僕のことを応援してくれている。講演会というと中身が勝負に思えるが、僕の場合はそれ以前に大きな壁があった。
◆東京に引っ越してきたころ、保育園の潮干狩りに行った。引率の先生が「今日は楽しい、しおしがり、だぁ」と、マイクで言ったときの衝撃は忘れない。これかぁ!と思った。でも和歌山弁と違い、そういう方言があるのは知っていた。世の中に認知されているものはラクだ、と思う。東京なんて地方出身者の集まりだから、僕と同じ悩みを持つ人もいるに違いない。
◆いつか、白根全さんを田(デン)さんでなく、全(ゼン)さんと呼んでみたい。
■11月4日。南極遠征の延期をSNSにて一般発表した。南極のスタート地点に行くための飛行機をチャーターしなければならないのだが、契約交渉が折り合わず来年11月に丸々1年の延期を決定した。行かれなければ達成者になることはおろか敗残兵になることすら叶わない。人が行かないルートを選択した極点遠征においてロジスティクスは最大の障害だ。金がかかる。交渉に賢くならなければならない。
◆延期発表時、円安により米ドル建てのチャーター費が集まらなくて行けなかったとの意見が散見されたが、資金の算段はすっかり立てて、相手方の請求書さえ届けば、いつでも払えるところまでこぎつけた。装備も揃えてあったし、後は行くだけ。交渉は本当にギリギリまで粘った。こちらから強めに意見したが飛ばすことができなかった。
◆実行する以上に延期することはパワーを使う。ポジティブではないことをお伝えしなければならないのだから、決して楽しいものではない。心から悔しいが、落ち込んでいる暇はない。今年、南極に行くというので人さまから金を集めているのだ。行かなければ“詐欺師”と罵倒されるのを甘んじて受け入れる覚悟がいる。まずはご説明をして、希望があれば返金をする。2018年にも飛行機契約がうまくいかず南極遠征を延期にした経験がある。その際は約300万を返金した。現在11月14日の時点で返金は5000円のみだ。その事実が、いかに僕の活動を信用してくれているかというリトマス紙になっており、持つべき責任の重さを感じる。
◆よく人から、「それって世の中のためになるんですか」と聞かれるが、「ないんじゃないですか」と答える。そんなことはやってみなければわからないし、諸手を挙げて迎合されるなら冒険でも何でもない。挑戦者は理解されないもの、孤独なものだ。人から理解されて生きたかったら舞台を降りればいい。理解されようがされまいが、やりたいことをやる。そんなワガママを人に応援してもらっている。
◆鶏が先か、卵が先か。資金が先か、遠征が先か。ジレンマと矛盾。夢と現実。相反する中で迷いながら苦しみながら己に立ち向かう。延期発表の文章を書きながら浮かんでいたイメージは、植村直己さんがフォークランド紛争により南極遠征を中止せざるをえずソリを自ら解体している姿だった。先人の心情に比べたら自分の心情などチンケなものだ。
◆南極に行くつもりでやってきたので、スケジュールが南極と被る可能性がわずかでもある仕事はお断りしてきたし、南極後の遠征計画の妨げにしたくないので、来年の仕事も同様にお断りしてきた。狂愚でありたい、自分の生き方のスジを通すため。来年11月の確実な南極遠征の実行と達成。それが本懐。簡単に敵わないからこそ夢。だから人生を賭ける価値がある。オレはしつこいぞ。[阿部雅龍]
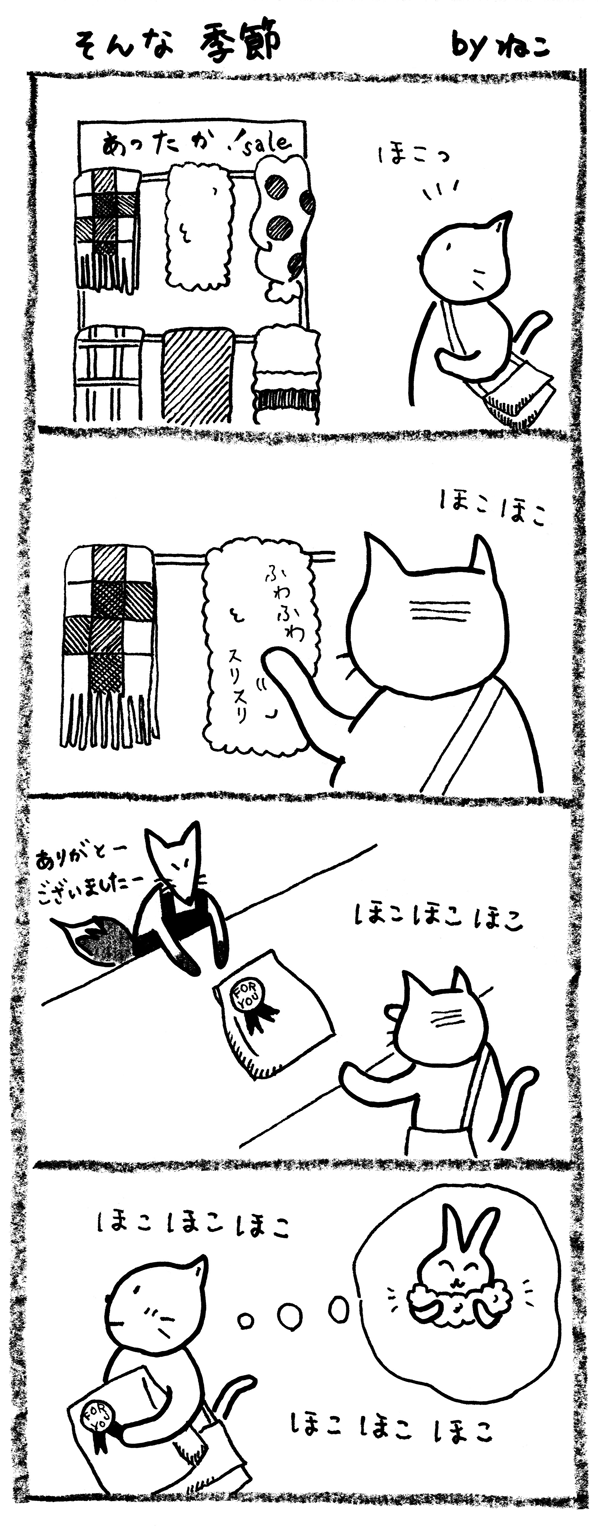
《画像をクリックすると拡大表示します》
「突然ですが、豊が昨夜亡くなりました」。電話口から聞こえてくる麻田美晴さんの声がいったい何を言っているのか理解できず、脳がしばらくフリーズした。えっ! あの豊先生が? まさか!■10月24日の夕食後、食器を洗おうとしたのか、もう一杯飲もうとしたのか、キッチンに立ったところ、家族の目の前でまるで映画のシーンみたいに崩れるように倒れて、そのまま意識を取り戻すことなく亡くなったのだという。心臓発作による突然死だ。享年74歳。あまりにも早すぎる。
◆麻田豊さん・美晴さんご夫妻とは、家族ぐるみのお付き合いをさせてもらってきた。「麻田さん」ではどちらなのか紛らわしいし、「豊さん」と呼ぶのもなんだか気が引ける。結局「豊先生」「純君」と互いに呼び合うようになった。
◆最初の出会いは思い出せないが、外務省所管の財団法人「日本・パキスタン協会(日パ協会)」の席だったはずだ。当時の日パ協会は、報告会や泊まりがけのシンポジウムの開催、月刊の会報や文献案内の編集・発行と、とても活発に活動していた。東京外語大でウルドゥー語を教え、現地での体験も長い豊先生は、日パ協会の文化活動には欠かせない存在だった。もともと音楽に関心の深かった豊先生が、民族音楽を専門とする令子に声をかけてくれたのがきっかけだったのかもしれない。偉ぶるところなく、誰にでも気さくに接してくれる、懐の深い方だった。
◆1987年、弘文堂から『もっと知りたいパキスタン』という書籍が刊行されたが、11人の共著者の一人として、私も「カラーシャ族の生活」と題する小論を書いた。このとき、編集を担当していた豊先生が、私の原稿に登場する地名などのカラーシャ語をすべてウルドゥー語的な表記に直してきたので、それはウルドゥー語帝国主義だ、現地語表記を優先すべきだと私が反論して、大げんかとなった。言葉の表記で豊先生にかみつく者なんて、どこにもいない。編者の小西正捷先生(立教大学教授)が間に入ってくれて、結局、私の言い分がほとんど通った。
◆その後どうやって仲良くなったのか、まったく記憶がないが、ご夫妻でわが家に来てもらって令子の作るパキスタン料理でしこたま飲んだり、次は麻田家におじゃまして美晴さんのパキスタン料理をいただいたりするようになった。お二人とも本場のパキスタン料理をよく知っているし、食へのこだわりも大きいので、緊張する。でも、こちらのアイデアや工夫もお二人ならわかってくれるので、いつも楽しみだった。酒豪として有名な豊先生に付き合うのも、相応の覚悟が必要になる。
◆地平線会議にとっての豊先生といえば、2007年3月の地平線報告会に8人の教え子のみなさんと出てくれたことをいまでも鮮やかに思い出す。インドとパキスタンは1998年に核実験を競い合ったが、その両国の聴衆の前で2005年から3回にわたって、ヒロシマを描いたウルドゥー語劇「はだしのゲン」を上演してきたのだ。語劇とは、毎年秋の外語祭で各国語専攻の学生たちによって演じられる演劇で、失礼ながらなかには学芸会レベルのものもある。それを現地の聴衆の前で上演するまでに育てるには、とんでもない勇気と度胸と訓練が必要だ。まったくの素人だった学生たちが、どうやって印パで30近い公演をこなし、聴衆を魅了するまでになったのか。これぞ地平線報告会と言うべき、胸が熱くなる報告だった。なお、このときの模様は大西夏奈子さんの名レポートと、豊先生を含めた報告者のコメント集として、いまでも地平線のウェブサイトで読むことができる。
◆豊先生のウルドゥー語は、発音も正確で美しく、ネイティブも驚くほど語彙が豊富で、南アジアの文化や歴史への深い教養がにじみ出るといわれる。外語大の修士課程を修了してカラチ大学大学院に留学していた豊先生は、カラチの日本総領事館に付属する文化広報センターの仕事をするようになり、学者や作家、音楽家、メディア関係者、ファッションデザイナーなど、パキスタンの一流文化人たちと幅広く交流を重ねた。机と本にかじりついていたのでは身につかない本物の教養は、こうして培われたのだろう。
◆論文を書くのに興味がなかった豊先生は、2009年に准教授(助教授)のまま外語大を退職する。その後は府中刑務所でパキスタン人受刑者の通訳を担当したり、映画の字幕や評論を引き受けたりしながら、これまでもテーマとしてきた南アジアの音楽文化や映像コンテンツの世界にどっぷりとはまりこんだ。当初は熱心なコレクターとして収集するのを楽しんでいたようだが、やがてツイッターやFacebookで情報を交換し、自らも積極的に発信していくようになる。酒や料理、飲み会などの写真も数多く投稿し、フォロワーたちをうらやましがらせた。
◆大好きな言葉の世界で遊び、音楽と映像を楽しみ、美酒とおいしい料理と洗練された会話を満喫し、教え子たちに慕われ、思う存分に生きた。見事な人生だったと思う。ご冥福をお祈りいたします。[丸山純]
■2008年2月7日。チベット暦のロサで日本の新年にあたる日だった。私は珍しくスキー歩きのトレーニングで戸隠の山小屋にいた。雪の中でケータイが鳴った。「父がさきほど亡くなりました……」西川由起さんの声だった。西川一三さんのひとり娘である。山から飛んで帰って盛岡に向かった。
◆西川一三さんがかなり重い病気にかかっていると聞いたのはその1か月前だった。話ができるうちに一眼お会いしたい。そう考え、2007年12月21日、盛岡駅前、バスターミナルから盛岡繋温泉行きのバスで雪道を病院に向かった。病院の4人部屋の一角に西川一三さんが寝ていた。鼻の脇に大きなガーゼがあてられている。私を見て人が来たことはわかったらしいが、誰かは理解できないようだった。
◆付き添っていた夫人が話してくれた。2003年12月鼻のわきにガンが見つかった。翌2004年1月手術をしたが、良好な結果は得られず、目への転移も疑われた。そして、認知症が発症、2007年12月4日には歯科の階段を転げ落ちて動けなくなり、完全に入院生活となった……。結局、本人とは話をすることもできなかった。チベット、モンゴルを自分の足で歩き通した真の“豪傑”が静かに人生の幕を下ろそうとしていた。戸隠の山小屋に一報が届いたのはそれから1か月後である。
◆雫石川に面した斎場は、ひっそりしていた。通夜の客は14、5人。西川一三さんのことを地元ではほとんど知らないようだった。無理もないかもしれない。ここでは仕事一筋の暮らしで、65年前のチベット潜行のことなどいっさい口にしたことはないらしいから。
◆葬儀は2月10日に「友人葬」という簡素なかたちで営まれることとなっていた。つまり創価学会葬儀である。西川さんの破天荒な生き方に夫人も娘さんも苦労も多かったらしい。「学会がなければ生きてゆけませんでした」と、夫人。入院中に西川さん本人も、入信したという。
◆夫人や友人代表と相談し、私は当日弔辞を読むこととなった。近隣の方々が初めて聞くチベット、モンゴルでの故人の豪快な話をしっかり語らせてもらった。元気な頃私たちが企画した「チベットと日本の百年の会」からの花輪も飾られた。西川一三についてまったく知らなかった、という人が多く、何人もの方がいい話でした、と葬儀の終了後わざわざお礼を言いにきてくれた。西川さんにささやかな恩返しができた気がした。[江本嘉伸]
■モンゴルから大人気男性ラッパーDESANT(デサント)と女性ラッパーGennie(ジェニー)が間もなく来日! 彼らをゲストに迎え、東京在住のモンゴル人ラッパー兼タトゥーアーティストのKA(カー)と私で急遽イベントを企画しました。そのお知らせをさせてください。
◆実はモンゴルって、ポップスよりラップが大好きなヒップホップ大国です。今年私が出会ったバヤンホンゴル県の草原の子どもたちも、「デサントが好き!」と大興奮で叫んでいました。デサントはザブハン県の遊牧民出身、ジェニーはウランバートルのゲル地区出身。モンゴル語の発音はハッ!とかカッ!とかルルルの巻き舌とかなんだか激しく、ラップを歌うとめちゃくちゃカッコいいのです。ラッパーたちのタトゥーも激しいですが、心はモンゴルの大地を愛する温かく素敵な人たちです。モンゴル人の熱さと激しさがほとばしるヒップホップを目の前で見られる貴重なチャンスなので、ご興味のある方は大西まで直接ご連絡ください。
開催日:2022年11月29日(火)DOOR OPEN 20:00 LIVE 21:00頃〜22:00頃
会場: CIRCUS Tokyo(東京都渋谷区渋谷3-26-16)
チケット代:3,000円(ドリンク代別)
お問合せ:(大西夏奈子)
■先月の通信でお知らせして以降、通信費(1年2000円)を払ってくださった方は以下の方々です。カンパを含めて送金してくださった方もいます。地平線会議の志を理解くださった方々からの心としてありがたくお受けしています。万一、掲載もれありましたら必ず江本宛て連絡ください(最終ページにアドレスあり)。送付の際、最近の通信への感想などひとことお寄せくださると嬉しいです。
中村保(10000円)/田中律子(10000円 5年分の通信費をお振込みしました。地平線通信が届く度にもう1か月たったのか。と月日があまりにも早く経過するのを感じています。町中でも紅葉している木々を目にするようになってきました。冬に入り背中を丸めてしまう前にこの秋晴れを楽しみたいものです。朝晩の気温差が激しくなってきましたので、どうぞご自愛ください。星野道夫事務所勤務。追記:2022年11月19日から2023年1月22日まで、東京都写真美術館において写真展 「星野道夫 悠久の時を旅する」を開催します)/菅原茂(10000円 江本さん、スタッフの皆様、いつも地平線通信ありがとうございます。カンパです)/廣田凱子
■先月の地平線通信が届いてから、シリア難民の取材を書いた小松由佳さんの文章にいまだに圧倒されっぱなしだ。小松さんの文章と向き合うには覚悟がいる。読めば読むほど深淵に触れる気がして、集中できる環境を整えてからでないと、とても正対できない。繰り返し読むほどにその場の空気や心の動きが伝わってくる。
◆世間の関心は移り気だ。ニュースで流れる戦争の舞台はシリアからウクライナへと変わり、そして時を経てシリア難民のニュースを目にする機会はめっきり減ってしまった。そんな中、シリアと深い縁で結ばれた小松さんは、シリア、そしてシリア難民の取材に長くじっくり取り組まれてきた。継続してきたからこそ見える避難先のトルコ社会の変容とシリア難民の変化。
◆そして、今夏11年ぶりに、覚悟のシリア入国。取材先では、ご自身がてんやわんやな状況にも関わらず、そしてメトリタイ騒動でさえも俯瞰した視点で綴られる文章に心を打たれた。異文化とは何か、人間が生きるとは何かを考えさせられた。と、同時にどうしてこんなに深く伝わってくる文章を書くことができるのだろうかという疑問が頭の片隅に残り続けた。
◆数日を経てその疑問に対する答えが出てきた。ああ、この人はすべての物事に対して真摯に真正面から向き合って、折り目正しく生きてきたんだなというのが自分なりの答えだった。小松さんの文章からは、生き方が文章に出ているというか、大地に根を張って生きている様が伝わってくるのだ。
◆自身の近況を書く。この1年、山らしい山に登っていない。毎年恒例となっていたGWの北アルプス、夏の薬師沢、赤木沢といった遠出は鳴りを潜め、向かうのはもっぱら日帰りで済む近郊の山や沢だ。理由は、仕事での不完全燃焼感だ。
◆私は、メガネで有名な福井県のメガネ会社に勤めている。主な仕事は、自社で企画・デザインしたメガネフレームを海外工場で生産し、メガネ店へ納めることだ。勤め先の売上の9割以上はこの仕事だ。そのメガネの仕事をメインにしつつ、仕事でも登山と関わりを持ちたいという想いから、好奇心の赴くままにサングラスを登山メーカーや釣具メーカーに提案し、製造を担ってきた。
◆本来、メガネとサングラスは似て非なるもので業界的にも異なる。国内(福井県)では主にチタンという加工が困難な軽い金属製のフレーム生産がメイン、海外では成形機を使ったプラスチック製のメガネフレームの生産がメインで、それぞれの生産設備も異なる。勤め先は後者であったため、偶然にもメガネからサングラスへの製造の垣根が低かったのだ。
◆苦労は多かったが、周囲の協力や人とのつながりに助けられた。そして、3年前からは縁あって鉄道会社の運転士向けのサングラスフレームの企画・製造を任せられるようになった。コダワリが強いため、スマートに進められず、しなくてよい苦労や回り道も多かったと思う。
◆そんなとき、社内で新たに立ち上がった新規事業部門を任された。主な任務は本業であるメガネ店以外の異業種へ老眼鏡を販売すること。すでに1年近く経とうとしているが、商品ラインアップ、販売ルート、提案資料などすべて無い無いづくし。ゼロをイチにすることの大変なこと! 当初想定していたよりもすべての取り組みに時間がかかる。密かに目論んでいたほどのスピードで結果を残せていないことに加え、立ち上げの忙しさも相まって最近は山から遠ざかりつつある。山へ行きすぎると仕事へ注ぐ力が分散してしまう気がするからだ。
◆道のりは長く険しい。小松さんが、何かの折りに「K2よりも、その後の日常生活のほうがサバイバルだと感じています」と語っていたのを思い出す。新たな挑戦をすると当然障害はつきものだ。本業の仕事のほうは、来年に向けた話が少しずつ決まりだし、ようやく展望が見えてきた。昨夏、南極観測隊向けに用意したサングラスはベストは尽くしたものの時間がなくいくつか心残りがあった。
◆その置いてきた宿題を片付けることにも継続して取り組んでいる最中だ。自分なりの挑戦は続く。コロナ禍で報告会が開催されない中、小松さんを始め、地平線通信から受け取るメッセージを興味深く読んでいる。自分の苦労なんか大したものでないやと思いながら、これからもずっと試行錯誤が続く日々だ。来年は心置きなく山に行けるよう今を頑張ろう![福井市 塚本昌晃]
■10月号の20ページを今号も熱心に読んだ。フロントページの出だしは習近平の中国。江本さんは、わが国のこれからに大きな意味を持つ時局に触れたが深くは追わず、をわずか2行でとばして次へ。“連れ”といっしょに味わった谷川岳の紅葉に誘った。9月16日は日曜日、天気が良くてなによりでした。
◆江本さんと同じように、私にとっても谷川岳は忘れられない新人合宿の場だった。1956年(昭和31年)の大学山岳部入部。マチガ沢出会いにテントを張り、雨の中、雪渓できびしく鍛えられた。古い時代をシゴカレて育った。
◆マナスルの初登頂があり、ヒマラヤ登山ブームが到来していた。1965年、未踏の8000m峰を目指した。しかし、途中足場を崩して転落、気を失っているところを助け出された。それから40年後の5月、江本さん夫妻と同じコースをそのときの仲間と高倉山に登り、谷川岳の双耳峰を眺めた。……何とも懐かしい記憶。思い起こさせてくれた江本さんに感謝。生きていてよかった。
◆あらためて40年という歳月の重さを思う。「地平線通信」はこの11月号で、発行以来43年。523号を数える。その間、わたしはずっと読者でいた。ということは、毎号異なる「地平線通信」のユニークな題字を見てきたことになる。10月号はひらかなのキノコ文字だった。《ちチタケ》《せンボンシメジ》《マんネンタケ》など秋のキノコが季節にふさわしく楽しい。いつもながら長野さん(画伯)の並外れたセンス。
◆各ページのレイアウトがこの夏あたりから変わった。2ページ以降、天地に引いてあった罫線が無くなり詰め込んだという感じがしなくなった。わたくし的には好ましい。この先、[旅について]のコーナーを若い人たちがどんどん埋めてほしい。[今月の窓]では、地平線に向けて、鋭く、やさしく、時代感覚にあふれた窓を開けてほしい。投稿者と新垣さんに期待。
◆われらが「地平線通信」、20ページくらいあるのに「目次」がない。それがいいかどうかは別として、たぶん意識的、伝統的に目次を置かないのだろう。したがってページをめくり読み進んでいかないと中身がわからない。読ませる工夫なのかナ。ま、目次はなくても「いいね」。
◆時評の終わりに提案。そろそろ、密閉した空間などを除いてマスクを外したらどうだろう。3年も経っている。顔の見えない人と、こもり声で話すのが不自然に思えてきた。人の命はもちろん大切だが、風の吹く屋外で、自然の中で、山や森、海辺でマスクしている必要はないと思うのです。[成川隆顕]
■井口亜橘様、初めまして。私、地平線会議の周辺をうろうろしている中嶋敦子と申します。あれは明石太郎さんの報告会(476回)二次会の会場、チベット料理のお店でした。そのとき、樋口さんのテーブルにとても楽しそうにおしゃべりなさっている方がいるなあと何故かとても印象に残りました。翌月の通信で井口さんのお便りを拝見、きっとあの方が井口さんに違いない、以来お話ししたかったなあとずっと思っておりました。
◆久し振りに520号でお名前を見つけて胸がいっぱいです。お人柄が文面に溢れていました。私事ですが、亡き父が慕っていた研究者仲間が、北大ワンゲル部の部長さんでした。あるとき遠路はるばる札幌から我が家(実家)に遊びにいらしてくださいました。話題が山の話に及び、その折り帰ってこない愛弟子のことを切々とお話くださったそうです。私が帰省したときに、母が涙を浮かべながら話してくれました。情の深い先生に恵まれて、井口さんはワンゲル部でかけがえのない豊かな時間を過ごされたのかなと思いました。札幌にも冬将軍到来ですね。お体に気を付けてどうかお元気にお過ごし下さい。
◆そんな訳で福澤卓也さんのお名前と雪崩事故防止研究会の存在がずっと気に掛かっておりました(私が在籍していた山岳会は、深刻な雪崩事故を経験していたこともありましたので)。北海道まで飛んで行きたいけれど旅費がねえ、と思っていたところに、2019年本州での雪崩事故防止講演会・講習会が実現したのです。講師の方々は愛車をフェリーに乗せて、慣れない道を飛ばしてタフなスケジュールをこなして下さいました。志の高さに頭が下がります。
◆今冬も講演会が開催されるそうです。以下直近のご案内ですが、ヤマヤはもちろん、バックカントリー、ゲレンデスキーを楽しまれている方も是非ご参加下さい、とのことです。主催者ではありませんが、志高き皆さんを支援したく地平線皆さんにもお知らせします。詳細はウェブサイトをご参照下さい。東京会場はオンライン併用です。コロナ8波が懸念されますが盛会となることを願ってます。[中嶋敦子]
講演会「雪崩から身を守るために」
主催:雪崩事故防止研究会(ASSH)
*いずれも事前登録制 https://www.assh1991.net/
第5回講演会 in宇都宮
11月26日(土)10:00〜17:00(9:30開場)
宇都宮大学峰キャンパス峰ヶ丘講堂
第4回講演会 in東京《オンライン併用》遠方にお住まいの方是非ご参加を!
11月27日(日)14:00〜20:00
青山学院大学青山キャンパス
第3回講演会 in白馬
12月12日(月)14:00〜21:00
白馬村ウイング21ホール
*2019年に開催された雪崩サーチ&レスキュー講習会は日程未定の様子です
*テキスト『増補改訂版 雪崩教本』山と渓谷社1,430円 増補改訂版が2022年11月12日に出版されました
■先月の地平線通信522号で鶴田幸一の文章を読んだ。そうか。還暦をすぎたのか。ぼくは彼より20歳ほど年長、傘寿をこえた。二人とも人生の半分がマングローブとともにあったことになる。お互い、この状態はまだまだつづくだろう。
◆本稿では、ぼく自身の“マングローブとの関係”を述べてみた。だが、その前に、子ども〜大学時代のことを少しふれておきたい。マングローブと一直線につながっているからだ。小学校時代は昆虫少年、蝶々とりに夢中だった。やがて山登りになる。奥多摩の低山歩きからはじまり谷川岳や穂高岳の岩登り、厳冬期の極地法登山(大日岳〜劔岳、北鎌尾根〜奥穂高岳)も経験する。
◆大学で山岳部に入ったのはヒマラヤに行くためだった。でも部内ではだれも相手にしてくれない。当時、日本は貧しく、国外に出ることもままならない時代だった。ヒマラヤを現実のものと考えられないのは当然のことだったかもしれない。でも……。なんのための山岳部なのか。悩みに悩んだ。人生初めての苦しみを経験する。詳細は省略するが、結果、探検部を設立することになる。
◆そして1年後、奇跡がおこり、ヒマラヤに行けたのである。杉野忠夫教授が全面的に支援してくれた。それがなければヒマラヤどころか、いまのぼくはない。いくら感謝をしてもしきれない。1年半をネパール・インドですごした(『一人ぼっちのヒマラヤ』1964、ベースボール・マガジン社)。いま思えば、この旅によって人生が一変する。定まった道をすすまず、好きなことしかしない自由な人生……。
◆本題のマングローブの話をしたい。はじまりは45年まえの1967年、沙漠の国クウェートだった。忘れられない一つの光景がある。沙漠につけられた一本の舗装道路。その彼方、蜃気楼のように高層ビルの群がゆらめく。市内に入る。超高級車ロールスロイス、純白のディスダーシャ(アラビア服)を身にまとったクウェート人が運転していた。世界中の富を集めたと云われたアラブ産油国の豊かさを目の当たりにした。
◆ひらめいたのは、帰国後のあるときのこと。植物が大好きな武蔵野良治との雑談をしていたときだった。革命的な砂漠緑化を考えた。海辺にマングローブの森をつくるのだ。森の緑はイスラームの教えが説く「楽園」につながる。それを目玉にして分譲別荘地を売りだそう。顧客はアラブの金持ちたち、いくらでもいるではないか。そうなのだ。マングローブで億万長者になれるのだ。
◆アイディアの細部を検討する。否定的な要因はまったくない。塩生植物のマングローブは貴重な淡水を浪費することがない。海が育ててくれる。だから森の管理にお金はかからない。つぎは土地。クウェートの中心地は東京なみ、いや東京以上に地価はたかい。だが、遠く離れた沙漠の海辺、タダ同然で手にはいるはずだ。マングローブの苗木も問題はない。空路でクウェートに行く途中、バンコクやムンバイで種子を採ればよい。
◆はじめに声をかけたのは宮本千晴だった。日本探検協会設立や南極大陸最高峰初登頂計画を企てた仲間である。次いで山や探検の仲間たちに声をかけた。おもしろそうだ。反応は上々、ただちに“株式会社 砂漠に緑を”の発足となった(蛇足だがこの一風変わった社名はわが妻の紀代美さんの命名、ちなみに地平線会議はその1年半後に誕生した)。株主は24人、いま思えばなぜ一人30万円もの大金を拠出してくれたのか。まさか「成功の暁にはロールスロイスを進呈」という甘言に惑わされたのではないだろう(あとの話になるが、“砂漠に緑を”は野村総合研究所から“将来有望企業”と折り紙をつけられたことがある。アイディアには人を引きつける魅力があったようだ)。
◆ことの次第は『緑の冒険―沙漠にマングローブを育てる』(岩波新書)で書いた。ここでは冒険論としての側面を論じてみたい。
◆『緑の冒険』第1刷(1988)の帯にある短い文章が印象的だ。“非常識に挑戦する男たちのロマン”。執筆を勧めてくれた編集者の宮部信明さん(のちに岩波書店の代表取締役専務)によるキャッチコピーである。そうなのだ、真の冒険は非常識な行為なのだ。またアラビアの諺に「旅とは困難を乗り越える行為」とある。たしかに“沙漠のマングローブ”は非常識であり、いくつもの困難を越えねばならない息の長い旅だった。
◆10年を振り返る。会社設立のすぐあと、夢いっぱいで出かけたクウェートだが、現実は厳しかった。アイディアは感心してくれたが、クウェートの金持ちは現実的な商人でもあったのだ。必ず利益を生むならばいくらでも投資しよう。だが「夢」にお金はださない。共同経営者になってくれるクウェート人には、ついに会うことができなかった。
◆長期戦を覚悟する。せめて滞在費くらいは稼ぎたい。武蔵野のアイディアでテラリウムを作ってみた。ガラス瓶に観葉植物を封じ込めたあれである。すばらしい出来栄え、でも買ってくれるものはいなかった。2回目のクウェートでは造園業を試みた。緑と水が調和する日本庭園、これぞイスラームの「楽園」ではないか。日本から二人の専門家に同行してもらった。注文がひとつとれた。だが問題がおきる。池の底に水色のペンキを塗れという。わびさびを重視する日本庭園にはならない。文化のちがい、日本の造園家には無理難題と感じたのは当然だろう。造園業もあえなく終わった。資本金の500万円は2回のクウェートで消えた。
◆2年がすぎた。マングローブ計画はすこしも進展しない。奇跡がおきなければそこで終わっても不思議はなかった。だが奇跡はおきたのだ。通産省外郭の(財)海外貿易開発協会(海外貿/JODC)が2年間のクウェート駐在を認めてくれたのである。
◆再びクウェートの土がふめた。しかし暗中模索の状態は変わらない。いや、さらに深刻になったというべきか。安全弁と考えて造園の専門家も来てもらった。だが、思い通りにはいかず、彼との関係は最悪になる。パートナーになってくれるクウェート人もつかまらない。それに加えて今回は海外貿を世話してくれた葉室さん(アラビア石油/中東協力センター)や野々内さん(通産省、のちに資源エネルギー庁長官)までを巻き込んでいた。責任の重さに苦しめられる。しばしば胃がキリキリと痛くなったのは精神的な原因にちがいない。何度も思ったことか、二度とこんな思いは味わいたくない。
◆妻の紀代美の感想は「お金の心配をしないですむ2年間」と「いつも心細い留守番だったのが、今度は家族4人で暮らせたこと」が何にましてもよかった、という。幼い二人の娘(江美と美陽)は、日本人学校でよい友達もできたし、いつでも家のすぐ前のプールで泳げたし、飼っていたジャミール(猫)が可愛かったし、春の沙漠で一面に咲くアイリスも見られたし……、楽しいクウェート暮らしだったよ、という。よかった。よかった。
◆どんな苦しみもいつかは過去のものになる。ある日、アラビア石油カフジ駐在の秋元一浩(信州大山岳部OB)がやってきた(カフジはサウジアラビア領だが、クルマで1時間ほどの近距離にある)。連れて来てくれたのが、おなじ職場の同僚・熱海(あつみ)伸男だった。マングローブに関心があるという。理由を聞いて納得した。かれの父親はアラビア石油設立初期のメンバー、子ども時代はダーラン(サウジアラビア)で過ごし、高校はベイルートで学んだという。いうなればアラビアが第二の故郷、石油の関係だけではなくアラビアと日本を結ぶ何かをもとめてきたという。コーネル大学農学部で学んだ熱海にとって、“沙漠のマングローブ計画”はその求めていたものだった。そんな人間がすぐ近くにいたのだ。奇跡を信じざるを得なかった。もし熱海に会わなかったら、秋元が連れてきてくれなかったら、どうなっていたか。
◆なぜかこのとき、ぼくは父親のことを思いだしていた。手遅れにちかい末期癌、食道全部と胃のかなりの部分を切り取る大手術をした。そのとき不思議な「夢」をみたという。あたり一面は黄色に染まる菜の花畑、そこの道をすすむと二股にわかれる分岐点にぶつかった。右か左か。迷ったあとに、右をえらんだ。気がついたら病院のベッドにいたという。もし左をえらんでいたら、この世には戻れなかったろう。
◆熱海の熱意でカフジ鉱業所の予算がついた。緑の冒険をはじめてから3年目、1981年1月、ようやく山の麓にたどり着くことができた。カフジでマングローブの植栽試験ができるようになったのである。
◆億万長者の夢はとうに消えていた。所詮ぼくには金儲けは似合わない。だが、代わって、もっと意義があるつぎなる冒険がはじまったのだ。誰もが成しえなかったアラビアのマングローブ植林である。これぞ宮部信明さんが評価してくれた“非常識への挑戦”が待っていた。格好つけていえばチェリーガラードの名言「知的好奇心の肉体的表現」である。
◆活動は多岐におよぶ。核となる活動はむろん海辺での植栽試験である。カフジでは3代にわたり研究員(初代:須田清治、2代目:塚本剛正、3代目:鶴田幸一)を駐在させることができた。それに加えて環境が少しずつちがう試験地も確保される。アブダビのムバラス島(アブダビ石油の依頼)、オマーンのクルムとサラーラ(オマーン農業局と協働)、パキスタンのカラチ(パキスタン森林局と協働)の3か国4か所である。ついで植物地理的探検。ほとんど知られていない中東のマングローブを明らかにした。カバーした地域はインド(グジャラート)、パキスタン、クウェート、サウジアラビア、バーレン、カタール、アラブ首長国連邦、オマーンである。
◆文献からわかったこともある。かつてのアラビアは、今と違い、豊かなマングローブ林があったのだ。紀元前4世紀、アレクサンドロスのインド遠征、帰路ネアルコス(海軍提督)はアラビア湾を航海し、マングローブをみていた。“緑の冒険”は、古代にあったマングローブの復元という意味もあったのだ。
◆その後、マングローブの活動は考えてもみなかった方向に進展する。ミャンマーのマングローブ植林、NGO活動、気候危機、地球環境問題、古植物学(マングローブの起源を求めて)などである。だが、紙面は終わりにちかい。つぎの地平線通信で書くことにする。
■「人間は死ぬまで働かなければならない。年寄りも年金なんかあてにしてはダメだ」というのが西川一三さんの口癖だった。私も賛成だ。しかし、最後に医療機関を頼ることになることは誰も否定できない。
◆マレーシアで97才のマハティール元首相が上院に立候補したが落選。日本の福島では19日夜、97才の男性が運転する車が暴走、42才の母親をはねて死なせるといういたましい事故が起きた。老人が頑張り過ぎないようにするにはどうしたらいいか。西川さんに聞いてみたい。
◆河田真智子さんが夏帆さんを産んだ時、半年ほどして東京女子医大病院にお見舞いに行ったことがある。日赤未熟児センターで様々な治療をして正月に向けて退院したものの再度てんかんの発作が出て、外来を受けに行った女子医大病院に入院した、のである。
◆その時、「なっちゃんは病気かもしれないけれど、真智子さんは病気ではないのだから。月に1本でも仕事をしたらどうか」と私が言ったことがその後の真智子さんの「障害児を育てながら仕事をしていく」きっかけになったそうだ。としたら、ありがたいことだ。真智子さんも夏帆さんも私たちにおだやかな光を与えつつ生きてくれている。[江本嘉伸]
 |
《画像をクリックするとイラストを拡大表示します》
今月も地平線報告会は中止します。
第8波が流行しはじめているため、地平線報告会の開催はもうしばらく様子を見ることにします。
地平線通信 523号
制作:地平線通信制作室/編集長:江本嘉伸/レイアウト:新垣亜美/イラスト:長野亮之介/編集制作スタッフ:丸山純 武田力 中島ねこ 大西夏奈子 落合大祐 加藤千晶
印刷:地平線印刷局榎町分室
地平線Webサイト:http://www.chiheisen.net/
発行:2022年11月21日 地平線会議
〒183-0001 東京都府中市浅間町3-18-1-843 江本嘉伸 方
地平線ポスト宛先(江本嘉伸)
pea03131@nifty.ne.jp
Fax 042-316-3149
◆通信費(2000円)払い込みは郵便振替、または報告会の受付でどうぞ。
郵便振替 00100-5-115188/加入者名 地平線会議
|
|
|
|
|
|