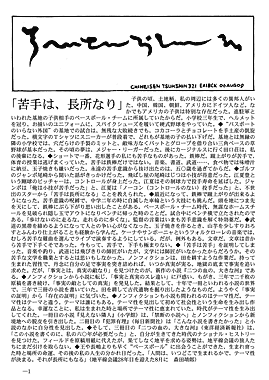
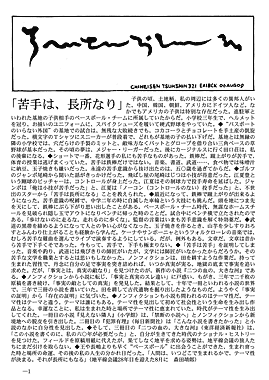
子供の頃、土地柄、私の周辺には多くの異邦人がいた。中国、韓国、朝鮮、アメリカにドイツ人など。なかでもアメリカの子供は特別な存在だった。進駐軍といわれた基地の子供相手のベースボール・チームに所属していたからだ。小学校三年生で、ヘルメットを冠り、お揃いのユニフォームに、スパイクシューズを履いて硬式野球をやっていた。
◆“パスポートのいらない外国”の基地での試合は、無残な大敗続きでも、コカコーラとチョコレートを手土産の凱旋だった。横文字のTシャツにスニーカーが普段着で、どれもが基地の子の払い下げだ。基地とは無縁の隣の小学校では、穴だらけの手製のミットと、敵味方なくバットとグローブを借り合い三角ベースの草野球が基本だった。その頃の夢は、メジャー・リーガーだった。後にカージナルスに行く田口荘は、私の後輩になる。
◆ショートで一番、花形選手の私にも苦手なものがあった。鉄棒だ。蹴上がりが苦手で、体育の授業は逃げまくっていた。苦手は鉄棒だけではない。音楽、書道、武道……、食べ物では味噌汁に納豆、玉子焼きも嫌いだった。永遠の苦手意識から抜け出たのは、五〇歳を過ぎてからだ。
◆ゴルフのジャンボ尾崎から聞いた話がきっかけだった。飛ばし屋の尾崎はじつは小技が得意だった。江夏豊という剛球のピッチャーは、コントロールが身上だった。江夏はその制球力で投手寿命を延ばした。ジャンボは「俺は小技が苦手だった」と、江夏は「ノーコン(コントロールのない)投手だった」と、不世出のスターから「苦手は長所になる」ことを教えられた。
◆最近になって、鉄棒で蹴上がりが出来るようになった。苦手意識の呪縛で、中学二年の時に自滅した車輪という大技にも挑んだ。頭を地につま先を天にして、鉄棒にぶら下がり思い出したことがある。ベースボール・チーム時代、無謀なホームスチールを見破られ隠し玉でアウトになりベンチに帰った時のことだ。試合中にベンチ横で立たされたのである。「歩けないのに走るな。走れるのに歩くな」。監督の言葉はいまも苦手意識を解く特効薬だ。
◆武道の黒帯を締めるようになって人との争い心がなくなった。玉子焼きを作るとき、山芋を少しすりおろすとふんわり仕上がることも経験から学んだ。ケーナやサンポーニャというフォルクローレの音楽では、むしろ苦手な難曲を選んでライブで演奏するようにしている。だが、例外もある。文章だ。文章は昔から苦手で下手くそであった。今もって、苦手で、下手も極まりない。
◆「苦手は苦手」を証明してしまった。音楽や釣り、武道には飛びきりの師匠がいたが、文学には師匠がいなかったからだろうか。その苦手な文学を職業とするとは思いもしなかった。ノンフィクションは、田を耕すような作業だ。持って生まれた習性で、丹念に自分の足で事実を突き詰めれば、いつか真実が実る。地獄の底まで事実を追い求めた。だが、「事実とは、真実の敵なり」を見つけたのが、新作の小説『二つの血の、大きな河』である。
◆ノンフィクションから小説に転じ、「事実と真実のスレ違い」に戸惑い、もがき、三年で二千枚の原稿を書き続け、「事実の敵としての真実」を発見した。結果として、十年で一冊といわれる小説の世界で、三年で三冊の小説を書いていた。田を耕して古代遺物を掘り出したようなものだ。ようやく「事実の証明」から「存在の証明」に気づいた。
◆ノンフィクションも小説も問われるのはテーマ性だ。テーマ性はテーマと違う。テーマは誰にもある。テーマ性を見出して初めて社会性という生命を生み出し作品となる。幸運なことに、私は生まれた時と場所でテーマ性に恵まれていた。時代がテーマ性を生み出してくれた。一冊目の小説『見えない隣人』(小学館)は、「禁断の小説へ」とノンフィクションから新境地への脱皮を引き出した。二冊目の『犯罪有理』(毎日新聞社)は「こんな小説を書きたかった」と小説のなかに自分性を見出した。
◆そして、三冊目の『二つの血の、大きな河』(東洋経済新報社)は、「この小説を書くのに、私の六〇年が必要だった」と、自分が生きてきた時代のナショナル・ヒストリーを見つけた。フィールドを原稿用紙に代えたが、果てしなく地平を求める姿勢は、地平線会議の旅人たちにまだ引けを取らない。
◆王や長嶋よりも早く“ベースボール”に出会うことができた、生まれ育った時と場所の命運、その後の私の人生の分かれ目だった。「人間は、いつどこで生まれるかで、テーマ性が決まる。それが長所にもなる」(地平線会議28年目を迎えた8月に 森田靖郎)
梶光一さんはエゾシカの研究者だが、スタートはヒグマの研究だ。北海道大学のヒグマ研究会、通称「クマ研」。東京から北大に進学し、何か人のやらない研究をしたいと思っていた梶さんは、部員達の醸すユニークな雰囲気に惹かれてクマ研に入部。柔軟な脳ミソと体力に任せて、トライ&エラーを大胆におこなうヒグマの生態研究・調査の面白さにのめり込んだ。
◆日本最大の大型野生獣であるヒグマについては、その生息頭数はもちろん、行動範囲、エサ、生殖的なサイクルなど判らないことが多かった。昭和30年代に道内でパイロットファームが次々と作られ大規模な牧草地が造成されるまでは、人とクマはなんとか棲み分けていたのだ。しかし人が急激にヒグマのテリトリーに踏み込んだ結果、接近遭遇も増え、危機感を覚えた人々はこの時期大量にヒグマを殺した。当時は動物学の権威ですら“ヒグマのようなケダモノを生かしておいては文明国の恥”という論調だった。
◆クマ研は、こうした風潮に反発を覚えた学生有志が、「生態も良く解ってない動物にそういう断罪はないだろう」と調査を始めたのをきっかけに生まれたそうだ。もともと反骨精神から始まった、学生の任意団体なのだ。クマに電波発信機を仕掛けてテリトリーを割り出したり、食痕やフンの分析からエサの傾向を調べるなど、基礎データの蓄積に力を入れた。時間と、体力と、あたま数が揃うという学生の立場を生かした調査データは、現在も北海道の野生動物管理の上で大きな役割を果たしている。また梶さんを始め、専門的な研究者を輩出したという点でも社会に大きく貢献している組織だ。
◆梶さんが知床にヒグマ調査に入った70年代は、ヒグマを見つければ殺すという時代がようやく終わり、数を獲らなくなってきた時期だった。しかしまだクマの頭数は回復せず、痕跡を追って山を歩いていても、滅多にヒグマに出会えない。当時の調査の模様が紹介されたスライドには、冬眠穴や、クマがフキを食べた痕、雪の上に残された足跡など、様々な手がかりが写っているものの、クマそのものの写真はほとんど無い。
◆ところが、後半のスライドでは、カナダかアラスカで撮ったのかと思えるほど鮮明で、近距離から写されたヒグマの姿が記録されていた。実は90年代から道の方針は大きく変わり、「共存」がテーマになったのだ。時代の流れが変わった。その影響でヒグマの生息数も増え、人とヒグマの関係も、「気にし合うけど、互いに素知らぬ振りをする」関係に変わってきたという。
ヒグマに関する卒論で林学科を終了した梶さんは、クマ研の中に「シカ研」を立ち上げ、エゾシカの生態調査に着手した。群で行動をするシカは、ヒグマよりも、個人で行う研究対象には妥当と判断したからだ。エゾシカもまた、その生態は把握されていなかった。年間捕獲頭数から生息数の推移は推測できても、越冬地はどこなのかわからず、行動範囲もわからない。
◆明治期には絶滅の危機に瀕している。北方進出のために軍需用の毛皮の需要があり、肉は輸出用の重要な産業資源となった。当時は10万〜12万頭/年間という狩猟ペース。乱獲である。あまりに獲りすぎて数が減ったため、20世紀初頭から半世紀近く禁猟とし、戦後ようやく解禁になったという経緯がある。梶さんがエゾシカの調査を始めた70年代末はまだ回復期で、道内の年間捕獲頭数は約1500頭。やはり山中でシカに会うのは至難の業だった。78〜79年には梶さんは根室士別の黒牛牧場を拠点に、馬に乗ってシカの痕跡を追う調査をしている。シカの越冬地を探すのが目的だった。このとき乗馬を覚えた事が、後にチベット高原での調査研究に役立つが、それはまた後の話し。
知床で調査を開始したものの、より効果的に調査ができる地域を求めた梶さんは洞爺湖の中島という島をフィールドに加える。限られた閉鎖系の環境だから、頭数の確認もしやすい。群の推移がわかりやすいなどのメリットがある。ここで梶さんはエゾシカの生態を調べるための様々な調査手法を開発した。西欧の事例を参考に、クマ研で培った手法を応用したのだ。
◆エゾシカの生息数を把握するためには、歴史的な数の推移を知る必要がある。いつ頃、どのくらいとれていたのか、農林被害がいつどのくらいあったかなど、聞き取り調査をかさねる。中島では1970年代に、人為的に3頭のシカが島に移されたという経緯が判っている為、その後の数の推移から、気象や食料との関係性が浮き彫りになった。
◆現状の頭数を知るためには視認による計数を行う。これはヘリコプターによる空中からの群の視認(ヘリセンサス)や、あらかじめ複数のルートと計測時間を定め、一斉に車を走らせてルート上に現れた個体を数えるルートセンサスなどがある。ルートセンサスは現在も有効で、道内167か所の設定ルート上で定期的に一斉頭数確認をしている。
◆しかし中島のような閉鎖的な環境では、大人数で追い出しをかけて数を数える「追い出し法」が一番精度の高い視認ができる。スライドで紹介された追い出し法の現場写真には、学生達が輪になって、原始人のようにシカを追い込んでいる様子が生き生きと記録されていた。
◆また、採食ラインといわれる食痕を追い、シカの食態を把握することで、群がどの程度まで環境変化に対応できるかを知るのも、数の把握につながる。シカは特定のエサに依存するというのが定説だった。だから個体数が増えると相対的にエサが減り、自然と頭数が調整されるというのがアメリカの研究者などの結論だった。
◆ところが、梶さんをはじめ、日本のシカ研究者の調査では違う結果が出ている。エゾシカの場合、環境によってエサを換えることで生き延びるのだ。基本的にはササに依存しているが、群の密度が高くなると、落ち葉や、ハイイヌガヤ、あるいは太い木の皮まで喰うことがわかった。
◆捕らえたシカに電波発信機を取り付け、群の行動範囲や個体の移動距離を測る手法も、ヒグマ調査の応用だ。90年代の道東部での調査では、100キロを超える移動をしたメスの個体が確認されている。
梶さんをはじめシカ研の活動で蓄積されたデータをベースに、公金を使った体系的な調査が始まったのは1990年、梶さんが道の研究施設の職員に採用されてからだ。それまでの調査では以下のようなエゾシカの生態的特性が判明していた。
◆1.年に16〜20%の増加率。2.90%以上の高い妊娠率。3.幅広い食性。 4.群を成すので局地的な被害を引き起こす。5.越冬時の気象条件に生死を分ける。豪雪に弱く、群の絶滅がおこる。
◆100年単位で考えれば、シカの頭数は自然に増減する。しかし農林業被害や、シカと車が接触する交通事故が増え続け、人為的に頭数管理をせざるを得ない時期に来ていた。96年からは、道副知事を旗頭に、全道を挙げてエゾシカ対策を取り始める。そのベースデータとして、まず数の変動を把握することになった。
◆調査のヘッドに立った梶さんは、一番被害の多い道東地域をフィールドに、160か所で夜中に一斉に車を走らせ、ヘッドライトの中に浮かび上がるシカの目を数える「スポットライトセンサス」をはじめ、ヘリセンサス、ハンターや農林業被害地からの聞き取り調査を実施した。95年から03年にかけては、全長3010キロに及ぶネットフェンスを設置して頭数確認を行ったこともある。「おそらく、地球上で一番長い人工物ですよ」と笑う梶さんだが、その実施にかかる労力は並大抵ではなかっただろう。
◆こうした調査の上で打ち出したエゾシカ管理の基本方針は、「フィードバック管理」と名付けられた。曰く25万頭を適正な数値と設定し、50万頭を越えたらメスを獲り、それ以下ならオスを獲るというもの。この管理を維持するためには、常に頭数を把握する必要がある。ちなみに、98年の“道東地域エゾシカ管理計画”では、次のようなテーマが掲げられた。1.大発生を防ぐ 2.絶滅は避ける 3.狩猟による持続的収穫を維持。
◆この管理方針の結果、道東では頭数が抑制されたが、道南ではまだ増え続けている。管理方針は決まったものの、現実のシカがどの様な動態で推移するかは自然相手のこと。2004年には、非常事態宣言が出されている。
「いずれにせよ、今日本人が直面している大型野生獣との関係性は、過去100年で初めて出会う事態です」と梶さん。明治の大減少期以来、ヒグマはエゾシカを喰わなかったが、現在はしばしばエゾシカを襲う例が見られるという。「忘れていた味を思い出したんですね」と梶さん。エゾシカに喰いついたヒグマの写真も紹介されたが、これまでの、鮭を食うイメージとは違う肉食野生獣の迫力に満ちていた。
◆戦前までのエゾシカ生息頭数の動向は基礎データが少ないが、戦後少なくともこの50年弱で、世界に例を見ないほど頭数が回復した理由は、梶さんの示した植生図がわかりやすい。昭和30年の前後で、カシワの雑木林が、大規模に農耕地に開墾されているのだ。一方でエゾシカが越冬するために必要な針葉樹の林は昔も今もあまり面積が変わらない。
◆つまり冬の隠れ家はそのままで、夏のエサが増えたと言うことだ。環境がいい上に、繁殖率が高い動物が増えない理由はない。その上、以前に比べて狩猟者が高齢化し、数は減り続けている。「ハンターが絶滅危惧種」とは、最近何度か聞いた笑えない冗談だが、事実である。こうした現状もふまえた上で、北海道が手掛けたエゾシカの個体数管理システムは、生態系重視の日本の先駆的事例といえる。
◆管理システムはとりあえず整ったが、では、獲ったエゾシカをどうするかが問題となる。エゾシカの影響は、農業被害もさることながら、人工林の若樹の葉や新芽を好んで喰うため、森林再生を阻む一番の加害要因にもなっている。そこで梶さんは「エゾシカを林産物にしよう」と提唱する。
◆人との関わりのタイミングで、いきさつ上人為的に管理される成り行きになったエゾシカ。管理計画に沿って資源化を図られる以前は、「有害鳥獣駆除」という名目で狩猟対象となっていた。いわばゴミ扱いされていたのが現実だ。いずれにせよ人間の都合で殺すなら、せめて、なるべく無駄無く活用を図るのが、同じ生きものとしての礼儀だろう。今北海道では全道を挙げてエゾシカ肉の普及に努めている。地産地消をとりあえずの目標にしているが、東京にもエゾシカのステーキを出す店がいくつもあるそうだ。
◆「エゾシカを林産物に」とのスローガンは林学科出身という梶さんの面目躍如たるものがあるなと感心していたのだが、「歴史的には昔から言われたことだよ、勉強してないなあ」と怒られてしまった。実は私(長野亮之介)は梶さんの大学での後輩に当たる。81年に洞爺湖中島のシカ調査にも参加したことがあるのだが、梶さんの仕事の流れをよく知らなかった。今回体系的な話を聞かせていただき、初めて梶さんの仕事の全貌を知り、あらためて梶さんの研究者魂を実感した次第。ものすごく充実した報告会でした。
◆梶さんはこの四月から東京農工大学大学院教授に着任し、北海道を離れた。担当は野生動物保護学である。「とにかく今は、日本で野生動物の現場に携わる専門家が少ない。人材の育成が急務なんです」と梶さん。これから10年は現場に人を送り出す側にいるつもりと話す。学生時代から大学にいるより現場にいる方が長い人だったので、大学の箱の中ではなく、現場で人材育成に当たっている姿が、今から目に浮かぶ。(長野亮之介)
地平線ポストでは、みなさんからのお便りをお待ちしています。
旅先からのひとこと、日常でふと感じたこと、知人・友人たちの活躍ぶりの紹介など、何でも結構です。
〒173-0023
東京都板橋区大山町33-6 三輪主彦方
〒160-0007
東京都新宿区荒木町3-23-303 江本嘉伸方
E-mail :
Fax: 03-3359-7907(江本)
夏は若者の季節というのは昔の話。いまやおやじたちも元気いっぱい、時には多少のムリをしつつ踏ん張っている。そんな風景のいくつかをポストから紹介したい。
シーカヤックの先駆者として知られ、週末を利用した日本一周カヌー旅などさまざまなカヌーの挑戦で知られるカヌーイスト、吉岡嶺ニさんが68才のこの夏、ついにヨーロッパに艇を乗り入れた。7月末に『北海から地中海へ・欧州運河2000キロ』のパート1・パリ〜アムステルダムの旅から帰ってきたばかりの吉岡さんに貴重な「運河旅」を報告してもらった。(E)
セーヌ川でカヌーは漕げるのか。パリに着いて早々、河畔の水上警察を訪ねた。答えは「ノン」。市内中心部でのチビ舟航行は禁止されているという。それでルーブルやノートルダムを見上げて漕ぐことは断念した。次は今夏のルート720キロの中にある108ヶ所の“関”(英語でロック、フランス語ではエクルーズ)が越えられるかどうかである。
◆6/26、日本から持ち込んだ「サブロー8号」(長さ4.2m)でパリ郊外のシャトー・クロワジーからスタート、僅か20キロだがセーヌ川を漕ぎ、コンフランでオワーズ川に入った。いきなり面食らったのは、巨大なバージ(水路運搬船)である。ヨーロッパで運河は完全な産業ルート、言わば高速道路の中に三輪車で入り込んだようなものだ。最初の二つの関は大型船で満杯、やむなく愛艇を崖上まで担ぎ上げて運ぶことになった。その先が思いやられたが、三度目の正直だ。今度は大型バージの後ろに隠れ、タイミングを見計らって強引に突入した。結果オーライになった。
◆カヌー旅ではどこで寝るかが最大の課題だ。フランスは治安がよくないというが、なんとかたどり着いた田舎町にホテルなどはない。結局は長年慣れたテント泊になった。寄り道してはミューゼアムを覗き、河畔の古城を訪ねていく旅は楽しかった。
◆思わぬアクシデントにあったのは、7/2、シャウニー(コンフランより137キロ地点)を出発した日である。岸辺に運河局の車がやってきて、この先は通行止めだという。オワーズ川に並行して走る側設運河は、およそ200年前にナポレオンの命令で建設されたもの。老朽化が進んで全面的な改修が必要なのだそうだ。いまさら引き返すことは出来ないが、カヌーならば担いでも行ける。ここで万一のために備えて持ってきたカヌー運搬用のカートが威力を発揮してくれた。エクルーズに差し掛かる度にカヌーを降り、上陸ルートを探し、大小10数個の荷物を積み替えての探険ごっこになったのである。
◆最大の難所は7/5、僅か7キロの間に12ヶ所のエクルーズが待ち構えていた。ならば一気に行こう。荷物を積み込んだカヌーを曳いて側道を歩いて消化した。7/7、ジュールモント(270キロ地点)を過ぎてベルギーに入った。感激したのはシャールロワ(312キロ地点)の巨大なエクルーズ、大型バージが何隻も入る凾なのだが、カヌー1隻のために待ち時間なしで開けてくれた。もちろん無料。
◆シャールロワを過ぎた所で自転車で岸沿いを走っていた中年の男・ムッシュー・グランシャが声を掛けてきた。ムッシューの本業は古本屋なのだが、新聞社のレポーターでもあるようだ。7/10、ナミュール(360キロ地点)のマリーナで手渡されたのは地元の新聞。「ザンブル川を行く日本人」の見出しで大型船の後を漕いでいく写真が掲載されていた。翌朝には再度新聞社のインタビュー、そしてTV取材までやってきた。その後は、「レイジ、もっと綺麗な川に案内しよう」と誘ってきた。彼もまたカヌー大好き人間、それで、アルデンヌ高原の奥深くまでオプショナル・エクスカーションに連れていってもらい、その夜はムッシューの家のベッド、最高の中休みになった。
◆7/13、リェージュ(423キロ地点)を過ぎてオランダに入った。と言っても標識など何もない。その先も連日、ヨーロッパ各国からやってきたモーターヨットとの交歓が続いた。マーストリヒトからやってきたホッフ一家に招待され、使い古しだけどとプレゼントしてもらった航海地図が有り難かった。現地で購入することにして予め準備してきたのは、道路地図だけだったから、その先3日分のルートを詳しく知ることが出来た。
◆ワール川を横切った所でメルヴェーデ運河の入口が見つからずにいた。又々助け船がきた。水上警察の警備艇である。道を尋ねるだけのつもりで漕ぎ寄せたのだが、本船に乗り移れという。メルヴェーデ運河の入口まで曳航してもらい、その上アムステルダムまでの航海地図をコピーしてくれたのである。お陰で超弩級のバージが大波を曳いて航行するアムステルダム運河を避けて、ヨーロッパ運河の中で最も景色がよいというヴェヒト運河をたどっていくことが出来た。複雑に張り巡らされたアムステルダム市内の運河網を抜けていった先は、上陸目標にしていたマリーナがあることも、しっかりとマークしておいてくれた。
◆7/21、アムステルダム着。トータルで26日、思い返しても胸のすく旅だった。この先の道は長い。アルプス越えだから、関の数も200以上、どうやって行こうか。(8月6日 吉岡嶺二Faxで)
地平線会議のみなさん、お元気ですか? ぼくは7月の1か月間、バイクで東北、北海道を走ってきました。その距離は約1万キロ。いやー、なんともすさまじい夏で、ほとんど連日のように雨でした。おまけに北東北や北海道は雨プラス寒さ…と散々でしたが、それをどこか喜ぶ自分がいるのですね。
◆梅雨のない北海道なのに、まさに梅雨状態。おまけに「この寒さは異常だ」と、みなさん嘆いていました。とくにオホーツク沿岸の寒さはきつく、7月だというのにほとんどの家ではまだストーブを使っていました。東北ではまったくといっていいくらいに日がささず、稲作に大きな影響が出るのではないかと心配されていました。
◆ところで今回の東北、北海道は林道が一番の目的で、全部で100本以上の林道を走り、1000キロ以上のダートを走破しましたよ。ぼくは「林道の狼・カソリ」といわれているのです。8月16日に出発しますが、今度は「シルクロードのカソリ」にガラリと顔を変え、バイクでシルクロードを走破してきます。
◆神戸から中国船でバイクともども中国の天津に渡り、シルクロードの玄関口の西安へ。そこから蘭州、玉門、敦煌…とシルクロードを西へ、西へと走り、新疆ウイグル自治区に入り、シルクロードの天山北路、天山南路を走ります。その間では北のジュンガル盆地からアルタイ山脈の山麓まで足を延ばす計画です。天山南路のオアシス、コルラからはタクラマカン砂漠を縦断し、崑崙山脈北麓のニヤへ。そこからはシルクロードの西域南道でホータン、ヤルカンドと通り、中国西端のカシュガルへ。
◆カシュガルから世界の屋根、パミール高原のトルガルト峠(3752m)を越えてキルギスに入り、カザフスタン→ウズベキスタン→トルクメニスタンと旧ソ連の中央アジアの国々を通りイランへ。ゴールはトルコのイスタンブールです。全行程約1万5000キロ。思う存分にシルクロードを走破してきます。イスタンブールからは10月の半ばに帰ってきますが、そのあとは「温泉のカソリ」に顔を変え、日本中の温泉、3000湯をめぐります。名づけて「日本全湯(とう)制覇計画−目指せ3000湯!」なのです。(賀曽利隆)
ワールドカップも終わって一息ついた。わが奥さんは、「野球と違っていつ点が入るか分からないからビール飲んでいるヒマがない。オジサンたちにはサッカーは流行らないよ!」と言う。私の好きなサッカーにケチをツケやがって!おもしろくない。でもその通りで、サッカーはオジサンの見るスポーツではない。自分でやらなきゃ。
◆早速子ども用のサッカーボールを取り出して、近くの河川敷で蹴ってみた。ゴムボールなのに思うように飛ばない。ここ十数年キックをする筋肉を使っていないので足首、足の甲、親指すべてが痛い。それでもボールを蹴る気分はよみがえってきた。先日の三浦雄一郎さんの報告会のあと、賀曽利くんが「ボクは今でもサッカーやってますよ〜ぉ」と挑発してきたので、対抗上「俺だってやってるよ…」とつい言ってしまった。
◆そこへ高校の大先輩から、「60歳以上のシニアサッカーチームを作るから出てこい!」とのお話。世の中には元気なオジサンがおり、いくつかのチームでリーグを作っている。シニアはお金もあるので、豪華に芝生のグランドで、月に7、8回の練習試合をしている。我が高校OB会は強力チームだが、物故者が多く、弱体化したため強化に取り組むことになった。
◆でも一応選考テストがあるという。メンバーは高校や大学で全国大会に出た人たちがほとんどだからあまり下手だと失礼になる。あるレベルが必要ということらしい。私は全国には出たことはないが、関東大会の代表にはなったので(参ったか、賀曽利!)まあ誤差の範囲で、経歴はクリア。あとは現在の実力だ!
◆それと見た目も大事なので、前日に大枚はたいてパンツとストッキングをそろえた。スパイクは捻挫する恐れがあるのでやめて、練習用の運動靴にした。走るだけなら負けないが、技術はちょっと! 千石にある母校のグランドに集まった。すでに若手OBと現役高校生の試合中だ。ワールドカップを見慣れた目には、高校生の試合はまだるっこしい。しかしグランドに入ってみると高校生のスピードはすごい。
◆年寄りOBの相手は、今年から中高一貫学校になって初めて入ってきた中学1年生チーム。これぐらいの相手ならと思ったのが大きな間違い。私はボールを思いっきり蹴っても3mくらいしか飛ばない。子どもボールと違い石のように固い。一回蹴ると足の骨がグジャグジャになった感じだ。守備にまわってゴール前に戻ると、ハアハアゼイゼイで心臓は破裂しそう。こんな短距離を、全力?で走ったことがないので、腰が抜けそうだ。2週間前のぎっくり腰がまだ完治していないので、ボールが来ても足が伸びず、親指の先でちょいとさわるのがやっと。頭で考えていることが、全く足に通じていない。
◆これほどまでに体と頭がバラバラになっているとは思っても見なかった。「シュートが遅い!」などテレビ画面に向かって叫んでいたが、自分はどうだ。ゴール2m前にゆっくり転がってきたボール、3m蹴る能力があるのだから、難なく入るはずなのに、無情にもボールはそのままゴールの外に。15分ハーフ、計30分を一応無事走り通したが、試合は2:0で完敗。中学生と侮った報いだ。
◆試合の後の懇親会。入団結果は発表されず、もう一度練習しようということになった。次の練習には私より下手そうなOKA田やFUJI城を呼ぼう。それまでに5mくらいは飛ぶように密かに練習しておこう。お隣の国のテポドン発射やミサイルが飛び交うレバノン情勢の中で、こんなことやってていいのかと思いながら、暑さの中でボールを蹴り始めた今日この頃!(三輪主彦 8月3日)
このところ地平線にはご無沙汰していた。今回の通信では月曜日とのこと、無理だよなと思いつつ、行ければラッキーと、いつものように鞄に通信を入れて出勤した。が、行けるではないか…。パタパタと仕事を片付けて会場に駆けつけた。
◆今回の報告会“狩って食うシステム”は、ひきつけられる題材だ。1978・1981・1983と3回のマッケンジーの旅は狩って食う人々の生活をつないでいく旅だったのだ。そんな自分が、会社に勤め 週末アウトドアーのみしか出来ない状態で出遭った会津が、あの時の記憶を呼び起す土地だった。
◆その会津の渓谷に川小屋を構えて13年になる。まだ30代の後半だった。無謀にもログキットを購入し自分で組み立てる計画を立てた。助人として参加したN画伯やS氏からアウシュビッツ並みの扱いだという非難を受けながら、週末と祝日のみで丸5か月で仕上げたのはメーカー言うに最速記録であった。まったく若気の至りであった。
◆会津でも野生動物の目撃が多くなった。雪が深くてニホンシカの生息数が少ないといわれていたが、最近は多く獲れるらしい。尾瀬にも現れ植生を荒らすという。又、熊の目撃談も多い、肉のお裾分けもある。サルも多くなってきた、裏山に茸獲りにでかけると、よく目にするようになった。サルは小屋を建てた当初は聞いたことが無かった。保護されているニホンカモシカにいたっては、人家近くまで出没し頻繁に目につく。どうしてなんだろうと素朴な疑問で今回の報告会には興味があった。
◆昨年、今年と全国各地大雪であった。地元の人も体験したことのない雪だそうだ。わが小屋も昨年の大雪で煙突がつぶれ煙道をふさぎ石油ストーブのみですごした。屋根に堆積した湿雪は重く、それが1m以上にも達し小屋をつぶしにかかる。
◆今年は、昨年の大雪の教訓から雪の付いた屋根に上がって雪を落とすシュミレーションを行って挑んだ。まともに食らうと強烈な雪崩に巻き込まれる、カヤックのパドルを改良し雪落としを制作し挑んだ今年の雪落としは、うまくいったはずだったが、屋根の反対側に落とした雪のブロックはその強烈な破壊力でテラスの直径25cmのコンクリの柱を4本もなぎ倒してしまった。スゲー。
◆雪や大雨の季節を過ぎると山には風倒木が散乱する。この2年はそれがいやに多い。昔なら山に入り山の恵みとして薪をひろい、人々の生活のエネルギーとした。人は森に入り森を育てた。今はそれがない、荒れたままだ。だから沢に引っかかった倒木が自然のダムになって土石流の元凶となる。数年前我が小屋の横を流れる沢が小さな土石流をおこし道をふさいでしまった。これは人災だ。せめて風倒木を集めて盛大な焚き火を囲み山の恵みを堪能しようではないか。
◆そういえばこんな大雪なのに村には若い人が少ない。自然の豊かな土地には若い力が必要なのに雪下ろしをやっているのは大半が老人だ。屋根のひさしが折れた家や建物ごとペシャンコの家もよく見かける。ここで自然と共に生きていける生活基盤がないから、そして便利な生活がないから若い人は皆町に出てしまう。今回の報告者梶さんが、狩猟する年齢層が高くなってそれが又野生動物の異常な繁殖の一因になっていると言っていた。自然と共生することが出来る人が少なくなっていることは、自然のアンバランスの大きな要因になっていることを実感している。
◆とはいえ生活は確実に便利になっている。この小屋を建てた13年前現場にガスも水道もなかった。電気はすぐに発電機を借りて使えるようになったが、あとは沢の水と焚き火で過ごしていた。それが近くまでホースに水が通り、コールマンのツーバーナーを備えたとたん生活が一変して感激した。ちゃんとしたご飯が食べられるようになって十分に便利になった。それが昨年電子レンジをいただいたとたん料理の腕が落ち、工夫がなくなってしまった。やはり不便も楽しみの一つ、チンひとつでの簡単ご飯の誘惑に駆られつつも焚き火とダッジオーブンが最近の川小屋生活の必需品になっている。
◆遊びも様変わりした、最近のカヤック雑誌を見ていると横文字の技が氾濫していて、カヤックでも「エアリアル」なんて技があるようだ。カヤックの長さが身長ほどになってしまったので、ある程度の技術を取得すると小さな波でもくるくる縦にも横にも回る。
◆過日、地元の那珂川を昔のファルトボートで漕いでいたら、どこかのカヌースクールの先生だろうかクルクル回っている若い人に、「そんなカヤックでは危ないよ」と言われたンンンン…!?30年前からホームゲレンデにしている那珂川で言われたので思わず周りを見回してしまった。自己紹介しようと思ったが、オトナゲないのでやめといた。以来、わが会津の人知れぬスポットで新しい技の猛練習をしている。いつか、メジャーなゲレンデで技を披露出来るように…オトナゲないか!!(河村安彦 1983年8月報告者)
7月29日午前1時半。今年もまた、カラフルなレーサージャージーに身を包んだ物好きたちが、稲毛のサイクルハウス「ジロ」に集まってきた。太平洋に面した千葉から日本海に面した直江津まで走り、餃子をつまみに生ビールを飲む。ただそれだけのために集まってきた30人のサイクリストたちである。彼らは2時ちょうどにいっせいに走り出すと、各々たどりたいルートに分散しつつ路上で10台ほどの自転車を吸収し、40台に膨れ上がったところで本格的な北上を開始した。
◆今年はノーマルルートと呼ばれる碓氷妙高組、2000年を記念して誕生した2000m台峠越えの渋組、17号直進の三国峠十日町組の3グループに分散した。これらのうちもっとも速く到着するのが碓氷妙高組で、三国峠十日町組もまた似たような時間にたどり着く。一方325kmと距離こそ最短でも、1時間以上余分にかかるのが渋組。960mの碓氷峠は一気に越えられても、2172mもあっては一息にとはいかないからである。しかも「トライ360」には、直江津0:24発の急行「のと」に乗って帰るというタイムリミットまで付随する。そんなイベントが毎年7月の最終土日、直江津で飲もうを合言葉に開かれている。
◆こんなばかげたイベントに参加するなんて、さぞやロードレースのエキスパートばかりかと思われがちだが、実態はさにあらず、女性もいれば62歳の長老も混じるアットホームな、しかも40人もの大集団である。そんなイベントへの参加も今年で7回目になった。これまですべて別ルートをたどり計6コースを走ってきたが、さすがに新ルートにも枯渇、そこで今年は東に大きく膨れる400kmコースを検討していたところ、初参加を熱望する友人が現われた。ここに先導をテーマにした初回以来の碓氷妙高ルートを走ることになる。コースはいたって単純で、都心突破の川越街道、高崎、碓氷峠、長野、妙高高原経由、直江津行き。通過するのは、14号、254号、17号、18号と、たった4本の国道である。
◆ところで海外を走ってきた自転車連中は、どういうわけか帰国すると走らなくなる傾向にいる。地平線でも名の知られた友人など、みごとに貫禄ある姿になっている。熱望したのはそんな連中ばかりの中でも比較的走りこむふたりで、少なくとも腹は出ていない。
◆2時半、私も自宅(検見川浜)を出て1時間後に市川でひとりをピックアップすると、さらに小一時間で川崎から走ってきたもうひとりを秋葉原に回収、川越街道へと乗り出した。出発時は盛夏満天の星も、涼しく明るい朝になっていた。走り出して3時間半、朝もやの川越に到着したが、それでもまだ70km、直江津まで五分の一も走っていない。ここで朝飯をかき込みそのまま北上、熊谷で中山道に合流、吹きはじめた夏特有の南風を浴びて軽快な走りになるかと思った矢先、深谷でひとりのタイヤが破裂、自転車屋を探すはめに陥った。
◆修理はほぼ一時間で完了し、以後も順調に高崎、安中と通過したものの、碓氷の登りでもうひとりが遅れだしたため、軽井沢到着は2時半になってしまう。もはやリタイヤ・タイムである。碓氷峠はちょうど中間点、ここまでに12時間も費やしては0時の到着すら危うい。しかも200kmを越えて、碓氷のダウンヒルすらままならぬほどに太腿が張っているという。おかげで長野到着など7時を過ぎてしまった。
◆しかも長野の先には二本目の道が登る。すでに真っ暗、道路状況などまるでわからぬうえ、ただでさえ遅れがちのひとりはますます遅れていく。けれども長野から登場した上越(高田)までの距離版の数字は、少しずつ着実に減っていった。これを唯一の励みにピークの野尻湖を越えて、残すは一気のダウンヒルのみ。ところが闇に視界が利かずでは、悔しいがブレーキを絞りながらでしか下れない。眼下では、新井、高田、直江津の夜景がきらびやかに散らばっている。
◆後半の盛り返しが効いたか、23時過ぎになんとか直江津に到着できた。一時はリタイヤ寸前にまで追い込まれかけたものの、初心者を引っ張っての「直江津トライ360」を今年も走り抜くことができた。本来なら直江津に着いてもなお、輪行作業と急行「のと」への乗車作業が待っているが、翌日も休みならまだまだ走りたい。一泊のち、中越地震で救護活動した川口町へと向かうことにした。
◆あれから2年、川口町は予想以上に復興していた。壊滅状態だった小高地区は放棄されたままだが、その下流の田麦山地区では著しい勢いで新築家屋がならんでいく。その力強い波に思いのほか安心できた。もし走りたい方がいたら先導請け負います。いなければ来年は、千葉−今市−田島−奥只見−小出−直江津で走るつもりです。(埜口保男)
8月12日(土)夜9時−11時9分フジテレビ系で放映! モンゴル、シベリア、サハリンの「北方ルート」が主題。お見逃しなく!
「海を泳ぐ駅伝大会に出ませんか?」というメールが、地平線会議の古株、増島達夫から届いたのは6月下旬のことだった。その月、私は背中に不審な痛みを抱え、大学病院を2つも受診して精密検査を受けていた。私の歳で背中が痛むのは極めてヤバいと脅されての受診だったが、結局、内臓疾患は見つからず、一安心している時に増島から誘われたのだ。それと前後して、スリランカの遺跡探検計画を話し合うため出た会合で、私は法大探検部の後輩OBから「侮り」を受けた。「岡村さん、今でも10キロのザックを背負って1日30キロ歩けますか? できないと今度の参加は難しいですよ」。言ったのは私が30年前にスリランカへ連れて行き、おかげでスリランカ研究者に育った後輩だった。その恩義を忘れた物言いに頭に来た私は、増島のメールを思い出しながら怒鳴った。「ふざけるな! 俺の体力をなめるなよ。俺は今度、海の遠泳駅伝にも出るんだバカヤロー!」。そんなわけで、私は快気祝い(?)と意地とを兼ねた理由から、大会に出なきゃならないことになったのだった。
◆さて、出るとは言ったものの、果たして本当に泳げるのか。泳ぐ距離はわずか400メートルだというが、実はこの数年、まともに泳いだ記憶はない。手始めにプールに行ってみると100メートル泳いだら息が切れてしまった。沸き上がった不安に周囲の脅しが追い打ちをかけた。「海はプールと違って波もうねりも潮流もある。背も立たないから、下手すると溺れるぞ」。しかし、意地は男の最大のエネルギー源だ。それからは毎日、酒も飲まずにプールに通い、必死に泳いだ。1週間で400メートルを楽に泳げるようになり、2週間目には1キロを気持ちよく泳げるようになった。海での練習も、なんと、あのドーバー海峡日本人初横断の大貫映子(実は増島の女房)がコーチについて実施した。会場の横浜市八景島・海の公園にも1人で行って曇天の冷たい海で試泳してきた。1か月で体調も技量も完璧に仕上げて「第3回ジャパン・スイムEKIDEN in ヨコハマ」の試合に臨んだのであった。
◆8月5日の大会当日、天候は快晴。酷暑で水温も上がった。「ほら吹きアヒル」と名づけてエントリーしたチームのメンバーは、1区・大貫映子、2区・榎本昌代(37才、ママさんスイマー)、3区・増島達夫、アンカー・不肖わたくしの4人である。大貫は主催者側で大会の顔でもあったが、亭主の応援と弱小チームてこ入れのため出場することになったらしい。号砲一発、52人のスイマーが浜から海のコースに向けて殺到する。大貫は高校大学の水泳部、トライアスロン野郎、ライフセーバーら目の血走った連中を先に行かせて悠々と泳ぎ、真ん中ほどの順位で帰ってきた。続く榎本さんと増島が順位を下げ、いよいよ小生の番となる。前を行く泳者の一団を追って縋り付くと、そこはプールとは違って肉弾戦の場であった。クロールを振り下ろす手で殴る、上からのしかかる、バタ足で頭を叩く……。私も負けじと敵を蹴飛ばし、抜けたと思ったときには不覚にも息が切れていた。それでも必死にペースを守って、結局は5人を抜いてゴールイン。無我夢中と疲労困憊の7分22秒の戦いだった。
◆最終結果は52チーム中33位のていたらく、いや健闘であったが、面白さと悔しさと満足感が残った。目標を持って1か月間、健康的に過ごせたことと、体力への自信を取り戻せたことが何よりの成果であった。このぶんなら、来年以降のスリランカの密林遺跡の探検もまだまだ大丈夫であろう。余勢をかって、2年後の60歳からはマスターズの水泳選手権も目指してやろうか……。おかげさまで、密かにそんなことまで考え始めた昨今の私であります。(岡村隆)
昨日、旧暦の6月24日は豊年祭の綱引きとウスデーク(女性だけの円陣舞踊)がありました。ここ浜比嘉島の比嘉地区は、実は東と西に分かれておりそれぞれ踊りも唄も違い、昔からふたつの集落が競いあってきたんだそうです。ちなみにエイサーも前はふたつに分かれていて踊りを競いあっていたそうですが、全島エイサー大会出場を機にひとつにしたそうで今は東も西もありません。でも、ウスデークはいまだに別なのです。綱引きも東と西で引き合います。ここ数年は西が勝っているそうです。人数が多いからだって(ずるい)。
◆さて綱引きは夕方から始まりました。西と東がそれぞれに、大綱と幟旗とをかかえ村を練り歩きます。綱の先には武者の格好に着飾った子供ふたりが乗り、大綱をおとこたちがかかえ、回りでは女たちがカチャーシー(手踊り)しながら場をもり立てます。中には道化役でかつらをかぶって厚化粧したおばさんやらチョンダラが舞い踊ります。互いが村の中心に集まったところで綱の先を連結し、区長の合図で引っ張るのです。今年も西が勝ちました。私達の東は連敗脱出ならず。この通信をお読みのみなさん、来年は加勢に来てください。
◆そのあとはウスデークの着物に着替え鉢巻きして、いよいよぬん殿内(ノロの在所)から、奉納の踊りに続きウスデークの踊りが始まりました。ぬん殿内を皮切りに五カ所ほどの神屋を回り踊ります。夜でも暑いからおばあたちも大変だろうけど元気です。ぬん殿内で踊ったときは、去年、エイサーをぬん殿内の塀の外から背伸びして見たことを思い出しました。今はぬん殿内の中で自分が踊っているのだ!「ああ島の人の一員になれたなあ」という実感がこみあげました。
◆さて実はウスデークは本来女だけの踊りなのですが、人が少ないので今年は太鼓役におとこ達を入れたのです。ウスデークのかすりの着物を着て帯しめて化粧して、ほうかむりして! それがすごい受けて盛り上がり、男たちも女装が楽しいみたいで大喜び。もちろん外間(ほかま)のお父さんも参加。島の子供たちからは「おかまだ!」と言われてましたが。ウスデークが終ってもまだ終りではありません。
◆今度は村の真ん中(それも十字路のど真ん中!)に舞台を作り、余興大会です。小学生のチョンダラ踊りやかわいい幼児達の「ちんぬくじゅーしー」や、島の踊り達者な人たちが次々に舞台で披露。私は地方(じかた。三線伴奏者)で参加させてもらいました。余興大会が終ったのは夜中12時すぎ。そのままそこで男達の宴会が遅くまで続いていたのはいうまでもなし。さて翌日も夜からウスデークと余興大会があります。さあ昼間はがっちり昼寝しておこうっと。(外間さんは今日は日帰りカヤックツアーのガイドで浮原島に出かけていますが)豊年祭が終わったら8月ウークイのエイサー練習が始まります。当分は島は祭の雰囲気に包まれます。(7月20日 浜比嘉島で 外間晴美)
江本さま。今日、『季刊東北学』が納品されました! 「現代アジアを歩く」という特集は、とても嬉しい仕上がりになりました。こころから深く御礼を申し上げます。懐かしい『あるく・みる・きく』の香りがしています。皆さん御多忙中にも関わらず、本当に寄稿して下さり有り難い気持ちで一杯です。宮本千晴さんや光さんにも贈っておきます!
◆これでやっと、僕がここへやってきたことの意味を確認できたような、そんな喜びを感じています。この後『季刊東北学』は9号「家畜とペット」、10号「アジアの中の日本の狩猟」と続きますが、1年に1号は『あるく・みる・きく』を彷彿とさせるような特集を組んで行きたいと思っています。
◆今、とても興奮をしています。おとなげありませんが、18年前の昭和64年(平成元年)3月30日。当時の観文研の仲間と観文研のオフィスを最後に後にしたとき、中央のテーブルに一輪挿しのバラを置いてきた、あの時抱いた感情に酬いた気がします。ともかく、今後ともお力添えのほど宜しくお願い致します。本当に嬉しいのです。ありがとうございました!(7月31日 田口洋美)
★『季刊東北学』は田口さんが昨年4月教授に着任した山形市の東北芸術工科大学東北文化研究センター発行の学術誌。8月1日発行の「2006年夏第8号」は「現代アジアを歩く」を特集テーマに、賀曽利隆、永瀬忠志、江本嘉伸、岡村隆、松本榮一、西牟田靖、丸山純、森本孝各氏ら地平線会議の報告者たちが執筆している。
『あるく・みる・きく』は、日本観光文化研究所(観文研)の旅と民俗学の月刊機関誌。その質の高さで知られていた。田口氏の言う3月30日は観文研が閉鎖された日をさす。(E)
江本さん、チンギス・ハーン800年で賑やかなモンゴルでニつばかり大兄を思わずにいられないニュースに接しました。
◆7月19日夜エンフバヤル大統領に迎賓館の公邸に私的に呼ばれ1時間半ばかり懇談したのですがその際、彼は明日はバヤンウルギー県に行きタバンボグド(4653m)に登ると言うのです。まさか大統領がモンゴル最高峰に登るとは、と驚きましたが私には猫の手があるから大丈夫、つまり匍っても登れるということでした。
◆ところが、今テレビを見ていたら、エベレストに登頂した登山家のリードで副首相も登り、彼らはやせた雪山の頂上で国旗を振り、なんと馬頭琴を弾いて国歌を合唱していました。大統領がこの登山は個人の内なる勇気を知るものであるとインタビューに答えていたのが印象に残りました。
◆もう一つは昨年の男性登山家の登頂に引き続きモンゴルは本年エベレストに女性登山隊を派遣したのですが残念ながら高さで148メートル、ルートで300メートルを残し下山したそうです。(8月1日 ウランバートル発 花田麿公 97年2月報告者 元モンゴル大使)
地平線報告会で何度か紹介した注目の映画です。近く発売の『岳人』誌にはマッシャー、本多有香さんと監督のニコラス・ヴァニエ氏との対談が載るそうです。東京は12日からテアトルタイムズスクエアほか、大阪では19日からテアトル梅田ほかで。
地平線会議の皆さん、ご無沙汰しています、石川直樹です。昨年はいろいろご心配をおかけして申し訳ありませんでした。報告会にも久しく顔を出していなかったので、近いうちに足を運ぼうと思っています。
◆つい最近、2回ほど岐阜県の徳山村へ行ってきました。徳山村は今年10月にダムの底に沈んでしまう山間の小村です。文化的には岐阜よりも福井県に近く、徳山村に伝わる民話と同じような話が一山越えた福井県のほうで多く受け継がれています。この村で生まれたアマチュア写真家に増山たづ子さんという方がいます。今年3月に88歳で亡くなりましたが、その直前まで徳山村を撮り続け、それらは数冊の写真集となって出版され、何度か展覧会なども開かれています。
◆増山さんは77年から「ピッカリコニカ」と自ら呼ぶコンパクトカメラを手に、徳山ダムの湖底に沈む村の風景や暮らしを撮影し、残された写真は7万枚以上におよびます。地元では「カメラばあちゃん」として皆から親しまれていました。その増山さんと徳山村の風景を写した7、8分の短いドキュメンタリー番組が作られるのですが、そのナビゲーター役を自分が務めることになり、ここ数週間のあいだに二度、村を訪ねたのです。
◆ぼくは増山さんとは面識がありません。ただ、ぼくは彼女の写真集をもっていて、何度もページをめくっているうちに、昔からの知り合いのような気がしていました。増山さんの写真集は、自分が写真集を編んだり、展覧会をするにあたって指針とする支えのようなもので、そこに撮影行為の原点と、目の前にある世界そのものの力を率先して引き受けていく人間の姿勢を感じます。
◆増山さんは民話の語り部としても有名でした。その語り口、あるいは写真集にでてくる文章(キャプション)や文体には、動物と人間が交換可能な神話論的な思考がいとも自然な形であらわれています。彼女はカメラを手にとる前から元々ストーリーテラーだったそうですが、そういったシャーマン的な要素を持ちあわせた人が、カメラを持ったときに果たしてどのような写真を撮るのでしょうか。
◆たとえば、『増山たづ子 徳山村写真全記録』(影書房)という本の中に、「ともだちの木」というタイトルがつけられた見開き二点の風景写真があります。家の前に流れる川とその対岸に生えた木を、夏と冬、同じアングルで撮影して並べたもので、写真にはキャプションが添えられています。そこで増山さんは木に語りかけているのですが、決してポエティックな表現などではなく、自然な形で木と接し、対話していることがよくわかります。
◆彼女は人間と自然の間を自在に行き来している。そういったお年寄りは日本にも世界にももちろんたくさん存在します。ただ、そういった方がカメラという道具をもち、膨大なフィルムに定着させてきたその視線や無意識の現れにぼくはとても惹かれるのです。彼女は徳山村というほんの小さな土地に踏みとどまりながら、そこに世界の在り方や動物と人間の関係やこの世のすべてを見ていたような気がしてなりません。
◆世界中を旅せずとも、ある一部分を突き詰めると、そこから世界のすべてが見えてくる。むしろ部分から全体をとらえることのほうが深くて難しい冒険なのではないかと最近思い始めています。家の玄関を出て見上げた空がすべての空で、そこらに生えている草木に世界のすべてがあるのではないかと。ぼくのなかでは場所へのこだわりは少なくなり、今は偶然出会った目の前にある小さなものにどれだけ深度をもった視線をもち、そこから願わくば大きな世界を見ていこうという気持ちが強くなっています。
◆徳山村は今では暮らしの痕跡はほとんど消され、更地になっています。家を完全に取り壊さないと国から補償金がでないのです。草が生い茂り、当時の面影を残すものは地名が書かれた電信柱しかなくなっていました。移りゆく世界の残滓は、ただただ美しかった。蝉や鈴虫の音が東京に戻った今でも耳の中で反響しています。
◆番組は8月23日23時より、NHK総合の「ゆるナビ」という番組で放映される予定です。もし機会があればご覧ください。7月も終わりだというのに、厳しい暑さが続きますが、どうかお身体ご自愛ください。また皆さんに報告会などでお会いできるのを楽しみにしていますね。(石川直樹)
江本さま (もう残暑っていうのでしょうか? お作法がわかりません…)
暑中御見舞申し上げます。
自信作(??)の「NOJUKER」Tシャツを作ったので、これはぜひとも江本さんに着ていただきたいっ。とお送りしちゃいます。どうか、どうか、捨てないで下さい。
◆報告会にぜんぜん行けないので口惜しいです。8月は夏休みが取れたので、九州に野宿旅行に行って来ようと思います。歩こうと思うのですが、最近体がなまっているのでどうなるか怖いです。真っ黒になって来ます。(加藤千晶『野宿野郎』編集長)
真っ黒な生地に白抜きで「NOJUKER」と書き込んだTシャツとともに葉書で。捨てませんよ、そんな大事なもの! ちょっと暑そうだけど…(E)
江本嘉伸様 盛夏の候、如何お過ごしでしょうか。5年がかりで取材したシール・エミコさんのドキュメンタリーは、7月末に全国ネット版を放送し、インド〜ネパールで命の価値を再確認した彼女の旅の記録者としての役目をようやく果たせました。番組を通じて、彼女の地球一周の動機が「20歳の時に一度は自ら命を捨てようとしたことにある」と知った皆さんは、大変驚かれたと思います。
◆道中、私はエミコさんに「世界を走る理由が『人とふれあいたい』というだけで17年も続くとは思えない。何か別の動機があるのでは?」と何度か問い掛けました。そして「それがないとただの旅番組にしかならない。ジグソーパズルの真ん中のピースが足りない」とも話しました。それは彼女が心の奥に封印していた過去の傷をえぐり出す、残酷な問いになりました。それでも彼女は語りました。負の経験を意味あるものにするために…。
◆2日間かかったカトマンズでの告白から放送までの間、エミコさんは何度か不安を漏らしました。かつて命を粗末にしようとした事実を明かすことで「周囲から白眼視されるのでは」と恐れたのです。しかし懸念は杞憂でした。放送後、近所の人達からは「よく頑張って生きてきたんだね」と感激され、大阪では同じ病気に苦しむ女性に「生きる勇気を貰った」と号泣されました。私の会社にも沢山の共感の声やエールが届いています。旅人シール・エミコの「いのちの旅」は、確かに誰かを救い、そして彼女自身を救ったのです。「過去と初めて向き合えて、背負っていた十字架がやっと外せた…」
◆実は今回、エミコさんが私に全てを明かしてくれたきっかけは、その直前にありました。ネパール中部の山中に、23歳の日本人女性・佐野由美さんが7年前、車のひき逃げで亡くなった現場があり、土砂崩れで流されたと聞いていた慰霊碑を私達は数年ぶりに見つけたのです。彼女は阪神大震災で瓦礫の下から救出され、その後ネパールの貧困層を支えるボランティアに取り組んでいました。私は、彼女の生前から取材し、その後ドキュメンタリー映画『with…若き女性美術作家の生涯』を作って現在も全国自主上映をしていることもあり(注:オフィシャルサイトhttp://www.c-space.co.jp/with/を参照のこと)、異国の山中での再会に涙が止まらなかったのです。そのドキュメンタリストとしてはぶざまな姿を傍らで見ていたエミコさんは、逆に私を信じてくれたのです。写す側が痛みを偶然さらけ出したことが、図らずも家族にも明かしていなかった彼女の人生の核心に迫ることにつながりました。
◆「人の痛みを公表する厳しさと、そこから生まれる可能性」を、ジャーナリズムの先輩として見届けて下さったこと、心から感謝しています。悲しみを勇気に変えて走り続けるエミコさんを追う私の旅も、まだまだ続きます…。(8月5日 榛葉健) (注:榛葉さんはMBSのディレクター。5月号の通信フロント原稿で「しいば」としたのは「しば」が正しい読みなので訂正します=E)
台湾を走ってきました〜! 4分の3周、計971km。もち自転車で☆4年ぶりの自分へのリベンジというか目標達成というか、癌の手術一年後にトライしたときは後遺症で120kmで断念…。今回は満足感いっぱいの帰国です ( o )/。
◆これは台湾の自転車仲間「踏板上的勇者」(日本語で「ペダルの勇者」)に、所属しているJACC日本国際自転車交流協会(日本人初の自転車世界一周を成し遂げた池本元光氏が事務局長)が交流サイクリングとして参加しているもので、舞台は7月の台湾。今年は20周年ということもあり40名以上が盛大にスタートをきりました。全行程を走りきった10数名は私たち女性3名以外、50〜70歳代の年配者。気温32℃の炎天下を連日8〜9時間走行し、台風に直撃されても黙々とペダルを踏む。弱音もはかず励ましあう姿に熱い熱い感動をおぼえました。「エミコさん、これは人生と同じです。晴れの日もあれば雨の日もあります」。雨槍に刺されたセンさん(70代)の笑顔がいつまでも心にやきつきます。あきらめないこと、走り続けること、そして力を合わすことが人間を無限の可能性へと導いてくれたのです。
◆最近、親しい友人にこんなことを言われました。「エミちゃんには敵やライバルがいないのね」と。意識したことがなかったのでビックリしましたが敵やライバルっていうのは自分の心がつくるもの。私のライバルはくじけそうになった自分だけ。だからどんな運命も乗り越えられる(のかもしれない)。人生は生まれてから死ぬまでの旅。これからも色んなことに挑戦していきたいなぁと思っています(ダメもとでね☆)。
◆今回、『第2回 モンベル・チャレンジ・アワード』に選ばれましたが、自分のために必死にやってきたことが誰かに認められたということに正直、驚きと、それによって生き方が報われたような、そんな感動でいっぱいです。[8月5日網戸にカブト虫がとまる奈良の古民家から、エミコ・シールより♪]
■8月8日午後、モンベル渋谷店でシール・エミコさんへのモンベル・チャレンジ・アワード授賞式が賑やかに行なわれた。辰野勇社長からレリーフと100万円相当の賞を受けたエミコさん、スティーブとともにこれまでの旅をスライドで報告し、チベットに入る来年2007年の旅への抱負を語った。
きのう8日午後のシール・エミコさんのモンベル・チャレンジ・アワード授賞式には、モンベル社長の辰野勇、動物写真家の岩合光昭さんらオペル冒険大賞時代の選考委員仲間が顔をそろえ、賀曽利隆、風間深志、山村レイコ、安東浩正の諸氏、山や旅の雑誌の編集者など、あちこちで出会う顔ぶれと話が弾んだ。伊豆の海で初めてカヤックを教えてくれたシーカヤッカー、内田正洋さんとも久々にお会いできた(あれは関野吉晴さんのグレートジャーニー出発前のトレーニングだった)。人と出会う「場」は嬉しい。エミコさんとスティーブの頑張りが本人の受賞だけでなく、そういう場を提供してくれる機会ともなっていることに感謝した。
◆ただし、懇親会になって反省がひとつ。辰野氏の笛の演奏は折りこみ済みだったが、直後賀曽利隆の大声の持ち上げで思わずモンゴル語で「旅行く鳥」を歌ってしまったのだ。確かに私の声は悪くはないかもしれないが、これでは辰野さんの優雅な笛の印象を薄めてしまうのではないか。カソリよ、それくらいのこと気がつけよ、と言いつつ2次会では今度はロシア語で歌うハメになった。うつくしく加齢することは難しい、とつくづくため息をついた渋谷の夜だった。
◆上州、信州、甲斐へ、と移動すること多い8月。土地によっては持参するパソコンのつながりが悪く、締め切りを前にハラハラもした。でも、暑い盛りおやじ世代を中心にいいものを書いてくれた。ありがとう。今号では地平線ポストはすべて「夏便り」とさせてもらった。(8月9日 江本嘉伸)
 |
地平線ビンボロジー事始め
少々おなかが空いても我慢して、食事代を浮かせて1枚のチケットを買ったこと、あるでしょう。旅を続ける為に、日常生活のレベルを必要最小限におさえる。そんな価値観を地平線ビンボロジーと名付けてみました。 「ボクのビンボーは道楽」と言い切るのは久島弘さん。地平線会議黎明期からの仲間で、『何をして食べているのか不明リスト』筆頭。編集者、ライター、イラストレーターと多才でありながら、あえて選択的ビンボー生活実践者であり、旅人です。 極私的不定期刊行の「貧困通信」には、熱狂的なファンがいます。「20代で体験した、タイの少数民族の生活が原点かなあ」と言いつつ、実はH.D.ソローの「森の生活」の影響も大きい。便利過ぎる生活に、動物的な勘で「ヤバイなえ」と感じる感性の持ち主です。 今も裸電球一つのアパートで、カセットコンロで調理する生活。一方で「ビンボー人は健康第一」とうたい、ダシにこったり、高価なナベを買い込む一面も。「要は限られた収入を何に使うかだよね」と久島さん。 恒例の地平線夏休み企画、今回は久島さんのビンボロジー実践報告を基調に、複数のビンボリジストを混じえて、華やかにビンボー自慢をして頂きます。皆さんも、ビンボロジーエピソードを携えて御来場下さい!!
|
| 通信費(2000円)払い込みは郵便振替または報告会の受付でどうぞ 郵便振替 00100-5-115188/加入者名 地平線会議(手数料が70円 かかります) |
|
|
|
|
|
|