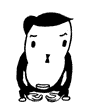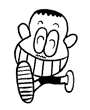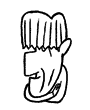■1月の地平線通信・254号のフロント(1ページ目にある巻頭記事)
 火は絶やさざり 青あらし
火は絶やさざり 青あらし
●あけましておめでとう。21世紀第1号の地平線通信です。大晦日は、体重40キロのオオイヌに2キロのチビイヌが加わり3人で年越し蕎麦を食べながら過ごした。師走も押し迫った頃、飼い主予定者の外国転勤で行き所をなくした6ヶ月のチビイヌが我が家にやってきたのだ。
●あちこちの寺の鐘がテレビで鳴りはじめ、20世紀も最後の10分、というところで電話が鳴った。ネパールの奥地ドルポでの四ヶ月の滞在を終え、カザフスタンから帰国した関野吉晴からだった。ドルポの人たちの暮らしはアンデスの雰囲気にそっくり、うんうん、そんな感じだよな、というような話を含めてあれこれ長話するうち、地平線会議にとって歴史的な21世紀に突入していた。そうだ、関野のグレートジャーニーも当初の計画では「2001年1月1日オルドバイ渓谷着」の予定だったっけ。
●「歴史的な」とオーバーな言い方をしたのは、地平線会議は「とりあえず21世紀まで」を漠たる期限目標にしてぼそぼそ始めた活動だからだ。そんなわけで、今号の通信は、地平線会議を発足させた頃、発起人となった世話人たち、中核を担ってきた世話人たちに近況、感想、なんでもよし、ということで書いてもらった。20数年前とまったく変わっていない、地平線会議ならではの顔ぶれなので、そのメッセージを受けてください
●“公約”を果たしたのだから地平線会議は役割をまっとうした、という考えもあるが、せっかく21世紀まで来たのだ、若い顔も多少はふえているのだからもっと先まで行ってみよう、という選択もある。新世紀の始めにあたって、私たちは当分このまま歩き続けることを宣言しよう。
●さて、21世紀を迎えた地平線会議にとって、予期していなかったことがある。1979年9月の第1回地平線報告会以来ずっとお世話になってきたアジア会館が改築されるようなのだ。まだいろいろ手続きを要するらしいのでここだけの話だが、おそらく来年早々には新装に向けてほぼ1年休館になるだろう。20数年続いてきた場所だけにちょっと困ったが、待てよ‥、と考えた。
●昨年は1月に山形県鶴岡で、9月には福島県伊南村でそれぞれ地元の人たちが中心となって地平線報告会をやり、実に面白く盛り上がったではないか。それ以前にも神戸や植村直己冒険館でもアジア会館では得られない日本の現場、普段知り合うことのなかった人々の熱にふれることができて刺激的だったではないか。そうだ、ノマドの思想に学んで地平線会議も漂泊すればいいのだ。
●そんなわけで21世紀は週末をつかってもっと動いてみたい、と思う。無論毎度はムリだが、鶴岡や伊南村がそうだったように、地元にひとり火を持つ人間がいてくれれば可能なことだ。すでに11月頃、長野県青木村で面白いのをやろう、という計画が持ち上がってもいる。毎日登山家、三重県の東浦奈良男さんと一緒に山に登って話を聞くのもいい。この人は59才の定年の日に始めた連続登山を雨が降っても嵐の日も、もう6000日近く続けている。
 ●アジア会館は大事な場だが、いつもいつも座って講師の話を聞いていればいい、というのは正直地平線会議らしくない部分がある。地平線報告会は、報告者が自分を賭して本音の報告をしてくれる点で日本では稀な場であり、聞き手もまた停滞していてはいけないのだと思う。
●アジア会館は大事な場だが、いつもいつも座って講師の話を聞いていればいい、というのは正直地平線会議らしくない部分がある。地平線報告会は、報告者が自分を賭して本音の報告をしてくれる点で日本では稀な場であり、聞き手もまた停滞していてはいけないのだと思う。
ついでながら20世紀最後の報告会、土屋守の話は非常に面白かった。いまやスコッチ専門家、エッセイストとして売りだし中の土屋がインド北部ラダックやザンスカールで過ごした探検部時代の話からどのようにスコットランドと知り合っていったか、話の展開は地平線会議だからこそのものだった。比較的近年に土屋と知り合ったという彼の理解者から「土屋さんのああいう話ぶりははじめて目のあたりにしました」とわざわざ便りを頂いたほどだ。11月の中山嘉太郎報告も(三輪が別紙に書いているように)単に物好きのランナーの話ではなかった。地平線報告会の底力を時に大声で言いたい衝動に駆られる。
●年頭にあたって、駆出し記者時代、縁あって知り合った老コラムニストがくれた一句を紹介する。「心奥に 火は絶やさざり 青あらし」。[江本嘉伸]
|
先月の報告会から(報告会レポート・254)
|
スコッチの民俗学
土屋守
|
|
2000.12.22(金) アジア会館
|
◆いよいよ世紀末も佳境に入り、地平線報告会も今世紀最後となりました。世界中のあらゆるジャンルとあらゆるシーンを報告し続けてきた地平線の二十世紀を締めくくるのは、世界で五本の指に入るウイスキーライター、スコッチ研究家である土屋守さん。スコットランドの魅力と、そしてチベットのザンスカールの旅の報告です。
◆話しは20年前に遡ります。当時学習院大学の探検部員だった土屋さんは、ラダックのチベットの世界にすっかりはまっていました。地平線会議黎明期の1980年、第7回の報告者でもあるのです。舞台はインダス河の支流ザンスカール川。その川が厳冬期に凍りついた時だけ通れるという、氷の回廊チャダル。完全に凍りきれてないので、薄い氷を踏み抜いたらおしまいです。両岸は絶壁に挟まれ、落石のカーンという音が凍てついた谷間に響き、おおかみの遠吠えが聞こえてきます。
◆何年もそんなラダックの世界に通っていた土屋さんですが、藤原新也さんに出会いその手伝いをしたのがきっかけで日本でフォーカス誌の記者になります。当時、週刊誌は最盛期の時代。事件を追いかけ駆けずり回る日々に、土屋さんは記者の醍醐味を感じ、ここでも夢中で仕事にはまり込みます。
◆そこで再び転機が訪れます。結核に倒れて入院。それは三年も前にチベットでかかった結核菌が、今更ながら活動を始めたのです。チベットにいた頃は金と無縁だった土屋さんも、夢中で働いているうちに大金が溜まっていました。結婚し子供までいた土屋さんに、「では家を買いましょう」という奥さんの悪魔のささやきが。好きな記者の仕事ですが、先が見えてきたのも事実。それを契機に新天地を求めて家族と共にイギリスに渡ります。
◆当初英語の学習に励んでいましたが、思っていたより金の減りが早い。そこで現地の邦人向け情報誌の編集に携わるようになります。政治、社会問題、ジャンルを問わず数々の取材を続けてゆくうちに、出会ったのがスコットランド。そこにはイングランドとは全く異なる文化があることに気付かされます。
◆スコットランドといえばキルトのタータンチェックにバグパイプ。アザミの花が咲き誇り、手つかずの自然が残ります。土屋さんの歴史の話はストーンサークルの時代に始まり、謎の民族ピクト、ケルト人、バイキングとの戦い、映画「ブレイブハート」のウィリアム・ウォレスの世界へ。
◆そして話題はいよいよ皆さんお待ちかねのスコッチウイスキーの世界へ。会場にはスコッチの瓶が並べられていて、そのテイスティングを心待ちにしていた人も数多くいたようです。2種類のスコッチが配られます。なにしろパブで飲んでも一杯1500円はくだらないという最高級レベルのスコッチを、2種類づつでみんなに配られるんだから大奮発ですね。しかも世界を代表するウイスキーライターの土屋さんの講義を受けながらテイストできるなんて滅多にあることではありません。100ヶ所以上あるすべての蒸留所を巡った世界で唯一の土屋さんの言葉には重みがあるというものです。会場にはシングルモルトウイスキーの香りが漂います。
◆ウイスキーの樽は外の空気を呼吸しながら生きているといいます。まずは一杯目、モルトのロールスロイス、マッカランは山の中で育ち、花の香りをその中に封じ込めています。二杯目はその対極をいくスコッチで、大西洋の海岸で潮の香りを吸って育ったラフライド。たっぷりのオゾンと海草の香りが染み付いています。
◆ウイスキーは寝かせているうちに10年で20%のアルコール分が樽の外に逃げてゆきますが、その代償として外の香りを封じ込めます。スコットランドの手つかずの自然が、スコッチの香りを育ててゆくのです。その減ったアルコール分を「天使の分け前」と呼ぶそうです。
◆ザンスカールのチベットの世界と、シングルモルトウイスキーのスコットランドの世界。一見、二つの全く異なるテーマのようであり、それだけで判断すると共通点を見つけるのは難しそうです。だけれど週刊誌というジャンルにとらわれない編集者としてのバイタリティーに溢れた土屋さんには、探検部の世界もウイスキーの世界も同じことだったのかもしれません。
◆今、土屋さんはザンスカールを20年ぶりに訪れる企画をNHKと共に進めています。当時は毎年通って、行く度に写真を撮って翌年にプリントしたものをおみやげに持っていきました。20年前にもまた来ると約束したまま足を運べずにいました。当時16歳だった娘も今や36歳。当時のプリントがまるでタイムカプセルの役割を果たしてくれるに違いありません。20年ぶりの約束を果たす旅、どんな物語が土屋さんを待っているのでしょう。それは20世紀と21世紀の架渡しになる旅でもあり、しいては地平線会議の歴史と重なる旅でもあるかもしれません。さてさて、来たるべき新世紀での地平線諸氏の活躍も楽しみですね。[安東浩正]
|
>>> Pole to Pole 2000 >>>
|
|
石川直樹 現地報告 《12月30日、南極点到達!》
|
◆石川直樹ら各国8人の若者から成る「Pole to Pole 2000」チームは、チリ時間の 2000年12月30日23時45分、南極点のスコット・アムンゼン基地に到着、 9か月に及んだ地球縦断の長旅を終えた。
◆12月はじめスキーで歩き出した一行は、時に周囲がまったく見えなくなるホワイトアウト現象やにサスツルギ、そして疲労に悩まされ、助け合いながら南を目指した。
◆とりわけディランの疲れがひどく、皆が彼の橇を引くのを助けた。クリスマス・イブの12月24日には18キロ進んで南緯88度54分地点に到達。「南極でクリスマスを迎える幸運」を祝った。25日17.2キロ進んで南緯89度03分に達した時、石川は「どんよりした、寒いクリスマス。皆疲れてはいるが、気分はいい」と隊のウェブサイトに書いている。26日は21キロ進み、28日19キロ、29日19.6キロと最後の頑張りを見せ、ついに30日21.1キロを踏破して南極点に達した。
◆通信手段が限られるため、南極をスタートしてから本人からのダイアリーは入っていないが、ともかくも新ミレニアムのうちに極点に到達して21世紀の新年を南極点で迎える当初の計画は達成された。
石川直樹 Pole to Pole 2000ホームペーメ(ナオキドットコム) http://p2pnaoki.com/
 |
地平線会議とその前史
向後元彦 |
◆21世紀をむかえた。世界のあちこちからにぎやかな祭りさわぎが聞こえる。だけど、なにがめでたいのだろうか。それは、たんなる時計の針との関係にすぎないのに。なにもしなくても時間はすぎていくものだ。
◆その点、地平線会議のほうはちがう。発足して23年、よくここまでこれたものだと感心する。心からの祝辞をのべたい。
◆そこで思い起こすのは、地平線会議の発足にむけて議論をかさねていた頃のことである。ほくは、この企ての提唱者である江本嘉伸にこういったことを憶えている。(多分、江本は忘れていると思うけど…)。「重要なのは、ながく続けることだね。とりあえず目標を紀元2000年としようか」。
◆江本への言葉は、自分自身に言い聞かせたことでもあった。なぜか。話しはすこし長くなるが、時計の針を40年ほどまえ、1960年代にもどしてみたい。
◆ぼくが東京農大に探検部をつくったのは1961年、そのクラブからヒマラヤにいったのが1962〜63年。そのころの状況は、山の作家で知られる深田久弥が書いているように、まず、海外に出ること自体が一大事業だった。ヒマラヤに行くのも、登頂できるか否かではなく、日本を離れれば8割の成功、といわれた時代である。
◆この状況が劇的に変わったのが1964年。海外渡航が自由化されたのである。それを契機に冒険的な海外の旅にでる若者が急増する(そうした状況を知るには本多勝一の評論『探検の大衆化時代の意味』−朝日ジャーナル1967.1.1、のちに『本多勝一集4・探検部の誕生』に収録−が参考になる)。
◆そんな時代、ぼくもそのひとりだったが、海外での経験をすこしでも日本の社会に還元したいと願った若者たちがいた。大袈裟にいえば、希望ある未来をつくるのは冒険者(もしくは旅人)の役割だと考えた若者たちである。
◆ここで地平線会議とのつながりが出てくる。1960年代末〜70年代中頃に実施された主な活動を列記すると、全国の大学探検部があつまった“探検会議”、日本の僻地の小中学校をまわり、海外経験を子どもたちにつたえた“探検おじさんキャラバン隊”、観文研(日本観光文化研究所、所長宮本常一)に、たむろしていた多くの大学探検部OBなどによる諸々の活動(探検学校、異色な旅の記録のまとめ・ミニ出版)、などがある。
◆だが、残念ながら、それらの活動は線香花火でおわった。古人いわく「継続は力なり」。継続しない活動は線香花火でしかない。そこで冒頭で江本にいった自戒の言葉となったわけだ。
◆23年もの長きにわたり、地平線会議がすばらしい活動がつづけられたのは、むろん、江本や三輪主彦、丸山純、長野亮之介などの中核メンバーや、彼らを支えた多くの人たちの努力によるものである。しかし、地平線会議の「さきがけ」というべき活動を経験した者たち(たとえば、宮本千晴、伊藤幸司、恵谷治、岡村隆、賀曽利隆、関野吉晴など)の参画が地平線会議に貢献したことも、ここに記しておきたい。
◆さて、これから地平線会議はどんな展開をみせてくれるのか。いや、そんな第三者的発言はいけない。ぼくも参画者のひとりとして、がんばろう。
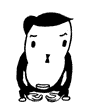 |
グレートジャーニーと地平線会議
関野吉晴
|
◆年末ぎりぎりにカザフスタンから帰国しました。帰ってくるなり、江本さんより「通信の原稿を三日以内に書け。」「ついでに今世紀最初の報告会で話せ。」という指令を受けました。私と地平線会議とは「ハイ、了解しました。」と即答しなければならない、ただならぬ関係にあります。
◆私は1968年に一橋大学に探検部を作りました。先輩もいないので、いきなり主将で、どこに行くにもリーダーでした。試行錯誤しながら活動していましたが、技術を磨くため社会人の山岳会に入り、知識、情報を得るために他大学の探検部を訪れ、合宿に参加させてもらったりしました。その時に、恵谷治、岡村隆、坂野皓、野地耕治、伊藤幸司さんらに世話になりました。その後日本観光文化研究所に出入りし、宮本千晴、向後元彦、向後紀代美、神崎宣武、賀曽利隆、田村真知子、田村善次郎、森本孝、街道憲久、近山雅人さんらと親しくしていただき、指導もしていただきました。
◆1971年からアマゾン通いを続けていましたが、70年代後半に法政大学で、「全国学生探検報告会」という催しが行われました。この時に報告者の一人となったのですが、この催しで知り合った江本嘉伸、森田靖郎さんや宮本千晴、三輪主彦さんを中心にして地平線会議が発足しました。地平線会議の核となった人々は、それ以前に私も知っている人ばかりでした。その後に、丸山純、白根全、長野亮之介、渡辺久樹、淺野哲哉、山田高司といった若い(その当時としては)行動者たちが登場し、刺激を受けました。
◆20年間の南米通いを終えた後、「グレートジャーニー」の足跡を辿る旅をしています。アフリカで誕生した人類は世界じゅうに拡散していきました。その中で、シベリア、アラスカを通り南米最南端まで行った人々が、最も長い旅をした人々でした。(何百世紀もかけてですが)その人たちの旅路を英国人考古学者が「グレートジャーニー」と命名しました。そのルートを動力を使わずに辿る旅を始めて3年目になり、ようやく中央アジアの入り口に到着しました。
◆この間多くの人々の支援をいただきました。支援の中核になったのは団長恵谷治、事務局を野地耕治さんとする「グレートジャーニー応援団」という組織ですが、おもしろいことにこの組織の中核になっている人々と初期の地平線報告会の報告者たちがまったく重なっているのです。ただならぬ関係とはそういうことなのです。中南米、シベリアとたいした事故もなく通って来れたのも、自分のもっている「幸運力」とこれらの人々の支援のおかげだと思っています。
◆実は2001年初頭をアフリカのゴール到着という目安で計画を立てました。マイペースより早いペースで、慌ただしく旅してきたのですが、まだ中央アジアの入り口に入ったばかりです。ゴール到着は来年になるでしょう。パタゴニアの海や南部氷床、ダリエン地峡、ベーリング海峡、極東シベリアなどの難所を通り抜けた時は達成感がありました。ゴールに着いたときも大きな達成感を味わうことが出来ると思います。しかし旅で得られるものは達成感ばかりではありません。旅の醍醐味はやはり途中で出会う人々、自然との交流です。自分の足で歩き。自分の目で見て、話しを聞き、自分の肌で感じ、自分の頭で考える。旅を通して自分の抱えている疑問や謎を解決していく。異なった価値観に触れて、自分を触発する。
◆この醍醐味は30年前に始めてペルーアマゾンに行ったときから味わってきました。来年のゴールも「グレートジャーニー」のゴールであって、私の旅人生の中ではひとつの大きな区切りとなりますが、最終的なゴールではありません。自分の持っている幸運(仲間、時代、境遇などすべてにわたって)が続けば、あと2,30年は生き続けるでしょう生き続ける限り、自分の体力や気力に見合った旅を続けることと思います。大きな飛躍はしないがボチボチと続けていくということに関しては同じ地平線会議と並んで歩いていくことになると思います。
 |
ムシの目と、イワナの目
森田靖郎
|
◆イワナ釣りは“朝まずめ”と“夕まずめ”が勝負である。“まずめ”とは、職漁師の言葉で、一日のうちの黎明な朝と、黄昏の夕暮れの曖昧模糊をした時間帯をいう。平安人は“雀の羽色時”と、文学的だ。この日は、夕まずめに勝負をかけていた。二十世紀の最後の竿を伝説の銀山湖で下ろすことを決めていた。釣果は五人の同行者次第である。中学生五人は重荷だ。五人は不登校、保護観察などいずれも問題児で、親や学校から見放され、嫌々ついて来た。前日は、フライの毛ばり作りから始めた。
「マッチ・ザ・ハッチ」という釣りの言葉がある。イワナが捕食するハッチ(羽化)しているカゲロウに似せて毛ばりを作る。子供たちを川岸に誘い、鬼チョロ(カワゲラ)、キジ(ミミズ)、スナムシ、バッタなどを取りにやらせた。ヒトをナイフで殺せる中学生が生きているムシやミミズに後ずさりする。毛ばりは水中昆虫の生態と関係している。幼虫時代を模しているのがニンフ・フライであり、水底を這っているように動かす。ウエットは、サナギから羽化する時のように水に沈めて誘う。小魚に似たのがストリーマーである。そして、ドライ・フライはアダルト昆虫のように水面に浮かせて使う。水面を飛ぶ虫を読み、水の流れや天候などで数種の毛ばりを結ぶ。雨が近づけば、ドライの他にウエットを付け加える。
ゴルフの前夜、十八ホールの戦略を考えているうちに夜が明けたということは少なからずあった。ゴルフも釣りも記録より記憶のスポーツである。何匹釣ったかでなく、どのフライで、どの季節、いつの時間帯に、どんなキャストで釣ったか。記憶を辿りながら、フライを結ぶのである。子供たちは、フライ結びに飽きて石投げに夢中である。イワナがライズ(水紋を描く)するあたりに石を投げる。
イワナが岸に寄り始めた。もうすぐ雨が近い事の知らせだ。「どうして」。子供が初めて口を開いた。「イワナは十キロ上流の出来事を読む能力があるんだ」。子供たちが集まってきた。「イワナは、岸辺に寄って砂を飲み、体重を重くする」。「・・・・」。「雨で増水した川の水に流されないように水底で構えるんだ」。勝負の日は、やはり朝から雨だった。小雨のなか、フライのキャストには子供たちはやる気だ。キャストは投げるより、鞭を打つようにラインを伸ばすスポーツ感覚である。イワナのいるポイントにまるで生きたムシが落ちるように着水させる。
◆雨上がりの夕まずめ、ようやく川に竿を入れた。増水する急流へ腰が引ける子供たちを引き込んだ。「川に喰らいつけ」「イワナは尻で釣れ」「竿を持ったら邪念を払え」「自分は山川草木の一部であれ」など、釣師に言われたとおりを子供たちに言っていた。
◆帰りのバスは華やいだ。「あのCMはヘンだ」。不登校の子供が口火を切った。Y養蜂場のベテランの蜂師は三万回ミツバチに刺されたと自慢にしているのがウソっぽいという。「プロがどうしてミツバチに刺されるのか」。「ミツバチはハチの一刺しといって、針に返しがついている。毛ばりと同じだ。刺した針を抜くと内臓も出てしまうから、一度刺すと死ぬんだ」。
◆バスが東京に着く頃には、夜が明けていた。「やはり、CMはおかしいよ。師匠、そのプロの爺さんは五十年の労働年数と考えると、一日あたり最低でも三匹のミツバチを殺していることになるよ」。問題児の中学生はいつか私を釣師とよんでいた。一人は夜通し、計算していたに違いない。「養蜂場のひとが三万匹のミツバチを死なせていたなんて、信じられないよ」。子供たちは、ムシの目になって物事を見つめるようになっていた。二十一世紀の竿おろしを雪代(雪解け)の乳頭山と決めている。その頃、子供たちはイワナの目になっているかもしれない。
☆20世紀末の12月15日、『東京チャイニーズ』(講談社)の第三弾『密航列島』(講談社)を出版しました。
 |
チトラル発地平線Webサイト
丸山純
|
◆ピーガッガッガッビーッ――内蔵の小さなスピーカーからモデムがネゴシエートする音が聞こえてきた。やった! ついにインターネットにつながったのだ。
◆ここはチトラル。パキスタン北西辺境州の西北端に位置する、山あいの小さな町。電話している先は、はるか南、インド洋に面した大都会カラチ。ここまでくる道中、何度やってもイスラマバードのアクセスポイントが応答しなくてめげていたのだが、わざわざカラチまでダイヤルしてようやく接続できた。さっそくメールを受信してみる。反応がおそろしく鈍くて、数十通たまっていたメールを落とすのに20分もかかってしまった。さらにNIFTY-Serveを巡回して、メールと地平線HARAPPAを覗く。さすがにこのスピードでは地平線のWebサイト(ホームページ)はほとんど画像が表示されず、画面がフリーズしたままだ。
◆タイムスタンプを見ると、ついさっき送信されたばかりのものもあった。峠が雪で閉ざされる12月から4月、チトラルは陸の孤島となり、飛行機の欠航が続いて2ヵ月近く郵便が届かないこともめずらしくない。それが、こうしてインターネットを使うと、日本にいるのとまったく変わらない感覚で連絡をとりあえる。頭ではわかっているはずなのに、不思議な感動が込み上げてくる。
◆いつものとおり、地平線への問い合わせや出版物の申し込みも何通か混じっていた。きわめつけは地平線へのクレーム。この問題に関する地平線会議としての見解をうかがいたいなどと、ややけんか腰だ。本人の許可を得てWebサイトに掲載している写真なのだが、じつはそのカメラマン氏が撮影したカットだったとのこと。なるほど、笑顔の本人が写っている。しかもこのメール、なんとナイロビから発信されていて、私がすぐに返事をよこさなかったのに怒り、強い調子の第二信まで届いていた。パキスタンの山奥で、ナイロビに向けて釈明とお詫びのメールをせっせと綴る。うーん、これがインターネットなんだな。
◆1990年からパソコン通信をやっていたのに、パソコンとモデムを持ってきたのは、この99年の旅が初めてだった。パキスタンは通信事情がめちゃくちゃ悪い。私たちが滞在するカラーシャ族の村には電気がない。悪路をジープで走らねばならない。極度に乾燥していて土ぼこりがひどい。
◆――などというのは表向きの理由で、じつは日本の日常を持ち込むことに、大きな抵抗があった。カラーシャは文字を持たず、3つの谷に孤立して生き延びてきた少数民族だ。村に入ってカラーシャ語でしゃべりだしたとたん、私のなかにあるスイッチがパチンと切り替わって、日本のことなど、どうでもよくなってしまう。私にとってパキスタンに出かけるのは、こういう非日常の時空にしばらくのあいだ自分を置くということにほかならない。それなりに決意が必要な、けっこう重い行為のつもりである。そこにメールを持ち込んだりしたら、旅が軽くなってしまうのではないか。それが怖かった。
◆それでも今回パソコンを持ってくることにしたのは、チトラルから何度もメールを受け取るようになったからだ。道路や宿泊事情を尋ね、日程の打ち合わせをしたりしているうちに、こうして人と人とがつながる、気軽にコミュニケーションできることのほうが、いまの自分にとって価値のあるように思えてきた。
◆この旅では、メール以外にもデジタルカメラの画像の保存先などとしてパソコン(PowerBook2400c)は活躍してくれたが、いちばんうれしかったのは、妻と開設しているチトラルとカラーシャについてのWebサイトを、ディスクに保存したデータではあったが、テレビを見たこともない山奥の人々に見てもらい、音を聴いてもらえたことだ。黒っぽいプラスチックの箱を開けると、突然広がるマルチメディアの世界。大人も子どもも、きらきら光る目でそれを覗き込む。
◆新しい世界を見てみたいというすさまじい好奇心に、圧倒される思いがする。やっぱり人類はもう後戻りはできないのかな、という気がしてきた。
☆地平線会議のWebサイト(http://www.bekkoame.ne.jp/~jun-mar/)を探すと、この特集の書き手たちについて、いくつか情報が得られると思います。また、ミラーサイト(http://peach.ise.ous.ac.jp/~horizon/)では、全文検索エンジンが稼働中。単語を入れて検索ボタンを押すと、該当するページがヒットします。どうぞご利用ください。
 |
逝った友へ
白根全
|
◆まずは謹賀新年・祝新世紀ですね。自分が世紀をまたいで生きているなんて意識すらしてこなかったから、今更ながらちょっとびっくりです。今世紀の目標:長寿…めざせ、22世紀! とりあえずの希望:仕事納め(昨年分…、トホホ…)なんていうのが現実なのですが、まあ来し方を振り返ってみるのにはいい機会かも知れません。地平線会議と前世紀に出会って以来、怪しい関係は絶えることなく続いてきた訳ですが、そもそもはと思い起こしてみれば、今は亡き友・西野始の記憶につながるのですね。
◆21世紀まで続けようと大層な意気込みで地平線が走り出したちょうどその時期、私は南米の山やらジャングルに入り浸って、放浪と無頼の日々を満喫していました。当時の山の相棒が北大探検部OBで、長野画伯のアラスカ・ユーコン川下りのメンバーだったり、パタゴニアで一緒になったのが農大探検部の南米三大河川縦断航行を終えたばかりのカリスマ植木屋・山田高司だったりと、この業界の狭さには呆れてしまいますが、もう20年近い年月がたっていたというのも驚きですね。世界一周バイクツーリングの途中だった西野に出会ったのはちょうどその後、1982年夏ペルー・リマ伝説の安宿ペンション西海でした。日本に帰国するチケット代まで使い込んでしまった私は、ブラジルに向かう西野と一緒にアンデスを越え、アマゾン源流のロスト・ワールドで砂金掘りに励みながら、怪しく不気味な、それでいて切なくなるほど楽しい日々を共に過ごしていたのでした。
◆数年ぶりに戻った日本で社会復帰に苦労している私のもとに、アフリカに渡った西野から一枚のハガキが舞い込みました。以来、禁断の大地を漂う彼との間に、幾多のラブレターが行き交うこととなりました。もちろんインターネット云々の時代ではなく、アナログ手紙をGPO局留めとか大使館気付でやりとりしながらでしたが、その中から賀曽利氏に原稿売り込みをお願いしたり、加藤大幸氏にアフリカ情報を教えてもらったりと、いつの間にか地平線会議とのつながりはごく自然に生まれていたように思います。
◆バイク旅から帰国してすぐシンガポールに引っ越した彼とは、まだ旅をしているような感覚でずっと付き合い続けていました。お互い離れているのが常でしたが、よけいな説明なしに何でもわかり合えるホットでクールな関係だった。突然の航空機事故で3年前、唐突に姿をくらました時の衝撃と辛さは、とても言葉で表せるものではありません。
◆前世紀最後の3年間は、どこに行っても彼の不在の意味をさがす日々でした。グレートジャーニーの偵察やカーニバル通いなど旅の合間をぬって、彼の思い出を集めた1冊の文集を作りました。それは胸の詰まるような苦しい作業でしたが、書き残したものを広げながら彼は何を思っていたのか、自分にとって彼の存在は何だったのか、それまで以上に彼のことを考える時間を持つことができたと思います。彼だけではなく、早世された田村真知子さん、斉藤実氏、広島三朗氏ほか、地平線会議にとってかけがいのない大切な人々の思い出は、世紀が移り代わっても忘れることはできません。[白根全]
(なお、文集『西野始』はまだ若干在庫があります。彼を知る人、その足跡に興味のある人で文集を希望される方は白根全までご連絡下さい。e-mail : )
 |
時間の流れについて
伊藤幸司
|
◆たしか1年前には「Y2K」という名のハルマゲドンにおびえて右往左往していたんですよね。20世紀を代表する発明品のコンピューターが単に1900年代を下2桁で表したというささやかな節約手法によって、千年紀につまづくというかなり印象的な事件でした。
◆千年紀のそういう構造的なハプニングがあったおかげで、百年紀のほうの世紀末はずいぶんと気分的なものになってしまったという印象があるんですが、どうでしょうか。千年紀と百年紀のどちらが偉いかといえば、もちろん千年紀のほうでしょうしね。
◆その千年紀末にアメリカ人が主宰したインターネット・サロンで生み出された『2000年間で最大の発明は何か』という本の翻訳者で元百科事典編集者のTさんが、百年紀の秋にぼくに電話をかけてきました。アメリカに永く住んでいた従兄弟が「ナショナルジオグラフィック」をもらってくれる人を探しているんだけど、いるだろうか?
◆地平線会議の神経中枢となっているMさんに伝えたら、すぐに、還暦になって新聞記者をやめたばかりという作家のYさんが名乗り出たようでした。
◆Yさんの山小屋が黄色の背表紙で埋まってアメリカの田舎屋のようになるのかと思っていたら、世紀末もギリギリになってその持ち主が「もういい、自分で処理する」と怒りだしたというのです。
◆ぼくは当事者ではないし皆さんから事情聴取したわけでもないので全部憶測で書きますが、63歳の翻訳家が60歳の作家とようやく連絡を取りあって、いよいよ本を動かそうかという段になったときに「そんじゃあ、もういい」と76歳とかの持ち主がヘソを曲げていたとか。
◆だれが悪かったとかいうことではなくて、60代の元気盛りの人たちと、完全にリタイアしていよいよ終の住処に引き下がろうとしている人との間の時間の流れがまったく違っていたということのようです。
◆還暦を過ぎたはるかかなたの高齢者の人々の世界ですら、1年は同じ1年ではないのですから、十人十色というのはまさに時間のこと。地理的差異が時間軸の違いを生み、世代の差が時間流量の違いとなり、生活様式が時間をどんどん個別化していきます。
◆5年ほど前にぼくの周囲にいた中高年の人たちとの間で、一種の終身契約を結んで山歩きを始めました。多い人は年に20回以上という頻度で一緒に山を歩きながら5年もたつと、何本もの時間軸が山でひとつに束ねられているという感慨にひたることがあります。見当でいえば、65歳あたりを境にして、人の時間軸は急激に折れ曲がっていくような気がします。ぼくも還暦に向かって片手の指で数えられる年になっちゃった――という複雑な気持ちを込めて――新しい年を、おめでとうございます。
 |
80才ジジーライダーへの道
賀曽利隆
|
◆『世界を駆けるゾ! 40代編下巻』(フィールド出版)が出ました。『20代編』からはじまった『世界を駆けるゾ!』シリーズですが、これで一応の完結。自分の実年に、 20世紀中に追いつくことができました。『20代編』、『30代編』、『40代編上下巻』の4冊の本で“カソリの30年旅”を書いてみました。
◆『世界を駆けるゾ! 20代編』が出たのは1999年7月のことです。それから1年余の間に『中年ライダーのすすめ』(平凡社)、『日本一周バイク旅4万キロ(西日本編)』、『日本一周バイク旅4万キロ(東日本編)』(ともに昭文社)、『旅の鉄人 カソリの激走30年』(JTB)と全部で8冊の本を出すことができました。まだの方、ぜひ、ぜひとも8冊全部をお読み下さ〜い。
◆20世紀から21世紀へと移り変わろうとしている今は、自分の来た道を回顧し、これから行こうとしている道を展望するのにちょうどいい時期だと思います。峠道でいえば、九十九折の登り坂を登りきって峠の頂上にさしかかったようなもの。そこからは、自分がこれから下っていこうとしている道がはっきりと見ることができます。
◆「生涯旅人!」をモットーとしているぼくですが、我が旅人生は今から30年余前の1968年に始まりました。カソリ、20歳の春のことでした。約2年をかけてバイクでの「アフリカ一周」を成しとげました。22歳になって日本に帰ってきたぼくは、「よーし、これからは徹底的に世界を駆けるゾ!」と固い決心をしました。カソリ、“22歳の決心”。世界を駆けめぐること、もうそれ以外の人生など、まったく考えられないほどの思い込みの強さでした。
◆20世紀から21世紀に移り変わるこの大きな変わり目は、我が旅人生のまさに折り返し地点だと思っています。あともう30年余、「よーし、これからも徹底的に世界を駆けるゾ!」と固い決心をしています。これがカソリの“53歳の決心”なのです。
◆日本の近隣諸国はどこもバイクで行くのはきわめて難しいのですが、2000年にはその壁をブチ破って「サハリン縦断」と「韓国一周」を成しとげました。ですから今度はその第3弾、那覇からフェリーでバイクともども基隆に渡り、「台湾一周」ができたら‥‥と願っています。中国もバイクの持ち込みはきわめて難しい国ですが、大阪からフェリーで上海に渡り、「中国一周」ができたら‥‥と夢見ています。
◆ぼくの夢は限りなく飛んでいきます。ほんとうは50歳のときにやりたかったことですが、30年目の「アフリカ縦断」。ケープタウンを出発点にしてアフリカ大陸を縦断し、ロンドンをゴールにするというもの。さらにロンドンからは「モスクワ→ウラジオストック」の「ロシア横断」をぜひともやってみたいのです。もう20年も前から「ロシア横断」はやるゾ、やるゾ!といっておきながら、いまだにできないままでいます。「雲南周遊」も、「インド一周」も、「シンガポール→カルカッタ」も‥‥。
◆すべてはこれからです。21世紀での話です。今、こうして足を突っ込んだ21世紀がすごく楽しみです。ぼくは80のジジーになるまではバイクに乗って世界を駆けるつもりでいます。さきほどの『世界を駆けるゾ!』シリーズも、10年後には『50代編』が、20年後には『60代編』が、30年後には『70代編』が出ますので、みなさん、ぜひとも末ながいおつきあいのほど、よろしくお願いします。
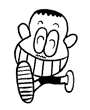 |
勘違い! 21世紀
三輪主彦
|
◆正月は実業団駅伝、箱根駅伝で「アッ」いう間に終わった。3日はテレビを見ながら満員電車並のゴール付近をウロウロした。東海道はとぎれることない人々であふれ、2日間で200万人が応援したという。正月でヒマ人が多いとはいえ、すごい。昨年は高橋尚子の走りで日本中が熱くなった。本当に日本人はマラソンや駅伝が好きなんだ。
◆しかし待てよ。日本人は本当に走ることが好きなんだろうか。私の周りをみるかぎり、テレビ観戦が好きなだけで、走るのなんかまっぴらという人がほとんどだ。高校生は「かったるそう」というだけで、テレビ観戦さえ興味を示さない。正月駅伝はヒマを持て余すおじさんのためにテレビが作ってくれた「筋書きのない」ドラマなんだ。
それに踊らされてテレビにかじりついてたなんて ・ ・�・、例年のように自分で東海道を走ってればよかった。私は地平線ノー天気三人組の賀曽利、江本と同様に、自分の面白いことは他の人も面白いはずだと勘違いしていた。マラソン好きは「走り好き」とは限らない。
◆昨年11月の地平線報告者は西安からウルムチまでシルクロード2800キロを一人荷物を担いで走った中山嘉太郎さんだった。シドニーのマラソン人気もあったので、「走り」と「旅」、さらにシルクロードが組み合った報告会にはさぞや人が集まるだろうと期待した。
しかし中山さんの仲間のランナー以外はごく少数だった。私は、走ることの哲学的楽しさ、さらに「旅」の手段としての「走り」について吹聴してきた。もうそろそろ「走り旅」も世の中の認知を受けたと勘違いしていた。走りやさんの世界では「走り旅」はすぐに受け入れられたが、どうも「山や」さん、「旅や」さん達には印象が悪い。「駆け足の旅」ってのは軽蔑の対象らしい。しかし私の「走り旅」は、ゼイゼイ、ハアハア走るだけではない。ほとんどの時間のんびりテレテレ走っているのだ。
自転車の世界にスピードを競うケイリンやツールドフランスもあれば、急がないチャリンコ族の旅があるように、テレテレ族の走り旅があってもいい。走ったからこそ、見え、考えられる世界だってあるのだ。当の中山さんは3月までの南米縦横断の走り旅の途中だ。
◆20世紀は、個人的な情熱に根ざしたおもしろく個性的な旅が讃美された。しかしこのところ世の中、保守的な現状維持と原状回復の思潮が、新たな変革や個性を押しつぶしているかに見える。若者達の閉塞感はその表れだ。多様化した価値観に慣れない人々は、自分の価値観を捨て、強力なリーダーや国家による画一的価値観を求めるようになっている。大いなる時代錯誤だ。21世紀は画一化とは全く逆の動きをする時代なのだから。
我田引水ではあるが、これまでの歴史の中で、中山さんのような面白く、バカバカしい冒険精神が新しい時代を切り開いてきた。若者の新鮮な試みを押しつぶす方にまわらず、一緒に楽しめるかどうか、それがわが地平線会議の役割ではないか。ノー天気でもこれぐらいは考えている。でもこれも勘違いかも!
 |
入る者は拒まず 去る者は追わず
惠谷治
|
◆地平線会議の創設当時、私が一番こだわったのは組織形態だった。
◆地平線会議に参加している顔触れを見ると、探検部出身者が多かったが、現在の代表世話人の江本嘉伸さんのように山岳部出身者や、部活動とは無関係の人びともいた。そうした依って立つ場が違う人びとが、気軽に集える組織が、果たして作れるのだろうか?
◆地平線会議に対してと同様、それは自分自身への問いかけでもあった。大学探検部時代に中途で退部した部員が探検部にいたことを口にするだけでも許せなかったり、他大学の探検部に強烈な競争意識を抱いていたほど、現役時代の私は先鋭的な意識が強かったからだ。しかし、大学を出て5、6年が過ぎており、現役当時の過激な気分は和らいでいたものの、他大学出身者や探検部以外の人びとと、どんな活動ができるのか、私は不安だった。
◆そして、私が一番懸念したのは、地平線会議を探検部的な存在感のある強力な組織にすれば、必ず組織分裂が起きるということであり、そうした愚行はなんとしてでも避けたかった。そうでなければ、新たに組織を作る必要性はないと感じたからである。何回かの世話人会議で老練な向後元彦さんや宮本千晴さんなどに私の懸念をぶつけると、彼らは辛抱強く私の主張を聞いてくれ、いつの間にか彼らの説明で私は納得していたのだった。
◆地平線会議の最大の活動は、探検や冒険、旅などの行動を記録するということで一致しており、組織形態は会員制など閉鎖的な集いにはせず、世話人(中核)だけを決めて、「入る者は拒まず、去る者は追わず」というまったくオープンの組織にすることになった。そうした柔軟な組織にした結果、月1回の「地平線通信」の発送、「地平線報告会」の開催と年1回の報告書『地平線から』の発行などの費用の捻出にも苦労し、すべての活動は手弁当となった。その後に「地平線賞」や「地平線ポスト」(ちなみに、このコピーは私の命名です!)などが設けられた。そうした活動には浮き沈みがあったが、多数のボランティアに支えられて、今日まで続いているのは驚異というべきだろう。
◆「去る者は追わず」という原則のお陰で、私自身はすでに10年以上も地平線会議の具体的な活動に参加しておらず、心苦しく思っている。その代わりと言っては失礼かも知れないが、地平線会議で親しくなった仲間たちとともに「関野吉晴のグレート・ジャーニー」の応援に力を注いでいる。地平線会議で培った、いわば「インター探検部」の発想が、グレート・ジャーニーの応援団の原点となっている。
◆地平線会議の歩みを振り返るとき、当初は世話人の代表を持ち回りにしていたが、ある時点からもっとも活動に熱心な江本さんを代表世話人に決めたことが、地平線会議を今日まで継続できた秘策だったと私は考える。どんな活動でも意欲的な先導者(前衛)が必要であり、地平線会議の場合はそれが「代表世話人」であり、江本さんの情熱が地平線会議の原動力となっていることは疑いない。その意味で、私は「関野吉晴のグレート・ジャーニー」の応援団長を引き受けたのだった。
◆私たちのような当初の世話人が一線から離れ、世代交代していることも地平線会議が長続きしている一因だろう。当初、私が懸念した仲間割れや組織分裂なども起こらず、稀にみるユニークな組織が生き続けている。今では、個人的には地平線通信の文面で名前しか知らない多くの人びとが、21世紀の地平線会議のために新たな地平を切り拓いてくれることを切に願う。
 |
地平線仲間をテーマに大宅壮一賞を!
岡村隆
|
◆小川渉という人物がいる。早大探検部で恵谷治と同期だった男で、1968年の早大ナイル河全域踏査隊に参加し、副隊長だった伊藤幸司さんと共にナイル河の最長源流の水源地点を発見した実績を持つ。
私とは学校違いの同期の間柄で、私が最初のモルディブ遠征から帰って法大探検部の主将になったとき小川は早大探検部の幹事長になり、ともに向後元彦さんが提唱した「動アメーバ運動」(アムカス)に加わった。これは地平線会議の前身とも言うべきもので、詳しくは向後さん自身が書かれていると思うが、ともあれ日本観光文化研究所(宮本常一所長)に間借りしたそのアムカスで、小川や私は宮本千晴、三輪主彦、賀曽利隆といった先輩方に揉まれて育ったのだった。
◆大学卒業後、小川は自転車メーカーの最大手に就職して、しばらく私たちの前から姿を消した。いつまでも「生き方」としての旅や探検にこだわってやくざな暮らしを続ける私たちと違って、きっぱりカタギになったわけだったが、その実、やくざ根性は捨てきれなかったらしく、裏では可愛がってもらった深田久弥さんの『日本百名山』のひそみに倣い、『日本百名瀑』を編纂するため日本中の滝巡りを続けてもいた。
その小川渉が、21年勤めた会社を突然辞めたのは6年前のことである。「やっぱりサラリーマンの片手間仕事では『百名瀑』は作れない」と覚ったらしく、それからは月に20日を滝巡りの山旅に当てる生活に入った。ところが1年ほどすると、今度は「宮崎の綾町に移住するから」と、宮崎県出身の私に仁義を切りに来た。綾町といえば、日本一の照葉樹林を背景に、前町長が提唱した町ぐるみの自然農法で知られるところ。そこへ女房子供だけでなく生粋の東京人だった父母も引き連れて移り住み、自然食のパン屋を開いて暮らすのだという。
◆驚いているうちに本当に移住してしまった小川は、折からの「田舎暮らし」ブームのなか、しばらくは「エリートサラリーマンの転身」といった形でマスコミにも登場したが、次にはまた新たな姿で私の前に現れた。綾町の照葉樹林を横切って高圧送電線を通す計画が浮上したため、自然保護の立場からそれに反対する人々のリーダーとして躍り出たのだ。
◆この送電線敷設計画は、宮崎県串間市に計画されていた(現在もくすぶっている)原発建設を前提とするもので、自然豊かな深山を削る揚水ダムの建設を伴い、さらなる自然破壊と原発そのものの危険性とがセットになった計画でもある。綾町は町是であった自然重視の姿勢から、当初はこの送電線敷設に反対していたが、町長が代わって以来、その姿勢に動揺を見せ、昨年はついに現町長が九州電力による環境アセスメントの受け入れを表明するなど、小川たちの危機感を煽る事態が出来している。
それに対して小川は昨秋、揚水ダム反対の全国フォーラムを綾町に招致し、政界の紋次郎こと中村敦夫参議院議員を講演に招くなどして、必死の巻き返しに出ているのが現状である。
◆環境アセスの結果が出て、送電線敷設の可否が決まるまで残り数カ月。私は、自分の編集する雑誌、月刊『望星』で、小川の活動を軸にその経緯を追い続けている。これはひとえに小川渉という人物が面白いからだが、それだけではない。綾町の旧住民と新住民の意識の違い、著名な前町長の後を継いだ新町長の複雑な想い、都市と農村の格差、開発と保護をめぐる日本の新思潮の行方など、哲学や文学にかかわる普遍的なテーマもそこには集約されているのだ。
私としてはもっと多角的にこの問題を追いたいので、地平線の仲間で誰か本気でルポしてくれる人はいないだろうか。地平線の古い仲間の生き方をテーマに、地平線仲間の雑誌で大宅壮一賞を狙うというのも面白いと思うのだが……。
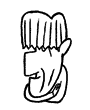 |
個人的なむかしばなし
宮本千晴
|
◆地平線会議の活動がまだ続いている。えらい人たちだ、と思う。
◆はじめるとき、10年は続けないといかん話だからなあ‥‥といったときの気分を思いだす。いや、今世紀中は続けるよ、と、江本嘉伸が口ごもるようにいった。
◆ぼくはすでに疲れていて、気が重かった。いまさら何をやればよいのか、ほんとのところ分からなかったし、いずれにせよ自分は2、3年もすれば飽きてしまうと知っていたからだ。だとすれば、これから声をかけていこうとする人たちに対してこんな失礼な話はない。江本以外はみんな多かれ少なかれ疲れていて、口が重かった。
◆いいです、ぼくが一年間集会をやります。賀曾利隆が振り切るようにいって結論が出た。伊藤幸司も、地平線(電話)放送を丸山純・青柳正一とやってみますと。岡村隆はすでに探検史料収集をやるといっており、もっとも疲れる持続のための裏方を三輪主彦がまた引き受けてくれるという。
◆疲れたのはすでにいろいろあったからだ。
◆ぼくにとって最初は「日本探検協会」だった。たとえばヒマラヤを見ると、戦前からずっと時を待っていた第一世代の探検家や登山家たち、それに加わるには若すぎたが、ずば抜けた個性で孤軍奮闘して自分たちだけの道を開いた第二世代の人たちがいる。そしてぼくらは60年代のはじめから運よく出られた若い有象無象の走り、第三世代だ。若かったから異世界の体験に心身をゆさぷられ、若くて有象無象だったから、みな友だちになり、仲間になった。で、64年の暮れだったか、早稲田の探検部の肝入りで大隈会館で旗揚げをやったわけだ。
◆旗はあげたが、それだけだった。集まっただけでは力は生まれない。で、探検をいうならもっと足元を見ろ、日々を研ぎ澄ませ、と原理主義に向かう人もいたし、いや、とにかく行動だと、未踏であった南極大陸の最高峰ビンソンマッシフに夢中になる連中もいた。たくまずして9つの大学のOBたちが参加していたところに時代があった。向後元彦や宮木靖昌や川井康男やぼくはこの組だった。だが力不足はいかんともしがたく、当然のようにアメリカのチームに先を越されて、ぼくらのは探検ごっこだったと恥じる。メンバーはそれぞれの思う修行に散っていった。
◆ぼくの修行は、旅にわが身を掛けようという多くの若い人たちとの日本観光文化研究所(観文研)の設立と運営、『あるくみるきく』の刊行、それから街道憲久や磯野哲志君ら東海大学極地研究会の若者たちと進めたカナダ北極圏の探検行と友人たちの遭難だった。
◆観文研はきたるべき旅のありようを探るクラブをつくるという課題を与えられ、向後を迎えて託した。向後は反体制風の吹き荒れる全国の大学探検部を訪ねて歩き、法政大学の山小屋で白馬探検会議を開く。そして観文研の担当分として「AMKAS/あむかす(あるくみるきくアメーバ集団)」なるサロンを開き、伊藤幸司、小川渉、岡村隆、武蔵野良治その他の若き探検家たちに手伝ってもらいながら、探検的な旅のための情報を収集し、刊行し、探検学校や野外集会によって老若の旅好きのひとたちとさまざまな旅を試みた。観文研もあむかすも、いまから見てもちょっとした梁山泊で、三輪主彦も若き日の賀曾利隆も関野吉晴もここのスプリングの出たソファに座っていた。
◆しかしその先が難しい。向後が去り、挑戦も色あせた。若者たちも生活に直面する歳になり、観文研の環境も変わっていた。そして地味にしぼった仕事は面白みに欠けた。
◆それから、東京のいくつかの大学の探検部の人たちが新しく探検会議を開き、かつて山岳部のサブリーダーとして知っていた江本が記者として興味を持って現れた。学生たちの動きには期待を持たなかったが、江本のしつこさには無視しきれない可能性があった。観文研で挫折したものを、野生に育てたいなら、資金的な支援のまったくない野に放つしかない。それでつぶれるならそれでよし。生き残るなら、やるに値したことだったのだ。
◆「地平線会議」はぼくのこうした小賢しい思いをはるかに越えて、生きつづけている。生かしてきた人たちが、やはりすごい。
●まず、多忙なさ中、期日を守って原稿書いてくれた世話人たちに感謝。いつもながらいざという時には相当なムリも聞いてくれる同志の存在がありがたい。今回はスペースの都合で書き手を限定せざるを得なかった。そして、長年、年報や通信の制作、発送、販売、報告会の受け付けや準備、その他黙って陰で汗をかいてくれた人たちに深く感謝。いちいち名はあげないが、地平線会議はこれまでもこれからも、そういう人たちの力で成り立っている。[E]
■僕がはじめて通信のイラストを描いたのは、第62回報告会。報告者は高野久恵さん。当時は未だハガキ一枚で、報告者の紹介だけの通信。それまでの紙面は文字が主体で、時々カットがあったかな。当時地平線会議に絵を提供していたのは、青柳清子さん、久島弘さん、浅野哲哉さん、それに江本さんや三輪さんも。江本さんから「すきにやっていいよ」と言われたものの、取材力も文章力もない。結構広いハガキスペースをうめるべくイラスト導入を決行し、今に続きます。そしてそれが僕のイラストレーター修行の第一歩でした。多謝。[長野亮之介]
◆大学生活最後の夏のことです。高校時代の担任で、地学部の顧問でもあった三輪主彦さんに連れられて、四谷の喫茶店「オハラ??」へ行きました。そこには江本嘉伸さんをはじめ、今月号に寄稿してくれたほとんどの人たちがいて、当時学生だった丸山純さんと私を除けば、全員が30歳代でした。探検部にも山岳部にも所属していなかった私には、わけの分からないことをいうオジサンたちに見えましたが、何度目かの会合で、地球を這いずり回る人たちのネットワークを作ろうとしていることがわかりました。そのときから地平線会議に関わりつづけ、すでに当時の彼らの年齢をはるかに越えてしまいました。地平線会議が産まれた「オハラ」はもうなくなりましたが、私は相変わらず地平線会議の使いっ走りをしています。[武田力]
■今月の地平線報告会の案内(絵:長野亮之介)
 |
グレートジャーニー
ユーラシア蹄の道行
(ひづめのみちゆき)
1/26(金) 18:30〜21:00
January 2001
¥500
アジア会館(3402-6111)
御存知ドクトル関野吉晴の、グレートジャーニー地平線報告会第3弾は、ユーラシア紀行。'99〜'00の旅はベーリング海を渡った極東シベリアからスタート。モンゴル、チベット、ネパールヒマラヤと進みます。
今回の旅はトナカイ、馬、ラクダ、羊、ヤク……と、遊牧の民を訪ねる機会が多く、旅の足にも動物が活躍しました。特にモンゴルのラクダキャラバン、ヒマラヤのドルポ地域の農牧民の暮らしは、関野さんに深い感銘を与えました。
「ドルポはアンデスに似てるんだよ。信仰に生きる人々なんだよね」という関野さんに、地平線会議21世紀最初の報告会の幕を開けてもらいます。 |
通信費(2000円)払い込みは郵便振替または報告会の受付でどうぞ
郵便振替 00100-5-115188/加入者名 地平線会議(手数料が70円 かかります)
|
 |

|
|
Jump to Home
|
Top of this Section
|
 火は絶やさざり 青あらし
火は絶やさざり 青あらし ●アジア会館は大事な場だが、いつもいつも座って講師の話を聞いていればいい、というのは正直地平線会議らしくない部分がある。地平線報告会は、報告者が自分を賭して本音の報告をしてくれる点で日本では稀な場であり、聞き手もまた停滞していてはいけないのだと思う。
●アジア会館は大事な場だが、いつもいつも座って講師の話を聞いていればいい、というのは正直地平線会議らしくない部分がある。地平線報告会は、報告者が自分を賭して本音の報告をしてくれる点で日本では稀な場であり、聞き手もまた停滞していてはいけないのだと思う。