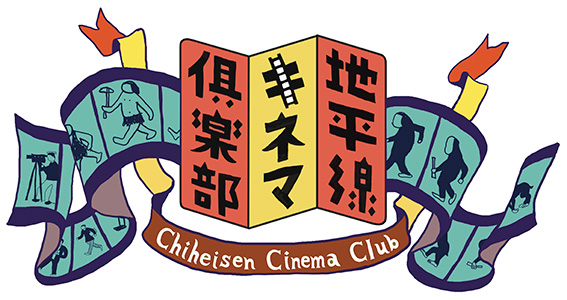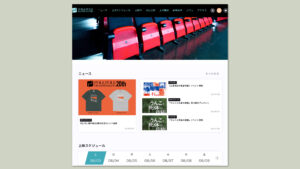笹谷監督からいただいた公式パンフレットから、「『馬ありて』の旅」という監督本人が書いた文章を紹介します。この不思議な作品がどのような経緯で作られていったのか、その一端が垣間見られるような気がします。

「馬ありて」の旅
監督 笹谷遼平
なぜ馬を撮ったのかとよく聞かれるので、ここに記したいと思う。私は「放浪記」などで有名な林芙美子が昔から好きで、特に「蒼馬を見たり」という初期の詩に強く惹かれていた。
(略)
古里の厩は遠く去つた
そして今は
父の顔
母の顔が
まざまざと浮かんで来る
やつぱり私を愛してくれたのは
古里の風景の中に
細々と生きてゐる老いたる父母と
古ぼけた厩の
老いた蒼馬だつた。
(略)
(林芙美子著「蒼馬を見たり」より抜粋)
馬と縁がある人生ではなかったが、私は馬がいる日本の田舎の原風景に憧憬の念を抱き、また馬には普遍的な美しさがあると思っていた。そして2011年。東日本大震災、福島第一原発事故に、誰しもが衝撃を受けた。私もそうだった。一瞬にして人間や、動物、植物、土地、そして営みが飲み込まれ、放射能が空に舞い、踏み込んではいけない場所が誕生した。戦争を経験していない世代の私は「人間は開けてはならないパンドラの箱を既に開けていた」と、その時初めて思い知らされた。
災害、人災によりあらゆるものが壊された。しかし、本当に全てが無になったのだろうか。血脈のように流れている人間の営み、土地の記憶は失われるのだろうか。その是非を知りたく、私はいつしか「この列島の古層の記憶、そして命を撮りたい」と考えるようになった。そんな思いと、馬への憧憬が重なり、この映画がはじまった。

2013年1月、私は北海道帯広市のばんえい競馬場に立っていた。マイナス25度、一番寒さが厳しい夜明け前、午前7時頃。マフラーで口を塞ぐと、息が目にかかり、まつ毛が凍る。体中の温度が一瞬にして奪われる。しかし、私の眼前では馬がソリをひき、ばんえい競馬のレースに向けた訓練をしていた。夜明けの薄明かりの中に馬の汗と熱い息が煙になり、もうもうと辺り一面に立ち込めている。それらはすぐに氷となり、馬の体毛に張り付く。人々はその氷をアルミの器具で引っ掻き落とす。ソリがひかれる独特の金属音が間断なく響くなか、私は呆然とした。ここにいる全ての馬や人々にとっては日課ではあるが、私は眼に映るもの全てに厳しさを感じた。このような世界があったのかと。そして初めて見る二メートルを超える大きな馬「重種馬」の迫力に圧倒された。
馬といえばサラブレッドのようなしなやかさ、速さ、格好よさを想像するが、体重約1トンの重種馬にはそんな要素はなかった。一歩一歩ずっしりと歩いていく力強さに惹かれた。そしてこの重種馬は北海道開拓の象徴でもあった。明治時代初期、本州の人間が次々と北海道に入り、馬がこの大地の原野を切り開き、広大な田畑に変えていったのだ。馬は、北海道にもともと暮らしていたアイヌの人々にとっては大きな脅威だったに違いない。しかし、本州の人間にとっては開拓の誇りであった。それが現代につながり競馬になった。コインの裏表である。映画に登場する戸田富治氏は私に「笹谷くん、僕は君をなんだか旧知の友人のように思っている。だから、表面的な映画は作らないで欲しい」と語った。この言葉に背中を押されてか、私は北海道だけでなく、馬をもっと広く知りたいと思うようになっていた。帯広を始点に、馬の旅は始まり、私は日本の固有種(*在来馬)のいる鹿児島県トカラ列島、長野県木曽町を訪れ、私が馬に何を求めていたのか、この映画の終着点は何なのか、次第に輪郭が見えてきた。私は「古来から続いてきた馬と人間の営み」に出会いたかったのだ。

何度も通った土地もあれば、一度しか行っていない土地もある。各地で映画の断片を拾い集めた。その中でも一番印象的だったのは岩手県遠野市である。柳田國男の「遠野物語」で有名なこの地にて、私は現代に続く日本の古層に出会えた。見方芳勝氏の「馬搬」という昔ながら仕事は、馬と人間が共生していた時代と現代とが地続きであることを教えてくれた。
そして遠野にて、忘れられない体験がある。映画の材料が概ね揃った時、どうしても撮りたいものがあった。それは馬が生まれる瞬間だった。一度目は遠野のある牧場で2泊し待ったが生まれる瞬間には出会えなかった。二度目は4泊したがこれもまたダメだった(すべて車中泊)。馬の赤子は夜中に生まれることが多いので、一晩中10分に一度産気づいていないか馬房の様子を覗く私。母馬もたまったものではない。ストレスがかかっていたのだろう。
三度目に訪れた遠野のある牧場の主人・谷渕隆朗氏は、私を見つめて言った。「君は馬に触れたことがないだろう」と。私はドキッとした。それまで色んな場所を巡り、馬を撮ってきた自負のようなものがあった。しかし、私は軽い乗馬以外に本当の意味で馬と触れ合ったことがなかった。撮影者であり、傍観者だったのだ。谷渕氏は一瞬にしてそれを見抜いた。住居と繋がっている馬房の前で「撮るのはいいけど、うちの馬・キキとコミュニケーションをとってからにしてほしい。これでお尻を撫でてやってくれ」と彼は言い、私にブラシを渡した。無知な私でも馬の後ろに回り込むことがいかに危険なことかは知っていた。無論、とてつもない力で蹴られるからだ。重大な事故の例をいくつも聞いたことがある。私の恐れる顔を見て「大丈夫。キキは絶対に人を蹴らない。ただ、ビビったら伝わる」と谷渕氏は言う。

私は意を決し馬房の柵をくぐり中へ入り、首のあたりからブラッシングをはじめた。そして後ろへ回り込み、両手でゴシゴシとお尻にブラシをかけた。キキは嬉しそうにお尻をグイグイ寄せてくる。私は馬房の壁とお尻に挟まれる格好だが、私の手には彼女の温もりが伝わり、動物の匂いを直に感じた。肉体的なコミュニケーションだった。この時私は見方氏の山での動きを思い出していた。
木を運ぶ馬と同様に、山の一部のように溶け込み、叫び、全身で馬とコミュニケーションをとる、極めて肉体的な見方氏の、人馬一体のあの雰囲気である。
馬房にてキキにブラッシングを続ける私。大分慣れてきた。「じゃあ俺にやったみたいに自己紹介して」と谷渕氏が言う。私は一瞬「どうしたらいいんだ?」と戸惑ったが、どこか得心して「心の中」で自分が誰か、なぜここに来たかを言いながらブラシをかけた。しかし、そういう意味ではないらしい。「……そんな小さい声で……何やってるの。実際話さないと意味ないだろ。はっきり言うんだよ」と谷渕氏。その瞬間、私は馬に話すことを恥ずかしいと思った自分を恥じた。何を勘違いしてたのか、「馬は誰よりもちゃんとわかっている」という戸田氏の言葉を聞いておきながら、キキとのコミュニケーションを遮断していたのは私自身だった。「私は笹谷遼平と言いまして、馬の映画を作ってます。あなたの赤ちゃんが生まれるところを撮影させてください。お願いします」と私は言った。キキは無反応だった。しかし、どこか吹っ切れて、私はブラッシングを続けながら色んなことを話した。家族のことや出身地のこと、各地で見て来た馬について。今思うと、一番馬を近くに感じた瞬間だった。そして初対面の私に大切な馬のお尻を撫でさせる、谷渕氏とこのキキの信頼関係に心から感服した。ここの家族と、キキには文字どおり以心伝心、信頼があった。これが古来からあった馬と人間の関係だと確信し、その片鱗に触れられたことにこの上ない喜びを感じた。
その後、ここで7泊したが終ぞ生まれる瞬間には出会えなかった。そして私が東京へ戻った次の日、元気な雌馬が生まれた。谷渕氏の好意で私の妻の名前がついた。その2週間後、四度目の挑戦の初日に、別の牧場にて出産の瞬間が撮れた。

私が見たり経験したことは、馬と人間の関係の一端でしかない。1800年ほど続いて来た日本における馬と人間の暮らしは、もはや当たり前ではなく、終着点に近い。見方氏の家に、もう馬はいない。「機械が仕事を取っていく」と彼は言った。体を動かし、生きるために生きる時代ではなくなっているのだ。しかし、生活が変化しただけでなく、私たちの身体能力や心が変化していったことは看過してはいけないように思う。馬の動力はトラクターに取って代わり、馬に餌をやるくらいならエンジンにガソリンを注いだ方が効率的だと誰もが思っている。空を見て時間を言い当てることもない。明日の天気は画面を撫でればすぐにわかる。私たちは、世界は年々進歩していると思い込んでいるが、その実は衰えているものの方が大きい。私たちは当たり前の身体能力を次々に失い、ボタンを押すだけの存在になりつつある。私は「この列島の古層、命」を撮ることが出来たのだろうか。それは観てくれた人に委ねたいと思う。しかし、この列島の古層には、馬を、ひいては自然を敬う心があったということが、おぼろげながら見えてきた。だからこそオシラサマや馬頭観音などの信仰が脈々と続いてきたのだろう。
「自然」という言葉は近年では英語におけるネイチャーという意味で使われることの方が多いが、自然の本来の読み方は「じねん」であり、人間も含めた世界の全てを指していた。「人間様」ではなく、人間も自然の一部に過ぎないという考え方が根底にあったのだ。身につまされる思いである。
馬ありて。この映画は私自身への更生の旅だった。何も考えずに生きていた私であったが、馬が多くのことを教えてくれた。そして人間が自然の中でいかに生きるか、そんな問いに辿り着いた旅でもある。この自省の旅は、終わることはない。
*在来馬……外来の馬種とほとんど交わることなく残ってきた日本固有の馬。現在では日本各地に八品種が現存している。