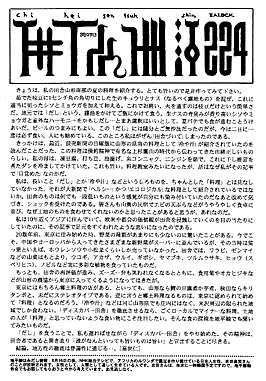 きょうは、私の田舎山形南部の夏の料理を紹介する。とても旨いので是非作ってみて下さい。
きょうは、私の田舎山形南部の夏の料理を紹介する。とても旨いので是非作ってみて下さい。 |
|
■7月の地平線通信・224号のフロント(1ページ目にある巻頭記事)
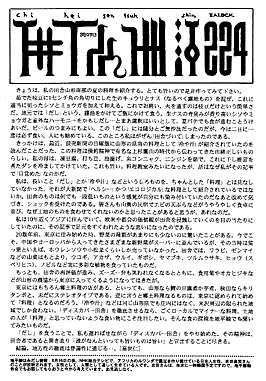 きょうは、私の田舎山形南部の夏の料理を紹介する。とても旨いので是非作ってみて下さい。
きょうは、私の田舎山形南部の夏の料理を紹介する。とても旨いので是非作ってみて下さい。
茹でた枝豆に1センチ角の角切りにした生のキュウリとナス(なるべく露地もの)を混ぜ、これに適当に切ったシソとミョウガを加えて和える。これでお終い。火を通すのは枝豆だけという簡単さだ。地元では「だし」という。醤油をかけてご飯にかけて食う。生ナスの青臭みが香り高いシソやミョウガと意外なハーモニーをかもしだし…とまあ講釈はいいとして、夏バテでも食が進むことうけあいだ。ビールのつまみにもよい。この「だし」には随分とご無沙汰だったのだが、今は二日に一度は必ず食い、人にも勧めている。このところ私はがぜん「田舎づいて」しまったのである。
きっかけは、最近、読売新聞の日曜版に山形の県南の料理として「冷や汁」が紹介されていたのを読んだことだった。この料理は倹約精神で有名な上杉鷹山の時代から伝わってきた由緒正しいものらしい。私の母は、凍豆腐、打ち豆、油揚げ、糸コンニャク、ニンジンを茹で、これに干し椎茸を煮たダシを冷ましてかけていた。これも旨い。料理教室みたいになったが、話はなぜ私がその記事で「目覚めた」なのかだ。
私は、長いこと「だし」とか「冷や汁」などというしろものを、ちゃんとした「料理」とは見なしていなかった。それが大新聞で「ヘルシー」かつ「エコロジカル」な料理として紹介されているではないか。田舎のものは何でも一段低いものという感覚が自分にも染み付いていたのだなあと改めて気づき、ショックを受けたのである。皆さんも山奥の民宿でエビの天ぷらなどがうやうやしく食卓に並び、なぜ土地のものを食わせてくれないのかと思ったことがあると思うが、あれなのだ。
私は10年近くアジアに住んでいて、欧米や都会の価値観が田舎を侵蝕していくのを目の当たりにしていたのに、その記事で足元をすくわれたような思いになったのである。
20数年前、東京に住み始めた時、野菜の種類があまりにも少ないのに驚いたことがある。今でこそ、中国やヨーロッパから入ってきたさまざまな新野菜がスーパーに並んでいるが、その当時は菜っ葉といえば、ホウレンソウや小松菜くらいしか売っていなかった。田舎では、ワラビ、ゼンマイなどの山菜はもとより、ウコギ、アカザ、ウルイ、ギボシ、ヤマブキ、ツルムラサキ、ヒョウ(スベリヒユ)、ノビルなど実に多彩な植物を食っていたものだ。
もっとも、田舎の再評価が進み、ズーズー弁も笑われなくなるとともに、食用菊やオカヒジキなどが山形の農協から東京に入ってくるようになってはきたが。
東京にはもちろん郷土料理の店がある。といっても、山形なら鯉の甘露煮か芋煮、秋田ならキリタンポと、未だにステレオタイプである。逆に言うと郷土料理なるものは、東京に認められて始めて「料理」となるのだろう。「冷や汁」などは同じ山形県でも庄内にはなく、米沢周辺の限られた地域でしか食わない。「ディスカバー田舎」を徹底させるなら、ごくローカルでマイナーな料理、土地の人が「料理」と思っていないような食い物にこそ注目したい。そんな食の探検を地平線でも聞いてみたいものだ。
「だし」を食うことで、私も遅ればせながら「ディスカバー田舎」をやり始めた。その精神は、田舎者であると開き直り「誰がなんといっても旨いものは旨い」と宣言することに尽きる。
結論。地方性の徹底は普遍性に通じる‥。[高世仁]
|
|
|
大西暢夫(30) |
|
|
◆地元岐阜県出身でカメラマンの大西さん、オフロードバイクにまたがり誰もいないはずの徳山村に行ってみたら、そこには村に舞い戻ってどっこい生活しているおじいおばあがいたそうな。見るからに人なつこそうな大西さん、すっかりおじいおばあと仲良しになって、写真撮ることは二の次になっちゃって、徳山村にせっせと通っては山の暮らしに夢中になったそうな。
◆スライドをまじえながらおじいおばあの話をする大西さんは本当に楽しそう。まるで恋人の話でもするようだ。一緒に山仕事をする話、山のごちそうをたらふく喰う話、生活の知恵に関心する話。
◆楽しそうで、うらやましくて、会場で聞いている私たちからも思わず笑いがこぼれる。それにしても、なんて元気な人たちだろう! 80歳を超えている人とは思えない。五合飯にたくさんの山菜のおかず、またあるときはものすごく大きいぼた餅を大西さんと競い合ってペロリとたいらげ、けわしい沢をがんがん登るばあさん。橋がない川に自分で索道を作って、ぴゃーっと川を渡ってさっそうと家に帰るじじばば夫婦。いやいやすごい。これは人間国宝級の集団ではないでしょーか。
◆だけど同時にむなしい現実も映し出される。廃校になった校舎。ひと気のない道。ここはやがてダムのそこに沈むのだ。じじばばのパラダイスが沈んでしまうのだ。
◆学校も親も教えてくれないようなこと、大西さんにとって今まで考えてもみなかったようなこと。おじいおばあのふとした言葉やしぐさが大西さんを感動させ、何回も徳山村に通わせるのかもしれない。
◆道を歩いていたらおばあが突然おじぎした。なんだろうと思って聞いたら、「ここには前に神様の祠があった。今はダムのため別の所に移されてしまって、ここに祠はないんだが、わたしには今でもここに神様がいるような気がする。だから意識せずとも自然と頭がさがってしまうんだよ」
◆山を下りて新しい土地に暮らすようになったおばあの言葉。「山の暮らしだったらいくら歩いてもぜんぜん苦じゃなかった。だって山には一服出来るところがそこら中にあるから。でも都会はそういうところがない。休んでいると若い人が心配する。だからこっちも一生懸命歩かにゃならん。本当に都会は不便じゃ」
◆一緒に山に木の実を取りに行った時のこと。今までダムの話題なんかぜんぜんしなかったおばあがふと漏らした。「動物の分は残してあげることだよ。ここはまだ動物が来ていないようだから、残してあげなきゃね。人間は欲張ったらいかんよ。昔は水がないときも神様がちゃんとなんとかしてくれていた。だのに人間はダムを造って水を管理するという。神様のやることに人間が手を出してしまった。」
◆ここに暮らすおじいおばあは、ダムに反対で居座っているとか、そういうんじゃない。ここで暮らしたいからここにいるんだ。だって、ここはおじいおばあの居場所なんだもの。自分の生きた証を残すんだって、村が沈んだあとのぎりぎり水が来ないところに、桜の苗木を植えるじじばば夫婦。あるがままを受け入れる強さにじんとくる。
◆大西さんは言った。ダムが必要か必要でないか、データ的なことは専門家にまかせるしかない。でも自分はこの山の暮らしが好きなんだ、このじじばばが好きなんだ、と。大西さんの書いた本のタイトルは、「僕の村の宝物」。徳山村でおじいおばあと過ごしたいろんな出来事は、きっと大西さんにとって、お金じゃ買えないかけがえのない宝物なのだろう。そして、それはきっと、おじいおばあにとっても。[サイゴン]
|
地平線ポストから ■地平線ポストではみなさんからのお便りをお待ちしています。旅先でみたこと聞いたこと、最近感じたこと…、何でも結構です。E-mailでも受け付けています。 |
| 地平線ポスト宛先: 〒173-0023 東京都板橋区大山町33-6 三輪主彦方 E-mail : TAB00165@niftyserve.or.jp 武田力方 |
●生田目が行く! バイクで中央アジアへ!
オートバイでは「世界初」
◆シルクロードをバイクで走りたい! そんな思いで発足したツーリングクラブ「シルクロード」の旅も今回で3回目となり、90年と93年で中国のタクラマカン砂漠を一周し、いよいよ98年は中国からキルギスタン、カザフスタンを走り、ウズベキスタンのサマルカンドまで足を伸ばすことにしました。
◆目標は決めたものの、初の中国脱出、情報の少ない中央アジア。バイクの調達、メンバーの募集(毎回、雑誌などで全国から募っています)など、問題は山積みでした。8月5日の出発まで1ヶ月を切った現在でさえ、行ってみなけりゃわからないことだらけなのです(トホホ・・)。
◆それにつけても会長の私ですら面食らったのが旅行代金でした。何せ個人の手配旅行のグループ版ですから、どう見積もっても安く上がらないのです。当初の70万円でもビックリなのに円安も手伝ってか、とうとう100万円近くかかってしまうこととなり(おかげで私はあくせくと昼夜仕事三昧の資金稼ぎの日々となり名ばかりの会長職となってしまいました)、初回及び2回目参加組のクラブ員ですら家庭の事情や仕事の都合でほとんどが残留サポーターとなってしまい、最終的にはクラブ員5名、初参加5名の10名が集まりました(内女性5名は結構凄い!)。
◆東南アジアなど、10万円もあれば1ヶ月は沈没できる時代に、たった2週間の旅に100万円の大枚はたいて苦労しに行く酔狂な(ありがたい)仲間が10人もいるとは、不況日本もまだまだ大丈夫だなと思わされます(笑)。「若いうちの苦労は100万円かけてもしろ」の一例。
◆中国西域カシュガル空港に我々は自分たちのツーリング用品の詰まった大荷物と共に着けるのか? ――前回は荷物が積みきれず別便(翌日)となり出発が遅れてしまいました。
◆カシュガルまで無事にバイクが来ているか? ――日本製のオフロードバイクなので盗まれる?
◆中国、キルギス国境(トルガルト峠3600メートル)はB級国境(国境にAとかBとかランクあり)――B級は土日は休みで24時間OPENではない! 富士山よりも高い国境で開いてなかったら鼻水どころか笑いも凍りそうだ!
◆国境を越えて高山病と闘いながら、寒空野営なのです。――だって宿がないのヨ(キルギスは中央アジアのスイスと言われています。高地→高山病→寒い→つらい→笑)
◆カザフ、ウズベクは今40℃近いらしい。北風と太陽か、スイスからサハラか‥すごいな。「ニュース速報」7月9日付け、本日、キルギス、カザフ国境大洪水により行方不明者70余名にのぼる模様・・・・えっ? まじ? 道残っているのかな? 我々キジルクムキャラバンは無事に青の都サマルカンドに辿り着けるのか?! 事の顛末は次回報告にて! 乞う御期待!! [生田目明美]
|
地平線びとの声 その1 |
|
|
素敵な人である。いつも微笑んでいる。19歳の大学時代から今に至るまで、延べ200以上の島々に関わり、島の人々との絆を作り続けている。
――大学では旅関係のサークルにいたんですか?
「大学の『地方文化研究会』というサークルに入ろうと思ったんです。でも、『山村で旅館に泊まって村を調査する』というのに引っかかって入りませんでした。自分たちだけ旅館に泊まって調査に行くなんていやだなって」
――それで、どういう旅をしたんですか?
「大学1年の秋に、岩手県の大野村の村長さんに『農家に泊めて下さい』って手紙を出したんです。そしたら、10日間本当に泊まれました。そこで言われたんです。俺たちのとこに泊まりたいって言ったのはあんたが初めてだ。民俗学の先生とか調査に来る人は、旅館泊まっていい車乗って、村の目立って可哀相なことばかり書いていくって」
――じゃあ、それなりに信頼されたわけですね。
「こうも言われました。河田さんは、僕んちの財布がどこの引き出しにあるか知ってるよねって」
――実際、知っていたんですか?
「目の前で、毎日同じとこから財布を出し入れしてるんだから、わかっちゃいますよ! そこの家の人も、台所には絶対に調査の先生を入れないって言ってました。この時の経験が、その後の私の旅の原点になったんですね」
――それで、島旅への切っ掛けですが?
「兄が、沖永良部は天国みたいだって言ってたから、行きたくなったんです。大学1年の春休みに行きました」
――やっぱり良かった?
「すごくよかった。そこでも、農家のタケおばさんと一緒に畑仕事しながら10日間を過ごしたんです。私は初めから食費だけは出すつもりで滞在していたんだけど、『そんなつもりで泊めたんじゃありません。次の旅費に使いなさい』って、受け取ってくれなかったんです。今思えば、これで旅が続いたんです。私にすれば、本来払うべきお金を逆に預かったという発想ですよね」
――沖永良部には20回くらい行ってるそうですが、再訪した時はやはり喜ばれたんですか?
「それもあるけど、それ以上にびっくりされました。こんな遠い所まで二度来る人はいないって。当時は交通も不便だったし」
――それが3回、4回と回を重ねていくと・・
「もう『お帰りなさい』の世界ですよね」
――沖永良部を切っ掛けに島旅にはまっていったんですか?
「北の島も行き始めたんです。小さな漁師の島は、男が漁に出て島は女だらけとか、とっつきにくいけど、仲良くなると心を許してくれるなど、南と北の違いが旅人でも分かって面白かった」
――大学卒業後、会社勤めしていますね。就職という道を取れば、旅が制限されることに抵抗はなかったんですか?
「うーん、私、今のダンナとは1年生の時から結婚前提で付き合っていたんです。恋人いなければ旅はできたけど、20年以上も前は、恋人のいる女性はいつまでも旅は出来ないってことを当たり前に思っていた時代でしたね」
――卒業後の進路は?
「就職浪人してから、あるPR誌で1年働いて、マリンスポーツ誌に転職しました」
――島の愛好家集団『ぐるーぷ・あいらんだあ』を立ち上げたのは丁度その頃ですね。
「そう。25歳。マリン誌就職、あいらんだあ設立、そして結婚。この3つが全部25歳の時なんです」
――でも『あいらんだあ』の活動が原因で会社を辞めることになる。
「若い女性が島旅をしているということで、マスコミの対談の企画が持ち込まれたんです。その対談のため休暇許可も得たんですが、直前になって会社から『お前は仕事を取るのか、あいらんだあを取るのか』って。いやみですよ。また、ひどい労働条件で、土日も休めず、2年間全く島に行けなかったので、島に行きたくてしょうがなかったんです。私は『あいらんだあ』を取りました」
河田さんは、これを機会にフリーランサーになることを決意。退職後、八丈島で50日間の居候生活に入ったのを皮切りに、伊豆諸島を歩き回る。28歳で奄美諸島や沖縄に、29歳でマーシャル諸島の旅に出る。そこで100番目の島(一周3分もかからない無人島)にも上陸した。島関係の取材や写真などの依頼も増えてきた。日本の離島に本を送る運動も始まった。そして人生に転機が訪れる。87年7月16日。34歳で出産。重度の脳障害をもった女の子だった。
――娘の夏帆ちゃんはどんな状態で生まれてきたのですか?
「仮死状態で生まれて、2、3時間後には痙攣が始まっていました。あと何日生きるのかもわかりませんでした」
――自分自身が旅することは・・
「不可能と思いました。その時想定されたのは、年に半分は入院、つまり、私が付き添うんです。残り半分は家での24時間看護。この想定パターンと旅は両立しないなって・・」
――その数ヶ月後の地平線会議で、河田さんの近況報告を見てたんですが、表情は重かったですね。
「うん。想定されたパターンが1年半続きましたから。入院といっても、身の回りの世話は私がするんです。トイレに行きたいなあって思った瞬間にゲーって吐かれたり、発作が起こったりしたらその対処におわれて、数時間後ホッとした瞬間に、そうか私はトイレに行きたかったんだって・・。それに、一つのベッドで娘の隣に寝るので、いつも横向き。娘は睡眠障害をもっていて、発作的に泣き叫ぶので私も眠れない。仰向けで寝たかった」
――周囲の励しもありましたよね。真智子なら大丈夫。今までいろんな島々を一人で旅してきた真智子じゃないかって。
「あっ、それ言ったのウチのダンナです。あの時、本当に私はなんて素晴らしい人と結婚したのかって感激しましたよ! あの土壇場で夫が見せてくれた人間性は今でも忘れられません」
――旅の再開を思い始めたのはいつからですか?
「入院初期は、夏帆との面会時間は3時から3時半の30分だけでした。生後三ヶ月の時、あんまり自分が落ち込んでいるんで、思い切って、3時半のあとの飛行機で八丈島に行ったんです。次の日の3時前にはまた戻ってきました。そしたらすごく辛くて・・。病気の子を置いて旅するなんてって、内臓が煮えくり返るような思いでした」
――気持ちが楽になったのはいつからですか?
「生後6ヶ月の時、主任看護婦が『お母さん、長期戦なんだから、仕事に戻りませんか。もし何でしたら、ナースステーションで預かります』と言われたんですね。その時思ったのが、あっ、夏帆は病気だけど、私は病気じゃないんだ。病院で付き添いしていても、月に一本はエッセーは書けるかもしれない。年に一泊なら旅に行けるかもしれないって。そのうち、夏帆の状況も好転していって、年に二泊なら行けるかなと、だんだんと発想が転換されていったんです」
――そして仕事に戻る・・
「出産直前に新潮社から『島が好き海が好き』という本を出版していたので、仕事が入る時ではあったんです。でも状況が状況だから、ひいていく人もいた。わざわざ病院まで仕事を持ってきてくれたのは、江本さんとJICAの『国際協力』誌の人でしたね。そして、外に出かけた仕事が生後9ヶ月の時。琵琶湖への一泊取材でした」
――それが可能になったのは、夏帆ちゃんの介護のための「ちいママ」(小さいママ)グループがあったからですね。
「そう。あの主任看護婦さんに言われた言葉で、人の助けを受け入れればいいんだって思えるようになったんです。そこで仲間に頼んで週に一度病院に来てもらったんです。それで私は週に一度は自宅でゆっくり寝ることが出来たんです」
――ちいママって、『あいらんだあ』の人もいたんですか?
「ほとんどが『あいらんだあ』の仲間ですよ! いかに絆が強かったかですね!」
生後1年3ヶ月の時、河田さんは夫婦で、愛知県の夫の実家に、1年8ヶ月の時には心の故郷の沖永良部に夏帆ちゃんを連れて行く。
「生きるか死ぬか必死の毎日でしたから、死ぬんなら、辛い思い出だけじゃなく、せめて楽しい思い出を作ろうとした旅でした」
――純粋に楽しもうということでの旅は?
「それは1年と9ヶ月目の時。佐渡に『ちいママ』と夏帆とで3泊4日の旅をしました。この頃からです。また旅に出れるかなって思ったのは」
――実際、翌年の90年、フィジーへの一人旅を再開していますね。不安はなかったんですか?
「ありました。万一、娘が危篤でもすぐには戻れないわけですから。でもこの旅は、障害児をおいても旅に出れるのか、私が今後「河田真智子」として再び生きれるのかの試金石だったんです」
河田さんは2週間の旅の間、毎日夏帆ちゃんに手紙を出している。そして、旅の終盤にはこう書いている――「お母さんはなっちゃんをおいて旅に出てもその旅はつまらないものだろうか、旅に出る前に気にかかっていました。果たして旅人になれるのだろうか。答はYESです。(中略)旅を続けていこうと思います。(中略)そしてなっちゃんも一緒に行こうね」
その2年後、5歳の夏帆ちゃんと、奄美大島、加計呂麻島へと二人きりの一週間の旅が実現した。
「出産前は、子どもの手を引いて二人だけで旅するのが夢だったけど、出産後は諦めちゃったんですね。でも夏帆の状態が安定していたことと、5歳以上になると、体も大きくなって物理的に無理になるので、今しかないって、行っちゃいました」
――どれくらいの荷物だったんですか?
「夏帆が13kg、車椅子15kg、荷物17kg。合計45kg! でも島は下見が出来ていたし、現実的には、二人きりの移動って200メートルしかなかった。空港には人が迎えに来ていたり、バスの乗り降りも地元の男の子に手伝ってもらったりで。バスで行きますって言ったのに『人脈という足もあるよ』って車で送ってももらいました」
――思い出深かったのはどこですか?
「加計呂麻島へ行く時のフェリーで見た夕日。空は曇っていたんだけど、自力で行った家族旅行ですよね。夏帆の手を握りながら見た夕日は世界一きれいでした」
河田さんは闘っている。
「助けてあげたいっていうボランティアの人は苦手です。献身的に夏帆を世話してくれますが、根底には、障害児は『可哀相』、その母親も『質素に頑張っている』べきというイメージがあるんです。だから私がテレビに出たり、海外に行くと『なぜそういうことができるわけ』って思うみたいですね」
91年、河田さんは障害児の母親でも仕事ができるのが当たり前ではないかと、夏帆ちゃんの4歳の誕生日に、たった一人で、障害児の母親同士のネットワーク「マザー&マザー」を創立した。
――どうやってネットワークを広めたんですか?
「自分で勝手に創刊号を作って、知っている病院や知人に配ったんです。当初は20人くらいの賛同者が集まればいいかなあと思っていたのに、とたんに電話の鳴りっぱなしですよ。読売以外の全ての大手新聞に取り上げられ、すごい反響でした。会員は今250人くらいでしょうか」
――相当深刻な相談も多いんですか?
「うん。一本の電話は最低1時間半。中には、死にたそうに話す人もいるので、電話が終わったら、その人の家に直行したこともありました」
――それにしても、島旅とライター、あいらんだあ、マザー&マザー、娘の介護と、これを一つの人生でやってるなんて凄い。
「あっという間に、何十年分も生きているみたいです。でもやっぱり忙しいのは事実。今思っているんです。もっともっと自分のやりたいことをやれる人生でなきゃって」
――夏帆ちゃんが生まれる前と後で、島の人との関係に変化はあったんですか?
「障害児の母になってから、島の人との信頼関係は強くなったと思います。逃げれない場所でも動き続けていることが共通項なのかもしれませんね。最近は島の人によく言われるんですよ。『河田真智子を支えているのは夏帆だからな』って」
――それは当たっているんじゃないですか?
「うん、当たってます」
8月は夏帆ちゃんを連れて佐渡へ。9月は一人で北アイルランドへ。河田さんの旅は続いている。(文責:樫田)
ちょっと宣伝・・昨年出版された河田さんの「島旅の楽しみ方」(山海堂)は超お勧め。お金がなくても旅に出ようという元気が湧いてきます。
●編集部より…
◆暫定編集長を言い付かってから早三ヶ月。そろそろ辞め時ではあるのですが、交代要員がいないという予想通りの現実的問題にぶち当たりました。江本さんのニヤニヤした顔が夢に出てきそうです(ウッ!)。◆とはいえ、今月の河田さんへのインタビューのように、まとまった時間話してみて初めてわかる生きざまもあります。その意味で、編集部ゆえの役得はあります。ところで編集部といっても、イラストの長野亮之介、レイアウトの武田力、地平線ポストの三輪主彦、そして編集長(実質「原稿お願いしまーす」係)の樫田秀樹の4人のみ。◆そこで、ここに編集部員を募集します。東京、地方、老若男女を問いません。行動者たちへのインタビュー、誌面作り、企画作り、情報発信、テープ起こし、エトセトラ。楽しくやることを基本としたいと思います。毎月、江本さんから茶代も出ます(だといいな‥)。気軽に声をかけて下さい。
 |
7/31 FRIDAY 6:30〜9:00 P.M. アジア会館(03-3402-6111) \500 月へのベースキャンプ 今年5月25日、続(つづき)素美代さんは日本女性として初めて、エベレスト北稜ルートを通って8848mの頂に立ちました。従来のエベレスト登山家達と違い、続さんは山岳会に所属せず、学生山岳部の出身でもありません。 続さんとエベレストの最初の出会いは96年。仕事で関わっていた記録映画の撮影のため、8000mまで登ったものの、ケガでそれ以上の登攀を止められました。 「可能性を人に止められたのが納得できなくて」と言う続さんは、特にハードトレーニングをするでもなく、97年に8400m、そして3度目のトライで頂上をきわめました。 「あたし、あんまり登山って好きじゃないんです。だからエベレストが大変な山っていう常識がなくて、かえってそれが良かったみたい」と続さん。続さんにとって、世界最高峰は、自分の可能性を試すフィールドの一つでした。 「次は月へ行ってみたい。可能性はゼロじゃないでしょう?」という続さんに、今月はエベレスト体験を報告してもらいます。必聴、必見! |
|
|
|
|
|
|