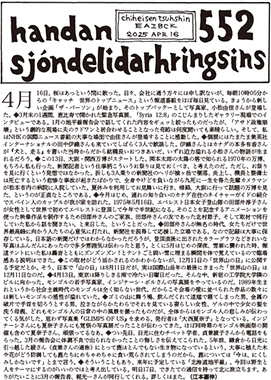
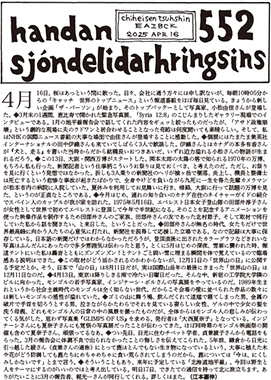
4月16日。桜はあっという間に散った。日々、会社に通う方々には申し訳ないが、毎朝10時05分からの「キャッチ 世界のトップニュース」という報道番組をほぼ毎日見ている。きょうから新しい企画「ザ・パーソン」が始まり、そのトップバッターとして写真家、小松由佳さんが登場した。
◆3月末の1週間、恵比寿で開かれた緊急写真展、「Syria 12.8」のこじんまりしたギャラリーの現場でのインタビューである。1月の地平線報告会で話してくれた内容をギュッと絞ったものだったが、「アサド政権崩壊」という劇的な現場に夫のラドワンと居合わせることとなった奇跡は何度聞いても素晴らしい。そして、私はNHKの国際ニュース番組の大事な場面で由佳さんが登場することに感動した。
◆個展にはたまたま集英社インターナショナルの田中伊織さんも来ていてしばらく3人で歓談した。伊織さんとはカナダの本多有香さんが『犬と、走る』を書いた当時からだから結構長いおつきあいだ。いずれ迫力溢れる小松さんの物語が生まれるだろう。
◆この13日、大阪・関西万博がスタートした。岡本太郎の太陽の塔で知られる1970年の万博、もちろん私も行った。新聞記者という仕事柄こういうお祭りは見ておくべき、と考えたのだ。ただし、お祭りを見に行くという発想ではなかった。折しも3人乗りの新聞社のヘリが槍ヶ岳で墜落、炎上し、機長と整備士は死亡するという悲惨な事故が起きたばかりで、全身やけどを負いながら九死に一生を得た先輩カメラマンが松本市内の病院に入院していた。夏休みを利用してお見舞いに行き、帰路、大阪に行って話題の万博を見た、というのが正直なところである。
◆今月はじめ、連れの知り合いのカナダ在住のネイチャーガイドの紹介でスペイン人のカップルが我が家を訪れた。1975年5月16日、エベレスト日本女子登山隊の田部井淳子さんが女性として世界で初めてエベレストに登頂して今年で半世紀になる。そのことを記念するアニメーションを使った映像作品を制作するため田部井さんのご家族、田部井さんの友であった北村節子、そして取材で同行していた私から話を聞きたい、と来日した、ということだった。
◆田部井さんが無名の時代、女たちだけで世界最高峰に向かう人たちの心意気に打たれ、新聞社を説得して応援した立場である。なので記録は大事に保存している。日本語の新聞だけではわからなかっただろうが、登頂直後に出されたカラーグラフなどきれいな写真はふんだんにあったので多少雰囲気は伝わったと思う。とくに5月はじめ深夜、雪崩に襲われたとき、報道テントにいた私は轟音とともにズンズンズン!とテントごと固い雪に埋まる瞬間を体で覚えているので臨場感ある説明はできた。
◆この取材がどう活かされるのかわからないが、12月11日の「世界山の日」に公開する予定だとか。そう、日本で「山の日」は8月11日だが、実は国際山岳年の最後にきまった「世界山の日」は12月11日なのだ。
◆4月13日。東京は降りしきる雨で冷たい日曜日だった。そんな中、新宿の工学院大学隣のビルに向かった。モンゴルの若手写真家、インジナーシ・ボルさんの写真展をやっているのだ。1989年生まれというから社会主義時代のモンゴルはまったく知らない世代。だからこそ会場の壁に並べられた作品の数々には新しいモンゴルの感性が溢れていた。
◆ゴミの山に舞う鳩、飲んだくれて道端で寝てしまった男、金属の破片で手首を切ろうとする男、泣きながらかたわらでそれを見ている妻らしい女性、ゲルの中で少女の髪を洗う母親、どれもモンゴル人の日常の中の風景を撮ったものだが、全体からはモンゴル人の悲しみが伝わってくる気がした。思わず写真集『GLIMPSE OF US』を求める。発行者は「大西夏奈子」となっている。インジナーシさんにも夏奈子さんにも覚悟の写真展だったことが伝わってきた。ほぼ同時期のモンゴル映画祭の開催も含めて夏奈子さん、頑張ってるなあ。
◆つい先日、日光に住むチベット学者、貞兼綾子さんから電話をもらった。3月の報告会に体調不良で出られなかったことの悔しさを伝えてこられた。5年前、鎌倉から日光に引っ越した綾さん(貞兼さんの通称)にとって鹿はとんでもない生き物になっているという。大事に植えた木や花がどう防御しても鹿たちにめちゃめちゃに食い荒らされてしまうのだから、鹿については「今は、にくしみしかないです」とまで言う。
◆そういうこともあり、来年に予定している「北海道地平線」。今回は野生と人をテーマにするのがいいのではと考え出している。明日17日、できたての通信を持って北に旅立ちます。ありがたいことに3月の報告者、梶さんが同行してくれる。詳しくはまた。[江本嘉伸]
■今回の報告者は、東京農工大学名誉教授・兵庫県森林動物研究センター所長で、知床自然アカデミー(旧知床自然大学院大学設立財団)代表理事の梶光一さん。2006年にも一度報告をしていただき、今回は約19年ぶりの報告となる。
◆北海道大学大学院農学研究科博士課程修了でヒグマ研究グループ、通称「クマ研」の一員だった梶さん。クマ研が発足した1970年、北海道ではヒグマによる人身被害や家畜被害が相次いでおり、ヒグマの根絶を目指した「春グマ駆除」政策が行われていた。北海道の開拓が進む中でも最大の阻害要因となり、世界で最も凶暴と恐れられてきたヒグマ。そんな中、詳しい生態もわからずに殺すのはおかしい、と反発を覚えた学生たちが調査を始めたのがクマ研設立のきっかけである。クマ研の活動がスタートして3年がたったころに梶さんは入部。ヒグマの生態研究・調査にのめり込んだ。
◆クマ研1年のとき、スカンジナビアのヒグマ管理の歴史に強く興味をもった梶さん。スカンジナビアでは17~19世紀に、森林伐採と高い報奨金をかけた駆除によって絶滅寸前となるまで激減し、19世紀末から20世紀半ばまで保護政策がとられていたことを知る。当時の北海道では、まさにヒグマの根絶作戦を展開しているところであり、「これを進めればヒグマは絶滅するのでは」と疑問に思った。卒業論文ではヒグマの分布と捕獲統計の解析を行い、春グマ駆除は幼獣や母獣を多く捕獲するので個体群存続を危うくするとの警告を発した。その後、梶さんの予想通り個体数は減少し、ヒグマによる被害も低減したということで、1990年に春グマ駆除制度は廃止された。
◆大学院に進学するも予算や体制がなくヒグマの研究を断念し、シカの研究に転向する。北海道では明治以降、エゾシカは「乱獲→個体数激減→保護政策」という事態が繰り返されており、梶さんは、エゾシカを資源として利用しつつ個体数を安定的に管理する必要があると考えるようになる。そして、エゾシカの個体群管理を目的に、個体数の増減の仕組みとその要因を探る個体群動態研究に取り組むことにした。
◆調査のフィールドは、生息環境の異なる洞爺湖中島と知床岬に設定した。1980年に開始した中島でのエゾシカ生息数調査では、約100頭から始まり1983年秋には299頭とピークに達し、1983~84年冬に群れの崩壊(大量死)が生じた。野生のシカは「増えすぎると崩壊する」という説と「自己調節能がある」という説がぶつかり合う中での、初めての爆発的な増加と崩壊であった。大量死の原因は餌不足による餓死で、生息数の増加にともない、植生が劇的に変化したことが関係していた。ここには「シカ騒動」と呼ばれる「間引くべきか放置すべきか」の議論も巻き起こっていた。地元の営林署や環境庁などからは、森林被害を防ぐために、調査を中止して一刻も早く間引きを実施すべきであるとの意見が出されたが、梶さん含め研究者らはもちろん研究の継続を主張した。道主催の会議では意見対立のまま終了したが、最終的に道は間引きを決定した。自然死67頭、人為的に95頭が島外へ搬出。「非常に残念な結果」と語る梶さんだが、科学に基づく野生動物管理政策の必要性を実感したことと、今日のシカの増え過ぎ問題を40年前に先取りしたことから、科学と政策を考える契機であったと振り返る。さらに北海道は、自然保護課「野生動物分布等実態調査」事業に破格の予算措置をとるなど、鳥獣行政には専門的な知見が必要だという認識が広がったそうだ。
◆中島の調査では、シカの大量捕獲方法の確立に苦労した。1981年に全数捕獲を目指した捕獲作戦を実行したが、12日間、延べ345人で3頭捕獲にとどまった。大量捕獲の目途がたたず断念を決断するも、無報酬・重労働ながらも献身的に協力してくれるクマ研メンバーに申し訳が立たないと、思いとどまる。「できるかできないかじゃなく、やらなきゃいけないときはやらなきゃいけない。やる価値があるかどうかが重要」と梶さんは言う。作戦を全数捕獲から一部の越冬集団の捕獲に変更する。1982年、追い込み罠による捕獲作戦では15日間、延べ321人で54頭の捕獲に至った。その後も、移動式シカ用囲いワナの一種であるアルパインキャプチャーシステム、大型囲いワナなどさまざまな捕獲方法で、1980~2002年に563頭の捕獲に成功し、標識装着、体重計測、妊娠診断を行った。さらに餌植物の調査では、落葉広葉樹林における植物現存量の99.9%はシカの不嗜好植物であり、餌を食い尽くしたシカは、落ち葉が周年を通じた重要な餌となっていることが明らかになった。夏に高栄養の落ち葉を採食して、脂肪を蓄積して越冬する。落ち葉は無限にあるので、シカが増えても餌は減らないという仕組みだ。つまり、エゾシカの生態的特徴として、嗜好種の餌がなくなっても高密度が維持されるということだ。捕食者や狩猟者による高い捕獲圧がなければ、シカは高密度に達して、自然生態系に強い影響を与えるということがわかった。
◆知床岬でもシカの爆発的増加と崩壊の一連の現象が観察された。知床のシカは、1970年代に明治期の大雪による絶滅を免れた阿寒地域の残存個体群が再分布して定着したと言われており、その個体群は年率21%(3年で倍増)で増加を続けてピークに達すると大量死亡が発生した。600頭近くまで増加して大量に死ぬ、その後再び個体数が回復することを繰り返し、知床岬の植生に強い影響を与え続けていることが判明する。これ以上放置した場合には植物が絶滅するリスクがあると考えられたため、発生しうる最大の被害を未然に防ぐ「予防原則」に基づいて密度操作実験を開始することとなった。それにより、当初目標としていた知床岬の越冬個体数(メス成獣)の半減を達成。シカ生息数の減少に伴い、2016年度までに知床岬を含む遺産地区の一部の植生で回復傾向、知床岬の草量の増加など、部分的な効果が確認された。
◆洞爺湖中島と知床半島での調査を検証すると、次のような知見が得られた。第一に、自然の推移に委ねてはシカによる森林植生への影響を緩和できず、個体数増加の初期段階からの個体数管理が必要であるということ。第二に、長期的な採食を受けた森林植生は、シカの数を減らしても回復しないため、長期間の低密度化の実現が必要であること。梶さんらは、これまで日本になかったエゾシカのさまざまなモニタリング手法を開発するとともに捕獲個体の繁殖力調査や年齢査定を行った。その結果、個体群変動のメカニズムに「自然調節機能がほとんど効いていない」という事実が明確化した。人為的に導入したか自然定着か、閉鎖的か反閉鎖的かといった生息環境に関わらず、人間による捕獲がなければシカは増加し続けるということだ。つまり、「個体数管理は必須」なのである。梶さんらは、管理目標を仮説、捕獲を実験と見立て繰り返し、不確実な情報をもとにした順応的管理と呼ばれる方法で「為すことによって学ぼう」と試みたことで、個体数指数に応じて雌雄の捕獲数を調節するフィードバック管理によって道東のシカを二度減らすことができた。しかしながら、全道的にシカの分布拡大と個体数急増によって、今や人間の手に負えない管理不能な状態に陥っているという。
◆私たちはこれから野生動物とどのように付き合っていけばよいのか。2000年代以降、ニホンジカやイノシシ、クマなどの大型獣の分布域は急速に拡大している。同時に捕獲数も駆除により急増。北海道においては、ヒグマの生息数・捕獲数は右肩上がりで、人身被害や農業被害は深刻になっている。2019年には、札幌市郊外にもヒグマが50年ぶりに出没した。2019年~2023年6月末までに合計66頭の牛を襲ったオスのヒグマ「OSO18」は、記憶に新しい。北大クマ研の40年にわたる調査によると、ヒグマの痕跡の発見率は、春グマ駆除制度期間中は減少していたが、駆除制度廃止後は上昇していることが分かった。北海道は、2022年度から2026年度のヒグマ管理計画において、生息数35%減を目指すよう改定している。
◆良好なヒグマの生息環境が維持されてきた知床半島では、地域住民の生活や産業を守りながら、ヒグマの本来の生活と個体群を将来にわたって維持することを目指している。知床のヒグマは、海と陸の物質循環の橋渡しをしてくれる非常に重要な役割を担っており、適切に管理していく必要があるからだ。国立公園や国指定鳥獣保護区の指定、春グマ駆除制度の廃止等、1980年代以降に保護政策が強化されてきた知床半島だが、ヒグマの個体数を把握できないまま飽和状態で維持されてきた。そのためか、餌不足に見舞われた2012年、2015年、2023年度の3回にわたり、市街地や農地への大量出没があった。クマの大量出没は、人命に関わる危険を伴い、ヒグマの大量捕殺を招くので、大量出没を発生させない個体数水準を維持することが必要だと考えられるようになった。今年三月には、従来の問題個体(人の活動に実害をもたらす、人につきまとう、または人を攻撃するクマ)管理に加えて個体数管理を併用することが合意された。ヒグマと人間がどう折り合っていくかを軸に、個体数のモニタリングおよびフィードバックを行い、問題個体と総個体数を管理する仕組みを構築していくことが課題なのだそうだ。
◆一方、シカの個体数は有史以来最大規模かそれに近いという。シカが増えすぎることによって起こる問題は、生態系被害、農業被害、林業被害と森林被害、列車事故・自動車事故、都市出没問題、野生動物感染症などかなり多様であり、その被害は全国的な社会問題となっている。ここまで深刻になった要因に、野生動物の増加、里山の放置、林業政策の失敗、農村の過疎と高齢化等が関係しているといわれており、梶さんは「動物の力が一番強くて、人間の力が一番弱い時代に、我々は直面している」と話す。法的な仕組みは明治時代から変わらず、為す術がないのだという。
◆なぜ、管理不能になってしまったのか。ヨーロッパでは土地管理者が狩猟権を持つ猟区制度、北米では管理ユニット(管理単位)を設定して捕獲数を割り当て、狩猟によって個体数管理が実施されている。しかし、日本には管理ユニットのような捕獲数の割り当て制度はなく、管理地域が市町村や都道府県など事業によって異なるために「誰が管理するのか」があいまいである。管理責任の所在が不明確である事例として、土地管理の一環として野生動物管理が行われていないということがある。公有地でシカの生息の場となるのは、国立公園、国有林、自衛隊駐屯地など一般市民が入れない地域であるので、国家行政組織がシカ管理の主体となるのは当然のことである。ところが、日本の法制度上、土地所有権と野生動物の所有が関係づけられていないために、国有地の野生動物管理は都道府県や市町村に丸投げ状態なのだ。公有地での捕獲は限定的であり、これらの地域は野生動物の避難場所と化している。捕獲の空白地帯をつくらないために、「野生動物管理は基本的な土地管理義務」とする考え方が必要だという。
◆では、野生動物管理をどのように進めたらよいのか。梶さんは「補完性原則——自助・共助・公助による獣害対策」という、市民に近い地域レベルから始める地域主権型の方法を示し、それは次のように進められる。(1) 集落・地域による被害防除(自助・共助)(2) 市町村による駆除(公助)(3) 都道府県による個体数管理(公助)——この手順で行うためには、市町村と都道府県の緊密な連携が必要になる。必要に応じて上の組織が下の組織を補完し、専門職員として市町村に鳥獣対策員、都道府県に野生動物管理専門員を配置し、国と協働できる仕組みの構築が求められる。
◆現在、日本の鳥獣管理の専門職は圧倒的に不足している。梶さんが北海道を離れたのは、次世代の野生動物管理専門人材を育成する手伝いがしたいと覚悟を決めたからである。野生動物管理教育の研究拠点を広げ、人材育成の輪を広げる準備が進んでいるのだそうだ。梶さんは、その一環として「知床ネイチャーキャンパス」という現場で学ぶ独自の教育を実施している。高校生から社会人まで、海・川・陸といった現場で学び、野生動物管理の専門家(ワイルドライフマネジャー)の養成を目指して活動を行っている。
◆日本では、近年、シカとイノシシがそれぞれ約60万頭、合計120万頭が捕獲されており、ドイツ(211万頭)、フランス(142万頭)に次いで捕獲数が多い。ところが日本の現状は、捕獲は狩猟の役割が低く、駆除がほとんどである。将来は、狩猟による資源利用と駆除による被害管理の組み合わせによる相乗効果が求められる。梶さんは、資源利用として私たちにできることは、「獲って食べる」ことだという。日本列島北部周辺の先住民族であるアイヌ民族はヒグマを山の神(キムンカムイ)として敬い、資源として利用してきたそうだ。野生動物と人間が共存する手段の一つとして、適切に管理・利用させてもらうという姿勢は大切にしなければいけないだろう。狩猟に対して、そして野生動物に対する私たちの価値観の転換がいよいよ求められている。
◆報告会には、シカの研究に興味があるという片倉景道さん(中2)が参加していた。梶さんの論文を読み、梶さんについて知るうちに今回の地平線報告会に辿り着いたそうだ。シカに興味を持ったきっかけを語ってくれたのだが、専門用語を用いてスラスラと話す姿には驚いた。梶さんが代表を務める知床自然アカデミーの「知床ネイチャーキャンパス」には、高校生も参加しているというのだから、人材育成の輪を広げる梶さんの取り組みは、確実に若者の心をつかみ始めているのではないだろうか。[杉田友華 4月から北大修士]

イラスト 長野亮之介
■2006年7月の報告会で「狩って食うシステム」という内容の話をした。北海道では、エゾシカの個体数の増減に応じて、雌雄の捕獲数を調整するフィードバック管理によって、北海道東部のシカの個体数を減らすことができたこと、林産物として管理する必要があること、野生動物管理の担い手の育成が急務であることを述べた。
◆その状況は今でも変わっていない。だが、この20年間でヒグマもエゾシカも分布拡大と個体数増加が生じ、ヒグマは保護から管理へと政策転換があり、エゾシカは管理不能となるまで増加した。前回「いずれにせよ、今日本人が直面している大型野生獣との関係性は、過去100年で初めて出会う事態です」と述べた。だが、今回の報告会では「有史以来、これほど人間の力が弱く、野生動物の力が強くなった時代はなかった」とさらに危機感を強調した。
◆捕獲の担い手育成、野生動物管理の専門家の育成、資源利用の仕組みの3つの柱をたてることが必要であると言い続けてきたが、その歩みは遅い。だが、国がジビエ認証制度を設立し、「野生動物管理教育モデル・コア・カリキュラム」の支援を行うようになったことなどの進歩があったことは嬉しい。
◆今回の報告会にあたって、江本さん、長野さんとの事前の打ち合わせなど、きめ細やかな対応をしていただいた。2時間半の長丁場をどう話すのか、悩ましかったのでとても助かった。また、報告会の感想を記述するというフォローアップ活動も素晴らしい。北大大学院に進学した杉田友華さんの手による報告会レポートは、細部まで正確に記述した力作である。長時間、膨大な内容をどこまで理解していただけたのか、正直不安だったが完璧な理解力である。
◆会場には最年少の片倉景道君(中2)から最高齢の90歳の川口章子さんまで参加されていてお話することができた。片倉君は、なんと拙著『日本のシカ——増えすぎた個体群の科学と管理』(東京大学出版会)という専門書を読み、もっとシカのことを勉強したくて参加したそうだ。川口さんは長く日本山岳会の自然保護委員会に所属されており、シカによって山が荒れているのを心配して、何とかしたい思いで参加したという。孫の世代に美しい山を残したいとの思いを二次会で語ってくださった。その話を伺い、山を楽しむ人たちにも野生動物問題をもっと知ってもらう必要があることを思った。
◆今回、報告の機会を与えていただきありがとうございました。また、拙著『ワイルドライフマネジメント』(東京大学出版会)の会場での販売の労をとっていただき御礼申し上げます。売上金は、「知床自然アカデミー」に寄付しました。地平線会議が世代を超えて地球で活躍する方々のプラットフォームとして継続し発展することを願っています。[梶光一]
■先日地平線報告会に参加させていただいた武蔵中学3年の片倉景道と申します。梶先生のお話を聞けて、とてもためになりました。以下に感想文を記させていただきます。
◆私は、中1の課外授業で赤城山に行ったとき、シカの頭骨、大腿骨などを見つけ、数人の仲間と土に埋まっていた骨たちを探したところから、シカへの情熱は始まりました。その中で梶先生のことを調べていたら、この報告会を見つけました。最初は、地平線会議???どんなところだろう。想像がつきませんでした。いざ行ってみると、優しい方々が多くてとても参加しやすかったです。ありがとうございました。
◆そして、梶先生の講演が始まると、前半から胸がドクンドクン。前に読んだ「日本のシカ」でわからないことが紐解かれてゆき、しかも、捕獲方法や個体数の調査方法が確立されていない中での試行錯誤が大変興味深かったです。
◆前半で語られた「狩猟圧」の意義、そこで私の心の中に1つの疑問が浮かびました。「どのようにして狩猟圧をかけていけばよいのか」。その中で始まった後半、私の疑問が丁寧に解説されてゆきました。そこで出てきた3つの単語「捕獲」「管理」「利用」。これはただの単語の羅列ではなく、つながっている大切な言葉でした。
◆今回の報告会は私に新たな視点を与えてくれました。素晴らしい講演をしてくださった梶光一先生、私を温かく受け入れてくれた方々に改めて感謝申し上げます。[武蔵中学3年 片倉景道]
■3月下旬、江本さんから地平線通信(2025年3月号)を送っていただいた。日中の作業を終えて帰宅後、自宅近くの森で採取したイタヤカエデの樹液を薪ストーブで煮詰めてカエデ蜜になっていくのを待つ傍らで、半袖一丁になりビールで喉の渇きを潤しつつページを開く。冒頭から「2025年、世界は大変だ。でも今この瞬間の『暮らし』が大切。羊は『暮らし』そのもの…」、という中畑朋子さんによる「本出ますみさん報告会レポート」に惹きつけられた。
◆羊毛は糸、フェルト、さらには古くなった毛をほぐして再び繊維素材として使え、果ては堆肥に。羊の乳からはチーズやヨーグルト。屠畜すれば肉、血、内臓も調理でき、毛皮は服や断熱材に適する保温性がある。脂は化粧品、石鹸、ろうそくなどに加工可能。“生きている在庫”という言葉が示すように、いかに羊が歴史的に人類によって重宝されていたかを物語っている。
◆僕は生きるために畑仕事を選んだが、住む場所は、大家さんの所有している一軒家に格安で住まわせてもらっている現状だ。自分で住む場所を作りたい、さらにはその素材を自給したいという考えにまでは及んでいない。衣類に関してはほとんど貰い物。糸を紡いでさらにそれを編んで服に仕立てるなんて途方もない作業に思え、衣類の自給もまったく頭の中にはなかった。
◆服に関してはイチから作るくらいなら買ったほうが楽、という気持ちでいた。かつて誰もが生きるために必要な衣食住の素材の多くを自給し共有していた過去があった。生きるために本来必要な衣食住の自給は機械生産を主とした効率化・画一化により、資本の手に多くを委ねられるようになってから久しいが、1人1人の衣食住も金次第という条件が絶対的につきまとう。
◆国産・輸入品問わず様々な製品や中古品にあふれている日本では、お金があれば物質的に豊かな暮らしを送れる。しかし、アジア、アフリカ、南米の多くの国々では人口増加が続いており、地球温暖化による食糧供給の不安定化も重なっている。「国内で足りないものは輸入すれば良い」というこれまでの考え方がいつまでも通用するだろうか。確かに、国家間の経済競争で日本が負けないために、限られた平地面積で効率的にお金を稼ごうと思うと一次産業ほど非効率なことはないのだと思う。
◆自然を相手にしてその恩恵を収穫する産業は時間がかかる。畑では勝負できるのは1年に1度。失敗すればその年の収入に影響が出る。燃料代、肥料・農薬代、農具・農業機械代、設備費用等が軒並み値上がりしており、夏の猛暑の影響も大きくなっている。ワンシーズンにかける費用が大きくなっている一方で、費用値上がり分の商品への価格転嫁は消費者の商品購入を判断するハードルを上げてしまうので簡単には通用しない。これでは年々ハイベットかつハイリスクな勝負になってしまう。
◆僕は今年新規就農したばかりだが、畑で大切にし続けたいと思うのは土づくりだ。物理的にも化学的にも生物的にも土壌が作物の生育に適していれば、近年の夏の猛暑をはじめとする環境による負荷に耐えられる可能性は拡がるのではないか。そこでいま注目しているのが馬糞だ。
◆今年に入って仲間の紹介もあり、馬と触れ合う機会を何度かいただいた。ロバ、ポニー、鞍の高さが背丈を超えるようなばん馬などさまざま。中富良野町でばん馬を育てながら馬糞堆肥を作っていらっしゃる方のもとを訪ねたときに堆肥を触らせてもらえた。手でつかんだ時の感触はふかふかで土も軽い。水分も十分に含まれているのだが、容積の割に土が軽いのはそれだけ空気も含んでいることと思われる。
◆そしてつかみ取った堆肥の中には大小さまざまなミミズがたくさん棲んでいた。匂いも腐葉土のような香りで心地よい。馬と暮らすことができれば馬糞も手に入るし、馬糞堆肥を作れば土を肥沃にしてくれるミミズも集まってきてくれる。仮に燃料が手に入らない時代が訪れたとしても耕起や運搬作業で馬力を発揮してくれるだろう。まだ馬のことは全然知らないし、飼うための環境も整っていないので、現状では馬と暮らすにはもっとアイデアを温める必要があるが……。
◆馬に限らず畜力を備えていることは、いかなる状況に置かれても衣食住を揃えるための大きな助けになり、それは1人1人の生活の安全保障になると思う。本出ますみさんのお話の中に、日本も戦後の衣料品不足を補うために国内の羊が昭和20年からの10年間で100万頭にまで増えたという報告があったが、それを聞いて畜力は生活の安全保障であるという思いが一層強まった。[山川佑司→先月の通信551号10ページの山川「祐介」は間違い。お詫びして訂正します。編集長]

■私の家にはモンゴルのいろいろな友人が泊まりにくる。先月はゲイの男性が居候していたが、彼が帰国したのと入れ替わりで、今度はふたりのモンゴル人がやって来た。一人は韓国で4年間の出稼ぎ生活(食用豚の解体)を始めたばかりのレズビアンの友人、もう一人はウランバートル在住のシャーマンの女性。「最近のモンゴルのニュースを教えて」と私が聞いたら、「今年初めての雨が降ったよ」とシャーマンの彼女が教えてくれた。
◆モンゴル人は、1年のうち最初に降る雨を特別な思いで楽しみにしている。今年は3月10日に初めての雨が降って、メディアでもニュースになった。冬はマイナス30度まで下がる極寒地なので、降るのは雪ばかり。天から水の粒が落ちてきたら「春が来た!」と嬉しくなって、外に飛び出すらしい。初めての雨が4月や5月に降る年もあり、「辛い冬が終わって春を知らせてくれる雨を肌で感じたいから、傘はささないよ」と彼女たちは笑った。私は一度だけ、初めての雨の音を聞いたことがある。シロシロという穏やかな音だった。建物の屋根にあたって一瞬で消えてしまいそうな、やさしい雨だった。
◆今回ふたりの友人は、新宿で4月14日まで開かれるモンゴル人ドキュメンタリー写真家インジナーシ・ボルの写真展を見るために日本へやってきた。モンゴル人はとなり町を訪れるかのように外国へさっと遊びに行く。まさに遊牧民マインドだと思う。
◆この写真展の企画者である私も会場に在廊し、100枚以上ある写真を毎日眺めている。そのなかで見れば見るほど気になってくるのが、水色っぽい寂しげな写真。1人の少年が部屋の窓から外を眺めていて、顔は見えない。窓にかかった薄い青色のカーテンが、外から吹きこんだ風で舞っている。キャプションには「彼がこの部屋で過ごした6回目の春。2017年」とだけある。写真の場所は、周囲100キロメートルに人がほとんど住んでいない田舎の学生寮の部屋。撮影したのは、その年初めての雨が降った瞬間だったという。寮にいた他の子どもたちは「雨だ!」といっせいに外へ走り出してはしゃいでいたのに、その少年1人だけ部屋にじっととどまっていたので、インジナーシはシャッターをきったそう。
◆少年は寮に暮らして6年目。この狭い部屋に閉じこもって何を考えていたのだろうかと、インジナーシは撮影から時間が経った今でもふと考えるらしい。彼自身、この5、6年は思うように写真が撮れない苦しいスランプのなかをさまよっている。狭い部屋から飛び出せない小さな少年の姿に自分が重なって、だからこそこの1枚を展示にどうしても加えたかったという。
追伸:第1回日本モンゴル映画祭が無事終わり、新宿と横浜の映画館に地平線会議の皆さんがたくさん来てくださって本当に感激しました。心よりの感謝をお伝えしたいです。どうもありがとうございました。
■明日が仕事の最終日。あと10時間後には職場である郵便局に行き、20時間後には仕事は終わっていると思う。今までも旅に出るために何度も仕事を辞めた。でも今度の退職は人生の大きな転機な気がする。
◆2005年に北米横断ランニングに出た。帰国して、何か働かねばと思っているとポストに郵便局のスタッフ募集チラシが入っていた。とりあえずそれでいいや、と、始めて、20年が過ぎた。北米ランは自分の中では美しく終わったから、ランニングへの興味は深い場所へと沈んでいった。でも消えてはいなかった。ひっそりと成長していて、とうとう意識の側まで上がってきてしまった。
◆というわけで北米ランの続きをやります。まずは前回の終了地点であるNYに行き、そこから大西洋を越えてリスボンに入り、ユーラシア大陸の西の果て、ロカ岬からスタート。聖地スペインのサンチャゴでコンポスティアーラの巡礼路3本を繋いで、フランスのルピュイまで。おおよそ2500キロ。そのへんでEUのビザ3か月が終わりそう。なので、そこからEUの外に出て走ろうかな、と、アバウトな計画。
◆もともと記録を目指すものではないので、気分でルートは変わる。こんなこと言ったらウルトラマラソンの師匠に怒られそうだけど、もう「走る」でも「歩く」でもどっちでもいい。自分が納得すれば、完結するはず。[3月30日 心が日常から離れつつある坪井伸吾]
■例年になく遅めの開催となった今年のカーニバルは、懸案事項だった南米大陸右肩に位置するフレンチギアナの主都カイエンヌを攻略した。半世紀近い地平線会議の活動でもその地名が登場したことは皆無で、足跡を刻んだ体験者も見つからない。文献記録もない超絶未知の地に刻まれる祝祭はいかなるものか。それより何より現地で驚かされたのは、この辺境が混迷を極める世界情勢の最先端と化していたことだ。
◆仏領ギアナはフランスがいまだに維持している海外地域圏、つまりは植民地の一つで、北海道の面積に人口約30万という超過疎地。旧英領のガイアナ、旧オランダ領のスリナムと並んでギアナ3国を構成し、南はギアナ高地、東は隣国ブラジルにつながるジャングルだが、海岸線を除いて陸路は存在しない。内陸には逃亡奴隷か先住民の小規模集落が点在するだけ、それもカヌーで行き来する川が唯一の交通路だ。もとは帝政時代からの流刑地で、脱獄映画の名作『パピヨン』の舞台になった悪魔島とアリアン宇宙基地を除けば、世界でも有数の希少種昆虫生息地として蝶や甲虫ファンの間でかすかに知られるくらいだろうか。
◆かくも忘れ去られた地に暮らすのは、半数超が奴隷の子孫である黒人系だが、残りは西欧系インド系アラブ系中華系ベトナム系など多彩で、ラオス系の少数民族であるモン族といった変わり種もいる。とはいえ、この辺境の地もフランス共和国の一部で、公用語はフランス語だし通貨はユーロ、パリからは国内線である。
◆カーニバルの音楽や演出などに多少は隣国ブラジルの影響があるかと想像していたが、リズムはカリブ海のマルティニークやグアドループなど仏国文化圏に直結している。広義のラテンアメリカ文化圏といっても、オサレなフレンチ文化の薫り漂うヨーロッパ系祝祭の亜種に分類される存在といえそうだ。
◆「トゥールールー」という全身を飾るロングドレス姿の、まったく肌を露出しない仮面女性(といってもこれでは容姿も年齢も不明)が壁際にたむろする男どもを次々に誘って踊る徹夜の仮装舞踏会が催され、しかもこれは毎年1月11日から毎週末開催の世界最長のカーニバルとされている。全体にまったりだらしなくて濃厚な祝祭空間に、突如勃発する暴力沙汰が香ばしい。残念ながら希薄な人口密度を反映してか、ダンスのノリはよくても人数が足りていない隙間感が漂う。
◆ところで、大河アマゾン河口にはベレンやマカパなど大都市があり、この地へ出稼ぎにくるブラジル人労働者は以前からかなり多かった。加えて、完全に経済破綻したベネズエラからの不法越境者も急増しているという。彼の地ではシリアを超える800万人超の難民が近隣諸国へ脱出し、陸路で米国入りを目指す人々も多い。コロンビアからパナマに至るパナマ地峡は、このベネズエラ難民に加えて、世界中から多国籍移民が集まるホットゾーンと化してきた。アフガンやシリア、イラク、ウクライナ、イエメンなど紛争地からの難民に加え、中国やキューバ、ハイチ、その他アフリカ諸国など、故郷を離れざるを得ない人々は、有り金をはたいてコヨーテと呼ばれる越境業者に命を託す。
◆ところが、米国でトランプ政権が発足したとたんに不法移民狩りが急速に進められ、国外追放処分が現実のものとなった。これに代わる経由地として注目を集めつつあるのが、フレンチギアナになったわけだ。どうにかして国境を越えればそこはもうEU圏。最低賃金の3分の1でいいから仕事をくれ、という違法滞在者の需要はいくらでもある。しかも国内法は出生地主義で、現地生まれの子どももその親もむやみに国外追放することはできない。かくして、アメリカを目指して北上していた難民は、いまやEU圏を目指してフレンチギアナへ移動しつつあるという。しかも、これまでメキシコのカルテルが仕切ってきた麻薬密輸ルートが使えなくなったため、先進国の需要がある限りは代替ルートとしてもこの地は利用され続ける。
◆先般、地球永住計画でドクトル関野氏との対談に登場したゴンザレス丸山氏とすれ違った際、この地の現状を話したところ、次回のクレージージャーニーはここかも、というような展開となったのがおかしかった。GoogleとAIにより空白地帯がなくなったはずの地球も、まだまだ広く奥深くその闇は濃い。カーニバルもまた深淵を漂う異次元空間で、おあとがよろしいようですな。[Zzz-全@カーニバル評論家]
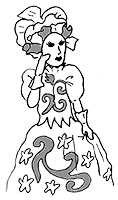
イラスト ねこ
■夕飯に何か食味の違うものを食べたくなり、セネガル料理のメニューが出ていた店へ向かう。「ウサギが食べられるかも」と妻のまきちゃん。いつもと違う料理に期待が高まる。店までは宿から2キロほどか。そろそろ暗い。舗装が壊れてデコボコの歩道に転ばないよう気をつけて歩く。途中にあるぬいぐるみの店(?)に、今日はお客さんが4、5人群がっていた。ここはいつも、路上にはみ出すように広げた布の上に、無造作にぬいぐるみが積み上げられているのだ。ゲームセンターの景品のような安っぽい人形が、車に舞い上げられた赤い土埃をまとったまま山をなしている。これまで何度も通りかかったが、店番をする人を見たことがない。捨ててあるのか?とちょっと気になっていた。売り物だったのだ。そして買う人がいるのだ。
◆アフリカ中央部の西側に位置するカメルーン。首都ヤウンデから長距離バスで7時間ほど北西に走った西部州のこの町チャンは、標高1300mほどあるので、乾季も終盤のこの時期でも、昼間は暑くても陽が落ちれば過ごしやすい。人口は約10万人(2015年の推計)。国立チャン大学もあり、同国ではやや大きめの町だ。今向かっているレストランは大学に近い町外れにあって、街灯もあまりない。薄暗いので停電かと思ったが、バラックのような個人経営の小さなお店にも電灯がついているから大丈夫(ホテルやレストランなどは停電時に発電機を使う所もある)。
◆ようやく辿り着いた店には客がほとんどいなかった。もう店じまいか? テーブルで子供と食事をしていたおばちゃんが立ち上がり、「食事は用意できるけどウサギはない。できるのはンドゥレだけだよ」と。我々が毎日のように食べてるソース料理だ。まきちゃんと顔を見合わせるが、腹も減っているし疲れた。建物の外に天幕を張ったテラス席に座る。途端に停電。珍しく今日は電気が切れないと思っていたのに。お店の人が発電機を回し始めると、夜目にも白い排気ガスが盛大に店の中に噴き出した。なんで店の中に排気口が向いてるの?この匂いの中で食事は厳しい。席を立つのを止めるように、頼んだビールを運んで来たおばちゃんが急いで開栓する。仕方なく少しだけ口をつけ、料理はキャンセルして店を後にした。
◆カメルーンはアフリカの縮図とも言われる。在位37年にも及ぶ91歳の大統領が独裁的に治める多民族国家で、250以上の部族語があり、仏語と英語を共通語に定めている。キリスト教、イスラム教、アニミズムがそれぞれ同程度の割合で普及しているが、宗教的な対立は少ない。一部紛争地はあるが、アフリカでは比較的安定した国だ。赤道に近く、南部の熱帯雨林や中西部の山岳地帯、多湿の海岸沿いに北部の乾燥地帯と、気候帯が多様なのも縮図といわれる所以とか。山の多いここチャンでは、この時期朝方はいつも濃い霧が発生する。
◆チャンをフィールドに、庶民市場の社会学的研究をしている妻にくっついて、3月に初めてこの国を訪ねた。カメルーンは国としての歴史も若いが、人口の年齢構成的にも子供や若者が多く、町中が賑やかだ。ことに市場を歩くと喧騒が凄まじい。ひっきりなしに行き交う人々の売り買いの声、子供の声、バイクタクシーの警笛にスピーカーを通した宣伝文句、時々喧嘩の声も混じる。帰国してから東京の新宿を歩いたら、日本はなんと静かなことかとびっくりした。
◆さて、期待していたウサギにはありつけず、ありふれた停電の夜にすきっ腹で再び路頭に彷徨う我々だったが、この時間帯、いわゆる食堂はなかなか見つからない。おっちゃんたちがたむろする居酒屋的な店は散見できるし、固い焼き鳥や焼き豚を売る屋台などはあちこちに。バーらしき店もあることはあるが、落ち着いて食事ができる場所を探すのが難しい。結局ホテルに程近い、いつもの「エステルの食堂」に行くと、閉めようとしていた店を快く開けてくれた。まきちゃんがエステルと懇意にしているおかげだが、時間的にギリギリセーフだ。事情を聞いたエステルは「最初からうちに来ればよかったのに」と言った。まあね。作りかけの4階建ビル(町中にはこんなビルがたくさんある)の2階にある店内は、もちろん停電で真っ暗。スタッフなのか友達なのかよくわからない3名の女性が我々のテーブルの周りに座り、さりげなくケータイのライトで照らしてくれた。(停電なのに)まだ冷えてる国産のkadjiビールを飲みながら、マカボ芋にスズキのピーナツソース掛けという定食にようやくありついた。同じ食事でもなぜか毎回微妙に違う勘定を支払い、ぱらつく雨の中を幸せな気持ちで宿に戻った。[長野亮之介]
■3月7日から3月13日までの7日間、Vストローム250SXで東北太平洋岸最南端の鵜ノ子岬(福島)から、東北太平洋岸最北端の尻屋崎(青森)まで走った。東日本大震災から14年経ち、今回が第30回目となる「鵜ノ子岬→尻屋崎」。3月7日の10時に鵜ノ子岬の東北側の勿来漁港を出発。その日は四倉舞子温泉の「よこ川荘」に泊まった。地平線会議の集会でも使ったことのある「よこ川荘」は我が定宿で、今回が40回目になる(日帰り湯を含む)。
◆「よこ川荘」には、毎年来てくれている渡辺哲さん、古山里美さん、滝野沢優子さんのほかに、斎藤孝昭さんと小林進一さんが来てくれた。斎藤さん、小林さんとは道祖神のバイクツアー『賀曽利隆と走る!』の「シルクロード横断」や「南米・アンデス縦断」を一緒に走った仲間だが、お二人とも東日本大震災のときはボランティア活動に励まれた。翌3月8日は8時15分に「よこ川荘」を出発。滝野沢優子さんとはここで別れたが、残りのメンバーとは5台のバイクで東北の太平洋岸を北上し、17時、相馬市の蒲庭温泉「蒲庭館」に到着。温泉に入り、タイやイシガレイの刺身、タラ鍋などの海鮮料理を食べながらの宴会。これが楽しい。若女将は地酒を差し入れしてくれた。
◆ところで、「鵜ノ子岬→尻屋崎」の第1回の出発は震災から2か月後の2011年5月11日のことだった。今との比較で、ぜひともそのときのことをもういちど、知ってほしい(あまりの違いの大きさに昔話をするような気もするが)。その前日(5月10日)、常磐道で東北に入り、20時、いわき勿来ICに到着。常磐道はここまでまったく問題なく走れた。夜の勿来の町を走る。大地震、大津波の影響はほとんど見られなかった。常磐線の勿来駅に行ってみると、いつも通りの勿来駅だ。勿来周辺はほとんど被害を受けることはなかった。
◆勿来駅前から東北と関東の境の鵜ノ子岬へ。岬を境にして東北側が勿来漁港、関東側が平潟漁港になる。人影のまったくない勿来漁港岸壁の屋根の下にバイクを止め、その脇で寝る。そこへ渡辺哲さんが来てくれた。うれしいことにカンビールと「バタピー」、「アーモンド&マカダミア」、「チーかま」を差し入れしてくれた。地平線会議の江本嘉伸さんに現状を伝えようと電話していると、巡回中のパトカーがやってきた。「まずいな」と思ったが、「これから北へ、青森までいきます」というと、若い警官は「ご苦労さん!」といって走り去っていった。
◆翌5月11日は鵜ノ子岬から蒲庭温泉まで行ったのだが、それは難行苦行の連続だった。国道6号経由で小名浜に行くと、大津波の生々しい被害を見せつけられた。道路は波打ち、信号はすべて消え、警察官が交通整理をしていた。大津波の直撃を受けた東北最大の水族館「アクアマリンふくしま」は休業中。小名浜港は商港も漁港も大きな被害を受けた。魚市場の建物は残ったが、お目当ての「市場食堂」は休業中。ひとつうれしかったのは、漁港の岸壁に乗り上げた1000トンクラスの大型漁船が3000トン級のクレーン船でつりあげられ、海に戻す作業が完了したことだ。小名浜漁港復興の大きな第1歩になった。
◆四倉舞子温泉「よこ川荘」の前を通ったが、温泉宿はかなりの被害を受けた。だが女将さんは負けてはいない。「できるだけ早く再開しますよ!」との声には元気があった。国道6号沿いの大型温泉施設「いわき蟹洗温泉」は大きなダメージを受けて休業中。海岸のトンネルを抜け出た波立海岸はさらに大きなダメージ。「焼きはまぐり」の波立食堂は無残にも建物がつぶれていた。ほかの国道沿いの食堂も軒なみやられていた。
◆国道6号を北上。いわき市から広野町に入り、さらに行くと、楢葉町との町境に着く。Jヴィレッジのあるところだ。そこが東京電力福島第一原子力発電所の20キロ圏ということで、その先は立入禁止。この20キロ圏の北側に行くのは大変なことだった。バイクの機動力を発揮して五社林道→黒森林道と2本の林道を走りつないで国道399号に出た。そしていわき市→川内村→田村市→葛尾村→浪江町と通って飯舘村の長泥に入った。浪江に通じる国道114号は通行止なので、その1本北側のルート、途中に10キロ近いダートの残る県道62号で原町(南相馬市)に出た。このルートが20キロ圏を迂回する最短ルートなのだ。
◆南相馬市、相馬市の太平洋岸は、あまりにもすさまじい被害に目を覆いたくなるほど。堤防が粉々に砕けているところもあった。かつては100戸、200戸とあった集落が跡形もなく消えていた。そんな中で奇跡の現場があった。一軒宿の蒲庭温泉「蒲庭館」だ。ここは震災直後に営業を再開。夕方の6時過ぎに飛び込みで行ったのだが、心やさしい若女将は部屋をあけて泊めてくれた。夕食も用意してくれた。というのは日本中からやってきた仮設住宅建設の業者のみなさんが泊まっていて満室だったからだ。
◆若女将の津波の話は衝撃的。ちょうどそのときは高台にある小学校での謝恩会だったという。そこからは巨大な「黒い壁」となって押し寄せてくる大津波が見えたという。巨大な「黒い壁」は堤防を破壊し、あっというまに田畑を飲み込み、集落を飲み込んだ。多くの人たちが逃げ遅れ、大変な数の犠牲者が出てしまった。「地震のあと、大津波警報が出たのは知ってましたが、どうせ5、60センチぐらいだろうと思っていました。まさかあんな大きな津波がくるなんて……」
◆「蒲庭館」も我が定宿で、今回が21回目の宿泊になる。その蒲庭温泉を出発すると3月9日は石巻、3月10日は宮古に泊まり、3月11日の午後3時30分、尻屋崎に到着。その夜は八甲温泉(東北町)に泊まった。3月12日は石巻に泊まり、3月13日に鵜ノ子岬に戻ってきた。「鵜ノ子岬→尻屋崎」の往復は1694キロになった。
◆東日本大震災から14年。各地の復興は進み、大地震や大津波の痕跡はもうほとんど見られない。太平洋岸の防潮堤は完成し、三陸道は全線が開通し、災害公営住宅の建設も終わった。高台移転した新しい集落が各地に誕生している。残るは爆発事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所だ。廃炉まであと30年〜40年かかるといわれているが、気が遠くなるような年月、しっかりとその行程を見続けなくてはならない。ということで、我が「鵜ノ子岬→尻屋崎」は、これからもまだまだ続く。エンドレスの世界だ。[賀曽利隆]
■2011年3月11日以降、定期的に訪れているいわき市の四ツ倉舞子温泉「よこ川荘」。賀曽利隆さん、古山里美さんと共に毎年3月に東北の太平洋岸を北上する旅の出発地としている宿です。この宿は目の前を流れる仁井田川を逆流してきた津波により1階が浸水してしまいましたが、半年後には再開させ工事業者を受け入れて地域復興へ貢献してきました。他のお客さんで満室のときでも我々のために無理に部屋を空けてくれたり、時には大広間に泊めてもらったこともありました。
◆今では2階ほどの高さの防潮堤が宿の目の前に完成し、川面を眺めることはできなくなってしまいました。また近くの県道に掛かる橋も新しく架け替えられて、宿周辺の整備も進んできています。最近は工事業者の受け入れはほぼ終わって、落ち着いてきているそうです。宿の女将さんもお元気で、我々の宿泊を毎年楽しみにしてくれています。先日泊まった際は、小名浜港に上がったアンコウで鍋をご馳走してくれました。バイクで走っていく我々に「寒いのに元気だね。気を付けて行くんだよ」と毎回優しい声をかけてくれ、そんなお心遣いがとても嬉しい。
◆震災から14年が経過しましたが、思えばこの宿を通じて復興の軌跡を見続けてきたように感じます。被災から立ち上がり、震災を乗り越えてきた宿との関わりを今後も大切に持ち続け、これからの旅でも訪れたいと思っています。福島の復興と共に。[渡辺哲]
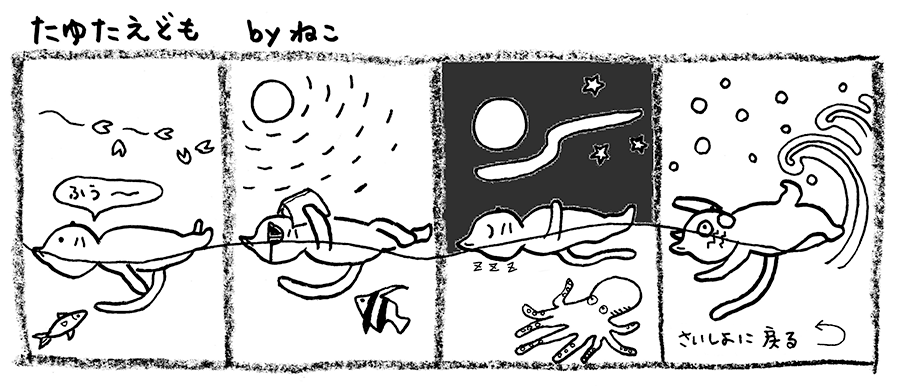
《画像をクリックすると拡大表示します》
■本業の勤めを辞めたのちの人生の基本計画は、「三拠点生活」であった。拠点となるはずだったのは、いま住んでいる東京と、空き家の実家がある故郷の宮崎県小林市、それにスリランカのコロンボだ。できれば故郷には年に3〜4か月住んで家や庭や畑を整備し、野菜を作り食料を確保する。コロンボには年に2〜3か月ほど拠点を置いて、日本から来る仲間とともにスリランカ各地のジャングルで遺跡の探検を続ける——。そんなことを夢見ていた。
◆当初はうまくいくかと思われたし、実際、うまくいっていた。2018年の「スリランカ密林遺跡探査隊」では、以前からの宿願だったタラグルヘラ寺院遺跡の発見に成功し、九州の田舎では古い大きな納屋を解体撤去した跡に、小さな倉庫を作って農具などを整理し、いつでも小菜園を耕す準備ができていた。東京ではもっぱらスリランカでの探検成果をまとめつつ、仲間を集めて次の探検計画の準備を進めていた。
◆その順調な日々の推移を、すべてぶち壊したのは、まず「新型コロナ禍」だった。2020年に計画していたスリランカの遺跡探査は、世界中が「鎖国状態」になったことで頓挫し、田舎に帰るのも「都会からのコロナ持ち込み」を恐れる地元の空気から、憚られるようになった。自分自身も「蟄居」を余儀なくされた八方塞がりの状態は、周知のようにやがて緩んで、2年後の2022年には少し先も見通せるようになってきたので、私はコロンボに飛んでスリランカ政府考古局と協議し、翌年からの探検計画を立てたのだったが……、それをまたぶち壊したのが、「病気」であった。
◆骨髄異形成症候群——。放っておけば白血病になり死に至るので、進行を止めるしかないという不治の病が、発覚したのは2023年6月のことだ。スリランカ側と緻密な計画を詰め、隊員も資金も装備も集まって、7月の先発隊出発からの全日程も決定した矢先に、総隊長だった私は入院し、病室から指揮を執る(実態は現地からの相談に応じるだけ)しかなくなった。現地ではトラブル続きで、己の無力感と隊員らへの申し訳なさを、いやというほど感じた夏だった。
◆病気は、進行を止めるために毎月7日間連続の、いや、その途中には土曜・日曜・祝日が挿まるので、実質9〜10日間の通院治療(腹部への皮下注射)の期間を必要とする。そして毎月の治療期間中と終了後の数日間は体力も気力も萎えるので、外ではあまり動けない。退院後は、それが私の日常となった。つまり、月のうち半分ほどは東京の住居に縛り付けられるのだ。これでは「三拠点生活」も何もあったものじゃない。ちょうど「後期高齢者」にもなったことだし、ここはもう「諦めが肝心」と悟るしかなくなった。
◆以後の私は、そんな毎月のリズムのなかで「動ける時期に、やれることだけをやる」生活を続けている。遺跡探検のためのNPOの理事長職は退き、昨年は夏に2週間だけスリランカに行った。前年の隊の追加調査に行く隊員らとは、コロンボで落ち合ったが、医師の厳命でジャングルには入れずに、自分で設定したテーマの調査をしただけだった。毎年、そんなふうにしてでも、行けるのだったらそれでいい、とは思えたのだが……。
◆九州の実家のほうも、4か月に一度ほど、治療の合間を縫って帰省している。毎回10日程度の滞在で、間も空くから野菜作りは諦めたが、毎回の草刈りと樹々の伐採・剪定などは欠かせない。今年3月には不要となった登山道具のほとんどを実家に送り、「木登り剪定」や土手の草刈りで使用した。高い木の上でセルフビレイして大枝の伐採をしているフェイスブックの写真を見て、三輪主彦さんは「年寄りがそんなことをしてはいけない!」と諫めてくれたが、医師でもある関野吉晴は「気力が充実しているみたいだね」と褒めてくれた。驚いたのは、そろそろ米寿の声も聞こえる宮本千晴さんが、自分もザイルやシュリンゲを使い、「体を縄だらけにしながら」、まだ木登り剪定をやっている、と嬉しい「連帯の声」をかけてくれたことだった。これでは私も、まだまだ頑張らないわけにはいかないだろう。
◆東京では外出できる日が限られるため、「地平線報告会」を含めて種々のイベントや集まりには「不義理」の連続だ。選考委員を仰せつかっているノンフィクション関連の二つの賞の選考会の日程なども、私の体の都合を優先していただいている。一方の田舎では、兼業ながら稲作を続けてきた従兄弟たちが、後継者もいないため、そろそろ「農じまい」を考えているという現実に、足元から「土台」が崩れていく日本の将来を憂え、スリランカでは、行けば行ったで「あと何回来られるだろうか」と焦りを覚えずにはいられない。「それでも、まあね……」と、仲間や友人知人の皆さんには申し訳ないけれど、いまはまあ、こんなマイペースでやっていますので、どうぞよろしくという、やや居直りの近況報告でありました。スミマセン。[岡村隆]
■この一文は2025年4月1日に書いている。エイプリルフール、4月バカの日。世界的にウソを言っていい日になっている。ということを前提に以下、虚実織り交ぜて書きますので、そのつもりで御用心の上お読み下さい。3月のある日、江本さんから電話「次の地平線通信、3バカたかしの賀曽利と岡村が書くから、山田も書かんわけにはいかんでしょ」「そりゃ、いかんですね」てな話があった。過去20数年、年に2回、お中元とお歳暮のころ、江本さんから連絡あり通信に寄稿してきたが2か月続けてはなかった。3バカの先輩御二方が登場とあっては新参バカとしては失礼があってはいかんと書いている。
◆5月から、南房総の館山市に引っ越します。2017年末に四万十より奥多摩に引っ越して、森の仕事をしながら高野秀行君のお供で、イラク、トルコ、中国の川巡りの旅をしてきた。このたび、念願の海の見える館山に新居を購入した。1958年、高知県足摺岬の突端で生を受けて以来、中学校を出るまで海を毎日見る幼少期を過ごしたので、ときどき無性に海が恋しくなる。いろいろ課題があり、あと数年奥多摩の森暮らしをしてから、海辺に移る予定を少々早めた次第。奥多摩の7年で、初心だった我が人生の3学を明確に思い出し再学習していた。曰く、今西自然学、梅棹人類学、小松探検学である。1970年代後半に大学探検部(農大)で過ごしたころ、世界中に飛び出し帰国した先輩方から「本を読め」とよく言われた。勉強不足を痛感したらしい。探検部室に、本多勝一編集の『探検と冒険』が卒業生贈物としてあった。この全集の中に、1956年、本多勝一が日本最初の京大探検部を作ったときの顧問の重鎮今西錦司、梅棹忠夫ほか京大旅行部(現山岳部)初期の方々の対談もあったと記憶にある。今西錦司は晩年、自然全体を総合して瞬時「永遠の今」に掴む、独自の今西自然学を提唱していた。梅棹忠夫は「地球時代の人類学」を著し、植民地主義を脱した新たな人類学を模索していた。SF作家小松左京は『探検と冒険』で「一方通行の少年期の探検から相互交流の壮年期の探検の時代」が来るべき探検だろうと書いていた。3氏ともヨーロッパ人主導の科学観に異を唱えていて、小生の琴線に響いた。20歳代、30歳代はいつもこの3学を意識していたが、「頭で考えるより、体で行動する」を優先しているうちに、いつの間にか忘れていた。1978年農大入学以来、我が探検人生は奥多摩の川と山から始まり、日本中、世界中に拡がった。だから、若いころの日々をここで思い出し、再学習するには絶好の場だった。この3学プラス2学=5学が小生の今後も続ける課題だが、長くなるので、その詳細は別の機会に譲る。
◆さて、南房総の海では、長年温めてきた夢がある。乙姫号と織姫号による、7つの海と銀河の空へのあらたな航海だ。南房総はその昔、阿波国の漁師たちが移り住んだのが、安房国の由来らしい。四国への望郷心をそそる。そして屋久島にも安房港があり、長江下りとチャド植林時代の後輩、野々山富雄がガイドのレジェンドとして現役でいる。野々山の協力を得て館山と安房港を母港にする帆船にして太陽光発電船の乙姫号はすでに進水している。隣の種子島宇宙センターには、南米3大河川カヌー行の親友松岡誠が農水省の技官として働いていたころ、4人姉妹の一人が嫁いでいて、その尽力で宇宙船織姫号も造船中である。2000年正月、当時のベースにしていた四万十中流の十和村で成人式の記念公演をした。演題は好きなのをとのことで、「青い星の川を旅して木を植えて」を初めて使った。サブタイトルに「木を植え、林を育て、森を愛で、川に託し、海に恋し、星を想う」とした。そのとき、世界の海と宇宙への夢も話した。それ以後、密かに2つの船の計画を進めてきた。地球大学の練習船である。
◆もうお気づきでしょう。2つの船の話は、4月バカのウソ(ホラ=夢)です。でもその前の話も1970年代はウソ(ホラ=夢)でした。人生至る所、青山あり、緑水あり、自然あり、人類あり、探検あり。やりたいことは尽きない泉の水のように湧き出してきます。奥多摩ではナラやブナの森を歩き回りましたが、館山のフィールドはシイやカシの照葉樹林です。[山田高司]
■地平線通信551号の発送作業は、3月12日、19時には無事終了しました。プリンターのトラブルによる宛名ラベルの欠落を伊藤里香さんが発見。急遽手書きで対応しました。この後、北京のあとに開店した「新北京」(そういう名前で開店しているのに驚嘆した)は満席で入れず、近くの小さな洋食屋に。意外に美味しく、ハンバーグ定食は1300円とそんなに高くもなく、今後もこういう作業の後は、この手のお店もいいかな、と思った次第。作業に参加してくれた方々は、以下の皆さんです。長岡のりこさんが手作り小倉あんであんパンを作ってきてくれたほか、白根全がチョコレート、武田君から出張先の三沢土産の南部せんべいの差し入れあり、感謝。発送仕事に参加してくれたのは以下の皆さんです。
中畑朋子 車谷建太 伊藤里香 落合大祐 高世泉 白根全 長岡のり子 武田力 中嶋敦子 江本嘉伸
■私はこの春に法政大学を卒業し、北海道大学環境科学院に進学しました。卒業論文では、南極大陸の冬至の祝祭「ミッドウィンター祭」をテーマに、南極観測隊の活動成果を記載した報告書『南極観測隊報告』の祝祭に関する記述と、南極観測に携わる方々へのインタビューをもとに、その姿を調査しました。研究の中で最も興味深いと感じたことは、同じ祭であっても隊によって見方・捉え方が多様であることです。太陽から最も離れた極夜期のどん底の日に祝われるこの祭ですが、例えば初期の観測隊は「単調な基地生活における娯楽」という認識にとどまっていましたが、その後の隊では「祭による疲労が良い睡眠をもたらす」とか「後半に向けた英気を養う」のように、各々の隊が新たな価値を見いだしていく様子は調べていてかなり面白かったです。「自分の足で調査し論文を書く」ことは簡単なことではありませんでしたが、楽しみながら研究できたことは大学院への進学を決意するきっかけになったと思います。
◆大学院生活の中でやりたいことは数え切れないほどあり、一日が24時間では足りません。研究テーマは担当教員と相談中ですが、北極圏やグリーンランドをフィールドに人文社会学的な要素で研究ができればと考えており、いずれは南極に行きたいと思っています。講義や実習では、これまで東京の大学ではできなかった実践的な学びを得て研究に生かしたいです。慣れない土地での忙しない日々に戸惑いもありますが、この刺激的で雄大な環境を堪能したいと思います。
◆東京を離れる直前、梶光一さんの報告会レポートを担当させていただくことになり、その打ち合わせで江本さんとお会いしました。大学卒業祝いも兼ねてスイーツをご馳走になり、さらにその後には「エモ散歩」に連れていっていただきました。JR武蔵小金井駅から南に向かって野川(幼い時よくメダカやザリガニを獲った懐かしい川です)に下り、川沿いを歩き、多磨霊園を通って浅間山の山頂まで、途中休憩も挟みながら2時間ほど歩きました。不思議な時間でしたが天気が良くて暖かく、とても気持ちのいい「エモ散歩」でした。江本さんの新聞記者時代の話から犬が大好きという話まで、たっぷり語り合うことができて嬉しかったです。江本さん、貴重な経験をありがとうございました。[北海道大学環境科学院修士課程1年 杉田友華]
■立正大学に入学してから早くも1年が経過した。私の大学生活は、音楽に染まりきったものだった。心理学において興味を持ったことを探求するでもなく、特に勉学に励むでもなく、ひたすら音楽活動に打ち込んでいた。入部早々に何故か新入生歓迎ライブに出演させられ、一度も歓迎されないまま軽音楽部の一員となることになった。ライブでは常に前線に立たせてもらい、幸せな限りである。
◆また、軽音楽部では大きな出会いもあった。同級生で凄腕のギタリストがいるのだが、高校時代メンバー同士の揉め事により、思うようにバンド活動ができなかったのだという。彼を私のオリジナルバンドに招き入れ、グループを結成した。先日、ライブハウスからライブ出演の依頼をいただき、私自身も初となるオリジナルバンドでのブッキングライブも決定した。これから波乱万丈な日々が幕を開けるのだ。[長岡祥太郎]
■先月の通信でお知らせして以降、通信費(1年2000円です)を払ってくださったのは以下の方々です。万一記載漏れがありましたら必ず江本宛メールください。通信費を振り込む際、通信のどの原稿が面白かったかや、ご自身の近況などを添えてくださると嬉しいです(メールアドレス、住所は最終ページにあります)。
マングローブ植林行動計画 (10000円 未納の何年分かの通信費です) 長野恵 清登緑郎(3000円)
◆今日は入学式だったが、級別はわからない。明日の始業式でわかる。育英資金要望書に記入のためレントゲン検査を受けに行った。生まれてはじめて血沈検査もした。帰りにジュディー・ガーランドの「スタア誕生」を観た。迫力ある胸を打つ映画でジュディー・ガーランドとジェームス・メイスンはますます好きになった。本当に感激した映画はこの他に「シェーン」と「エデンの東」それから「山河遥かなり」等である。
■昨年の10月「地平線通信546号」に蛇を襲うイワナの話を載せていただいた。その後、京都に住む釣り少年の話が、ある新聞に載り私の目にとまった。高校生になった彼は小学生のころから渓流釣りを楽しみ、現在はヤマトイワナを追い求めているという。そのフィールドが木曽川源流部だと。
◆私の故郷は木曽川沿い岐阜県境の小さな町。木曽川でいえば中流域よりやや上流部である。もちろんその支流にはイワナが生息しているが多くはニッコウイワナである。では一体、木曽川のどこにヤマトイワナが生息しているのだろうか。
◆イワナは「渓流の王者」といわれ、中でもヤマトイワナは渓流アングラーから羨望と畏敬の念をもって「渓流・孤高の哲学者」の称号を受けている。そのヤマトイワナの純系保存と繁殖を試みている「長野県水産試験場木曽試験地」をこの3月末、私の国鉄時代の先輩で木曽漁協組合長の案内で訪ねることができた。中央アルプスの主峰、木曽駒ケ岳の麓の静かな森と綺麗な水が流れる場所にある。北大出身の研究者と職員たった二人で大小58面ある試験池を管理しているのである。その理由はヤマトイワナは多くの人間の管理を嫌うからだという。だから見学は厳しく管理されている。
◆さて、採卵、受精までは比較的安易に進むが、孵化し稚魚となる直前でヤマトイワナは人為的行為、つまり餌付けを極端に嫌うのである。そこで、孵化直前の卵を漁協と協力し、山奥の源流に種苗するという。逆にニッコウイワナはそれらが比較的軽くクリアされ成長も早く、多くの河川で放流されている。その結果ヤマトイワナは最上流の僅かな住処へと「移住」させられている。
◆では何故に木曽川でヤマトイワナの保護と繁殖は成功しているのか。木曽川源流部は御岳山と中央アルプスに囲まれ、湧き水が豊富で夏でも水温15℃以下、冬は5℃前後に保たれ、しかも水質が彼らに適しているという。しかし、その根底には試験地の研究者と漁協の並々ならぬ努力と協力がある。日本の本州は「サケ科イワナ種」が棲む地球上の最南端である。しかし、年々その住処を失っている。中でもヤマトイワナは住処と生息数を急速に減らしている。地球温暖化と人間の行為がそうさせているのか。
◆繁殖や養殖が比較的容易なニッコウイワナ。人間の行為や干渉を極端に嫌うヤマトイワナ。京都の釣り少年のヤマトイワナに寄せる熱意と愛情が私の思いをかりたてた。少年に感謝である。[松本市 田口哲男]
■今年度も中学3年生の担任になりました。今回で3年生を受け持つのは6回目。自分で希望したのではなく、選ばれたというわけではなく、学校全体の人事の影響によってそのポジションに収まるということが多いです(人事希望で毎回「一任します」と書くため)。
◆6回目だけれど、生徒は毎回違います。様々なことが昨年通りにはいきません。教員という仕事の面白さだと考えていますが、生徒一人ひとりの考え方や性格、体調などを見て、声をかけたり、授業を工夫したりしていく必要があります。そして、必ず生徒同士のトラブルや人間関係の悩みが出てきます。大人ならある程度距離感を持ったり、気持ちを切り替えたりすることができますが、生徒は「自分」も「周り」も、とにかく気にする年齢です。教員の仕事は、そんな生徒たちと一緒に悩んだり、考えたりして成長に寄り添うことだと思っています。
◆うまくいかないことがわかっていても、まずは生徒の考えを大事にしたいです。一緒に悩むことはAIにはできません。そして、一緒に悩んだ後の判断(これからどうしていくか)は生徒に任せます。最終的に生徒が「自己決定」できることが、自立につながり、一人の人間として大切にされていると感じるきっかけになるといいなと思っています。
◆江本さんや山田隊長(山田高司さん)と出会った四万十ドラゴンラン(2007年)のときは、教員の道を目指すか悩んでいた時期でした。江本さんや山田隊長を始め、そのとき参加していた人生の先輩方が、真剣に私の話を聞いてくれたことを今でも覚えています。ゆっくりカヌーを漕ぎながら、温かいボルシチ(江本さん特製)を食べながら、お話しできた時間をイメージして、寛容な心で生徒の話に耳を傾けたいと思います。また、「今」を生き生きと過ごしている地平線の皆さんの生き方や視点が、考え方のヒントになることが多いです。あるクラスの、たった1年間ですが、目の前の生徒をしっかりと観察し、成長に寄り添っていきたいと思います。[静岡 クエこと杉本郁枝(中学校教諭)]
■昨年11月に、地平線キネマ倶楽部で「すばらしい世界旅行」シリーズでの代表作ともいえる「クラ—西太平洋の遠洋航海者」の上映の機会を得た市岡康子です。わたしは80代半ばにしては基礎疾患もなく、健康体を誇っていましたが、新年早々、夜中にベッドから立ち上がった瞬間に転倒し肩を骨折して入院手術、腰椎もいくつか潰れてこちらは自然治癒を目指して鎧のようなギプスを装着しています。「すばらしい世界旅行」の撮影中にフィールドでかかった感染症(急性肝炎、デング熱、赤痢)で3回入院した以外、自前の病気で入院したのは初めてです。
◆プロデューサーの牛山純一さんが“非ヨーロッパ世界の民衆の生活様式や価値観”を日本の視聴者に紹介することを目指して「すばらしい世界旅行」の企画に取り掛かったのは1965年夏でした。日本が敗戦の日を迎えてやっと20年、テレビの放送開始から12年目でした。牛山さんはNHKの「日本の素顔」とともに、日本のテレビドキュメンタリーの始まりとされている「ノンフィクション劇場」をすでに制作していて、この中でベトナム戦争に従軍した『南ベトナム海兵大隊戦記』を監督として制作していました。この作品は3部作を目指しながら、1作品目が放送されるや、2作目以降は放送中止の憂き目にあいました。戦場の実相が衆目にさらされるのを怖れた米国の介入という見方もありました。この1年後に始まった「すばらしい世界旅行」を評して、「牛山は硬派から軟派に転向した」などと言った放送評論家もいますが、内側から見ていた私にはベトナム戦従軍こそが、次なるシリーズへとつながったように思います。
◆ベトナムはアメリカと闘って勝利した数少ない国と民衆ですが、彼らが徹底抗戦して戦ったのはその歴史にあったのでしょう。何百年も中国王朝の植民地支配に苦しみ、独立闘争を押しつぶされてきて、次にはフランスに支配された民衆の民族独立に対する渇望を理解できず、共産主義に対する楯にすることしか考えなかったアメリカの政策は、かの地の歴史や民族感情への無理解から発していることを現地で痛感したようです。日々起こる戦争や事件、つまり時事問題を扱うのが放送の主流ですが、その背後にある「異なった環境や社会に暮らす民族の伝統的な生活と文化の核」を知らずして、これらを本当に理解することはできないと考えたからです。
◆しかし当時は海外取材など夢のまた夢、海外渡航の経験があったのはベトナムに行った牛山さんとスタッフだけでした。外貨事情も悪く、持ち出し外貨枠は500ドルでした。これでは番組制作はできないので、プロジェクトごとに日銀に特別枠を申請するのですが、領収書を添付して事後報告の必要がありました。欧米などならホテルや車代、食費など領収書がとれますが、フィールドの主流だった発展途上国ではそうはいきません。ニューギニア縦断を試みた先輩、豊臣靖ディレクターの清算報告には、字の書けない荷物運び数十人のポーター一人ずつが署名代わりに書いた「おしるし」の束がついていました。
◆取材地は首都から遠く離れた僻地で、航空ルートも旅行代理店任せとはいきません。現在ならネットに目的地を入れれば簡単に路線も料金も出るでしょうが、当時は電話帳より厚い通称「ABC」2冊と首っ引きでフライトスケジュールを自分で確定し、代理店に発券依頼をするのが普通でした。
◆現地に入ると、今度は移動のための車や船が必要です。レンタカー屋などなく、伝手をたどって個人からピックアップ・トラックを借りるとか、モーターボートや船外機をもちろん有料で借りることになりますが、この手配で消耗します。いっそのこと車の通れる道路がなく、歩くしかない方が諦めもつきます。
◆さて居住場所ですが、上映した「トロブリアンド島」の場合は、撮影の中心になる村で、あるときはヤム芋の貯蔵庫に入り口と窓を開けてもらって居住用に転用、キャンプ用のコッヘルとケロシンバーナーで自炊生活です。村は水場の近くにあるので、洗濯や水浴びは小川に行き、トイレは自分たちで指揮して掘ってもらいました。当時の取材先の村々ではトイレのありかを聞くと「あっち」と指さされ、その方向に行っても建物らしきものは見つからず、バナナ林の奥などがそれにあたるという風でしたが、これには閉口で最低の設備を自前で整えたのです。
◆たいていのロケ地でお米は手に入りましたが、副菜は単調になりがち。どこでも手に入るのはサバのトマト煮の缶詰めとコンビーフ缶が中心で、野菜の類はほとんど入手できず、初めに持ち込んだ玉ねぎなどを大事に使いました。タイの山中ではかぼちゃと冬瓜、トロブリアンドではヤム芋が野菜の代理でした。フィルムケースの底に敷いてあった週刊誌の裏表紙にマヨネーズの広告として野菜サラダの写真など見つけると、あこがれの思いいっぱいで見とれたものです。
◆トロブリアンド島では沿岸のマングローブの林で蟹がとれます。マッドクラブという名の通り少し泥臭いですが、身入りのいい蟹です。島人は土曜に取りに行って取れた蟹を売りに来ます。物々交換でスティックたばこと交換しました。一回断ると2度と持ち込まれないので、全部買い取りますが、生きたままだと爪や足がしっかり結んであっても、夜中にごそごそ動き出すし、犬が狙うので、入手した蟹を全部ゆでて身だけにします。スタッフ4人で一日中蟹を剥いたこともあります。蟹入りピラフ、卵とフーヨーハイまがい、つぶしたヤム芋に混ぜてカニコロッケなど、手のカニ臭さが数日続いたほどです。サバ缶とコンビーフとは違い、“フィールドのグルメ”と言えるでしょう。

■原健次・典子夫妻の長女、戸田由起子さんからメールがきました。ご本人が遠慮されていまは地平線通信を送っていないのですが、通信551号を読んだ旧知の富山県の読者が知らせてくれたとのこと。そうとは知らずに私から今月の通信を送ったのが届いたという次第。典子さんの遺稿に登場する彦根市の妹さんからの感想ともども紹介します。[江本]
■こんばんは。夜分遅くにすみません。地平線通信、本日届きました! あらためて紙面でも拝見させていただき、お心遣いに感謝しております。昨年、父の13回忌と母の7回忌の法要を一緒に行いました。亡くなってからも今もこうして思い返していただき、父母も喜んで空から眺めていると思います。私が股関節の手術で、3か月半入院している間、一歳で両親に預けていた息子も4月に大学生になります! 直接報告したかったなぁ~と、寂しい気持ちもありますが、きっと近くにいて見守ってくれているとも感じています。今後とも地平線会議のご発展と江本さんのご健康、心よりお祈り申し上げます。お礼まで。[花巻市 戸田由紀子(原健次・典子長女)]
■地平線通信を送っていただき、ありがとうございました。姉の手記を、改めて読む機会をいただき、当時のことを思い出しました。私は3人姉妹の末っ子です。福岡へ行った姉が、具合が悪くなり無事に宇都宮に帰れるのか心配していたら、帰りの新幹線の連絡をもらい、いてもたってもいられなくて時刻表で彦根の近くを通過する時刻を調べて、新幹線が見える高台がある所へ行きました。
◆付き添いの姉とメールでやり取りをしながら、新幹線を待ちました。一瞬のことなので、良く見える様にと思い、着ていた上着を脱いで、大きく振りました。あっという間でしたが、上の姉から、二人が手を振っているのが、ちゃんと見えたと、メールをもらったときは、嬉しかったです。姉夫婦が、付き添ってくれたので、無事に帰れたと思います。そのことを姉が手記にしてくれて、また当時のことを思い出すことができて、本当によかったです。
◆今回の通信には原健次と典子の思い出が書いてあり、今まで知らなかったことを沢山教えてもらい、ありがとうございました。大切に保存しておきます。[彦根市 徳留容子(原典子妹)]
■横浜の花田麿公さんからメールをいただいた。
◆わたしがかつて、前世紀の前半に起こった日本の戦争について、日中戦争、インドシナ戦争、東南アジアとその旧植民地本国との戦争、日ソ・日モ戦争、太平洋戦争をアジアの戦争であり、日本がからむ戦争ですので、西欧、南米は含まないので第二次大戦というにはしっくりこず、いずれも昭和に発生したので、「昭和戦争」と呼ぶことを提案しました。
◆ところがナベツネさんが、昭和という時代精神を背負った戦争と言う意味で昭和戦争を提案されていたことを最近知りました。理由が異なれど、同じ用語に嬉しく感じますとともに、ナベツネさんの理由が、歴史的には正当なのでしょう。戦後、先の戦争、つまり昭和戦争について、いちばん厳しく、一番きっちり判断を下されていて、その行動が一致していたのはナベツネさんでありましたので、腑に落ちました。
◆渡邉恒雄についての評価はさまざまだが、花田さんの論評はとても大事と考えている。[江本嘉伸]
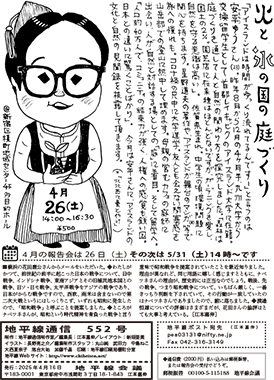 |
火と氷の国の庭づくり
「アイスランドは時間がゆっくり流れてるんです!」と言うのは安平(やすひら)ゆうさん(23)。昨年8月から12月の4ヶ月半、九州大学から交換留学生として首都レイキャビクのアイスランド大学に在籍。庭づくりを通して人と自然の関わり方を探究しました。 「森林は国土の2%。園芸店に在来種はほとんどないですが、ガーデニングを愛し、自然を守る意識は高い」。佐賀県生まれ。中学生の頃、環境問題に関心を持ちます。星野道夫の著作や、アイスランドが舞台のマンガ(*)等で旅への憧れも。 コロナ禍の只中に大学進学。友人とも会えない閉塞感を山岳部での登山に熱中して埋めます。母親の営むカフェの庭師に出会い、人が自然と対話する場としての「庭」に着目。そして留学へ。「人口約40万人で、コミュニティの結束力が強く、人権への感覚も鋭い国。日本との違いに驚くことばかり」。 今月は安平さんにアイスランドの文化と自然の見聞録を披露して頂きます。(*『北北西に曇と往け』) |
地平線通信 552号
制作:地平線通信制作室/編集長:江本嘉伸/レイアウト:新垣亜美/イラスト:長野亮之介/編集制作スタッフ:丸山純 武田力 中島ねこ 大西夏奈子 落合大祐 加藤千晶
印刷:地平線印刷局榎町分室
地平線Webサイト:http://www.chiheisen.net/
発行:2025年4月16日 地平線会議
〒183-0001 東京都府中市浅間町3-18-1-843 江本嘉伸 方
地平線ポスト宛先(江本嘉伸)
pea03131@nifty.ne.jp
Fax 042-316-3149
◆通信費(2000円)払い込みは郵便振替、または報告会の受付でどうぞ。
郵便振替 00100-5-115188/加入者名 地平線会議
|
|
|
|
|
|