

1月
1月15日。世界が固唾を吞む中で2025年がスタートしている。ドナルド・トランプがこの20日、2期目のアメリカ大統領に就任するのだ。もうバイデンもカマラも昔の人だ。1人の人間が国を超えてこれほどのインパクトを与えつつ登場するとは誰が予想したか。そして、日本のリーダーはこの剛腕男にどう対処するのか。
◆お隣の韓国では尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の「非常戒厳」措置をめぐって緊迫していたが、つい先ほど15日午前11時前、内乱の容疑で大統領の逮捕状を取った「高位公職者犯罪捜査庁」(いかめしい名だ)が「内乱を首謀した疑い」で拘束令状を執行、大統領はついに拘束された。これからどう展開するのか。
◆12月28日、2024年最後の地平線報告会は盛り上がった。日頃、この通信の印刷に頑張ってくれている車谷建太君の初めての報告会であること、そして長くお世話になったお馴染みの中華料理店「北京」がこの日で閉店し、最終営業日を地平線会議貸切にしてくれたからである。建太君の報告会は実に面白かった。こんなに長くつきあってきたのに彼について大したこと知らなかった、と反省。内容のある報告だったので今月の報告会レポートは思い切って長めです。
◆北京最後の宴も賑やかだった。地平線会議から花束を「ママ」細貝容子さんに贈ったほか、彫刻家の緒方敏明さんが特大の陶器の餃子をママとお店のスタッフにプレゼント、さらに建太君の三味線に長岡竜介さんのケーナで皆が合唱し、最後は万歳三唱までしてしまった。ありがとう、北京、ママ、皆さん。
◆翌29日、早起きして上野駅に向かう。何度目かの能登行きを計画した落合大祐君が誘ってくれたのだ。思えば2024年は、元日に起きた能登の震災と羽田空港の航空機衝突、炎上事故で始まった。能登では地震の復旧が進まない中、9月21日には集中豪雨で山が崩れ、家々が森に呑まれた。金沢駅からレンタカーで行く。落合君がよく道を知っていることに驚く。自転車で各地を旅をしていることは知っていたが、なんと日本の海岸線をすべて踏破しようとしているらしい。え? 何千キロ?
◆あちこち漁港が多い。石川県内の漁港69のうち、60か所が海底の隆起や津波で被災した、と新聞は伝えている。能登は北前船で栄えた半島なので陸の交通路は他の地域ほどには重要ではなかったのだ、ということが来てみて実感された。2日間の行動については、現地で迎えてくれた東雅彦君と、落合君自身のレポートに詳しい。年の終わり、友の助けで深刻な被災地の現場を見ることができたのはありがたかった。
◆東君の実家のある町野町では父上の家と少し離れた母方の実家に入らせてもらい、荒れ果てた住居の様子に衝撃を受けた。3.11の時、支援作業としても他人の家にボランティアがずかずか入り込むことは許されなかった。ついこの間までこういう生活があったのだ、とご先祖の遺影、家族の写真を拝見しながら胸が締め付けられた。東君、落合君、ありがとう。
◆年が明けて初詣は、上田の白蛇さまに行った。以前ここに書いたかと思うが、正式には「宗教法人松尾宇蛇教会拝殿」。昭和に入って建てられた新しい教会で本殿と離れた祠には白く、太い木の枝が蛇のようにくねった形で安置されている。白蛇さまである。正月以外には扉は閉められているが、内部は伺えるので上田に行く時は必ず白蛇さまを拝みに行く。
◆蛇というと思い出す景色がある。まだ4歳の頃、父方の故郷である愛知県知多郡の田舎に家族で疎開した。当時、都会から田舎に疎開する者は貴重な食料を食い潰すからという理由で歓迎されなかった。近所に「大野がんつ」(大野部落のガキという意味か)と呼ばれる子供グループがおり、私たちを見つけると石を投げてきた。その都度、稲や麦の畑に逃げ込んで頭を抱えてしゃがみ込んだものである。
◆ある日、田んぼの畦道を歩いていると蛙が泳いでいるのに出くわした。その後に長いものがついている。蛇が蛙の後足を咥えて泳いでいるのだった。私と姉は懸命に石を探して投げ、蛙を解放しようと試みたが、2匹はどんどん離れていってしまい、引き離すことはできなかった。
◆夫のラドワンとシリアに入った小松由佳さんが帰ってきた。アサドが去った喜びとともにサイドナヤ刑務所はじめ虐待のひどい現場に胸が締め付けられたという。8歳になったサーメルにむごたらしい現場を見せる羽目になったことも。さまざまな思いでシリアの地を踏んできた由佳さんにお願いして2025年最初の地平線報告会を開きます。歴史的な報告会になるでしょう。1月25日、遠路の人も是非![江本嘉伸]
■2024年を締め括る車谷建太さんの報告会は、三味線の弾き語りでスタートした。♪~むかあしい むかあしい 私 車谷の先祖は 越中富山の薬売りでございました。♪~ 当時は 日本中に富山から 薬を運んでいたわけでして ♪~ 私の祖父の祖父 つまり曾々お爺さんは 富山の滑川という町を出て ♪~ 山を越え谷を越え また山を越え 海に出ました。♪~ そこは伊豆の国 下田の港町。曾々お爺さんは そこで恋に落ちました。♪~ 季節は巡り やがて曾お爺さんが産まれました。めでたきかなめでたきかな~! ベベベンベンベン♪~
◆「三味線には、元来、歌舞伎や浄瑠璃などの伴奏の役目がありました。テレビのない時代、世界中で物語と音は共にあり、ぼくは楽器のそういう一面が大好きです」。その狙い通り、のっけから、会場は心地よい語りの世界に包まれた。
◆祖父も下田で生まれた。彼、車谷弘は文学青年だった。気の進まない東京薬学専門学校で学んだ後、菊池寛が立ち上げたばかりの文藝春秋社に薬剤師として入社。文学界の旧き良き時代、内田百閒ら個性的な文士たちと交流しながら、最後は編集長にまで登りつめた。その祖父は、1978年、建太さんが1歳半のときに他界した。だから記憶にはない。けれど、彼が作家たちとの交流を綴った「わが俳句交遊記」を読み、その人柄や人物を見抜く力、人と距離を取って接する人生術に感銘を受けた。母方の車谷姓を、建太さんは22歳のときに継いでいる。
◆「小学生のころは、まだ地元に空き地や駄菓子屋があって、いまは桜の名所の目黒川も鼻を摘まないと渡れないドブ川でした。教科書にもヘドロ川の代表として載っていて、授業で紹介されたときは教室がシーンとしました。それが、大人になるまでの間に恵比寿にガーデンプレイスができたり、どんどんお洒落な街に変わっていったんです」。
◆一方で車谷少年は、夏休みなどには伊東の祖母の家に通い、カニやヤドカリをとって遊んだ。その自然との触れ合いは、いまも貴重な体験となっている。小学5、6年のときは「お受験」で勉強に集中し、中学から大学までの一貫校に進学。中高ではバスケに明け暮れた。街の学生生活をエンジョイしていたが、20歳のとき、突然、日本の伝統的な暮らしに興味を持った。
◆親戚に農家がなく、日頃食べている米のこともわからない。それを知るためにも、日本を自分の足で歩いて見てみたい。そんな思いから、18きっぷと寝袋を手に出たアテのない一人旅。そこで強く感じたのが、色々な人の家に泊まる面白さだった。
◆「能登半島でバス待ちしていたとき、少し年上の女子二人組が声を掛けてきて、一人が『旅してるんでしょ。ウチに寄ってって!』って宝塚の実家の電話番号を渡してくれたんです。半信半疑でしたが、電話したら弟さんが迎えに来てくれて、六甲山を案内してもらいました。夜は、兵庫県の知らないその家で、味噌汁飲みました。その不思議さと嬉しさでドキドキしたぼくは、『受け入れてもらえた。この旅は面白くなるぞ』と思ったんです。翌朝、お母さんが、自分の子供にするようにお握りを作って持たせてくれました。それを食べているうちに、人情の温かさを知りました」。
◆その後、「農業を体験したい」の思いで、宮崎から鹿児島を目指して100kmほどを歩いた。が、願いはなかなか叶わない。ある日辿り着いた都井岬の露天風呂で一緒になったお爺さんも、「俺が見つけてやる」と翌日軽トラに乗っけて探してくれた。けれど、農業経験もない都会の若者がアポなしで行っても、断られるだけ。最後、「ここが駄目なら諦めよう」と立ち寄ったサツマイモ集荷場でまさかの歓迎を受け、ようやく居場所が見つかった。
◆7、8人いる従業員の家に、交代で泊めてもらうことに。仕事はサツマイモの検品・ランク分け、箱詰め、スタンプを押して発送などなどだったが、誰もがユーモアに溢れていて笑いが絶えない。お蔭で単調な作業にもかかわらず、少しも飽きなかった。集荷場には、毎年一番優秀なイモを運んでくるベテラン農家がいた。その老夫婦に、「この子、もらってゆくよ」と引き取られ、ついに志布志のサツマイモ農家へ。日中は畑で汗を流し、夜は御飯を美味しく戴いて温泉に入る。ぐっすり眠って、翌日、また働く。そんな、机上ではわからない、学校でも教えてくれない農家の普通の暮らしに、初めて触れることができた。
◆三味線に出会ったのは、その旅から戻ったころだった。バスケ部の加藤士文(しもん)先輩に誘われ、彼の練習についていった。そこで、ラーメン屋の大将にして師匠の西村伸吾さんが弾く、津軽じょんから節に衝撃を受けた。東京生まれで祭りとも縁がなかった車谷さんにとって、そのリズムは新しくて懐かしく、また、エネルギーにも強く惹かれたという。
◆季節はちょうど桜の時期。大将と士文さんは、翌日、多摩川の桜並木で流しをやる。「お前もやれ!」と、車谷さんも一棹あまっている三味線を渡された。そんなのできるわけがない。断ったが、お酒も入った江戸っ子気質の大将は聞かない。「お前は横でチンチロチンチロ弾いてりゃいい」と押し切られ、3人で土手に立った。
◆「大将は、一番端っこの見晴らしいのよい土手に陣取りまして、じょんから節を弾いたんです。ぼくはリズムに合わせてチンチロチンチロをひたすらやりました。そしたらどんどん人が集まってきて、けっこう拍手が起こるんです。一か所終わると、別のグループから『こっちでやってくれ』と呼ばれまして、そこで座って演奏するんですけど、割り箸に挟んだりティッシュに包んだお札が飛んでくるんですよ、こちらに。ぼくが人生で見た初めてのおひねりでした。それだけじゃなく、なみなみとコップに日本酒が注がれたり、ホタテの貝柱を御馳走になって、歓迎されるんです。酔っ払ったお客さんに『俺でもできるぞ』と三味線を取られたりもして、気付いたら桜並木の2kmを走り切っていました」。
◆川があり、桜があり、楽しそうな酔った顔があり。その光景に、「江戸時代にタイムスリップした」と感じた。しかも、それを外側からではなく、演奏する側から見ている。人と人の垣根を取っ払う歌の力に圧倒され、「この音はどこから来るんだろう」とぼんやり考えた。そのときは言語化できなかったが、のちに「ぼくの田舎暮らしの憧れは、昔の暮らしへの憧れだったんじゃないか。三味線も、ぼくが旅で目指した昔の世界からやって来て、その時代の物語をたくさん知っている。自分の旅は、この楽器、この音色がどこから来たかを知るための旅だ」と悟り、「あの日こそが人生の転換期だったんだ」と気付いた。
◆車谷さんは、1年間かけて三味線を猛練習した。そして翌年、3人で再び同じ土手に立つ。「この日、甲子園の決勝戦で沖縄尚学高校が優勝したんです。あの辺りは沖縄出身の方が多く、大きな車座が何組もありました。大将の西村さんも奥さんが沖縄の人なので、沖縄の曲を弾けます。その車座の中でカチャーシーの曲を弾いたら、もう皆さんが立ち上がって踊り出すんですね。『凄いぞ、凄いぞ』と思いながらぼくは必死で付いていったんですが、なんだかお札の色が違うんですよ。でも、沖縄の人にすればお金のあるなしじゃない。めでたい席にその音が来れば反応するし、三味線を持っていない自分たちにそれを提供したぼくたちへの、感謝の気持ちもあったと思います。この写真、夕方の駐車場なんですけど、楽器ケース開けたら風でお札がパーッと飛んで、拾い集めて数えたら、土日の2日間で30万円もありました。沖縄尚学が優勝したミラクルもありましたが、こういう、沖縄と音楽と三味線との貴重な体験をしました」。
◆日本を旅し、三味線も手に入れた車谷さんの関心は、次にモンゴルへと向かった。いまだに電気もガスも水道もない遊牧民の暮らし。一時は世界を支配する大帝国を築きながら、いまは小さな落ち着いた国に戻っている。そこに感じた「人が、出て行った土地にまた還ってくる」的な魅力にも惹かれた。ただ、どうやってゆけばよいのか。そこで、渋谷のインターネットカフェに出掛け、「モンゴル」「ホームステイ」などのキーワードで検索。たった1件ヒットしたのが、山本千夏さんのmongol horizonだった。
◆彼女が現地で会社を設立し、乗馬ツアーなどを始めたタイミング。そこには「一発芸求む」みたいな煽り文句もあった。早速、国際電話を入れると「来なさい。そんな君を待っていた」のリアクションが。そのモンゴルでは、ウランバートルから800kmほど北のオラン・オールで乗馬ツアーを体験し、その後も他の参加者と別れて居残った。「晴れて遊牧民との暮らしが始まりました。憧れの草原が目の前にあって、ニコニコした子供たちがいて。こんなにワクワクする状況はないですよ」。
◆あえてモンゴル語の辞書は買わず、三味線一丁だけで来たから、言葉はまったく通じない。けれど徐々に意思疎通ができるようになり、1日のルーティーンを学んでいった。朝起きると、子供たちと一緒に牛の柵を開け、乳を搾る。井戸まで何往復もして羊やヤギの水を汲む。川で魚捕りもした。夏は午後9時くらいまで明るい。夕食後もみんなで遊んだ。ホームステイ先は、モンゴルの北部、中央、南部の3か所で組まれていた。それぞれの違いを体験できるよう、との千夏さんの計らいだった。そのトータル1か月を、車谷さんは、チーズを干したり、ジャムの材料のベリーを採りに行ったり、牛糞を集めて乾かし、お茶を沸かしたりして過ごした。
◆モンゴルでは、来客があったときなどに羊を屠る。すでに何度か、車谷さんも現場を見てきた。そんなある日、「ケンタ」と呼ばれ、「今日は君の番だよ」と告げられた。「来ていきなりだったら怖くて出来なかったんですが、3週間くらい一緒に暮らして、家族のように愛している羊たちの水を汲んだりしてましたから、心の準備もできていました。
◆屠殺のやり方は、羊の胸にナイフを入れ、そこから手を入れて指で首の大動脈を引きちぎります。ケンタがやるんだ、ということで凄く丁寧に真剣にリードしてもらい、ぼくもその気持ちが嬉しくて、必死にやりました」。そのとき、車谷さんは「自分の手の中に命をスッと受け止める」のを感じたという。「それは、滞在中もずっと細胞では理解していましたが、草原にいると目に見えるすべてが循環しているのがわかるんですよね。
◆雨のひと粒にも無駄がなく、草に入って羊たちが食べ、それを食べる人間も土に還ってゆく。日本ではなかなか辿れなかった基本的な人の暮らしの、そこにある、何か「水脈の井戸を汲みに行く」みたいな感覚……。このモンゴルに来てみんなと同じ呼吸の中で暮らし、最後に羊の屠殺をやらせてもらいました。それは、ぼくの人生にとって特別で、凄く大事な経験でした」。
◆モンゴルの人たちはよく歌う。中でも印象的だったのが、ろうそくを囲んで器に注いだアルヒという酒を回し、それぞれ飲んでは1曲歌うルールだ。順番が回ってきたとき、車谷さんも「椰子の実」を歌い、号泣してしまったという。報告会会場では、「可愛い仔馬」という歌を披露した。子供から教わり、井戸へ水汲みに行くときなどに歌っていた曲で、車谷さんは、帰国後もシャワーを浴びたりしながら歌っている。そうすると、「4Kくらいの鮮やかさ」でモンゴルの草原が目の前に甦るのだ。
◆帰国後、車谷さんの人の縁は津軽へと広がった。ラーメン屋の大将が津軽三味線の全国大会シニアの部で優勝し、酔っ払った勢いで地元の名人・渋谷和生さんを口説き、直々にラーメン店で東京教室を開く話をつけてしまったのだ。その流れで、車谷さんも彼の弟子となった。「『津軽のカマリ』って向こうの人は言うんですけど、津軽三味線には、土地の訛りや感覚が曲のフレーズに入っています。ぼくがステージで弾いていると、『おめぇの三味線っコは、まだまだ東京弁だなぁ』と言われます。吉田兄弟や上妻さんたちは凄腕ですが、県外者。渋谷さんは青森出身で、5歳くらいから民謡の世界に入り、歌も歌えるし、伴奏もやってきました。聴いている地元の農家の人も涙を流しているんです。その師匠の演奏を横で見ながら「盗む」んですが、指から物語りが紡がれてゆくのが見える。そういう本物の現場へ行けて、本当に勉強になりました」。
◆音楽の道が開ける一方で、もう一つのテーマ、「伝統的な農村暮らしを知りたい」にも新たな展開が訪れた。最愛の祖母が95歳で亡くなり、目黒の家から下田まで、リュックを背に歩いて墓参りした途中、「ちょっとお兄さん、ゲストハウス作ったから寄っておいで」と、軽トラのお姉さんにチラシを渡された。その南伊豆は、車谷さんも知らない土地だった。が、行ってみると、日本昔話に出てくるような昔ながらの里山が続いている。
◆ゲストハウスの向かいでは、車谷さんと同い年くらいの夫婦が田植えの仕度をしていた。聞くと、自給自足をするため、川崎から移り住んできたという。念願の田植えのまたとないチャンス。「ぜひ手伝わせて欲しい」と、挨拶もそこそこにお願いした。その「まーくん」こと金子雅昭さんも、オーストラリアを旅したり、お遍路を廻ったりしてきた人物だった。すぐ仲良くなり、田植えの後にお礼とお別れを言おうとしたら、「建太、稲刈りもおいでよ」のお誘いが。それから10年通い続け、金子さんたちの試行錯誤の無農薬農業を手伝っている。
◆「農家って、1年に1回しか結果が出ないんですよね。50年やっても50回しか試せない。まーくんは、草取りとか頑張って、1年目から凄い結果を出しています。そうやって自分で汗を流したお米は、やっぱり美味しいです。地獄のような草取りとか、そこで聞いた虫の声とか、そういうものが米一粒に全部入っているんです。和太鼓集団の鼓童は、「生きる」を「息る」と捉えていて、まず呼吸を知ることが大切だと言っています。そして、自分たちの音を出すために、佐渡島で暮らしながら日本古来の米作りのリズムを養おうとしています。ぼくはそのために通った訳じゃないけど、とても勉強になりました」。
◆2007年9月、車谷さんは金井重さんの報告会で、津軽三味線を演奏した。そのとき、一番後ろで聴いていたウルトラマラソンの海宝道義さんに声を掛けられた。自分が企画する宮古島の100kmマラソンで弾かないか、朝5時、景気付けにキミの津軽三味線をみなに聞かせたい、というのだ。その誘いに乗って当日600名のランナー出走と同時に演奏し、コースでバナナなどの補給をする「エイド」も手伝った。
◆せっかくなので帰りの飛行機を1週間伸ばし、島に残った。なんのアテもなかったが、スタッフで来ていた妹尾(日野)和子さんがトランスオーシャン航空の機内誌「コーラルウェイ」の編集者で、沖縄にめっぽう詳しい。そこで相談すると、平山さんというおじさんの連絡先を教えてくれた。「早速電話したら、『明日昼のフェリーで伊良部島に来なさい。三味線持ってきてね』と。港で笑顔で迎えてくれまして、車に乗せられて辿り着いたのが伊良部小学校だったんです。その体育館に全校生徒が集まっていて、多分ぼくの人生で最初で最後だと思うんですけど、『歓迎 車谷建太』ってメチャメチャ大きな横断幕が用意されているんですよ。ぼくも「なんで?」と思いましたが、嬉しくて、みんなの前で三味線を弾きました。そのあとも、平山さんが宮古高校の音楽授業だったり、幼稚園だったり、どんどんブッキングしていくんです。アッという間に1週間のうち5日間くらいが埋まりました。その行く先々のオジイ、オバア、子供たちの目の色が、見たことないくらいキラキラしてるんです。離島ってこともあるんですけど、尋常じゃないんですよ、皆さんの好奇心の眼差しが」。
◆「何でこんな化学反応が起きるんだ」と車谷さんは驚いた。けれど、思い当たるものがあった。リュート属楽器の三味線のルーツはエジプトだ。それが西に行ってギターやバイオリンになり、東はシルクロード経由で約500年前に沖縄へ伝わった。津軽に辿り着いたのは、たった百数十年前のこと。沖縄のオジイにすれば、三味線は三線の孫みたいなもの。「それを持った青年が目の前を通れば、捕まえないワケはない」と車谷さん。
◆「ぼくが有名かどうか、腕が良いかどうかなんて問題じゃない。三味線が人間や音楽と一緒に移動して根付く、例えばその昔に瞽女さんが北陸から東北に伝えた、そんな瞬間があったはずです。文化と文化が本気でぶつかった瞬間、凄いエネルギーが噴出するし、感動があります。その一番風を、ぼくは一番目の前で感じることができた。これこそが、三味線と旅が掛け合わさった旅の醍醐味だなって気づいたんです」。
◆宮古島で揉みくちゃにされたときの人々の目の輝きは、江戸時代のそれと違いはない。車谷さんは確信した。ちょうどそのころ、関野吉晴さんがグレートジャーニーをやっていた。同じ視点で見れば、津軽は三味線の終点だ。鮭が源流へ上るように、そこからたった一人が沖縄に来ただけで、こんな化学反応が起きてしまった。そう考えたら、音のグレートジャーニーのイメージが湧いてきた。ラクダに乗って、三味線担いでエジプトをゆく……。「これ、誰もやってねえぞ、って気持ちで顔を上げたら、台湾という島国が、ぼくに向かって扉を開いて待っていたんですよ。ここに行くしかない」。
◆そこで、報告会の会場で誰かれ構わず「台湾に行きたい」と話した。すると本所雅佳江さんが本を貸してくれ、相川弘之さんは台湾に住む知り合いを紹介してくれた。その片倉佳史さんは、歴史や鉄道の著作もある作家だった。訪ねてきた車谷さんの「三味線を持って台湾の人と交流したい」という希望に、さっそく東海岸の、先住民訪問旅のアテンドが決まった。ただ、準備には数日掛かる。折悪しく台風が迫っていたが、片倉さんの「暇だったら腕試しに行ってみたら?」のアドバイスで、北の港町・淡水を訪れた。
◆「広場に着くと、トランクで腕時計売ってる行商人みたいな人とか、いっぱいいるんです。そこでぼくも三味線組み立てて掻き鳴らしました。最初はみんな驚いて、遠巻きに見てるんです。そんな中で、笑顔の女性が『なんで来たの?』と話し掛けてきました。先ほどの理由を答えたら、『だったら、あなたに紹介したい人がいるわ。明日、ちょうどライブがあるから一緒に行きましょ』って、アーティスト名を書いた紙をくれたんです。
◆その夜、片倉さんに『ストリートやってきましたよ。そこで、こんな紙もらったんですよね』と見せたら、目を丸くして、『車谷君、キミは運が強過ぎる。この人は台湾の北島三郎だよ。ぼくの経験から言わせてもらえば、君の旅で、この人以上に相応しい、出会うべき人はいない』というんです。その陳明章さんは、台湾の三味線である月琴や、伝統的な北管音楽、南管音楽、クラッシックやオペラまでマスターした、神様みたいな人なんだそうです」。そして片倉さんは、「ぼくは忙しくて行けないから、妻の真理を通訳に連れていけ」と送り出してくれた。
◆野外のライブ会場で昨日の女性リニーさんと合流し、コンサート後、3人でステージ袖を訪ねて陳さんに挨拶した。すると、彼が両手を挙げて言った。「お前みたいなヤツを待っていた。明日、うちに来い」。次の日、真理さんの付き添いで陳さん宅を訪問。まだ幼い子供や、月琴の生徒らを紹介された。「夕飯をご馳走になったとき、真理さんが目を丸くしているんです。『どうしたの?』って訊いたら、陳さんは毎月、恆春にいる月琴の人間国宝の朱丁順先生が地元の生徒さんに開く教室に通ってるんですが、そこへキミも連れて行くって話してる、と言うんです。でも、ぼくは先住民ツアーの計画がある。『どうしよう』と真理さんに言ったら、『なに言ってんの。こんなビッグウエーブに乗らないワケがない。私たちのツアーはどうにでもなるから行きなさい』と背中を押してくれました。翌日、半信半疑で約束の時間にホテルの玄関を開けたら、もうタクシーが停まってて陳さんが手を振ってるんですね。そのまま台北の駅に行き、新幹線で一緒に弁当を食べながら、恆春に向かいました」。こうして、それから16年間で、お宅に500泊もする陳さんとの付き合いが始まった。
◆2008年の初訪台から16年。その間には何度かブランクもあった。東日本大震災翌年の訪問も4年振り。それを待ち兼ねたかのように陳さんから、彼が創設した「台湾月琴民謡協会」と、青森の渋谷師匠が会主の「和三絃会」との姉妹縁組の話が出た。
◆陳師匠は、車谷さんと出会う前から津軽三味線をよく知っており、それぞれの土地に楽器が根付いていることや、月琴も盲目の人の生きる手段だったことなどを話題にしたという。日本の、芸能の故郷の人たちとの月琴を通じた交流は、そんな陳老師の大義でもあった。そして翌年、双方から各々20数名が参加した、第一回「日本・台湾友好音楽祭」が弘前で開かれた。
◆その、いつも控えめで謙虚な車谷さんが「ぼくの人生で一番誇れること」と胸を張るイベントは、想像を超える苦労の連続だった。たった一人のスタッフとして、企画書作りからプレゼン、ボスター作り、会場やバス、音響機材の手配、市長の表敬訪問などに奔走し、「国際交流ってこんなに大変なんだ」を身を持って知った。おまけに、津軽は良くも悪くも閉鎖的。シャイな土地柄だ。外の世界の芸能に触れる機会も少なかった。
◆けれど、フレンドリーで人懐っこい台湾の人たちのパワーで、ワークショップは津軽の人たちにとっても楽しく有意義な時間となり、また、交流会で地元の手踊りや唄に触れた陳師匠も大満足だった。こうして、「一人の旅人のぼくがですよ、台湾の月琴と津軽三味線を結婚させたんです」の音楽祭は、成功裏に幕を閉じた。同イベントは、その後も2015年と17年に開かれている。
◆2015年、車谷さんは、正式に陳さんの音楽グループ「陳明章&福爾摩沙(フォルモサ)淡水走唱團」の一員となった。他のメンバーも、台湾内外から集まった優れたミュージシャンたちだ。いつも自然体の陳さんは、あのプレゼンテーション番組のTEDにもフラッと何の準備もなく出演し、月琴の講義も演奏もサラリとこなす。ついつい気負ってしまう車谷さんに、「力むな、テイク・イット・イージーだ」と語りかけ、忍耐強く見守ってくれている。
◆コロナ禍のブランクの後、24年3月、久々に台湾を訪れた。仲間たちがどうやって音楽活動を続けていたのか、また自分のポジションが残っているかもわからない。でも、まずはみんなに合ってハグしよう。そんな思いだった。が、すべては杞憂だった。6月の「総統府音楽祭」にも陳明章&福爾摩沙淡水走唱團として参加。その情景は、地平線通信8月号に生き生きと描かれている。
◆車谷さんが、これがあれば人生は幸せだ、と大事にしているキーワードが三つある。一つ目は、「何百年を超える三味線もそうだけど、世界を大きな尺度で見ていきたい」という、スケール。二つ目が、「サツマイモ畑で出会ったときから、人生の豊かさにとって絶対に必要だと思った」のユーモア。最後が、「セッションなどでは、ギターとかベースとかドラムとかが何もないところから風を起こすように音を出し、だんだん音楽になって、ワッショイワッショイと躍動感が出てきます。それは音楽に限りません」という、音楽用語の「グルーヴ」だ。
◆「みんなと呼吸を合わせて、直感で楽しくやってれば、未来も大丈夫なんじゃないか。ぼくは楽観しています」。車谷さんは、なぜいつもにこやかで、穏やかな空気を纏っておれるのか。恐らくそれは、これら旅の経験で得た哲学から滲み出しているのだろう。残り時間が迫ってきたところで、話題は一転。スライドを交え、通信がどのように刷られ、封入され、発送されるかが、駆け足で紹介された。2時間半の「誰も知らなかった車谷建太」は、最後にお馴染みの「印刷局長」に戻り、本年ラストの報告会は終了した。
◆エピローグ:報告会レポートを書くにあたり、電話で追加取材した。その幾つかはレポートに活かしたが、驚いたのは、本番に備えてきちんと綿密なリハーサルまでやったこと。さすがはミュージシャン。けれど、「作ったら終わりだ」の思いでカンペは用意しなかった。野菜や米作りへの関心も、気分的なものではなく、実は深い思考に基づいており、大学時代には先生から「尖っている」と見られるほど、先進的かつオルタナティブな考えの持ち主だった。そして、こうも。「三味線という旅の杖は、ぼくにとって1000年の時間すら超えるタイムマシーンであり、音楽の畑を耕す鍬であり、その向こう側のご縁と繋がる道具なんです」「ラダックやトルコにも行ってみたい。いつエジプトに辿り着けるか判りませんが、風が吹けば……」。長く遠く、魔法の杖を手に、旅は続く。[久島弘]
■報告会に向けて人生を振り返ってみて、いかに自分は『ご縁』に恵まれ、そのご縁にいかに支えられてきたのかということを身に沁みて感じました。昭和時代の幼少期に都会と伊豆の自然を行き来しながら育ち、小学生のころにアニメで観た「母を訪ねて三千里」が僕にとっての最初の旅のイメージでした。まだコンビニの少ない日本を巡り、たくさんの人の家に泊めさせていただいた経験は今となっては貴重な財産です。
◆そして巡り逢った三味線という楽器。「日本人の暮らしを知りたい。たくさんの土地を巡りたい」一心だった僕を導いてくれ、唄というものがその土地の暮らしや歴史の物語そのものであることを教えてくれ、やがては「世界は唄で繋がっているんだ」という自分の世界地図を授けてくれました。「三味線は僕にとって旅の杖なんです」と表現しましたが、この杖のおかげでたくさんの土地や人と出逢い、物語を交換して、さらにその先の土地を耕してゆけるような感覚が芽生えました。
◆長い人生の途上では「こんなことをしていて本当に自分の人生は成就するの?」とか「自分には音楽家としての才能はさほど無いのにこの道のりを歩んで行けるの?」などと途方に暮れることも多々あるのですが、そんなときに決まって背中を押してくれるのもまたご縁の力でした。出逢った人々の愛情だったり、これまでに自分の心に描いてきた世界から来るワクワク感だったり。心の奥底の方から湧いてくるそういった力が自分自身をその先へと押し上げてくれるのでした。
◆僕はたまたま三味線を手にしましたが、僕自身の人生の本質的な願望は「人の暮らしのなかに飛び込んで一緒に呼吸をし、愛情を分かち合い育みたい」という一点に尽きるのだとも思います。だからこそそんな一つ一つのご縁を大切にしたいのです。今思えば、モンゴルや米作りなど、その旅路の出逢いの過程の何かひとつでも欠けていたら台湾での陳老師との出逢いには辿り着けなかったのでは?とさえ思います。
◆報告会でお話ししたように、今は台湾で陳老師をはじめとする仲間達と一緒に同じ景色を眺めてゆきたい一心で三味線に取り組んでいます。陳老師が背中で教えてくれている『自然体』というオープンハートな究極の人生術。師匠から受け取った「Take it easy」の精神を胸に、これからも旅の杖を通じて「三味線のグレートジャーニー」をかなりゆっくりとしたマイペースではありますが、歩み続けてゆけたらと思っています。
◆二次会は地平線会議がずっとお世話になってきた「北京」での最後の宴となりました。「ありがとう」では言い尽くせない気持ちを三味線も交えて皆さんと一緒に北京の皆さんに手渡すことができ、そんな運命的なお役目を果たせたことがとても嬉しかったです。ご紹介した通り榎町センターでは、毎月熱々のこの通信の発送作業を皆で和気藹々と楽しげにやっていますので、皆さん是非ともふとしたときにふらっと立ち寄ってみてくださいね。きっと幸せな気分になれますよ。いつでもお待ちしています。このたびはご清聴ありがとうございました。[車谷建太]
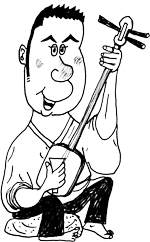
イラスト 長野亮之介
■12月29日、年の瀬を故郷で過ごそうと暗いうちに都内を出発した。566km、9時間30分、我が身に起こった2024年の出来事を振り返るには丁度よいドライブだ。あの日のうめき声、夜空が赤く染まっていたこと、何もできない無力な自分、お金に価値がなくなること、すべての財を失うと我先にと人を助けようとすること、すると、みんなが心で繋がっていくこと、そして奪われるものには大した意味はなく命の他に大切なことなど何もないと地震と豪雨で実感させられたなということを反芻していた。
◆30日7時30分、能登町天坂のファミリーマートに到着。ここは1月3日に父と無事に再開出来た場所だ。父の安堵した表情は心に残っている。この場所で28日に能登半島へ入っている江本さんと落合さんと合流する段取りをしたが旅の予定は変わるもの。10時30分に故郷町野唯一のスーパーもとやで落ち合うことになった。
◆3代目社長の一知(本谷一知さん)を江本さんと落合さんに紹介。地震の日から、1日も休まず故郷のみんなの心の拠り所、灯火となっていた、もとやスーパーだったが、9月21日に奥能登豪雨が発生した。致命傷だった。もとやスーパーそばの五里分橋で流木が引っ掛かり川の流れが変わった。みるみるうちにスーパー入口から店内に土砂が流れ込み、大木が突き刺さった。あっという間の出来事だった。
◆もうこの場所でスーパーをやっていくことは難しいと肩を落としていた一知だったが故郷輪島の野球部員が店内に流れ込んでしまった土砂をかき出す姿、多くの人々の応援で、負けていられないと再度立上りわずか2か月間、11月にスーパーを再開させた。故郷の人らは「町野のロッキー」と一知のことを呼んでいる。
◆一知は大晦日は年越しそばをみんなに配るし、元旦には餅つきをしてみんなに食べてもらいたいから必ず来てと私に話した。餅つきは吉野屋さんに協力してもらうとのことだった。
◆吉野家さんの現社長、吉野さんは私の1つ上の先輩だ。吉野さんは地震にこてんぱんにやられていた。だから餅つきイベントは吉野さんにと背中を押しているのだ。この一知の笑顔と気配りは先代の一郎さん譲りだなと思った。学生のころ、吉野さんと私はよく争いになっていたけれども今は私は痛恨の傷みを分け合う仲間だと思っている。
◆豪雨は町野トンネルを流れて町中を水浸し、甚大な被害をもたらしていた。これは、地震で踏ん張った気持ち、積み重ねた想いを根こそぎ流してしまった。さて、もとやスーパーを後にして江本さんと落合さんに私の実家と母親の実家の中を見ていただき、町野町の町内から、私の学生のころの通学路、輪島市街地、焼け焦げてしまった朝市の現状をみてもらいながら2台の車で移動した。
◆その間、電話を繋ぎっぱなしにし、外の風景を説明しながら2人に私の想いを聞いていただいた。時間は有限である。最後に子供のころから食べていたソウルフード8番らーめんに3人で立ち寄り江本さんは醤油らーめん、落合さんと、私は塩バターらーめん、それから3人前の餃子を頂いた。食後、お二方は地元新聞を買って帰るとのことで、ここで見送り別れた。
◆私はその足で、震災前からライフワークとしている撮影を行うため、千枚田へ向かった。この日は冬の奥能登らしく晴れたり雨が降ったりするグズついた天気だったが晴れ間に恵まれ撮影することができた。これが2024年の最後の撮影になった。大晦日、朝から天候が悪く一日中ほとんど雨が降り強風が吹いていた。
◆まるで昨年末のようで嫌な感じがした。2023年11月8日はM7の地震がインドネシア付近で発生している。2024年11月15日に、M6.7の地震がパプアニューギニア付近で発生した。どちらもリング・オブ・ファイア上の出来事で日本もその線上に位置している。そして両年共に年の瀬に虹がよく出た。似た経緯を辿っている。
◆時を遡ると2011年2月22日にM6.1の地震がクライスト・チャーチで発生している。故郷の友人知人と「追い討ちがなけりゃいいな~」とか、「欲しい物は何もないです。こうして平穏に生きていられるだけでありがたいです」と話し合った。こうした不安な思いを胸中に抱え込みながら大晦日を過ごしたのが故郷みんなの本音だろう。
◆2025年元旦10時、私はもとやスーパーの餅つきイベントに参加した。吉野さんは慣れた手つきでよいしょーっ、よいしょっと杵臼でつかれた餅をきな粉餅と、つぶあんこ餅にこしらえていく。「流石、手慣れてるな~」と私がつぶやくと、吉野さんは「なんも、1年ぶりでだめや。なまっとる」とつぶやく表情はとてもうれしそうにしていた。とても美味しかった。
◆もとやスーパーの一知にこれからのことを聞くと、「地震と豪雨でお金に何の価値もないことがよーくわかった。スーパーの中に流れ込んだ土砂を出すのにどんだけお金がかかることか。もうお金は全部もらった。だから、これからは恩返ししていくだけやわ」とこれからのプロジェクトを話してくれた。
◆16:10、黙祷を終えてようやく新年を迎えられたような気がした。ちょうどSNSで連絡が入った。母のことを慕ってくれていた職場の歳下の同僚からだった。何事も起こらず時計の針が10分を過ぎて心が少しだけリセットできたという内容だった。私は町並みを眺めていた。県道沿いの家から公費解体が進んでいる。町の光景は少しずつ変わっている。だけども解体が終われば、何もなくなる。誰もいなくなるし、どうなっていくんやろね、と視線は遠く、寂しそうな故郷の声色を思い出していた。[東雅彦]
■2024年1月1日に能登半島を襲ったM7.6の地震のことを「元旦の地震」と表現する人が多いのは、日没間近の夕暮れが夜明けの雰囲気を感じさせたからか。16時10分は「元日の朝から午前中」という定義に当てはまらないけれど、新年の華やいだ空気を覆した衝撃を表現するのに「元旦の地震」はそれほど違和感がないような気がする。
◆年末に1泊2日でまた能登へ行くことにした。今回は江本さんと2人旅だ。心配していた雪は上がったが、のと里山海道は強い向かい風。此木の交差点に出て、珠洲道路へ直進。1月の渋滞が幻に思えるほど交通量が少ない。江本さんも人の少なさ、車の少なさが気になっているようだ。
◆珠洲道路のひび割れはほぼ修復されており、のと里山海道よりも走りやすい道になっていた。桜峠は心配したほど積雪なくてよかった。あんなにボコボコだった神和住のあたりの道路も奇跡のように修復されていた。
◆まずは珠洲市。飯田の旧街道は思ったより建物が残っていたが、年の瀬に営業しているのは床屋だけだった。2016年の写真と比較すると、あいあいパークの手前のタクシー屋がなくなり、建物もかなり歯抜けになっている。道路にはまだ泥が残っている。「シーサイド」はもぬけの殻で、看板が強い風に揺れていた。「シーサイド側のイルカの壁画の建物は奥能登国際芸術祭の作品会場でもあり作品もあったんです」とあとで東さんからメッセージもらったが、そのときはイルカに気付けず、残念。
◆国道249号を若山川沿いに遡る。田んぼが広がる山田は、9月にその川が氾濫したのか水害の跡があった。大谷峠の下、大坊に出て、国道は「この先通行止め」のサイン。でも向こうから走ってくるクルマもあるので、Aバリが片側だけ置かれた交差点をそのまま進む。次第に周囲の雪が深くなってきて、トンネルの手前で本当に通行止めに。どうもみんな旧道を通っているらしい。後ろに富山湾が見える。小さな地蔵が立つ峠を過ぎたところで、東さんの写真にあったような日本海の水平線が見えた。15時すぎ、日が暮れかけているし、凍結も心配なので峠を越えずに引き返す。
◆森本真由美さんが学生時代に調査で滞在されていた火宮を訪ねる。人の姿はない。川が溢れた跡が見え、その上の広場にプレハブの仮設が建てられていた。東雅彦さんが元日に地震と建物倒壊に遭遇して足止めを食ったのは、まさに火宮の建設会社の前だった。東さんの目の前で崩れた大きな家は、すでに更地になっていた。戻って鵜飼の町中に出ると、津波に襲われた痕がほぼそのままになっていた。もう1年経つのに!
◆宝立中学校は大丈夫だった。見附島へは東さんが元日の一夜を過ごしたファミマの角を曲がって、国道にいったん出なければならなかった。駐車場から見覚えのある松林を進んでいくと、沖合に禿頭になった島。地震の崩落で痩せ細ってしまった。案内板も津波にやられてスカスカに
◆その晩は「縄文温泉の宿 真脇ポーレポーレ」で1泊。無料入浴支援は11月から輪島市、珠洲市の登録者だけになっていた。露天風呂の夜空に、オリオン座が見えた。
◆翌朝8時。真脇漁港まで降りて一服。朝日が眩しい。トンネル抜けて小木へ。朝の小さな港町を一周する。港近くはバッテンの描かれた建物ばかり。それでも通勤するクルマ、人影があるのが嬉しい。
◆海沿いに宇出津へ向かう。静かな湾に面した海岸はまるで津波を想定していない。きのう訪ねた鵜飼なども想定外の津波だったはずだ。人間の考える「科学」がどんなに浅いものなのか思い知る。
◆宇出津から柳田温泉を抜けて町野川沿いを下る。北丸山は静まり返っていた。その先で交互通行。1月は通れなかったところだ。
◆佐野の先が9月豪雨で土石流災害があったところ。「山津波」とはこういうことか。7月の庄内豪雨と同様、想像を絶する大量の雨が局地的に降り注ぎ、木々や土を押し流すのだ。地球温暖化が収まらない限り、こういう豪雨災害がこれからも各地で発生するのだろう。これまで見たこともないような災害に、私たちは備えなければならない。それにしても地震と同じ場所を狙うとは、雨の神様を恨む。
◆町野の中心、五里分に着くと、もとやスーパーの駐車場に東さんの顔があった。10月の通信に「世界一温かい」と東雅彦さんが書いていたスーパー。一緒に話している赤いジャンパーをもとやの若旦那、本谷一知さんと紹介された。6月にVストローム250で訪れた賀曽利隆さんに熱いコーヒーを入れてくれた人だ。こういう人が能登に残っているのはほっとする。
◆NHKのクルーが来て、本谷さんの仕事の合間に質問していく。店内は手前にスーパーの売り場、奥がボランティアの拠点に分けられていた。壁の上のほうに9月の浸水の跡。裏から屋根に上がってしのいだのだそうだ。電器屋のほうは傾いていて、公費解体するらしい。
◆東さんに町野から輪島市街地までを案内してもらった。猛火に襲われた朝市通りは更地になっていた。Wikipediaに写真が載っている3階建てのビルも解体されていた。3人で一回りするうち、雨が強くなってきた。いろは橋は通行止め。川の西側までは延焼せず、対岸の火事を不安に観ていたのだそうだ。
◆2011年の東日本大震災と比較すると、復興のための支援も予算もまるで足りていなくて、愕然とするほど遅い。この13年間、少子高齢化、地方の過疎化、円安と物価の上昇など社会課題は解決するどころか、増えるばかり。それが自然災害の被害をより悲惨なものにしている。でも「対岸の火事だからどうにもできない」と諦めてはいけない。
◆直接手助けできなくても、想像力を広げて身の回りの防災意識を高めることや、作り手の顔を思い浮かべながらその土地の産品をできるだけ選ぶことが、災害対策や復興の役にたつ。そして百聞は一見にしかず、ぜひ能登半島を訪ねてほしい。
◆最後に3人で訪ねた8番ラーメンは大混雑だった。餃子は一昨日の「北京」のと比べ物にならなかったが、お腹いっぱいになった。[落合大祐]
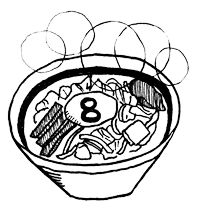
イラスト ねこ
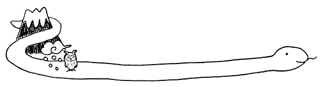
■鷹匠の松原さんに弟子入りしてから初めての冬が訪れました。私は11月からワシミミズクのボーボを訓練しています。ワシミミズクは大きさも体重もクマタカくらいある最大級の猛禽です。フクロウの仲間ですから愛嬌もあるのですが、少し神経質な子で、いつも一緒にいる私や松原さんに対しても「フーッ」と威嚇の声を時々あげます。
◆ある日私がボーボの体重を計ろうとしたとき、オレンジ色の瞳で私の顔を見上げてきましたが次の瞬間、私の顔めがけて飛び上がってきたのです。「まずい!!」。そう思い手で顔をガードしたのも束の間、ボーボは手をすり抜けて、私の顔につかみかかってきました。ものすごい衝撃と激痛が加わるのを感じ、鮮血がポタポタと畳に落ちるのを右目で確認し、すぐに隣の部屋にいる松原さんを呼び、頭にがっしりと爪を立てているボーボを引きはなすのを手伝ってもらいました。
◆もしかしたら左目はもう駄目かもしれないと不安に思いながら左目を開けると「見える!!」。私はこのとき心の底から安心したのでした。
◆師匠からはいつも「据え回し(鷹を腕に止めて1日中歩き回ること)の鬼になれ」、「雪洞とまりの鬼になれ」と言われている毎日ですが、私の行く先にはどんな鬼たちが待ち受けているのでしょうか。[宗萌美]
■宗さんがボーボに襲われたのは11月28日の朝。隣の部屋から「顔をつかまれた!」という宗さんの切迫した声に「まずい!」と思いながら急いで駆けつけると腰を折るように前かがみになった宗さんの顔面につかみかかっているボーボの姿。爪の長さだけでも4センチ、その握力は人間の大人の2倍ほどもあるワシミミズクにガッチリ顔をつかまれている。眼球に爪が刺さっていないことを祈りながら5、6分かけてようやく爪をはずすことができたのだが、爪がくいこんでいたのはまぶたの上1センチの場所と顔、右頬と左頬の計4か所。眼球をそれていたのは不幸中の幸いだった。
◆その日はアルバイトの仕事があり、カットバンを貼った傷だらけの顔のまま仕事に出かけたのだが、皆に驚かれ、すぐ病院に連れていかれて治療を受けたという。
◆私もこれまでにクマタカに数十回も手足をつかまれ、顔面も数回襲われているのだが、人生にはそれ以上に多くの苦難や哀しみが横たわっていることをいつか知るだろう。ボーボに傷つけられた宗さんに次の言葉を伝えたい。
◆「人が命をかけてでも追い求める道とは何を意味するものであろうか。夢で誓いをたて現実にあざむかれ、主よ教えてくれ、我らはどこへ行くのか」(金子光晴)[松原英俊]
■今年も雪国の人々は黙々と雪を投げる。11月29日から12月30日(今日)まで雪が降らなかったのは2日だけ。北国の雪は根雪になれば5月まで溶けない。だからじっくり淡々黙々と雪に挑む。雪に負けまいとも勝とうとも思わない。大雪を前にして気落ちもしなければいくつも越えてきたおごりもない。
◆毎日普通の生活をするために毎日黙々と雪を投げる。毎日の仕事が普通にできるようにするために毎日黙々と雪を投げる。毎日仕事が普通にできるようにするためにまず毎日黙々と雪を投げる。投げた雪は高くなり、家屋、倉庫、牛舎……すべてのまわりが山となる。電線に届きそうにもなる。
◆それでも雪国の人は黙々と雪を投げ続ける。腰、肩、ひざが痛かろうが、時の大臣が防災省を作ろうが、103万円の壁よりはるかに高く雪国の人は黙々と雪を投げ続ける。
◆年が明けてもまた、雪国の人は黙々と雪を投げ続ける。ただ希望に満ちた春、大雪の年は豊作と心の片隅に持ちながら。
(封筒の裏に)江本さん、今年の冬は厳しそうですよ。呉々もお身体大切にして下さい。地平線の人のつながりの広さにはただただ感心しています。江本さんの存在は大きいですね。とにかくお元気に過ごして下さい。[田中雄次郎]
■1月4日朝6時半に家を出て、安曇野を望む長峰山へ。夜に付いた薄雪に人の足跡はまだない。誰もいない静かな山頂で、田畑が半分を占める平野と稜線が雲に隠れた西山を眺める。一人で自然の中にいるのが好きだ。長峰山は中学生のころからたびたび一人で登ってきた。家から徒歩15分で登り口に着いてしまうので、私は裏山とも呼んでいる。山頂からそのまま稜線を伝いお隣の光城山へ。山頂の神社に手を合わせ、横に置いてある記録ノートを開く。日時の後に「今年も生きる」とだけ綴った。
◆今から思えば、生きるなら何でもいいの?と突っ込みたくなるので、ここで「私を」を追加したい。「今年も私を生きる」。足の怪我のため、帰りは林道を歩いて下山した。[小口寿子 安曇野]
■2024年、登頂したピーク64、観た映画25、行った音楽ライブ15、本業の主婦業の他に外仕事も103万円の壁スレスレまでやった。2025年はそれらを越そう、とはまったく思わない。13回目となる毎年恒例の3月11日中心の東日本大震災エリア巡り、一昨年知人が行方不明となった伊豆山中訪問第2弾(第1弾は昨年11月に決行)、能登半島巡り第2弾(第1弾は今年1月3〜6日に決行)の3本を柱に、マイペースで行こう。1月の能登半島では再開したのと鉄道に乗り、のとじま水族館も訪問。半島北部の主要道路、国道249号線は一般車両の通行ができなく、不便なう回路を使った。北部の復旧はまだ遠いと感じた。地元の方々の日常が早く戻ることを切実に願う。[古山もんがぁ~里美]
■今年の干支は蛇、巳年生まれは「金運に恵まれる」と言われるが、そうでもない気がする。それより私は蛇には何となく「魔力」を感じるのである。
◆私には1歳年下の弟がいる。これがとんでもない蛇使いならぬ、蛇扱いの名人である。近所には3人の従弟がおり、よく5人で日曜日には山へ遊びに出かけた。そのたびに山道で蛇に会う。私は蛇が苦手で棒で突くと、弟が「そんなことするな! 俺にまかせろ」と言って素手でひょいと掴んでジャンパーのポケットに入れる。時々、首に巻き付け遊んでいる。蛇もおとなしく逃げようともしない。不思議である。
◆その弟が東京生活でマンションやアパートで蛇が出没となると「区役所から出動要請」が来る。大概は「アオダイショウ」だが、区の職員が棒や網で捕まえようと苦戦していると、弟が梯子を使ってひょいと手で捕まえ一件落着する。弟は「ネズミを捕らえる貴重な使い」と保護を求めたと言う。子どものころ、木曽の山中で蛇と遊んだ弟の話である。[松本 田口哲男]
■測量会社に勤めて3年目をむかえました。能登の災害復旧の現場にも訪れ、測量が様々な形で社会に貢献していることを日々実感しています。
◆昨年12月、シリアでアサド政権が突如として崩壊しました。2022年6月、僕はシリアに足を運びました。そのときの政権はアサドが握っていましたが、10日間ほどの旅をする中で、経済の悪化、国民の不満、戦闘が小康状態になっている中での兵士の怠慢などを感じ、ほんの一押し、反体制派が攻撃をかければ、倒れてしまうような危うさを僕は感じていました。
◆今、多くのメディアがシリアから報道しています。でも、それはアサド政権がどれほど多く人々を殺害したかをリアルタイムで伝えるものではありません。今後、シリアの戦争から何を学べるのか、今回の政権崩壊で多くの人々に考えてほしいテーマだと思います。[桜木武史]
■「医療への信頼」(みずのわ出版)を上梓したのがきっかけで、日本医学ジャーナリスト協会西日本支部の会員になりました。昨年から「島の医療」取材を続けています。娘と、心臓に懸念のある私自身の感染予防のため、ほとんど出かけないのですが、島の病院へ取材に行きます。なんとなったら入院させてもらい、患者体験の写真を撮らせてもらいます。6月には三重県津市のgallery0369で写真展「医療への信頼より・島旅の楽しみ方」を開催します。旅の途中にお立ち寄りください。[河田真智子]
追記 2020年8月に心臓に突然死の波が出て、10月に埋め込み型除細動器を胸に入れ、心臓内の左心室に電線を入れました。医師との会話から、3年、うまく行って4年の命と踏みました。3年以内で本を作り上げ、写真展をやりました。さらに1年、鹿児島の南日本新聞の客員論説委員をしました。途中で死んでもいいので書いて欲しいと言われ、島の医療をテーマに原稿を書きました。4年経って、まだ死ぬ気配はないので、どうしよう? そこにまた甘いお誘いの言葉がきました。「納骨写真展」をやりませんか? 「河田さん、死んでいてもいいので」というお誘いです。もう、途中で頓挫してもいいのだと思いながら前に進むしかありません。
■江本さん、北京の閉店ならば、ですが残念ながら勤務、しかも病棟責任者の立場なので、宴会たけなわのころは救急搬送や看取り対応に忙殺されているころだと思います。インフルエンザとコロナにかかわる自粛はいつまで続くのやら、まだしばらくは参加できるのは発送にとどまりそう。
◆機会があったら、会えぬ仲間にひとこと伝えてください。埜口は、十分に世界を堪能してきたので、今後は医療の現場にとどまります。目標は殉職。前のめりでの最期。
◆これほどの最高の人生はないと、病棟単位ですが12年で4000人を看取ってきての思いです。[埜口保男 12月28日]
■2025年、いーから黙って南米チリのドキュメンタリー映画パトリシオ・グスマン監督『私の想う国』を見よ。わずか30ペソの地下鉄料金値上げに反対した民衆は、武器もリーダーもイデオロギーも持たないまま立ち上がり、政府を倒し、世界でもっとも若い36歳の大統領を誕生させた。政治を揺るがし、国を変えた150万人の若者、とりわけ女たちの闘いを目撃し、そして怒れ! 吉祥寺アップリンクほかで上映中。ついでに、先住民写真家マルティン・チャンビの100年前の作品を目撃せよ。なぜ写真を撮るのか、なぜその瞬間なのか、脳髄と脊髄で考えろ。突き詰めろ、立て、立ち上がれ、媚びるな、一人で闘え! 25日まで@阿佐谷「ひねもすのたり」。さて、今年のカーニバルはフレンチギアナとパナマの掛け持ち、だぜっ。[Zzz-全@カーニバル評論家]
■地平線会議の皆様、あけましておめでとうございます。昨年は、ヨーロッパ取材のため12月7日に日本を出発し、12月8日に到着したロンドンで、アサド政権の崩壊を知りました。そこから8歳の息子を連れたまま政権崩壊後のシリアへ。
◆子連れであることから、混乱のシリアに入ることについては大変悩みましたが、やはり歴史の転換点にあるシリアをこの目で目撃したいと思ったのでした。
◆取材には、政治的な問題から13年間シリアに戻れずにいた夫も合流し、二度とできないだろう素晴らしい取材ができました。このタイミングで激動のシリアを目にできたことは、ただただ幸運としか言いようがありません。帰国した今は、取材したものをいかに発表していくか、ここからが正念場です。
◆このシリア取材については、急な取材地の変更によって大きな取材費がかかりましたが、皆様にカンパを呼びかけさせていただき、沢山の大変ありがたい応援をいただきました。皆様、本当にありがとうございました。今月の地平線報告会では、心を込めてご報告させていただきます。引き続き、どうぞ宜しくお願い致します。[小松由佳]
■11月13日の通信発送後にいつもの町中華「北京」で夕飯の円卓を囲みに行ったときに、来年1月の予約を取ろうとしたら、ママが申し訳なさそうに「年内で店仕舞いすることに決めたのよ……。1月の予約はもう取れない」と。35年間続けてきた88歳のママの決断を初めて聞いた。人手不足とのことだったので、私で良ければアルバイトに来ますよと翌々日から夕方5時から閉店まで赤いエプロンを付けることに。
◆生ビールのジョッキを2つしか持てなかった新米の私を見て、ママはいっぺんに4つ運ばないと泡が消えてしまうでしょと。皆んなが同時に乾杯できるようにするのよと教えてくれた。ビールジョッキ4つを持てる88歳現役あっぱれなり!! 11月30日に閉店の貼り紙をしてから予約の電話は鳴りっぱなし、連日満席で賑わった。
◆地平線会議も30年間、報告会の二次会でお世話になってきたから、北京の餃子の味を忘れられない人も多いと思う。12月28日は報告会後、地平線貸切で報告者の車谷建太さんが掻き鳴らす津軽三味線の音色と共に北京最後の夜は更けていった。
◆さて新年、毎月第一土曜に行われる榎町地域センターの3月場所取り抽選会に向かっている。心新たに、地平線会議46年目のスタートである![高世泉 1月11日]
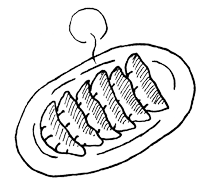
■早稲田の中華「北京」が、もう地球のどこにも無いなんて、いまも信じることができません。北京は、私にとって唯一入れるレストランでした。なぜか、いつしか、二次会北京にて、報告者のかたに「陶ギョーザ」を受け取っていただくことにしてしまいました。受け取ってくださったみなさま、ほんとうにありがとうございます。美味しい北京の餃子を忘れません。
◆北京は、閉店したとしても。ひとりひとりの「こころの北京」は、いつまでもいつまでも営業中ですね。ママさんから紹興酒をいただきました。「細貝容子」サイン入りです。みんなでまたいっしょに飲みましょう。独りで飲むのは寂しい。[緒方敏明]
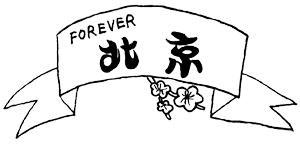

■地平線通信548号(2024年12月号)は、さる12月18日印刷、封入作業を終え、発送しました。12月号は24ページの力作となりました。印刷、封入に時間がかかりますが、そこはベテラン揃い、江本が駆けつけたときは封入仕事は終わり、宛名ラベルを貼るだけのきれいな仕事だけでした。いつもながら精鋭たちに感謝です。参加してくれたのは以下の皆さんです。埜口さんは久々の登場。ありがとうございました。作業のあと、閉店まで2週間となった「北京」でしみじみ餃子を味わいました。
車谷建太 中畑朋子 伊藤里香 坪井伸吾 中嶋敦子 高世泉 長岡竜介 白根全 渡辺京子 落合大祐 久島弘 埜口保男 江本嘉伸 新垣亜美
■江本さん、あけましておめでとうございます。原稿がギリギリになってしまいすみません。実は昨日と今日、タイムリーに(?)我が家で使っている薪ストーブのことでずっと悪戦苦闘していたのです。
◆私は北海道の「ちえん荘」という共同生活家屋の住人ですが、しばらくの間、他の住人たちは家を留守にしており、今は私一人です。煙突の「横引き」(水平の区間)が長い我が家のストーブは2週間に一度の煙突掃除が必要で、吸い込みがかなり悪くなった昨日、私は掃除を一人で行いました。いつもは誰かと行うので、一人で行うのは初めてです。
◆しかし、仕事からの帰宅後、すべての煙突を外し(我が家は部屋の構造上、横引きの煙突をかなり長くしている)、極寒の屋外で一つ一つすすを落とし、さらに「煙道火災」を防ぐために、各円筒内にべったりとこびりついたタールに火をつけて燃やし尽くし、またすべての煙突を元通りに設置する、という作業は、一人ではとても時間のかかる仕事。それで、昨日は一部の煙突だけ掃除して、「残りは週末にやろう」と残したのですが、その横着が大間違いだったようです。
◆なんだか逆に煙突の吸い込みが悪くなり、部屋の中はもくもくと煙だらけに。火のつけ方が悪いのか?選んだ薪が悪いのか?などと原因を探って色々試しているうちに状況はどんどん悪くなり、部屋は一向に温まらず。換気のために窓を開けるので逆に寒くなるし……。そうこうしているうちに3時間以上経ってしまいました。煙を吸いすぎて息が苦しいし、晩御飯も食べずにずっと作業していたため、空腹と寒さと焦りでかなり辛くなってしまい、もうやめることにしました。気休め程度の温風を噴き出してくれるパネルヒーターで暖をとって就寝。
◆今日は、「リベンジ!」と意気込んで仕事から帰宅し、昨日やらなかった部分の煙突を掃除。そうして火をつけても、やはり家じゅう煙だらけ。「昨日掃除した部分も、煙でもう汚れたのか?」と思い、急いでストーブを消火して、昨日やった円筒ももう一度掃除。それでも煙もくもく。さすがに今日はストーブを復活させたい……と、一人で泣きそうになりながら、たまに五十嵐(宥樹)に電話で助言をもらいながら、色々と試して、またご飯を食べずに4時間くらい四苦八苦して……ようやく、いつもの「ボッボッボ」という威勢の良い吸い込み音が聞こえてきたときには、心底安堵しました。
◆新年早々、煙突掃除ひとつうまくできない自分の未熟さを思い知ったわけですが、私は煙だらけの寒い部屋の中で「しんどい……。いつも通りやってるのに何がダメなんだ……」と切羽詰まった気持ちになりながら、一方で、「こんな風に、うまくいかないことに直面しながら生きていきたいなあ……」とも、思ったのです。ボタン一つではどうにもならない「不便」なものを使っているから、経験や知識がないと、うまくいかないときに、うまく対処できない。でも逆に、経験すれば確実に、自分の実になる。
◆私は今、とっても便利な暮らしをしていて、生活の中で苦労したり、しんどい思いをすることは、滅多にないです。だけど本当は、「不便だけど自分の経験と工夫次第で快適にできる暮らし」をしてみたいと思っています。例えば、電気もガスもない環境で、薪ストーブとランプで暮らす……とか。極端な例えに聞こえるかもしれませんが、実は五十嵐とは、こういう生活を近々しよう、と話し合っているのです。そんな生活をもし始めたとしたら、今日の出来事の、何十倍も、何百倍も、不快な瞬間を味わうのだろうな……と、燃えないストーブを前にしてふと思いました。だけど、色んな「うまくいかなさ」にうまく対処できるようになったとき、今の生活の何十倍も何百倍も、ワクワクするんだろうな…とも。
◆自分のこれからの人生に、少し思いを馳せた、2025年のはじめです。[北海道東神楽町 ちえん荘住人 笠原初菜]
追記:実は昨晩、原稿をお送りした後にまたどんどんストーブの吸い込みが悪くなり、最終的に、煙は漏れ続けるわ円筒の連結部分からタールが漏れ出すわで、今まで経験のないほど悪い状態になってしまいました。明らかに何かがおかしいのに原因がわからないし、もう自力でできることはほとんど試したので、一端解決を諦めて、週末、友人にも来てもらってゆっくり向き合おうと思います。今晩は倉庫から引っ張り出してきた小さい灯油ストーブの前にへばりついています。2匹の猫たち、右近、左近とともに……。外は−4℃、薪ストーブだと一瞬で温まる室内も、灯油ストーブでは何時間たっても寒く、もうさっさと布団に入ろうと思い始めています。原稿では、無事に解決したように書いてしまったので、一応メールで追記させていただきました。
■昨年は世界的な選挙イヤーで、70か国で重要な選挙が行われた。米国ではトランプ氏が圧勝。大統領就任を前にしてグリーンランドとパナマ運河さらにはカナダまで米国の一部にすると公言し、閣僚人事の恐るべき顔ぶれとあいまって今後の大波乱が懸念される。なぜ、こんな選挙結果になったのか。投票行動に関する不正や不公平、国外からの干渉も影響してはいるが、問題は民意そのものではないか。トランプ支持者の声を聞くと——
◆今はさびれたかつての製造業の中心「ラストベルト」では、生活苦の吐露とともに、伝統的なコミュニティへの郷愁が聞こえてくる。「(50年代までは)街全体にモラルがあった。公立学校では聖書をきちんと教えていたので、みんな勤勉で、礼儀正しくて、犯罪も起きない。外出時も就寝時も自宅にカギを掛けたことなどない。他人の子でも自分の子どものように大人がしつけをしていた」
◆南部の敬虔なキリスト教徒からは——「(リベラル派が裁判を起こして)お祈りを学校から追放してしまいました。それ以降です。アメリカ社会が変わり始め、ついには『メリー・クリスマス』も言わなくなった。店は誰をも喜ばせる必要があるので『ハッピー・ホリディ』と言うようになった。私たちの長年の習慣を変えてしまった。習慣を変えることはキツイ。誰でもそうでしょう。『モーゼの十戒』の石碑も公共施設から撤去されました。この国で何が起きているか理解できません」(金成隆一『ルポ トランプ王国』より)
◆トランプ氏を押し上げたのは、格差やインフレといった社会・経済的な要因だけではなく、民衆の大切な心の支え、倫理の根っこが崩壊することへの危機感があったと私は見ている。だからこそ人々は彼に「古き良きアメリカ」の再来を熱く託したのではないか。「生きる意味」が世界の政治までをも奥深いところで動かす時代になったようだ。
◆日本でも東京都知事選、兵庫県知事選と意外な結果が話題になった。人権などおかまいなしとする強引でパワハラ体質の人物に多くの票が集まる現象は米国大統領選に通じる。正しい情報が有権者に届いていれば、あんな結果にならなかったと、SNSや報道のあり方が議論されている。しかし、そこがポイントなのだろうか。人々は、そんな候補者「なのに」投票したのではなく、そんな候補者「だから」投票したのではないか。あるトランプ支持の女性は、彼の女性醜聞を知っているかと尋ねた記者に、「知ってるわ、でもうちの娘のデート相手じゃないから」と笑って答えている。トランプ氏が、弱いものを虐げる、醜聞と汚職まみれの人物であることを百も承知で人々は彼に投票したのである。
◆普遍的な価値観と道徳が失われるとき、「人が生きる意味」に残るのは「私の幸せ」だけになる。それはエゴイズムとニヒリズムの世界である。共有する正義がないとすれば、力の強い者に従って、「私」が“おこぼれ”にあずかろうとするのは自然の成り行きだ。
◆アフガニスタンで殉職した中村哲医師は、日本が「古い道徳に代わる何ものも準備せず」に過去の遺産を破壊したために“精神性”と“道徳”が崩壊していると憂いていた。社会制度を改革するだけで世直しはできない。中村さんの言う「古い道徳に代わる」ものを準備しなければならないのだ。私が『中村哲という希望』につづいて、昨年末『ウクライナはなぜ戦い続けるのか』(旬報社)を上梓したのもそのためだった。本書の狙いは、日本の「平和」についての考え方が、薄っぺらい、エゴイスティックなものではないかと自己反省するきっかけを提供することである。
◆ウクライナでは多くの市民が自分の能力や適性に応じて祖国防衛戦争に参加している。彼らの希望は「平和」ではなく「勝利」である。日本人は国が侵略された場合に「戦う」と答える人は13%しかおらず、世界で突出して最下位。「正義の戦争はない」「命がいちばん大事」といったワンフレーズでこれが正当化されるのだが、突き詰めれば「私」が死にたくないというだけではないのか。ウクライナ人は自分の家族、同胞とこれから生まれてくる次世代の命のために、自分の命を捧げて戦う。いま進行中の戦争から人が生きて死んでいく意味を問い直す。これを「古い道徳に代わる」ものを獲得していくプロセスにしたい。
◆今月いよいよトランプ第二期政権が始動し、世界はさらなる争いと混沌にさらされそうだ。私はYouTubeチャンネルを立ち上げる準備を始めた。今年私は72歳になるが、「年寄りの冷や水」と笑われるのを覚悟で、エゴイズムとニヒリズムの蔓延に映像メディアで抵抗してみたい。[高世仁]
■「定年を迎えます。先のことは何も考えていません」。1月6日に届いた年賀状。差出人の住所も名前も書かれていない。文面と字は男っぽい。定年ということは60歳。あるいは65歳。雑な走り書きで、自分の言いたいことだけ言うところは旅人臭がする。6日に届くなら年明けてから書くタイプ。賀状ありがとう、と、書かれてないから、こっちからは出していない。誰だろう? わからん。まぁいいか。ありがとうございます。
◆ヘンな知り合いが多いから、ヘンな年賀状がくる。自由な人はルールからも自由で、2月や3月にも届く。数年前に9月にきたことがあり、もはや年賀かもわからない。本人に聞いたら「出し忘れていたのを見つけたから出した」って返事だった。
◆今日は7日。部屋でこの原稿を書いている。年が明けて3日、5日、7日と仕事が休み。郵便局で働きだして19年になるが、正月にこれほど休みがあるのは初めて。年賀状はわかりやすく減ってしまった。
◆さまざまな郵便物の中で年賀状は特別なものだ。個人情報の固まりであり、縁起物でもあるので配達間違いは許されない。にもかかわらず枚数が多いため、ありとあらゆる間違いが入っている。名前、住所、書き間違い、郵便番号間違い、加えて、何十年も前にその住所に住んでいた人宛てなんてのもくる。同時にこちらが把握できていないものも。
◆そんなときは地域精通者に聞く。「ショコラ? この家にガイジンいました?」「あ、それね、犬」「ここ、2世帯住宅ですよね。部長って、お父さん、息子?」「大丈夫、うるさい家じゃないから、お父さんの方で」と、何でも答えてくれる。
◆間違いにもパターンがあり、何をどう間違っているのか、も、社員同士なら、ある程度わかる。そこから先は個人の匙加減。間違っていても年賀状なら大目に見る。特に子供が出している場合は、みんな優しい。勤務している某局は日本有数の年賀配達物数を誇っており、かつては元日一日で500万枚を配っていた。その試練を乗り越えると、特定の配達区には相当詳しくなれるのだ。
◆明日は8日。もう年賀状はそんなにこない。扱いも通常郵便物と同じになる。今年も年賀は終わり。後は苦情がこないのを祈るだけ。苦情はかならず時がたってからくる。年齢と共に記憶が怪しくなるので恐怖でしかない。[最後の年賀状配り終えました。春からは旅人に戻る坪井伸吾]
■北欧という地は、私の旅の候補にあがったことはなかった。理由はシンプルで寒いのが苦手だから。それに暑い国特有の、人や動物が入り乱れて生きているギラギラした喧騒感やむせぶような匂いとか、そう言ったものに身を置いてこそ旅と感じていた私としては、何か物足りないんじゃないかとも思っていたので、デンマークにいる家族に「いつ来るの?」と言われるまでまったくその気になっていなかった。
◆しかし言われてからの動きは早く、2週間後の夜には、私はコペンハーゲン空港に降り立っていた。そして不思議なことに空港に着いた途端に、「ああ、私、ここが好きだな」と感じていた。とてつもない安心感に包まれた気がしたのだ。特にその日、街はうきうきとした空気感が漂っていた。
◆2024年10月11日は、年に一度のkulturnatten(Culture Night)だったからだ。チケットを購入すれば、数あるミュージアムに入れ、オペラや芝居を自由に観覧でき、ふだん入れない官庁なども見学可能、公共交通機関も一部無料で乗れるお祭りの夜だ。
◆みんな胸にチケット代わりの缶バッチをつけ楽しそうに友人や家族と思い思いに歩いている。そんな楽しい気分というのは、言葉はわからなくても伝染してくる。それに皆の佇まいから余裕のようなものを感じ、人々の表情からは充足感が読み取れた。さすがは世界の幸福度ランキングでいつも上位にいる国だけあるなと私は身を持って感じていた。
◆無駄な広告など一切ない美しい駅や乗り物にも感動した。日本はなんて情報量が多くてゴチャゴチャしているんだろう。そんなことにいちいち感動しながら、まずはホテルへ急ごうと、地下鉄駅のホームに動かないエスカレーター(美しいがまぁまぁいろいろ壊れている)で降りた途端に、電車は行ってしまった。
◆次の電車はすぐに到着したが、なぜか先ほどの電車より手前で止まっており運転手と目があったがその目は大きく見開いていた。なかなか電車が動かないのでしばらくするとホームはざわつき始めた。ホームの真ん中あたりに居たおじいさんが神妙な顔でこちらに歩いて来たので「何かあったのか?」聞いたところ、深いため息をつきながら「Jumping(飛び込み)」とジェスチャーつきで教えてくれた。
◆たちまちホームは困惑した人々で騒然とし、消防隊がザッザッと列をなして大勢降りて来た。私は一気に夢うつつから現実に引き戻され、壊れて階段と化したエスカレーターで重いスーツケースを引きずり上げて、地上に出た。地上に出てみると、辺りは消防車が何台も停まり、真っ青なサイレン灯がぐるぐると街のあちこちを放射状に照らし、世紀末のサイバーシティーのようだった。私は着いた途端に洗礼を受けたように感じ、その後の旅にも不安がよぎった。
◆しかしそんな思いは杞憂に終わり、その後はますますデンマークを好きになる人々との交流や景色や経験で溢れていった。古城とモダンな建造物が違和感なく融合している街並み。環境意識も高く、老若男女問わず自転車を利用しているので、よく整備された広い自転車道。世界一に選出されたレストランが幾多もある美食の街で、見た目にもこだわるから目も胃袋も喜ぶ美味しい料理。
◆人々は過干渉ではないけど親切で、母語はデンマーク語だが、誰でも英語が話せる。何より先にも書いたが、皆あくせくしておらず余裕を感じ、民主主義が正しく機能している国というのはこういう感じなのかな?と思えた。
◆デンマークの懐の広さは、町の中心部をクリスチャニア自治区というヒッピー達の居住区に譲っているところからも窺い知れる。この辺りに来ると落書きだらけの壁が現れ、明らかに周囲と異質の空気が漂っている。クリスチャニアの住人はデンマーク政府にお金を払っておらず、クリスチャニアに月額約2,000クローネ(約43,000円)払うという仕組みになっていて、独自のルールがあり、独自の国旗も持っている。そのルールの一つが車に乗らない、ということなので、荷物を載せる大きな荷台が自転車の前かご辺りについた三輪車が発展した。コペンハーゲンの街では自治区に限らず、そのクリスチャニアンバイクに乗っている人も多く、大人が犬を抱いて荷台に乗っていて後ろで必死に漕いでいる人を初めてみたときには驚いた。
◆世界一美しいといわれる、眼前に海が広がるルイジアナ美術館、海岸沿いを行く路線バスから眺める人々の営み、日本にはない赤い実が紅葉に混ざった秋の風景、お父さんも当たり前に子育ての中心になり仲良く動物園で過ごす週末の親子の姿。何もかもが美しく見え、日本に戻ってからも、あの国から、彼らから、醸し出されるあの幸福感はどこからきているのか知りたくて、北欧の政治や民主主義に関する本ばかり読んでいる(特に今、民主主義とは?が私の中のテーマのようで)。唯一残念に思ったのは山が見えないところだろうか? 東京の私の住む街からも富士山や多摩や丹沢の山々が見渡せるので、それが当たり前に感じていたから、どこにも山並みが見えないのは少しだけ寂しく思えた(でもそれはデンマーク人も同じ思いらしく、自分たちで人工のHillを作っており、冬はそこがスキー場になるらしい)。しかし、とにかく食わず嫌いはやめた方が良いなと心から思えた今回の旅だった。
◆そこで、でも思い出されるのは冒頭の飛び込み事故だ。そんな幸福感に満ちた街でもやはり孤独や深い憂鬱に包まれてしまう人は一定数いるだろう。日本にいたら、みんな何かしら不安や不満はあるし、仕方ないかなぁ自分だけじゃないし、とあきらめもつくけど。光の部分が多いからこそ、わずかな影の部分にいる人たちの孤独感たるや、と想像して何かやるせない気持ちになったりもする。ほんの一部を見ただけで何かわかるわけじゃないから、またきっと私はあの地に確かめに行くんじゃないかな?と予感している。[中山綾子]
■地平線関係者に誘われてグリーンランドの先住民の撮影をしている遠藤励さんの写真展に行った。平日の夕方、新宿御苑の近くのギャラリーに僕ら以外のお客さんは一人だった。初対面の遠藤さんに「2023年にグリーンランドで行方不明になった山崎哲秀さんの友達なんです」と自己紹介する。遠藤さんの表情が曇った。
◆会場の別室で白い雪原を走る犬ぞりの映像を見る。遠藤さんの作品なのだが気持ちはどうしても山崎さんの方に向いてしまう。この人に聞いてみたいことがある。だが問いは軽くない。新たに入ってきたお客さんと談笑している間に割り込んでは聞きにくい。そうこうしているうちに18時となりギャラリーは閉館の時間となる。とうとう言い出せずに会場から出る。
◆ギャラリーの下の歩道で仲間二人と話していると遠藤さんが降りてきた。「待ってください。一つだけ教えて欲しい。山崎さんは本当にセイウチに海中に引きこまれたと思いますか?」「状況から考えて、それしかないと思います」遠藤さんから笑顔が消える。ネット上にセイウチ説は出ていた。極地のことはわからないが説得力がある内容だった。だが暗く冷たい水中に引き込まれる状況を想像すると息が苦しくなる。認めたくない推論だ。
◆「山崎さんらしいと思います。僕らは極地で活動する以上、その可能性は覚悟しています」遠藤さんがキッパリと言う。「オレは病院で苦しみ続けて死ぬより全然いいと思う。山崎さんは自然の輪廻に入った。ある意味憧れる最後だ」遠藤さんの言葉を受けて、隣にいた仲間が答える。その通りだと思う。彼が「自然の輪廻」と表現した食物連鎖に日本人が合法的に入るのはほぼ不可能だ。唯一の可能性が野生動物に食べられることかもしれない。
◆理屈では納得できる。だが友達としては納得できない。行方不明というのは残酷だ。何か答が欲しい。そしてこんな問いに明確に答えられる人はそうはいない。今日僕もそれなりの覚悟を持ってこの場に来た。遠藤さん。言い切ってくれてありがとうございます。その言葉受け入れます。[坪井伸吾]
■先月の通信でお知らせして以降、通信費(1年2000円です)を払ってくださったのは以下の方々です。先月号で記録漏れがあった数人の方の記録もここに掲載しています。すみませんでした。今後も万一記入漏れがありましたら必ず江本宛メールください。通信費を振り込む際、通信のどの原稿が面白かったか、ご自身の近況などを添えてくださると嬉しいです(アドレスは最終ページにあります)。
三羽八重子 (10000円) 久保田賢次(10000円 登山関係の仕事で時間を取られ、最近は発送のお手伝いもできず失礼しています。先月の車谷建太さんの報告会に参加して三味線、モンゴル、台湾とさまざまな出会いを見事に活かしてきた報告者に感銘を受けました。元山と溪谷誌編集長) 富岡裕 坂井真紀子 寺沢玲子(10000円 3年分+カンパ4000円) 宮本千晴(10000円 通信費5年分) 三澤輝江子 北村操(10000円) 渋谷(松本)典子 本出ますみ 宮崎拓 小高みどり(10000円) 秋元修一(4000円) 笠島克彦(10000円 カンパです。どうぞ良いお年を!! 外語大山岳部OB) 上田京子(20000円 548号で終りにして下さい) 宮内純 原田鉱一郎 森本眞由美(5000円 江本さん、能登の火宮に行ったのですね? 学生時代、観文研の仲間と調査に通った集落。とても懐かしいです) 松尾清晴(10000円) 鰐淵渉(4000円 通信費2年分を払い込みさせていただきました。今年は我が家にとっても大きく動く年になりそうです。何よりも息子が大学に進学する事で、僕の方にも少しは余裕ができるかな?と期待しています。身近な所からでも旅に出かけたいなと、地図を眺めながら目下妄想中です。さてその息子ですが、インド映画に始まり、今インドに熱く燃えています。初めての海外行はぜひともインドに行きたいとの事。それなら地平線会議でもインドは取り上げられる事が多いから、興味がある回にでも一度参加してみてはと、声をかけています。いつか報告会に息子がお邪魔するかもしれませんので、その時はどうぞよろしくお願いいたします)
■私の職場である東京外国語大学のアフリカ地域専攻が行ったアフリカ留学生の渡航費支援のクラウドファンディング(以下CF)が1月10日に終了しました。12月の地平線通信への掲載と報告会で告知の機会をいただき、大変お世話になりました。高野秀行さんには、1月8日に応援講演をしていただきました。おかげさまで、当初の目標額150万円達成で3名、ネクストゴール100万円達成でさらに2名、計5名の学生の留学が可能になりました。心より御礼申し上げます。
◆アフリカ地域専攻は2012年の設立以来、アフリカ各地の大学と交流協定を結び、2020~24年には文科省の世界展開力事業に採択され、日本とアフリカの学生の交換留学を徐々に広げてきました。しかし事業終了に伴い、留学生の渡航費を捻出するためCFを実施することになりました。
◆そもそも、アフリカの学生は日本で学びたいのか? まわりからは「本当は欧米に行きたいんじゃないの?」「他に選択肢がないから日本に来るんでしょう?」という声も聞こえました。でも留学生たちに話を聞くと、その答えは明確かつ具体的。欧米とアフリカは歴史的にネガティブで複雑な関係で固まっている。でも日本は関係が浅いので、自分たちの国と適切な距離が取れて客観的に物事を見ることができる。
◆日本の治安の良さはアフリカの日常に比べたら天国のよう、差別意識が少ないので居心地がいい。広島・長崎について高校で学び、日本の戦後復興の歴史を深く学びたくなった……。本学には紛争・平和構築学科という大学院があり、多くの留学生を受け入れています。交換留学後にこの修士・博士コースに戻ってくる学生も複数います。「なぜこんな社会が可能になったのか?」と問いかけ、その学びをアフリカに役立てたいという気持ちで日本を留学先として選ぶ彼らから、私たちが学ぶことは多いです。
◆今回は教職員だけでなく、ガーナ、南アフリカ、ルワンダ、カメルーンに留学中の学生たちがチームを結成、日本にいる下級生とネットで連携してリードしてくれました。彼らがどれだけアフリカ留学生との交流を待ち望んでいるか、その気持ちの強さに心打たれました。
◆そして今回一番驚いたのが、アフリカ人からの寄附です。あるカメルーンの実業家は留学中の本学学生からCFの話を聞き、「アフリカと日本の未来に必要だと思う」とぽんと10万円を寄附。アフリカの元留学生、再来日中の大学院生、現在留学中の学生たちからの寄附にも泣けました。中には生活費を削って3万円も出してくれたルワンダ人学生も。
◆このCFを始めるとき、よくある「貧しいアフリカの学生に支援を!」というストーリーには絶対したくないねと話し合いました。でも学生たちは、そんな懸念は軽々と飛び越えて「お互い様の交流」を実現していました。近い将来、アフリカの奨学金で日本人学生がアフリカ留学したり、アフリカの企業に就職したりという世界が見えてくるかもしれません。その先の日本・アフリカ関係はさらに面白くなりそうです。
◆以下のサイトで、アフリカ学生の日本体験や交流についての記事が読めます。https://readyfor.jp/projects/asc-africa2024/announcements[坂井真紀子]
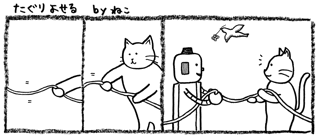
《画像をクリックすると拡大表示します》
◆《父親が郵政省の役人だった縁で中学3年、高校1年のふた冬、年賀状仕分けのアルバイトを横浜駅前の郵便局でやった。都内23区を担当し、慣れてくると分厚い賀状の束を手に下を向いたまま、23区のそれぞれのボックスに猛スピードで1枚1枚放り込むことができた。大学生ばかりの中でちょっとした自慢だった。得たお金で初年度は詰襟の学生服を買ったが、2年目は……覚えていない》アルバイトしているとしてない時より生活に張り合いが出てくる。暇がない。○は入ってくる。面白い(たまには飽きる)。
◆8時22分のバスで家を出る。僕はバスより電車の方が嫌いだ。県庁前や本町でバスからだいぶ降りる。しかし、僕はゆうゆうと乗っている。桜木町へ来ると残る人はあまりいない。「自分は降りないんだな」と思うと変な優越感を感ずる。横浜駅で降りよう。
◆はじめて郵便局へ来た時は少々頭がぼやあんとしてしまった。何しろ騒々しい。モーターがブンブンまわっている。局員の声がわんわん言っている。慣れてくるにしたがってだんだんと興が乗る。隣に横浜国大生のYさんとNさんがいる。局の「坊主」と呼ばれているAさんも面白い。なんとなく石濱朗《当時の若手映画俳優》に似ている人もいる。皆、少なくともつまらない人たちではない。
◆ところで、これから映画に行く。not time なので後はいつかのお楽しみにー。
◆《かなり踊っている字で》アルバイトではじめて給料をもらった。家で歓待された。お酒を飲まされた。頭がおかしい。まっすぐに歩けない。大みそかだが、酔ったためこんな日記に終わる。
◆夜、パンをうんと食った。お父さんが帰ってきた。お母さんがお父さんのためにゴハンとトンカツを作ったが兄さんが不平を言った。お父さんが食べ終わった頃、兄さん、僕等にもトンカツ飯をくれた。ところが兄さんは「こんなにいい肉トンカツよりテリヤキにして食べた方がうまいのにな」という。おかあさんが「お前は一回もおいしいと言ってゴハンを食べたことがないね。だまって食べなさい」と言った。僕は「トンカツの方がテリヤキなんかよりよっぽどうまいよ」と言いながら本当にうまいと思って食べていたが、兄さんは「大体パンを食う時はなにか一緒につけて出すのがあたりまえだよ。いつも卵一つくれやしない」と言う。
◆このあたりから僕は兄さんに憤怒の念を持ち始めた。せっかくうまいトンカツなのになんであんなことを言っているんだろう、バカヤロめ。お母さんは「Mさん《近くの家》を見なさい。大人が4人もいるのに肉50匁しか買わないんだよ。家なんか小さい子ばかりなのに100匁も買うんだからきまりが悪くなっちゃった」。兄さんが言うに「うそだよ、Mさんちのパン食は牛乳にリンゴ1つ付くんだよ」。僕は全く兄さんの他人のことばかり言っているのに対し情けなくなってしまった。本当に能なしだとその時思った。まだ2人で言い合いを少ししているうちお父さんのカンシャクが破裂した。「何言ってるんだ! そんなことどうだっていい、よその家のことばかり言って……」。その時の兄さんの顔、ビクッとしてすごく驚いた顔をしていた。僕は思い切りそのたまげた顔を笑ってウップンを晴らそうとしたが怒られそうなのでやめた。とにかくこういう時だけは本当に頼りない兄さんだ。
■みなさん、あけましておめでとうございます。お正月はどのようにして過ごされましたか。ぼくは元旦の0時をもって我が家に近い相模三宮の比々多神社を参拝し、夜明けとともに愛車のスズキVストローム250SXを走らせて大磯海岸へ。太平洋に昇る初日の出を見ました。一片の雲もない東の空に昇る朝日はそれは神々しいものでした。帰り道の平塚では初富士を見ました。「今年は良い年になりますように!」という願いを込めた初詣、初日の出、初富士でした。
◆昨年は最悪の幕開けになりましたね。1月1日16時10分、「能登半島地震」が発生。震源地は珠洲市でM7.6という大地震。輪島市と志賀町で震度7を記録しました。できるだけ早い時期に被災地を見てまわりたいと思っていましたが、2月には地平線会議の渡辺哲さんと、震災直後の被害が生々しく残る能登半島の全域を車でまわりました。その後、4月、5月、6月とバイクでまわりました。その間では能登国の全式内社47社(論社を含む)をめぐりましたが、多くの神社が大きな被害を受けていました。
◆そんな能登半島に、再び大災害が襲ったのです。9月21日から23日の「能登半島豪雨」では、またしても甚大な被害を受けてしまいました。その直後の10月にバイクで能登半島をまわりましたが、能登に始まり、能登で終わった一年です。「頑張れ、能登!」と声を大にして応援しつづけたい気持ちで一杯です。
◆3月11日には第29回目となる「鵜ノ子岬→尻屋崎」に出発しました。2011年の東日本大震災で壊滅的な被害を受けた東北太平洋岸の全域をまわったのですが、各地で復興が進み、大防潮堤もほぼ完成し、震災から13年目にして大津波の痕跡は、ほとんど見られなくなりました。爆発事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所の周辺を除けば、すべての道は通れるようになっています。
◆ところで昨年は「楢葉キャンプ」でのトークショー、「東北のライダーズ神社4社の立ち上げイベント」、能登のバイク市場きゃぷてんの「伊勢神宮参拝ツーリング」、箱根の「バイカーズパラダイス」のトークショー、SBS(静岡放送)の番組「ヨエロスン」の「渥美半島一周」、アウトドア用品のデイトナの「茶ミーティング」、風間深志さん主催の「SSTR」でのトークショー、若狭を盛り上げる「若狭湾風遊騎」、台鈴工業の「台湾ツーリング」、スズキ本社で開催された一大イベント「Vストロームミーティング」、昭文社とノマディカ合同の「ならここキャンプ」でのトークショー…と、様々なイベントに呼んでいただきました。「カソリ大モテ」。ありがたいことだと思っています。
◆12月16日から12月18日までの「伊豆七島紀行」では東海汽船の「橘丸」で八丈島に渡り、2座の式内社、優婆夷命神社と許志伎命神社を合祀する優婆夷宝明神社を参拝しました。さんざん苦労した伊豆半島と伊豆七島の「伊豆国式内社めぐり」は、これにて終了です。そのあと八丈島から青ヶ島に渡ろうとしたのですが、またしても失敗に終わりました。青ヶ島は難しい……。
◆我が旅の相棒ですが、昨年7月1日の『ツーリングマップル東北版』の実走取材開始を機に、Vストローム250からVストローム250SXに乗り換えました。Vストローム250では23万6000キロを走りました。SXでは東北の全域を駆けめぐり、下北半島の大間崎や津軽半島の龍飛崎に立ち、3か月で2万キロを走りました。100キロより1000キロ、1000キロよりは10000キロと「距離命!」なのです。
◆2025年1月1日現在のカソリのバイクでの走行距離は187万2127キロになりました。1968年4月12日に「アフリカ一周」に旅立って以来、現在までの57年間の距離ですが、大きな目標にしている地球50周分の200万キロまであと12万7873キロです。ぜひともVストローム250SXで200万キロを達成させたいと願っています。旅した日数の方は8593日になりました。目標にしている1万日まであと1407日。まだ先は長いですが、これも、何としても「達成させるぞ!」と、気持ちを高揚させています。
◆我がモットーは「生涯旅人!」です。我が憧れの生き方は「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」(芭蕉)です。さ~みなさん、大きな夢に向かって、2025年も頑張って行きましょう~!
■年が明けても相変わらず散歩は続けている。すっかりお気に入りとなった東京農工大の農場。畑の上の空が何もなくて広いのがただただいい。その農工大、学生たちは畑仕事や牛飼いに明けくれているわけではない。
◆暮れの12月26日、連れに誘われて三鷹市公会堂で開催された東京農工大ピアノ部の「120th Concert of the Error」というのを聴きに行った。驚いた。この日は5部に分かれて42人の学生が登場したが、皆さん、大した弾き手ばかりなのだ。
◆1949年に創設されたピアノ部、今年で創立76年になるという。コンサート名は「間違い(Error)を恐れずに音楽を目一杯楽しむ」という意味だそうだが、私は聴きながら羨ましくて仕方なかった。こういうチャレンジは価値あり、と。皆さんなら何を?[江本嘉伸]
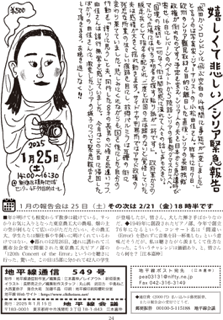 |
嬉しくて悲しい/シリア緊急報告
「成田からロンドンに飛ぶ空白の14時間に事態が一変しました」と言うのは写真家・ジャーナリストの小松由佳さん。昨年12月7日、欧州のシリア難民取材を目的に離日した直後、シリアの長期独裁政権が倒れたのです。予定を変え、シリア人の夫を日本から急遽呼び寄せ、16日にレバノンのベイルートから陸路シリアの首都ダマスカスへ。「国境の検問も一切なく、街は開放感に溢れて人々の話し声も大きい。マルジェ広場には行方不明者を探す貼り紙が一杯です」。 政府軍からの脱走兵として指名手配され、二度と故国の土は踏めないと覚悟していた夫は感情が大きく揺れ動きます。サイドナヤ刑務所ではアサド政権の残忍な所業の生々しい痕跡を目にし、故郷パルミラは瓦礫の街に変わり果てていました。悲しみにくれながらも、国をあとにした自分の行動を「誇りに思う」と夫。同行した8才の長男の心情を気遣いつつ、由佳さんは諸行無常を感じていました。 今月はこの元日に帰国したばかりの由佳さんに、激変したシリアの様子について緊急報告をして頂きます。お聴き逃しなく!! |
地平線通信 549号
制作:地平線通信制作室/編集長:江本嘉伸/レイアウト:新垣亜美/イラスト:長野亮之介/編集制作スタッフ:丸山純 武田力 中島ねこ 大西夏奈子 落合大祐 加藤千晶
印刷:地平線印刷局榎町分室
地平線Webサイト:http://www.chiheisen.net/
発行:2025年1月15日 地平線会議
〒183-0001 東京都府中市浅間町3-18-1-843 江本嘉伸 方
地平線ポスト宛先(江本嘉伸)
pea03131@nifty.ne.jp
Fax 042-316-3149
◆通信費(2000円)払い込みは郵便振替、または報告会の受付でどうぞ。
郵便振替 00100-5-115188/加入者名 地平線会議
|
|
|
|
|
|