

4月17日朝。抜けるような青空なのに、朝、新聞はビニールに包まれて届けられた。傘を忘れずに、とテレビも伝えている。
◆10日ほど前、上野近くで山田高司と会う用件があって、せっかくだから桜を見ていこう、と上野公園に足を伸ばした。公園の入り口の植え込みに座って缶ビールを飲んだだけだが、外国人の花見客にまじって2024年の上野の花見を満喫した。近くのアメ横にひさしぶり入り込んでみた。そしたら、狭い路地に机と椅子を並べただけの、懐かしい屋台がずらり。
◆ただ、メニューらしきものを見て、ひそかに青ざめた。このようなラフな屋台でも、注文はスマホを通してしなければならないのだ。幸い、山田高司がなんとか操ってビールと焼き鳥でささやかな花見の宴は持たれたのだが、あらためて「情報弱者」となっている我が身のレベルを痛感したのであった。屋台の注文もできないとは。
◆アメ横は、18歳のころ通った懐かしい場所である。山岳部に入りたての新人はここで寝袋を調達するのが最初の仕事だった。朝鮮戦争に送られた大量の米軍の物資が終戦とともに日本に送られ、アメ横でさばかれたのだ。2500円から3000円で買えた寝袋は貧乏学生にはほんとうにありがたいものだった。一説には米兵の遺体を移送するのにも使われたそうだ。もともと飴を売る店が多かったので「飴屋横丁」と言われていたが、アメリカからの物資がさばかれた場所として知られるようになり、いつのまにか「アメリカ横丁」の意味も持つようになった。
◆痛恨の知らせである。昨年9月、脳の腫瘍除去手術を受けて経過が心配されていた、あの元気者の阿部雅龍さんが郷里の秋田に帰った3月27日に亡くなった、と伝えられた。23年9月5日、脳に腫瘍ができました、2日後、全身麻酔の手術をします、と告白してから8か月、ついに復帰は叶わなかった。41歳だった。阿部君は、秋田の偉大な先人、白瀬矗(のぶ)がなしとげられなかった「白瀬ルートからの南極点到達」を目指し、ひとり戦った勇士である。
◆2015年10月30日には「南極の白い跡」のテーマで報告会をやってくれた。人力車夫をして鍛錬しながら資金を稼ぐ生き方が多くの仲間たちの共感を得た。南米自転車縦断11000キロ、北米大陸ロッキー山脈縦貫トレイル踏破、アマゾン川筏くだり2000キロなどの冒険を果たし、2021年には「白瀬ルートによる南極点徒歩到達に挑戦」の実績で26回植村直己冒険賞を受賞している。
◆私の部屋の壁には冒険学校の設立を夢見て子どもたちを抱いて破顔一笑する阿部君の写真葉書が止められている。2021年8月にもらった残暑見舞い。「今夏は夢見てきた冒険学校設立への第一弾として冒険ウォークと題して子どもたちと三陸海岸自然歩道『みちのくトレイル』を南三陸-女川町間100キロを踏破してきました。1000キロの自然歩道を10年かけて毎夏歩きます」としてあった。「今年こそ念願の南極の夢を叶えてきます」とのペン書きを添えて。同じ秋田出身の小松由佳さんの追悼の言葉と阿部君の最後の言葉は21ページにあります。
◆この数か月、中学、高校時代の日記を引っ張り出して、地平線通信の余白を埋めるのに活用させてもらっている。昔から記録することは好きだった。そうした中で何冊も大事な記録がないことに気がついた。2年半前、荻田泰永君が経営する「冒険研究所書店」に蔵書を寄贈した際、そうした資料が紛れ込んでしまったらしい。書店の側でも、本だけでなく雑多な書類が大量にあることに困惑していたそうだ。
◆事態を知った岡村隆、丸山純が動いてくれ、3月25日に冒険研究所書店に地平線の面々9人が集まって、蔵書や資料類の仕分けをやってくれた。結果、私に返還すべしと判断した個人的な書類や写真などをダンボール4箱分見つけだし、それを荻田君が送り返してくれた。
◆厳冬期のモンゴル遊牧草原の記録など、必死で探していた貴重な資料類がこうして我が家に返ってきた。自分のいい加減さを今更ながら思い知るとともに、この厄介な仕事を1日でやりとげてくれた地平線の9人と荻田君にしみじみ感謝した。
◆緑の季節である。森や川べりの散歩が実に楽しみだ。1年前にいためた右のふくらはぎは完治した。きのうもいつものように浅間山を歩き、木のテーブルで一休みしていたら知った顔があらわれた。やぁ、今日もあたたかい紅茶あり? 宮本千晴は黙ってテルモスを出し熱いお茶を注いでくれた。しばしの年寄り談義。帰って連れに伝えると「いいねえ、G3たちのホットスポット!」と返ってきた。まさに。[江本嘉伸]
■今回の報告者はアラスカ北西部・ポイントホープに通い続ける高沢進吾さん。「ポイントホープの人たちとの生活があまりにも面白く、学ぶことも多くて結果的に30年も通うことになっています」と語る。報告会では通い続ける動機の一つ、クジラ、アゴヒゲアザラシ、ハクガンなどの猟や、町での生活をたっぷりと話していただいた。
◆ポイントホープはアラスカ州北西部の海岸沿いから飛び出した岬に位置している。人口は800人ほどの小さい町だが海に突き出た地形を生かしてクジラ猟が盛んにおこなわれてきた。高沢さんのアラスカ行きの最初のきっかけは中学時代に読んだ植村直己の冒険記だ。これを読んで北極圏のエスキモーの生活に憧れるようになったと語る。植村直己は北極圏の旅の途中、立ち寄った町でクジラ猟に参加する、その町こそがポイントホープだった。高沢さんは社会人になり、お金がたまったのをきっかけにこの町と深く関わっていくことになる。
◆1993年8月、何のあてもなく訪れたホワイトホープの海岸にテントを張って過ごし、町や海岸を散策した。「目に入るものすべてが珍しかった」と高沢さん。しかし町から丸見えの平原に張られた奇妙なテントはすぐに噂になり、好奇心にかられた子どもたちが大量にやってくる。そのうち「いじめられてるやつがいる」と子どもから聞いて駆けつけてきた大人から家に招かれることに。その後もポイントホープに通ううちに親交を深め、遂にはクジラ猟にも参加するようになった。転職した今でも毎年3か月の休暇を取り、猟期に町を訪れているのだとか。コロナ禍の2020年は出国ができなかったが翌年には厳しい制約を乗り越えてポイントホープ通いを続けていたそうだ。
◆ちなみにエスキモーは彼ら自身のことも「エスキモー」と呼ぶ。ポイントホープはイヌピアックという種族でそちらで呼ぶこともあるが差別用語ではない。一方で彼らの言葉は先住民の同一化政策で失われつつあるが一部の単語は残っている。
◆クジラ猟でターゲットにしているのはヒゲクジラの一種、ホッキョククジラであり冬は氷のない南の海域で暮らすが春、4月上旬から5月中旬にかけて海氷が割れたところに餌を求めてやってくる。体長は15mほどに達し、とにかくでかい。これが町の沿岸を平然と泳いでいる。動画を見ると怪獣物の映画みたいで非現実感がすごい。
◆クジラ猟のため、乱氷帯を整地したトレールの先、海氷の末端部に拠点を設営し、テント生活。町からは温かい食べ物を持ってきてくれる。キャンプにはホッキョクグマも来たがこの時期はクマに構っている暇はなくクジラに集中する。ポイントホープでは十数組のクジラ組があり、キャプテンの下、男たちがボートで狩りに出かける。近年では開氷面が広がったこともあって伝統的なウミアック(アゴヒゲアザラシの皮を使ったカヌー)はほぼ使われなくなったそうだ。
◆以前はシャッター音さえ気にしていたそうだが現在ではエンジン音を轟かせながらクジラを追いかけている。クジラに追いつくとダーティングガン(銛)を目標に打ち込む。銛の先端には弾体(ボム)が搭載され体内で爆発する仕組みだ。これは100年以上前から使われているらしい。複数の組がダーティングガンを打ち込み、息絶えたところを岸まで曳航する。
◆アラスカにおける捕鯨数は厳密に管理されており、ポイントホープには1シーズンに10頭ほどが割り当てられている。また、肉を市場に流通させることはできない。大半のアメリカ人は自国でクジラやアザラシ猟が行われていることも知らないのではないか、と高沢さん。
◆続いて解体作業に移る。まずは分け前をマーキングしておく。取り分は銛を打ち込んだ順番に決まる。部位は細かく分類されており、特に尾びれは重要な部位でキャプテンの取り分。次に氷上に支点となる穴をあけて滑車とロープを使い引き上げるのだが、この作業が一苦労で30〜40人で5時間くらいかかることもあるとか(クジラは1フィート当たり1トンにおよぶそうだ)。
◆解体はさらに大変で3日3晩におよび、白夜のため夜も作業は続けられる。ナイフは脂ですぐに切れなくなり10分に一回研ぐ。ナイフを持ったまま血まみれで寝ていたこともあった。少々グロテスクだが日本のスーパーに売られている肉からは想像もできない、貴重な命のやり取りの現場を垣間見ることができる。猟の関係者に均等に(階級は関係ない)分配したところで終了。細かく切ってニンジンや玉ねぎと一緒に炒めたり、皮の部分(マクタック)を茹でたりして食べる。ちなみに彼らは生食はせず、加熱するか、永久凍土で凍らせてから食べるそうだ。
◆クジラ猟が終わると今度はハクガンという鳥の猟。流木のブラインドに隠れて見事に撃ち落としていく。少々グロテスクだが骨を砕いて脳みそまでいただく。脂が多く、うどんに入れると味がものすごく濃くておいしいそうだ。高沢さんは去年は40羽ぐらい捕り、1日に3〜4羽のペースで捌けるとか。
◆町では猟がひと段落した6月中旬、クジラ祭り(カグロック)を行っている。クジラがとれたことに感謝し、町の人に様々な料理がふるまわれる。クジラの尾びれ「アヴァラック」は組のキャプテンからかかわりのあった人々に直接手渡される。ちなみにエスキモーの人々にとって名前は非常に特別なものらしく、同名の人を「アチャック」、配偶者と同名の人を「ウーマ」と呼んで大事にしている。
◆肉は最終的に会場にいる人全員に配られる。町では酒は禁止されているが炭酸飲料は大好きなので太っている人が多い。「アクトック」というカリブーとアザラシの脂肪を使ったエスキモーアイスクリームもふるまわれ、世界一脂っこい食べ物とのこと。酒はなくともなかなかジャンキーなお祭りだ。他にもクジラやセイウチの内臓の皮を張った太鼓を使ったエスキモーダンスや、アゴヒゲアザラシの皮を使った人力トランポリンに興じる姿を覗き見ることができた。
◆話はアゴヒゲアザラシ猟にうつる。体長2mほどになる大型のアザラシで、猟は5月下旬から6月中旬にかけて行われる。まずは海から頭を出したところを鉄砲玉でとらえ、銛を打ち込んでとどめを刺す。クジラより小さい分、余計に生々しい。船上で若者が銃を放ち、スマホで町に連絡を取っている姿がとても不思議な光景に感じられる。曳航し、小型の扇状のナイフ(ウル)を使って器用にさばく。皮はかつてウミアックに使うため丁寧に剥いでいた。
◆夏にはウミガラスの卵拾いもやっている。長いくちばしに白い腹、短い羽根はまさにペンギンだが北極にペンギンはいない。海沿いの崖に卵を産むのでロープで下降し回収する。ロープはガレージセールで買ってきたものを垂らして2〜3人で支えているだけなので引き上げには結構てこずるそうだ。最近では高沢さんが縄梯子を自作したとか。こういうものを自分で作れてしまうのは本当にすごい。卵はゆで卵にもするが、高沢さんは日本人らしく卵かけごはんだ。
◆高沢さんはすっかり町の人からも頼られる存在のようで、ダーティングガンの火薬の充填を任されたり、ハクガンの皮の剥ぎ方を指導したり。わざわざ電話がかかってきて「物置に置いてたはずのあれ、どこにあったっけ?」と聞かれることも。長く通っていると、かつてトイレの世話をしていた子どもが成長してすっかりたくましくなっていたり、月日の流れを感じさせる場面もあるそうだ。
◆月日が流れれば、人も死ぬ。毎年町を訪れると訃報に接することもある。町から大きな病院までは遠く手遅れになってしまう人も多いらしい。お墓の周りにはクジラのあごの骨が立ててある。町の人はこの骨を人生の大切なものとしてとらえているそうで、クジラ祭りの会場にはこの骨が飾られている。かつてはこれを骨組みにした家に住んでいたそうだが今は西洋式の家に、石油式の暖房を効かせて暮らしている。固い凍土を掘って土葬するのも一苦労だ。それでも寂しいし悲しいからひたすら掘り続ける。この30年で、お墓の数はどんどん増えていった。
◆ポイントホープは実に小さい、陸路もない閉鎖的な町という印象を受ける。事件や自殺を見聞きすることもあるそうで、去年の滞在中には銃乱射事件があったとのこと。それでもその家族まで憎んだりすることはなく、刑期を終えた人も普通に生活できるそうだ。人口が少ないため、事件や自殺の発生比率としては高くなってしまう。酒やドラッグの問題も抱えている。町を出てホームレスになる人もいる。
◆飛行機から撮影された、物寂しい村の姿。アメリカ大陸の最果てで陸路もないこの町、極地に住む人々の現実を思い知らされた気がする。極地やへき地にあこがれることはあるがそれは良い面に惹かれてのことだ。長期にわたって町に通い続けてきた高沢さんの生の報告はポイントホープもいい面ばかりではなく、理想郷ではない、都会とは違った問題があると語りかけてきてくれたような気がする。高沢さんのポイントホープ通いのモチベーションは学ぶことが多いから、とのこと。場所や環境を求めるだけではなく、自分の成長や経験を通して、人生を充実させていくことこそが大事なのかもしれない。[竹内祥太]
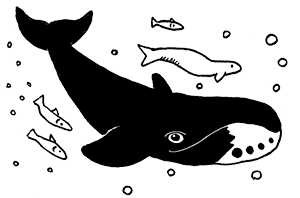
イラスト ねこ
■「30年も同じ町に通っているなんてまさに地平線会議向きの話だからぜひお願いしたい」と江本さんに言われ、9年ぶり2回目の報告会。初めてポイントホープへ行ってから30年。猟に参加するようになって20年以上。毎年やっていることはほぼ同じ。しかし自分が彼の地で何をやっているのかは謎に違いない。その様子を写真で紹介してみよう。
◆見せたい写真は山ほどある。ただし、ほとんどの写真は解説がないと意味不明だろう。枚数を増やすと時間内に終わらなさそうだ。動画もある。時系列で写真を抽出。これで2時間くらいか? すべての写真に解説を書き、時間確認をしようと写真を見ながら書いた文章を読み始める。読むたびに言いたいことが増え、時間の確認ができないまま、解説はどんどん増えていく。写真枚数、動画の時間から、こんなもんだろう、足りなくなったら最後の雑感を削ればいい、時間が余ったらエスキモーダンスの動画もある。
◆今回、報告をするにあたっては、昨年グリーンランドで行方不明になった山崎哲秀氏のことは外せない。最初の10分ほど彼の話をする。妙な緊張感に原稿を読むだけで精一杯。客席をみる余裕はなく、そして言葉が詰まる。先が思いやられる。しかし本編は、いつもやっていることを説明すればいいので、言葉に詰まることはなくなり、緊張も解けていった。
◆ポイントホープに通い続ける理由。昔は何かそれっぽいカッコいい理由を探していたが、そんなものはいつまでたっても見つからない。ふと我に帰れば「面白いから」「楽しいから」通い続けている、ということに気がついた。毎年、友人たちが帰郷を温かく迎えてくれる。技術、知識、自然の様子など、毎年のように何かしら新しいことを知ることができる。自分にとって、こんな面白いことは他にない。一つ言い忘れていたが、「氷の上にいること」それは自分にとって、この上ない幸せな時間なのだ。これも毎年ポイントホープへ行く理由の一つでもある。
◆キャンプへ向かう乱氷帯の中のトレイル。顔に当たる痺れるほどの寒風さえも心地良くてにやけてしまう。氷点下20度の薄暗い深夜の氷の上も、氷上のクジラを徹夜で解体し、血まみれで疲れ切っていても、そのどれもが幸せな時間だ。これまでこの生活を続けられたのは、日本でもアラスカでも、すべて人との出会いのおかげだった。今まで出会ったすべての人たちに感謝したい。そしてこれからもよろしく。今年も間もなく出発です。行ってきます。
■2023年12月最初の土曜日、山崎哲秀氏が行方不明になったというメールを受け取った。慎重な彼が行方不明になるはずはあるまい、何か読み間違えているに違いない。何度もメールを読み返すが、その事実は変わらない。
◆数時間後、何を書いていいのかわからないまま、自分が混乱した状態にあることを伝えるメールを彼の奥さん宛に送った。まもなく奥さんから返信があった。短いながらも達観したような奥さんの文章を見て、それが事実であることを認めざるを得なかった。
◆12月中旬の週末。頭の中がモヤモヤしたまま、いつもの(エスキモー)ロール練習のために、仲間とカヤックを漕ぎに出かけた。カヤックを漕ぎ出し、体を倒してロールを行う。頭が水の中に入った瞬間「もしかしたら彼が最後に聞いた音はクジラやアザラシの声だったのでは?」という思いが浮かぶ。自分が水中にいた時間は1秒にも満たない。カヤックを引き起こしたあとも考え続ける。「もし水中でそんな音が流れていても、パニック状態だったら何も聞こえなかったのでは?」。その日は水の上にいることが何となく怖くなってきて、早々にカヤックを降りた。
◆『つなぐ 地平線500!』に「生きる極意は死なないこと」という文章を寄せた直後ということもあり、落ち込む日々が続く。ある日、こんな考えが浮かんできた。「彼は海の食物連鎖に組み込まれた」。現代の日本人は、滅多なことでは明確な食物連鎖の一部になることは不可能だ。なんと羨ましいことだろう。いや、羨ましいなんて思っちゃいけない、彼には家族がいる。
◆自分にとってバイクとは、知らない道をのんびりと走ることのできる、とても楽しい乗り物だ。しかし12月以降、通勤で短時間乗るのさえ怖くなっていた。いくら慎重に運転したところで、車が突っ込んできたらそれまで。ヘルメットを被ると「死なない方法」を考え始めている。ヘルメット内蔵のスピーカーからは、同じ歌が繰り返し流れている。
◆年が明けてしばらくそんな状態が続いていた。1月終わり頃の土曜日の朝、目的地だけ決めて地図を見ずに走り始めた。相変わらず「死なない方法」を考え続けているが、スピーカーからは色々な歌が聞こえてくるようになった。少しは心が落ち着いてきたのかもしれない。
◆仲間を失うことほど辛いことはない。だから自分もいなくなってはいけない。哲ちゃん、自分はしばらく死なないからな。その時が来たらまた会おう。それまでは家族と仲間のことを見守っていてほしい。[高沢進吾]
■高校三年間の課程をすべて終了し、3月2日に東京都立神津高等学校を卒業した。神津高校50期生代表として、卒業式では答辞を述べるという大役を任された。高校生活の思い出や、先生方と両親への感謝、50期生の一員であることへの誇りを胸に、思いを伝えることができた。
◆卒業式が終わると、荷物の整理などの寮を去る準備に追われた。離島留学を決意してから、本当に沢山の経験をし、沢山の人に支えられながら3年間を全うした。卒島までの一週間、新しい生活への期待がある反面、寂しい気持ちやもう少しだけ残りたいという気持ちもあった。しかし別れの日はやってくる。お世話になった方々に見守られる中、3月10日に神津島を後にした。
◆船に乗る直前、一年生の後輩が号泣してしまい、私のコートで涙と鼻水を拭かれた。私にとって神津島は第二の故郷となった。帰りの船はあっという間に竹芝桟橋に到着した。ここでちょっとしたサプライズが我々を待ち構えていた。私が1、2年生だったころの寮の先輩たちがターミナルで出迎えてくれたのだ。2年ぶりに再会する先輩もいた。私はこの3年間寮生に「We are family!」と半分冗談で言い続けてきたが、寮生の絆は一生ものだと思った瞬間だった。
◆家に帰ってからは大学進学に向けての準備が始まった。スーツを新調してもらい、履修する科目などを調べ、4月1日に入学式を迎えた。私は正式に立正大学心理学部対人・社会心理学科に入学した。今年度は心理学や統計学の基礎をしっかりと学び、2年生から始まる研究に役立てたいと考えている。大学では新しい友達ができ、サークル活動も始めた。これからの新生活が楽しみである。[長岡祥太郎]
■夫の服部文祥が前号で、相棒犬ナツの阿蘇山での失踪事件について書いた。横浜に暮らす家族は、現地に行っても力になれないという判断から、夫と有志の方々に捜索をお任せし、在宅本部として情報を整理するくらいのことしかできなかった。地元の方たちが、親身になってナツや文祥のことを心配してくれたことが、ありがたかった。
◆ナツは失踪から9日目に発見され、阿蘇で2日間療養し、新幹線で新横浜駅へ帰ってきた。私と娘は、友達のSちゃんに車を出してもらい、ドキドキしながら再会の瞬間を待った。
◆ところが、ようやく会えたナツに声をかけても、目が合わない。ケージに押し込まれ、熊本から横浜へと新幹線と車でワープしているのだから、訳がわからなくてあたりまえかな、と思ったものの、ナツは自宅に着いてもここはどこだろう、という戸惑うような素振りを見せたのだった。額や背中に深い傷を負っているだけではなく、精神的にもダメージを受けてしまったのだろう。これまでの記憶が一時的に失われるほど、9日間で過酷な経験をしたのかもしれない。ナツは家の中に入り、自分の寝床の匂いをかぎとり、ようやく少し尾っぽを振った。それから鹿肉をガツガツ食べて、水を飲んで、四肢を伸ばして眠った。
◆生きているナツと、ようやく会えたことが嬉しくて、私と娘はまた、写真を撮り始めた。しかしやがて、むなしくなった。人はなぜ、こうやって自分が見ている世界の一部を切り取ろうとするのだろう。二次元に取り込んで自己表現のツールにしたり、かわいい、などと自分を癒してる。そんなくだらないことをしていたところで、ナツの生には何の関係もない。半野生に戻ってしまったナツのおびえた瞳が私を見る。自分に都合良くナツを切り取ることは、失礼なことのような気がした。XにLINE、写真に動画、と溢れる情報は便利な側面もあるけれど、大切なことは情報ではなくて、もっと謎めいた全体的なこと、ナツの身体が発している匂い、言葉や映像にできないものの中にあるのではないだろうか。
◆普段目にしているさまざまな情報も、すべて誰かの意図で切り取られたものだ。この世界のことにしろ、ナツが今回の事件で経験したことにしろ、私は何もわかってないし、知らないでいる。
◆実は最近、眠っているナツに声をかけても、反応しないことが多くなった。この春8歳になるナツは、銃声の影響もあり、耳の聞こえがかなり悪くなっているようだ(鉄砲耳)。このことが、阿蘇での遭難の原因のひとつとなっているのかもしれない。ナツという特異な犬の運命を受け止め、言葉を持たない異種の命の‘’わからなさ‘’と向き合っていきたいと思っている。[服部小雪]
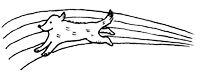
■またしても、2月末から3月いっぱい、西穂山荘(2367m)でアルバイトをさせていただいた。3月は年度末ということもあり、例年多くの登山者が訪れる。今年は暖冬の影響で積雪量が少なく、2月末の入山時点では300cmに満たなかった。加えて、気候の変化もあってか、山荘付近の丸山にむかう斜面が二度、雪崩れた。この場所は例年、雪崩れることがほぼない場所で、小屋のベテランスタッフも驚いていた。3月に入ると南岸低気圧がやってきて、西穂でもドカ雪になった。3月21日にはやっと、積雪量が300cmを超えた。朝のニュースが桜の開花予想で盛り上がるなか、窓の外は吹雪で真っ白だった。目まぐるしく変わる山の中で、小屋での生活は続いていった。登山者は山に登りにくるが、小屋のスタッフは生活をしている。そのリズムの違いが毎回面白い。
◆昨年の3月、アルバイトとして初めて西穂に入山した。スタッフや環境に慣れたいま、小屋は人が生かしている場所であるということを強く実感する。西穂山荘は、森林限界のぎりぎりに位置しており、いわば「奥山」にある。黄金のような朝日、一面染まる夕暮れ、雪面に残るライチョウの足跡。息をのむ景色とやすらぎを求め、登山者は登ってくる。清掃や食事の提供に加え、燃料の調整、食糧の管理、機材のメンテナンス、赤旗の設置、仕事は多岐にわたる。時にはビンタのような強風を受けながら除雪をし、凍える手で燃料を補充する。短期のアルバイトで出入りする私とは違い、中には10年、30年と山の仕事に携わっている方々もいらっしゃる。山にどっしりと根を下ろす人たちを見て、とてもかっこいい、と感じていた。
◆山荘にいると、私は生かされている、という実感が強まる。下界では生活の基盤が様々な担い手に分散されているのに対し、小屋ではその一つ一つが小屋番に委ねられている。もちろん、真に小屋だけで成立するというわけではないが、あらゆるものが当たり前ではない。下界の生活がどれだけ複雑な網の目のなかで営まれているかを想像すると、自分の生活が他者の手に委ねられているような気さえしてくる。
◆山はある種のアジールなのかもしれない。「下界に帰りたくない」、「(山に来ると)つまらない仕事から離れられる」、そんなことをおっしゃるお客さんに会うことも少なくなかった。どのような形、態度で山に向き合うのかは、本当に千差万別だ。多くの人にとって、生活の基盤は下界。嫌気がさしても戻っていくのは、山が本来人の住む環境ではないからだろうか。そんなことを考えるうちに、ひと月はあっという間に過ぎていった。
◆下山時はいつものように、もう少しここに居たいという気持ちと、これからやりたいことへの期待とが混じり合っていた。私は山に登りたいし、山小屋での生活も好きだった。けれどどちらかといえば、登りたい、という気持ちが強かった。これから先、山が生活になるようなことがあるのだろうか。少なくとも、そのときには本気(マジ)になって進まないと生きていけないだろうな……そんなことを考えながら下山の途に就いた。
◆今は大学の研究室に戻り、キーボードをたたいている。私の中には確かに、しんしんと雪が降るなか佇む小屋のリズムと、穏やかな時間が流れている。それはふとした時に深呼吸をするような余白を私にもたらしてくれる。とりとめのない内容になってしまったけれど、これから先も、山に登ることで救われたり、しんどくなったりして、山に生かされていくような気がしているこの頃です。[安平ゆう]

■南米の旅から帰ってきて1週間経ったが、いまだに想いをうまくまとめきれていない。本当にいろんなことがあった。それらをひっくるめてここにまとめるのは忍耐がいる。旅の記録をA4ノートに書き記し始めたが、1日分を書き終えるのにかなり時間を費やしている。出来事もそれに対する想いも溢れに溢れかえっている。
◆2月23日、長野の家を出て東京へ移動して伊沢正名さんの報告会を聴いた後、千葉の西船橋で一泊(山に還りたい自分としては伊沢さんのお話はとても興味があり、このタイミングでお話を聞けるのは運命にも感じた)。その翌日に成田から旅立ち、帰ってきたのは3月の27日。まる1か月、南米のペルーとボリビアを旅してきた。
◆それまで日本から一歩も出たことがなく、一人で国際線の保安検査場に入るところから緊張した。しかし一番どきどきしていたのは出国の日やその前日ではなく、長野の家を出る日の前夜だった。旅に備えてよく寝るぞと勢いよく布団に入るも、急に一人の心細さが出てきた。荷物をすべて整えこの家を出たら、もう引き返せない。間違いやトラブルを起こさないか、いくら調べても調べたりない気がして不安70、でもなんだかんだでなんとかなるでしょう(そのトラブルさえも旅のいい思い出になるだろう)という期待でわくわく30だった。
◆小中高、そして大学でも一時的に、人間がとてつもなく嫌いになった時期があった。他人のことも自分のことも大嫌いで、外に出るのが億劫だった。不登校や引きこもりにはならなかったが、コンビニに行くのも通学電車に乗るのも人の目が気になって怖くてしかたなかった。でもそんな自分が、一人で海外を旅するようになった。これはもしかしたら凄いことかもしれない。人によっては特別思い悩むこともなく、当たり前のようにできることかもしれない。
◆まず首都リマから24時間以上バスに乗ってクスコの街へ移動してマチュピチュ訪問、歩いてでしか行けないインカの遺跡へ4日間トレッキング、レインボーマウンテンツアーに参加、クスコからボリビアのラパスへ移動、世界一登りやすい6000m峰といわれるワイナポトシ(6088m)に登頂、ラパスからウユニへ行きウユニ塩湖訪問。
◆マチュピチュとウユニ塩湖はタビイクの仲間と行動し、1か月間のうち半分は日本人の仲間と、もう半分は一人で、行動した。単独行動は危険だとも聞いていたが、少なくとも私の訪れた場所では、人に関して恐怖を感じたことはなく、むしろ吠える野犬の方が怖かった。
◆同じ街に数日間滞在し、遠くに出かけず歩いて行ける範囲で街をぶらぶら見てまわるのも楽しかった。ボリビアでは、十年に一度行われるという国勢調査にぶつかり外出が制限されて全く動けない日もあった。自分にはちょうど良い休息日だった。
◆言葉がわからない環境でも笑顔や簡単な挨拶だけで通じ合えることの奇跡を身をもって体験したが、一人で旅したときは不安の8割以上が言語のわからなさからきていると感じた。第一に英語そして第二にスペイン語を身に付け、また旅をして今回友達となった人たちともっとたくさん話したいと思った。
◆世界をみれば、いつだって旅に出られることをありがたく思う。戦争や虐殺が起き、飢餓や貧困に苦しんでいる人たちがいる。今回の旅のなかでも、ただ生まれた場所が異なるだけで思うように国を出られなかったり稼げない人たちを見た。もしかしたら自分もそのなかの一人だったかもしれない。
◆旅に出る資金があるのなら困窮した人へ寄付した方が世のためになる……。そういうことも考えるが、旅に出ることを決めた。あえて飛び出すことにした。それは自分にとって必要なことだと感じたからだった。世界を知りたい、世界の山を感じたい。自分自身もお金にそれほど余裕があるわけではないけれど、旅に出られる環境ができた以上、あえて旅立った。
◆そして、海外に出てみても山にいたい気持ちは変わりなく、やはりもっと世界の山も見てみたくなった。日本とは規模の異なる遥かに広大な山で自給自足的に暮らす人たちを、たくさん見た。山に暮らすことは何も特別なことではなく、これほど世界には山があるし山にいる人がいる。それを嬉しく感じた。
◆4月1日から林業の職場に復帰したが、その際に「気持ちを切り替えて復帰してね」と言われた。仕事である以上そう言いたくなるのは頷ける。しかし、「切り替える」という言葉にとても大きな違和感も感じた。すべては今の自分に繋がっていて地続きなのだと。あの旅の最中の気持ちも、あれらの国での出会いも出来事も、すべて自分の一部になっている。今回の旅は仕事の合間にバカンスに行ったという感覚はなく、もしかしたらそのままそこに住み着くかもしれないという気持ちすらあった。一生に一度訪れられたらそれでいい、ではなくて、またあの場所に行きたいし、またあの人たちに会いたい。
◆海外(とりわけインドがよく出る)に行けば悩みごとが小さく思えて思想がひっくり返るだろうという話を聞くけれど、そう言うなら目の前にいるあなたが私の思想を覆させてくれよ、と思っていた。新しい場所に行って本当に悩みが吹き飛ぶとしても、そこに行くまではとても勇気がいるし、もちろん時間もお金も必要なことが多い。飛び出す前は0でも一度飛び出してしまえば1になるとして、その0と1のあいだには途方もない終わりの見えないだだっ広い海がある。日本の自殺者の数を聞くとやるせなくなるが、私のように悩んだ人、悩んでいる人はきっと日本にたくさんいるかもしれない。
◆そんな人に、こうやって生きている人間もいるのだとヒントのように示せたらいいし、そうでない人にも暗い話だとシャットダウンするのではなくおもしろく捉えてもらえたらと思う。海を渡ることができたこと、ここまで生きてこれたことに、本当に感謝したい。温かく励まして送り出してくださったみなさまに、この場をお借りして感謝を申し上げます。[長野県安曇野市 小口寿子 24歳]
■4月8日から新学期がスタートした。今年は中学3年生の担任。4月は1年のうちで最も忙しく、人間関係をつくるのに大切な時期である。私はたいてい憂鬱になるのだが、ここ2年はそれほど緊張していない。その理由は3月に江本さんとウメ(香川大同期の日置梓)と直接会って話ができているからだ。いつも2人から刺激をもらうことができ、近場だが街歩きをすることでその土地の魅力に気づく。家族や学校の集団の一人ではなく、個人として純粋に楽しめる1日は、本当に貴重だ。
◆今回の集合場所は「北鎌倉駅」。江本さんおすすめの駅で、到着してその理由がわかった。駅舎もホームも落ち着きがあり、静かだった。また、北鎌倉駅は円覚寺というお寺の境内に位置するため、参道の途中に踏切がある。不思議な光景だなと思った。3人が駅に集まり、ホッとするとともに本日のタイムリミットを確認。それ以外はあまり細かく決めないのが3人の散歩である。まずは、円覚寺の階段を上る。円覚寺の建物は自然の中に溶け込みながら、どっしりと構えていた。飾らない美しさと、芯の強さを感じた。境内は急な坂や階段が多く、後で調べてみると、丘陵地が侵食されてできた土地であり、高低差があるらしい。
◆次に訪れたのは、明月院。あじさい寺として有名で、5月から6月あたりは大変混雑する。私たちが回ったときには、桜の開花前というのもあり、3人だけの貸し切り状態で本堂後庭園を散歩することができた。江本さんは高校時代に明月院で写生をした場所を探していた。今回は、場所がはっきりわからなかったが、その絵は今も大切にとってあるそうだ。明月院は「悟りの窓」という丸窓も有名である。窓の美しさ、奥に広がる景色の美しさに引き込まれ、自然と心が落ち着く。しばらくして3人とも小腹がすき、境内のウサギ小屋の前で小休憩をすることにした。近くの木々には野生のリスがいた。……とこんな感じで、半日かけて2つのお寺をゆっくりとまわった。
◆その後は、鎌倉駅方面へと徒歩で向かい、お昼を食べ、喫茶店でコーヒーを飲んで解散した。道中、仕事や育児の話、山田隊長(山田高司さん、四万十ドラゴンランでのニックネームが山田隊長)が植村直己冒険賞を受賞した話、服部文祥さんの山旅犬ナツが見つかるまでとても心配した話、糞土師伊沢正名さんの話は今こそ聞くべきだという話、野菜たっぷりエモカレーを最近作って(食べて)いないという話など、話題は尽きない。
◆そのなかで、江本さんが「最後は自分一人になる」と言っていたことが印象的だ。仕事も終わり(定年)があり、子どももいつか巣立っていく。そのときに、自分が何をしたいのか考えておく必要があるということだ。私はまったく考えていなかった。子どもが自分の世界の中心になり、最近は少し仕事も育児も安定してきた。しかし、安定優先で、自分があまり挑戦できなくなっているとも感じた。江本さんの話を聞いて、自分は自分の人生を生きていることを思い出すことができた。今年は生徒に「進路」について考えさせる場面が多い。私も一緒に考え、自分自身が「やってみたい」「こうなりたい」と思えることを探そうと思った。
◆16年前の四万十ドラゴンランで偶然3人が出会い、今でも交流を続けられているのは江本さんの存在が大きい。すごい人なのに全然偉そうにしないし、チャーミングでとっても話しやすい。そして、私なんかにも声をかけてくれる。日々はあっという間に過ぎていくが、この3人旅が毎年できたらいいなと考えている。[クエこと杉本郁枝]
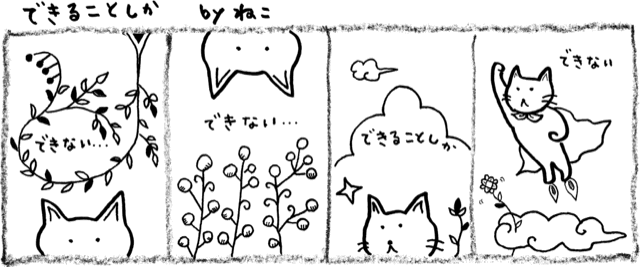
《画像をクリックすると拡大表示します》
■昨年の秋口から地平線報告会に顔を出せなくなっていたのですが、実は「青天の霹靂」ともいえる事態が降りかかっていたからなのであります(なかでも、石川直樹氏のシシャパンマでの壮絶な体験をじかに聞く機会を逸してしまったのは痛恨の極みでした)。
◆昨年一年間は、越冬隊長の帰国事後処理やあちこちから依頼された講演行脚で終始しました。それもようやく終わって、やっと自分の研究を再開できるとトップギアに入れようと思っていた矢先、なんと、学部長に選出されてしまったのでした。おかげでバックギアに入れ直すくらいのシフトチェンジを迫られて右往左往していたのです。内情についてはここでは述べませんが、自然科学者として文系の社会学部に所属する私には、そうした要職が回ってくるはずがないと考えていたのに、なぜか「人畜無害のタフガイ」という評判が学部内で立ち、強い支持を受けておしつけられてしまったのでした。
◆こうして、南極観測隊員という、一見社会学部とは無縁の経歴の持ち主が、2000人の学生と百数十名の教職員を抱える学部の運営を担うことになりました。正直大変な重圧を感じていて越冬隊長の方がよほど気が楽だったと思う反面、その経験が生きるのではないかと思っているところもあります。
◆ここで改めて自分の立ち位置を考えてみますと、雪と氷に閉ざされた極寒の地で、私は人間社会の縮図ともいうべき営みを目の当たりにしてきました。地球規模で見れば、世界各国の観測基地は、広大な大陸に距離を隔てて点在しつつも、どこの国の領土でもないという特殊性や国際協力を重視するという共通理念の下に、ユニークな連携コミュニティを形成して互いに支え合うことで科学観測を遂行しています。少人数で一冬を過ごす越冬基地の中にも小さな「社会」が芽生えます。限られた資源を有効活用するための工夫が生まれ、時に意見が対立しても対話を重ね、自律的に問題解決を図ろうとする姿勢があります。
◆こうした、極限環境下にこそ顕在化する、社会が本来持つダイナミックな営みの本質に、私は多くを学びました。また、極寒に耐える肉体的な強靭さだけでも決して極地は生き抜けません。前に地平線通信に寄稿した際にも紹介した米国の極地探検家リチャード・バードの言葉どおり、肉体的な強さだけでなく「内面に蓄えた教養を糧に悠々と生きる」ことが極地を生き抜くために重要だとも学びました。さらに、いまや私たちは、自身が地球に大きな影響を与える存在となった地質年代である「人新世」を生きていますが、この時代はまさに教養を糧とした生き抜く知恵が問われている時代でもあります。
◆私の学部は、こうした社会の本質と人新世を生き抜く知恵を探求することを使命としているといってもいいでしょうから、そこに自分の強みを生かしていけば、こんな私でもそこそこ務まるのではないかとも思っています。さらに、学部で主流を占める社会・人文分野の教授陣とは異なる視点を持つことも、地平線会議で様々なバックグラウンドを持つ方々とお付き合いさせていただいてきたことが、きっと役にたつのではと思います。「異人種」ともいえるほど彼らの考え方は私とは違いますけれど、それがかえって刺激になれればと思っています。
◆もう一つ、最近読んだ『「冒険・探検」というメディア:戦後日本の「アドベンチャー」はどう消費されたか』(高井昌吏著 法律文化社)が、社会学と自分の立ち位置を考えさせてくれました。この本では、探検や冒険の「消費」のされかたが丹念に分析されており、まさに身にしみる内容でした。戦後復興期のエクスペディションが戦前の知的財産を引き継いでいたという指摘や、マナスル初登頂を成し遂げた今西壽雄氏の「ぼんやりとした顔つき」に「真正性」を見いだした白州正子の分析など、引き込まれる考察の数々に、ようやく生粋の社会学者たちのものの見方が少しわかってきた感じがしたのです。
◆正直なところ、これまで地平線報告会に連れてきていた学生が書くレポートを大学のゼミでの成果物として評価してあげることに困難を感じてきていました。この本で「冒険者は外部と日常をつなぐ媒介者だ」という指摘を得て、現代を生きる若者の自己探求のモノローグとして捉えることができるのではと思わされています。単なる体験談ではなく「消費」の在り方を映す一つの視点として評価できるのだと理解できたからです。さらにこの本では、北杜夫・小澤征爾・小田実ら60年代前半の青年冒険家たちが発信する内容の消費のされかたの考察に「インテリだから、冒険する」という言葉が引用されています。それから半世紀以上経った今も、若者の自分探しのモノローグとして共鳴するものがあるのだと感じました。時代を経ても変わらない人間の根源的な営みを捉えられることが、社会学的な視点の価値なのだと思います。
◆今までの自分の立ち位置に気づかされ新しい視野を得ることができた本だけに、学生たちにも大きな刺激を与えられる、この本や地平線会議との連携も検討しながらゼミを展開していきたいと考えているところです。[澤柿教伸]

■『舟唄』『津軽海峡冬景色』『石狩挽歌』など歌謡曲、演歌の舞台は、北国、風雪、港の赤提灯、つまり冬の日本海、恋に落ちぶれた女の悲哀でなければならない。南国土佐には、すがる女のエレジーはにあわない。何といってもハチキン(男勝りの女性を指す土佐弁で、お転婆のこと。語源は、男4人分、睾丸の数にすると8個分のパワーがあるという意)のお国柄だから、うじうじせず活発で明るい女がもてる。酒も男に負けない。土佐の男は、一般的に頭が悪いくせに頑固で夢ばかり喰って、仕事をろくにしないで酒ばかり飲んでいる(私のことではない)から頼りにならない。だから、土佐の女は強くたくましくなければ生きていけない。ハチキンは誉め言葉である。
◆民俗学に登場する女の悲哀は全国津々浦々にあって、北国の専売特許ではないが、やっぱり北国がにあう。水上勉が好きでよく読んだ。厳しい風土と理不尽な宿命にけなげに生き抜く女たち、『越後つついし親不知』『はなれ瞽女おりん』『飢餓海峡』は胸にジンときた。
◆船乗りには、港々に女がいなくてはならない。山男には、自意識過剰のもてないロマンチストが多く、色恋ごとには無縁だが(私のことではない)、船乗りには、脛に傷持つ腕っぷしの強い女たらしがにあう。夢より現実、金払いのいい男がもてるのは当然だ。ハゲデブ加齢臭、年金暮らしの高齢者は、マドロス(マドロスもヨットもオランダ語である)にはなれない。
◆佐伯順子『遊女の文化史』(中公新書 1987年)は重厚なすぐれた学術書である。比較文化史で扱われる遊女について少し確かめておこう。冒頭は、「遊女――この言葉はもはや、男にもてあそばれる女、という意味しか持ちえないようにみえる。遊ぶのは男であって、女ではない」で始まる。次にホイジンガの『ホモ・ルーデンス』が引用される。「文化は遊びの形をとって生まれた。つまり、始め文化は遊ばれた」ときた。ホイジンガとカイヨワの『遊びと人間』は、山岳部で流行った本だった。読んだけれど、難しくて内容はほとんど忘れた。佐伯は、遊びと文化の関連を、遊女の発生から近世、現代につながる売笑婦の変遷をたどることで、克明に表そうとする。
◆古今東西の古典を引きながら、時代を越えて通底する性を俯瞰する。性的快楽の神聖視は明快だ。「その恍惚感が、自己と他者の境界を消滅させ、宇宙的なものと一体となる機会として、尊重された。(中略)生命の創造につながるゆえに、また行為そのものの神秘性ゆえに、性的交渉は二重の意味で神聖視された」
◆神事には歌舞音曲がつきものだが、それを担う巫女の芸能の中に宗教的役割を見出す。時代が下るにしたがって、巫女は神聖性交の名のもとに巫娼化していく。遊女も、元々遊ばれる女ではなく、神聖な歌舞(性的咒術=文化)を遊ぶ女と考えている。佐伯は、男が語り継いできた遊女=売笑婦の図式を壊す。
◆アルピニズムは、カイヨワの分類した遊びの四つの要素をすべて持っているように思うが、特に眩暈の要素が一番強いような気がする。岩登りでは死の恐怖がアドレナリンを分泌させて、快楽と興奮を呼び起こす。遊ぶということは、切羽詰まった行為なのだ。仕事(なりわい、真面目、責任)の対語としての遊び(余暇、享楽、適当)ではない。真剣を遊ぶのである。遊女の遊も、そういう意味を含んでいるといえるかもしれない。それゆえに、説話につづられてきた女たちの赤裸々な必死が胸を打つ。
◆柳田国男の説として、万葉集に出てくる遊行女婦(ウカレメ、アソビメ)という漂泊の女芸人が、遊女の始まりではないかとあった。遊行女婦は、朝廷の遊部(アソビベ)に属する巫女(死者の霊魂を鎮めるための歌舞、神楽を司る女性)が殯の廃止とともに、その職能を活かす道として、鎮魂歌舞と遊行を選んだことが始まりで、歩き巫女となり門付け芸をして諸国を巡った。
◆やがて、田舎わたらひ、歌比丘尼、女歌舞伎、白拍子、傀儡女など、見世物小屋掛けして歌舞音曲を技芸とする漂泊民の中で分化していった。春をひさぐものがいたことは容易に想像がつく。門付けを守り通した瞽女社会には厳しい掟があり、生涯男と交わらなかったという(五来重『異端の放浪者たち』角川書店 1995年)。
◆遊女というと吉原の花魁をイメージしやすいが、これらは近世以後の話である。漂泊から定着へ変遷は、遊女論の大きな転換点であるように思う。遊女を遊郭(娼館)という悪所に閉じ込めたのは、秀吉からだとあった。室町時代以前には、遊里はあったが娼館はなかったのだ。歌舞(神アソビ)という芸妓から女郎売春(人アソビ)に重心が移り変わったあたりから、遊女説話には悲惨な話が多くなる。
◆『枕石』は、漂泊から定着の中間にある遊女説話である。舞台は、峠とか川の渡し場とか、人里離れた境目がほとんどだ。境界にある一つ家に夫婦と娘の家族がいる。旅人が一夜を請うと、娘が夜の伽(売春)の相手をする。ことを終えて眠り込んだ旅人の頭を、夫婦は石で砕き金品を奪う。このなりわいを恨んだ娘は、男を逃がし身代わりになって、旅人になりすます。夫婦はそれとは知らず、娘の頭を砕いてしまう(『あしらう――接客婦の世界』小沢昭一編 白水社 1982年)。この手の伝承はいたるところにあって、遊女を山姥や鬼女に変えて旅人を殺す話は、性と死に直結する。
◆港の女の登場は、遊行女婦が境界に定着するところから始まる。昔の湊は河口に発達したものが多く、海、川と里の境界にあった。そこは領国と他国(異国)との境界でもあり、交通要衝の地であった。そこに宿場町(遊里)ができ、聖、巡礼、商人、遊行漂泊の者が行き来した。この遊里を舞台にした能『江口』は、遊行僧西行と遊女妙の贈答歌(新古今和歌集)を題材にしている。江口は大阪湾に面した神崎川と淀川の合流するところ、遊女の乗る小端舟は、音曲を奏でながら贈答歌を交わして客を引く。中には、木偶(デコ、男茎形の人形)を振りかざす雑芸で漂客をもとめる遊女もいた。
◆「歌舞の菩薩・遊女に託された能の美学。ここには、宗教性を離れて、ある演劇哲学が熟そうとする芽生えがある。(中略)神遊びの歌舞が、演劇という『文化』へ羽ばたこうとする」。佐伯は、世阿弥を論じる中で、あくまでも歌舞と色恋の女神としての遊女にスポットを当てたがっている。
◆レトロな雰囲気の漂う鄙びた港町をたくさん訪れたが、強く印象に残っている港に、広島県大崎下島の御手洗がある。この島のある呉市の安芸灘とびしま海道は、一部フェリーを使うが、しまなみ海道大三島につながっている。自転車で一度、ヨットで一度、御手洗港を訪れたことがある。島々にぐるり囲まれた天然の良港だ。風待ち潮待ちに格好の港で、広々として水深が浅く、潮流もゆったりしている。中世の瀬戸内は、陸地沿いの地乗り航路だったが、入り組んだ島々、急な潮流、水軍(海賊)の危険にさらされた。江戸時代になって、瀬戸内海中央部の沖乗り航路が開かれると、北前船のような大型貨物商船の中継地として、無人だった御手洗は賑わうようになる。
◆人が集まれば遊里ができる。今は柑橘類の栽培と観光が島の主な産業で、港の周辺に昔の街並みが保存されている。狭い土地に神社、商家、待合茶屋、船宿などがひしめき、華やかな花街があった。「若胡子屋」という茶屋跡が残っている。全盛期には100人の芸妓が在籍した。九州地方の出身者が多かった。ここにおぞましい言い伝えがある。花魁鉄漿伝説である。既婚女性は鉄漿(お歯黒)を付ける。それに習い、一夜妻の花魁もお歯黒を付けた。座敷から催促する馴染み客、お歯黒をうまく化粧できない花魁は、何に苛ついていたのか、控える禿(遊女見習いの幼女)の口に熱した鉄漿を注いでしまう。禿は黒い血を吐き、のたうち絶命してしまう。何とも痛ましい。廓の生活が想像される。まさに苦界なのだ。
◆御手洗の下級遊女におちょろ舟がある。茶屋での接客ではなく、4〜5人乗りの小舟で沖に停泊する船に出張する。花魁は宿で女郎は舟で、ここにも階級社会がある。江戸時代の遺構、石造りの千砂子波止が残っている。ここから漕ぎ出したのだろう。食糧や日用品の販売、繕い物、洗濯もしたという。何だか世話女房風だ。船の往来は季節に左右される。繁忙期に近在の女が出稼ぎに来ていたのか。年増の漁師の嫁が、陸の茶屋に上がれない、若い水主たちの相手をしたのだろう。何だかのどかな感じもする。波止場近くの展示館におちょろ舟の模型が飾ってあった。木で間仕切りした屋形船である。薄板一枚では寝物語も筒抜けだっただろう。
◆遊女のイメージを『江口の君』(『西行』白洲正子著 新潮社 1988年)で締めくくろう。私があこがれる最高の旅人は歌人西行である。俗名は佐藤義清、平清盛の同僚で御所警備の北面の武士だった。弓の名手で筋骨たくましいイケメンの偉丈夫だったと想像する。西行は、江口の里で時雨を避けて雨宿りを遊女に乞うが断られる。
世の中を厭ふまでこそ難からめ
仮のやどりを惜しむ君かな
遊女妙は、ちょっと皮肉っぽい返しを詠う。
家を出づる人とし聞けば仮の宿に
こころとむなと思ふばかりぞ
二人は意気投合して夜もすがら寝物語りする。妙は四十過ぎだが容色衰えず、立ち振る舞いも上品だった。妙は身の上を語る。この歳ではもう客を取ることもない。尼になって仮の浮世と別れたいと泣く。二人は再会を期して別れる。月日を経て通い文が途絶える。西行は使いの者に消息を託す。
かりそめの世には思ひをのこすなと
ききし言の葉わすられもせず
あのときのあなたの言葉が忘れられないと西行は詠う。妙の返答が艶めかしくいじらしい。
わすれづとまづきくからに袖ぬれて
我身はいとふ夢の世の中
髪おろし衣の色はそめぬるに
なほつれなきは心成りけり
妙は、江口にはいなくなっていた。いにしえの門付け比丘尼に戻って行ったのだろうか。
■4年ぶりの台湾!!! この瞬間をどれほど待ち焦がれていたことか。空港のゲートを出るとそこには一番会いたかった陳老師が出迎えてくれていた(台湾で有名な音楽家・陳明章さんは15年前に台湾で出逢って以来、僕を楽団に引き入れてくれ、僕は “先生” という意味の「老師(ラオスー)」の愛称で呼んでいる)。思えばコロナ禍を経て、東京の暮らしからは台湾が霞んで見える日もないわけではなかった。4年という月日は個人だけではなく多様な変化がそれぞれにあったはずで、直接触れてみなければわからない。現に僕自身は三味線と少し距離を置く生活をしていた。「とにかくここに来てみんなと会いたい」。これまでの人生でこれほど “再会” というものが心に沁みたことはなかったかもしれない。
◆老師の車の助手席に乗り込むと、止まっていた台北の街並みが一気に流れ始める。彼との共通言語は簡単な英語、台湾華語、台湾語のミックス。お互いに伝えたいことが多すぎて、頭の隅で眠っていた言葉たちを総動員させながら止めどなく会話が弾む。会えなかった時間が距離を縮めているの? 何だか以前よりも遠慮なく何でも話せている自分にびっくり。
◆もう一つ、大好きだった台湾料理の数々との嬉しい再会も。「あ〜〜〜、旨い!」。身体と脳の反応に心が全然追いついてこない。一口ごとに悶絶していると、気がつけば僕の台湾メーターは満タンになっていた。後は短パンサンダルに履き替えたら一丁あがり。こうして僕の台湾とのタイムラグは一瞬にして埋まったのであった。
◆一見変わっていないような街並みだったが各信号機にはAIカメラが設置されていて、交通違反の取締りが強化され、ほとんどの駐車場にはナンバープレートの自動読取り機が設置されている。コロナ対策で国民IDと各種機関との紐付けが日本よりもずっと進んでいることにも驚いた。台湾物価もやや上がり、対台湾ドルの兼ね合いもありお財布事情には苦笑するしかない。
◆宮殿のように聳える台北で一番目立つホテル「台北圓山大飯店」。今回はここの大ホールで開催する楽団演奏会に参加させていただいた。久しぶりの観衆前でのソロ演奏は一発勝負。当然緊張もするが、大切なのは皆の輪に感謝の気持ちを持って飛び込むこと。一人ステージに立ち、台湾語で「台湾と日本は永遠の親友だよ!」と挨拶し、一心不乱に演奏すると温かい声援に包まれた。
◆ 『撼山河』は台湾人のアイデンティティが山河を揺るがす程に熱く込められた陳老師渾身の戯曲のような一曲(同タイトルの陳老師のドキュメンタリー映画は昨年台湾のアカデミー賞である金馬賞にノミネートされた)。老師の月琴ギターを筆頭に、笛、太鼓、二胡、三味線……。皆と息を合わせて音を重ねていくと、僕の心の中ではステージ上が船に変わり、観客席の向こうから大海や山々が浮かび上がってくる。歌のなかで老師が「兵を挙げろ〜〜!」と叫ぶと、楽団メンバーと観衆は「おおおぉぉ〜〜!!!」と呼応する。自分の人生において唯一無二の「この景色が見たかったんだ」。ただただ皆と心を通わせる楽しさを全細胞で噛み締めた。
◆4月3日の午前7時58分。深い眠りから突然の揺れに目が覚めた。「これは夢? 現実……?」。脳は半分寝ていても揺れはどんどんメリーゴーラウンドのように大きくなってゆく。僕が寝ていたのは陳老師のマンション14階の子供部屋。恐竜の頭蓋骨やらドラゴンボールの人形が降ってくる。「あと一段大きくなったらヤバいな」と思ったところで揺れは次第に静まっていった。「20年住んでいてこんな大きな揺れは初めて」と家族たちは驚き動揺し、老師は大事なコレクションの陶器が割れて悲しんでいる。それでも壁に掛けてある30本のギターはストッパーのお陰で無傷で、電気水道インターネットが止まらなかったことがありがたい。
◆まもなくテレビからは倒壊したビルの映像が次々と流れてくる。台湾当局の発表によると震源地は台湾東部の花蓮でM7.2(日本の発表ではM7.7)の25年ぶりの大地震。台湾全土が揺れたのは僕の記憶でも初めて。台北の震度は5弱で、都市機能はその日のうちに通常通りにまで復旧。震源が陸地ではなく沿岸だったことで現地の被害は最小限に抑えられているようだった。
◆特に状況把握の速さと正確さ、救助の初動の速さ、そのチームワークが際立っていた。台湾有事に備えていることもあるが、コロナ防疫がSARSの教訓を生かしていたように、教訓に学び改善してゆこうと進化する、台湾政府の危機管理の姿勢にはいつも感心させられる。どこにいてもいつ地震がくるかわからない。いつでも自身の経験からいざというときのイメージを更新させておく重要性を改めて学ぶ機会となった。
◆久しぶりに念願の台湾の空気を思いっきり吸っていた2週間。僕は終始とてもリラックスしていてオープンマインドだった。周りにいるみんなと息を合わせて過ごすにつれ、4年前までにあった「期待に応えなきゃ」「こうでなきゃ駄目だ」という肩の力が抜け、自然と「いまこの瞬間に集中してベストを尽くそう」と思えるようになっていた。
◆台湾選挙のこと、楽団員の人生相談など、どんな話題も心を通して語り合えたと思う。いま僕が台湾にいることが運命なのだとするならば楽しまない手はあり得ない。そして結果的に自分にしかできない役割を果たしたい。「ここから見たい景色はみんなと一緒に作るんだ」。これからも人生は台湾と共にある。今回も自分を温かく受け入れて支えてくれた陳老師、その家族と仲間達に感謝したい。ただいま!台湾!!![車谷建太]
■地平線の皆様、今回の津波警報の際はご心配のメールを数多くいただき、ありがとうございました。幸い津波は来ませんでした。が、かなり焦りました。
◆あの日、朝ごはんを終えわんこの散歩に出ようとしていたとき、ラジオから「台湾で地震」という緊急地震速報が聞こえました。とっさにヤバいかも、と思いました。台湾は沖縄の目と鼻の先です。そしてすぐに津波警報が出てしまいました。うわー。
◆予報は3m。到達予想は40分後。能登の災害風景が頭にうかびました。こちらは東側とはいえ海の近くにある自宅は浸水すると思い、貴重品、三線、着替え、薬、寝袋など可能な限り持ち出せるものを車に積み、わんこを乗せ急いで牧場へ。
◆牧場から旧比嘉小学校跡へ続く津波避難道が数年前にうるま市によって整備されています。見上げるとすでに何人かが心配そうに高台からこちらをみています。牧場も海抜は低く安心できないので、すぐにすべてのヤギを小屋から出して、昇が山へ連れて行きました。私はヤギたちが戻って来られないように山道にバリケードをしたあと避難道を駆け上がり、学校へ。
◆グラウンドには40台ほどの車が並んでいて、かなりの人が集まってました。反対側の浜集落からも来ています。旧比嘉小学校は東日本大震災が起きた年に廃校になり、比較的新しい校舎一棟を残して取り壊されてしまいました(ちへいせん・あしびなーのときに山田高司さんが講演をしてくれた体育館ももうありません)。でもその日校舎は施錠され中に入れず、水もきていないのでトイレも使えません。
◆備蓄品もなし。よく晴れた日中だったからよかったものの、寒い日や夜であったなら一体どうしたのでしょう。年寄りが多いので、これは問題だ、と思いました。廃校から14年、いまだに跡地利用計画も示されないままです。幸い、津波警報は昼には解除となり、みんな次々に帰って行きました。ヤギたちも何事もなく満腹で山から戻ってきました。
◆今回は避難訓練と思って、次に来るであろう危機に備えたいと思いました。私はとっさに自分たちと動物たちのことしか頭に浮かばなかった。隣の人には声かけしたけど、島には足が悪く車を持たない人や年寄りがたくさんいる。彼らはどうしていたのか、しっかり検証する必要があると思いました。
◆海人はもずく収穫の最盛期で、海にはもずく船がたくさんでていたはずです。港に消防がパトロールにきていましたがどうしたかな。それにしてももし津波が来ていたらもずくは全部ダメになっていただろうと思うとゾッとしました。災害はいつ起きてもおかしくない、そう切実に感じた出来事でした。[浜比嘉島 外間晴美]
地平線通信539号(2024年3月号)は3月13日に印刷、発送しました。先月号は編集作業を早め早めに進めたため、余裕がありましたが、発送作業もベテランが揃い超速で18時過ぎには終わりました。北京の餃子もおいしかったですが、祥太郎くんリクエストのかた焼きそばも絶品でした。今回ものり子さんのあんパン付きでした。のり子さんありがとう。みなさんおつかれさまでした。参加してくれたのは以下の皆さんです。
車谷建太 中畑朋子 高世泉 伊藤里香 渡辺京子 長岡のり子 長岡祥太郎 久島弘 秋葉純子 江本嘉伸 武田力
■1月2日、時刻は14時30分くらいだっただろうか、母の実家を後に3km程先にある実家へ向かった。昨日まであった光景は変わり果てていた。飼い主が避難して残された犬は私と弟の気配を感じて家の中から鳴く。尋常じゃない声だ。外で繋がれている犬は私たちをジッと見て警戒していた。普通じゃない表情だった。怖い思いをして警戒しているのだと思った。
◆この子たちは主人がいなくなり心細いだろうし、お腹も減るだろうけども今の私にできることは何もなかった。子供のころにソリ遊びをしていた神社の社号標は崩れていた。電子部品を製造している工場の1階部分が潰れ、辺り一帯にビービービーと警報音が鳴り響いていた。
◆少年時代よく歩いた通りは右も左もペチャンコになっている。能登地方は能登瓦屋根がほとんどだ。雪は水分を多く含んで重く、そのため瓦は雪や潮風に対する耐久性が求められ重くなる。震度7は容赦なくその弱点を突いた。瓦が道路に散乱している。2階の部屋のカーテンが路上に吹く風でそよいでいる。家が崩落して車が押し潰されていたり、電柱が弓形になっていたり、倒れかけの点灯していない信号機に母校の名前が書かれた標識、目頭が熱くなる。
◆架空の映画のような世界が私の目の前に広がっていた。私が学んだ町野小学校は在籍していたころ、すでに100年ほどの歴史があった木造2階建ての校舎だった。廊下や体育館の床などは面取りされておらず木の節がそのまま活かされた趣のあるものだったが数年前に子供が減って小学校を合併するということになり新校舎になった。校舎は避難所になっており斜向かいの公民館と共に人が集まっていた。
◆校庭ではキャンプ用品で焚火が行われていた。子供も大人も集まって暖をとっている。年配の方は公民館で長蛇の列を作っていた。何の列かと先頭を見ると公衆電話で連絡を取ろうとしていた。この公衆電話は明朝には壊れてしまい電話をしたい者は15km先まで歩いて行かなければならなくなるのだ。公民館と小学校が避難所になっていることがわかり通学路を通り実家に向かった。
◆通学路は私の親や祖父母の時代には映画館が2軒もある通りで、どんどろ通りと呼ばれていた。どんどろとは「ぞろぞろ、どんどんと人通りが絶えない」が由来だそうだ。私の幼年期には映画館はなくなっていたが、洋菓子店や中華食堂、鮮魚店や肉屋さん、スーパーや美容室に電気屋さんが営業しておりそれなりに賑やかで、お盆祭りには町野小学校鼓笛隊で練り歩き、夜祭りには屋台が端から端まで並んでいた。「どんどろ通って帰ろう」などと言っていたものだ。
◆その通りも左右崩れ落ちて見る影もなくなっていた。首がくの字に折れる。崩れた家の窓枠にいる猫は西日に照らされこちらを観ていた。眠そうだ。遠目に見えてきた実家は倒れていなかった。一見すると瓦が崩れているだけで大丈夫なんじゃないかと思うくらいだったが母の実家同様でもう住める状態じゃなかった。基礎がズレ、柱が折れていた。
◆16時20分実家に帰宅。夕陽に照らされて妙に赤く染まっていた。仏壇に供えてある過去帳はどうなっているのかと仏間に向かった。東家の先祖が記された大切なものだ。燭台や香炉は散乱していたが、お念珠入れされている仏壇の仏様と仏間は驚いたことに何ともなかった。広間のお念珠入れした如来像は畳の上に転がっていたが、綺麗なお顔をしている。
◆広間に損傷は見当たらない。2007年3月25日の能登半島地震震度6強のときも無事だったのだ。なんといえばよいのか人の意志ではない大いなる意思を感じる。仏様と如来様と過去帳を余震で家が倒壊しないうちにと思いバックパックに入れ持ち出せるように整える。外はすっかり暗くなっていた。来た道のりを思い返すと夜道はリスクが高いので今晩は居間で休むことにした。
◆弟は散乱している家具の中から鍋や食器を見繕い、ペットボトルにためてあった水を使い、大晦日に使ったカセットコンロで味噌汁とカップラーメンの夕飯の支度をしてくれた。その間に居間のテーブルに祖父と祖母と母親の遺影を立て時計を添え、ろうそくは余震で揺れると危険だからオイルランプを灯した。
◆それから、しまってあった反射式石油ストーブを準備して暖をとった。私は「実家の居間で食べる最後の食事になるかもね」などと弟に話しながら、味噌汁を飲んだ。暖かくて安らぐ。遺影と兄弟2人の団欒。29日からテーブルの足元にポテトチップスBigサイズが置いてあったのがそのままある。ぼんやりとありがたいけどもお腹いっぱいで手を付けなかったポテトチップスは、風にゆらゆら揺れるランプの光に照らされて妙に神々しかった。あるということは何と豊かなことか。
◆弟は疲れたのであろう布団を敷いてすぐに眠りに落ちた。雨が降ってきた。私は近所にある先祖代々の墓が気になり傘をさして墓地まで歩いた。智徳寺は倒壊はしていなかったが戸が外れていたので中がなんとなく見えた。中は滅茶苦茶のようだった。本尊は大丈夫なのかはわからない。境内は舗装されていない。泥が雨と残雪で混濁、油断すると転びそうだった。
◆無事なお墓は1つもない。足元には東家と彫られた燈籠と南無釈迦牟尼仏と彫られた墓石が砕け落ちていた。どこのお寺も同じだろう。雨足が強くなる。町野は壊滅だと思った。家に戻りしばらくすると用を足しに弟が外へ出た。どこでしたのか聞いて同じ場所にした。
◆排泄すると元気になるものなのか体が軽くなって疲れが取れた気がした。体というものはそういった作りなのだろう。居間に戻ると余震で家がギシギシと軋む。実家の居間で不安を覚えることになるとは思ってもいなかった。何かあったらすぐに外へ出られるように、玄関に荷物を置いた。弟に「こうして頭を並べて居間で一緒に寝るのも今晩が最後かも」などと話しながら横になる。夜通し肌感覚で2kmか4km程先で空から鉄球が地面に落下したようなドーン、ドーンと不気味な音が響く。ビリビリ、ギシギシと家が軋むたびに飛び起きて外へ走り出ること10回、朝がやってきた。[東雅彦]
■前回は地平線会議の渡辺哲さんの車で、大地震から40日目の能登半島をまわったが、今回は大地震から100日目の能登半島をバイクでまわった。「名古屋モーターサイクルショー」でのゲスト出演を終えると、スズキSX250を走らせ、富山へ。富山駅前の「東横イン」に泊った。翌4月8日早朝、富山駅前を出発。富山ICから北陸道→能越道で七尾へ。今も昔も変わらぬ能登の中心地の七尾では、能登国分寺址を見てまわった。「のと里山里海ミュージアム」は休業中。復元された南門前の園地では年配の人たちがパターゴルフを楽しんでいた。
◆七尾から北へ。能登最大の温泉地、和倉温泉では共同浴場の「総湯」が営業を再開した。能登島大橋を渡った能登島では満開の桜並木の下でバイクを止めて一人で花見。ここでは海辺の「ひょっこり温泉 島の湯」が再開し、レストランも営業を開始している。七尾から県道1号→国道249号で奥能登の玄関口の穴水に向かったが、道路に沿って走る和倉温泉〜穴水間ののと鉄道は4月6日に全線が開通。途中の能登鹿島駅は「能登さくら駅」で知られているが、桜並木を見に大勢の人たちが花見に来ていた。
◆穴水からは国道249号で宇出津(能登町)を通り、珠洲へ。中心地の飯田の町から海沿いの道を走り、狼煙へ。道の駅「狼煙」は休業中。能登半島突端の禄剛崎の灯台を見たあと、日本海沿いの外浦海岸を行く。しかし、前回同様、椿展望台で通行止。飯田に戻ると、今度は国道249号で大谷峠を目指した。峠下の集落が火宮。『地平線通信』の3月号で森本真由美さん(故森本孝さんの奥様)が若き日の思い出として紹介されたところだ。
◆森本真由美さんは観文研(日本観光文化研究所)の仲間。奥能登・火宮の調査の話は何度か聞かせてもらったし、『あるくみるきく』(第64号)の「奥能登の村」では詳細な調査報告を読ませてもらった。今となっては貴重な資料だ。そんな火宮も大きな被害を受け、大屋根の家が何軒もつぶれていた。
◆火宮からさらに国道294号を行くと、『地平線通信』の1月号で能登半島地震を書かれた東雅彦さんが地震に遭遇した現場の大谷峠になる。しかし国道249号は峠の登り口で通行止め。そこで山中の迂回路を走り、日本海側の大谷の町に出た。ペシャンコにつぶれた「スーパーおおたに」が目に飛び込んでくる。ここから海沿いの国道249号で曽々木に向かうと次は長橋の集落。「長橋」のバス停がある。
◆今から40年以上も前のことになるが、ぼくは50ccバイクで「日本一周」した。長橋はそのときの思い出の地。ちょうど秋祭りで、キリコと呼ばれる京風の山車が2台出た。ここでは自転車で「日本一周」中のチャリダーと一緒に祭り見物をした。すると近所のおばさんが盆に赤飯とサトイモ、シイタケ、コンニャクの煮物を持ってきてくれた。おいしかった。その夜は長橋のバス停で寝た。
◆我が懐かしの長橋。国道249号はこの先は通行止めで、曽々木には行けなかった。ここまでが第1日目で、前回同様、高浜(志賀町)の「はしみ荘」に泊った。翌日は大雨。嵐のような天気。そこでカソリ、どうしたかというとバイクは宿に置き、レンタカーを借りてまわった。トヨタのワンボックスカーの「VOXY」。大きすぎるが仕方がない。レンタカーで温泉をめぐった。
◆第1湯目は和倉温泉の「総湯」(入浴料490円)。大浴場と露天風呂。ゆったりまったり入れる。第2湯目は「ひょっこり温泉 島の湯」(入浴料550円)。湯上りにレストランで食べた「カキの釜めし」(1500円)は美味だった。第3湯目の輪島の「ねぶた温泉」は休業中。第4湯目の門前の「じんのびの湯」は能登半島地震の影響で閉鎖された。第5湯目は「ユーフォリア千里浜」(入浴料550円)。大浴場と露天風呂にどっぷりつかった。
◆この日は田鶴浜(七尾市)の徳田大津ICから穴水ICまで自動車専用道路の「のと里山海道」を走ったが、その間のやられ方のすさまじさには背筋が冷たくなるほどだった。地震に弱い日本をみせつけられた。想像をはるかに超える惨状で、田鶴浜から穴水までの海沿いを走る国道249号はまったく問題なく通行できるのに、あまりの違いに驚かされてしまう。「脆すぎる」と思ってしまう。下り車線のみが開通しているが、完全復旧にはおそらく2年とか3年はかかるであろう。
◆第3日目は快晴の青空で、絶好のバイク日和。ただ風が冷たい。高浜(志賀町)から県道3号→国道249号で穴水から宇出津へ。そこからは県道6号で柳田、町野を通り、日本海の曽々木に出た。輪島市の町野町には前述の東雅彦さんの実家がある。先月の地平線報告会の後、東さんからは町野町の惨状を聞かされていたが、県道6号のバイパスを走り抜けると、その惨状がわからないまま通り過ぎてしまう。
◆ということで今回は旧道に入り、壊滅状態の町並みを見た。町野町から曽々木に向かうと、平家の落人伝説が伝わる上時国家と下時国家の豪農の家がある。上時国家は大屋根が落ち、完全に潰れていた。国道249号に出ると、まずは右へ、大谷方向に行く。曽々木海岸のシンボルの「窓岩」は見るも無残に崩れてしまった。その先で国道249号は通行止め。海に向かって崩れ落ちた山が国道を飲み込んでしまっている。曽々木から輪島方向への国道257号も同様で通行止めだった。
◆曽々木から県道6号→珠洲道路→県道1号で輪島へ。輪島からは国道249号でまずは曽々木方向に行ってみる。ねぶた温泉のある寝豚を通り、白米千枚田までは行けたが、その先は大崩落で通行止め。輪島に戻ると外浦海岸沿いの道で大沢経由で門前に行こうとしたが、大崩落で通行止め。次に国道249号で門前へ。途中の中屋トンネルの崩落で通行止めになっていたが、ここには迂回路があった。中屋峠越えの旧道で門前まで行かれた。
◆輪島市から志賀町に入るとホッとした。もう大丈夫。海沿いの道で「能登金剛」北部の関野鼻、ヤセの断崖、義経の舟隠しを見てまわる。富来(志賀町)からは「能登金剛」南部の機具岩(能登二見)、巌門を見てまわる。巌門の食堂「一海」が営業を再開しているのはうれしかった。最後に千里浜(羽咋市)の「なぎさドライブウェイ」を走り、のと里山海道で北陸道の金沢森本ICへ。富山駅前からここまでの走行距離は716キロ。レンタカーを含めれば913キロになる。[賀曽利隆]
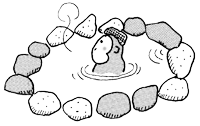
■先月の通信でお知らせして以降、通信費(1年2000円)を払ってくださったのは以下の方々です。万一記載漏れがありましたら江本宛メールください。最終ページにアドレスがあります。通信の感想、近況など短く付記してくだされば嬉しいです。
田立泰彦(5000円 「ケセラセラ」の103才はスゴイ! 90才はまだまだ若いか。残りはカンパ) 津川芳巳 中村鐵太郎(10000円 ツウシンヒトカンシヤデス) 猪股幸雄 藤本亘 石田昭子(毎月通信が届くのが楽しみです) 奥田啓司 清登緑郎 野口健志(6000円 通信費2年分+カンパ) 大塚善美(10000円 3年分通信費+カンパです)
■南米大陸のど真ん中に位置する内陸国ボリビアは、正式な国名を「ボリビア多民族国」という。1825年の独立以来ボリビア憲政史上初めて、先住民の出身で大統領に選ばれたエボ・モラレス氏が、天然資源の国有化や先住民の権利拡大、農地改革、大土地所有制限などを謳う新憲法を国民投票で議決選定。2009年3月に、ボリビア共和国から現在の国名に変更された。ケチュア族やアイマラ族ほか、混血を合わせると人口比では8割以上が先住民系で、36もの言語が使用されている、文字通り多民族国家である。
◆ボリビアといえばアンデス高地の国、ニポンでは自動的にウユニ塩湖、というのがお約束だが、実際は国土の半分が標高500メートル以下のオリエンテ(東部)地方と呼ばれる低地で、ジャングルやサバンナが広がる緑の大地だ。80年代初頭以来、何度となく訪れてきたが、久しぶりに足を延ばしたのは当然カーニバルでしょ。取材済みの南米3大カーニバルのひとつオルロは外して、ブラジルにもほど近い低地最大の都市サンタクルスを選んだ。アンデスの先住民系とブラジルのアフロ・ラテン系がせめぎ合う境界で、両者が混在する未知の祝祭空間が見られるのでは、などという甘い考えでの選択だった。
◆が、結果からいうと大外れで敢え無く撃沈! 初日の大パレードを除くと、ほとんど町内会の飲み会で酔っぱらいが騒いでいる程度の、芸も技もない水かけ祭りが3日間続いた。撮影機材ごと狙い撃ちされるため、ろくにカメラも出せない。この一枚の決めカットが撮れず、また課題を残すことになってしまった。苦しい言い訳はさておき、今回ボリビアを選んだのは別の理由もある。
◆そもそも海外からの観客ほぼゼロというカーニバルで、歩いているだけでもよそ者は目立つ。悪ガキどもの標的にされて、2階からバケツの水をぶっかけられたり、風船に入れたペンキ爆弾や泡スプレーの集中砲火を浴びたりと、やたらにツライ思いをする日々となってしまった。だが、ウクライナやパレスチナの戦場では、とてもこんな寝惚けたことをいってはいられないだろう。
◆ガザ侵攻以降、世界に先駆けてイスラエルと国交断絶したのがボリビアだったのはやや意外な気もするが、とりあえずイスラエル人は入国できなくなった。伝統的に庶民レベルの反米意識が強いラテンアメリカでは、ウクライナに関してはどちらか一方に与することはなく、停戦と交渉を呼びかけてきた。他方、その昔からパレスチナ問題では、アメリカに庇護されたイスラエルを非難することが多かった。ボリビア政府はガザで行われている攻撃と、非対称的な武力攻勢を拒絶/非難する声明をいち早く発表し、チリとコロンビアも大使召還、アルゼンチンやブラジルも抗議声明を出すなど後に続いた。現地で生の声を直接聞いてみたい、という思いもあって、高値安定のチケット代に泣きながら合計26時間の空の旅に出た。
◆たまたま現地で接近遭遇したキューバやベネズエラ、メキシコ、スペインなどなど、地元住民を含む多国籍多民族との間でやや興奮気味の論争となったのは、当方の不用意な不謹慎発言がきっかけだったのかも知れない。「ヒロシマ・ナガサキ以降、核実験や核兵器事故の犠牲者は多々あれど、核兵器による攻撃の犠牲者は一人もおらず、すべては通常兵器による」という趣旨で、単純にヒトゴロシで軍需産業が儲けるのはけしからん、というつもりだったのが、夜を徹する侃侃諤諤阿鼻叫喚の展開となってしまったのだ。
◆確かに第2次世界大戦以降、頑ななイデオロギーと憎悪のプロパガンダを駆使し開発投入された通常兵器の銃弾砲弾爆弾によって、どれだけの人々が犠牲になったことか。被害が大きいクラスター爆弾や対人地雷を制限する動きも一時はあったが、戦闘がエスカレートすれば敵を殲滅する手段に躊躇することはない。そもそも、残虐ではない人道的対人兵器とはいったい何だろうか。ピンポイント攻撃のスマート爆弾には、知性も理性も存在しない。
◆しかし、実際に先住民を有害生物として狩猟/駆除した暗黒史を刻むこの大陸の住民たち、さらには60年代以降の軍事政権による過激な自国民への拷問/暗殺を経験した人々に、ラブ・アンド・ピースは想定外のお花畑らしい。ましてや、実際に戦火をくぐってサバイブした難民やテロ被害者に核兵器廃絶や軍縮を訴えても、説得力があるとは思えない。誰もが単純に思いつくであろう兵器削減は、まるで表ざたにしてはいけないタブーのようにも見える。
◆シンガニという70度を超えるブドウの蒸留酒が減るほどに論争はエスカレートする一方で、次第に混迷度合いを増してきた。戦争は最大の環境破壊だから、15歳だったグレタちゃんに兵器輸出禁止を説得せよ、とスウェーデン人に絡むボリビアン・ギャルも現れた。我が方も、せめて兵器輸出を防衛装備移転と呼び変えて進める愚行は、再考すべきではなかろうか。[Zzz-全@カーニバル評論家]
■極端に雪の少ない冬だったが、3月に入ってから慌てたように雪が降り、春分の日の気温は3度。翌日の雪予報を気にしながら東京へ向かった。地平線キネマ倶楽部の上映作品は今井友樹監督の『おらが村のツチノコ騒動記』。未公開の最新作を試写会という名目で上映するのは異例だが、昨年6月の報告会で今井さんが話したときの反応がよほどよかったのだろう。
◆わたしがツチノコと出会ったのは50年前。もちろん本物にではなく、当時少年マガジンに連載されていた『幻の怪蛇バチヘビ』という漫画の中で。作者は『釣りキチ三平』で知られる秋田県出身の矢口高雄さん。秋田では“ツチノコ”を“バチヘビ”と呼ぶそうだ。この漫画をきっかけに(諸説あります)、日本中で空前のツチノコブームが起こったが、あれはいったい何だったのだろう? 別の方が書くと思うので映画の内容は割愛するが、出演者のほとんどがツチノコの存在を信じていることが伝わってきて、上映後はすがすがしい気持ちに包まれた。
◆今井さんは民族文化映像研究所(民映研)の姫田忠義所長に師事した最後の方だと聞いている。前作の『明日をへぐる』はたしかに民映研の流れを感じたが、『…ツチノコ…』は『鳥の道を越えて』と同じく今井さんにとって身近なテーマを撮ったせいか、民俗学的な側面に加えてプライベートフィルムのような雰囲気も濃く、これまでの民映研作品とは異なる新しさを感じた。
◆民映研の映画に接したのは、山形市にある東北芸術工科大学で1998年に開催された公開講座「映像民族学への招待」が最初だろうか。全6回の講座では『越後奥三面』をはじめ代表作13本が上映され、最初と最後の回では姫田所長が講演した。全回出席したかは覚えていないが、この講座で民映研の映画に魅せられた。
◆それから早や20数年。いつかやりたいと思っていた民映研の自主上映会を昨年5月から始めた。山形国際ドキュメンタリー映画祭(YIDFF)の作品を中心とした自主上映会は1999年から続けているが、民映研の上映会は準備から映写までを一人で行うごく小規模な会。会場はわが家から車で10分ほどの隣町にある公共施設で、スクリーンは小さいもののプロジェクターと音響設備が完備された80席のミニミニホール。椅子の用意は不要なので、受付も含めてワンオペでこなせるのがありがたい。
◆3回目となる1月の上映会では、近くまで来たからと立ち寄ってくれた民映研の小原信之さんに解説をしていただいた。上映作品は『うつわ 食器の文化』と『奥会津の木地師』。小原さんによると『奥会津…』は『うつわ…』の撮影から生まれたスピンオフで、民映研の原点ともいえる大切な作品だそうだ。次回以降の上映会は未定だが、4月下旬からポレポレ東中野でロードショー公開されるデジタルリマスター版の『越後奥三面』も上映したいと考えている。
◆地平線キネマ倶楽部で上映された『ガザ 素顔の日常』は、地元でも自主上映会が行われ鶴岡まちなかキネマでは劇場公開された。コロナ禍中にオンライン開催されたYIDFF2021のインターナショナル・コンペティションでは、イスラエル出身のアヴィ・モグラビ監督の『最初の54年間―軍事占領の簡易マニュアル』(審査員特別賞)が印象に残った。タイトルは1967年にイスラエルがガザとヨルダン川西岸を軍事占領してからの年月に由来し、その経緯を軍事占領のマニュアルに見立てて、元イスラエル兵の証言やアーカイブ映像を駆使して構成されている。今年1月に酒田と鶴岡でこの映画を上映したが、イスラエルがなぜパレスチナへの攻撃を止めないのかがわかると同時に、タイトルに「最初の」と付けた意味が今になると予言のように思えてぞっとした。
◆『おらが村のツチノコ騒動記』を観ている間、脳内で「ツチノコ…♪」のフレーズがループ再生を始めた。そのときは思い出せなかったが、山形県出身の歌手・朝倉さやさんの「伝説生物」という歌だ。伝説生物といえば、朝日連峰の山中にある大鳥池には「タキタロウ」という巨大魚が棲んでいる(らしい)。今から50年ほど前に『釣りキチ三平』で「O池の滝太郎」として紹介されてから一躍全国区になった。1982年には旧朝日村(現在は鶴岡市)が大規模な調査を行い、2014年には大鳥集落の住民と有志による調査も行われたが、その正体は今も謎に包まれたままだ。
◆6月下旬に公開予定の飯島将史監督の『プロミスト・ランド』は、山形市出身の小説家・飯嶋和一さん(個人的には新作を待望する唯一の小説家)が1983年に現代小説新人賞を受賞した同名作品の実写劇映画で、大鳥集落と月山麓の志津山中などでロケが行われた。その際に大鳥のマタギ衆(地元ではマタギと言わず「鉄砲撃ち(ぶち)」などと呼ぶ)を取材した映像が、『MATAGI―マタギ―』というドキュメンタリー映画になっている(U-NEXTで配信中)。
◆マタギといえば、関野吉晴さんも通っている新潟県の山熊田に移住した大滝ジュンコさんが『現代アートを続けていたら、いつのまにかマタギの嫁になっていた』というエッセイ集を出版した。山村の文化や暮らし、古代布の復活などを軽やかに綴っている傑作だ。山熊田と山を隔てた大鳥は直線距離で10km程度。かつては行き来もあり、熊谷達也さんの小説に、大鳥に住み着いた阿仁マタギが山熊田に嫁いだ娘のために重い婚礼箪笥を背負って雪山を超えていくシーンがあったと記憶している。
◆映画の話になると止まらず、つい長くなってしまいました。地平線キネマ倶楽部の上映会、これからも楽しみにしています![山形県酒田市 飯野昭司]
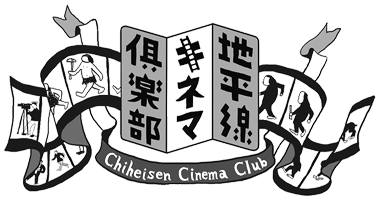
■3月20日の春分の日、新宿歴史博物館で第2回目の「地平線キネマ倶楽部」上映会を実施した。上映したのは、今井友樹監督の『おらが村のツチノコ騒動記』(71分)。昨年6月の地平線報告会では、未完成だった作品のハイライトシーンを断片的に見せてもらっただけだったので、一本の映画としてぜひ観てみたいと地平線の仲間たちから期待が寄せられていた。今井君と配給元のご厚意で、5月18日から予定されている劇場公開(ポレポレ東中野ほか)に先駆けて、試写会として特別に先行上映させてもらうことができたのだ。参加者は41名。
◆驚いたのは……と書き始めて、ふと思う。ここで映画の内容や感動を私が書いてしまうと、劇場で観るつもりでいるみなさんにとってはネタバレになってしまうのではないか。ううう、言いたい。書きたい。分かち合いたい。でも、初めて観たときの感動はやっぱり大切だ。今井君のこれまでの作品とはちょっと異なるタッチになっている、とだけ匂わせておこう。へぇぇ、あの今井君が……いけない、いけない。ここまでにとどめておかなくちゃ。
◆上映後のトークで、今井君に制作者としてのさまざまな話を聞かせてもらった。撮影を担当した伊東尚輝さんにも登壇していただき、撮影上の苦労話や今井君の監督ぶりを聞くことができた。1時間半近くに及んだトークのおかげで作品の理解が深まり、立体的になった。これこそが地平線キネマ倶楽部の醍醐味だと、つくづくと感じた。
◆特筆しておきたいのが、今回はバリアフリー版を上映してくれたことだ。登場する人たちが語るすべての台詞に字幕が付き、効果音や音楽にも短い解説が付く。地平線報告会でみんなが感じた「方言がなかなか聞き取れないよ〜」も見事に解決。伝統文化を記録する映像にとっては、大きな味方となるだろう(劇場公開版では専用のアプリをインストールして、スマホで字幕を見ることになるそうだ)。
◆親しい関係なので、トークで失礼な突っ込みをいっぱいしてしまったなと反省していたが、今井君から翌日「上映後もいつもと違う話の展開になって僕も色々な気づきや発見をもらいました。また、昨日お伝えしそびれたのですが、エンドロールには、協力者として『地平線会議』のクレジットも載っておりました」というメールをもらい、ホッとした。劇場で観るみなさん、ぜひエンドロールをしっかり確認してきてください。
◆次回の地平線キネマ倶楽部は6月1日の土曜日(地平線報告会の翌日)。笹谷遼平監督の『馬ありて』を上映する予定。詳しくは次号で。[丸山純]
■春を通り越し初夏の陽気となった3月16日(土)、JR巣鴨駅に15人の地平線仲間が集まった。この日はちょうど1年前に84歳で亡くなった森井祐介さんの一周忌。毎月発行される地平線通信のレイアウトを20年間近く担当された森井さんは今、すがも平和霊苑の飛天塚に眠っている。
◆豊島区が発祥地だというソメイヨシノ、花はまだ固いつぼみだったが、その見事な老木が立ち並ぶ染井霊園を通り抜けて歩くこと約15分。合葬墓である飛天塚の周りにはたくさんのお花が供えられてにぎやかだ。皆、森井さんのお名前が刻まれたプレートに触れてみたり、手を合わせたりと、各々に森井さんを偲んだ。
◆ そしてこの霊園には、不思議なご縁も。巣鴨駅からここまでの道のりは、18歳から23歳までの5年間、江本さんが東京外国語大(現在は府中市に移転)へ通った道だという。さらに、当日も参加されていた関根皓博さんは、18年ほど前にカメラマンとして「すがも平和霊園・もやいの会」の機関紙の写真撮影を担当していたとのこと。お二人が語られたこの地での思い出話を、森井さんも空の上で興味深く聞いていたに違いない。
◆お墓参りのあとは、外語大の跡地を散策。ここは現在「西ヶ原みんなの公園」という防災公園として利用されており、様々な世代の人がのんびりと過ごせる空間になっていた。江本さんがこの地を訪れるのは実に60年ぶりだという。景色は変わったけれど、学生時代に走ったグラウンドのおもかげが残っているそうだ。ちょうど満開を迎えていた河津桜の枝をぴょんぴょん飛び回るメジロの姿に、皆ほっこり。
◆その後は高岩寺と地蔵通商店街を散策しつつ、白山通り沿いにあるお蕎麦屋さん「駕籠町藪そば」へ。ここは落合大祐さんのご実家で、ご両親とその姉妹の方で営業されている。ありがたいことに14時から貸切にしてくださった。丸山純さんが沖縄で撮影した森井さんの遺影と長野亮之介さんが新しく作成したイラストを前に、献杯。ここで、通信編集用のメーリングリストに森井さんが投稿した言葉の数々を、江本さんがゆっくりと読み上げた。大阪在住の中島ねこさんが1年前に編集してくださったものだ。
◆「2013年8月14日 本日はおしまい。412号、16頁の姿がようやく見えてきました。ちょっとくたびれたので本日の作業は終わりにします。明日早朝から作業開始」。なつかしい、森井さんの誠実で穏やかな語り口。まるでこの場に帰ってきてくれたかのようで、皆静かに聞き入ってしまった。このメールが投稿されたのは、通信412号の印刷・発送当日。おそらく深夜0時をまわっていたのだろう。碁会所での仕事をしながら、締切直前までレイアウト作業をしていた様子が伺える。
◆私が通信のレイアウトを引き継いで、はや1年半。今でこそ印刷の3〜4日前には原稿(フロントとあとがき以外)を揃えるよう江本さんにお願いしているが、森井さんは飛び込んでくる原稿をギリギリまで待っていた。それを印刷開始までに、偶数ページに収まるようにレイアウトする。書き手の思いが伝わるように、読者が読みやすいようにと試行錯誤する時間は、楽しくもあり、ヒヤヒヤもしただろう。全体の見通しがつくまでの緊張感は、私も毎月感じている。もちろん、無事に終わった時の安堵感や達成感も。
◆ふと、森井さんとの最後の会話が思い起こされた。2022年8月、入院中の森井さんは酸素マスクをつけたまま、ビデオ通話にしたスマホの画面越しに「レイアウト楽しいでしょ」と微笑んだ。あのとき、森井さんの地平線通信への想いを受け取ったような気がしたのだった。
◆森井さんの投稿メールは、さらに続く。原稿の進捗状況、仲間への感謝のことば、レイアウトの相談、体調の報告など。その中には、通信3月号のあとがきにあるように、風邪気味の江本さんを気遣う内容のものもあった。今もそうだが、編集作業が進むにつれて熱量が高まっていく江本さんと共に通信を形にしていくには、こちらも相当のエネルギーがいる。森井さんはすり合わせを重ねることで、江本さんと深い信頼関係を築かれていったのだと思う。
◆その後、季節の天ぷらや美味しいお蕎麦をいただきながら、みんなで森井さんとの思い出を語り合った。プレゼントでもらった電動自転車でよく出かけていたこと、メンバーで日帰り温泉へ行ったこと……。仲間たちの心の中には、いまも優しい笑顔の森井さんがいる。こういうつながりっていいなあ、と改めて思った。あたたかな気持ちにさせてもらった一周忌となった。[新垣亜美]
◆森井祐介さん一周忌の参加者
伊藤里香、江本嘉伸、落合大祐、かとうちあき、久島弘、車谷建太、白根全、新垣亜美、杉山貴章、関根皓博、高世泉、長岡竜介、中嶋敦子、長野亮之介、丸山純(50音順)
■あなたとは同郷の秋田市出身で同い年。東京では地平線の集まりや、さまざまな場でよく顔を合わせ、共通の知人も多く、共感し合える仲でした。
◆さしたる深い話をしなくとも、「言わなくてもわかる」という雰囲気が互いにあったよね。突き詰めれば、自分がこれだと信じる道をひたすらに開拓し、挑戦し、進んでいくだけ。そんな思いを共有していました。
◆昨年8月にあなたが突然病魔に倒れたとき、その精神力と行動力で、あなたなら病魔との戦いさえも冒険に変えて帰還すると、私は信じていました。そしてあの人懐っこい、ヒマワリの花のような笑顔を、また私たちに見せてくれるのだと。
◆今年3月初め。あなたのお母様からの電話で、東京の病院から郷里の秋田市に移ったことを知りました。私は月末に、秋田であなたに会うつもりでいたのです。しかし秋田に帰った3月27日のその日に、あなたは旅立ってしまいました。
◆翌28日、白い布団の上で静かに眠っているあなたと最後のお別れをしました。秋田に来てからは、痛くて苦しい治療をすべてやめて、だんだんと安らかな表情になっていったのだそうですね。あなたが魅せられていた冷たい極地でではなく、故郷で、お母さまのもとで、愛され、見守られながら、旅立ったあなた。
◆「故郷の秋田に冒険学校を作りたい。そのときは、講師の一人になってよ」というあなたとの会話が、胸によみがえりました。冒険学校を作り、次の世代に冒険を引き継ごうとするあなたを見たかったし、あなたが夏に主催していた冒険ウォークに、あと2年経ったら小学3年生になる息子を送りたかった。あなたと一緒に、私も夢を見せてもらっていたことに、いまさらですが気がつきました。
◆あなたの肩書は「夢を追う男」。長年夢に見ていた、白瀬ルートでの南極点到達。その挑戦を年末に控えていたタイミングで病気に倒れ、さぞ残念でならなかったでしょう。でも、「人の遺志は受け継がれる」とあなたはよく言っていました。あなたが、秋田県にかほ市出身の南極探検家、白瀬矗(のぶ)の活動を引き継ぐことを夢に見たように、あなたが見せてくれた熱い心や誠実さ、努力、ひたむきさを、私たちは忘れません。そして、あなたから受け取ったものをしっかりと受け継いでゆきます。
◆本心を言えば、あなたが夢を語る姿をもっともっと見たかった。夢を追うあなたとともに走りたかった。残念で、寂しくてなりません。でもあなたは、“阿部雅龍を生きる”という冒険を、あなたにしかできない冒険人生を生き切りました。最後まで「夢を追う男」として。その生きざまは、全部ひっくるめて、やっぱりカッコよかった。
◆「41歳、早すぎるよ」と言いたいけれど、あなたは人の300年分ぐらい濃厚な人生を生きた。世界中を歩き、誰よりも見聞し、さまざまな人に出会った。そして誰よりも、周りの人を応援し、大切にした。だからこそ、たくさんの人から応援され、深く愛された。
◆駆け続けた日々だったから、今はどうか、ゆっくり休んでください。またいつか、あなたに会える日がくると信じています。友よ、ありがとう。冒険よ、永遠に。[小松由佳 2024年4月11日]
2023年9月5日、阿部雅龍さんが久々にSNSを更新した。思いがけない内容だった。彼を支えてきた仲間たちへのメッセージだった。地平線通信の読者に知っていてほしいと願い、以下全文を掲載する。このメールが阿部雅龍の最後の文章となった。合掌。[江本嘉伸]
■いつも応援ありがとうございます。プロ冒険家の阿部雅龍です。事情がありSNSなどから離れていました。実は南極前に過去最高難易度の冒険に出ることになりました。脳腫瘍(脳ガン)が見つかり手術をすることになったからです。
◆お盆の間に突如として激しい頭痛と吐き気に襲われ、痛み止めを飲んでも眠れず、あまりの痛みで幻覚を見るほどでした。救急外来で病院に行き脳のCT検査後、そのまま緊急入院。大きな腫瘍が脳室にあり、腫瘍から出血したことが原因でした。
◆腫瘍はこの1年で一気に大きくなるものではなく、何年もかけて大きくなるもの。思いおこせば思い当たる節はありました。急に頭痛に襲われたり、視力が一時的に落ちたり、物覚えが極端に悪いときがあったり。8月に富士山に登ったときも、十分に有酸素系トレーニングをしているのに標高3,000mで頭痛があり驚かされました、過去ではあり得ないことだったので。すべて長年の冒険人生のダメージ蓄積によるツケのようなものと思っていましたが、それらは悪化しているサインだったのかもしれません。
◆不幸中の幸いといえるのは、腫瘍の出血が脳室という水が通るための空洞になっている部分だったので運動や言語などの麻痺が“今は”ないことです。とはいえ、腫瘍がかなり大きく、放置しておくと水頭症になるため対策しなければなりません。頭蓋骨を開けてみないと癒着の具合はわからないとのことですが、腫瘍が大きいので癒着の可能性はあります。
◆9月7日(木)に全身麻酔による手術があります。記憶をつかさどる海馬の近くに腫瘍があり自分で判断ができないようになる可能性があるかもしれませんし、記憶ができなくなるかもしれません。南極と違い、自分が望んだ冒険ではないけど、病気という冒険に自ら勇気を持って立ち向かいます。今回の舞台が南極ではなく病魔であるだけです。今までどんな逆境にも負けずに笑顔で立ち上がってきました。受け身ではなく自ら選んで挑戦者として闘う。それが阿部雅龍という男であり冒険家を職業とする人間としての生きる姿勢です。
◆しらせルートによる南極点単独徒歩到達の夢を達成させる。応援してくれるお一人お一人の気持ちに寄り添えるように、何より自分の夢を叶えるため。
◆だから、挑む。行ってきます。[感謝を込めて 阿部雅龍]
■「『卒論って意味あるんですか』と言われ、ゼミ生が論文を書いてくれない。どうしたもんだろう」。お世話になった教授から、卒業生グループLINEに届いたSOS。どうやら、今どきの学生はコスパとタイパを重視するため、時間をかけて自ら調べ、数万字におよぶ論文を書くという効率の悪い(?)学問に意欲を示してくれないのだとか。大学なんて、無駄に時間を費やし、社会の役に立つかどうかわからないような趣味に没頭し、屁理屈と揶揄されそうな哲学なんかに熱を上げるものだと思っていた。それが、コストやタイムのパフォーマンスを求められる時代になってしまったのか……。
◆ちなみに、わたしの卒論は「大学生の精神的欲望とその表出行動」という、思い返せば気色の悪いタイトルだった。「精神的欲望」とは、芥川龍之介の『河童』に出てくる「阿呆の言葉」の一節。「物質的欲望を減ずることは必ずしも平和をもたらさない。我々は平和を得る為には精神的欲望も減じなければならぬ」から拝借した。歴史的に大学生はどのように「精神的欲望」を満たしてきたかという疑問を、60年代に学生運動をしていた活動家や宗教にハマった現役学生など、さまざまな猛者にインタビュー取材をし、考察した。
◆かつての活動家はインタビュー当時も活動家で、国会議事堂まで一緒にデモ行進をしながらインタビューをさせてもらった経験はとてもスリリングで、当時の胸の高鳴りを今も覚えている。担当教授からは、何度も「公安に気をつけろよ」と心配されたことも微笑ましい思い出だ。この卒論が何か意味があったかといえば、答えはノーであるし、コスパもタイパも悪い。ただの自己満足であった。けれど、わたしの「精神的欲望」は満たされたし、自分の足を動かして好奇心のままに生身の人間を取材する、わたしの原点ともいえる経験だった。
◆前置きが長くなってしまったけれど、この一年ほど、コスパやタイパと真逆に生きる人びとを取材していた。舞台は、奈良県宇陀市にある日本最古の私設の薬園「森野旧薬園」。約300年前、吉野本葛粉の老舗・森野家の当主・森野藤助が自宅の裏山に拓いた。ときは、疫病で多くの民が命を落とした時代。徳川吉宗は、薬種の国産化と薬草栽培に望みをかけていた。吉宗は、全国に隠密で採薬使を派遣した。もちろん、薬草が豊かに茂る宇陀にも。宇陀は、推古天皇が日本ではじめて薬猟りをしたといわれるほど薬草の歴史が深い土地。宇陀に派遣された採薬使が、紀州藩出身で吉宗の御庭番、植村佐平次で、その案内人に抜擢されたのが森野藤助だった。そして、この採薬行から持ち帰ったカタクリが、薬園に植えられた最初の薬草となった。
◆薬園は、今も当時の姿そのままに250種以上の薬草木が根を下ろす。その世話をするのが、藤助の再来かと思わせる91歳の原野悦良さんとヒデ子さん夫婦。雨の日以外、薬園に毎日通い、淡々と丁寧に薬草の命をつなぐ。原野さんは、手間を惜しまず「かわいらしい、かわいらしい」と、わが子のように薬草を慈しむ。ある人が「薬草は、気づいたら消えている。手をかけないといけない」と言った。毎年、同じ場所で育てているだけだと枯れてしまうのだという。原野さんは、その年の土の状態、日照時間、水捌けを見極めながら、どの薬草をどこに植えるか、頭の中でシミュレーションしながら10年先を見るのだとか。
◆薬草の儚く神秘的な美さと、原野さん夫婦のチャーミングな姿に心惹かれ、薬園の春から夏にかけてを撮影した番組『Herbal Symphony/薬草歳時記』を制作し、去年の9月にNHKの国際放送(英語版)とBS(日本語版)で放送した。番組は、海外からも好評で第二弾の制作が決まり、この3月に秋・冬編を制作し、国際放送(英語版)にて放送した。
◆「伊勢神宮に行きたい」。第二弾の制作が決まってまもなく、打ち明けてくれた原野さんの願い。じつは、採薬使の植村と藤助は、採薬行の道すがら伊勢神宮に立ち寄り、薬木を植えていた。興味深いのは、伊勢神宮の建立の起源に疫病からの影響があったこと。2000年前も300年前も、疫病が影を落とす。人類の歴史は疫病との戦いの歴史でもあることを、コロナ禍を経験した今、あらためて実感する。
◆藤助は、伊勢神宮に植えた薬木が枯れたと耳にし、その薬木の命をつなぐため、苗木一本を携えて宇陀から伊勢神宮に何度も通ったという記録がある。なぜそこまで? コスパやタイパを考えると、非常に効率の悪い話である。さらに、現在、薬園の世話をしている原野さんは、この藤助の思いを汲んで、伊勢神宮に植えたといわれる薬木の苗木を自宅で密かに育て、伊勢神宮へ植え替える機会があった場合にと備えていた。自己満足なだけなんだよと、はにかみながら「雑草なんてない。薬草ひとつひとつに命があるんだよ」とまっすぐな瞳でいう。原野さんと伊勢神宮へ向かう道すがら、その姿が何度も森野藤助と重なり、時空を超えた旅をしている気持ちになった。そして、伊勢神宮で発見された当時の日誌を目にし、思いがけず目頭が熱くなってしまった。
◆手をかけることを惜しまず、ちいさな命たちを慈しむ人びとは、薬草と同じように気づいたときには消えているのだろうか。どうかささやかにでも、輝き続けてほしい。そんな思いを込めながら、いま日本語版の番組を制作中です。日本語版は、残念ながらBSでの放送は厳しいようで、奈良局限定ではありますが4〜5月に春・夏・秋・冬それぞれ25分で全4回(4月18、25日、5月16、17日)の放送が決まりました。奈良にお住まいのかた、ぜひぜひご覧ください。英語版はHerbal Symphonyと検索すると、全編がご覧いただけます。
◆明日で夏休みが終わりなのを知って驚いた。今日はもう30日だった。この夏休み、勉強もよくやったが、遊ぶこともよく遊んだ。悔いなしとは言えないが、毎週3回O君と学校で勉強したことは家にいればすぐ遊んでしまう昼間を有効に使えたと感謝している。今日は映画を見た。スカラ座で「恋愛時代」と「侵略者」であった。
◆今日は静かで天気もそう悪くなかったので朝、熊助《当時飼っていた黒い雑種犬。江本の最初のわんこ》を散歩に連れて行った時は実に快適だった。金もあるしどこかに行こうと思っていた所、IとNとIが近くのU君の家にやって来た。僕の誕生祝いと聞いて驚いたり喜んだり。とくに女性が2人見えたと聞いた時にはバットとボールをおっぽり放して家へ駆け込んだものだ。おかげで20円のマリを1個なくしてしまった。大きな立派なアルバムをもらって非常に嬉しかった。こういう時の友はありがたい。3時頃に映画に行った(男3人で)。「沈黙の世界」と「赤い風船」とを横宝で見た。「沈黙の世界」は流石に赤道直下の海底の事だけあって実にきれいだったが、「青い大陸」の方が印象深く感じた。「赤い風船」は美しい色調、フランスの下町だがすすけた彩(いろ)も青々とした感じで、又主役の少年が可愛らしく短編であったが、見応えのある作品だった。その後30円のカレーライスを食うのをやめてもう1本「あの高地を取れ」という米陸軍物を見た。リチャード・ウィドマークは良い。
◆「マナスルに立つ」を見た。この前のエヴェレストも良かったが、今度の方が日本人のものだけにうたれる所があり、一層良かった。頂上までカメラに収め、途中の部落の様子等も興味深かった。そうして、空の色が実に素晴らしい。真青というが、あまりに蒼い。その空に白銀の嶺がそびえ、雪の中を黙々とすすむ一行は印象的だった。日本でこれだけの映画ができるのだからすごい。
◆オリンピック 《メルボルン》が昨日から始まった。何よりも素晴らしい。開会式の選手の感激もわかる気がする。聞いているだけで胸が躍ってきてしまう。陸上は振るわないが破れてもいい。ラジオに全神経を集中させてしまう。
◆映画「Gone with the wind」を見る。期待に違わぬ名編であった。3時間半〜4時間の間終始全神経を集中して見ることができた。既に「Gone with the wind」5巻を中学時代に読んでいたので映画を理解するのに非常に役立った。ヴィヴィアン・リーというひとは「欲望という名の電車」に主演してアカデミー賞か何かもらったのだがそれと今日の映画を見た僕には忘れ難い女優のようだ。
■毎号、長野亮之介画伯がどんな題字を描いてくるか楽しみだ。今月のはわかりますか? わからないよね。本人によれば、タイトル文字は伊豆七島の形を模しているそうです。「左から、大島、利島、新島、『通』が神津島で、三宅島、御蔵島、八丈島になります」とのこと。そうか7つの島で描いてきたか。さすが、長野亮之介。そして、上の文章を読みながら私も一度は「祥太郎君の島」に行きたいぞ、と強く思った。あの、10メートルから飛び降りたあの崖を見に。
◆きのう16日、衆議院島根1区、長崎3区、東京15区の補欠選挙が告示された。アメリカ政府に国賓として招かれた岸田首相の議会演説はユーモアを含めて好評だったようだが、国内に帰れば、派閥の政治資金問題など混迷が続く政治。とくに東京15区(江東区)には9人もが立つ賑やかさ。
◆なぜか気になり、夜に開かれた青年会議所など主催の「ネット討論会」を思わず最後まで聞き入ってしまった。しかし、ほとんどの候補者はこれまで通りの無難な発言に終始。これだけ混迷を深める世界にどう対処してゆくのか、相当な緊急事態と思うのだが。[江本嘉伸]
 |
神集う島の異邦人
「校舎の窓からギランギランに光る海を見て、ここなら青春できると思って」と言うのは長岡祥太郎さん(18)。コロナ禍の最中、学芸大附属中学から伊豆七島の都立神津高校へ島留学しました。一学年18名のうち、留学生4名以外は幼馴染です。 ほとんど島から出たこともない同級生達と共有できる体験もなく、異文化交流に戸惑う日々。膠着状態を打開したのは、高さ10mの崖から海への飛び込みでした。地元でもできる人が少ない大ジャンプを決めた祥太郎さんは、いわば通過儀礼を経て、神津島の村社会に認められます。 以降はリーダー不在のクラスをまとめ、文化祭ではドラムを叩き、生徒会長も務めるなど、島の自由な環境の中で自分の様々な可能性を発見しました。島の生活を描いた「島ヘイセン通信」は当通信に不定期連載され、反響を呼びました。 この春から都内の大学で対人社会心理学を学び始めた祥太郎さんは、両親と同じ音楽家の道も模索しているそうです。今月は祥太郎さんに、島で暮らす中で考え、見えてきたことを語って頂きます! |
地平線通信 540号
制作:地平線通信制作室/編集長:江本嘉伸/レイアウト:新垣亜美/イラスト:長野亮之介/編集制作スタッフ:丸山純 武田力 中島ねこ 大西夏奈子 落合大祐 加藤千晶
印刷:地平線印刷局榎町分室
地平線Webサイト:http://www.chiheisen.net/
発行:2024年4月17日 地平線会議
〒183-0001 東京都府中市浅間町3-18-1-843 江本嘉伸 方
地平線ポスト宛先(江本嘉伸)
pea03131@nifty.ne.jp
Fax 042-316-3149
◆通信費(2000円)払い込みは郵便振替、または報告会の受付でどうぞ。
郵便振替 00100-5-115188/加入者名 地平線会議
|
|
|
|
|
|