

8月9日。お、朝は涼しいぞ、と思っていたら急にどしゃぶりの雨。きのう8日(立秋である)は、都心で今年17回目の「猛暑日」を観測し、史上最多記録となったばかりだが、確かに雲や森の緑に秋の気配が強く出てきている。といいつつ台風6号が九州を直撃しそうな気配で線状降水帯の発生が警戒されている。そして7号もすぐそこに。
◆ロシアは、相変わらずウクライナと西側各国を相手に戦争をやめる気配はない。ゼレンスキー大統領はきょう、「反転攻勢は非常に難しい」と率直に語り、あらためてアメリカほか各国に武器の支援を求めた。昨年2月24日に始まったウクライナへのロシア軍の侵攻からやがて1年半。私を含め世界はプーチンの暴挙にもう慣れてしまった感じだが、とんでもないことだ。
◆『夕暮れに夜明けの歌を 文学を探しにロシアに行く』という本がこの夏、私の心から離れないでいる。32回紫式部文学賞を受賞したというこの作品、高校卒業後の2002年、ロシアに渡り、ロシア語とロシア文学をひたむきに学んだ日本の女子学生だった奈倉有里さんがロシア国立ゴーリキー文学大学を卒業して帰ってくるまでの6年を綴ったもの。ロシア人の中に入って懸命に文学を学ぼうとする主人公のひたむきな生き方に深く胸を打たれた。「本気を出せるかどうか」がいちばんだいじな基準だったという奈倉さんの心情。そして、敬愛するロシア人教師との深い交流をあらわすいくつかの章はただただ、感動させられ、時に私としたことが涙が滲み出るほどだった。
◆この本、実は梅棹忠夫山と探検文学賞の候補作(今年は4作品)の1つで、私は文句なしに推すつもりだったが、選考の席を外れることとなり、自分が受賞者の1人になってしまったため、機会はなくなった。しかし、文学が果たす役割を久々に思い知らせてくれた本である。一度だけここに書かせてもらう。
◆7月24日。長野市でのその梅棹忠夫山と探検文学賞の受賞式。当日の模様は受賞者の1人、大石明弘君に書いてもらっている(21ページ)のでここでは省く。前にお知らせしたように選考委員は12回目の今回で役目を終え、あとは岡村隆さんが継いでくれることが正式に発表された。
◆その足で北陸新幹線で金沢経由福井に向かった。前々から福井にいる塚本昌晃君(通称めがねや)に一度行くぜ、と声かけしており、今回はちょうどいい機会だった。福井というと兵庫県豊岡市の植村直己冒険館に行き、やはり梅棹賞のため米子に泊まり、長野に向かった何年か前の体験しかない。あの時は、魚の内臓を塩漬けしてさらに糠漬けするへしこというもの味を知ったのだった。
◆地平線報告会にかなりの頻度で(ほんとうにしばしば)参加している塚本君をこちらから訪ねたい気持ちが少しあった。結果的に何から何までお世話になってしまい、恐縮でした。駅近くのホテルにチェックインしてすぐ魚の美味しい割烹に連れて行ってもらった。翌日は休みを取った塚本君の車でまず勝山市の白山神社へ。苔と森の深い緑に包まれた静謐な場所だった。ここだけでも私は満ち足りてしまったが、九頭竜川の支流、塚本君が飛び込みを仲間を募ってやるという川の淵を見おろして爽快な気分となった。そして、清流に脚を浸してぼうとした時間を過ごすことができる“脚冷やし流れ”もとても気に入った。
◆そして、恐竜である。福井は今や日本の恐竜の中心地ともなっている。1988年、勝山市で恐竜化石が発見されて以来、日本の恐竜研究は一気に進んだそうだ。こればかりは自分の勉強不足を恥じ、その道の権威、三輪主彦さんに電話した。三輪さんによれば日本では福井、石川県を流れる手取川流域の手取層群が恐竜化石を埋蔵する場所として以前から知られていた。それを現在の観光地にまで押し上げたのは研究者の熱意の賜物という。
◆1987年、社会主義の国だったモンゴル人民共和国を旅した際、ボルガン・ソムという村で「炎の崖」の名で知られた恐竜の発掘現場に立ち入らせてもらったことがある。ここが古生物学上重要なのは、ここで「卵」が発見されたからだ。モンゴルが社会主義の看板を下ろし市場経済への移行が決まったころ、ウランバートルの外国人アパートには恐竜の卵を売りにドアブザーを押す遊牧民がしばしば現れた。もちろん、禁じられていることだが、何よりもドルにしやすいものだったのである。
◆恐竜博物館は、子連れの家族たち、外国人ツーリストで賑やかだった。なんと年間100万人も来館者がいるそうだ。福井駅前には2頭の大きな恐竜が咆哮しながら睨み合う迫力の場面まで用意されていて“恐竜王国福井”は見事に実現されているのだ。皆さん、福井は水がいい。恐竜がいい。そしてなによりも、苔がいいです。[江本嘉伸]
■7月の報告者は、昨年の今頃まさに南極で「越冬」真っ最中だった澤柿教伸さん(56歳)。第63次南極観測隊越冬隊長としての任務を全うし、この3月に帰国した。氷河地形学・氷河地質学の専門家として、20代のころより計4回の南極越冬を経験。30年間に渡り最前線の現場に立ち続けている、まさに「南極観測の生き字引」と呼ぶにふさわしい存在だ。「報告会予告に向けた取材の際に長野さんと話していて、引き出されたものがあって」とのことで、生い立ちから最新の現場報告まで、南極一直線の人生をたっぷり語っていただいた。
◆1966年、母の実家のある石川県羽咋市で誕生。奇しくもそこは、日本初の南極探検船「開南丸」の船長、野村直吉の出身地だった。富山県上市町で平安時代から続く浄土真宗のお寺の長男として、「愛してやまない、様々に表情を変える立山連峰」を仰ぎ見ながら育つ。剱岳で遭難した方の法要が寺で営まれるのを見て、子どもの頃から「山は怖い。でもあんなに綺麗なところなんだから、やめられないんだろうな」と思いながら過ごしていた。
◆高校生のとき、星降る夜道を自宅へと歩きながら詠んだ歌がある。「月光の紫に 眠る剱岳 雪鳴らしゆく 玻璃の夜の家路(みち)」。和歌は住職の祖父に訓練され、橙庵(とうあん)という名もつけてもらった。雄大な自然の中で生きる喜びを全身で感じながら育った青年時代だった。
◆このころの愛読書は「探検と冒険(朝日講座)」全8巻。今も折に触れて読み返す。澤柿さんは「本や人との出会いが、今の私につながっている」と振り返る。特に記憶に残ったのは、白瀬矗、アムンセン、スコットの3人が同時期に南極点を目指した1911年の「南極点到達競争」だ。南極点一番乗りはアムンセンに譲ったが、この時の白瀬の功績のおかげで、約50年後、日本は敗戦国という不利な立場にも関わらず国際社会から黎明期の南極観測に参加する権利を与えられる。それが1956年の第一次南極観測隊発足、そして昭和基地建設へとつながっていくのだった。
◆南極探検についての本を読みふけるうちに、そこに登場する人物に北大出身者が多いことに気づいた。第一次南極観測に参加した富山県芦峅寺出身の山岳ガイド、佐伯富男。昭和基地が建つ東オングル島と西オングル島の間にある小さな瀬戸の発見者で、「中の瀬戸」という地名の由来になった中野征紀医師……。「北大に入れば南極に行けるかもしれない」という考えは、高校生らしい自然な発想だった。
◆北大に進学した澤柿さんは、第一次南極越冬隊員で地質学および犬ぞり担当だった菊池徹が在籍した理学部地質学教室に入る。菊池は映画「南極物語」で高倉健が演じた主人公のモデルとなった人物だ。卒業後は「寒冷地の野外研究者」を目指し、大学院環境科学研究科へと進学。ここは「環境科学」という名称が初めてつけられた、その分野の最先端をいく大学院だった。
◆「開拓者は矢を受け、入植者は土地を手に入れる」という格言がある。澤柿さんの研究モットーは「…されど、開拓者たれ」。その言葉を体現するかのように、ヒマラヤ、パタゴニア、ヨーロッパアルプス、スバールバル、グリーンランド、カムチャツカと、世界中を飛び回って地質調査に明け暮れた。
◆1991年、北極圏にあるスピッツベルゲン島(ノルウェー領)で行なった現地調査の映像が映し出される。大自然の中に身を置く澤柿さんは実に活き活きとしていた! しかも地平線会議でもおなじみ、研究室の4年先輩にあたるというハワイ在住の極地環境研究者・吉川謙二さんの姿もある。
◆20代の若かりし2人は、急きょ現地入りすることになった指導教員を迎えに行くため、なんとゴムボートで川を下って空港へ向かう準備をしているところ。川と河原と岩山しか見当たらない極北の大地の中、この川下りは一体どんな旅だったのだろうか。続いて映ったのは、人ひとりがやっと入る大きさの氷の穴を掘り、その奥に潜り込んでいる吉川さんの姿。氷の内部構造を調査しており、穴が潰れるのが怖いので、ときどき澤柿さんが生存確認をしに行ったという。
◆澤柿さんは、自らの研究内容を「『氷の下の見えない作用』や『過去の現象』を、科学的理論と想像力で復元する」と言い表した。30年以上も前、地球のてっぺん付近の大自然の中で、日本の若者2人は本当に楽しそうに過ごしていた。毛糸帽を被りスコップを担いだ吉川さんは、満面の笑顔だ。こんな映像を見せられると、現地で自らが見たことをつなぎ合わせ、壮大な地球の歴史を紐解いていく地質学研究の面白さが強烈に伝わってくる。フィールドワーカーとしての澤柿さんの根底にあるものを見た気がした(澤柿さんと吉川さんの調査話は、2023年4月の地平線通信528号に記載あり)。
◆また、年間100日以上を登山に費やすほど打ち込んでいた北大山岳部での経験も、現在の南極研究に活かされている。南極にはつるつると磨かれたような岩があり、それは氷が削ってできたとする氷派が優勢だった。しかし澤柿さんは、それが学生時代からの沢登りで見慣れている「水が作った地形」だと考え、劣勢の水流派=「開拓者」として矢を受ける立場にいた。すると近年、南極の2000m級の氷層の下に液体の水が存在することがわかった。澤柿さんの読み通り、水流派が巻き返しつつあるのだという。
◆初めて南極越冬隊に参加したのは1993年の34次隊、大学院博士課程1年のとき。一緒に調査をしていた極地研究所の先生に声をかけられたのがきっかけだった。27歳の澤柿さんは、1次隊以来36年ぶりにボツンヌーテンという山に登った。「憧憬の 雪原に立ちて 夢はたし 日高に眠る 友と語らう」。一緒に南極に行きたいと常々語り合っていた山岳部の学友は、日高で亡くなった。彼も来られたらよかったと、思わず出た歌だった。
◆大学院卒業後は北大研究室の助手やカナダの大学への在学派遣などを経て、2015年に法政大学社会学部教授・国立極地研究所客員教授として着任した。地平線会議にも積極的に参加し、法政大学の「探検と冒険ゼミ」に所属する若い学生たちを報告会へと導いている。ゼミ生たちによる毎年の研究発表会では「地平線会議を40年支えた人たち」「ランタンプラン」など地平線会議に関連したテーマを取り上げた。地平線会議代表世話人である江本さんが「山の日」施行に向けて書かれた論考を読み、学生たちと共に「人間の生きる力」を見つめ直した事もあったという。地平線会議とのつながりが深まる中、荻田さんの北極ウォークに参加する学生も出てきた。
◆副業としては、南極観測の若い後継者を育てるための教科書作成、フィールドワーカーと社会の活動をつなげるNPO法人としてシリーズ本の出版、雪崩事故防止研究会の活動など、研究者でありながら「若者に伝える場」を多岐に渡って作られているのが印象的だ。
◆大学院時代の34次隊(27歳)を筆頭に、研究者としての道を進みながら、47次(39歳)、53次(45歳)、そして今回の63次(55歳)と計4回の南極越冬を経験した澤柿さん。南極に何度も行く人はいるが、「20代の頃から、程よい間隔で30年間に亘って行けたというのは非常にまれ」という。古い時代も新しい時代も知る、貴重な存在だ。
◆南極観測は国家事業であり、各省庁や研究機関が参加して「オールJAPAN」でことに当たる、横つながりの巨大な組織。そのいちばん末端の実行部隊が南極観測隊だ。そして、それを指揮するのが観測隊長と越冬隊長。
◆2021年秋出発の第63次南極越冬隊は、準備期間も含めてコロナ禍の真っ只中にあり、イレギュラーな対応が多かった。封鎖された環境である南極生活にコロナを持ち込むわけには行かない。出発前の10月末から14日間の隔離生活を送った。そして11月10日、南極観測船しらせは、いつもの晴海埠頭ではなく横須賀の自衛隊基地からひっそりと出航した。
◆昭和基地のある東オングル島までは、日本から約14000km。ひたすら南へと進む。寄港地のオーストラリアでは外国人は完全にシャットアウトされ、軍港で燃料補給だけを受けた。日本で隔離生活を始めて1か月半以上が経過した12月16日、ようやく昭和基地に到着した。
◆しらせが接岸しているのは、南極の夏に当たる12月中旬から2月の2か月間だけ。実は今の南極観測隊の主力は、この2か月間だけ効率よく活動して帰る夏隊だ。越冬隊30名に対し、夏隊は80名もいる。しかし、夏隊が観測に100パーセントの力を出せるのは、越冬隊が1年間昭和基地にとどまり、設備の維持や研究の下準備など全部お膳立てしているからこそ。「それが越冬隊の役割」と聞いて意外に思ったのは、私だけではないだろう。
◆そんな越冬隊のサイクルは、12月中旬に南極入りし、2月にしらせが帰国する際に「置いてきぼり」にされて越冬。翌年12月にやって来たしらせが連れてきた次の観測隊に引き継ぎをし、2月に南極を離れる。南極滞在期間は通算14か月。今回は全行程512日、隔離14日だった(南極到着前後のエピソードは、2022年1月の地平線通信513号に記載あり)。
◆第63次南極越冬隊は32名。さらに直前でコロナ感染者が出た時に備え、4名の交代要員をお願いしていた。越冬隊長1名、観測部門13名、設営部門17名、同行者(報道)1名という構成だ。昔と違い、実際に観測に従事するのは半分以下。設営部門は車両、発電機、建築土木、通信、野外観測支援、医療、調理などで、生活環境の構築や観測活動のサポートを担う。今回同行した医者は2名とも女医で、これは史上初のこと。その他の隊員は全員が男性だったので、いつもは女性隊員のために日本とインターネットで医療相談用のホットラインを作るところ、今回は男性用のホットラインを作ったという。
◆昭和基地は国際的にも重要な観測拠点であり、観測部門のうち気象庁から派遣された5名は、3交代制で24時間途切れなく定常観測を続けた。その他にも個人の研究や、1000本のアンテナを立てて行う大掛かりな大気観測、地震や重力の長期的な観測など、やるべきことは数多い。
◆南極観測は6年をひと区切りとして進められ、63次隊は第IX期6か年計画の最終年度を担った。6年間の総ざらいをし、次の6か年に引き渡す役目だ。トピックとして、いくつかの成果が紹介された。
◆昭和基地にある約60もの建物を30名ほどの越冬隊員で管理するのは非常に大変なので、観測に関わる様々な部門の建物を集約して3年前に新しい建物「基本観測棟」が完成していた。今回、シャッターに不具合があり使用できていなかった放球デッキ(高層気象観測のため1日2回気象隊員が気球を上げる)の修理を終え、本格利用を開始できた。旧放球棟は、第64次夏隊が解体する。
◆大気観測用のUAV(無人航空機)を気球につなげて上空数万mまで上昇させる「エアロゾルUAV観測」。飛行機は成層圏での観測終了後に気球を切り離し、プログラムに沿った自律飛行で昭和基地へ帰ってくる。飛行機が行方不明になって探しに行ったりもしたが、計4回の飛行を成功させることができた。
◆観測の付随業務や、生活のためにやらねばならないことも多い。雪がほとんどない3月4月は、冬ごもりの準備として燃料を保管場所へ運び、タイヤで走るタイプの車は車庫に格納する。火事で住居を失うと命取りになるため、限られた水で初期消火できるように消防訓練は頻繁に行う。年間を通して氷点下という気候の中での作業はさぞ大変だろう。
◆今回、基地内をリフォームしてスタジオを新設した。隊員の出身校などに向けて開催する南極教室を始め、情報発信も越冬隊の重要な任務だ。夏隊で同行する学校の先生たちや報道関係者にも新しいスタジオを使ってもらった。屋外中継についても、これまではマイナス30度の中ポキポキと折れてしまうカメラケーブルとの戦いだったが、近年性能が飛躍的に上がっているスマホの電波「ローカル5G」を使用することで、基地から離れた場所での中継が手軽に行えるようになった。
◆自然現象に合わせ、臨機応変な判断を求められる場面も多かった。気温がプラス4℃を上回ったことによる、まさかの雨漏り事件。季節外れのブリザード、行動を制限される海氷の流出……。自然の巨大な力に翻弄され、隊員の安全とミッション遂行を背負った隊長としての緊張感は相当なものだったに違いない。
◆そんな張り詰めた日々を乗り越えるためでもあるのだろう、雪と氷ばかりの南極で少しでも生活感を出そうと、季節行事はきっちり行った。ひな祭りやお花見(ちり紙で桜の木を作った)、鯉のぼり、七夕。南極名物そうめん流しは、氷山に溝を掘ってお湯を流す。めんつゆとお箸を持って氷の大地にひざまずく隊員たちは、手袋をしたままで、ちょっと食べにくそう。全天を覆う緑色のオーロラは冬の楽しみの1つだが、マイナス30℃の寒さとの戦いだ。
◆海洋生物調査という名目で釣りもする。電動リールを工夫し、水深600mにいる深海魚のライギョダマシを3匹同時に釣り上げた。これは観測隊史上初めてのこと。魚拓をとり、美味しく食べた。
◆日本で夏至を迎える6月ころには、南極の冬至をお祝いするミッドウィンター祭が開催される。外が暗くて仕事ができないこの時期に4日間を遊び倒す、越冬隊の一大行事だ。隊長による開会宣言と氷のお椀への聖火点灯を皮切りに、専用コースを作ったボブスレー大会、クイズ大会などが繰り広げられた。メインイベントは、全員が正装で参加するディナー。ちょっと改まった形でフルコースの食事をして、越冬後半戦に向けて英気を養った。
◆南極では基地間の国際交流も盛んだ。世界各国の南極基地とシーズナルグリーティングカードを交換したり、昭和基地のオリジナル映画を作って南極映画フェスティバルに参加したりと、越冬同志たちとの関わりを楽しんだ。初開催の南極越冬基地スポーツ対抗戦のダンス部門では雪の中みんなでよさこいソーラン節を踊り、パワー系競技では入賞もした。
◆ここ数年、基地間で小型航空機を飛ばす“DROMLAN”という南極の中だけの国際航空網が活用されている。飛行機の管制業務、天候などの情報の通信業務などをインターナショナルに行うのも最近のミッションのひとつだ。昭和基地沖の海氷上を雪上車でならして滑走路を整備し、5便を受け入れた。ここでもコロナ感染対策のため、昭和基地にやってきた人は1週間別の建物に隔離し自炊生活してもらってから初めて接触するようにした。
◆南極地域の利用について定められた南極条約の締結から、昨年で60周年を迎えた。日本を含めた原署名国は12か国だが、今や加盟国は46か国。これは地球上の人口の約80パーセントに相当する。以下、4つの基本原則。「南極の平和利用」「科学調査の自由と国際協力」「領土権・請求権主張の棚上」「核爆発・放射性物質の処理の禁止」。
◆観測隊はこの条約のおかげで自由を享受できている一方で、実行部隊として、条約が南極の現場できちんと守られているかを監視する役目も担っている。澤柿さんは「自由とは、各国が監視しあった中で初めて成立するものです」と、きっぱりと言い切った。
◆観測隊が国際戦略の最前線にいることを象徴するような出来事があった。63次隊を乗せたしらせが氷を割って作った航跡を使い、なんと中国の船が入ってきたのだ。中国からは何の連絡もなく、これは明らかに南極条約違反である。彼らは昭和基地の30km先に小屋を建てて帰っていった。
◆澤柿さんには、30年前に一緒に南極で越冬した同い年の中国人研究者、ヤンさんという友人がいる。南極越冬から帰国した後、彼は中国の極地研究所で長らく所長をしていたが、今回の件が起こる直前に退職していた。「おそらくヤンさんは、日本に近すぎるということで更迭されたのではないか。彼が所長だったら、私に連絡しないはずがない」。このように、非常に微妙な国際関係の瀬戸際に置かれているのが昭和基地なのだ。
◆澤柿さんは「査察制度や事前通告制度をちゃんと運用することで南極条約は維持されている。これがなかったらやりたい放題の大地になってしまう」と警鐘を鳴らす。ちなみに外国の観測隊員が昭和基地に査察に来るのは大歓迎だが、実は外国人から見ると、昭和基地は立地的に「行ってみたいけれど、なかなか行けないところ」なのだという。というのも、地図上でインアクセスシブル(到達不能)と表記されていた土地をあてがわれた日本が何とか建ててしまったのが昭和基地だから。へえ〜!
◆領土権が凍結されている南極はどこの国のものでもないのだが、歴史的な経緯や地理的要素などから、自国の領土だと主張する国もある。一方で、日本は完全に南極条約を守り、領土権は主張していない。そういう立場からすると、今後起こるかもしれない各国間での領土権争いの仲介や調整役として、日本の重要性は増していくのではとも考えている。
◆領土権に関しては、帰国前のコロナワクチン接種の際にも一悶着あった。昭和基地は日本の領土ではないので、国が購入し供給しているコロナワクチンは基地内では打てないと言われてしまったのだ。ウイルスのいない南極で過ごすと、帰国後すぐに風邪をひいてしまうくらい免疫力が低下してしまう。何としても帰国前にワクチンを打ちたかった。
◆ここで解決の糸口になったのが、旗国主義という考え方。飛行機や船舶など、移動しているものの中はどこの国かという話だ。観測船しらせは日本船籍なので、船に乗ったらそこは日本!ということで、帰国途中のしらせの上で、ようやくワクチンを打つことができた。
◆越冬生活を振り返ると、隊長として隊員たちに様々な苦労をさせたと思う。夜も寝ないような重労働を課さなければならないことや、悩みに答えられなかったこともあった。だからミッドウィンター祭でサプライズプレゼントされた盾に、自らの座右の名「開拓者は矢を受け〜されど開拓者たれ」が刻んであったのを見たときは、隊長として合格点をもらえたようで心から嬉しかった。さらに厳しい越冬後半戦も無事に乗り越えた63次隊は、帰国後に作成した記念アルバムのタイトルを「開拓者」とした。澤柿さんの南極にかける情熱が隊員たちに伝わった証だ。
◆ペンギンの群れの中で最初に海に飛びこむ1羽を「ファーストペンギン」と呼ぶ。南極の開拓者を言い表した「ファーストペンギンたれ」という澤柿さんからのメッセージは、これから南極観測に参加する人や南極に憧れる人たちの心を鼓舞し続けることだろう。
◆澤柿さんのお話を聞く中で、南極が持つ様々なギャップがたまらなく面白かった。生命を脅かすほどの厳しい寒さを恐ろしく感じる一方で、美しい自然と生き物たちの営みに心がときめく。また、国際的、科学的に最前線の現場でありながら、そこで生活するためには泥臭く地味な労働もすべて自分たちでやらなければならないという圧倒的事実。そのような環境をメンバーが協力して乗り越えていくことが、越冬隊の大変さであり、醍醐味の1つでもあるのだろう。
◆報告会終了後の会話の中で、澤柿さんは「越冬隊には、研究に打ち込み、情熱を語れるような人が必要」と話された。誰かの熱意に自然と周囲が巻き込まれていくことで、自発的に協力し合えるチームを、南極生活30年の中で見てこられたのだろう(これってまさに地平線的?)。そして澤柿さん自身もきっと、熱く語り、率先して動き、南極越冬生活を楽しむ姿を見せてくれた越冬隊長だったに違いない。これからもずっと開拓者であり続けて欲しい。南極の涼しい風を感じようと思って参加した報告会だったが、澤柿さんが届けてくれた南極の風は激アツだった![新垣亜美]
■準備期間を含めて足かけ3年余にわたって従事していた南極観測隊のほとんどの期間はコロナ禍中で、500日あまりにわたって地の果てに隔絶されていた南極滞在中は当然として、国内準備期間でも、在宅リモートワークか観測準備室に隔離され、社交がまったく停滞してしまった日々だった。この間、地平線報告会も対面での開催はずっと中断していたので、帰国直後の4月に再開された報告会は私にとっても地平線諸氏にとっても、長いトンネルを抜けたあとの久しぶりの再会であった。実際、地平線諸氏との久しぶりの対面は“南極に行っていたから”という意味でのブランク感はまったくなかったし、皆さんから「太りましたね」という反応をいただいたことも、恥ずかしさ以上に親しみと労いが感じられて非常に嬉しかった。
◆越冬隊長職は3月末で解かれたものの、この7月で帰国して4か月が過ぎたというのに、報告書のとりまとめをはじめとして、お世話になった各所への挨拶回りや報告会でのプレゼンなどの残務が、いまだに絶え間なく続いている。これもほぼ無給のボランティア。所属する学会の活動や大学の校務や講義も帰国翌日から始まったため、一年半のブランクを埋めるリハビリをする余裕はまったくなく、南極と大学の二足のわらじをはいた状態のままで否応なしの娑婆への順応を強いられることとなった。
◆そんな最中に江本さんから7月の報告者としての依頼がやってきた。南極残務と学務が山積みで、正直なところ地平線での報告の準備が間に合うかどうかまったくの挑戦ではあったのだけれど、隊長としての立場で通り一遍の「きれいな成果報告」を繰り返している日常に飽き始めていたというのと、これまでにゼミ生を連れて報告会に参加させてもらってきたことへのお礼をどこかでしなければと常々考えていたこと、そして、これまでの報告者に比べれば地平線らしいことはなにもできていない自分のバックグラウンドを知ってもらうための機会にもできるのではないかという期待もあって、躊躇することなく引き受けることにした。
◆報告会開催アナウンスにむけた事前インタビューで長野亮之介さんと話しているうちに、長野さんの巧みな話の聞き出し術につられてあれこれしゃべっていたらあっという間に2時間が過ぎていた。そうか! 今しゃべったこれをそのまま話せば地平線らしい私の報告になるんじゃないか、と気づかされた。あとは一気に材料をあつめて流れを調整して……といい気になって作業していたら、肝心の校務資料の作成や授業準備のほうが間に合わなくなって右往左往したり、と、なかなかスリリングな直前数日間となってしまった。
◆こうしてあたふたと準備した内容を報告会当日に見直していたら、とても時間内には収まりそうにない分量に膨れていたことにハタと気づき、出だしから1.5倍速の弾丸トークになってしまった。聴衆の皆さんには大変申し訳ないことをしてしまったと反省している。地平線報告会がくだけた場所だというつもりはけっしてないのだけれど、地平線でなければ話しても意味のない(くみ取ってもらえない)話というのはやっぱりあって、今回はその部分をおもいっきり放出させてもらえてすっきりできた。二次会・三次会での四方山裏話の部でも、(他の講演会や報告会には期待すべくもない)地平線ならではのツボを押さえた感受性豊かな交流ができて、あらためて自分の居場所を再確認した次第。猛暑の中足を運んでいただいた皆様に心より感謝いたします。[澤柿教伸]
■澤柿さんの報告会の中で突然「国際山岳年」のポスターと「山の日」についての私の論考の表紙がうつし出された。2002年は(日韓W杯開催の陰で目立たなかったが)「国際山岳年」であった。「We are all mountain people(我ら皆山の民)」というスローガンのもとに各国で山岳をテーマに委員会ができ、日本でも国際山岳年日本委員会が組織された。田部井淳子さんを委員長に、江本が事務局長となって「山岳」をテーマに各地でさまざまな催しが実行された。
◆その中で私は「この機会に日本に山の日を」と訴えた。朝日新聞のコラムに「日本に山の日を」(2002年5月13日付け『私の視点』)と書かせてもらい、7月には静岡県富士宮市での「富士エコフォーラム」で小学生たちに「日本に山の日を」と読み上げてもらった。当時、すぐには具体的な動きとはならなかったが、やがて政治家たちが動き出し、2011年の3.11東日本大震災後、具体化した。
◆2014年5月23日、毎年8月11日を祝日「山の日」とする祝日法改正案が賛成多数で可決した。澤柿さんがスクリーンで見せたのは当時私が日本山岳文化学会の会報に書いた「祝日としての「山の日」は何を意味するのか。山の世界は2年後の実施に向けて何をするのか」という長いタイトルの論考の表紙である。ことし8月11日の「山の日」は沖縄を主会場に実行される。「山の日」について考えていることは、別の機会に。[江本嘉伸]
■私はこれまで、「大学教授」としての澤柿先生しか知りませんでした。特に文系学生である私からすると、専門的な用語を使い世界中を飛び回って研究している先生は、まるで別世界の人のように見えていました。しかし、今回の報告会では、私の知らない先生の姿がたくさん詰め込まれていました。浄土真宗のお寺の長男として生まれ、高校生で南極に憧れを抱きながらも、大学では勉強より登山に熱中……。遠い存在だと思っていた先生が、私と同じように子どもだった時期も、新しい出会いに感動した瞬間もあったことに気づかされました。報告会が終わったときは、失礼ながら「先生も私と同じ人間だったんだ」と思い、すこし嬉しくなってしまいました。
◆大学1年生のころに受講していた授業で、澤柿先生は「情熱をもって夢を育ててほしい」というお話をしてくれたことがあります。いろいろな出会いから生まれた目標に向かって、一所懸命やることが大切だと、私たちに伝えてくれました。このときのお話を思い出し、ひたむきに努力を積み重ねてきたからこそ、今の澤柿先生があるのかなと思いました。
◆私は、社会学部の学生で、澤柿先生が専門としている内容はなかなか理解ができません。しかし、先生はいつも「どうしたら文系の学生にも伝わるか」「社会で生き抜く人間に育てられるか」を考えて講義をしてくれています。私たち学生は、それをしっかり受け止め、学びを深めていくことで応えられるはずです。まずは出会いを大切に、そしてたくさん学び、澤柿先生のように世界で活躍する人になりたいと思います。
◆地平線報告会を聞くのは4度目となり、さらに今回は初めて2次会にも参加させていただきました。人生の先輩方からお話を聞くひとときは、私にとって新鮮で、面白くて、勉強になることがたくさんあります。自分の世界がどんどん広がり、まるで冒険をしているような気持ちです。この経験を自分の力に変え、自ら冒険に出かけられる強さを身につけていきたいと思います。これからの地平線会議でどんな発見ができるのか楽しみです。[澤柿ゼミ3年 杉田友華]
■いつか参加したいと思っていた地平線報告会に今年からようやく参加することができた。4月の報告会、前席の方のジャケットには「JARE」のロゴとよくみると「SAWAGAKI」の刺繍が……。声をかけると案の定、部活と大学院の大先輩である澤柿さんであった。直接お会いするのは初めてであったが落ち着いたしゃべりぶりからはなんとなく懐の深さとルーム(山岳部の自称)を出た人間の波長を感じられた。3回目の今月はその澤柿さんの報告であった。
◆多摩ニュータウンで家と団地に囲まれて育った自分はただ広大な大地にあこがれて北大に、山岳部に入った。山岳部では夏、冬、春の長期休暇を利用して1〜2週間程度のメイン山行を行う。夏は沢靴、冬は骨董品化しつつある旧式ジルブレッタスキーを履き、沢から沢、山から山を繋ぎながら繰り広げる水平的、旅行的な山行にすぐに取りつかれた。休日は山、平日は山行記録や書籍漁り。北大の山岳館はあらゆる登山者、探検家や冒険家の書物の宝庫だ。夜になればストイックにアルコール摂取。1留、大学院進学を経て計7年の札幌生活はあっという間に過ぎ去った。
◆就職して断腸の思いで北海道を離れたところで折よく地平線報告会が再開されるとのニュースが。成し遂げたことよりも彼、彼女らが考えたことや行動原理の方に興味を惹かれており、その声を直接聴ける機会に飛びついた。今回は澤柿さんの南極越冬隊の報告会。「開拓者たれ」のモットーのもとに生きる澤柿さんのトークに引き込まれた。記念品のエピソードは隊長としていかに素晴らしかったかを象徴するものに感じられた。

◆率直な感想を言うと、「うらやましい、自分も行きたい」に尽きる。大学院ではコロナ禍、戦争もあってロシア極東での海外調査は叶わず、後ろ髪をひかれながら就職した。また、北大山岳部式山行に取りつかれた自分にとって南極はまさに水平的旅行の極致というべき場所であった。チャンスがないわけではない。就職先の国土地理院からは夏隊に職員1名が参加し測量業務に従事している。いかにも後追いペンギン的な思考だけど、せっかくファーストペンギンが切り開いた道を利用しない手はあるまい。[竹内祥太 国土地理院研修中]

黒部の主、往年の名クライマー、和田城志さんから爽快な便りが届いた。なんと海から。その後も書いてくださることを前提に不定期連載とし随時掲載します。(E)
■すでに何度か書いてきたことである。私が山から海に転進したのは、ハロルド・W・ティルマンの影響である。彼の伝記『高い山はるかな海』を読んで、いっぺんに魅せられてしまった。私がもっとも崇拝する探検登山家であり、海洋冒険家である。冒険家と言わずに海洋探検家と言いたいところだが、すでに探検すべき未知な海域はなく、彼は高緯度海域、グリーンランドやパタゴニアの海に活路を見出した。戦前のナンダ・デビィ初登頂を皮切りに、ヒマラヤ、カラコルムの未踏査山域を広範囲に探検登山した彼は、エヴェレスト初登頂の前年に、ヒマラヤが騒がしくなったと山から海に転進した。その歴史的偉人の真似をしようかと考えた。もとより、そのスケール、内容、アイデアは比べるべくもなく、ティルマンを真似るなど笑いぐさだ。
◆彼が山を去ったのは55歳だった。私が右膝十字靱帯を失い登山の第一線を退いたのは38歳だったが、まだだらだらと山にしがみつき、50歳で本当に山をやめた。さて何をするか。で海に行くことにし、山の知り合いからヨットを購入した。SK31(加藤ボート)、戦後ヨット建造の草分け的存在である渡辺修治設計のクラシックな外洋艇である。彼は東京帝大船舶工学科出身で、戦時中は技術将校として潜水艦に乗務していた。
◆ヨットはちょっと乗っただけですぐに飽きた。海で何をやるか、明確な目標がなかったからだ。やっぱり山に行きたいなあと思った。そのときちょうどネパールに行く機会があった。ランタン・リルン遭難の50回忌法要がランタン谷で行われたからだ。26年ぶりのネパールだった。ヒマラヤの壮大な景観が変わらずそこにあった。激しい登山はできなくても、ヒマラヤに触れることはできる。
◆2015年、ネパール大地震でランタン氷河からレスキューされた。右膝の障害は限界になり人工関節の手術を受けた。もう歩くことが苦痛になった。ヨットは、マリーナの片隅に何もせぬまま10年間打ち捨てられていた。船はボロボロになり、大幅なレストアが必要になった。錆びた鉄の塊のようなエンジンは、漁船メンテの専門家にオーバーホールしてもらった。新品を買うほど金がかかった。自己流でマストを下ろし、ドッグハウスもコックピットも作り変え、セールも新調した。5年以上かかっただろう。乗るより作る方が楽しくなった。出来上がるにつれ、何をやるか何がやれるか、考えるようになった。酒浸りの日々、肥満した体、体力、知力、気力は衰え、痛風、高齢者に突入した私に何ができるのだろう。
◆ティルマンの真似で高緯度海域、カムチャツカ半島やアリューシャン列島を巡るのはどうだろう。素人同然のにわかセーラーに、大それたことができるはずはない。ならば海の旅はどうだろう。鑑真や空海がたどった東シナ海も悪くない。朝鮮通信使の航路、身近で実現可能なのは北前船航路探訪だろう。河村瑞賢が最初に開いた菱垣廻船、樽廻船の航路も面白い。これらは、東北から江戸に物資を運ぶためであり、または大阪から紀州を経て江戸に下り物を運ぶための運搬航路であった。この後に登場する、動く総合商社と言われた北前船西廻り航路につながっていく。これらを巡るのは素敵な海の旅になるだろう。
◆日本海に入ってからは、北前船の寄港地を丁寧にめぐっている。横帆一枚だけの弁財船とエンジン、パソコン補助航海アプリ搭載のヨットを比べることはできない。かつての北前船は冒険的航海といえるが、現在のヨットは単なるマリンレジャーに過ぎない。私の最初で最後の山旅(トレッキング)は2013年のネパール・ヒマラヤ全山域トラバース(GHT)だった。その後の10年は、この北前船航路との出会いのための助走期間だったのだと思うことにしよう。
◆私は土佐の海辺の港町で生まれ育った。いつも水平線を眺めていた。今ヨットから眺める水平線はそれとは違う。ぐるり360度水平線に囲まれる。目印がないから不安になる。私にとって、地平線に郷愁はない。砂漠とか草原とか雪原とか、限りなく続く地平はほとんど見たことがないからだ。共通しているのは、平線の上はすべて空だということ。
◆水平線を破るのは島影である。島は喜びである。海から見る地平線(つまり陸地)は、不安から安心への兆しである。大航海時代以前は、水平線に果てがないかもしれないと恐れていた。地平線にはその恐怖はない。そういう意味で、地平線は夢の広がりを表しているといえる。どちらに向かおうと、必ず終着がある。北前船の船乗りたちは、本物の地平線を見ることはなかった。沿岸航路で多くの寄港地を巡る商船だったから、水平な陸地を見ることはなかった。その代わりに変化にとんだ島並、山並を見てきた。海から見た山、次回はそのことについて語ろう。

■4月下旬のポイントホープ。3月に降った豪雪のため、雪は家々の壁を覆い、場所によっては屋根に届くほど。防寒装備の入った物置の扉も雪の下。物置を開けないことには猟に出られないので、到着するなり雪を掘る。かろうじて扉が開くまで雪を掘り、防寒装備を取り出す。部屋に戻って一息ついたころ、海氷の上から迎えがやってきた。午前中に捕れたクジラの解体をしている最中だそう。
◆スノーマシン(スノーモービル)に乗せてもらい氷の上に向かう。海岸から海氷上のトレイルへと入り、乱氷帯を抜けて行く。氷点下の冷たい空気を顔に感じながら乱氷原を見ていると、今年も帰ってこられたんだ、という実感がじわじわと湧いてくる。それと同時になんともいえない幸福感も湧いてくる。たとえどんなに寒くても、仲間と一緒に氷の上にいると、それだけで幸せな気持ちになれる。
◆やがて乱氷の向こうにクジラと仲間たちの姿が見えてくる。再会の挨拶とハグ。仲間たちの満面の笑顔が嬉しい。引き上げられたクジラはある程度解体が進んでいるものの、大型のクジラゆえ解体作業はまだ中途。簡単な食事の後、作業に加わる。合間合間に人々に「おかえり!」と声をかけられ、握手をしたりハグをしたり。クジラに取り付いての作業は、全身、血まみれ脂まみれになる。新品の手袋もあっという間にベトベトに。数時間の作業ののち、大量の肉を町まで運び、我々の取り分の解体は終了。汚れた上着類はその辺に脱ぎ捨てて、おそらく手や顔にも血や脂がついているだろうが、そのままベッドに潜り込む。
◆そうやって始まった今年のポイントホープ滞在。その後もクジラ猟は続き、若い新人キャプテンや60歳を過ぎたキャプテンが初めてのクジラを捕るなど、合計9頭のクジラが上がった。今期は何かと話題性の高い猟期だったためか、地元新聞の取材が入っていた。どうしたことか自分がその記者に見つかってしまい、自分自身について取材を受けたのは猟期の終わりごろ。9頭もクジラが捕れているので6月に行われるクジラ祭りも賑やかなものになる、はずだった。
◆クジラ祭りの始まる数日前、アラスカ北極海沿岸に沿って張られた海底光ファイバーケーブルが巨大な流氷に引っ掛けられ切断されてしまった。この海底ケーブルはアラスカ北極海沿岸の町を繋いでいて、携帯電話回線とインターネット回線を担う重要なもの。それが切れてしまったため、携帯電話はほぼ不通となり、インターネットも不通に。しばらくは通信衛星を用いたネット回線を契約している人だけがインターネットを使えるという状態だった。
◆携帯電話があれば、数時間後の詳細な天候を即座に確認できるが、今確認できるのはテレビやラジオの大雑把な天気予報のみ。クジラ祭りは3日間にわたって行われる。そして早朝に数時間後の風向きを予想して来場者のために風除けを作る。しかし雲を見て今後の風向きを予想できる人はおらず、祭りが始まったときには風向きが逆になっている日もあった。
◆クジラ祭り3日目、男性たちは風除けの前に座り、女性たちの作った料理を一日中食べ続ける。携帯電話を覗き込む人はなく、電話も鳴らず。お年寄りの話に耳を傾け、猟の話をし、思い出話をし。携帯電話普及以前の時代に戻ったような、懐かしい雰囲気のクジラ祭りだった(その後2週間程度で携帯電話、ネット回線は復旧)。
◆近年、クジラ猟は海氷の動き始める5月上旬頃に終わる。そして早い年では5月中には海から氷が無くなってしまうこともある。今年は6月に入っても氷はまったく動かず、クラックも水面もできず。次第に薄くなってきている氷は危険で、氷上にも出られず、アゴヒゲアザラシ猟はなかなか始められない(この間、アラスカ大学の研究者の方の手伝いをするなど、それなりにやることは多く、忙しいと言えば忙しかった)。
◆6月中旬、ようやく氷が動き始め、ボートを使ったアゴヒゲアザラシ猟に出ることができた。しかし、一旦動き出した氷は次第に細かく砕けていき、1週間程度ですっかり視界から消えてしまう。氷が消えると同時にアゴヒゲアザラシ猟は終了。今期は3回程度しか猟に出られなかったものの、短い猟期に9頭捕れている。家族や親戚一同が食べるのには必要充分な量だ。
◆7月。ポイントホープを去る日の朝、前の晩、猟に出かけて行った家主たちが朝一番にカリブーを数頭捕って帰ってきた。町を出る飛行機は昼過ぎの便。時間はあるので朝飯も食わずにカリブーの解体を手伝う。久しくカリブー猟には出ていないものの、解体だけはほぼ毎年手伝っていたので特に悩むこともなく11時過ぎに解体は終了。
◆やり残していた用事を済ませ、軽く昼食を食べ、空港まで送ってもらい、あちこちにカリブーの血や毛のついたままの格好で、別れの感傷に浸る間もなく飛行機に乗り込みポイントホープを去った。最後の最後まで、慌ただしくも楽しくもあった今年のポイントホープ滞在だった。[高沢進吾]

イラスト:ねこ
■7月30日、千葉県から鷹匠志願の女子高生が来て翌31日、1日と早速飯豊山に登りに行きました。彼女は登山経験はないが強くて、少し重い物は背負って平気でした。山頂の少し下に山小屋があるのですが、なんとそこにオゴジョがやってきました。それが人懐こく、高校生のまわりをちょこちょこ歩き回り最後には彼女の山靴の上まで這い登ってきたんです。もちろん初めての体験でびっくり、喜んでいました。テントで2晩過ごしていったん下山。8月末までいるというので今から朝日連峰や鳥海山に連れて行くつもりです。楽しみな夏になりました。[鷹匠 松原英俊 山形]
■月山に登ってきました。大阪から実千代とねこさんも一緒です。空港で飯野さんとサトちゃんの出迎えを受けてエキスパートの先導で登山は万全の体制です。豪雨の中を無事頂上小屋に到着。美味しい山菜料理を満喫です。山小屋とはいえ個室なので、快適に眠れます。翌朝3時半に起きてご来光を拝み、月山神社にお参りをして胎内巡りで心身ともに清められました。下山後は温泉と美味しい山形の蕎麦を味わい大満足です。出羽三山を巡って立派な御朱印をいただき、飯野さんの自宅ではあみりんや落合さんも途中参加して、賑やかな夜を過ごしました。秘湯の肘折温泉にも一泊することができて、本当に充実した4日間の山形滞在となりました。[岸本佳則 大阪]
■初めて韓国を訪れた。釜山で仕事した後、週末を使って江原特別自治道のソラク山(雪岳山)を目指した。韓国は災害級の大雨が毎日続いていたが、麓のソクチョに着いたときには奇跡的に日が差していて、渓谷沿いの遊歩道から登り始める。宿坊を備えた寺院がいくつかあって、それらをつないでいく参道でもある。やはり降ってきた雨の中、ペースが早い大学生4人組を追いかけていくが、途中で1人がバテて休憩していくという。
◆そこから1550mのソチェオン峰まで単独行になった。白い岩峰の尾根をたどる。眺望案内板によれば素晴らしい景色らしいが、ガスで真っ白だ。登山口から5時間、1664mのジュンチェオン小屋に着いた。ソラク山系最高峰のデチョンボン山頂まで距離600m。ピークから戻ってきた登山者が霧の中からぬっと現れる。強い雨風にみんな泣き顔だ。しかたない。ここで撤退。また今度来ようと誓った。[落合大祐]
■「夏だより」というには少し早い6月末のある日の朝、鷹匠の松原さんから電話があり、サクランボをたくさんもらったのでお裾分けしてくださると。月山に行く途中でアナグマが轢かれて死んでいるのを発見。ちょうど道路のど真ん中でどちらの車線の車にも轢かれず、きれいなまま残っていたので、車の流れが切れるのを待って大きなビニール袋に回収。電話をして待ち合わせ場所を決めて、松原さんと合流。2箱もの大量のサクランボと、まるまる太ったアナグマを物々交換しました(鷹の餌用)。大量のサクランボのお礼にふさわしい品になったなぁと、自画自賛です。
★7月号の通信のフロントで気になった部分がありました。あれは、猫がとってきた生き物コレクションを江本さんに見せるために炬燵の上に並べたもので、決してクマタカの餌として出したわけではありません。たまたま足紐を固定しないで部屋に放していたことを忘れていたために起こったハプニングでした。松原さんが餌をやるときはきちんと次の訓練を考えて、計算した量を与えます。食卓でそれをやることはありません。[網谷由美子 山形]
■地平線通信いつもおもしろく読ませていただいています。江本さんをはじめとする蔭のボランティアの方々の大変なご努力のおかげと感謝しております。また、再開された報告会も興味深く、特に澤柿さんの南極の話は聞きたかったなあ。でも、以下の事情により、かないませんでした。
◆夫の元彦が突然倒れた。中村哲さんの展覧会に行く途中の駅だった。隣にエスカレーターがあるのに、わざわざ階段を上った途端にふらついて、ばったり。おまけに壁の看板に頭をぶつけて……立ち上がれず顔をちょっと横にしても吐いてしまう。ありがたいことに駅の方がすぐ飛んできて、救急車を呼んでくださった。
◆脳梗塞だった。住居を探すとき「後ろに鎮守の森があるから、木は切られないね」と確認して購入。しかし自分たちが将来歩行困難になることは全く予想せず、エレベーターの止まらない階とした。
◆正に青天のへきれき! しかし幸いなことに言語も記憶も正常。手も動かせるので、毎日リハビリとパソコンに向かう日々。ただ、登山は永久に不可との医者の宣告。先日は、ひとつ隣の駅から最寄りの駅まで療法士さん二人に付き添われて電車でやってきた。凄い冒険! 今までより遠くへ、より高所へとしか考えていなかった冒険の定義を問い直す発見となった。
◆これまでも「女性初」とか「最年少」「最高齢」など制限付きの冒険があったが、我が事として深く考えていなかった。世界のためでもなく、国家のためでもない個人の視点からの「冒険」を考えなおす出来事であった。また、多くの人の善意と日本の医療政策のありがたさを実感した。建物などは古くても患者に接するときの行き届いた行動。世界に誇れる「ソフト面」と思った。[向後紀代美]
■暑い夏の日となった7月25日。江本さんを迎え、地元福井を巡った。勝山市の平泉寺白山神社。天高く大きな杉の巨木が延々と連なる人けのない静かな参道と苔むす鄙びた境内。同じく勝山市の福井県立恐竜博物館。江本さんたっての要望で訪ねた場所だ。夏休みの親子連れで溢れる館内で、動く恐竜の像や化石に興奮し、少年のようになった(失礼!)江本さんがスマホを向けたくさんの写真を撮っていた。知らなかった、モンゴルのゴビ砂漠で恐竜の化石の発掘現場を見て以来、恐竜に関心が高くなったそうだ。
◆大野市の家々が並ぶ街中の湧水スポット御清水(おしょうず)では、湧水で顔を洗い、二人で冷たい水に足を浸し、夏の暑さを忘れ穏やかな時間を過ごした。行く先々で、私がカメラを向けないような何気ない場所でシャッターを切る江本さんの姿を見た。その江本さんの目を通して地元の魅力を再発見できた一日だった。地元を案内するということは、地元を教わることでもあったのだ。移動中の語らいも含めて心に残る温かい時間だった。[塚本昌晃 福井市]
■7月24日、信毎で表彰式&講演をされたのですね。お見えになることは、事前に同紙で知っておりました。行きたかったのですが(久々にお目にかかりたかったです)、長野の学校の1学期は25日までありまして、お目にかかることができませんでした。 こんな機会、なかなかないので残念でした。
◆報告会が再開されたとのことですので(今月も行きたかった!)日程が合えば、参加したく思っております。信濃毎日新聞紙上の江本さんは大変若々しく見えますが、この猛暑ゆえ、どうぞくれぐれもご自愛くださいませ。[信毎本社の近くに住んでいる 南澤久実 長野市]
■一年で最も賑やかな季節となり、民宿で日々慌ただしく動いています。今春も隣村の小学校で非常勤講師をしつつ子どもたちと向き合っています。が、長期休暇は家業に専念しているため、夏休みに入ってからは毎日のように鮎釣りや渓流釣りのお客様と関わっています。鮎釣り宿の朝は、早朝から鮎のおとりや日釣り券を買い求める人たちがやってきます。おとりを「いけす」からすくいあげる技も、少しは上達したように思います。毎朝、食事作り、片付けをしている間も、玄関から「おとり〜、日釣り券〜」の声が聴こえてきます。気が付けば、お昼前になっていることもしばしば。こんな日常の鮎宿で元気に暮らしています。[酒井富美]
■中学校は夏休みに入りました。最初の2週間くらいは、会議や部活指導、研修等で忙しくしています。理科教員の定番イベント(?)として、「備品整理」というのがあります。今までに購入した3万円以上の物品をすべてチェックします。他の教科でも行いますが、理科はとにかく物が多いんです。今年もやるか、と重い腰を上げ、日頃のいい加減な整理整頓を反省しつつ、理科の先生方の仲を深めつつ、汗だくになってひたすらチェック。
◆面白かったのが、廃棄しなければいけない顕微鏡が平成10年とか20年代購入なのに、昭和60年代がまだまだ使える状態であること。昭和61年生まれの私は少し嬉しくなりましたが、もしかして平成10年頃から壊れやすくしてない?と陰謀論が一瞬浮かびました。先輩教員(歴40年以上のベテラン)に聞くと、鏡筒を上げ下げする部分の仕組みが少し違うようです。新しい物(技術)の方が優れているイメージがあったが、これからは耐久性や修理のしやすさなどに目を向けて開発して欲しいと感じました。もちろん、買う側も意識しなければです。
◆話は変わりますが、3月の江本さんとうめ(日置梓)との横浜歩きの後、地元(島田市と藤枝市)の昭文社の都市地図を買いました。1枚の大きな地図はスマホのスクロールより断然見やすくて面白かったです。道と道のつながりを見つけたり川を下ったり遡ったり。夏休み後半は地元の新発見をしていきたいです。地平線の皆さんと比べるとスケール小さいですが、私なりに楽しみます![杉本郁枝 静岡]
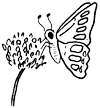
■一度ボツになった話かもしれない。でも新展開があった。コロナ前の話、バス停で可愛い青虫と目が合った。躊躇していると、妻の「連れて行ったら」の一言で買い物に連れて行き、育てることになった。初秋9月10日だった。二晩柑橘系の葉を驚くほど食してサナギになってしまった。年内の羽化が可能とふんだが、年を越してもサナギは微動だにしない。不安と諦めの交差する中、翌年5月に羽化した。なんともハンサムなアオスジアゲハ。でもかれの寿命は短い、「アオ」と命名したが直ちにバス停の前の柑橘系樹木に返しに行った。今は外出困難の妻が虫かごをだいて、団地の管理人に「ねえ、ハンサムでしょう」とアオを自慢していたのが思いだされる。木に放したら藪のなかに落ちていった。アオのその後について心配でたまらない数年が続いた。ところが、1週間前バス停の柑橘系の木にアオそっくりの美しいアオスジアゲハが舞っていた。見とれてしまい、写真を撮る暇もなかった。すぐにアオスジアゲハは飛び去ったが、アオの子孫に違いないと確信し、なにかほっとした。[花田麿公]
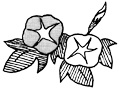
■遅蒔きながらコロナにやられ、寝込んでしまいました。熱は3日ほどで下がりましたが、いまも味覚・嗅覚障害やブレイン・フォグが続いています。頭はまったく働かず、こんな原稿でさえ四苦八苦。体もフラフラ。手に少し力を込めただけで動悸は激しく、ドッと汗が出たかと思うと、一転、ゾクゾクします。コロナ、手強い! 世間的には「2020東京オリンピック」並に過去のオハナシですが、まだの方、くれぐれも油断されませぬよう。[近所で「超激辛ラーメン完食チャレンジ」やってたら、行って賞金稼ぐのに、の久島弘]
■7月7日から、今回は6週間の予定でアビジャンに来ています。日本は猛暑とのこと。ここアビジャンは1年で一番すごしやすい季節で、今年はとくに涼しく、梅雨の終わりで大雨の日もありますが、雨があがるとさわやかな風が吹き、高原にきているような快適さ。東京の猛暑を聞くたびに、申し訳ない気がしています。
◆本題。世界の海で魚がとれなくなっています。理由は温暖化や気候変動もありますが、獲りすぎは昔も今も課題です。コートジボワール政府は今年初めて、夏の豊漁期に禁漁を実施。漁師への補償はなく、ひたすら辛抱の1か月。7月は魚屋から鮮魚がすっかり姿を消していました。今日8月1日、ようやく零細漁業が解禁され、アビジャンのロコジョロ漁港で華やかに出港式が行われました。目を見張ったのは、民族衣装に身を包んだ長老漁師さんたち。生地もデザインも美しく、派手な帽子も似合っていて、思わず「なんてお洒落なの!」と伝えたら、「着るもので褒められたのは初めてだ」と照れながら、手に持っていた楽器を鳴らし「これは王様に対して吹くもので、あなたたちのために鳴らしたよ」とうれしいお返事。
◆漁師さんたちのカッコよさ、照れる様子は日本と同じだなあと感じ入りました。禁漁の効果はこれから検証されますが、1か月の辛抱が意味あるものであったことを祈りたい夏です。[アビジャンで初めて禁漁の夏 佐藤安紀子]
■とろけそうな極暑の7/18、あてもなくふらりとホンダXR250-BAJAで、富士山方面に出かけた。炎天下の高速を走っているとき、長年の友人・中垣勝弘さんが途中の道志村にお住まいなのを思い出し、4年ぶりに突然寄ってみることにした。中垣さんは昔、都心のデザイン事務所に勤めていたが、完全有機無農薬クレソン栽培を志し東京を脱出。中垣さんとの出会いは、南極点・北極点などにバイクで到達した冒険家・風間深志さんが主催し、私もケーナで音楽特別講師を務めさせていただいている『地球元気村』を通じてである。水田を転用した彼の広大なクレソン畑はいつも青々としている。
◆さて、運よく仕分け場にいらっしゃった中垣さんを訪ねると、いま、ちょうど風間さんが近くにいるので、一緒に行かないかと誘われた。ご夫妻の車に案内してもらって着いたのは、地球元気村山中湖キャンプ場。風間さんは、自身の主催する日本縦断ツーリングイベントの途中、琵琶湖から移動してきたところだそうだ。参加者の荷物満載の大型二輪がずらりと並ぶ。風間さんと直接お会いしたのも4年ぶりである。俳優でありモトクロスライダーでもある息子の晋之介さんもいらっしゃった。晋之介さんは南米で開催時のダカールラリーを完走。壮行会のときには、私もケーナ演奏で応援させていただいた。
◆夜は、晋之介さんの流暢な司会のもと、風間さんの旅にまつわるトークショーが行われた。ゲストは木村東吉さん。元ファッションモデルだがアウトドア界に転向。30年以上前に東京から山中湖に移住したとのこと。現在のおしゃれなアウトドアスタイル普及の草分けの一人。古くて記憶があいまいだが、木村さんが東京在住の時代、お宅に一度お招きいただいたような気がする。風間さんは、明日もライダー達と共に宗谷岬へと旅を続けるそうだ。
◆ふと出かけたバイク散歩で、偶然にも多くの方々とふたたび出会えた一日となった。[ケーナ奏者 長岡竜介]
■7月31日から北海道で下宿生活をはじめました。下宿先はケーナ奏者の長岡竜介さんの奥さん、のりこさんの実家です。「光菅さん、苫小牧に行くんだって? だったらわたしの実家で下宿しない?」と冒険研究所書店でのイベント中にのりこさんから電話があり、あれよあれよと下宿が決まりました。
◆きっかけは地平線通信発送作業後の「北京」。苫小牧でしばらくテント生活を余儀なくされるという話をしたところ、長岡さんがそのことを覚えていてくれたのです。人の縁って不思議ですね。今は苫小牧東港そばの職場で仕事をした後、近くの海でサーフィンをしてから温泉に入り、下宿先に帰る毎日です。出張期間は約1年半。まずは短い北海道の夏を楽しみたいと思います。[光菅修]
■去る7月11日に父が逝去しました。葬儀のため北海道安平町の実家に滞在中、風の便りで光菅修さんが苫小牧に赴任すること、アパートを決めるまでの滞在場所に迷っているらしいことを聞きました。父は元来の世話好きで、困っている人を放っておけない人でした。15年程前にはバイクで北海道へ一人旅に来ていた女性が、夕暮れ時、雨の中転んで道に迷っていたところに遭遇し、我が家へ連れて来て晩御飯を食べさせ、宿泊させてあげたというエピソードもあります。葬儀も終えたばかりで家も片付いていないけれども、きっと父なら迷わずそうするだろうし、これから一人暮らしになる母に僅かな期間でも生活の張合いがあればと思い、私は光菅さんに実家への下宿のお誘いをしました。「なかなかない機会なのでお世話になります」と快諾下さり、さらに一週間後に「熟考を重ねた上で、もし私でよければ、お母さんの見守りも兼ねて長期での下宿も可能でしょうか?」と逆に仰っていただき、母とも相談して、お受けすることにしました。31日に実家で光菅さんをお迎えし、翌8月1日、私は東京に戻りました。かくして地平線のご縁で母と光菅さんとの奇妙な冒険生活が始まりました。[長岡のり子]
■8月2日は友人の私設こども図書館の開館初日だった。午後に出かけると、世界地図を机上に広げ高齢女性が話をしている。貝畑和子さん、倉敷在住のウルトラランナーで世界中をかけている。グリーンランドの話で山崎哲秀さんの名前が出たので、地平線会議を問うと、「江本さん」知ってます。「三輪さん」はランナーでよく知ってます。驚きのひと時だった。[北川文夫 岡山]
■この夏のLAアナハイム球場。僕はエンジェルスのダグアウト真裏の席で固唾を呑んでその光景を待っていた。彼はバッターボックスに真っ直ぐと立ち、涼しい顔で正面を見据え微動だにせずバットを構えている。ピッチャーが渾身の一球を投じた。ここからは瞬きもできないほどの一瞬の出来事。凄まじいフルスウィングで捉えると『カーーーン!』。甲高い音と共に僕はコンマ3秒で立ち上がり球の行方を追う。割れんばかりの大歓声が沸き起こるなか、美しい放物線を描きながらとてつもない速度でスタンドへと吸い込まれていった……。自分も一緒に宇宙まで飛ばされたような感覚。我に返ると彼は悠然とダイヤモンドを一周していた。「僕はこの眼で確かに見た!」これはツチノコではない。いまこの世界に実在するユニコーンの話である。[車谷建太]
■海の日に、沢登りのあとに荻田泰永の冒険研究所のトークイベントへ。「北極圏犬ぞり漂泊撮影行」角幡唯介×竹沢うるま×荻田泰永。話題は、北極、冒険、写真、表現、哲学。三者のはなしを聴きながら、自分はこれまでいったい何をやっていたのだろうっておもった。スケールの大きさと思索の深さと。よく他人とくらべても意味がないという。でも興味のある分野は他人との比較はしたほうがいい。落ちこんで、練り直して、自分の道を模索する。定期的に現実を突きつけられる機会は貴重だ。しょぼい成功を境に、ちっぽけなコミュニティに引きこもり、井の中の蛙や裸の王さまへと墜ちていった山屋や旅人やサイクリストをたくさんみてきたから。[田中幹也]
■林業の道に入って二度目の夏。季節に合わせて作業内容も変わり、夏は草刈りに追われる。登山では事故予防やトラブルに対応できるよう早出早着が基本だが、私の所属する山の現場作業班も朝が早く、暑さに対しても安全第一に動く。
◆7月から朝は2時半に起床して4時半に出勤、現場にもよるが10時には昼休憩となり、13時に終業する。朝の涼しいうちに作業を進め、午後の暑さがピークとなる時間の前に仕事を終える。大好きな山登りと同じように朝を迎え、街もまだ山と同じような静けさを漂わせていて、私は気持ちよく通勤している。この暮らしは自分の身体や心と合っているようで、本当にありがたい。[小口寿子 安曇野]
■91才になりました。2年前、脳梗塞を起こして運転免許証を返上、6月の上高地での撮影会には息子の運転で行ってきました。なんとも無念ながら歩いて一人であちこち行くことができません。先月の地平線通信でツチノコの映画のことを知り、とても見たくなりました。実は、私は10年ほど前、ツチノコらしき生き物を見ているんです。篠ノ井線の松本の手前にある「村井」という駅から美ヶ原方面に行く途中、2メートルほどの草の崖を登っていると目の前に30センチほどのヘビのような生き物を発見しました。形状から見てそれがおそらくツチノコでした。慌てて35ミリのカメラを構えましたが、間に合わず。そんなわけでツチノコの映画は是非見たいです。[山岳写真家 三宅修]
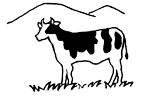
■1年中1日の休みもない忙しい牛飼いの最も忙しい季節。私が北海道に来て43回目の夏。広い牧草地で収穫作業に追われている。15才の夏、高校の三輪主彦先生にそそのかされ、日本中世界中を歩いて旅したいな、なんて夢を描いた。そんな私が43年前、酪農牛飼いに飛び込んだ。自分の無力さ経験不足に汗や涙が流れ続けた。私は悩み続けた。
◆それでも私は一途に牛飼いの道を好きな牛とともに歩き続けている。旅したいところは? 旅したい希望の地は私にはない。毎日毎日春夏秋冬1年中牛飼いしながら辺りの牧草地、山野、牛、野生動物の移り変わるちょっとした気配の変化の中に私は溶け込んでいきたい。
◆季節の中を歩いてゆっくり旅をしているように、43回目の夏。正直いろいろ衰えてきた。もう少しもう少しこの旅を続けていきたい。[田中雄次郎 北海道豊富町豊幌]
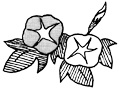
■8月3日に発売の福音館書店『たくさんのふしぎ』9月号「植物をやめた植物たち」の挿絵を担当させていただきました。写真がメインの本ですが、写真では表現できない土中の菌と根を描きました。作者の方と植物学者さんの監修が入るので大変な作画でしたが、土中で菌と植物が栄養を交換していること、光合成をやめキノコなどの菌類から一方的に栄養をもらう植物たちの存在など学びの多い仕事でした。
◆我が家では那須高原で掘り出したカブトムシの幼虫を育てていたこともあり、人が普段見ることのない土中の生き物たちの様子に想いを馳せました。[竹村東代子]
■今年もドタバタしております。5月に胆嚢炎で入院し、6月にはその胆嚢を除去手術いたしました。胆石12個ありました。前々からの足の痛さも悪化し、変形性股関節症で、人工関節にした方がいい、と言われてます。そんな状態なので昔のようなムチャな仕事はせず、自分のペースで。
◆ところで、屋久島の夏、南の島はさぞ暑かろうと思われがちですが、意外とそうでもないです。都会のように36℃とかはいきません。周りは海だし、森は深いし、自然の中での健全な暑さです。しかし熱い夏はやってきます。コロナも完全に収まったわけではないが、「もういいよ」という感じで、抑えられていたものが、爆発するかのようにお客様が増えています。今年は屋久島、世界自然遺産認定30周年ですし。規制も緩和され、特に海外からの方々が非常に目立ってきました。そこで自分もいい加減なハッタリ英語で外国人のガイドもするようになりました。島にいて外の国に出たような感じで、なかなか楽しです。[野々山富雄 屋久島]
■今年も母島に来ています。2018年春にはじめて来て以来、4度目です。船便しかなく、東京から父島まで24時間、さらに2時間で母島です。海と空の青さ、島の緑がどこまでも深く濃く澄み渡る、日本で一番遠い島です。2017年から関わっている東京都の森林関連の仕事の一環で、ここでは外来種駆除がメイン業務です。この5年で、東京都の奥多摩の森はもとより、関東東北の森にも足を伸ばし、ついでにカヌー旅も各地の河川に行けました。母島では属島にカヌーで渡ります。前回ご一報しましたように、山仕事は4月で一旦定年退職したのですが、今回は嘱託職員という名のアルバイトのようなものです。ギンネム(マメ科)、モクマオウ(モクマオウ科)といったアフリカで乾燥地植林の優良樹種が、ここでは極悪な外来種となっています。所変わればです。秋からは、奥多摩の原生林に帰りつつある森に、より深く分け入る予定です。[山田高司]
■私は今、西穂山荘の一室にいて、休息をとっている。外には笠ヶ岳の稜線にもくもくとした雲がかかっているのが見える……と書いていたらガスで何も見えなくなった。午後になって雲が湧きやすくなっている。
◆西穂山荘は穂高連峰の南端に位置する。上高地の登山口から3時間半、岐阜県側の新穂高ロープウェイの西穂高口駅からは1時間半でたどり着くことができる(コースタイムは『山と高原地図』を参照)。しかし今年はイレギュラーで、8月9日まで第2ロープウェイが運休している。その間、登山者は上高地、焼岳、奥穂方面から山荘にやってくる。私は今年の3月〜4月半ばに続き、6月末からまたこの山荘で働かせてもらっている。
◆コロナ禍が明けたことや円安の影響もあり、外国人登山者も多い。見ていて驚くのは装備だ。全員ではないが、日本の登山者と比べると軽装だという印象を受ける。ザックを背負ってない人やランニングシューズでやってくる人、色んな人がいる。タンクトップにショートパンツ、真っ白なスニーカーでやってきた女の子を見たときには驚いた。自分のなかの当然が、他人にとってはそうでないということがたくさんある。
◆夏山といえば雷かもしれない。7月27日の雷はすごかった。14時を過ぎたころ、焼岳、笠ヶ岳の方面から怪しい雲がやってきたと思った矢先、ドドーン!と大きな音がした。その後1時間弱だろうか、山荘からそう遠くないところにどっかんどっかんと雷が落ちていった。その間、山荘内の電気は落とされ、登山者もスタッフもヘッドライトを装着し、避難所のような雰囲気だった。火花が散った部屋もあったと聞く。私はけんちん汁を作ったり、おにぎりを握ったりしながら雲が過ぎるのを待った。山行途中だった登山者の身になるとゾッとする。幸いけが人はなく、次第に青空がのぞくようになった。こういうときに、自分は山にいて丸腰なんだなということを思い知る。他方で、この山荘が自然の厳しさを越えて守られてきたことを想像し、すごいところにいるなあと感じた。
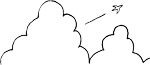
◆とはいえ、小屋の生活にも大分慣れてきた。仕事と生活のリズムがわかってきて、その中で動けるようになってきたという感覚がある。そうして空と山に挟まれた山荘で過ごしていると、山との距離感が近くなった気がしてくる。けれども、たくさんのエネルギー、物資、労力、思考、そういうものがあって私は小屋にいる。山は味方ではないということを踏まえていたいと思う。山で過ごしていることから、自分の山に対する態度が緩んで、登山時の危機感や想像力、準備の不足に繋がらないようにしたい。たくさんの登山者を見ながら、自分自身を見つめ直していきたい。そんなことを思いながら過ごすこのごろである。[安平ゆう]
■志望校も決まり受験に向けハードな毎日を送っている最中だが、離島留学最後の今年の夏は、特に充実していた。期末考査が終わりこれから夏本番というところで、黒潮杯が行われた。黒潮杯とはミニ運動会と球技大会を合わせた学校行事で、2日間に渡って行われる。1日目の競技は学年対抗戦で、台風の目、筏流し、二人三脚、しっぽとり、クイズ大会、ドッジボールを行った。そして、これが神津高校の魅力の一つでもあるのだが、なぜか教職員チームも加わり、大縄跳びとジェスチャーゲームでガチンコ勝負をする。もちろん校長先生も必死に跳ぶ。そこに忖度などは存在しない。2日目は全学年合同の縦割りチームで、今年はフットサルを行った。怪我人続出で一時はどうなるかと思ったが、白熱した試合ばかりでサッカー未経験の私でも楽しむことができた。
◆今年もマリーンデーが実施され、1、2年生はシュノーケリング、3年生はダイビングを行った。その日は天気にもめぐまれ、透き通った海の中ではサンゴや魚を拝むことができた。ボンベをつけて海の中で呼吸をするという体験は私にとって初めてであり、島の友人たちもダイビングは初体験者が多い。神津島にいる間にダイビングを体験することができてよかったと思う。大学に進んだらいつかダイビングのライセンスを取りたいとまで思った。
◆また今年は歴代の中でも群を抜いて寮生の仲がいい。皆で部屋に集まり夜な夜なお菓子パーティーを開いたり、映画を見たりなど、青春らしいことをした。海水浴に、浜辺でのスイカ割り。高校最後の夏を物語る花火。晴れた夜の天体観測。数えきれない思い出で溢れている。同級生とも、毎年恒例赤崎海岸での飛び込みやツーリングにも行った。10メートルの崖からも3回飛んだ。コロナ明けということもあり、今年は特に観光客の人数が多かった。
◆今までは当たり前に皆と行っていた場所だが、行くたびに少しずつ卒業が近づいているのを肌で感じる。9、10、11月は受験勉強が本格的に始まり、3学期は神津にいられる時間も短いため卒業の準備を少しずつ始めなければならない。さまざまな思いの中で過ごした夏は、間違いなく人生で一番輝いた夏だった。神津島にいられる日数を数えると、実質残り半年もない。だが感傷に浸っている暇はない。島での一分一秒を大切にしていこうと思う。[神津高校3年 長岡祥太郎]

《画像をクリックすると拡大表示します》
■茅ヶ崎に住んで丸2年。「慣れた?」と尋ねられる。海の近くという自然環境、新たな交友関係や少し早寝になった生活リズムのおかげで、毎日新鮮な気持ちで暮らしている。まだ旅の途中のような気分でもある。
◆引っ越したとき、陶製の青い火鉢を持ってきた。70年近く前、父と母が結婚したときに購入したもので、これでメダカを飼っている。飛騨と違って水が凍らないから、一年中外に置いておける。とはいえ、メダカの飼育は生まれて初めて。もちろん、どれが雌だか雄だかわからなくて、繁殖についてもまったく知らなかった。
◆1年目は数匹死んでしまったし、産卵もなし。水の中には、一昨年から生き残っている1匹と去年の夏にやってきた5匹の計6匹。6月、お腹の外側にツブツブをくっつけて泳いでいるのを発見! あれが卵か! 6匹のうち5匹がその状態。ということは、オスは1匹! お腹に付いているのはすでに受精している卵とのこと。しかも、何度も産卵。1匹のオス君、がんばったんだね。
◆お腹から水草に移された卵は成魚たちの餌になってしまうことが多く、稚魚となったのは20匹ほどだった。稚魚も成魚が食べてしまうこともあるので、6月末に生まれた、かわいこちゃんたちは別の容器で泳がせている。想像していたより愉しくて、熱心に世話をしている自分が面白い。
◆成魚たちはいつも、6匹で連れだって泳いでいたのだが、数日前から、どう数えても5匹しかいない。ふとした拍子に動かない白い身体になって、1匹が浮かびあがってきた。残念、寿命か。子どものころ、「ごめんね」と謝りながら、金魚、ひよこ、カブトムシ、セミたちを土の中に埋葬したのを思い出した。目の前の動かないメダカはすくい上げる間もなく、再び火鉢の底深く沈んでいって、少し濁った水の中で見えなくなった。水葬ということにしよう。
◆メダカの弔いのあと、実家のお墓のことが頭に浮かんだ。父が早く亡くなり、すでにお墓はある。一人っ子なので私が受け継ぐしかないのだが、私には子どもはいない。引き継ぐ者がいない。お墓はどうしておけばいいのか。時々思い出しては、ぐるぐる考えている。墓石を撤去して、菩提寺の中に設けられたコインロッカーのような納骨堂での家族単位の永代供養を計画しているのだが、墓石がロッカーになるだけ。本当にそれでいいのかな。
◆今年の春、連れ合いの実家が「墓じまい」をした。一族に引き継げる若者がいないわけではないけれど、お墓の管理を負わせないことにしたのだ。何代も前からの遺骨が入っていたので、お寺へのお布施や墓石と土台の撤去はかなり高額だったが、家族としては肩の荷が下りたという感じだった。私が興味を持ったのは、こちらのお寺の永代供養は共同墓地への合葬だったことだ。共同墓地というのは無縁仏の方々が集められた場所のように思い込んでいたけれど、それだけではないのだ。ほかにも、新聞で読んだ最近の調査では、新しく購入されているお墓は後継ぎ不要の樹木葬が5割を超えているとあった。選択肢は様々。今のところ、年に数回のお墓参りは、亡くなった人に逢いに行く大事な時間になっている。もう少し時間はあるはずだから、ゆっくり考えていこう。
◆さらに先のことも時々考える。私の遺骨の引き取り手はいったい誰になるのかしら。連れ合い? 引取り手として一般的なのは三親等まで。一番近い親族は従妹なのだが、これは四親等。今の法律だと、入るお墓が決まっていても、遺骨を引き取る親族(これが大事)がいなければ、無縁仏になって、行政の決めたお墓に入るらしい。海洋散骨をしている自治体もある。いやはや、気になってしまう。
◆亡くなった人たちに想いを馳せる8月、お盆。最近、あいみょんが歌う朝ドラ「らんまん」の主題歌「愛の花」が気に入っている。「命ある日々 静かに誰かを愛した日々 〜 空が晴れたら 逢いに逢いに来て欲しい 涙は枯れないわ 明日へと繋がる輪〜」。大切な人がいなくなる未来なんて来ないで。でもきっと亡くなった人たちは空から逢いに来てくれる。いつか天の上で手を結んで。そんな歌だ。難しく考えなくても、愛する人を想い、空を見上げて祈ればいい、と思えてくる。
◆最後まで書き終えたつもりで、一息。メダカたちの様子を見に行くと、成魚がたった二匹。急に三匹も逝ってしまった。そういえば、餌の食いつきが悪くなっていた。冬の寒さ、この暑さ、受精、産卵、がんばったね。あなたたちのおかげで、いろいろ経験して愉しかった。ありがとう、またね。[中畑朋子]
地平線通信531号は7月10日印刷、発送しました。6月は人手が足りず、苦労しましたが、今回は以下の方々が駆けつけてくれ、ページ数は多かったのですが、早めにやり終えて北京でご苦労さま会をやりました。駆けつけてくれたのは、以下の方々です。ありがとうございました。
車谷建太 中嶋敦子 中畑朋子 高世泉 長岡竜介 秋葉純子 白根全 伊藤里香 坪井伸吾 (以下は北京直行組)江本嘉伸 光菅修
■ここに古い写真がある。若かりしころの母の写真だ。50年以上前のモノクロ写真だが、カメラ好きの父が写したと思われるブロマイドのような作品だ。私が3歳ぐらいのとき、映画の中のオードリー・ヘップバーンを母と見間違えたことがあるくらい母はチャーミングだった(ただし性格は鬼ババア笑)。
◆飲食店内に座る母の背景にぼんやりと写るメニューを見つけ拡大してみると、「富士アイス」の文字が。さっそくGoogle検索すると、現存する店だということがわかった。長野県上田市に1店舗、山梨県甲府市に2店舗、そして「銀座富士アイス本店」なる店舗も甲府市にある。ここまでわかると実際にどの店舗に行ったのかが気になる。写真の母は可憐なアップスタイルの装いなので、もしや新婚旅行ではと当たりをつけ、確かめてみることにした。
◆今年86歳になった母は、妹やヘルパーさんなどの助けを借りながら神戸で一人暮らしをしている。体は丈夫で、時々おてんばなことをして骨折したりコロナに感染したりしながらも、高齢者とは思えない回復力で元気に過ごしている。週に2回はバスや電車を乗り継いで遠くの教会にも通っている。頭の方は大ぼけ小ぼけ状態で、あちこちで面倒をかけているし、詐欺や悪徳業者や悪い男に引っかかったりしているが(めでたいことに本人はどれも気付いていない)、とにかく大事に至らず日々楽しそうだ。
◆そんな母だが、昔の記憶は驚くほど鮮明だ。新婚旅行はどこに?という質問に、微に入り細に入り答えてくれた。一泊目は名古屋の高級ホテル、次は穂高に向かうため行商人も泊まる旅館、その次の日は穂高の滝谷方面の山小屋風の旅館……、という具合だ。滝谷近くを散策したときに聞いた落石の音も覚えているという。
◆山を目指していたとなると、富士アイスは上田市にしても甲府市にしても、こんなおしゃれな恰好では行かないだろうと、新婚旅行説は消滅した。もっと調べてみると、現在ある店はすべて銀座にあった富士アイスからのれん分けされたものだということがわかった。その店は関東大震災後の教文館ビルに入っていた人気のレストランで、ビルが前身のバラックだったころからあった名店だそうだ。
◆デザートだけではなく豪華な洋食も食べられるレストランで、大理石のらせん階段で一階と地階をつなぐたいそうおしゃれな店だったという。それなら納得だ。母は大学卒業後、新橋の日通航空に勤めていたのだ。普段のデートは新橋の地下のおでん屋などだったそうだが、たまにはおしゃれをして銀座のレストランに繰り出すこともあったのだろう。
◆次に、結婚式はどこで?と聞くと、これについては何も覚えていない。「あたしは忘れちゃったけど、ウサギのおとうさんに聞けばわかるよ」と言われた。私は……、ウサギのおとうさんを知らない。それ誰よ、だからウサギのおとうさんだよ、知らないってば、部屋でウサギがぴょんぴょん跳ねてたよ、麦丸もいたよ、あ!江本さん!とようやく話がつながった。
◆昭和44年の結婚式に、江本さんをはじめ東京外語大山岳部のみなさんにもご列席いただいたようだ。そういえば、と父の遺品から手作りの小さな歌集「山のうた」を取り出してみる。結婚に際し山岳部から贈られたものだ。三曲目に「虹芝寮歌」がある。虹芝寮というのは成蹊学園所有の由緒ある現役の山小舎だ。山岳部間の交流があったのだろうか。「山男の歌」「新人哀歌」「かわらぬ恋」などが並び、それぞれのページに山脈や山道具や、時にはへばっている山岳部員の挿絵が描かれていておもしろい。
◆もちろん全ページ歌詞は手書きだ。「雪山賛歌」は、♪外語の山岳部のリーベは山よ 俺たち山男元気で行こう、から始まり十番まである。ダークダックスが歌っていた日本語詞のものとはまったく異なる。外語大の替え歌なのか。いくつもの歌に穂高がよく登場する。挿絵もそうだ。改めて父がつけてくれた千穂子という名前を意識する。
◆最後のページには、F・S・スマイス『山の魂』より抜粋した言葉が載っている。その中からさらに抜粋する。「喘ぐ胸で、次第に衰える力で、人間はいつの日か地上最高の地点を踏むかもしれないが、征服者の精神によってではなく、つつましく感謝に満ちてふむのである」。山だけでなく、父の人生そのものにも重なり心打たれる言葉だ。裏表紙に「昭和44年5月20日 鳥山稔君、美紗子さんの結婚を祝して 東京外国語大学山岳部一同」とある。
◆さて、ここでまた富士アイスが気になってくる。教文館ビルは和光と同じく昭和8年竣工の現存するビルだ。華やかな銀座の街並みの中でもひときわ目を引く建物だったという。富士アイスの面影を少しでも見てみたいと思い、担当部署もわからぬままビルに入居する教文館書店にメールで問い合わせた。丁寧な返信を下さり、エレベーターホールや階段など、当時と変わらない箇所を教えてくださった。
◆さっそく仕事帰りに立ち寄り、趣のある階段から地階をのぞき、ここに富士アイスがあったのか、ほほう、この回転扉を通ってお店に入ったのかなどと感慨深く思った。たくさん写真も撮って満足した帰り際、メールの返信をくださった方に一言ご挨拶をした。当時富士アイスにあった大理石のらせん階段はこちらでした、と教えてくれたのは、さっき私がしみじみ眺めたクラシックな階段ではなく、影も形もしのべない書店内の階段だった。さらにそこに地下はなく、残念ながら私の空想力の限界を感じた。
◆母の古い写真から、思いがけず時空を超えて旅した気持ちになれた。いっとき重なっては離れていく歴史のかけらを垣間見られたことはとても心を動かされる経験だった。物心ついたころから母とはそりが合わず敬遠していたが、健在なうちに古い話を聞いてみるのもいいものだと思えた数日間の出来事だった。[瀧本千穂子]
■「母親との旅」は、北海道展覧会の裏テーマでした。というか自分的にはメイン。地平線会議の仲間の方々がいらしてくださってほんとうに嬉しかったです。ありがとうございました。
◆母親もぼくも帰宅。一年前から創っている新アトリエには仏壇があります。母親の今の在宅ポジション。新アトリエは神棚もある。旧アトリエでは「霊界(黄泉)の方々との対話の壁」と「神棚(いろいろよろず)」と「ちいさな森の御嶽」を、自分勝手に設けてました。それらは日々を生きるための支え。大仰かもしれませんが、アートの日々は「独り宗教みたいなもの」とか想うことがあります。
◆立ち退きと並行して新規アトリエを創りながらの引っ越しだったので一年以上かかってますが、そろそろ最終章です。この長い引っ越しも地平線会議の仲間たちにとてもお世話になっています、感謝恐縮であります。
◆旧アトリエは、当たり前にどんどん物が減る。昼間熱い。冷蔵庫無し。調理はカセットコンロのみ。水風呂は気持ちいい。すっかり何も無くなった家だけれども、それでも「すべてがある」。自分は「やっぱり此処が大好きだ」とこころから想える。30年使い慣れたアトリエ。床が抜けそう、屋根が抜け雨漏りで空が見えた、ボロボロのすてきなサイコーのアトリエ。ありがとうございます。感謝と、なんだか申し訳なさと云うか後ろめたさ……。物件とか土地の売買とは、まったく別の心情。もはや環境そのもの。
◆自分は巻貝。だとしたら、ふにゃらくるくるの「中身だけ」で、いったいどこに引っ越せるものだろうか? ダム工事で立ち退くかたがたの気持ちが、ほんの少しだけわかったような気になってる軽率な自分。そういうところから妄想を更新。[彫刻家 緒方敏明]
■激動のアフガニスタン現代史を駆け抜けた抵抗運動の指導者マスードと、ゲリラ戦の英雄マスードを自分のカメラで捉えたいと17年間にわたり同行取材を続けた私。映画は、マスードとの出会いと別れ。そして新たに生まれた『山の学校の子どもたち』への交流と大きく連なり叙事詩的に物語を紡いでいきます。4年を経て完成にこぎつけた『鉛筆と銃』は9月12日から恵比寿の東京都写真美術館1階ホールで先行公開されます(映画公式サイト https://enpitsutojyuu.com ?最後にイベントトークスケジュールも掲載されています)。
◆長い取材の中で、いつしか友とも思うようになっていたマスード。彼が大国や周辺国の干渉を排し、真の独立国家を創る日まで、追い続けたいと願っていましたが、2001年9月9日、彼はイスラム過激派の自爆テロで非業の死を遂げます。「終生、撮り続けるという夢」は絶たれましたが、彼が国の未来を託し、教育に力を注いだ思いを受け継ぐ形で、私は2004年から彼の故郷パンシールの山間の学校の支援を始めました。
◆出会い、カブール入城、首都撤退、マスードの死、その後に生まれた山の学校の子どもたちとの交流。映画は40年に亘る私の半生を「写真」と「語り」で河邑厚徳監督がドキュメンタリー映画として見事に作り上げました。構成、音楽、ナレーションとどれもが物語を盛り立て、優れたドキュメンタリーに仕上げてくださいました。それを地平線通信の読者の皆さんにぜひ、見て欲しいという強い思いで、この文章を書いています。
◆初公開劇場となる東京都写真美術館では、9月12日から24日まで、月曜の休館日をのぞいて連日、私と監督との舞台挨拶や多彩な顔ぶれのゲストを招いたトークが予定されています。ノンフィクション作家の柳田邦男さん、同じくノンフィクション作家の梯久美子さん、探検家の角幡唯介さん、映画監督・写真家の石川梵さん、元新聞記者でいまは独自の生き方を実践されている稲垣えみ子さん、写真家の大竹英洋さん、熱帯雨林保護団体代表の南研子さん、アナウンサーの山根基世さん、写真評論家の飯沢耕太郎さんなどの方々が登場してくださいます。
◆長倉洋海が写真で何を捉えようとしたのか。マスードと長倉が見た夢は何だったのか。河邑監督の構成力と尾上音楽監督の尽力で、みなさまに見ていただくことができる映画が誕生したと私は思っています。この映画がどのくらい皆さんに感動を与えられるかは定かではありませんが、私がマスードを通して伝えたかったものは間違いなく写し込まれています。「それを見てやろうじゃないか」という方々、会場にお越しください。私は連日、会場に詰めておりますので、正直な反応をお聞かせいただけたら大変、嬉しく思います。[写真家 長倉洋海 2023年7月31日]
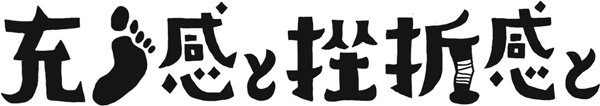
■若いときに、若いから怖いものなしでいけましたという記憶がほとんどない。十代後半から二十代前半にかけて集中的に登攀をやっていた時期があった。数年間で本チャン・ルートを200本ちかく登ったけれど、垂直の世界にはとうとう馴染むことができなかった。
◆本チャン・ルートに向かう前は、どんなに寝ようとつとめてもそのまま夜が明ける。登りはじめてもここならまだ中止して降りられるのではないか。下ばかりみていた。おそらく自分の心と壁とが向き合っていなかった。そうしたなかではじめたころに何度か自分と壁とが調和した登攀がある。恐怖感がほとんどなくスムーズな登攀だった。身体は流れるように動いた。
◆谷川岳一ノ倉沢3ルンゼ。天気は雨、途中から激しい雷をともなったどしゃ降り。フリーソロ。一ノ倉沢出合から国境稜線まで2時間弱。国境稜線に出ると落雷を避ける登山者はツエルトをかぶってハイマツのなかでうずくまっている。無知だったわたしは、ふつうに歩いて下山した。梅雨のまだ明けきらない7月。当時17歳。壁のコンディションは悪かったのに、恐怖心はなく身体はこわばらず。どしゃ降りの雨の3ルンゼのフリーソロは、自分のなかで数少ない会心の登攀だった。
◆このときの登攀を分析すれば自分が何をもとめているのか見えてくるのではないか。登攀がスムーズにいった理由をいくつかあげてみる。その1、十代後半は痩せていて体重が50キロなかった。濡れた岩と濡れた草付きは練習したわけではないけれどまあまあ得意だった。岩登りじたいもともとの身体構造や精神構造に向き不向きがかなりある。その2、雷の怖さを知らなかった。轟音や光に萎縮しなかったのは、落雷に遭えば致命的という認識がなかった。オバケと一緒で怖いとおもうから怖いくらいの解釈だった。その3、本チャンの登攀の経験がほとんどなかった。経験者の判断は的確でミスはすくないけれど、思考は凝り固まる。失敗を経験してひとつ賢くなるとふたつくらい臆病になる。経験者よりも未経験者のほうが、頭のなかで思い描く世界はひろい。経験の拙さは最大の武器。
◆上記3つがうまく噛み合ってスムーズな登攀になった。おそらく100回に1、2回のまぐれ。あとから聞いたはなしで、ダメな人ほどたまたまうまくいったときの状態を自分の実力とかんちがいするらしい。ドキッ、それ俺。真のアスリートはあらゆる悪いコンディションと仲良く付き合い成果を出す。
◆いずれにしても登攀をやりながら「これではない」という違和感がつきまとった。それでもキッパリやめられなかったのは、登攀には中毒性があるのではないか。心がまったく向き合っていないのに冬季登攀、ヨセミテ、欧州アルプス。これだけやればきっとなにかいいことある、と淡い期待。泥沼にハマるギャンブルにも似ている。
◆登攀は空まわりの連続だった。あるていどまでは達したじゃないかといわれる。でも自分が求めていたのは技術を洗練させることでもなければ難度をあげることでもない。もちろんやるからには成果を求めていたのはたしかだ。でも成果よりも心に引っ掛かっていたのは生き方だ。著名な登山家や冒険家が、天に昇った43歳というのがある。植村直己、長谷川恒男、星野道夫、河野兵市ら。あまり知られていないけれど十代後半から二十代にかけて、早死するクライマーがそれなりにいる。
◆並みはずれた集中力。死に急ぐのとはちがう。死が内在するからこそ生はより輝く。彼らが神々しくみえた。高校生のときに植村直己や長谷川恒男の著書に触れたけれどさして印象にない。何度も読み返したのが『二十歳の原点』(高野悦子著)と『十六の墓標 炎と死の青春』(永田洋子著)だった。弱いから死ぬのか強いから死ぬのか。どんなに考えても結論は出ない。いずれにしても自分は若くして果てるという星のもとに生まれなかった。努力によって道がひらけてくることはたくさんある。努力ごときでは太刀打ちできないこともまたたくさんある。
◆十代後半から二十代前半にかけて、手応えのある登攀をさして経験しないまま、わたしの登攀は終った。引退よりも中退がしっくりくる。何もかもが自分の思い描いたとおりにいかなかったけれど、そのおかげで後の水平の旅という展開となった。若いときにうまくいかなかったおかげで、まだつづきがある。
9月の地平線報告会は東京を離れ、神奈川県大和市の冒険研究所書店で行う予定です。詳しいことは次号の通信で。
■この夏を過ぎれば、共同生活家屋「ちえん荘」発足から丸2年になる。ちえん荘の一派は徐々に勢力を拡大し、現在5名が道北にある一軒家を拠点に生活している。それぞれが、無農薬有機野菜作り、家具作り、椅子張り、建築、樵といった仕事を生業とすべく、日々の授業や仕事に向き合っている。
◆私の妻も含め、仲間の半数が、今年で30歳を迎えた。一次産業や職人の世界でその道のプロを目指すには、遅すぎるスタートなのかもしれないが、「ちえん」の看板に偽りのない生き方を実践しているのさ、と笑い飛ばしている。
◆生活に必要なあらゆる物事を市場に頼って、交換と消費をし続ける生き方から距離をとりたい、という意識が私にとってのちえん荘の出発点だった。生きることからかけ離れた賃労働でカネを稼いで、モノを買って消費する一生よりも、生きることや作り出すことに近い仕事をして歳を取っていきたかった。一人ですべてを賄うのは容易ではないけれど、業(わざ)をもった仲間があつまることで、生産と消費の輪っかを、だんだん手元足元に引き寄せたい。「自給自足」とは少し違った、そうした環境を作り上げる、はじまりのアジトが「ちえん荘」なのである。
◆同じ釜の飯を食らいながら、修行先での体験談に花が咲く。森で木を伐る話をすれば、家具や家作りの話につながり、それを加工するためのカンナの話をしたかと思えば、無農薬野菜づくりの苦労に話題は移る。それぞれ、現場や学校で見、聞き、習ったばかりのあれこれを披露しあっては、耳学問の夜が更けていく。分野は違えど話がつながるのは、大きな機械に頼りすぎることなく、なるべく手足肉体を使った仕事に憧れをもつという共通意識が、話の垣根を低くしているからだと感じる。
◆今はまだ、賃労働者としての生活をしているにすぎないけれど、物が生産され流通する過程やその業界の表裏について、家族のような同輩から話を聞ける毎日は面白い。そして、仕事をするのにも、本当にいろいろなモノが必要で、それらの多くは世界的な市場によって支えられているという当たり前の事実も再認識させられる。将来的にそれをどこまで制限したいのか、そしてそれは意味のあることなのか、考えながら日々を過ごしている。
◆農業にしても、林業にしても、製造業にしても建築業にしても、「ちえん荘」が革命家集団でもない限り、その産業構造自体を変えることなど到底できない。しかし、「ちえんグループ」が独特な「仕事の輪」を形成することができたなら、本流に対して砂粒程度の一石を投じることはできるかもしれないと思っている。こう大きなことを書いてはみたものの、実際の生活は穏やかな日々の積み重ねで、革命だの世直しだのそういったことを本気で志向している集団ではないことをここで断っておきたい。
◆地球の反対側の労働力と世界的な輸送網に頼る割合を減らして、自分たちの手と足元の大地で慎ましく生きていこうとすること。そのことが、草の根から世界に向き合う一歩なのだと信じて、我々はよちよち歩いている。地平線通信の紙面上で江本さんから投げかけられた「世界とどう向き合っていけばよいのか」という問いは、今でも私の胸に抱えた課題だけれども、自分なりの答えは、もう出ているのかもしれない。[五十嵐宥樹 北海道東神楽町]
■先月の通信でお知らせして以降、通信費を払ってくださった方は以下の方々です。カンパとしていつもより多めに支払い、あるいは送金してくださった方もいます。貴重なカンパは未来を担う若者たちの購読支援に役立たせており、地平線会議の志を理解くださった方々からの心としてありがたくお受けしています。万一、掲載もれありましたら必ず江本宛て連絡ください(最終ページにアドレスあり)。送付の際、できれば、最近の通信への感想などひとことお寄せくださると嬉しいです。
久保田賢次(10000円 通信費5年分を宜しくお願い致します。とても充実した内容の通信を毎月読ませて頂けること、とてもありがたく感じています。最近は荒廃が進む登山道のために、何かできないかと活動しています) 澤柿教伸(注・5月の報告会で) 波多美稚子 10000円(5年分お願いします) 高橋千鶴子 古山里美・隆行(6月中旬と7月下旬と、2度新型コロナに感染です。後遺症がしばらく続き、行動が縮小……。マスク・うがいでは防ぎきれないと実感です) 豊田和司(3000円 通信費+カンパです。長い間拙詩を御掲載いただき誠にありがとうございました。今後は俳人目指してがんばります) 内山邦昭(10000円 82才の高齢者ですが、地平線通信を読むとこの日本にこれほどまでにチャレンジングで冒険心に富んだ人たちがまだいる事を知るだけで元気がでます。これからも楽しんで拝読させていただきます)
■『日本人とエベレスト 植村直己から栗城史多まで』が「第12回梅棹忠夫山と探検文学賞」に選ばれた。本書は、地平線通信編集長の江本嘉伸さん、神長幹雄さん、谷山宏典さん、柏澄子さんと私、そしてインタビュー記事を書いた山本修二さんによる共著。企画を立ち上げたのは、神長さん。きっかけは、エベレスト日本人初登頂から50年が過ぎた2020年に、日本山岳会が開いたエベレストの写真展だったという。そこには、連綿とつながる日本人とエベレストの関係が、心に訴えかけるようなビジュアルで展開していた。神長さんは、それを文字でも表現したいと考えた。
◆江本さんは3章分の執筆を行っている。授賞式の記念講演で、江本さんは1975年の日本女子隊のとき、報道隊員として同行取材をしたときのエピソードを話した。キャンプ2が大雪崩に襲われたとき、江本さんも現場のテントの中にいたが、奇跡的にテントが大破しただけで生還できたという。その隊は、隊員と報道隊員を合わせ22人の大所帯。そこにシェルパやポーターも加わっていた。70年代、80年代、エベレストはそんな大登山隊に登られていた。「個」ではなく「集団」の時代。しかし、そのひとりひとりが、熱いエネルギーを持っていた。まるで、誰もが熱く生き、国を作りあげていた昭和の日本を反映するかのように。
◆その後、バブルのときには、莫大な費用がかけられ、交差縦走と山頂からの生中継が行われている。最後の大遠征となったのは、バブルの余韻が残る1995年。日大隊による北東稜の登攀だった。その後、大登攀はなくなり、野口健さんらによる清掃登山が始まった。私は1998年、「清掃班」班員として、野口健エベレスト登山隊に参加していた。18歳のときだった。その後の2000年代前半、4度行われた野口さんの大規模清掃登山には参加していない。しかし、本人にリアルタイムでそのときのことを聞いて、その話をまだ鮮明に覚えている。だから「清掃登山と発信力」という章を神長さんから依頼されたときも、書き上げられる自信はあった。
◆当時、野口さんのエベレスト清掃活動は、たびたびテレビで取り上げられた。それは彼自身の発信力もあったが、それ以上に時代が「環境意識」や「サステナブル」という言葉に敏感になっていたことが大きい。バブル崩壊から10年が経ち、ミレニアムが過ぎても、経済は一向に回復の兆しは見えなかった。そんな中、成長ではなく今ある環境をどうやって維持していくかに意識が向けられるようになっていた。ある意味、その象徴としてエベレスト清掃がとり扱われている部分もあった。
◆時代の気運に後押しされ野口さんが清掃を行っている間、エベレストだけでなくヒマラヤ全体で、日本人による大遠征はほとんど行われていなかった。それは道具の進化により「ライト&ファスト」と呼ばれるような、少人数の短期速攻の登攀が登山界の主流になったからだけではない。未踏の大岩壁や長大な尾根が少なくなり、あったとしてもそれに挑戦する経済力のある組織が少なくなったという要素も大きい。
◆授賞式で山と溪谷社の萩原浩司さんは、「未登の空白部がなくなった今、個人のテーマがより重要になってくるであろう」ということを話した。江本さんも、「『初』の冠が付く時代は終わった。それよりも個人の満足感や、各々の冒険に対する考え方が問われる時代になった。冒険には『その人の生き方』が問われている」と語った。
◆今の時代の登山は、社会や他者とは共有することができない、個別のテーマが求められているのだろう。それは以前のように、社会や組織が提示してくれることはもうない。しかし、そのことは「地平線会議」では、とっくの昔から言われてきたことなのかもしれない。江本さんが言っていたこんな言葉を思いだす。「文章でも旅でも、固有のテーマをきめたら、それに向かって全力で行わなくてはいけない。他人の目を気にして躊躇してはいけない。そして、それを自分の名前を出して発表するべきだと思う。そのとき、世間や業界がどう思うかなんて関係ない」
◆記念講演の壇上で、私は江本さんの隣にいた。本の一部を書いただけで、受賞者とさせていただいた私は幸運でしかなかった。だがせっかくこのような機会を与えられたのだ。これから先も書き続けていきたい。私は『太陽のかけら アルパインクライマー谷口けいの軌跡』を以前執筆し、そこに書いたが、パンドラというヒマラヤの峰を登りたいと思っている。そして、それを自分の固有の物語として書きあげてみたい。そう強く、壇上で思っていた。[大石明弘]
■エベレストに初登頂したエドモンド・ヒラリーさんと最後にお目にかかったのは、2003年3月19日、海の見える高台にあるオークランドのご自宅でだ。日本で何回かお会いしていたジューン夫人とも気さくに話ができた。ヒラリーは、1975年、最愛の妻、ルイーズと末娘のベリンダをエベレストの麓、クーンブ地方での飛行機事故で亡くしている。ジューンさんはマカルー、南極とヒラリーと行動をともにした親友のマルグリューの妻だった。しかし、彼は1979年南極遊覧飛行のガイド中、墜死、1989年になって、2人は再婚した。「私たちは4人の友達でした。2人が亡くなり、残された2人が一緒になったのです」。爽やかにジューンさんが話したのが忘れられない。[E]
■東京から届いた「ちへいせん・あしびなー 『地平線会議 in 浜比嘉島』の記録」。2008年、私がまだ浜比嘉に移住する前にこのような大イベントが開催されたことを羨ましく思いながら、しかしそれ以上にワクワクしながら、この記録を拝読しました。誌面からは、世界を舞台に旅や冒険、民族調査や科学研究と活躍する行動者たちの熱い報告と、熱心に聞き入る聴衆の興奮がいきいきと伝わってきます。
◆1億5000万年前の恐竜のうんこの化石、中米ニカラグアの紙幣、南極で釣った巨大魚の魚拓、インドで紡ぎ織られた木綿、鷹匠の身を守るシェパードの毛皮、カーニバル報道用コスチューム、マッコウクジラの牙、そしてそれらを持ち帰った人々が現地で見て感じてきたことを伝える生の声。私も一緒に会場にいるような気分で読みました。が、実際にその場で報告者の声を聞きながら実物を見られたらどんなに楽しかっただろうかと思わずにいられません。
◆どれも浜比嘉島からは遠い世界の珍しい話ではありますが、自然とともに生き、身の回りのものの多くを自分たちの手で作り出して生活してきた浜比嘉の人たちにとっては共感する部分も多かったのではないかと思います。
◆そして比嘉小学校の子どもたちが撮った素晴らしい写真の数々! 「私たちの宝物」というタイトルどおり、子どもたちが写真を通して見せてくれる島の風景は、浜比嘉の自然に包まれた豊かな生活を切り取ったものばかりで、心が洗われるようです。デジカメ教室を企画し写真展開催まで尽力した丸山純さんや、関係者の皆さんのご苦労はいかほどだったかと思いますが、写真展で誇らしげに作品の解説をする子どもたちの顔や寄せられた感想の数々から大成功だったことがわかります。なにより、カメラマンとして島を走り回り、生まれ島を見つめ直したことは、浜比嘉の子どもたちにとって大きな財産になったのではないでしょうか。
◆記録を読みながら、私は大学時代に初めて外の世界に触れたときの興奮を思い出していました。沖縄県南部にある南風原文化センターという小さな会場で開かれた「アジア・沖縄 手織りの技法」という展示会で、会場にずらりと並べられたアジア各地の織物、そして現地で活動する人たちが語るその土地独自の織物文化に心を躍らせたことをよく覚えています(「ちへいせん・あしびなー」に登場した江上幹幸さんも登壇されていました)。
◆その中で特に興味を惹いたのは、インドネシア・バリ島のトゥガナン村で織られているグリンシンという絣でした。絣は「かすり」と読みます。絣とは糸を括って防染し、括った部分が模様になってあらわれる織物の技法で世界各地で織られていますが、グリンシンはバリ島で採取した植物を使い何十年もかけて染められた絣糸がとても魅力的でした。当時私は沖縄県立芸術大学で沖縄の絣を学んでおり、大学のバリ・ガムラン(インドネシア・バリ島の打楽器アンサンブル)のサークルに所属していたこともあり、どうしてもバリ島に行って、じかにバリ島の織物や芸能に触れてみたいと思ったのが、私の初めての海外旅行です。
◆バリ島ではバリ舞踊の先生の家に泊まって音楽や踊りを学びながら、バイクで島内の織物を見てまわりました。トゥガナン村では、村でグリンシンの調査をしている榊原茂美さんに案内していただき、織り手さんから直接お話を聞くという貴重な経験もしました。初めて聞く言葉、初めて見るもの。好奇心を刺激するその土地独自の文化。そしてその中に織物という共通の営みを見つけたときの共感と喜び。世界は広いが、自分が住む土地も世界と繋がっているのだと気づいたときの、言葉に言い表せないような感動は忘れられません。
◆自分の暮らす狭い土地から世界に視野が広がることは、同時に今まで見過ごしていた自分の足元にも目が向くことでもありました。旅を通してインドネシアの織物に惹かれると同時に、沖縄の織物の面白さ、美しさにも改めて気付かされました。沖縄独自の自然や文化を感じながら織物を続けたいと思い、9年前に浜比嘉島に移住したのも、あのころの経験が大きく影響している気がします。
◆きっと浜比嘉島の子どもたちにとって、「ちへいせん・あしびなー」で地平線の行動者たちの胸踊る報告に触れ、デジカメ教室を通して島の宝物を再発見したことは、世界に目を向け地元のよさを知るかけがえのない経験になったことと思います。そしてこのような場を設けた地平線メンバーの行動力は本当にすごい。浜比嘉島民としては、癖の強い島んちゅと地平線メンバーの間に入って調整役を担ったであろう外間晴美さんのエネルギーに脱帽です。
◆さて、江本さんはこの記録を「ちへいせん・あしびなー」を知らない若い世代に配るとのこと。読んだ後、浜比嘉島に興味を持ったら、ぜひ一度遊びに来てください。私もまだまだ島のことを勉強している最中ですが、見て欲しい場所やモノがたくさんあります。これを書いている現在島は台風6号の影響で大荒れですが、塩害や暴風でやられた植物もすぐに復活すると思います。先日、島の大きな相思樹の木が伐採されたので樹皮を剥いで糸を染めてみましたが、あまりに美しい色に興奮してしまい近所の人に自慢して回ったので笑われてしまいました。台風にも耐える沖縄の樹木の強さの秘密は樹皮に含まれるタンニンで、このタンニンが素晴らしい色を生み出すそうです。小さな島ですが、自然も文化も奥が深くて面白いですよ。[浜比嘉島 渡辺智子]
■「信頼できない大人ばかり見てきたけれど、こんなに信頼できる大人がいたんですね」。アフガニスタンで殉職した中村哲医師を描いた映画『荒野に希望の灯をともす』を観たある女子高生の感想だ。愚直に人の命を救い、平和を訴え続けてきた中村さんのぶれない生き方は、私たちに強く訴えるものがある。
◆去年秋にアフガニスタンで中村さんの灌漑と医療のプロジェクトを訪れて以来、私自身が人間、中村哲にハマってしまい、勝手に「語り部」を名乗って人に伝える活動をしている。7月は東京・小金井市の市民講座で「中村哲医師が命がけで私たちに伝えてくれたこと」を語った。なんと小4(9歳)の少年が、毎回最前列でメモを取りながら聴いてくれた。やはり映画に感動し、親に勧められたのではなく自分から申し込んだという。聴講者の最年長は90歳超。中村さんは老若男女とわず多くの人を魅了している。
◆今年2月、中村さんの現地活動を支えてきた福岡の「ペシャワール会」を訪ねる機会があった。中村さんが亡くなった3年前に1万6千人だった会員と寄付者の数が2万6千人へと没後急増しているそうだ。どうやら今、静かな「中村哲ブーム」が起きているらしい。ますます閉塞感きわまる世の中にあって、中村さんの生き方が輝く希望の星になっているのではないか。
◆中村さんのものの見方は、世間の多くの人とはまったく違う。もう十年以上前になるが、「毒入り餃子事件」があった。農薬の混入した中国製の冷凍餃子を食べた人が体調を崩し、大きな騒ぎになった。激しい中国バッシングのなか、中村さんはさらりと「因果応報というやつですよ」と言った。「ギョウザぐらい自分で作ったらいいのに。自分の手を汚し、汗を流してつくったものがまっとうでしょう。人の労働を安く買って、それで食ってるということの報いですよ」
◆餃子の皮に使う小麦粉の自給率は15%、外国から便利さを金で買ってくればいいという風潮を、中村さんは「日本人の道徳にもとる時代」と一喝する。まるで頭の古いおやじの説教だが、よくよく考えてみると正論だなと認めざるを得ない。その中村さんの目には、かつての「日本の文化や伝統、日本人としての誇り、平和国家として再生する意気込み」が息づく時代は去り、「進歩だの改革だのと言葉が横行するうちに、とんでもなく不自由で窮屈な世界になった」と見える。
◆そのとおり!と思う一方で、こんな世の中にしたのは、他ならぬ我々「信頼できない大人」なのではないかとわが身を振り返る。このごろ気になるのは、同じ年配の友人と話すと「おれたちは逃げ切れるよな」という言葉をよく聞くことだ。先日の週刊誌にも「50代は『逃げ切り世代』か」などという記事が載っていた。年金はじめ社会保障の破綻からの「逃げ切り」のことだ。このもとになっているのは「人生の目的は自分(だけ)が幸せになること」で、「死んだらオシマイ、せいぜい生きてるうちに楽しもう」という、利己的で刹那的な人生観だろう。「あとは野となれ山となれ」
◆倫理なき時代なのである。以前、TBSの特番でスタジオに呼ばれた高校生が「なぜ人を殺してはいけないんですか?」と質問したら、居並ぶ識者が誰も答えられなかったという「事件」があった。高校生がその問いを発したこと自体が時代を象徴している。
◆そんな今、中村さんの言葉は凛と響く。「己が何のために生きているかと問うことは徒労である。人は人のために働いて支え合い、人のために死ぬ」。「我々がこだわるのは、世界のほんの一隅でよいから、実事業を以て、巨大な虚構に挑戦する良心の健在を示すことである。万の偽りも一つの真実に敗れ去る。それが次世代への本当の遺産となることを信じている」
◆人のため、さらに次世代、後世のために生きる――今の風潮とは真逆のこの人生観に「不自由で窮屈な世界」からの突破口があるかもしれない。でも、とても真似できないと途方にくれそうになるが、中村さんは座右の銘「一隅を照らす」を引きながら、やさしく範を垂れてくれる。
◆「一隅を照らすというのは、一つの片隅を照らすということですが、それで良いわけでありまして、世界がどうだとか、国際貢献がどうだとかという問題に煩わされてはいけない。それよりも自分の身の回り、出会った人、出会った出来事の中で人としての最善を尽くすことではないかというふうに思っております。今振り返ってつくづく思うことは、確かにあそこで困っている人がいて、なんとかしてあげたいなあということで始めたことが、次々と大きくなっていったわけですけれど、それを続けてきたことで人間が無くしても良いことは何なのか人間として最後まで大事にしなくちゃいけないものは何なのか、ということについてヒントを得たような気がするわけです」
◆生きにくい世の中、自分にとっての「一隅」をまっとうに生きたい。そんな願いを、話を聴いてくれる人と共有しながら、「語り部」の活動を続けていこうと思う。
■さきほど久々に石川直樹君から電話があった。ほんとに久しぶりだ。8000メートルをいくつも登っていることは知っていたが、どうやらみんな登ってしまおう、と考えているらしい。ふぇー! 石川直樹、そこまでやるのか。
◆石川君がはたちのときだったと思う。北極から南極まで歩き通そう、という「Pole to Pole」計画に日本の青年を推薦してほしい、と頼まれ、田部井淳子さんらと相談して石川君を推したことがある。その後彼は次々に自分の世界を広げていって見事な表現者となったことは皆さんご存じのとおりだ。
◆そのかたわら、ラッセル・ブライスの公募登山隊に入って8000メートルに挑戦し続けてきた。今更私に相談することもないとは思うが、彼とは不思議な縁でもある。この通信の仕事が終わったら話を聞いてみよう。
◆今月の地平線報告会、上で長野画伯が紹介しているように、高野秀行、山田高司、コンビにお願いしますが、当日普段なら報告会で買えるはずの新刊『イラク水滸伝』、分厚すぎて(厚さ4センチあり)会場に置けないのでできれば冒険研究所書店で購入してください。では、26日の土曜日![江本嘉伸]
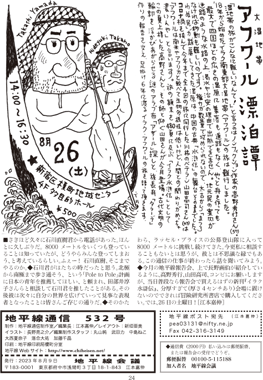 |
アフワール(大湿地帯)漂泊譚
「湿地帯の旅がこんなに難しいなんて!」と言うのはノンフィクション作家の高野秀行さん(57)。'18年から始めたイラク南東部大湿地帯(アフワール)の旅は難行しました。最大で四国ほどの広さの湿原に集落も道路もなく、やっと舟を作っても迷路のような水路の上、渇水や治安の理由で出航できません。地元民の案内がなければ移動も難しいのです。 権力が数量で攻められないので、太古から「まつろわぬ民」が跋扈してきた湿原は、中国の古典「水滸伝」の舞台そのままでした。コロナ禍を挟んで今年まで全4回の旅に同行した川旅のベテラン山田高司さん(65)は「アフワールは南米やアフリカと較べて生物多様性は低いけど、人間との関わりがめっちゃ濃いんや」と言います。 旅の顛末を480頁に及ぶ「イラク水滸伝」としてこの夏上梓した高野さんと、その師と仰ぐ山田さんが今月登場。古代文明の輪郭を浮かびあがらせる謎のアラブ布「アザール」探しと、族長舟「タラーデ」作りの報告を交え、足掛け6年に亘るイラク・アフワールの旅を語って頂きます。 |
地平線通信 532号
制作:地平線通信制作室/編集長:江本嘉伸/レイアウト:新垣亜美/イラスト:長野亮之介/編集制作スタッフ:丸山純 武田力 中島ねこ 大西夏奈子 落合大祐 加藤千晶
印刷:地平線印刷局榎町分室
地平線Webサイト:http://www.chiheisen.net/
発行:2023年8月9日 地平線会議
〒183-0001 東京都府中市浅間町3-18-1-843 江本嘉伸 方
地平線ポスト宛先(江本嘉伸)
pea03131@nifty.ne.jp
Fax 042-316-3149
◆通信費(2000円)払い込みは郵便振替、または報告会の受付でどうぞ。
郵便振替 00100-5-115188/加入者名 地平線会議
|
|
|
|
|
|