

3月11日。あたたかい。午後2時の新宿の気温は20度だ。今朝の新聞の一面トップは「新型コロナ イベント自粛10日延長」(読売)「避難なお4.7万人 人口34万人減 東日本大震災9年」(朝日)「地球異変 再生エネを首都圏へ(東京)」微妙に違うが、新型コロナ・ウィルスをめぐる世界的な動きが関心を集めている。
◆先月12日に地平線通信490号を出した時、コロナ問題は横浜港に停泊する客船「ダイヤモンド・プリンセス号」の船内に集中していた、と今にして思う。なんとなく、あの客船でおさまる、という根拠のない楽観があった。それがとんでもなかった。2日後の2月14日、世界は一気に変容した。“震源地”の武漢、を含む中国だけで何万という感染者がわかり、瞬く間に世界に広がった。
◆いまや、イタリアがかなり危ない地域となり、いよいよ「パンデミック」か、との声があちこちから出ている。日本語的で「感染爆発」と訳されるこの言葉、、第一次世界大戦中の1918年から1919にかけて猛威を振るったスペインかぜ(インフルエンザ)では「世界人口の約50%が感染し死者が2000万人以上」と言われている。武漢はじめ中国の感染がおさまり始めているので来月までに別の展開になるかもしれない。
◆そんなさ中、「第9回梅棹忠夫・山と探検文学賞」の選考委員会が2月20日、都内で開かれた。選考対象となったのは、『牙 アフリカゾウの「密猟組織」を追って』(三浦英之著 小学館)『転生する文明』(服部英二著 藤原書店)『極北のひかり』(松本紀生著 クレヴィス)『ダリエン地峡決死行』(北澤豊雄著 産業編集センター)の『考える脚』(荻田泰永著 KADOKAWA)の5点。地平線会議を代表する形で私は第1回から選考委員を勤めている。
◆毎年結構激論が戦わせられるのに、今回は驚くほどすんなりと決まった。われらが北極男の『考える脚』である(発表は信濃毎日新聞を通して3月6日に行われたが、それ以前にFB=フェイスブック=で情報は駆け回ったようであった)。内容については12ページの「地平線の森」を参考に、とにかくぜひ手にして読んでほしい、と思う。少し解説しておくと、この本は、「北極点無補給単独徒歩」「カナダ〜グリーンランド単独行」「南極点無補給単独徒歩」の三つの行動を記録している。
◆その二つ目の章の途中で荻田は「それにしても1970年代から80年代にかけては日本人による北極探検が盛んな時代だった」と、1978年、植村直己さんに先んじて北極点に到達した日本大学隊の中村進カメラマンの名をあげている。1975年のエベレスト、1978年の北極、1980年のチョモランマと三つのエクスペディションで私も一緒に現場にいた、懐かしい仲間だ。
◆中村カメラマンとは痛切な思い出がある。1980年4月、チョモランマ北東稜のアタック隊に加藤保男、中村進の2人が選ばれた。しかし、重いカメラを背負っての登高で消耗した中村は8600メートル地点で頂上を目前に稜線に残り、加藤1人が登頂した。その際、報道隊員として目の前のノースコル(7000メートル)にいた私は夜明けまで日テレ隊の岩下莞爾ディレクターに代わって“励ましコール”をハンディー・トーキーで送り続けたのだ。あそこで寝てしまったらやばい、という判断で中村にとってはいい迷惑だったかもしれないが、とにかくあの高所で夜が明けるまでありとあらゆる思い出話をし(話す内容はいくらでもあった)、眠るなよ、しっかり帰って来いよ、と言い続けたのである。
◆無事下山した中村はその後1988年の中国ネパール三国合同隊に参加して「世界最高峰頂上からの生中継」をやってみせた。1994年12月から95年1月までの40日間、南極点まで1200キロをスキーで走破(サポート付きだった)し、日本人初の「三極点に立った人」となった。帰国後の1995年2月28日には「ちょいと極点までクロスカントリー」というテーマで184回の地平線報告会で話をしてもらっている。2008年、名峰クーラカンリで雪崩のため帰らぬ人となった。
◆振り返ってみると自分は時代の結構いい現場に居合わせ、ずる賢くも生き残った人間なのだな、とつくづく思う。前にも書いたが、大した登山家ではないのに、山岳部で、とりわけ冬、春の北穂高滝谷の登高で鍛えたアイゼン技術(急傾斜の氷壁を怖がらずに登攀できた)が私にはありがたいほど役立ったのだ。地平線会議のような活動を飽きずに続けられるのは、残った人間の使命と感じてもいるからだ。
◆きょう11日は、あの東日本大震災から9年の日だ。政府が予定していた追悼式は新型コロナ・ウィルスの影響で中止された。そして何よりも観客が1人もいない大相撲の土俵に愕然とする。四股を踏む力士の足音、行司のかけ声、ガランとした会場。21世紀の“異常な現場”としてこの大阪場所をしっかり記憶しておこう。東京オリンピックはとんでもない、のかもしれない。(江本嘉伸)
■新型コロナウィルスが猛威を振るう中、前回の通信を読んで「長いこと閉ざされていたあのナガランドの報告だ!!」とワクワクしながら会場に入ると、飾らない佇まいに意志の強い瞳が印象的な女性が立っていた。延江由美子さん。今日はナガランドを含むインド北東部の暮らしや文化を300枚の写真とともに報告してくださる。延江さんはローマ教皇を頂点とするカトリック教会のMMS(メディカル・ミッション・シスターズ=医療宣教師)という女子修道会のシスターとして活動されている。
◆いくつもの部族の言語を操り異文化の中で軽やかにステップしているようにみえる延江さんにも、これまでに幾つかのターニングポイントがあった。高校生の時に交換留学生として一年間過ごしたアメリカで熱心なクリスチャンのホストファミリーと出会い、深い宗教体験や人生の見方を教わり、自らもクリスチャンの洗礼を受けた。帰国後、獣医をめざし入学した北海道大学でヒグマ研究グループ(北大クマ研)と出会い、さらなるカルチャーショックを受け、獣医としてアフリカで働くことを夢見つつも、大学院進学直前にカルカッタのマザー・テレサのもとでボランティアをして過ごすことになる。
◆結果、獣医学から看護へ針路を変更。獣医資格を取得後学費を貯め、アメリカで看護学部に入学。その時の友人の紹介でMMSと出会うことになる。アフリカへは行きそびれたが、2000年からインド西部マハシュトラ州と北東部でミッションに参加、今に至っている。
◆北東部赴任前に働いていたマハシュトラ州のプネのHolistic Health Centreでのダウン症の少年へのたった一回の治療の効果に愕然として、鍼治療も習得した。治療前後の写真を見て江本さんが思わず「これ、同じ人なの?」というくらいの表情の変化なのだ。鍼を刺して微弱な電気を流して気の流れを促進するという技術をひっさげて、延江さんのインド北東部でのミッションは始まった。
◆インドは人口が13億人、その4割が20代以下の多民族多宗教。多様性とコントラストの国だ。インドの人は“多様性の中の一致”ということに誇りをもっているが実際は州ごとに異なる公用語、宗教、カーストなどによって分断されていて社会集団間での対立は激しい。逆三角形の形のインドからバングラデシュの北東にちょこんとはみ出した小さい三角の地域がインド北東部だ。8つの州(アルナチャル・プラデシュ、アッサム、メガラヤ、ミゾラム、マニプール、ナガランド、トリプラ、シッキム)からなる先住民族(モンゴロイド系が多い)が多く住む地域でチベット・ビルマ系やモン・クメール系の言語を話す。一般的に想像する「インド」の人々とはかなり隔たりがあるような気がする。「インドであってインドでない」と延江さんがいうそこはいったいどんなところなのだろう?
◆北東部で国境がバングラディッシュと隣接する州の一つがメガラヤ州。メガラヤ州の西地域がガロヒルズ、中央地域がカシヒルズである。ガロヒルズにはクリスチャンが多く女系のガロ族、ヒンドゥー教のラバ族、ヒンドゥー教徒やムスリムのベンガル人、精霊信仰のハジョン族などが暮らしているが、延江さんが一番親しくしていたのはガロ族で、竹と藁の素朴な高床式住居での生活の様子が多数の写真で紹介された。土地が豊かなところやバナナの葉っぱのお皿に主食が米とは南インドのようだ。
◆『世界が100人の村だったら』13人が青空トイレをしている。そのうちの半分がインド人。女性には危険も多い。そこでインド政府が行ったクリーンインディアキャンペーンの一環としてガロヒルズにも立派なトイレができた。でもトイレだけでなく下水や汚物処理の教育も大切である。写真ではガロの家族や民族衣装が次々と紹介されていく。手織りの布の腰巻が美しい。同じガロ族でも山のほうに住んでいる人は、より先住民族に近いキリッとした顔つきだ。ガロの人々は豊かな自然環境のせいか心優しい人が多いが、お祭りの伝統的な衣装からも推測できるように昔は戦闘的な民族だった。
◆ガロの家族が延江さんのために踊ってくれた曲がチベットの歌謡曲のように聞こえてしまって、ああ、ほんとうに「インドであってインドでないな」と納得してしまった。ラバ族のキリスト教の儀式がヒンドゥー教の影響を受けていたり、ヒンドゥー教のプジャにベンガル人も参加していたりで渾然としている。溢れる民族衣装の写真に目が奪われる。
◆延江さんの重要な仕事である鍼治療は村の人々に喜んで受け入れられた。マラリアの後遺症の15歳の少年に3か月通って経絡を刺激する鍼治療をした結果歩けるようになったという。鍼治療は自転車にまたがって出張治療できるのが良いところだそうだ。自転車で出向く先々には面白い発見がたくさんある。
◆共同体で行う魚釣りも面白い。田んぼでの小魚釣り、池でも、川でも日がな1日魚釣り。冷蔵庫はないので獲れた魚はその日のうちにフライにして食べてしまう。小魚は干して竹の中に入れて発酵させる(ナッカム)。このナッカムを使っていわゆるインドカレーではないこの地域独特のカレーができあがる。週に一度はどこの町や村でも市がたち、肉や野菜や生活必需品が売られる。手の込んだ手織りの布も売られているが商売をしているのはビハール人かベンガル人。商売が下手なガロの人々は中間搾取されてしまうのだ。
◆機を織るのも米をつくのも秋の収穫も手作業。牛を歩かせて脱穀。時々牛が籾を食べてしまってもシェアの精神で気にしない。最近では気候変動で大洪水が起きて橋が流されたり季節はずれの大雨で収穫間際のお米が台無しになったり甚大な被害をもたらす一方、そこには店ができてピクニックスポットとなる。なんとも大らかでたくましい。ガロ族の紹介の間「本当に幸せそうなんですよ」という言葉を何度聞いただろう。経済的には貧しいが幸福度満点のガロの人々の笑顔に延江さんでなくても引き込まれてしまう。
◆メガラヤ州はバングラデシュと接しているのでバングラデシュから人(ムスリムに限らず)が流入しやすいし、バングラデシュ側にも昔からガロは住んでいた。一般的にムスリムの男性はハンサムなのでガロの女の子が「ポ〜」となってしまう。しかし結婚するとムスリムとなり、ガロの女の子が相続した土地がムスリムのものになってしまう。また、昔から現金を必要としない生活をしてきたガロ族はいざ現金が必要となると土地を担保にムスリムからお金を借りるので、そこでも土地がムスリムのものになる。
◆かつてはガロ族しか住んでいなかった場所に多くのムスリムが住むようになってきた。また、このようにムスリムの人々がどんどん増えていっている原因の一つとして、女の子たちは若年で結婚し、どんどん子どもを産んで大変な子沢山になるということも忘れてはならない。ガロヒルズでは、貧困によって多くの若者が武装集団に加わり洗脳され、治安が一時ひどく悪化したがピースキャンペーンの活動によって今は落ち着いている。
◆カシヒルズの中心地でメガラヤ州の州都でもあるシロンはイギリスの植民地時代の避暑地。ヒマラヤ桜に囲まれたイギリス風の建物が建つ美しい街だ。しかしシロンから一歩外にでると、全くの別世界で貧しい。写真ではチェックの布を纏ったエキゾチックな容貌のカシ族が印象的だ。ガロヒルズとは同じ州なのに全く違う。カシ族はアレカナッツの実と緑の葉を一日中食べて口を赤くしている(インドでいうパーン?)。
◆カシ族もほとんどがクリスチャンで肉は大好き。市場には牛の頭が鎮座している。血のソーセージ、血の混ぜご飯、豚の腸のサラダ、カシ族独特のカレーと食生活もけっこう強烈だ。米食(蒸す)で子沢山で兄弟姉妹の世話は当然、家族で団欒など、なんだか昔の日本のようだ。カシヒルズには炭鉱が多いのだが環境問題で閉鎖され、大事な現金収入の道が閉ざされて大打撃となっている。布を織るのも大切な現金収入でインド北東部ではどの地域でも機を織る。今日はたくさんの手織りの布が延江さんの後方に展示されている。ガロの手の込んだ花柄模様のダクマンダ(腰巻)、ラバとアディバシの来客の首にかける布(チベットのカターのよう)、アッサムに住むカルビの布、ナガの大判の厚手の布。使い方も模様もそれぞれ特徴がある。
◆メガラヤ州の北と東に隣接するブラマプトラ川流域に広がる平野がアッサム州。ブラマプトラ川は源流のあるチベットではヤルツァンポ川と呼ばれ、やがてはガンジス川と合流してベンガル湾に流れ出でる。ヒンディー教徒のアッサミーズやボド、イギリス統治時代にお茶のプランテーションに出稼ぎに来てジャングルを畑に開墾したアディバシ(ウラオン族、サンタリ族)をはじめ北東部で最も多様な民族を抱えている。
◆体格も言葉も宗教も風習も違う。向かい合ってものすごく丁寧で可愛らしい挨拶をかわすサンタリの人々には会場からも驚きの声があがった。顔や手に刺青をしている人もいる。北東部に住む先住民族には文字はなくアルファベットを使うのだが、ベンガル人の影響をうけたアッサム語だけは文字がある。梵字に似ている。さまざまな民族の歌や踊りの動画に魅せられたが多くの民族が暮らすアッサムのもうひとつの現実は……。
◆ヒンドゥー至上主義を掲げるモディ政権が、パキスタンやバングラデシュ、アフガニスタンといった周辺諸国から2014年までにインドに入国して5年以上住んでいるイスラム教徒以外の6つの宗教の信仰者に国籍を与える「国籍法改正案」を導入。今、まさにインド全国で起きている抗議の動きは北東部アッサム州全域をも巻き込んでいる。政府は「国民登録簿」を発表して「本物のインド人=ヒンドゥ教徒」を認定しなおすという。
◆1971年にパキスタンからバングラデシュが独立した時に内戦が勃発し多くの人が北東部に逃れてきた。その後彼らは住みつき選挙権まで持っている人もいるにもかかわらず、この「国民登録法」は「本物のインド人」を認定しなおすという目的で2015年に始まった。モディ政権はヒンドゥ教徒こそ「本物のインド人」とし、ムスリムや少数派を「よそ者」と位置づけている。2018年7月末で400万人が国籍を失いかねないといった危機的な状況にもある。
◆イスラム教徒への迫害であり、多宗教を認める「世俗国家」としてのインドという国の根幹を揺るがせかねない事態となっている。その上、ムスリム、クリスチャン、ダリット(カーストの最底辺の不可触民)等マイノリティーに対する迫害も激化している。延江さんのようなシスターたちは宗教の壁なく誰とでも親しく交流できているが、こうした現実もぜひ報告したかったそうだ。
◆ナガランドはインドでもほとんど知られていなかった地域。19世紀後半にイギリスがこの地域をナガランド、そこに住む先住民を十把一絡げでナガ族と名付けたにすぎない。ナガはサンスクリット語で「へび」の意味だがナガランドとは関係ない。ナガの人々がインドの支配下に置かれるきっかけをつくったのは19世紀から始まったイギリスによる植民地支配。地図を見るとナガ族はナガランド州、マニプル州、アルナチャル・プラデシュ州及びミャンマーといった地域に居住している。地図上のそういった区分はナガの人には関係なく区切られたもので、ある家などは家の半分はインドで残りの半分はミャンマーだったりするそうだ。大国が勝手に国境をひいてしまい、そこに住んでいた人たちが犠牲になってしまったのだ。
◆ナガの人々はほとんどがクリスチャンでその90%がバプティスト。「バプティストとカトリックは仲はよくないです。なぜならバプティストがカトリックを受け入れてくれないからです……」と仰る延江さん。ここにも私には測り知れない宗派の隔たりが存在するのだろうか。カトリックの立派な教会やキリスト像、美しい民族衣装でミサに集う婦人会の女性が映し出された。シスターたちの写真は全員が日本人のような……全員がナガ人のような……。延江さんもしっかりとけ込んでいる。「シスターはどの部族なの?」と尋ねられと「ジャパニーズ・トライブ」と答えるそうだ。
◆「ナガ族は30年くらい前までは『首狩り族』でした」さらっと仰る。ナガ族は部族ごとに自分たちの村で自分たちの文化を祝うお祭りを違った時期に一年を通じて催しているが、年に一度、ナガ族の様々な部族が一堂に集まってナガとしてのヘリテージを祝う「ホーンビルフェスティバル」というお祭りがある。戦闘的なコスチュームに大きな装身具、角や貝の飾り、士気を高めるダンスや儀式、どぶろくや肉のごちそうを食べて一週間も続くお祭りに世界中からカメラマンが押し寄せるそうだ。会場に展示してあった赤と黒の大判の布を長野さんがマントのように羽織ってみせてくれた。「かっこいいなぁ」と江本さんがつぶやいた。山岳地帯のナガランドでは毛布代わりにもなる布は重宝する。赤、青、黒が基調のかっこいい布だ!
◆コヒマはナガランドの州都で、カテドラルというカトリックの司教が住んでいる教会がある。コヒマの村は家々が密集して建っている。山の斜面にへばりつくようにできた集落の入り口にはその村独自のデザイン(文字がないのでゲートの石や木に文化を刻む。石もまたスピリットがある特別な存在)のゲートが建っている。昔は夜間や敵が攻めてくると閉めたそうだ。
◆理想的な民主主義が行われていたと文献にも書かれていた長閑な村。集落の写真はネパールの山岳地帯のようだ。電気はきているが暖房や煮炊きは薪。森林伐採は環境破壊の深刻な問題でもある。土間に囲炉裏での生活で、以前はお産さえも土間で行ったようだが、ナガ族は非常に頭が良く革新的な民族性なので生活はどんどん近代化してきている。スマホは当たり前。山を崩して国道も広げられている。
◆「石と土以外なんでも食べる」と自ら豪語するナガ族。干しガエルに驚いていたら「犬や猫がいないなと思っていたら、みんな食べちゃうんですよね」と解体される犬の写真が! ワンコを弟だと思っておぶっていたカルビ族とは正反対だ! 狩猟と焼畑の生活だったのだが、食はバラエティーにとんでいる。川ヘビ、蜂の子、蚕、カエルに昆虫。バッファローの頭や肉、鶏、干し魚、発酵した筍、ハーブや唐辛子の山、古着の山まである。
◆ラジャ・チリ(拷問にも使われた世界で最も辛いチリの一つ)やアクニという納豆(塩・唐辛子・生姜を入れてチャトニイにする)はご飯のお供となる。市場とはうって変わって棚田や田植えの風景はほっとする。田植えの時には歌をうたう。教会の婦人会の人が歌ってくれたハーモニーは、映画『あまねき旋律』のようなあの独特の美しい調べだった。
◆婦人会の歌の内容は「若い女の子への歌:少女たちよ、泣かないで。今、生きていることを楽しもう。将来どこか遠いところに行くことになるかも知れないのだから。今、こうして自分たちの地にいる時を大切にしてほしい」というものだそうだ。今を生きるシスターや神父志願の学生たちにもMMSも含むカトリック教会は教育の機会を与えている。
◆1944年日本軍がビルマからインパール攻略を目指した「インパール作戦」(現地ではジャパン・ウォー)。コヒマは激戦地となり、連合軍と日本軍の戦争なのに大勢のナガ人も犠牲になった。コヒマには連合国の戦没者墓地がある。日本軍の犠牲者は3万とも4万とも言われているがその遺骨のほとんどは未だ奥深い山のどこかに取り残されたまま。彼らの慰霊のための寄付が1989年にコヒマの教会に寄せられた。ナガの犠牲者には何かあるのだろうか……。
◆ナガには日本の軍歌を覚えている人がいる。「白地に赤く日の丸染めて……」この動画を見ながら、私はこれがナガの犠牲者への供養の形なのかもと思ってしまった。日本軍は土地に詳しいナガの協力を得るために学校を設立したりもした。ナガの独立支援を約束していた日本軍は敗退したが、独立を目指す方向は変わらず、1945年8月14日(15日にはインドがイギリスから独立)にナガは独立宣言をする。しかし、どこの国にも無視されてしまい、武装闘争へとすすんでいく。
◆この間、チベットを受け入れたインドに対抗して中国はナガを支援した。独立宣言が世界中から無視されたことも、イギリスやインド、中国といった大国の力に振り回されてしまったこともまるで過去のチベットをみているようで心が痛い。何度か和平協定の締結が試みられたが民族間の分裂も招いて泥沼化。今も戦闘こそないが解決には至っていない。1950年代にはインド軍による多くの拷問や暗殺があった。その後、全面的な戦いは1975年まで続いた。インド政府はその酷たらしい事実を国際社会から隠すために2011年までナガランドを許可証が無ければ入域できない制限地域にして、事実的に世界から隔離した。それ故にナガランドはその存在自体を知られることがなかった。
◆写真には仲良く並んで写っているMMSのもとにいる学生たちも、現地出身の若いシスターたちも部族間でいざこざが起きることが多いが、未来の社会には多の文化共存しかありえない。MMSはそういった活動をつづけていく。と延江さんは力強く仰った。市場に並んだ屠られたばかりの水牛の首、「でも、マグロの頭と一緒ですよね!」。首狩り族って……「でも、日本も戦国時代は晒し首してましたよね!」。なるほど、異なる文化を上手に変換して認めて共存していく方法を教えていただいた。(田中明美 チベット好きのデザイナー)
■メディカル・ミッション・シスターズ(MMS)という日本にはないカトリック女子修道会のシスターが、地平線会議で報告会?? それに巷は新型コロナウイルスの感染拡大ですったもんだの大騒ぎ。開催日は、会場が1か月間の閉館になる直前という間一髪のタイミング。今回、曲がりなりにも報告会を終えることができたのは恩寵としか言いようがありません。あらためまして、ご尽力くださった方々にこの場を借りて心よりお礼申し上げます。
◆さて。「インド北東部について」と大風呂敷を広げたものの、その内容はというと、私が2007年から修道女として関わってきたごく限られた民族(ガロ族、カシ族、ラバ族、アディバシ、カルビ族、ボド族、ナガ族)の生活場所と風習、彼らが置かれている現実とその歴史背景などを、これまたごく限られた私の個人的な経験とあれこれ見聞きしたことに基づいてまとめたものでした。これまでもキリスト教関係の場では何回か話をしてきましたが、今回はたっぷりとお時間をいただいたので、あれもこれも欠かせないとつい欲張ってしまい、結局、動画を含め300枚という膨大な写真をお見せしながらの報告となりました。二次会がなくなったぶん少し延長できたのですが、それでもやっぱり時間は足りなくて、もっと質疑応答できたら良かったし、お越し下さった方々ともっとお話ししたかったと残念でなりません。
◆私はMMSとして足掛け20年インドで活動をしています。北東部に移るまで5年間はムンバイのあるマハラシュトラ州で、プネを拠点として鍼やマッサージを通して地域医療に携わっていました。現地語であるマラティ語を学び、MMSの家があるヒンズー教徒の村とダリット(カーストで一番虐げられている人々)のコミュニティーに足繁く通い、彼女たちにミッショナリーとして育ててもらったと言っても過言ではありません。
◆その後北東部に赴任。そこに住む人々のおおらかさと多様な文化の素晴らしさ、思わず目を見張る興味深い生活習慣にすっかり魅了され今日に至っています。さんざん苦労して身につけたマラティ語は北東部にあっては当然使い物にならず、ガロ、カシ、カルビ、ナガミーズ、ロンマイと少しでもその土地の言葉を学ぼうと努めていますが、違う言語のフレーズや単語が頭の中でスープの具のようにぷかぷか浮いてるみたいで、どれをとっても「現地語レッスン1」レベルから脱出できず、いくつもの言語を自由に操る子供たちには笑われています。
◆こうして現地でのことにあれこれ思いを巡らせていたら、宗教や国の違いは人々を隔てる境界ではなく、むしろ「縁側」つまり人と人を繋げる「縁」が生じる「縁側」かも?という趣旨の文を見つけました。まさに我が意を得たり!というのも、ミッショナリーは境界線にいる立場の人間ですから。
◆宗教の自由を謳うインドですが、ヒンズー教原理主義団体がバックにある現政権下ではミッショナリーとして入国するといろいろ面倒なので、ここ数年は観光目的ということにして入っています。そして矛盾するようですが、ナガランドに到着すると修道服に着替えます(MMSはインドの他の地域を含め世界のどこでも修道服を着ません)。というのも、ナガ、ガロ、カシ、アディバシにはクリスチャンが多く、修道服を着ていれば身分は一目瞭然。相手は安心してくれます。北東部では日本人なら誰でもナガと思われますから、得体の知れないナガのおばさんよりシスターの方がなにかと便利なのです。
◆それにしても、ナガランドは例えば、「コヒマからディマプールに行くとインドに来たって感じる」と言われていましたが、2011年から許可がなくても入域できるようになったこともあってか、かつてのような強烈な非インド性は感じられません。凄まじい勢いで開発も進んでいます。ナガランドに限らず、ガロヒルズもカシヒルズもカルビアングロングもどんどん変わって行くのでしょう。もともと見知らぬ土地に行くのが好きなので、これからも機会を見つけて(あるいは作って)北東部を探っていこうと目論んでいます。またいつか世界のどこかでみなさんにお目にかかれますように。
■最後になりましたが、参考資料の地図について、お詫びのうちに訂正させていただきたいことがあります。まずはブラマプトラ川について。報告会の後で次のご指摘をいただきました。「<ブラマプトラ川>はディブルガーの先で北側に伸ばしてほしかったです。探検史で有名な『謎の大屈曲部』のあるヤルツァンポがブラマプトラ川の源流ですから」ということです(ディブルガーは地図ではアッサム州の北の端っこに黒丸で示されています)。もう一つ、記述が曖昧だったところがあります。1947年独立時には地域全体がアッサムと呼ばれていましたが、8つの州が徐々に別々の州となって行きました。シッキムは1975年に北東部の8つ目として最後に加わったのですが、それまでしばらくの間、彼の地の7つの州は「セブン・シスターズ」と呼ばれていたということを付け加えさせていただきます。他にもまだお気づきの点が多々あったと思いますが、どうぞご勘弁くださいませ!
追伸:インド行きは延期です
■3月3日にインド政府は日本人に発給していたビザを無効にすると発表。18日に予定していたインド渡航は延期です(中止になりませんように!)。3月中旬からのひと月間はインドにおける修道会の新規会員勧誘活動にとっては大変重要な時期で、今回も到着した翌日にはマニプールかカシヒルズへツーリングに出掛けることになっていたのですが……。
◆生徒たちにも「3月また必ずくるから!」と約束していました。北東部の姉妹たちによると、インドでも感染者は増えていて、人々はとても神経質になってきているそうです。今できることは一刻も早く事態が収束し入国制限が解除されることを祈り願いつつ、この事態だからこそできることに専念すること、でしょうか。Go with the Flow. というわけです。
◆私が冬と夏は日本に居る理由は年老いた母をサポートするためなので、娘がもう少し滞在することに母は素直に喜んでいます。それにしても、去年9月の渡航予定日は台風15号上陸にあたってしまったし、もしかしたらこういうことは今後、「よくあること」になってしまうのかも知れませんね。(延江由美子)
■「お前はコヒマから来たのか」30数年前、インドのロータン峠でいきなり声をかけられたことがあった。声の主の憐れみと見下すような視線を感じたのが「コヒマ」を実在の地だと実感した最初だった。我々の世代だと「コヒマ」と聞けば「インパール作戦」と即座に思う。「インパール作戦」に身内が参加したという友人たちもいるが、そのことは大っぴらに話してはいけないことで、話題にされたくないようであった。そのためか、私にとっての「コヒマ」は活字の世界の地でしかなく、語弊のある言い方をすれば「自分には縁のない地」であった。その後、不思議な縁あって「コヒマ」も「インパール」も身近な地名となった……。
◆そのコヒマに拠点をおいて活動している延江さんの講演があると知り、足を運んだ。動物好きでアフリカでの仕事をと考えて獣医資格を取得するも、大学院進学直前に体験したマザー・テレサの下でのボランティア活動が転機となり、アメリカ・カトリック大学に入学して看護師資格を取得。1995年に日本人唯一人のMMS(メディカル・ミッション・シスターズ)会員となった延江さんは2000年にインドに派遣され、2007年からはハリそしてマッサージなどのケアやセラピストとしてナガランドでのミッションに参加している。
◆延江さん自身の活動内容もさることながら、ナガランドの複雑な歴史背景や民族間の対立そして今なお続いている独立闘争への思いや、自分たちのミッションなど外部からの影響で若い世代が都市部へ流出することに対する葛藤など、通過するだけの旅人とは異なる視点での報告に、久々にすがすがしい思いがした。
◆「インドだけどインドじゃない」「インド人だけどインド人じゃない」インドで未だ事前に入域許可を取得しなければならない、ナガランドのさらに北側のアルナーチャル・プラデーシュ州北東部・ブラマプトラ川源流周辺の人たちも同じように「俺たちはインド人じゃない」と口にする。第二次大戦が始まっていることも知らないまま、一方的に「インパール作戦」の荷役に連れていかれたアディ族も当時の日本人に対して好印象を抱いている。
◆現政権の経済優先のための大規模開発はインド北東部全体に及んでいる。一見未だ<非文化的>生活を送っているように見える彼の地の人々には彼らなりの文化も文明もある。我々の国もそうであったように、遠くない将来彼の地もいわゆる<文化的な生活>となるのであろうが、願わくばその変化が緩やかに進むことを祈る。(寺沢玲子)
■約1年ぶりの報告会。参加者が少しずつ集まってザワザワしてくるこの雰囲気が大好き。アジア旅をしてきたのに、なぜかまだインドには至っていない。そのせいでしょうか、地平線通信の延江由美子さん紹介文に引き寄せられて、遥々参加することになりました。
◆会場には延江さんが持ち帰った美しい布が、数種類並べられていた。布はインドの魅力のひとつ。ガロ族の女性が腰巻として使うダクマンダと呼ばれる布。横縞と花柄の組み合わせが可愛らしい。ナガ族のものと説明されていた黒と赤の大胆な縞の布は、何度か訪れたベトナム中部の高地に住む民族のものと雰囲気が似ている気がする。背の高い長野亮之介さんがゆったり纏えるサイズ。
◆高山に戻り、ベトナムの写真集を広げた。なるほど、私はCOTU族やGIETRIENG族の衣服を思い出していたのだ。よく見ると、そっくりではないが配色や縦縞に類似点がある。ベトナムの布の素材はざっくりとした木綿。ナガ族の布は保温性があるが感触は羊毛ではない。ということはアクリルか? たぶん以前は木綿、もしくは獣毛(羊毛やヤクの毛)で織られていたのだろう。デザインが縞だけかと思いきや、黒地の部分に数カ所、赤い紋様が入っている。表からしか見ていないので確証はもてないけれど、東南アジアでよくみられる縦紋織かな。いったいどうやってこのデザインは伝わっていったの? ナガランドには他に草木染の柔らかい色を活かしたデザインの布もあるらしい。あれやこれやと妄想は膨らむばかりであった。
◆私は旅先で出会う魅力的な布について理解したいという想いから、染織を学び始めた。制作工程についてはある程度想像できるようになったけれど、それぞれの民族衣装が持つ歴史や制作技術の伝播など、知らないことだらけである。今回、訪れたことのないナガランドの布に触れて、様々に思い巡らして愉しんだ。旅をしなくちゃ。初心に返るきっかけをいただきました。ありがとう!
◆延江さんからは、現地の人々や土地への深い愛が伝わってきた。湧きあがった熱い想いに素直に行動。直感を疑わず、正直に生きてこられた素敵な方だ。お手本にしたい。そうだ! 振り返ってみると、迷いがない時は必ず上手くいく。進学のための上京、勤めを辞めての長期旅行、染織の専門学校入学、帰郷と染織活動。いくつかの決断と、流れに身を任せることの繰り返しで歩んできた。そして今は、実家の片づけに手こずりながら、これからの人生を共にする相棒くんとの暮らしについて思いを馳せている。
◆延江さんとはたぶん同世代。また、お話できる機会がありますように。そして現在、日本人にインドビザは発給されていない。一日でも早く戻れるように願っています。(山の麓から海の近くに移住予定 中畑朋子)
■江本さん、まず、人をその気にさせる会話術に感心いたします(こうして地平線通信に感想を書くことになったのですから)。そして、通信の次回報告会の報告者の風貌を描いた絵は毎回感心しきり、しています。けど、今回会場で語る延江シスターは絵よりもずっとずっと可愛く、生き生きしておられた。
◆そしてスライドを動かしながら語る延江シスターの愛情に満ちた口調。スライドに写し出される作為のない人々の表情。赤ちゃんをおぶう子供の、幼くして生きる大変さを知った眼、唄いながら田植えする女性たちの穏やかな、辛い労働の中の喜び。人生を表すようなくねった小川の流れ……。部落ごとに違う美しい絵柄の織物。……みんなそれぞれが素敵だけど多種の顔つきの部族のそれぞれに似合っているように見える。そして、その美しい織物を搾取的に(とシスターはおっしゃった、と聞こえた)に売る商人の、ちょっとズルそうな眼……。
◆話は私ごとになりますが、東京から秩父に来て30年。その時近所から働き者の奥さんが手伝いに来てくれたのですが、日毎収穫物を下げてきてくれ、我が家の小さな庭に台所からの生ゴミをうめ、雨どいから水を集め、周りから石を運び、素朴な花をつける野菜畑を作ってくれました。おまけにです! 月末の支払い時に渡した金額が「私はこんなに働いていない」と、余分を返してきました。畑仕事をしている時の、自然の中にいる時の、彼女の表情の美しさにうっとりしたことを思い出します。彼女は「両神」という「山奥出身者」でした。
◆スライドを見ながら自然と共に生きる表情に同じ美しさを見ました。車を脱輪させて往生していると前の家のオジサンが近所の男たちを集めて救ってくれましたっけ。
◆シスターも最後に語られたように、そんな自然の中に、質素ながら心豊かに生きる暮らしぶりも変わってきました。会場を後にしながら「私たちとこの奇跡の星、地球はどこに行くのだろう……」と、四角いビルとアスファルトの道を歩きながら頭をよぎる思いでした。それでも帰り道をたずねた方の親切なこと! ちょっと感動して、嬉しくなって「そう簡単には自然と人の心は壊れない、再生する」と思い、願い、祈りました。シスターからミッションのこと、教育のこと、沢山まだ伺いたいです。30年前、東京育ちが山里に移り、自然に生かされつつ教えられつつ。(斉藤宏子 1981年11月27日、第25回地平線報告会で「へのかっぱ号の漂流」という話をしてくれた故斉藤実さん夫人)
■はじめて参加した地平線報告会は、自分にとっては最高の報告会だった。スピーカーはインド北東部で医療活動に長年従事する、カトリック修道会シスターの延江由美子さん。新型コロナウィルスの感染拡大が日々報じられていたなか、会場の新宿スポーツセンター会議室には50人近い聴衆が詰めかけた。
◆ぼくはインドをメインとする南アジア研究者で、数年前からインパール作戦、それに現地の歴史や文化をテーマに調査を進めている。ちょうど年末マニプル州に滞在し、インパールを拠点に州内各地をまわってきたばかりだった。帰国後に自分の担当編集者から「笠井さん、こんな報告会がありますよ」と教えてもらったのが2月の地平線報告会だった。案内文の「インド北東部」「ナガ族」「納豆」といった言葉にぼくの心は躍った。締め切りが迫る原稿を抱えていたが、「これだけはなんとしてでも行かねば」と思い、会場に足を運んだ。
◆延江さんが語るメーガーラヤやアッサム、ナガランドの村々の話は、現場で人びとと直接関わってきた方ならではのリアリティに満ちあふれていた。各地で撮りためてきた写真や動画からも、彼女がいかに現地に溶け込んでいるかが伝わってきた。きっと一枚一枚に短い時間では語り尽くせないストーリーがあるのだろう。鍼やマッサージを通じて難病に悩む人びとを助けてきたとのことだったが、それだって現地の人びとと関係を築き、信頼を得るまでには並大抵ではない努力はあったのではないかと想像した。
◆時間の関係もあり簡単に触れるにとどまっていたが、納豆をめぐる話も興味深かった。インド北東部の納豆はぼくの調査テーマのひとつでもあり、インパールでは現地の家庭で納豆料理をふるまってもらったり、商品化されているドライ納豆を入手したりしていた。延江さんがスライドで見せてくれたナガ族の納豆はペースト状に近い感じで、日本の納豆のような粒状のもの以外にもさまざまな食べ方があることがわかった。北東部の納豆だけでも1回分の報告会になるくらいの深さと広がりを持っていると思う。
◆もちろん、明るい話ばかりというわけではない。ひとつは民族間の対立だ。メーガーラヤでは、母系制のガロ族のなかにはムスリムと結婚する女性も増えてきており、そうすると改宗するだけではなく財産をめぐる問題も生じているという。また、ガロは魚や野菜をとることはできても販売は不得手で、その部分はベンガル人やビハール人が担っているという話も、現地の経済構造の一端を垣間見た気がした。近年、反政府武装勢力の活動は沈静化していると聞いてはいたが、たとえばナガランドの組織は存続しており、まだ予断を許さない状況だということも伝わってきた。
◆延江さんの背後には、彼女が持参した北東部各地のカラフルな織物が何種類も掛けられており、文字通り彩りを添えていた。終了後に実際に手に取ってみたり羽織らせてもらったりしたが、赤と黒が基調のナガ族のものが印象的で、寒冷な季節もある高地に住む彼らにとって厚手で防寒にもなるという話にも納得だった。
◆参加前に読んだ『地平線通信』の次回報告会予告で、もうひとつ目にとまった文章があった。「高3の時に一年留学したアメリカで……」のくだり。四半世紀以上前のことになるが、ぼくも高2のときにAFSという国際団体を通じてアメリカに1年留学した経験があった。休憩時に延江さんとお話しした際に尋ねてみると、「わたしもAFSです」とのお答え。やはり! このところあちこちでAFS留学経験者に出会う機会が続いていたが、インド北東部がらみでもそれが起こるとは。時期もアメリカ国内の派遣先も違うが、高校留学という共通の体験で一気に親近感が高まった。
◆気がつけば時計の針は午後9時半を指していた。もう3時間も経ったの?と驚くほど濃密な内容だった。恒例という二次会で「延長戦」をしていただきたかったが、今回は中止になってしまったのが残念でならない。延江さんの話を聞いて、予定していた次のナガランド訪問を前倒していますぐにでも現地に行きたい気持ちになった。しかし、そんな最中に新型コロナの影響でインド政府が日本を含む感染拡大国からの入国を制限する措置を発表。当面のあいだ、一部のケースをのぞきインド渡航は不可能になった。この状況が一日も早く収束し、ふたたび北東部の地を踏めるのを願っている。(笠井亮平)
■無事にネパールドルポ越冬から下山できました! 感想をお伝えする前に今のコロナウィルスのネパールの状況をお伝えします。カトマンズのタメル(旅行者が集まるところ)では、観光客は少なく、これから山登りやトレッキングシーズンが始まりますが、キャンセルが続いてるようです。ネパール政府は5か国の国籍者(日本、中国、韓国、イラン、イタリア)に対し、ネパール入国の際、健康証明書の提出を求めるとの情報があります。3月10日以降は既にビザを持っていても同じくです。
◆これは事実上入国するには厳しい状況です。カトマンズはもともと空気が悪くマスク着用は日常でコロナの影響はわかりづらいけど、日本料理店のスタッフやお客さん(ネパール人)は、マスクを着用している所がありました。越冬の感想を一言でお伝えすると、天国にいるような次元の違う世界にいたような気がしています。降りてきた時は、下界の感触がありました。
◆ドルポは、東西南北どこから入ろうとも5000mの峠を越えないと入れない、平均高度4000mに村が点在する。私は2019年11月中旬から雪が降り積もる前に入りこみ、越冬計画をたてた。2003年から河口慧海師の足跡を個人的に辿りはじめ、最終的に河口慧海プロジェクトの故大西保隊長との出逢いでドルポに辿りつき、これまでに4度に渡って内部を横断した。それは夏から秋にかけてのベストシーズンで夏は高山植物で溢れ、秋の収穫時には黄金に輝くかのような大麦に目を奪われる。
◆更に、木が少ないドルポにも紅葉があり、草の赤色で山肌を染めそこに太陽の光がさし色気を感じるほどの美しさに驚き思わず足が止まる。冬、この地はどうなっているのか? 厳しい環境の中、厳冬期の生活はどうしてるのか? 山々はどんな景色を見せてくれるのだろうか? 気になって仕方がなかった。自分の目で肌で足で体感したい。そして、その3年後の2019年の冬、ようやく計画を実行した。
◆今回は、クラウドファンディングの力を借り、更にそれ以外からのご支援、応援が沢山あり、自分でも驚くほど資金が集まり借金覚悟の遠征が皆様のおかげで準備ができた。この場をお借りして本当にありがとうございますと、お伝えさせて頂きたい。まずドルポの何が知りたいか質問のリストを作り、出会う人にガイドの通訳を挟んで聞いていく。
◆しかし、しょっぱなからガイドに「いきなり聞きすぎだよ、そんなこと聞いたら失礼になる」などと言われ、私は「本当にドルポが好きで知りたいだけなんだけど、確かに根掘り葉掘り聞かれたら失礼だな」と自分でも思い、どうしたらいいのかわからなくなり戸惑う。今回持参した本『ヒマラヤ巡礼』(ディヴィット・スネグローブ著)の中に、目に止まった言葉があった。「常に大切なのは、じっくり落ち着いた観察とせっかちに知ることを急がないことだろう」と書いていた。これは辺境地での心構えだと実感し焦りがなくなった。
◆すると毎日少しずつ出会った人から様々な話を聞けるチャンスがやってきた。知りたいのはローカルの冬の生活や雪の状況。お金のある人達は暖かい地域、カトマンズやインドに行くという。しかしローカルは、ほぼドルポ内部にいて、「ここではお金をあまり使わないからいい生活だよ」と誰もが言っていた。現に私は3か月分の食料や燃料を持参したが、頂きものは多かった。
◆質問リストは42個となり、その中で1番印象に残ったのはやはり冬のプジャ(法要)。3日間に渡り行われ凄い風がきつく寒い日だったのに外で五体投地が行われていて、その姿には深い祈りを感じた。信じる力が人を美しく強くさせる、これは16年前初めてチベット文化圏に行った時思ったこと、今回久々に同じ事を感じた。みんな何を祈ってる? 聞いてみたら、村、家族、畑の事、そしてみんなの幸せと言っていた。
◆2012年ドルポで行われた12年に1度のシェー大祭では来世と言う言葉が出てきてたけど、今回は違ったのが印象的。しかし現代にこんなにも深い祈りの世界観があるってことがやっぱり凄いなと思った。読経してマニ車グルグル回して、ほんとに世界中に読経が広がっていく感じがした。そして環境が厳しいほど、人は自然に近づき動物的になる。
◆ドルポに住む人々は、チャングラー(標高の高い所に住むヤギ)のようだった。寒さに強く驚くような急な山路を駆け下り、太陽と月のリズムで生活をし、その中に祈りがある。少ない食料と燃料をみんなで分け合い助け合いながら生きている。そして誰もがラマ(僧侶)のように本当に優しかった。言葉がわからなくても私の動きを見て、寒そうにしてたら膝掛けをくれたり、接し方がすごく心の中に残っている。最後のお別れの時は何度も涙を流してくれた人もいた。下山は雪で一日停滞したが10日間歩いて無事に到着した。また会いたい人達ができてドルポがさらに好きになった。(稲葉香)
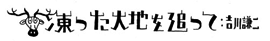
■やはり厳冬のアラスカは美しい。枝先までびっしりつまった氷の結晶(樹霜)と積もった雪がタイガの森を覆い、寒ければ寒いほど美しくなるから不思議だ。この冬しばらく留守にしたので、トナカイ達を戻すまで準備がちょっと大変だ。1マイルある私道の除雪から始める。膝ぐらいまでの積雪は、平地では難なく除雪できたが、上り坂は無理だった。
◆勢いをつけた5トンの除雪トラックが雪を押し切れず横滑り、派手に回転して路肩にハマる。−35℃の気温では明日ディーゼルエンジンはかからないだろうから今日中に脱出する必要がある。寒いところでエンジンをかけるのは簡単ではない。シベリアでは、夜は暖かい車庫に入れ、外に出たら一切エンジンは止めない。フロントガラスやその他のすべてのガラスをガムテープで2重にする。
◆フロントガラスを2重にすると凄い断熱効果だが、3台の対向車が6台に見えるとか、曇ったらどうにもできないとか若干の問題はある。窓が開けられなくなるのもちょっと不便だ。アラスカでは、エンジンオイルヒーターと冷却水のブロックヒーターをつけて交流電気で暖める。そのためのコンセントがフロントグリルから飛び出ている。
◆最近の4サイクルスノーモビルもこの方式にするしかない構造なので、7年前アラスカから大西洋(イカルイット)までのスノーモビル旅行をした時には発電機は必携だった。それでもガソリン車は、比較的簡単にスタートしてくれるが、ディーゼルは大変だ。燃料自体が寒くなると粘性を増してきて、噴気してくれなくなる。そんな時は面倒だが払い下げパラシュートで車を包み、ストーブの熱をエンジンの真下にくるようにして、3時間ぐらいかけて車ごと南国にするしかない。
◆さて、はまったトラックをどうやって道に戻すか? 一人では大変なので、デッチダイバーだったジョンを呼ぶ。ここでいうデッチダイビングとは、まだ娯楽のあまりない70年代冬のアラスカで車を派手に路肩に突っ込み、救出して遊ぶ車好きの若者のゲームのことである。ジョンとは20年来の付き合いで、金属加工工場を経営している。この工場で幾多の伝説の凍土用ドリルビットが完成した。研究者としてフィールドでやって行くには、その裏で無理難題の武器を作ってくれる職人なしでは決してうまくいかない。
◆仕事が終わったジョンが数々の脱出用の道具を携え登場してくれた。月夜が幸いし、3時間ほどで脱出に成功する。気温は−40℃近くまで下がってきた。日本にいると−30℃も−50℃も変わらないと思うだろうが、実は全く違う。−30℃までは、ガソリン車は暖めなくても運が良ければスタートする。−40℃では何もかも脆くなる。シャボン玉が凍って壊れなくなったり、お湯を投げると爆弾のようにすぐに蒸発したりするのもこのへんからだ。
◆ただ人間の温度感覚は相対的なので、−50℃で生活していて−40℃になると気分は天国だ。以前シベリア北部でトナカイ旅行をしている時、連日−50℃〜−60℃で辛かったが何が辛いといえば、毎朝放牧したトナカイを集めて、ソリの出発準備をするのだけど、どうしても集められない時があった。トナカイだって重い荷を引くよりは、地衣を気ままに食べていた方がいいに決まっている。昼までに集めきれなければ、諦めて明日の朝にしようという事になった。
◆結局−60℃の中でまた連泊する羽目に。明日だって集まる確信はない。落ち込んだその夜−45℃まで暖かくなった時には、気分も晴れ、鼻歌交じりで星を見ながら用を足したものだ。ところで−45℃になると車のショックアブソーバーが効かなくなる。車を運転していてガタガタ音がして、揺れが吸収されなくなったら、外は−45℃だ。そのあたりでスクールバスも危なくなるので、運転を中止する。アラスカではそれが寒さで休校になる境界だ。
◆ロシアのヤクーチアでは−45℃で低学年、−50℃で高校までの全校休校となる。以前コリマ川水系を札幌ナンバーのランドクルーザーで穴掘りと学校周りをしていた時、寒くて学校がどこも休校になり授業にならなかった事があった。ある深雪の峠で吹雪いたので朝まで待つことにしたら、その夜にロシア大統領にもこのことが知れてしまい、ロシア緊急事態省に連絡が行き、ロシア、日本を始め、中南米までニュースが駆け巡ってしまった。
◆翌朝村に普通に降りて、私もニュースに驚いたが、しばらくはこの話題で持ちきりになり、サインを求められる始末。ロシアでは、トヨタが密かにシベリアで極寒冷地テストをしているという噂になり、ランドクルーザーの次期モデルはすごい事になるぞとインターネット上で盛り上がっていた。わざわざ寒い時に旅するのは、冬道を使って僻地へ行くからだ。冬は、ツンドラや湖沼、河川が道に変わり、その間に1年分の物資を運び込む。春が近づくとこの便利な冬道をいつまで使うか? 結局毎春誰かが落ちるまで使うことになる。(吉川謙二)
2011年から始まったシリア内戦から9年。シリア情勢はますます複雑化し、収束の気配が見えない。国外に逃れたシリア難民は約560万人(2020年現在)にのぼり、そのうち最も多くのシリア難民が避難生活を送るのがトルコだ。トルコには約370万人のシリア難民が暮らし、その多くが南部に集中している。
2019年11月から2020年1月にかけ、トルコ南部を訪れ、高原都市オスマニエ、シリア国境の街レイハンル、アクチャカレでシリア難民の取材を行った。シリア人の私の夫の家族も難民としてこの地に暮らしていることから、こうしたネットワークにサポートをいただきながら、子供を連れての訪問だった。
ひとくちに「シリア難民」と言っても、それぞれが抱える背景は実に多様で複雑で、シリア人が異郷の地でどのように生きていくのか、一人一人の物語から見つめている。このトルコ南部で、2015年、2018年、2019年と継続して取材を行ってきた。シリア難民の状況は依然厳しいままだ。仕事が見つからない、見つかっても非常に低収入、トルコ社会での立場が弱く差別を受けるなどの問題を抱え、ほとんどの難民は生活維持が困難だ。
シリアでの戦闘や空爆に遭い、障がいや傷病を負った難民も多く、そうした人々への生活支援、医療ケアも大きな課題だ。それでも難民の家族には年々子供が生まれ、若者層はトルコ語を学び、小さな変革を繰り返しながら、若い世代から着々と、シリア人はトルコ社会に馴染んでいる。
2015年の取材時、ほとんどのシリア難民がトルコに来たばかりで、安全な土地に逃れた安心感と、これからの生活への希望に満ちていた。人々は“サナルジャー”(アラビア語で“みんなでシリアに帰ろう”)という言葉を合言葉のように繰り返していた。
この頃、人々は、難民としての暮らしが長期化するとは考えておらず、シリア情勢が安定化したならすぐにでも帰れると固く信じていた。そのため、冷蔵庫や洗濯機などの大型家電を買わず、移動に備えて生活を身軽にする家族も多かった。
しかしシリア情勢は悪化の一途を辿り、2013年頃からは大量のシリア難民がトルコ南部に押し寄せた。さらに2014年頃からシリア北部を過激派組織ISが占領すると、情勢はますます混迷した。トルコ南部で避難生活を送るシリア人は、次第に“シリア帰還”の夢が、遠い先のことだと理解していった。
2018年の取材では、避難生活に失望する多くの難民の姿があった。仕事が見つからず、困窮し続ける生活、終わりが見えないシリア情勢に人々は疲労を重ねていた。2015年の取材で満面の笑みで迎えてくれた女性が、2018年にはノイローゼとなり、表情なく虚ろな目で写真に映っていたこともあった。だが一方で、新しい土地に根付くための努力が盛んに行われ、家や土地を購入し、慣れない仕事を探してトルコ社会に生きる方法を模索する姿が目立った。
また2016年から、全てのシリア人の子供がトルコの公立学校に入学を許可され、シリア人の子供はトルコ人の子供と混ざってトルコ語の教育を受けている。こうした子供たちからトルコ社会への定着化が図られている一方、シリア人の子供がアラビア語を学ぶ場は家庭内に限られ、アラビア語の読み書きができない子供も増えている。今後、シリア人がどのように文化を継承していくのかが課題となるだろう。
2019年の取材は、シリア北部のクルド人支配地域をトルコ軍が攻撃するという状況下ではあったが、それぞれの街にシリア人が独自のコミュニティを形成し、その恩恵を受けながら、助け合って自立に向かう姿があった。人々はスマートフォンでSNS上にシリア人グループを作り、困りごとの相談や、薬品や衣類、食料の提供、ときに結婚相手も探していた。
取材先の家族に、次々と子供が生まれていたのも嬉しい出来事だった。生活は厳しくとも、子供を産み、育てていくことが幸福なのだ。暮らしは依然厳しいままだが、年々、取材先の家族の表情は生き生きとしたものに感じられる。年月を積むごとに、人々は異郷に生きる覚悟を決め、その上に新しい価値を築こうとしている。
また2015年頃は、同じシリア人の間に政治的な分断も多く見られたが、2018年以降、より共存に近い形に向かっているのを感じた。シリアでの政治観の違い、立場の違いで以前は衝突しあった人々も、異なる文化の中で同じシリア人として結束する必要が生まれたのが理由のようだ。人は、共通して守るべきものが目の前にあれば、互いの立場の違い以上に、共通性を守ろうとするようなのだ。
女性の社会進出も年々進んでいる。一家の男手をシリアでの戦闘や空爆で失い、シングルマザーになった女性たちが多く、なかには生活のために再婚する女性もいるが、単身で子供を育てていく選択をする女性も少なくない。女性たちの働き口としては、服屋の店員、縫製工場の職人、掃除婦、トルコ人家庭のお手伝い、資源集めなどが多かった。
こうした女性の労働が増えるなかで、育児に対するシリア難民の考え方も、この数年間で急激に変わってきたように思う。シリアの地方都市では保育園、幼稚園があまり一般的ではなく、子供たちは小学校に入るまで家庭内で育てるのが普通だった。シリアは大家族が多く、家庭には大人も子供もわんさかいて、また女性たちも専業主婦がほとんどだったからだ。しかし難民生活によって核家族化が進んだこと、また働く女性が増えたことで、子供を日中に、保育園、幼稚園に預けるという文化が広がりを見せている。
今、シリア難民は“ふるさとへの帰還”以上に、“いかに新しい土地に根を張るか”、そして“ルーツをいかに伝えるか”という問題に意識を傾けている。
世の中はコロナウィルスで騒然としているが、こんな時だからこそ考えたい。私たちの日常はもろい均衡の上に築かれていること。そして私たちは何を守り、何を次世代に伝えようとしているのか。ふるさとを離れ、激動の日常で新しい変化を生きるシリア難民の姿に、考えさせられることは大きい。

■この度、第9回梅棹忠夫山と探検文学賞を、拙書『考える脚』での受賞が決まった。梅棹さんの名前を冠した賞を頂けるというのは、大変に光栄なことだと感じ、これから益々精進せねばと気が引き締まる思いだ。本書のタイトル「考える脚」であるが、説明するまでもなく、パスカルの「パンセ」にある有名な一節「人間は自然の中で最も弱い一本の葦に過ぎない。しかしそれは、考える葦である」を意識している。北極を歩く一人の人間はとても弱い存在である。しかし、人は考え、困難を克服することで可能性を広げてきた、そんな思いを込めている。
◆本書には、北極点無補給単独徒歩、カナダ〜グリーンランド単独行、南極点無補給単独徒歩の三つの遠征を収めている。三篇の遠征は、それぞれに私にとって主眼が異なっている。それらを書き分けることを最初に考えていた。最初の北極点は、とにかく過酷な極地遠征の実態だ。効率の最大化を図り、薄氷を踏みながら死の危険を感じつつ、ひたすら前進することに特化した遠征の全て。そして、撤退を決めるまでの心の動きを記録したかった。
◆次のカナダ〜グリーンランド単独行は、一転して北極圏の文化や野生動物、イヌイットとの交流など、土地の話を書こうと思った。最後の南極点は、資金集めや装備開発などを中心に、準備や社会との接点に関して書き進めた。つまり、最初は個人の遠征、次に自分自身を取り巻く環境としての北極、そして最後に極地遠征と社会との関係性という、極地冒険を基軸にして同心円状に広がりを持った一冊の記録としてまとめたつもりである。
◆そしてもう一つ意識したことは、本書が出版された2019年の極地冒険の最前線を書き留めておきたかった。冒険手法であるとか、社会状況、自然環境など、現場に足を運んでいる私でしか書き留めておけないことをまとめておく必要があると思っていた。それは、未来のためでもある。私自身、これまでの極地冒険の中では、過去の探検家たちの記録を多く参考にしてきた。手法の変遷や、極地に赴く探検家それぞれの意思と動機に至るまで、彼らの著作の中から読み取り、大きな流れの末端に自分自身が存在していることを実感しながら自らの旅を行なってきた。いま、私が書き記しておく記録を、いつか誰かが参考にしてくれて、この潮流を絶やさずにいてくれたら最大の喜びである。みさんも、ぜひお手に取っていただけたら嬉しいです。読んでくださいね!(荻田泰永)
先月、娘の柚妃が国語の授業の一環で、荻田泰永さんにインタビューさせていただくことになり、神奈川県大和市にある冒険研究所を訪れた。その際持参した著書にサインしてもらったのが『考える脚』だ。
『考える脚』は前著『北極男』ほどわかりやすくない。本書を読みながら、何度も唸らせられた。思索が深いのだ。『北極男』以来、どこでどんな冒険をしたのか、叶わなかった北極点無補給単独徒歩のその後はどうなったか、とわくわくした気持ちで冒険譚を読み始めたはずだった。しかし「北極点無補給単独徒歩の挑戦」、「カナダ〜グリーンランド単独行」、「南極点無補給単独徒歩」という三度の冒険は臨場感を持ってすんなり頭に入ってくるのに、冒険というものについて考えるとき、荻田さんは深い潜考の海に沈んでいってしまい、途端に本書は哲学的要素に満たされる。
「俺は、北極点無補給単独徒歩を、余裕でゴールしたいのだ。今回は、違う。これで終わらせてはいけない。這いつくばるように、ギリギリで北極点に立つことは、美しくない」。
この結論を出すまでにさんざん逡巡して、なぜそう考えるのかについて更に考え、結論が出た後もクヨクヨしたりしている。次の年になってもまだ考えて、その時の自分の心の動きを深く考察し、分析する。
荻田さんにとっての極地冒険は、「自分にとっての幸福感」を追い求めることだ。幸福感とは何か。やるべきこと、やりたいこと、できることの三つが一致した人生のことだ。
北極点到達が成功しなかった原因を、自分の能力と北極海の状況から認識し、北極海をより深く理解できたという。この時に北極海を想像の範囲内に収めたことで北極点無補給単独徒歩は「できること」になり、同時に未知性を失ったことで「やりたいこと」ではなくなったのだ。荻田さんは記録樹立にも世間の称賛にも興味はない。「やるべきこと」ではないということだろう。それらは荻田さんの幸福感を満たすものではないのだ。読者としては、北極点に対する新たな情熱を持てるような未知の要素が今後現れるのかが気に掛かるところだが、三度目の挑戦をすることは、もしかしたらないのかもしれない。
荻田さんは資金の集め方にも信念があり、その考え方と行動にはまったくブレがない。荻田さんを広告価値でしか判断しない代理店や、単に自社にとってのメリットを要求するスポンサーは欲していない。あくまでも人間性、そして活動内容に賛同してくれる人や企業から支援してほしい、それには地道に自分の脚で歩いて探すことが必要だと考えている。そんな中でたまに出会う、荻田さんに興味を持ち応援してくれる人は大切だ。たとえ冒険の資金集めに直接つながらなくても、理解して仲間になってくれるだけでも力になるのだ。
南極行を前にどうしても資金が不足し、カナダ〜グリーンランド単独行でカメラ機材の提供をしてくれたパナソニックに、お金の援助をお願いしに行った。ところが、その時の担当である岡さんは、荻田さんが話を切り出す前に、グローバルマーケティング用の広告への起用をあらかじめ社内に通してくれていた。岡さんが、これまでに広告製作を通して知った新しいことにチャレンジする苦労や、人に救われる心強さを実感していたからこそ、南極点無補給単独徒歩という新しい挑戦、そして荻田泰永という冒険家に惚れ込んで支援につなげてくれたのだと思う。岡さんもまた、信念を持って荻田さんの広告起用にチャレンジした人なのだ。
国籍も専門も異なる4人のカメラマンが、それぞれの活動のフィールドの中で必要になる機能を備えたカメラを使いさらなる高みを目指す、という海外向けの広告企画だ。ピューリッツァー賞を二度受賞しているフォトジャーナリスト、中国のパンダクラブ、火山フォトグラファーと並び、極地冒険家・荻田泰永がこれでもかというほど格好よく起用されている。軽量で画質がよくビデオとスチールを1台に備えたそのカメラで撮った写真の数々は、精彩を放ち圧倒的な力で見るものに感動を与える。これは広告出演を依頼した企業側と、出演料をもらって南極点に行けた荻田さん双方が、互いに遜色なく大切なものを手にできた素晴らしい成功例だと思う。
私は、荻田泰永という冒険家に信頼を寄せている。極地冒険に出るたびに、装備にしろナビゲーションにしろ、とにかく突き詰めて考え納得できる答えを得た上で行動しているからだ。そして20年分の積み上げた答えが確信となり、根拠のある自信につながっている。自信は力だ。大場満郎さんとの運命的な出会いがかつての荻田青年を北極にいざなったように、その力で若者を北極圏に連れて行ったり、小学6年生と100マイルの冒険旅行を一緒に歩いたりしている。そうすることが、これまでの自己満足だった冒険に意味や価値を生み出すのだそうだ。私は、荻田さんが経験で得た力を若者に還元しなくても、とっくに意味も価値もあると思っている。だけどそうしてくれることで、若者は渇望感を満たされ、小学生は思いもおよばなかったすごいことを成し遂げられるのだ。
荻田さんは考える冒険家だ。冒険しながら哲学的考察をする。冒険がタフであればあるほど考察が深まっていく。自問を繰り返しても答えが見つからないこともある。導き出した答えに後悔することもある。しかし冒険について考えることが冒険と無謀とを分ける備えとなり、冒険そのものに意味を与えるのだ。(瀧本千穂子)
■先月の通信でお知らせして以降、通信費(1年2000円)を払ってくださった方は以下の方々です。数年分まとめて払ってくださった方もいます。地平線会議の活動は皆さん1人1人の志で支えられています。お礼を1円も払えないのに素晴らしい報告会をやってくれ、原稿料0でも最高の原稿やイラストを書いてくれ、なんの見返りもないのに毎月この通信の印刷や封入仕事にあたり、報告会の受付に座ってくれる方々の志に応えるためにも、通信費というかたちの志は大きいのです。万一、掲載もれありましたら必ず江本宛て連絡ください。
福原安栄(本年度通信費として送金いたします。長い年月、貴通信からエネルギーをいただいており、御礼申しあげます)/中岡久(5000円 通信費+カンパ)/岡村真(35年前、高校生のときに三輪先生に宛名貼りの手伝いをさせられていました)/西嶋錬太郎(3000円 1000円はカンパ)/中村鐵太郎(チヘイセンツウシンアリガトウゴザイマス)/一柳百(10000円 ツウシンヒ タイノウ シツレイシタ イチヤナギ)/辻野由喜/平本達彦/寺沢玲子(10000円 5年分)/田中明美(5000円 3000円はカンパ)/日野和子/横内宏美
■3月8日現在、世界中に蔓延拡大を続け、未だ終息の行方が見えないコロナウイルスだが、いまや世界中から称賛を受けている台湾政府の感染対策のことを皆さんはご存知だろうか。僕は以前台湾で居留証を発行してもらった経緯があり、ウイルス発生から毎日のように日本台湾交流協会発行の「在留邦人への喚起メール」が届くため、日本に居ながらも台湾政府の動向を把握することができていた。
◆台湾政府の初動の速さで際立ったのは、1月26日から中国湖北省、2月6日から中国本土からの入国禁止措置と学校関連の冬休みの2週間の延長措置(小学生の保護者には看護休暇申請措置も。現在は、教職員や生徒で感染者が1人出れば学級閉鎖、2人以上なら学校閉鎖するという基準を設け、授業を再開している)だった。台湾は中国大陸との距離が近く、人的往来も多い。その判断に一切の躊躇は無かった。
◆何故こんなにも迅速な決断が出来たのか。それは2003年のSARSで大きな被害を受けた(73名もの死者が出た)経験があるからだ。加えて、台湾の政治家の多くに医学出身者が多い(現副総統は伝染病の専門家)ことも特筆される。もちろん、今年1月に行われた総統選挙で親中派の国民党ではなく、民進党が政権を維持したことも大きいと考えられる。
◆どの国であっても国難級の有事の際には与野党問わず最善の国防措置を取るのが前提だ。現在台湾の医療は世界的に高い水準を維持しているにもかかわらず、国連に加盟出来ない故にWHOからは冷遇されている。そんな中で国内でできることは全て実行するという姿勢を貫いた。国外に対しても、ある台湾医師はコロナ感染患者のレントゲン写真を世界にいち早く公表した。このような有益かつ迅速な情報開示は世界中の医師にとってどんなにありがたいことだろう。その一方で、世界を牽引すべきWHOが見せた中国を忖度するかのようなこの度の挙動は世界中にある種の失望感を与えてしまっているように感じる。
◆僕自身、当初の日本の水際対策に関しては失望しつつも、「日本政府なりにも苦渋の決断には慎重にならざるを得ないだろうけど、然るべきタイミングでビシッと何らかの対策を打ってくれるっしょ!」との希望を抱いていた。しかし、連日のダイヤモンド・プリンセス号関連報道、政府への責任追及や政府対応への生活者の不満、買い占めなど不安を煽るかのようなワイドショーを横目に、台湾の友人からは「日本大丈夫……?」的なメッセージがたくさん届いていた。次第に今回のコロナ騒動に関する日本政府、メディア、国民の全ての危機意識は台湾とはかなりの温度差があることを痛感せずにはいられなかった。現に日本政府の一連の対応発表は後手に回っているという専門家の指摘があるが、タイミングを見てどう考えても、その殆どがWHOからの情報を最優先に過信した結果のように映るのだった。
◆新型ウイルスの驚異の一つに、無知から来る恐怖感が挙げられるが、台湾政府の緊急記者会見は毎日のように逐一行われ、全ての情報を包み隠さず公表していることこそが国民に安心感を与えている。日本でマスクが品切れになり、転売問題が発生するよりも前に、台湾では政府が大量のマスクを買い上げて、健康保険証の末尾ナンバー奇数偶数による振り分け販売を実施し、決して多くはないが全ての人が確実に購入できるシステムを確立させた。
◆この保険証に付随するICチップにより海外渡航履歴や治療履歴が分かるので、隔離などからは逃れられない程の厳しい国民管理も実施されている。混乱を防ぐため、感染者の移動ルートやマスク販売店の在庫が一目で確認できる携帯アプリ各種がその都度発明されて活用されていくスピード感には驚かされた。
◆SNS上のデマ情報への注意喚起も怠っていない。今現在も台湾における45名の感染者の感染ルートは全て把握され、アンダーコントロールと言える状況だ。蔡英文総統をリーダーとした官僚や専門家達(台湾にはアメリカのようなCDC疾病対策センターも設置されている)のチームワークは素晴らしく、その対応力の高さが民衆の琴線に触れ、総統の支持率が軒並み上昇中なのも頷ける。
◆今回の防疫で台湾人が得た最大の心情とは何か。それは国家が国民を確実に守ってくれるという信頼感の享受ではないか。この10年間、僕が台湾とそれなりに関わってゆく中で常々、肌感覚で「凄いなぁ」と感心させられる心情があった。無理矢理言葉にすると、「人間として当たり前のことを当たり前に行える」ことなんだと感じている。それは日常生活の中での思いやりや助け合いの精神だったり、国難に対する瞬時の決断力や政府と民衆が想いを一つにする一体感に表れている。
◆この点、今の日本ではそのようなポジティブな一体感がなく、あまりにもボンヤリとし過ぎているように感じてしまう。かつての東日本大震災では様々な場面で素晴らしい結束感を共有していた記憶を皆んな忘れてしまったのだろうか。この度の台湾の防疫対策から日本が学ぶべきことは多い。今からでも遅くないので、国と国民が団結して当たり前のことを実践してゆきたいと切に思う。(車谷建太)
■地平線通信490号(2020年2月号)は、2月12日に印刷、封入作業を行い翌13日、新宿局にわたしました。かけつけてくれたのは、以下の皆さんです。「北京」ではウィルス問題など当面のいろいろについて相談に乗ってくれました。ありがたいことです。
森井祐介 車谷建太 中嶋敦子 久保田賢次 兵藤渉 江本嘉伸 光菅修 武田力 八木和美
撮影20年の集大成となる写真集『ノースウッズ 生命を与える大地』(クレヴィス)の刊行、そして、東京ミッドタウンにあるフジフイルム スクエアでの初めての大規模な個展。これまでの写真家人生で、最も大きな節目となるイベントを終えた感想を、このような状況下で書くことになろうとは、昨年末の報告会の時には全く想像できなかった。
年が明けて新型コロナウイルスのニュースを目にするようになって、少し嫌な予感がした。2月初旬、札幌雪まつりの最中に、石狩の工場で写真集の印刷立ち合いをしている時にはすでに、周囲に不穏な空気が満ちていた。そして、ついにコロナの嵐は、写真展初日と写真集発売日を直撃。満席となっていたトークイベントは前々日に中止され、さらに勢いは衰えることなく、一週間の会期を残して写真展も突然の終了……。来る予定だった全員に連絡する術もなく、楽しみにしてくれていた人の何割が、あのプリントを見ることができたのだろうかと思うと、残念の一言ではとても伝えきれない悔しさがある。それは準備に関わった全員の気持ちだ。
今回ぼくがとても楽しみにしていたのは、自分が育った世田谷区の小・中学生たちの来場だった。地元出身の作家ということで世田谷文学館と一緒に芦花小学校でのワークショップを10年近く続けている。それに加えて、区内図書館での読み聞かせや、生涯学習センターでの講師などの実績が認められ、この写真展は世田谷区教育委員会の後援を受けて、区内の全小・中学生にチラシを配ることができた。その数、約4万5千人。自分ですら未体験だった横幅2メートルを超える大型銀塩プリントを見てもらい、遠い北米の自然や野生動物を写した作品の感想を聞きたかった。もちろん何人かの生徒は来てくれたが、「友達と来なかったの?」と聞くと、そばにいた親御さんから一言、「誘いづらい雰囲気なんです」と。それを聞いたとき、学校や家庭の現場では事態が想像以上に深刻であることを実感して悲しくなった。
写真展が明日で中止という報告があった時、動揺はまったくなかった。開始当初から予想できていたので、むしろ冷静に、「写真展の開催には感謝し、中止の決定は尊重するが、このまま終わったことにはしたくない」との希望を素直に伝えた。それを受けて、フジフイルムの方でも「落ち着いたらまた仕切り直して写真展をしましょう」と言ってくれたのは救いだった。
だが、現時点では、まだ再開の確証はない。そこで、もちろんその時までにウイルス拡散が収まっている場合に限るが、今回東京での展示を見たいと思っていた方は、たとえ遠方でも6/26からの大阪展に足を運んで欲しい(会場は富士フイルムフォトサロン大阪、会期は7/9まで。6/28は休館)。期待を裏切らないだけの準備はしてきた。さらに写真集もすでに書店に並んでいる。パネル展などのフェアも全国で始まっているので、見かけたらぜひ手にとってもらいたい。
中止になったとはいえ、オープニングトークの定員100人が募集開始1週間で埋まったことは確実に好印象を残すことができた。応募してくれた人々の思いは決して無駄になっていない。大阪展と写真集の評判次第では、東京での再開を、さらに大きな企画展にすることだって不可能ではないはずだ。この逆風をチャンスに変えるために、一人でも多くの人の力を貸して欲しいと切に願っている。(大竹英洋 2019年12月「北の森にオオカミを追って」報告者)
■勤め人ではないし、学校通いの子供もいない。だから、巷のコロナ騒動も、何となく遠くに感じてしまう。でも、せっかくだから流行に乗ってみるか。と、マスクを手作りした。ネット上には、キッチンペーパーやバンダナを流用した、芸のない製作方法が多数アップされているらしい。それじゃラクチンすぎるので、台所の三角コーナー用の不織布とネット、パン袋のタイ、だしパックなどを材料に、クリップシーラーを駆使し、手元にあった「超立体マスク」を複製してみた。オリジナリティーを重視する我が“後端技術”的には誇れる部分など何一つないが、誰もが「市販品と区別つかない」という出来映えだった。材料代は全部で5円。ヤフオクに出品すれば濡れ手に粟か!?
◆我々の周囲に氾濫している商品は、デッドエンドの完成品であると同時に、新たなモノの元となる資材だ。例えば、この使い捨てカイロ。使用後、酸素遮断に優れた外袋は食品の真空パックに、驚嘆するほど丈夫な内袋も、古い20年前の茶葉に詰め替えてヒートシール、靴の脱臭材に転用する。そんな目で周囲を眺めれば、マスク材料なんていくらでも見つかるし、トイレットロールがなくても、インド方式で凌げばよい。○○不足、◇◇不足で浮き足だつ人々を見ていると、我々が如何に飼い慣らされてしまっているかを、痛切に感じる。これって、一部の人たちの思うツボ? 今回の騒ぎだって、実はメディアが煽っているのでは? 何もかもひっくるめ、もっと冷静にならなくちゃ。他に伝えるべき、目を向けるべき大事なコトが沢山あるはず。コロナ一色に染まった世の中に、漠然とそんな不安を抱いている。(一字違いで回文にならぬ、マスクのクシマ)
■江本さん、ご無沙汰しております。この1〜2週間で一気に、新型コロナウィルスの感染防止を生活の最優先事項としなければならない(雰囲気の)日々となりましたね。コロナ影響とともに2月、3月は非日常の連続でした。74歳になる独居の母が大型の腫瘍摘出(結果良性でした)のため手術入院することとなり、私は思い切って介護休業を使って2週間の休みを取りました。
◆私の勤務先では介護休業取得はまだほとんど前例がないのに加え、ただでさえ子供(4、7、9才)のための時短勤務を取らせてもらっている身ですが会社は承諾してくれました。入院、退院後の介護生活(とは言っても“ごっこ”のレベルでしたが)にはそこまでコロナの影響は及んでいなかったのですが、1月末に入院準備の手伝いで上海から一時帰国した姉は翻弄されっぱなしでした。
◆当初数日間の滞在の予定が、中国への帰国を何度も延長、ようやく2月末に上海に戻り、今は現地で隔離生活をしています(ドアの前に置いておいてもらうだけの出前を取るにも許可がいるそうです)。私は職場復帰後、3月からテレワーク奨励で毎日在宅勤務、子供3名のうち小学生2名は休校で毎日弁当を持って学童保育に通っています。彼らには学童保育室の卒業式も控えていましたが、自治体からのお達しで保護者は観覧NG、無観客開催ならぬ無保護者開催となり、先生と子供たちだけで実施となりました。
◆3年間の集大成の式を見届けることができず、ただただ悔しい思いをかみしめるしかできませんでした。末子だけは普段と変わらず、保育園に預けていますが、各自持参した弁当を皆で集まって食べることがリスクになるとかで、楽しみにしていた遠足は遠出のお散歩に変更となりました。習い事も全てお休みになり、子どもは家でテレビかYouTubeをみるか、ゲームばかりという生活です。
◆“The Hu”という、世界で人気急上昇中のモンゴルのバンドの東京ライブが3月12日に予定されていて(私は発売日に即チケットを買ったのですが)、3月6日時点で「アーティストと開催の可否を協議中」とのアナウンスがありました。もし観に行けるなら、と一縷の望みをかけて感染対策用の物々しいゴーグル等も準備していましたが、密集密閉のライブハウスはやはり怖くもあり。主催者側から中止か延期を決めてくれるのが一番、気持ちは納得いきそうです。気持ちじゃなく、リスクで判断しなきゃいけないんですけどね……。
◆そんな状況下ではありますが私が強く感じるのは、今まで停滞していたもろもろのことがこの機会に一気に進んできてもいるのではないか、ということです。「感染防止対策」という名のもとで、拍子抜けするくらい、これまで放置されていたことがあっけなく進んでいるようにさえ見えます。従来、紙のプリントや校門への掲示だった小学校からの情報伝達手段もメールやウェブサイト上の掲載になりました。時差出勤や、会社の在宅ワークへの理解とインフラ整備が一気に進んで「もともと会社通勤する必要なかったんじゃないか」という声が多数聞こえます。
◆今まで当たり前だったことを少しグレードダウンや、いっそ、そぎ落としてもいいんじゃないかとも感じます。どのお店にもトイレットペーパーがない状況を見て、久々に昔モンゴルでやっていたみたいに10cm四方位の新聞紙1枚で拭いてみようかなとかも思いました。この非常事態下、翻弄されざるを得ないのは確かですが、自分たちの思考や行動のシフトチェンジも毎日試されている気がしてなりません。では、また。エモカレーもお願いします!(「40才になりました」三羽宏子 関野吉晴と遊牧民の少女プージェーとの交流を描いた映画「プージェー」翻訳者)
★追伸:3月9日の速報によると“The Hu”の東京と大阪のライブは延期となりました。手元にあるチケットはそのライブで有効だそうです!
■屋久島の小中高等学校は、3月2日から15日までが休校になっています。このままでいけば24日の卒業式、25日の終業式までに1週間ほどは子どもたちと過ごす時間が取れそうです。学習のまとめ、そして学級としての1年の締めくくりをどうしようかと日々考えています。
◆まだ鹿児島県内ではコロナウイルスの感染者は出ていませんが、状況次第では16日以降の休校もあり得ます。16日に学校が再開できたとしても、給食の管理や教室の消毒はどうするかなどまだ全く決まっていません。たぶん大丈夫と思いたいけれど、島は春の観光シーズンを迎えていて、春休みの学生をはじめ旅行者の出入りが増えています。100%安全とは言い切れない中で、ギリギリの判断を待つしかない状況です。
◆一番気がかりなのは、自宅待機になっている子どもたちの生活です。島の南部には学童保育所がないので、子どもたちは親や祖父母、兄弟たちと一緒にこの2週間を過ごしていますが、ストレスが溜まっている様子が窺えます。学校開放もしていますが、条件に当てはまる児童のみが対象なので利用は少ないです。何とかしてあげたいけれど、何もできずにもどかしい。1か月後には新年度が始まっています。全国の子どもたちが、安心して気持ちよく新しい1年のスタートを切れることを願います。(屋久島 新垣亜美)
■大相撲三月場所(大阪)は、新型コロナウイルスの影響で史上初の無観客開催となった。中継を見ていると、呼び出しの声がオペラ舞台のようにのびやかに響きわたり、約8千人の観客を失った場内はなんだか涼しそう。初日の取り組みを終えた力士に感想を聞いたら、「いつも以上に相撲に集中できた」という。関係者に1人でも感染者が出た時点で中止になるので、千秋楽まで全員が走り抜けられることを祈るばかりだ。
◆どの相撲部屋も関東に拠点があるため、地方場所に遠征するときはそれぞれ臨時の部屋を設ける。練習用の土俵も、土をトラックで運んできて毎回手づくりする。序ノ口は朝8時半頃から、幕下は午後1時頃から、幕内は4時頃からと、番付が上がるほど試合時間が遅くなり、力士は自分の出番にあわせて会場に入る。
◆今場所は公共交通機関ではなく、なるべくタクシーや車を使うという決まりだが、東京から大阪までの移動は恒例の「相撲列車」に乗ってきた。これは相撲協会が新幹線の一部を貸しきり、総勢200人ほどの力士や行司や床山が一緒に乗りこむもので、地方場所の風物詩になっている。しかし今場所は濃厚接触を避けるため、ファンとの交流もタニマチの激励会も自粛。静かな場所が無事に終わるとき、歓声のない土俵上でどんな優勝インタビューが行われるのだろう。
◆もしこれがモンゴルだったら、大相撲の開催なんてありえなかった。モンゴル政府は新型コロナウイルスの感染防止策として1月27日から3月末まで、多数が集まる芸術・文化・スポーツイベントや会議の開催を禁止しているのだ。1年でもっとも華やぐ2月24日の旧正月でさえ、「親戚や友人宅への挨拶まわりを控えて家族と祝いましょう」と、わざわざ大統領令が出た。
◆さらに同じ期間、国内すべての保育所・小・中・高校・大学・専門学校が休校になった。この間、小・中学校の授業はテレビ局とラジオ局が分担して放送し、大学の講義はインターネットで実施。生徒たちは自宅で学習している。2人の小学生のママである友人に「2か月間も学校がないなんて大変だね」と私が言うと、「そうね。でも怒ってもしょうがないね」とあっさり。彼女は会社を4週間休んでいるが、政府からの補償はない。別に期待もしていないらしい。
◆一番すごいと感じるのは、中国との接触をばっさりシャットアウトしたこと。1月末より中国国境が封鎖され、2月半ば以降は陸からも空からも人の出入りができない(物資の輸出入は可能)。トラック運転手の感染を防ぐため、石炭の輸出も一定期間停止。モンゴルにとって中国は輸出先の約9割を占めるお得意様だが、容赦なく締め出した。2月末以降は韓国、日本、イタリア、イランからの渡航者にも入国制限がかかっている。
◆私は3月にモンゴルへ行く予定だったが、やむなく日本で待機中。残念というより、こうなったら徹底的にやってほしい。モンゴルは中国と国境を5000kmも接していながら、国内で感染者をまだ1人も出していないのだから(3月9日現在)。大自然のなかで家畜と生きてきた草原の民は、未知の感染症の恐ろしさが身にしみている。非常事態に対する直感と行動力に長け、324万人しかいない国民を守るためには何でもする、という覚悟を感じる。
◆日本の場合は3月9日になってようやく、中国と韓国からの渡航者に14日間の自宅待機を求めるなど入国規制を強化した。なぜこんなに決断が遅くなったのか? 私が思う理由は、インバウンド特需への期待を捨てられなかったから、そしてオリンピックが控えているから、何より4月に習近平国家主席の国賓来日が計画されており中国に気を使ったから(結局来日は延期になったが)。
◆モンゴルは中国に後でしっぺ返しされないのだろうかと気になっていた矢先、2月27日にバトトルガ大統領が突然訪中したというニュースが飛びこんできた。中国への支援として羊3万匹や寄付金を贈ることを約束し、「コロナ騒動が発生して以来、最初に中国へ入った国家元首だ」と習主席や中国国民を喜ばせた。羊3万匹は約2億円分に相当する。国内の経済が不安定なのに、嫌中意識をもつモンゴル国民から反発が起きないのと現地の友人に尋ねると、「助け合いの心を届けたいから、うちの羊をどうぞって遊牧民たちが大統領にどんどん寄付しているよ」。一連の対応で株を上げたバトトルガ大統領は中国から帰国後、自ら14日間の隔離生活に入った。
◆モンゴル保健省が毎日国民に向けて行う記者会見を、オンライン中継で見るのが私の日課になっている。マスク姿(公の場で着用義務がある)の保健省職員が、世界の感染状況と国内の最新情報を報告する最中、チャット画面上にはこんなメッセージが次々に書きこまれる。「保健省の皆さんの素晴らしい仕事ぶりに感謝!」「医療従事者や警察官にもありがとう!」「昨日も感染者を出さずに乗りきった!」「モンゴル人よ頑張ろう、もう少しの辛抱だ!」。なんだか国全体が大きな壁に挑むアスリートのようだ。(大西夏奈子)
■極地の戦いという点で地平線通信でしか読めないドキュメントに皆さん、注目してくださいね。吉川謙二さんの連載「凍った大地を追って」。氷点下50℃と氷点下40℃の違いは、ほんとうに生命線の戦い、と言うべきものだ。吉川君、毎回ありがとう。■大西夏奈子さんの「今月の窓」とても興味深い内容だ。あのモンゴルがそこまで本気でコロナと戦っているとは驚きであり、みごとだと思う。実は、この直後(3月10日)についにモンゴルでもコロナ陽性が出てしまった。ただし、フランス人。以下、大西さんの続報。(江本嘉伸)
■ついに出てしまいました……ネット上で「こんなに頑張ってきたのに」「私たちの努力を返して!」とモンゴル人たちがめちゃくちゃ荒れています。コロナ陽性反応のフランス人は57歳男性で、鉱山関係会社の社員だそうです。ウラン採掘プロジェクトの担当者らしく、ウランに反対する感情もあおられて皆よけいに怒っています。この人の写真と名前もネット上で流れ、私の友人の女の子も「クソフランス人!」と罵倒しまくっています。
◆この人はロシア経由で飛行機でモンゴルに来たのですが、14日間の自宅待機を要請されていたのを無視して勝手に外出し、人に会っていたようです。警察はこのフランス人と接触した人々をすぐ見つけだし、彼らに検査をしてすぐ隔離しました。一部の人からは「外国人だから夜は売春だってあったかもしれないぞ。濃厚接触した売春相手は誰だ〜!」なんていう話まで出てエスカレートしています……。(大西夏奈子)
 |
渡りケーナ吹きの文明論
「文明が変わるときにはそれまでと違う異常災害が多発するもんなんだよ。気候変動、地球温暖化、水害、干ばつ、地震…。コロナウイルスも祖言うしたら変化の一つの兆しかも」と言うのはジャーナリストの森田靖郎さん(74)。文革時代からの中国ウォッチャーとして多数の著書を成し、近年は欧米にも足場を拡げて行き詰まった物質文明の行く末を観察しています。 「ネット社会がこれまでの世論の作られ方を変えてきてますね。東西の考え方の差さえ縮まっている。新たな文明はほっとすると国にも民族にも関係なく、もっと小規模な社会システムから始まるのかもしれない」。 森田さんが近年注目してるのは北欧の社会です。民主主義体制でありながら、社会主義的なシステムを実現している国々が多く見られます。「飽和した市場に依存し続けるのは難しい。それに替わるのはAIやIT文明なのか。それとも……」。 ケーナの演奏家としても秘かに活躍中の森田さんに、森田流文明交代期の世界の見方をたっぷり語って頂きます!! |
地平線通信 491号
1 制作:地平線通信制作室/編集長:江本嘉伸/レイアウト:森井裕介/イラスト:長野亮之介/編集制作スタッフ:丸山純 武田力 中島ねこ 大西夏奈子 落合大祐 加藤千晶
印刷:地平線印刷局榎町分室
地平線Webサイト:http://www.chiheisen.net/
発行:2020年3月11日 地平線会議
〒160-0007 東京都新宿区荒木町3-23-201 江本嘉伸方
地平線ポスト宛先
pea03131@nifty.ne.jp
Fax 03-3359-7907 (江本)
◆通信費(2000円)払い込みは郵便振替、または報告会の受付でどうぞ。
郵便振替 00100-5-115188/加入者名 地平線会議
|
|
|
|
|
|