

1月 15日。地平線通信の制作に没頭すると、パソコン、電話に多くの時間を費やし、うろうろ部屋の中を動き回るくらいしか体を使わない。もっと外の空気を吸おう、と14日、家を飛び出した。行く先は、近頃、滅多に足を向けない渋谷。あそこに最近とてつもなく高いビルができた、と聞いている。あとであげる理由によって渋谷は私にとってほろ苦い青春の思い出と重なる町だ。
◆新たなタワービルを「渋谷スクランブルスクエア」という。「都市再生特別地区認定事業」として2014年6月に着工。昨年11月1日、第1期の東棟が完成した。高さ約230 m、地上47階、地下7階建て。表示に従って移動するうちあっという間に屋上展望台「SHIBUYA SKY」の入り口に達した。ここでチケットを買うのだが、それが2000円。高齢者となり、あまり無駄遣いはできないぞ、と言い聞かせたばかりなのだが、まあいいか。
◆晴れ上がっていたこともあって、展望台は360度、素晴らしい眺望だった。完成したばかりの国立競技場がすぐ真下に見える。どうして渋谷に青春の思い出が?と問われれば、そこが「三方面」の中核だったから、と答えよう。1964年、東京オリンピックの年に新聞記者になった私は、前橋支局に配属され(多分、遭難の多い谷川岳があったため)、10月のオリンピック本番には本社に召し上げられ、レスリング担当として駒沢に通った。この当時のことはそのうち詳しく書く。
◆前橋で3年5か月仕事したあと横浜支局に転勤、海事記者倶楽部や県警キャップを1年7か月勤めてから社会部に引っ張られた。新人の社会部記者はサツ回りから始まる。私は警視庁の「三方面」を持たされ、渋谷署の記者クラブを拠点に世田谷、碑文谷、目黒などの警察署に通うこととなった。新聞の社会面は、事件、事故だけの取材にとどまらない。町の話題、大学や動物園も対象になる。その中で忘れられないのが三島由紀夫と東大全共闘の対決だ。
◆東大駒場で三島と学生がやりあったらしい、なんとか取材しろ、とデスクに言われたのが1969年5月13日。各大学とも学生たちが“武装蜂起”に近い形でバリケード封鎖をしていてその中を駒場の学生たちに呼ばれた三島はただひとり教養学部900番教室に向かったのである。すでに夕方。駆けつけた駒場は解散したあとだった。私は三島の自宅に電話を入れた。社会部の新米記者の話を聞いた作家は意外にも上機嫌だった。「いや、面白かった、彼らも彼らなりにフェアだったよ」という調子で1000人を相手にビクともしなかった己への満足を感じさせた。
◆声の記憶というのは、いつまでも耳に残るものだ。1年後、あのようなすさまじい最後が来るとは予想もできない、快活でセクシーな三島だった。この時の対決は、『討論 三島由紀夫vs.東大全共闘』として本ともなった。その記録がなんと今になって映像で再現され、この3月、上映されるそうである。さて、皆さんはどうとらえるか。
◆暮れの12月久々に浜比嘉島に行った。ゴンが17才になった、と聞き、どうしても会いたくなったのだ。初めて琉球犬のゴンに会ったのは、飼い主の外間昇さんが地平線仲間の晴美さんと結婚する前、ゴンは4才か5才だった、と思う。とにかく元気だった。男性には警戒心をむき出しにすると聞いたが、私の犬好きが伝わったのか、最初から懐き、島に行った時は毎日、一緒に海沿いを散歩した。時にリードをつけたまま遠くへ逃げてしまうこともしばしばだったが、最後には必ずつかまった。
◆浜比嘉島では12年前の2008年10月、私たちは「ちへいせん・あしびなー(遊びの庭)」という思い出深いイベントをやった。詳しい内容を紹介する紙数はないが、地平線のウェブサイトには当時のことを記録している『あしびなー物語×わたしたちの宝もの』の紹介があるので参考にしてほしい。前半は私たちのイベントの記録、後半は当時の比嘉小学校児童の写真記録である。表紙が両面にあるという丸山純さんの力作で最近地平線を知ったという人もいつか記録を手にしてほしい。
◆あの時、子供たちの声で沸いていた比嘉小学校は2012年3月22日、島びとの反対も虚しく廃校となった。その廃校式に参加したのが私の最後の浜比嘉だった。あれから7年あまり、再訪すると校舎は一ブロックを残して全て取りこわされ、あの美しい学校の再利用は果たされなかったことがわかった。外間さん夫婦の牧場だけが以前より賑やかになっていて私の心をなごませてくれた。
◆長野じゅんこさんの魂が散骨された平島の小さな、美しい浜には毎日ゴンと娘のポニョと通った。3日目、海沿いに歩いていると突然、ゴンがいなくなった。肝をつぶし、激しく反省した。ゴンは目が見えなくなっており、足を踏み外し、一瞬リードにぶら下がったのだ。ゴンを引き上げながら、また来るから待ってろよな、と語りかけた。(江本嘉伸)
アメリカとカナダの国境を跨ぐスペリオル湖は世界最大の淡水湖だ。その岸からはまるで大洋のような景色が広がる。時折、湖の上を白樺やポプラの樹々の間を抜けてきた風が、極北のにおいを運んでくる。そんなスペリオル湖から北西約2,000キロメートル先に位置するグレートスレーブ湖までの原生林をノースウッズ(北の森)と写真家・大竹英洋さんは呼んでいる。ノースウッズは日本列島の4倍の面積を持つ亜寒帯林の森だ。カナダ楯状地という先カンブリア期につくられた岩盤の上に、松やもみといった針葉樹や白樺やポプラなどの白い広葉樹が鬱蒼と生い茂っている。果てしなく続く原生林には人間の安易な侵入を阻むかのように大小無数の湖が点在し、その森の中でオオカミやムースといった沢山の動物達が生命の営みを繰り返している。「自然の奥にある秘密を伝えたい」という想いを胸に彼は20年もの間そんなノースウッズを撮り続けている。
■大竹さんは1975年京都府舞鶴市生まれ。幼少期に東京都世田谷区に引っ越し都会で育つが、大学時代にワンダーフォーゲル部に入部し沢登りを始める。「透き通る水の中を泳ぐイワナを捕まえて、焚き火で炙って食べるんです。そんな中、一息ついてふと夜空を見上げると、空には視点が定まらないほどの満点の星空が煌めいています。それは言葉を失うくらいの光景です。都会の中での暮らしは嫌いではありません。でも、都会の中では見えないものがあることをそのとき知りました。それがそうした活動にのめり込んでいくきっかけになったんだと思います」と語る彼は、いつしか自然の中に長期間入っていき、その奥にある秘密を伝えることを職業にできないかと考えるようになった。
◆しかし、実際にどうしたらそれを仕事にできるか分からない。漠然と写真家になることを考え始めていたが、何をテーマにすべきか決めあぐねていた。星野道夫さんのアラスカのように、一生をかけて取り組めるフィールドを探したが、一向に結論は出ない。「頭で考えていても、ダメかもしれない」と思い始めていたある晩、奇妙な夢を見た。
◆夢の中で暗い木造の小屋にいた。窓の外を眺めると真新しい白い雪が降りしきっている。その雪の降りしきる森の中から灰色の巨大な犬のような生きものが現れ、彼を見つめた。その瞳は何かを見定めるような、そして、誘うような光を宿していた。「オオカミ」と思った次の瞬間、すぐにその生きものは森の奥へと消えていった。それだけの夢だった。
◆夢を見てすぐ、図書館でオオカミについて調べる。目に飛び込んできたのは『ブラザー・ウルフ ──われらが兄弟、オオカミ』というジム・ブランデンバーグが撮ったオオカミの写真集だった。ジムはナショナル・ジオグラフィック誌で30年以上も契約フォトグラファーとして活躍してきた人物。その名は知らなくとも流氷に向かってジャンプする白いオオカミの写真を知っている人は多いだろう。その写真はジャック・ロンドンの『犬物語』(柴田元幸訳)の表紙にも使用されている。
◆『ブラザー・ウルフ』のページを捲りながら、魂を揺さぶられた彼は、後日ナショナル・ジオグラフィック誌の協会本部に「あなたのような写真家になりたい。もし叶うなら、あなたに弟子入りしたい」とジム宛の手紙を送った。しかし、返事が返ってくることはなかった。
◆就職活動はせず、大学を卒業したその年の5月末にジムに会うためにミネソタ州を訪れた。手掛かりは『ブラザー・ウルフ』の見返しにあった彼の撮影フィールドを記した手描きの地図。ジムの家は滝の傍にある。ミネソタ州の森の中で滝を見つければ、彼に会えるかもしれない。もし彼に会うことができなくても、その間にオオカミを撮影できるかもしれない。期待を胸にカナダとの国境に近いイリーの街に足を運んで見つけた地図には、ジムの手描きのものと一致する場所があった。
◆イリーの街からジムが住んでいるであろう土地まではカヌーで2泊3日の距離。「ゆっくりと土地の景色を胸に刻みながら漕いでみよう」と7泊8日の時間をかけ、その目指す場所に向かうと確かにジムに会うことができた。その後すぐ、ジムの友人である世界的な探検家のウィル・スティーガーを紹介される。ウィルは1986年に犬ぞりによる無補給北極点到達を達成し、1990年には総距離6,000キロの南極大陸犬ぞり横断を世界で初めて成功させた人物。この旅をきっかけにノースウッズは彼のフィールドになった。
■水辺の氷が解け始める頃、カナダグースの声が聞こえ始める。渡り鳥達が、子を産み、育てるために南からノースウッズに帰ってくるのだ。ハシグロアビはカナダの1ドルコインの裏側にも描かれノースウッズを代表する水鳥。蝶ネクタイを締めたような容姿で赤い目を持ち、陸の上を歩くのは苦手。忙しなく小魚を雛に与えるその上を白頭鷲が大きく旋回している。
◆一方、この地で冬を越す鳥もいる。同じ冬を過ごしたゴジュウカラには仲間のような連帯感を覚えるものだ。エリマキライチョウはその羽根を小刻みに羽ばたかせ、まるで太鼓の音のような重低音を響かせる。ノースウッズの春は実に賑やかだ。そんな鳥達の声に導かれるようにアメリカクロクマの子供達が現れる。風がヤマナラシの葉を揺らす音が眠気を誘うのだろうか。子グマ達はあくびをして、やがて木立の上で眠りについてしまう。
◆新緑の6月、獣道を歩いて倒木を乗り越えようとすると木漏れ日の中でバンビがうずくまっていた。危うく踏みそうになり、その場で様子を眺めていると長いまつ毛を持ったバンビが吸い込まれそうな黒い瞳でこちらを見返してくる。しかし、怯えているような素振りは見えない。母鹿を探すかのように辺りをきょろきょろと見回したバンビだったが、やがて周りの景色に紛れるように寝入ってしまった。そんな森の中では口の周りをベリーで真っ赤にしたシマリスが短い夏を謳歌している。
◆ノースウッズの移動手段のひとつが、カナディアンカヌー。その土地で作られた道具で旅をするとその自然が近くに感じられる。隣り合った湖に移動するにはカヌーも荷物も肩に担いで運ぶ必要があるが、山のない平坦な土地ゆえにそれほど苦にはならない。撮影の際は湖の水をそのまま飲料水として使う。人間の身体の6割以上は水でできているが、キャンプが長いと身体が湖の水に満たされ、だんだん湖との境界がなくなっていくようだ。
◆秋はノースウッズが色付く季節。冬眠をしないアカリスは厳しい雪の季節を乗り越えられるようにせっせと木の実を集める。そんなアカリスを横目にして、泳ぎが上手なウッドランドカリブーは大きな蹄で難なく湖を渡っていく。世界最大の鹿であるムースの発情期に、その習性を利用した狩りの方法がある。白樺の皮でつくったメガホンでメスの鳴き真似をして、オスを誘き寄せるのだ。掠れた少し悲しいようなその音を響かせると、それを聴き分けたオスが巨体を揺らし、トウヒの枝を折りながらやってくる。そして、南へ渡るトランペッタースワン達の声が聴こえなくなると水辺に氷が張り始める。
◆白銀のノースウッズの森の中を、音もなく歩くオオヤマネコが狙っているのはカンジキウサギ。頭から雪原に突き刺さるように飛び込んでいるのは、アカギツネ。雪の下の暖かい世界で冬を越そうとしているネズミを狙っているに違いない。そんな雪原に残る足跡はオオカミのものだ。オオカミの遠吠えを真似ると森の四方から伸びやかな声がこだましてきた。やがて一頭のオオカミが目の前に現れる。オオカミは大竹さんをひとしきり眺めた後、辺りを揺るがすような遠吠えをあげ、森の奥へと消えていった。凍てつくような夜には龍が天を駆け巡るようにオーロラが舞う。長い夜が明け、エリマキライチョウが求愛のダンスを踊り始めると春の足音が聞こえてくる。湖の氷が溶け、南から渡り鳥たちが帰ってくると、また新しい命の季節が巡ってくる。
◆「ノースウッズで野生動物と見つめ合う瞬間に感じたのは、「見ている」ではなく、「見られている」という感覚でした。彼らから「お前は何者なんだ?」と真っ直ぐな目で問いかけられると、自分たち人間がどうやって生きていくべきか深く考えざるを得ません」と語る大竹さん。著書『もりはみている』(こどものとも年少版2015年10月号/福音館書店)の中で、こう綴っている。
もりはしずまりかえり
なにもしゃべらないけれど
まつのきの
すあなのおくから
あかりすがみている
すぎのきの
こずえのかげから
ごじゅうからがみている
やまならしのきの
えだのうえから
こぐまのきょうだいがみている
そのしたで
おかあさんぐまも
じっとみている
ゆうぐれちかづく
こだちのむこうから
となかいがみている
よるのやみから
ふくろうがみている
もりはしずまりかえり
なにもしゃべらないけれど
いつだって
きみをみている
■2018年に、カナダ初の世界複合遺産として登録されたオンタリオ州とマニトバ州にまたがる土地は、ピマチオウィン・アキ(先住民オジブワ族の言葉で「生命を与える大地」の意)と呼ばれ、7000年もの間、狩猟採集民であるオジブワ族(自称アニシナベ)によって守られてきた。アニシナベはカヌーを使いワイルドライスと呼ばれる野生の穀物を収穫するのだが、その籾殻はかつて風を使って選り分けられていた。ピマチオウィン・アキはそんな風と共に生きた時代の名残が残る場所である。しかし同時に、先住民が虐げられてきた歴史を抱えた土地でもある。白人社会への同化を狙った「インディアン法」により、主に1970年代までカナダとアメリカの先住民は全寮制の寄宿学校に入れられ、部族の言葉を使うと舌に針を刺されるといった虐待を受けていた。ちなみにカナダで最後の寄宿学校が閉鎖されたのは1996年のことである。こうした背景から伝統文化の断絶が起こり、心に深い傷を負ったアニシナベがいる一方で、失われた先祖の儀式を取り戻すという動きも生まれてきている。「星野道夫さんはギリギリ間に合った世代だと僕は思うんです。文化の断絶の起こる前の世代の人達とも繋がることができました。でも、僕達はそうじゃありません。それでも今、次の世代がその失われたものを必死に未来へと繋ごうとしています。その姿を僕は見届けていきたい」と報告会の後に大竹さんは語った。そんなアニシナベの家族に連れられて森で彼が見たのは、ライフルで仕留めたムースの喉の皮を「昔からそうしてきた」と最初に切り取り、森の木々に捧げる姿だった。ムースの解体は子供達も手伝う。なんでも撮って伝えてほしいと頼まれた大竹さんだったが、家長の背後から写真を撮ろうとすると制止された。「解体中の体内は見てはいけない」と突然タブーがその場に立ち現れたのだ。その瞬間のことを「数千年前の世界と今が繋がった気がした」と大竹さん。一般的にムースを仕留めても白人は肉しか食べないのだが、アニシナベの人々は内臓も食べる。心臓や腸や胃袋は持ち帰って塩茹でし、腎臓はスライスして、オイルで炒める。珍味と言われるムースの鼻は、焚き火で毛を焼いた後に細かく刻んで3、4時間煮る。そうすると内側の軟骨も柔らかくなり、外側は燻されたような味が残る。大腿骨の骨髄はバターのように肉につけて食べる。どれもとても美味しい。そして、食べることで、子供達が舌で味を覚えていくことが大事なのだ。
■「ノースウッズは、まだほとんど知られていない地域ですが、いつかみんなが憧れるような土地になってくれればいいなと思っています」と話す彼だが、これまでの活動の集大成とも言える写真集をこの春出版する。序文は、ジム・ブランデンバーグだ。そんなジムとの出会いや彼が写真家となるまでを綴った書籍『そして、ぼくは旅に出た。』を出版した報告を兼ね、2018年の春先にミネソタを旅した彼はウィル・スティーガーにも会いにいったのだが、その日はウィルが南極大陸横断を達成してからちょうど28年目の3月3日だったという。南極大陸横断という偉業を成し遂げたウィルは当時45歳。久しぶりに再会した43歳になって間もない大竹さんに「キャリアが始まったばかりだな! お前の人生はまだ半分も残っている。これから40年は旅ができるぞ」と語ったウィル。講演会などで「どうしたら探検家になれるんですか?」と質問をしてくる子供達にいつもこう答えているという。
「Put your boots on and start walking!!
(ブーツを履いて歩き出せ)」
◆私事で恐縮だが、レポートの書き手である僕は昨年の12月に新卒から約17年勤務した会社を退職した。この春から始まるパラオからハワイ島までの1万キロの航海に参加するためだ。もちろん、乗船するのはアリンガノ・マイス。「4年前の航海のその先の世界を見てみたい」という想いが、最終的に僕を突き動かした。2020年は僕がスターナビゲーションを知ってからちょうど20年目の年に当たる。航海の先には何もないかもしれない。でも、もしそこに何もないのなら、そのないことをこの身体で確かめたいと思う。
僕の人生もまだ半分も残っている。
さあ、ブーツを履いて、歩き出そう。(光菅修)
■日本を代表する冒険家、探検家、ジャーナリストが集う地平線会議。目や耳の肥えた参加者たちに、果たしてノースウッズなどという、どこにあるとも知れない場所で、人類の記録に挑むのでもない、個人的な探求の旅の話が、どう受け止めてもらえるのか全く気にしなかったと言えば嘘になる。それでも会場に到着してからずっと、特に緊張もせず、むしろ温かい気持ちのままに報告を終えることができたのには、いくつもの理由があった。
◆まず、会場の新宿スポーツセンター。母校の戸山高校に近いこの施設は、じつは学生時代に空手道部の一員として、何度も練習にきた場所である。試合に勝った記憶もほとんど無い平凡な部員だったが、あのときかいた汗が、今もこの建物の床のどこかに染み込んでいるのかもしれないと思うと、なんとも言えない懐かしさがこみ上げてきた。
◆主な所属は空手道部だったが、スキー部と兼部をしていた。基礎スキー習得が目的で、春と冬の休みにはゲレンデ合宿があった。ぼくは初心者だったが、同学年には上級者の班に混じる者もいて、その中の一人が合宿の夜に、呆れたように話し始めた。「あの顧問の先生、まじで頭おかしいぜ。ゲレンデじゃないところをどんどん滑っていくんだ」。立ち入り禁止のバックカントリーに、顧問自らが生徒を連れ出すなんて、今の時代なら大問題かもしれない。その顧問こそが地平線会議の元代表世話人、三輪主彦先生だった。
◆三輪先生は地学の担任で、何を習ったのかはさっぱり覚えていないが、横道にそれた雑談が面白かった。例えば、「この前、死海で泳いでいたら、対岸が光るので、なんだと確認したらびっくり。銃口がこっちを向いていたんで、慌てて逃げたよ(笑)」と。いま思えば、テレビや新聞などのメディアを通さず、実際に体験した人の口から伝えられる世界情勢に触れた最初の機会だった。もしかすると、その後なんとなくジャーナリストというものに憧れ、進路を決めることになる種のようなものが、無意識のうちに撒かれていたのかもしれない。そんな三輪先生と高校卒業以来、じつに26年ぶりに再会できた。
◆ジャーナリストを目指し、新聞やテレビなどのマスコミへの就職率が多い大学と学部を探して、一橋大学社会学部に狙いを定めた。部活を言い訳に、全く受験勉強をしていなかったので、高望みも良いところだった。でも一度決めたら頑固なのは生まれつき。2年の浪人生活を経てなんとか入学した。しかし入学後は学業よりも、ワンダーフォーゲル部での沢登りに夢中になった。山頂に立つのは達成感もあったが、むしろそこに至るまでのキャンプ生活に惹かれた。自然の奥を旅する魅力に取り憑かれたぼくは、その先に見えてくるものを伝えたいと思うようになり、大学三年の秋に写真家になることを決めた。この報告会にも思い出深いワンゲルの先輩が、3人も駆けつけてくれたのは嬉しい驚きだった。
◆大学生のとき、ちょうど関野吉晴さんのグレートジャーニーがテレビでよく放映されていた。経歴を見ると大学の先輩である。地平線会議の存在を知ったのも、この頃、関野さんの活動を追っていたからだと思う。その時は「すごい人たちの集まりがあるのだな」と、遠目に見上げるだけだった。しかし、そのすぐ後、興味を引く報告会が開催された。
◆卒論にとりかかっていたぼくは、チュコト半島のトナカイ遊牧民のトナカイレースに関する民族誌を調べていた。ある日、ふとしたきっかけでチュコト半島ではないが、モンゴルの奥地のツアータンというトナカイ遊牧民について、地平線会議で報告があるというので参加した。それが、1998年10月30日にアジア会館で行われた山本千夏さんの報告会だ。そこでぼくは、ノースウッズと出会うのに大きな影響を与えた、モンゴル遊牧民の夢の話を聞くのである──ここから先の経緯は『そして、ぼくは旅に出た。:はじまりの森ノースウッズ』(あすなろ書房)に書いたので、詳しくは読んでもらうしかない──。その後、千夏さんとは別の場所でも話をする機会があり、今回もわざわざ旅の予定を変更して会場に駆けつけてくださった。
◆こうして1999年5月に始まったノースウッズへの旅。時は流れ、2018年の5月に、再び地平線会議がぼくの前に現れる。そのきっかけは先述の本『そして、ぼくは旅に出た。』が「第七回梅棹忠夫 山と探検文学賞」を受賞したことだった。他でもない、代表世話人である江本嘉伸さんが選考委員で、授賞式でお会いしたのだ。まさか自分が地平線会議の報告者になるとは思ってもいなかったが、江本さんからお誘いを受け、長野亮之介さんとも事前にじっくり話をする機会を設けてくださった。そうした手間と時間をかけて報告会に臨んだことも、当日リラックスできた大きな理由だと思う。
◆最後にもう一つ。予期せぬ再会があった。最近報告会に顔を出すようになった中川原加寿恵さんだ。次の報告者が古い知人の大竹と気づいて事前に連絡をくれたのだ。誰しも人知れぬ苦労があるだろうから、ぼくもあまり語ったことはないが、ここまでずっと順調にきたわけではない。ノースウッズに通って3年が過ぎた2002年、撮影が思うように進まず、精神的にも肉体的にも不調を来たし、どうにも動けなくなって写真家の夢を諦めざるを得なかった。
◆失意の底にいた時、原宿のとあるビルで行われていたオープンマイクのリーディングイベント「BOOKWORM」を知った。音楽家の山崎円城さんや青柳拓次さんらが主催し、本の一節や詩など、それぞれが好きな言葉を持ち寄って、人前で語ってシェアするイベントだ。参加者の中にカズエさんもいた。最初は人の言葉に耳を傾けていただけだが、ゆったりとした空気感に促され、あるときから自分もマイクの前に立つようになった。
◆好きな本や自作の詩だけでなく、ときにはミネソタの冬の気温を読み上げてみたりこれまでの旅の話を語るようになった。緊張したが、参加者の誰もが長年の友人であるかのように真摯に耳を傾けてくれたことが励みになり、心の傷は少しずつ癒されていった。そして、その励ましは、2003年秋に東横線学芸大学駅にある喫茶店「平均律」で行った、初めての写真展へと繋がってゆく。それまで誰も展示をしたことがなかったが、今は亡きマスターが「壁を使って写真展でもしたら?」と声をかけてくれたのだ。
◆フライヤーも準備して各方面に送ったところ、出版社から来てくれたのはただ一人、福音館書店のベテラン編集者だった。まだ何も世に出ていないぼくの作品を見に来てくれたことにも驚いたが、憧れの「たくさんのふしぎ」で「本を一緒に作りませんか」と言われたのにはもっと驚いた。こうして、ぼくはもう一度、夢に向かって歩き始めることができたのである。今回の報告で自作の『もりはみている』という写真絵本を朗読したが、そのようなことが人前でできるようになったのは、間違いなくBOOKWORMでの経験が活きている。カズエさんとの再会によって、挫折当時の苦い味を思い出すとともに、今こうして写真を撮り続けられている幸せを、しっかりと噛み締めることができた気がする。
◆「報告者のひとこと」という原稿依頼だったが、地平線会議との縁を思い出していると、ずいぶん長くなってしまった。言いたいのは結局、これまでずっと人との出会いによって生かされ、今があるということだ。人生には巡り合わせというものがある。ちょうど来月、2月21日からは人生で最も大きな個展がフジフイルム スクエアで始まる。それにあわせて、これまでの撮影の集大成となる写真集の刊行もある。桃栗3年、柿8年、ノースウッズは20年。機が熟すにはそれ相当の年月がかかり、収穫の時期を逃しては痛んでしまう。そうしたタイミングで、こうして地平線会議の報告者に呼ばれたのも、なにか大きな流れの中で、昔から決まっていたことのように思える。
◆今回の報告会を通して、過去から現在の自分を見つめ直し、さらに、地平線会議に集う皆さんと出会えたことで、人生の糸がより太く紡がれていくのを感じる。この先に何が待ち受けているのか、とても楽しみでならない。(大竹英洋)
■江本さん、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。12月報告会の大竹英洋さんのお話では、名前も知らなかったアメリカ北部の湖水地帯・ノースウッズの世界に魅せられました。オオカミの夢に導かれてたどり着いた、美しい湖畔の景色。極寒の地で力強く生きる人たちの目、生き延びるための智慧、獲った命を無駄なく使う術……。何十年も同じところに通っているからこその、ただ通り抜けていく一過性の旅とはまた違った奥深さと妙味を感じました。
◆そして「野生動物たちは道具も何も持たずに生身で過酷な自然を生き抜いている」という言葉に、極寒の森の中で身を潜め、動物と同じ目線で撮影をされている大竹さんの野生動物への畏怖とリスペクトを感じました。これはわたしも以前狩猟をしていた頃に感じていたことで、だからこそ自分は安全な場所にいて遠くから撃つのではなく、なるべく対等でありたい、罠をかけて彼らと知恵比べをして、正面きって対峙したいと思ったのです。
◆それでもなかなか罠にかかってくれなかったり、やっとかかってもそこから止めを刺す瞬間はいつも葛藤がありました。目の前にいる鹿の美しい目を見つめながら、自分はその命を奪うのに値する人間なのか?と突きつけられるようで、ナイフを持つ手はいつも震えていました。──そんなことを思い出しながらお話を聞いていました。
◆さて、昨年はわたしにとって大きな転機となる1年でした。自転車旅を終えて2年以上経ち、ようやく当時のことを『なないろペダル』という本にまとめることができました。その節は江本さんはじめ地平線会議の皆様にたくさんご協力や助言、励ましの言葉や嬉しい感想をいただき、本当にありがとうございました。本を携えてあちこちでお話会をさせていただく機会もあり、どれほど多くの人たちに支えられて今の自分があるかをあらためて実感しました。
◆その一方で、話す内容が過去のものになっていくにつれ、自分の気持ちが離れていくような感覚や行き詰まりを覚えはじめているのも事実です。過去よりも今にフォーカスするために、そろそろ次の旅に出る時期かなという気がしています。
◆というわけで、来週からインドにいってきます。今回は自転車も持たず、荷物も極力身軽にして、いろいろと歩き回ってみようと思います。昨年の秋からはじめたウォーキングツアーガイドの仕事の影響もあって、改めて「歩く」ことの魅力を感じています。インドの文化、思想、手仕事、家庭料理、自然の恵みを生かす智慧……。自分の目で見て聞いて味わって、全身で感じてきます。はじめてのインド、どんな出会いが待っているのかドキドキです。
◆また帰国したら旅の報告をしに伺いますね。現地の家庭料理を習ってくるつもりなので、インドカレーVSエモカレー、勝負しましょう(笑)。(青木麻耶)
■皆さんこんにちは。シリア難民の暮らしをテーマに撮影しているフォトグラファーの小松由佳です。この度、トルコ南部での一カ月半にわたるシリア難民の取材(2019.11/26〜2020.1/10)を終え、元気に帰国しました。今回の取材は、3才と1才の2人の子供を連れてということもあり、母親として子供たちを見ながら、かつフォトグラファーとしてどのようにオリジナリティのある撮影をするかが最大の課題でした。
◆覚悟はしていましたが、子供があちこち走り回ったり大声をあげたり、ものを壊したり子供同士でケンカしたりするなかでの撮影は、撮影する以前の問題で、想像を絶する大変さでした。三脚に頭突きされて写真がブレたり、背中に次男をおんぶして写真がブレたりはしょっちゅうで、撮影のタイミングを逃し、集中できず、じっくりと撮影できないもどかしさに悶々とすることもありました。しかし一方で、子供を連れたからこそ気付くことのできたシリア難民の姿もあり、撮影できないことで得られるものは確かにありました。“この取材では、写真を撮れないということを撮るのだ”と思っていましたが、まさに撮れない状況でどう撮るかが課題の毎日でした。
◆取材で出会ったのはシリア難民の約25家族。その中にはシリア中央部のパルミラ出身で、2016年にトルコに逃れた夫(シリア人)の家族もいました。内戦前、夫の家族は、ラクダの放牧業を生業に、オリーブやザクロの果樹園の管理、屠畜業や羊の飼育販売などを大家族で手がけ、生活してきました。しかし内戦後、政府軍と反体制派勢力の衝突でパルミラの街には爆弾が降り注ぎ、イスラム過激派ISの統治下にも置かれ、度重なる為政者からの暴力に耐えかねてトルコへ逃れてきました。
◆2008年に初めてシリアを訪ね、一家の内戦前の豊かな暮らしを知っていただけに、いかに彼らが劇的な変化をたどったかを感じています。夫の家族は今、高原の街として知られるオスマニエにて、放牧業や屠畜業などを行なって生活基盤を作ろうとしています。言葉や文化の違うトルコでさまざまな壁に直面しながらも、親族が集まることでよりサポートし合える環境を作り、経済的に援助し合い、昨年は土地を購入して家も少しずつ建てています。
◆今回、4年ぶりにトルコへの入国ビザが許可された私の夫(シリア人)もトルコに同行し、一つ一つの取材には同行しなかったものの(家族と過ごす時間を大切にしたいため)、家族との感動的な再会、特に父や母とシリアで過ごしたような素朴で静かな時間を愛しんで過ごす様子を見せてもらいました。
◆夫は父と野を歩き、オリーブの木を共に切ったり、薪を拾って火を焚き、そこへ何時間も座る、という時間をとても大切にしていました。それは特別な時間ではなく、ありふれたたわいもない時間で、そうした素朴で平和な時間こそが幸福そのものであるというかつてのシリア人の価値観を彷彿とさせるものがありました。夫はこのトルコ行きで、シリア人たることを家族と共に再確認したかったのだと思いました。
◆内戦から9年が経ち、難民生活が長期化しそうな今、シリア難民の生活にどのような変化が生まれているのか。それが今回の取材のテーマでした。2015年の取材では、「サナルジャー(みんなでシリア帰ろう)」がシリア難民の間では合言葉で、人々はシリア帰還がそう遠くないと固く信じていました。しかし今回の取材ではそうした人々の意思が変化し、シリア帰還が近くないことを覚悟し、現在の環境にいかに適応して今を生きるかに意識を傾けていることを感じました。
◆シリア難民は皆シリア人コミュニティによって生かされています。ほとんどの家族はスマートフォンを持ち、インターネット上のシリア人コミュニティから互いにサポートを受けています。シリア人同士が結束することで、皆で困難さを打開していこうと日々模索しているのです。シリア難民にはさまざまな背景があり、置かれている環境も全く異なります。なぜシリアから逃れてきたのか、シリアで何を失い、今難民としてどんな困難さに直面しているのか。そうした一人一人のエピソードに光を当てて今を生きる人間の姿を記録しました。
◆取材を通し、苦労も喜びも、やはり人との出会いの中にあります。苦労したのは、子連れドタバタの中で一期一会の瞬間をどう切り取り、人々の困難さや喜びや強さを表現するかという点。子供が一緒ということは子育ても同時進行であり、すべてにいっぱいいっぱいで、表現についてじっくり考える余裕すらないこともありました。
◆一方で、喜びを感じるのは、昨年取材した方が、希望を見出し前向きに生きていたり、家族に赤ちゃんが生まれて命の輝きに満たされていたりと、一人一人の人間が困難さの中でも何かを信じたり、何かに幸せを感じて生きようとしている、そうした姿を垣間見たときでした。シリアで10代の二人の息子を失い、自らも空爆による障害と病気を抱えながら暮らすムスタファ・カービースさん、同じくシリアで5歳だった息子を失ったカーセム・アウラージさん。お二人とも昨年の取材では悲痛な表情をされていましたが、今年の取材では、それぞれ新しい命を得て、家族が増えた喜びに心を震わせるように日々を生きていました。
◆またISによって拷問を受け、歩行ができなくなる障害を負ったジャーラッラーさんは、投薬治療や理学療法によるリハビリなどの新しい治療の結果、動かなかった手足が少しずつ動くようになり、状況が改善されている実感から生き生きとした表情をされていたことも忘れられない出会いでした。シリアとの国境の街であるレイハンルでは、近距離にミサイルが飛んできたり、シリア難民の動向を警戒するトルコ警察から尋問を受けたりと、緊張状態に陥ることもありましたが、一つ一つの出来事が、よりこの地でシリア難民として生きることの複雑さを感じさせてくれました。
◆宿泊は全日親族の家に泊まり、生活を共にさせてもらい、子育ても見守っていただきながらの取材の日々。仕事がない、お金がない、言葉や文化に馴染めないなどの外側から見えやすい困難さのほかに、結婚形態の変化に苦しむ人々の姿や、核家族化したことでの問題、子供たちの教育、コミュニティーを失ったことへの深い喪失感など、彼らの中で過ごすことで彼らが抱える内側の困難さも目にすることができました。
◆3才の長男サーメル、1才の次男サラームの二人の子供たちには、この取材で過酷な経験をさせてしまいました。難民の家族の家で極寒の夜を過ごさなければならず、風邪も引き、夜は部屋の隅に3人が川の字になって体を暖め合って眠りました。家のお湯が出ない、洗濯機がないのは当たり前、また雨が続いたことで、お風呂に10日間入らず、1週間ほど着替えもしないこともありました。しかし本当にたくさんの、それも大小さまざまなシリアの子供たちと賑やかに、泣いたり笑ったりケンカしたりドロドロになって過ごした日々は、子供たちにとって東京の生活では経験できないものでした。気がつけば、サーメルは私以上にアラビア語が堪能になり、1歳のサラームは、立ってトコトコ歩くようになりました。
◆シリアの血を引く彼らが、いつか自身のアイデンティティーに立ち返ることがあるなら、その時、こうした成長の過程で多くのシリアの難民に見守られてきたことを思い出すでしょう。シリア難民を見つめることは、私にとり、私の家族がシリアという自身のルーツを抱いてどのように今を生きていくか、という問題でもあります。激動の時代の中で、人は何を見出し新しい環境を切り開いていくのか。その姿を私は長い時間をかけてこれからも見つめ、人間の生き姿を記録していきたいと思います。
◆今回の取材にあたり、多くの皆様から大変大きなサポートをいただきました。おかげさまで、現地滞在費、交通費、撮影機器、取材へのお礼に十分な支出ができ、より質の高い取材ができました。本来は取材費は、自分で獲得した資金で向かうものだと思っていますが、日本での社会の壁に直面するシリア人の夫をサポートし、2人の幼い子供の育児をしながら働いて生活を続ける日々は容易ではなく、そうした中での取材をするにあたっては皆様からのサポートが本当に有難いものでした。多くの皆様からご理解をいただき、大変温かいサポートを頂きましたことに、改めて心から感謝をしております。本当にどうもありがとうございました。今後も、今回の取材の内容をより多くの方にお届けできるよう、努力いたします。(小松由佳)
■あけましておめでとうございます。2019年10月の報告者としてお話をさせて頂いた近藤瞳です。今回、あのお話からの後日談をお話させて頂きます。
◆2019年8月から、“自分を生きる”をするために、全国各地で地球を生きるワークショップ、なるものを開催しています、とお話しました(ワークショップの内容は省かせて頂きます)。ワークショップ開始当初の8月は数回の開催予定でしたが、参加者の方々の口コミ・リピート・紹介のお陰様で全国各地で62回開催される事になりました。
◆必要がなければ自然と声もかからなくなるだろうと終息するのを待つことにしましたが、ありがたいことに予想以上に声がかかり続け、自ら4月中旬で打ち切ることにしました。このワークショップを通して実行していた実験が形を見せてきたからです。
◆それは“自分を生きること”は仕事になるのか。ということ。ワークショップ、お話会、講演会という形で今まで、42回開催させて頂きました。ワークショップの代金に関してお話すると、1日で午前と午後計7時間し、それぞれ各2500円、お話会に関しては1人1500円を頂いています。売上は42回で869,200円に達しました。ワークショップ開始前に「瞳クラウドファンディング」と称してFacebookで活動資金調達。343,877円も集まり、その金額も合わせ“自分を生きる”ことは仕事になる、を実感。そして人脈やお金は後からついてくるもの、ということもしっかりと実感することができました。
◆先に私がどれだけの想いやエネルギーを持って事に取り組むか。最初お金がなくてもやるのか。ワークショップでお金が入らなくてもやるのか。それに対してイエスなら、それ相応のモノが形を変えて後から入ってくるのだなということ。いつだって何かを始める時はどうなるかわからない。その‘わからない’にいかに飛びこんでいけるか。人間は何もないと何かを生み出そうとする。火事場の馬鹿力は本当に存在するのだと改めて実感しました。
◆「今を生きる」「自分を生きる」を話し続けてきた私は、自分がいちばん番自分に洗脳され、4月から海外へ出発。ワークショップ屋さんという仕事を手放し、またしても何者にもならないことを決行します。そう、何者にもならないことは何者でも在ることだから。どうなるか‘わからない’にまたまた全力で飛びこんでみようと想うのです。どこに行っても“自分を生きる”ことだけはこれからもきっとしていく。それが今を生きることだから。こんな私を2020年もどうぞよろしくお願い致します。(近藤瞳)
■地平線会議の皆さん、明けましておめでとうございます。北大の探検部員として、山地民カレン族に伝わる「精霊の住む山トティコ」を追った活動を昨年6月に報告させていただきました、五十嵐宥樹です。堕落していた探検部の、本来あるべき姿を模索しながら過ごした7年の学生生活も残り僅か。報告から半年が過ぎ、現在は修士論文の執筆と、春からの記者生活に向けて心を整える毎日を送っております。今回は、報告を終えてからの半年間と、心境の変化について皆さんにお伝えしたいと思います。
◆昨秋、修士論文の最後の調査のためにビルマ(ミャンマー)カレン州に。隣国タイの難民キャンプから祖国(長い避難生活のため、もはや故国でない世代も多いのですが)に帰還する人々を対象とした聞き取りが目的でした。タイからUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の用意したバスに乗って本国帰還を果たす前に、まず交通費を自前で用意し、帰還先の下見や住所獲得のための「プレ帰還」を何度も行わなくてはならない。そうした事実が論文の「成果」になるはずでした。
◆しかし、へたくそな英語でなんとか終えた調査は、やっとの思いで帰還した難民の人々に対してただただ迷惑だったのではないかという懸念のほうが、今は強くあります。通訳を通じ何度も同じ質問を繰り返し、少なくない時間を分けていただいた現地の人に対しては、感謝と申し訳ない気持ちがないまぜになっています。大学で初めに習う「調査されるという迷惑」に気をつけていたつもりでいても、論文を書くという目的のほうに目がいってしまい、些か強引な滞在になってしまったのではないかという気がかりが残っているのが正直なところです。カレンの神の山トティコを追っていくうち、日本に住むカレンの難民、難民本国帰還といったトピックに向き合ってきたものの、ビルマ語が相変わらずできないなど、人と向き合う態度の未熟さを痛感しました。
◆地平線通信を読んでいると、学生時代が終わる自分は若くない、しかし行動者としてはまだまだひよッ子、ということをこの半年間は特に感じ悶々としています。学生時代は終われども、行動を続ける気があれば、まだまだ25という年は行動ができる年なのだと。ただ、どうしても自分の25才と、他人が25才でやってきたことの違い、選択の違いを比べてしまいます。何十年もかかってわかってくることがあると、続けることが大事なのだと、通信を読めばわかるのだけれど。学生時代が終わっても、いや、学生という立場が終わるからこそ、また一から、ミャンマーとの関係を深めていけばいいのだと、今は自分に言い聞かせ、何とも言えない焦りを抑えています。
◆トティコでは、山頂で暮らしていたユワ(精霊)は山から逃げてしまっているのだといいます。アジア太平洋戦争やその後の内戦で、多くの血が山に流れたためです。山の入域に関わるキーパーソンとのつながりを得たものの、今入域を依頼すべきなのか、この半年は悩みました。地域の情勢が今以上に回復し、ユワに召される形で山頂に辿り着くものなのではないか。そういう時期がきっとあるはずだと思います。
◆探検部員でいる間に達成すべき「課題」として自分の中で位置づけたのは私の都合です。「現役時代にこれをなした」と言いたいがための入域になっていないか? 私は自問します。当初は現役のうちに登頂する腹積もりでいましたが、もう少し自分のことを宥め、「その時」を待ちたいという気持ちがしています。「その時」にはどうか、地平線通信にてこっそりと報告をさせてください。ビルマ語の学習や、これまで調べてきたことの纏め直しなど、また一から登頂計画の準備にあたるつもりです。人生も四半世紀が過ぎました。トティコとユワ(神)に対して、不遜でない自分でありたいと思っています。もう現役を終える探検部員としてではなく、一人の人間として。追うのではなく、その向き合い方を、考えて生きていきたいと思っています。(五十嵐宥樹 北大大学院文学研究科)
■明けましておめでとうございます。2020年になり、12日の今日は「菜の花マラソン」(昔、江本さんも走りましたね)の日で、12800人のランナーが我が家の前を走り抜け、あるいは歩きぬけて行きました。開聞岳の麓の我が家に昨年4月25日開店したカフェ「紫苑」、おかげさまで順調に続けています。11時30分から15時までのランチがメインですが、最近は7時30分から10時までのモーニングもやっています。またふらりおいでください。(鹿児島県指宿市開聞岳山麓 中橋蓉子・野元菊子)
■すっかりご無沙汰してしまいました。5年前、いやもう6年前になります、2014年8月「ギャップ100℃の恍惚」というタイトルで話をさせてもらった関口裕樹です。
◆マイナス50度の厳冬期の北極圏から、プラス50度の真夏の砂漠へ、当時は気温差100度を体験する冒険をやり遂げて地平線報告会の場に立った。世界一暑い砂漠から帰ってきたばかり、当時27歳の僕はあのあと再び極地へ向かいました。
◆2016年、カナダ北極圏先住民の村タクトヤクタックをベースに、凍結した海氷上でソリを引き、34日間で450kmを単独徒歩踏破。この時は、衛星携帯電話は持たず、食料は現地のイヌイットから分けてもらったカリブーの生肉やクジラの油を素手で食らい、夜はカリブーの毛皮に包まって眠る、という昨今のスポーツ的になった極地冒険とは正反対のスタイルによって、北極という自然の中に深く溶け込めた感触を得られた。
◆その後、現在進行形で継続している数年がかりの長期計画「厳冬期カナダ人力縦断」を始動。計画の舞台は冬期極北カナダ。スタート地点はカナダ南部、アメリカ国境近くにある南北400キロのウィニペグ湖だ。地平線会議の皆さんには田中幹也さんが冒険されていた地として馴染みがあるのではないだろうか? 全面凍結したウィニペグ湖を縦断後、グレートスレーブ湖、グレートベア湖とカナダ3大湖の全踏破へ。
◆各湖の間は冬期間のみ現れるアイス・ウィンターロードで繋ぎひたすら北上、ツンドラ地帯を抜けて北極海へ。毎冬ごとにカナダの氷雪上を細切れで繋ぎ、目指す最終目的地は極地冒険の聖地と呼ばれるヌナブト準州「レゾリュート」だ。すでに過去2回の遠征を消化、2017年の第1次遠征でウィニペグ湖とそこから派生する川の氷上を徒歩で600キロ踏破。
◆2018年第2次遠征では雪に埋もれながら自転車で3600キロを走り、グレートスレーブ湖200キロを歩ききった。ウィニペグ湖ではソリをリード(氷の割れ目)に落とし、グレートスレーブ湖では氷が解けかかったシャーベット地帯を踏み抜き、マイナス30度の中で靴を凍らせるなど、ヒヤッとする場面にも出くわした。毎年冬の極地遠征をメインにしながら、夏には新しいテーマを模索するべく様々なスタイルでの遠征も並行して進めている。
◆知床半島一周、オーストラリア内陸部砂漠地帯リヤカー踏破。小型軽量ゴムボートパックラフトを使い陸路と水路を繋ぐ冒険のやり方を試行錯誤。今夏には世界一雨が降る地帯を雨期に行く「豪雨期」の冒険の可能性を探る為に、数年前まで入域規制がされていたインド北東部への偵察行も行った。冬には限界を追求、夏には可能性を広げる、そんなテーマで地平線報告会後も活動を続けている。
◆冒険、そして今の自分の生活のもう1つの軸、それが農業だ。スポンサー企業からの支援を受けながら、自己資金を確保する為に過去に様々なアルバイトをしてきた。それまで僕にとっての労働は、完全に冒険資金を稼ぐための行為であり、そこにやりがいを感じる事は無かった。しかし、ひょんなきっかけで始めた農業にはすっかりハマってしまい、今では遠征期間以外はずっと畑で過ごしている。
◆さくらんぼ、ラ・フランス、西瓜、レタスにナスにトマト……。今まで扱ってきたものをあげればキリがないが、それぞれの野菜、果物ごとに違った大変さ、そしてやりがいがある。登山、探検や冒険だけでなく、生活の中で自然と関わる農業だってアウトドア活動なんだと感じている。1月下旬には、厳冬期カナダ人力縦断第3次遠征として、前回第2次遠征の終了地点、グレートベア湖畔の村デレネへ出発する。グレートベア湖、ツンドラ地帯を縦断、北極海に出てからは北西航路を東進、植村直己さんが北極圏1万2千キロの時に越夏したケンブリッジベイを経由して、目指すゴールはジョアヘブン。ソリを引いて、1500キロの単独徒歩行だ。
◆今はみかん収穫の最盛期、収穫に励みながらも、仕事終わりにはトレーニングとして畑でタイヤを引いて北極用の身体に仕上げ、冒険の準備を進めている。5年前、地平線報告会の場で僕は言った「俺が冒険をするのは100%自分の為」その気持ちは18歳で冒険を始めてから今でも一貫している。好きだからやる、やりたいからやる、そんなシンプルな気持ちでこれからも僕は冒険を続けていきたい。(関口裕樹 32才になりました)
■あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします! 昨年12月23日に息子が生まれ、母になりました。予定日より10日早かったため、2666gと出てくるにはちょうどいい(?)サイズでした! 陣痛から分娩までは、約10時間かかりました。最後の2時間は地獄だ……と思ってしまうくらい痛かったです。何人も産んでるお母さんすごい!
◆なんとか痛みを乗り越え、生まれたばかりの息子を抱っこしたときは、すごく幸せな気持ちになりました。今は赤ちゃん中心の生活で、1〜3時間ごとに寝たり起きたりするのに合わせて世話をしています。毎日寝不足ですが、わが子のかわいい表情や仕草で癒されては頑張っています。仕事では13才〜15才の子たちに関わっていますが、どの子も大切に育てられた1人なんだなーと実感しています。まだまだ道のりは長いけど、健康第一で、自分のやりたいことにチャレンジする子に育って欲しい。そして、もう少し大きくなったら、息子を連れてエモーンに会いに行きますね!(静岡 クエこと杉本郁枝 中学理科教師 四万十の仲間)
■2020年元旦。爆弾低気圧で大荒れの宗谷岬に僕は立っていた。気温マイナス10度。風速20メートルの風が吹き荒れ、体感気温はマイナス30度。ちょっとした南極のような感じで心地良い。この遠征は僕にとってウケイ(注:古代日本で行われていた占い)のようなものだ。札幌からソリを引いて400キロメートルを歩いて宗谷岬に到達し、日本最北端の初日の出に南極の誓いを伝える。その為にこの地にいる。
◆去年は白瀬矗中尉の足跡を伸ばしての南極点徒歩到達に挑戦する予定だったが、出発1か月前という直前のタイミングで、出発地点の大和雪原に立つ為にチャーターする飛行機会社から、翌年への急な延期を一方的に告げられた。資金もある、装備もある、体力も万全。自分の周りの全ての環境が、南極行きを待望しているなかでの決定は断腸の想いだった。だが起こったことは変わらない。翌年に変更せざるを得ないなら、どう動くか、どう実現するかだろう。
◆冬の北海道を歩くことにしたのはトレーニング目的もある。普段から鍛えることをベースに生活しているが、極地をソリを引くというのは特殊な運動だ。一番は同じようにソリを引いて歩くことに限る。今まで毎年極地遠征に行き鍛錬してきた。それを維持せねば次の南極点は達成できない。また多少は耐寒訓練にもなると思った。行程では気温マイナス18度までしか下がらなかったが、ぬくぬくと家で寝るよりもテント泊しながら行動するほうが良いのは間違いない。
◆札幌入りするとまずは蝦夷一宮である北海道神宮に昇殿参拝し、出発は札幌の赤レンガ旧北海道庁舎とした。白瀬矗中尉は札幌道庁で働いていた時代がある。明治期よりあるこの旧庁舎に彼も通っていたのか、と思うと感慨深い。もしかしたら白瀬の残留思念に僕は憑依されているかもしれない。
◆雪の上でソリを引きに来たのだが、北海道は例年になく雪が少なく、札幌に至っては12月下旬に関わらず積雪がゼロだ。台車をソリにとりつけ十分な積雪がある場所まではガラガラと引いて歩く。台車にソリを乗せて歩く姿は道行く人から見たら滑稽に見えただろう。13日間かけて宗谷岬までたどり着いた。大荒れで初日の出を見れなかったがそれでも構わない。大事なのは自分の意思でここまで来たという事だ。宗谷岬のモニュメントで見えない初日の出に二礼二拍手一礼をする。今年は白瀬の夢を完結させる年にする。
◆正月は秋田の実家に戻った。80過ぎの祖母は戦後、樺太から稚内経由で引き上げてきた。もう少し遅かったらロシアの行動により樺太の人間になってしまうところだったと、懐かしそうに語っていた。こんな話を僕にしたことはなかった。派手な海外遠征だけでなく、日本の事を更に知る必要を感じる。(阿部雅龍)
■明けましておめでとうございます。昨年最後の報告会に参加することができ、とても良い2019年の締め括りができました! 久しぶりに報告会に出席させて頂きましたが、生のお話を聞けるということはなんと素晴らしいのだ、と感激しました。文字で読むよりも数百倍心に響くものが違います。
◆大竹さんが旅を始めてから20年。当初、写真家という道への強い覚悟や自分のテーマ決めに苦心された中、これだと思った事をまず実行された結果、人との出会いに導かれて今日まで続けてこられた事、勝手にも自分の現状と照らして聞き入りました。不安な中でも大竹さんの行動力と自分の感性を信じてきた結果が今にあるのではないかと推察致します。
◆私は本年で社会人10年です。20代までは考えるより行動。何事もやってみて考えようの精神でしたが、社会人としての年数を重ね仕事にどっぷりと浸かる日々が続くと、会社のビル、電車、PCという箱の中に留まって視野が狭くなっていた、と思います。また長く馴染みすぎて今度はそこから出ることが怖くなってもいる自分がいます。一度そうなると昔持っていたドキドキワクワクする気持ちや、好奇心のセンサーも鈍くなるようで、もっと知らないこと、やりたい事やらなくては!という意欲が小さく、仕事があることを言い訳に範囲の狭いで面白さを求めていた気がします。
◆大竹さんの広大な自然の写真、素敵な師匠との交友のお話、そして大竹さんの生きたお話を聞いて小さく固まった心を揉みほぐしてもらった気持ちになりました。私も今人生の分岐点で大いに悩み、自分に無かったことは行動力だと思います。私事ですが大いに悩んだ結果、1月に入籍し、4月からは喜界島という島に移ります。これから素敵な出会いがある事、美しい島の景色を見れる事がとても楽しみです。(四万十の仲間うめ 山畑梓)
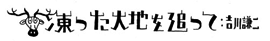
■快晴、風速5ノット、早朝のアンデス、ツプンガティート山頂クレーター5600mにヘリコプターがゆらゆらと着陸する。AS350 B3ヘリコプターのサービス高度を1000m近く高い地点での着陸にパイロットはかなり神経を尖らせている。この日のためにヘリエンジンを調整、椅子など不要なものを一切取り除き、完璧な天気を待っていた。3500mに作った燃料デポでボーリング機材、メンバーが待機し、往復最低量の燃料を積み、4往復する。
◆1回のペイロードは、5600m地点の気温がマイナス15度として約100kgだ。ヘリ高度飛行記録ではすでにこのB3が14年前にエベレスト頂上に触れているが、実務的な飛行高度としては高所に強かったラマやこのB3の5000mぐらいが限界だ。そう、ヘリや人類活動には、5000m〜5500mあたりに大きな見えない壁がある。永久凍土の下限高度も熱帯では5000m台なので、この高さとの攻防が鍵になる。
◆私のチリでの役目は、天文台建設のほか、チリ大学の修士学生の指導とチリ政府の永久凍土ネットワークの設置がある。今回のツプンガティート山頂ボーリングは、サンチアゴの水資源を考える上で、永久凍土の状態を知る第一歩になる。気温の低い早朝にやってきて、ボーリングを1時間以内で終わらせ、温度計を設置するミッションだ。
◆今回持ち込んだボーリングセットはあらゆる地質を掘れる最大3mまでの自作ポータブルセットだ。もともとは1960年代にアポロ計画で真空の月の表面を掘った仕組みを真似たものだ。チリにくる直前、急ぎモスクワに寄り、長年ロシア科学アカデミーに置いてあるシベリア辺境ボーリングに使っていたものを持ち込んだ。穴掘りに遅れが出ると気温が上昇し、マイナス5度まで気温が上がれば、ヘリが着陸できなくなる。そう、密度の低い暖かい空気だと私の体重では重すぎるのだ。そのため歩いて下山する準備もしてきた。
◆今回一緒に穴掘りを手伝ってくれているのが、氷河学者のジーノだ。彼とは30年以上前に大学で一緒だった。去年は、うちのトナカイファームに奥さんと共に逗留したが、今回は彼の家にお世話になる。週2回ほど近くの標高1200m(高度差450m)の山にトレーニングに行く。60歳前後のおじさんたちが走って登り、降りてくる1時間あまりの間、すれ違う若い人たちに好奇の目で見られる。我々のトレーニングの甲斐もあり、予定通り午前中にサイト建設が終わりサンチアゴに戻る。ほっとするが、来年以降アタカマからパタゴニアまで十数カ所の穴掘りが待っている。
◆チリ政府の仕事もひと段落し、アンデスの未来を考える会議でクスコへ向かう。ここでの一番の渉外は、ペルー環境省の山の研究機関に凍土ネットワークを手伝ってもらう確約をとることだ。最終的にはラテンアメリカのユナイテッドである。今までペルーアンデスでは、カラプナ(5200m)とチャチャニ(5350m)に凍土ボアホールがあり、観測を続けてきたが、できればコルディエラブランカとかペルー全体に広げたい。
◆また、人類が定住的に住んでいる世界最高所ペルーのラリンコナーダ(5100m)の継続的な支援をお願いする。そう、人類は大体海辺の半分の空気が住む限界なのだ。私も半年前、このラリンコナーダで穴を掘り、また、世界最高所の学校に教育機材を設置した。この街は鉱山起源の無法の街で最近警察がくるようになった。ゴミ処理の仕組みがなく、町中ゴミだらけ、まあ、ペルー人も近寄らない悪評判の街だ。それでも学校では、子供達がサッカーを講じている。街には娼婦もたむろし、この高さで人々は平然と人類活動をしているのに脱帽だ。
◆チューニョという、ペルー、ボリビアのケチュアやアイマラの伝統的保存食がある。私はあまり好きではないが、チューニョはインカ以前からあったと言われるフリーズドライ食品でジャガイモをアルチプラーノの冬季の夜間に凍らせて作るのだ。これがこれから温暖化とかで夜間凍結標高が上がると食文化に壊滅的な影響が出る。また、芋は糖分も含んでいるので凍結温度が0度を下回る。これを作るにはアルチプラーノでも夜間十分に冷え込む標高が必要なのだ。これも今後ペルーの山岳地域を考える上で重要な食料問題だと説得する。
◆クスコでの会議という名の連日のコカピスコ飲み会も順調に終わり、チリへの帰路につく。リマでメキシコ人のサマと落ち合い、サンペドロデアタカマに戻る。まず、空港でトヨタハイラックスを借り、来週からのオッホデサラド行きの準備をする。オッホデサラドはアンデスで二番目に高い山で、世界最高所の火山だ。そこにサマと共に行って、穴を掘る予定だ。
◆私の秘密兵器サマはメキシコ最高峰ピコデオリザバのボーリングの時に出会い、その後ファームを手伝ってもらったり、デナリの大蔵隊(注:大蔵善福 デナリでの気象観測を長期間続けている登山家。2006年11月、330回目の地平線報告会報告者)に参加したり、山に強くて性格の良い男だ。これから2週間、高度順応を経て、ドリルセットを携え、暴動の道路封鎖を避けながら、2000kmあまりのドライブの始まりである。(アラスカ大学教授 吉川謙二)
■私は埼玉で中学校の教員をしているのですが、吉川謙二さんとは、私の後輩が計画した南極大陸徒歩踏査が縁で出会い、もう30年くらいになるでしょうか。その吉川さんから1月8日の朝「明日に日本に来て13日まで滞在しますが、10日に中学校を訪ねることは可能です。急なのですが、折り合いがつくようなら教えて下さい」というメールが届きました。これを見て私が万難を排して折り合いをつけようと決心したことは当然ですが、何分学校というところは形式を重んじる面が強くて突発的なことやイレギュラーなことを嫌う傾向があり、質や内容よりも表面的なことから評価・判断する傾向にあるので、明後日という突然のことで大丈夫かなぁと心配しましたが、管理職のおおらかさに助けられました。昨年の秋に20年以上ぶり位に再会した折、私の勤務校で子どもたちに話をしてくれると言ってくれたのですが、こんなに早く実現したこと、そして何よりも約束が実現したことがとても嬉しかったです。
◆実際に世界を歩いて調査研究をしている方が、じかに中学生に話をしてくれるというのは、中学生にとって大変貴重な経験になるはずですが、私としては話の内容以上に、吉川謙二さんという人間を感じてほしいという気持ちもありました。ただし当日は、なんと6時間目に不審者対応特別訓練が予定されていて、折角来てくれたのに間違われたら困るなぁと少々不謹慎なことも考えてしまいましたが。
◆吉川さんは給食の時間から教室に入ってくれて、すぐに打ち解けて生徒と一緒にカレーを食べながら言葉を交わしてくれました。授業の方はアラスカの自然や暮らしを大型モニターに映し出した写真を交えて対話形式に紹介しつつ、自身の調査研究についてまでを幅広く話してくれる中で、吉川さんの住むフェアバンクスは気温の年較差が80℃ほどもあることや、体に群がる蚊を掌で潰すと手形が残るとか、1mも氷が張って冬期は道路になる川がいつまで通れるかを判断する目安は何かなど、興味深いエピソードを交えながら話してくれましたが、この時のテーマは「イメージトレーニング」ということで、それはこれからどのような道に進むとしても、どんな場面においても共通して求められる大事なことであるということを子供たちに強く語り掛けてくれました。自分が何かをしようとするとき、まず自分の動きや予想されることをイメージすることが大事で、もしイメージできないことがあったとしたら、それは準備ができていないということであるということも繰り返し話してくれました。私自身も分かったつもりになっていましたが、改めて原点に戻れたような気持になりました。しかもその夜は、私も長い間「地平線通信」を購読させていただいている縁から、江本さんを交えて遅くまで語り合えたことが今回の訪問に華を添えてくれました。吉川さん、ありがとうございました。(山本宗彦 日本山岳会副会長)
■先月の通信でお知らせして以降、通信費(1年2,000円。1979年の誕生以来据え置きです)を払ってくださったのは以下の方々です。数年分まとめて払ってくださった方もいます。地平線会議の活動は皆さんの志でささえられています。通信費振り込みの際、できれば江本宛てに近況などお知らせください。
田中雄次郎(5,000円)/小泉秀樹(5,000円 カンパ3,000円)/山崎金一(6,000円 通信費3年分)/宮崎拓/大槻雅弘(5,000円 ご無沙汰しております。昨年は90才になられた斉藤惇夫先生=元日本山岳会会長 医師=を1月と9月の2回登山のお供をしました。通信費2年分同封しましたのでよろしく)/新堂睦子(10,000円 通信費2,000円、カンパ8,000円 中村哲さんもある意味では冒険者ですね。冥福を祈ります)/ 櫻井恭比古(10,000円 夫が長い間お世話になりました。体調を崩し文章を読むことが難しくなってしまいました)/菅原茂(10,000円 いつも地平線通信ありがとうございます。通信費1年分と、残りはカンパです)/小澤周平(10,000円 いつもお世話になっております)/梶光一(10,000円 地平線通信をいつも楽しく読ませていただいています。3年分+カンパをお送りします)/北川文夫/土谷千恵子/覚正伴得

■私は4年前から「地球永住計画」というプロジェクトを始めた。地球永住計画は火星移住計画に対するものだ。火星移住計画はNASAや民間で調査研究が進んでいる。その結果分かってきたことは、この地球が命を育むのに如何に奇跡的な星かということの再認識でもあった。液体の水があり、酸素があり、太陽との距離も近すぎず、遠すぎない。オゾン層で紫外線を、磁場で放射線、宇宙線をブロックしている。
◆この奇跡の星の生態系を孫やひ孫の世代にいい状態で繋いでいくにはどうしたらいいのか。自然や宇宙とのつながりを身近な環境の中に再確認するところから始めようというプロジェクトだ。伊沢正名さんは最近偕成社から出版した『ウンコロジー入門』で「地球永住計画」に対するエールのような文章を書いている。
◆「現在の地球環境は、人間社会の発展によって危機的な状況にまで追い込まれてしまったのです。そんな地球に見切りをつけて、新天地で暮らそうという『火星移住計画』を考える人まであらわれるようになりました。しかしそれを実現するには、水と空気と食糧だけでなく、ウンコをあらたなごちそうに変える生態系の命の循環がなければ、安心して生きていくことはできません。……それよりも、いまわたしたちが暮らしている地球には、さまざまな多くの動物・植物・菌類が生活し、絶妙な共生関係をつくりあげ、永遠の命の循環がすでにできあがっているのです。あらたに困難なことを始めるよりも、この地球上の生きもの社会を元気にすることこそ、末永く安心して暮らしていくいちばんの方法です。」
◆私の身近に玉川上水があった。これまで自分の足で歩いて、見て聞いて、自分の頭で考え、自分の言葉で表現してきた。自分でフィールドワークができることは自分たちでやろうと思い、玉川上水の自然観察、自然調査を始めた。しかし、自分ではできないことがある。宇宙や太陽系の誕生、DNAやAIなどは自分たちで観察、実験、調査は難しい。それはその道のエキスパートに聞くのが一番いいだろうということで、これまでいろいろな専門家にお願いして、公開講座、公開対談を開いてきた。その公開対談に、伊沢さんを昨年、一昨年と2度もお呼びした。開口一番、ガツンとやられてしまった。
◆「関野さん、人間以外の生きもののために役に立つことを何かやっていますか」と聞かれた。ウーンと唸り、眼が泳ぎながら何か探そうと懸命になったが、声が出なかった。再生可能エネルギーもゴミの仕分けも、エコだと思ってやっていることはすべて他の生きものにとっては何も役に立っていない。「伊沢さんは何かやっているのですか」と尋ねると、表情も変えずに、でも自信をもって、「野ぐそをしています」と言った。伊沢さんは20才の時に自然保護運動を始めた。23才の時、キノコ図鑑の巻末の以下の解説に、目から鱗が落ちるほどに感動した。「枯れ木や落ち葉という植物の死骸、そして動物の死体やうんこは、キノコ(菌類)が腐らせて分解し、土に還し、その養分で植物が生き続け、その植物を動物が生き、そして菌類も生き続けてきた」
◆彼は自然保護で最も重要なことは、植物、動物、菌類によるいのちの循環を守ることではないかと考えるようになった。翌年から自然のためになる野ぐそを始めた。25才の時に、キノコや、苔、変形菌の写真家になった。本も20冊以上出版し、一流の写真家になっていた。しかし、写真では自然の中での命の循環を伝えることに限界を感じ始め、56才の時に、ノグソの大切さを直球勝負で訴えようと、「糞土師」を名乗るようになったのだ。
◆一方、私は20代、30代は20年間、ひたすらアマゾンを中心に南米を歩いてきた。アマゾンやアンデスにはむき出しの自然のなかで、自然と一体となって暮らしている人々がいる。彼らの村に入り、同じ屋根の下で寝て、同じものを食べて暮らすことを許して貰った。アマゾンの民族、ヤノマミとは40年来の付き合いだ。彼らの村に着くと、家の中に私のハンモックを吊る場所を空けてくれる。彼らの家はシャボノと呼ばれ楕円形の巨大家屋だ。村人全員100〜150人がその1軒の家で暮らしている。
◆ハンモックに横になって周囲を見渡して、いつも思うことだが、周囲にあるものは見事に素材が分かるものばかりだ。家を作っている屋根、柱、梁、柱や梁に載っている籠や漁網、ひょうたん、弓矢や糸巻き棒、燃えている薪、ハンモック等々。すべて自然から素材を取って来て、自分で作ってしまうのが彼らの流儀だ。それに対して都会で暮らす私は、自然から素材を取って来て自分で作ることはない。
◆作ったものはいずれ壊れる。バナナ、イモの皮、魚、動物の骨などと共に森に捨てられる。しかし、いつの間にかなくなっている。動物たちが持っていき、ムシや微生物が分解して土に還るのだ。私たち文明社会では邪魔者扱いのごみというものはない。ヤノマミ社会では、ヒトも自然の循環の輪の中にいるのだ。
◆地球永住計画では、玉川上水に着目した。アマゾンに比べると小さな自然だ。しかし保全生態学者の高槻成紀先生と歩いて見ると、草本が繁茂し、虫や鳥が飛び、動物たちが、動き回っている。その生き物たちがどのように繋がっているかはほとんど分からないと言う。「ほとんど分かっていない」と言う言葉に、私はすぐに反応し、血が煮えたぎった。高槻先生の指導があれば、大した器具がなくても調べられると聞いて、熱くなったのを覚えている。
◆どこにでもいるタヌキ、糞虫を中心に、調べ始めて4年近くになる。タヌキはトイレを持っている。もちろんノグソだが、同じところに糞をする。貯め糞という。その糞を調べれば食性、行動半径なども分かる。糞があれば糞虫、ダンゴムシ、ハエがやって来る。タヌキが草木の実を食べれば、糞の中に種が残り、いつか芽を出し、群落ができる。そこに様々な虫や動物もやって来て、その土地特有の生態系ができる。
◆今まで辺境の伝統社会の視点から文明社会を見てきた。今回はタヌキや虫の視点という、私にとっては新しい視点で文明社会を見れるのではないかと思った。すると伝統社会の視点も、タヌキや虫の視点も文明社会が同じように見えてくる。伝統社会は自然の循環の中に組み込まれているが、文明社会はその環から外れていることが分かった。同じように野生の動植物の視点から見ても、野生の生きものはすべてが繋がっているのに、文明社会は野生動植物の循環の環から外れているのだ。
◆文明社会は、野生の動植物がいなければ生きていけないのに、野生動植物は文明社会を全く必要としていない。むしろ破壊者として、野生の動植物の多くを絶滅に追い込んでいる。そのことをクリアに気づかせてくれたのが伊沢さんだ。最新の著書『ウンコロジー入門』の帯の文章を、光栄にも伊沢さんから依頼された。そこで書いた文章を以下に記す。
◆「伊沢さんは私の師匠だ。『ノグソをしないヒトは、命の循環から唯一外れた生きものだ。』と気づかせてくれた。」まさにそうなのだ、ヒトは自然なしには生きていけないが、自然は文明の恩恵を受けているヒトを必要としない。しかし、アマゾンのヤノマミのように野ぐそをすれば、少しは自然の循環の環に入れる。伊沢さんはそのことをあらためて気づかせてくれたのだ。
◆また伊沢さんは農文協から『うんこはごちそう』という絵本を出している。偶然だが、私も同じ出版社、同じ編集者で『カレーライスを一から作る』という絵本を出している。武蔵野美大の学生と皿、米、野菜、スパイス、塩、鳥やウサギなど材料をすべて一から作った。5年間続けて映画もできた。毎年問題になるのが鶏やホロホロチョウ、ウサギなどの動物を屠る時だ。同じ生きものでもコメの収穫の時は鎌で稲を刈る時、嬉々として行う。それが動物となると、屠る時だけ参加しない者もいるし、屠る学生、それを見る学生も深刻になり、悲痛な顔をしている。
◆学生たちは、生きるために、他の多くの生きものを食べて、命を奪っていることを実感する。どうやってそれらの命にお返しをするか。私も学生も「いただきます」「ごちそうさま」と言って生き物たちに感謝して、食べ物を無駄にせず食べ尽くそうということで済まそうとする。しかし、伊沢さんは食べたならば、その命に対して責任がある。そして命を返さなければいけないという。伊沢さんの信念が以下の言葉に現れている。「食は権利、ウンコは責任、ノグソは命の返しかた」。(関野吉晴)
■1月1日謹賀新年! ドルポで新年、不思議な感じ。今年も宜しくお願いします! シェーには行けなかったけど、サルダンの昔のゴンパを教えてもらって行ってきた。風キツい中サルダン帰って来た。後半村人と一緒に歩いたのがとても良かった! 1月2日レスト。屋上にテントはる。部屋寒い、千早(稲葉さんの住む大阪の村)と同じ太陽があるとテントの方が暖かい。
◆1月3日雪降ってきた。これから本格的な冬、厳冬期始まる。どうなるのか? 1月4日3日ぶりに晴れた。これからの過ごし方や、資料作りを考える。ドルポ伝統の織物のセッティングが始まった。ベース作りは外でやっていた。 1月5日織物見学予定だったけど、待ちぼうけした。いつも予定は未定。 1月6日雪降ってきた、散策中止。屋上のテント内にいる、昼間はここが一番暖かい。
◆1月7日今朝も雪降ってる。15cm〜、村人は、屋上や水汲みの道を雪かきしている。村人と一緒に雪かき、めっちゃはやい! スコップ持参で来たけど、追いつかず。冬道を聞いた。天気良ければ明日出発?! 今雪積もってるけど。ドルパパ強し! 1月8日今日も小雪が舞っている。昼から雪散歩予定。昨日の人は出発してないと思う。 1月9日昨日は強風で散策中止。
◆昨夜は家ごと飛びそう?だった。今朝は雪が吹っ飛んでる。1月10日 4日ぶりの穏やかな朝、快晴! 読経が聞こえる、今日は満月、プジャがある。満月プジャに心があらわれた。月に一度村人揃う貴重な時間、会う事が大事だと思った。(稲葉香)
地平線通信488号(2019年12月号)は12月11日印刷。封入し12日新宿局に渡しました。伊藤幸司さんの素晴らしい報告会についてのレポート、服部文祥さんの「犬との長い長い散歩」の記事など読ませる原稿が多く、この号も16ページとなりました。一箇所訂正です。伊藤幸司さんの「報告者のひとこと」の見出し【「糸の会」は「あるかす探検学校」のシニア版】の「あるかす」はもちろん「あむかす」の間違いです。お詫びして訂正します。なお、伊藤さんの「山旅図鑑」は、以下のホームページでご覧ください。驚くべき成果です。
糸の会 & 伊藤幸司……ホームページ「山旅図鑑」
http://itonokai.com/new_gallery-index.html
■通信の印刷、封入仕事に参じてくれたのは、以下の方々です。今月もほんとうにありがとうございました。
森井祐介 中嶋敦子 落合大祐 今井友樹 伊藤里香 石原玲 竹中宏 松澤亮 光菅修 江本嘉伸 高世泉
第24回 2019年は、世界に変化(エポックメイキング)のあった年として歴史に記憶されるかもしれません。9月の国連会議での、16歳のスウェーデン人少女グレタ・トゥーンベリさんの演説は世界中に流れました。「私たちの今と未来を奪わないでください。何もしない大人を許しません」と温暖化対策に有効な決断をできない世界の指導者たちに強く訴えました。
東日本豪雨災害、アマゾンとオーストラリアでの連続森林火災、プラスチックゴミの海洋汚染、約100万種の生命絶滅危機説などのニュースが続いたのも少女の声に注目が集まる後押しをしたのでしょう。多くの若者が呼応し行動しました。イオン電池の開発でノーベル化学賞受賞の吉野彰さんはこの現象に、世界が変わるスタートになる期待を語っていました。
1992年、リオデジャネイロ地球環境サミットでの13歳の日系カナダ人少女セヴァン・スズキさんの演説を思い出します。「元に戻せないものを壊すのはやめてください」との訴えは、環境活動をする人たちの間で語り草になりました。27年後、少女の訴えはより強い言葉になりました。反発の声も少なからずありました。大人たちは何もしなかったわけではないのですが、豊かさを手放したくない欲望の強さとそれを支える仕組みの複雑さの前に、敗退の連続でした。不公平な富の偏在のために、人類一致の協力ができなかったのも事実です。
1992年当時、国連への供出金トップだった日本は地球環境問題への取り組みのリーダーとして期待されていました。私自身の地球環境との私的な関わりも世界と日本の状況に不思議とシンクロしていました。
1982年1月、私は地球温暖化の前兆を体験しました。1981年、東京農大探検部の創部20周年活動として、オリノコ、アマゾン、ラプラタ川をつないで南アメリカをカヌーで縦断しました。この年、あと2つの目的がありました。アンデスの6000m級の高峰10座の登山と世界一周河川行のゴール予定地、パタゴニアとフエゴ島の偵察です。12月にアコンカグア峰に登った後、1月に南米南端のパタゴニアにやってきました。天を衝く角のようなパイネ山群を一周するトレッキング中、氷河が溶けてパイネ川が増水し、橋が流されてしまいました。渡らないと帰れないので筏を作りましたが、すぐに沈み泳いで渡りました。氷河混じりの水は凍るように冷たく、体は凍えアマゾンのナマケモノみたいに超スローでしか体が動かず命からがらでした。「最近暖かくて氷河が溶けている」とは地元の人に聞いていたのですが、まさか橋まで流されるとは予想できませんでした。パイネの北の岩峰フィッツロイ峰登攀に来ていた名クライマーの長谷川恒男さん(注:1981年10月第24回地平線報告会「アコンカグア南壁冬季単独登頂」報告者。1991年ウルタルII峰で雪崩に巻き込まれ星野清隆と共に遭難死)にこの話をしました。
帰国した5月のある日、長谷川さんの紹介で、この体験に興味があると朝日新聞科学部の記者から電話がありました。「近年、世界中の氷河が溶けている情報があり取材しています。ついては君のパタゴニアで泳いだ話は面白いので聞かせて」と取材を受けました。後日、世界の氷河溶解の連載記事の導入にこの話が使われました。後年参加した植林NGO『緑のサヘル』の理事で、地球環境問題にさきがけた記者石弘之さんに「そうか、山田くんは温暖化を最初に体験した日本人かもしれんな」と笑われました。温暖化しているかどうか、当時は専門家の間でも意見が分かれていました。
アマゾンの森林減少とパタゴニアの氷河溶解を体験したので、夢の計画「青い地球一周河川行」を実行する決心をしました。1980年アメリカ政府編集の「西暦2000年の地球」は地球環境問題を網羅して予測していましたが、情報不足は否めませんでした。ガイア仮説のように地球を一つの生き物に例えると、森は肺、海は心臓、川は血管。世界を河川から観て回れば地球環境報告(地球血液検査)ができると考えました。1985年6月、セネガル川河口をスタートしました。
1980年代は、川を旅する線の時代でした。1985年ニジェール川、干ばつのため飢えるアフリカで痩せ細り骨と皮だけになった子供達に出会いました。1990年代は木を植える点の時代でした。1991年から1996年まで、 NGO『緑のサヘル』に参加しチャドで砂漠化防止植林をしました。現地の人たちと泥水にまみれ汗を流す日々でした。
1997年から2004年まで、四万十川で山仕事ベースにナイル源流ルワンダでの植林支援をしました。2000年代は、流域圏作りの面の時代。2001年、西土佐環境文化センター四万十楽舎に参加。多様な自然と共生する循環型流域圏の日本モデルと持続可能森林経営の国際モデル作りに取り組みました。地元高知県の取り組みへの手伝いでもあり、くる依頼は断らないようにしました。東京、外国からの訪問者も毎週のようにあり、アフターファイブとウィークエンドは全て他人に予定をいれられるという恐ろしいことになっていました。
司馬遼太郎の『坂の上の雲』の秋山真之を真似て「1日休めば、地球環境の解決が1年遅れる」とウソぶき、とうとう2010年には心身ともにパンクしました。今反省することは、急な結果は望めないということ。スマホはタッチですぐ答えをくれますが、自然相手は100年の計、200年の画が要ります。壊れたものを戻すには同じ時間が必要のようです。
ひょっとするとホモサピエンスの20万年の歴史を反省する20万年の未来計画がいるのかもしれません。ただし現状判断と行動決定は早い方がいい。私自身は、いまここで一人でもできることから始めた1980年代の初心を忘れないように毎日森で働いて川から観察しています。
振り返ると、確実に世界と日本の時代の風の影響を受けて行動しています。同世代の仲間たちも、時代の波に乗ったり揉まれたりして生きてきたようです。
1980年代のアフリカの川旅が国境封鎖や政情不安で止まった時、パリとロンドンで勉強しながら働きました。パリの人類学者は縄文文明の持続可能性への興味を語っていました。ロンドンの地球生態学の先生は「今、我々は江戸時代の多様性循環型社会を研究している。君も早く帰って、江戸暮らしを勉強した方がいいよ」と諭されました。後年暮らした四万十流域には縄文遊び(狩猟採取)、江戸暮らし(循環型社会)の残影が残っていました。
1992年の地球環境サミットで行動計画アジェンダ21と森林原則声明を採択し、気候変動と生物多様性に関する2つの条約締結の時、私はNGO緑のサヘルに参加しチャドで植林中でした。2つの条約の成果に森林の果たす役割は大きいとされていました。
1993年、TICAD(アフリカ開発会議)で日本にやってきたマリ人NGO職員の通訳をした時のことです。ある講演会場で「わたし達にできることはなんでしょうか?」との日本婦人の質問に「日本の方に一番お願いしたいのは自分たちの暮らしを見直してほしいことです。ここの豊かな暮らしをアフリカで真似したらすぐに資源が尽きるように思います」とマリ人は答えました。当時南々協力とか民際協力と言われ、最先端技術より適正技術(オルタナテイブテクノロジー)の見極めが注目されていました。
1997年からナイル源流の国、ルワンダで植林事業を始める時はいい森といい川のあるところを日本のベースにと決めていました。東京の役人、記者、学者の知人の多くが四万十を勧めてきました。同じ年、日本は世界に向かって大きな役割を果たす決定を幾つかしました。COP3京都議定書(国連気候変動枠組条約締約国第3回会議、日本に温暖化対策の指導的役割期待。アメリカ、中国不参加)で温暖化対策の主導を宣言。同年、四万十川、空知川流域の森林計画区、持続可能な森林経営の国際モデルに。京都の環境NPOとはその後しばらく情報交換し行き来しました。これらの行動計画によく使われた3大言語が持続可能、多様性、適正技術でした。最近SDGs(持続可能な開発目標)のキャッチフレーズを頻繁に目にします。30年変わらない課題が続いているようです。
2001年、米国同時多発テロ。同年、「環境と情報の世紀」in 四万十と銘打って改革派4知事の鼎談が旧中村市(現四万十市)でありました。四万十の森を持続可能な森林国際モデルにと高知県知事は宣伝しました。情報公開、地方主権、住民参加が流行り、産官学民の協力が謳われていました。四万十の仲間には過労死した役場職員、過労自死した地方政治家も出るほど頑張った人たちもいました。2002年、ヨハネスブルグ地球環境サミット(米国のアフガニスタン、イラク攻撃で世界の話題にならず)。2005年、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)とゴア元米副大統領ノーベル平和賞(地球温暖化が人為によると研究者全員最終判断)。1990年代の冷戦終結による平和志向の環境問題への協調路線VS文明の衝突のせめぎあい路線は、2000年代に「衝突」へ大きく舵を切りました。
2010年、中国が日本を抜いて世界第2位のGDPに。2011年、東日本大震災。2012年、再びリオ地球環境サミット(20年前ほど話題にならず、ムヒカ・世界で一番貧しいウルグアイ大統領の名演説)。2015年、COP21パリ協定(COP3京都議定書成果を上げられず終了)。
2020年元旦のNHK特集では環境問題は2030年までの10年が最終リミットと再度確認していました。翌2日アメリカ軍がイラクでイラン人司令官殺害のニュース。1990年代以降の歴史をデジャビューで繰り返すか、違う選択をするか。人類一人一人の重大な責任を問われる年明けです。
グレタさんやそれに呼応した世界の若者たちの今後の行動に期待します。できれば「遊び心を大切に」してほしい。1990年代、「アフリカで飢えて死んでいく子供達をたくさん見たので、これからは木を植えます。一緒にどうですか?」と言った時、地平線会議の先輩の戦場ジャーナリスト故恵谷治さんは「そうか、それは俺の役割じゃない」、冒険王バイクライダー賀曽利隆さんは「うん、僕は死ぬまでバイクで世界を走る」と言いました。爽やかな風を受けた心地よさを感じました。
20代始めに地平線会議の立ち上げに関わり、地球を庭のように風の人となって遊ぶ先輩方に出会えたことは、代え難い財産です。環境を良くする行動はあくまで地球のグランド整備。ゴールは平和で良い環境になった地球を楽しく遊び暮らすこと。地球環境の整備は急を要しますが、遊び心を自分の中に持ち、他者の遊び心に拍手を送るゆとりを持ち続けたい、と思っています。
地球環境サミット(1992年)の当時、緑のサヘル代表の高橋一馬さん(農大の先輩、当時の環境NGO界のカリスマ)と私はこのサミットに参加を誘われましたが、「そういうのは、できる人に任せて、我々は現場で汗を流そう」と話しました。今も現場に身を置く姿勢は変わらずに持ち続けています。(東京農大探検部OB 山田高司 いまは奥多摩で山仕事に明け暮れる日々)
■毎月毎月地平線通信を出していると、新年だからといって「年賀状」を出すのはどこかダブるような気がして7、8年前から賀状を遠慮させてもらっている。しかし、いただくのは勝手ながら嬉しいものだ。いちいち返信できないが、ありがとうございます、とここで言わせていただく。
◆今年も年明け早々、トランプの指示によるイランの指揮官の殺害、イラン軍の報復、そして、カルロス・ゴーンなる実業家兼カリスマペテン師による奇妙奇天烈なベイルート脱出劇とその後の国際記者会見。さあ、東京オリンピックだ、というにはなんとも落ち着かない日々が続いている。
◆オリンピックというものを、「絶対素晴らしい」ととらえる考え方は1964年の時も私はとりませんでした。どう関わっても個性の抹殺につながる面はある、と考えたからです。もちろんアベベの快走には感動したし、目の前で5つもの金メダルをとったレスリング(当時は女子種目はありませんでした)の活躍は大したものでしたが。
◆何より1964年にひかれたのは、選手村食堂の食事でした。あんなに美味しそうなものはみたことがない。最後まで試食する機会はなかったけど。表紙の文字はアイヌの人の言葉で「大地からの手紙」の意味だそうです。(江本嘉伸)
 |
ナツとブンショーの長い長いお散歩
「犬という異種の生きものとコンビを組めるってのは、ホモサピエンスの特異な能力だと思うんすよ。それを検証したくて」と言うのはサバイバル登山家の服部文祥さん(50)。昨年10月1日から11月25日にかけて愛犬のナツ(雑種、3才)と北海道を縦断散歩しました。 宗谷岬から襟裳岬まで石狩山地と日高山脈を通るルート上にあらかじめ何ヶ所かに米をデポし、道中は財布も持たず、自給用の釣り竿と銃だけを持つ独特のスタイルです。出発して間もなくコンパスを失くしたり、焚き火のことで森林官とやり合ったりしますが、「とにかく北海道はエモノの密度が濃い!」とタンパク質補給には困らない旅が続きます。 子供の頃から憧れていた犬との旅は、種(しゅ)や、いのちを考えさせる時間でもありました。いち早くシカを見つければ早く撃てと促し、仕留めると神妙な面持ちになるナツですが、シカ肉は大好物でもキツネの肉は食べません。その様子に断絶を感じる文祥さん。0才の時から山に連れていき、北海道も何度も来ているナツは身軽に走り回ります。「オメーの分まで食料はオレが持ってやってるんだゾー」とボヤきつつ、夜はナツにマッサージをしてあげるのでした。 山中で数時間姿をくらましたナツを待っているときは、心配と不安と、行動予定を乱される腹立ちと空しさに襲われました。「この旅は、実はナツがオレにそうさせるよう仕組んだのかも?と思った」という文祥さんとナツの二匹の旅の顛末を語って頂きます。 |
地平線通信 489号
制作:地平線通信制作室/編集長:江本嘉伸/レイアウト:森井裕介/イラスト:長野亮之介/編集制作スタッフ:丸山純 武田力 中島ねこ 大西夏奈子 落合大祐 加藤千晶
印刷:地平線印刷局榎町分室
地平線Webサイト:http://www.chiheisen.net/
発行:2020年1月15日 地平線会議
〒160-0007 東京都新宿区荒木町3-23-201 江本嘉伸方
地平線ポスト宛先
pea03131@nifty.ne.jp
Fax 03-3359-7907 (江本)
◆通信費(2000円)払い込みは郵便振替、または報告会の受付でどうぞ。
郵便振替 00100-5-115188/加入者名 地平線会議
|
|
|
|
|
|