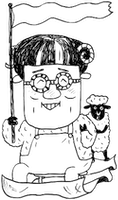
■今回の報告者はウールクラッサー(羊毛鑑定士)の本出ますみさん。京都で「原毛屋」を営み、羊にまつわる雑誌「SPINNUTS(スピナッツ)」の編集出版もされている。「Spin(紡ぎ)」と「Nuts(夢中になる)」を合わせた言葉だそう。染織の世界でよく知られた本出さんのお話を地平線報告会で聴けるなんて、想像していなかった。ありがたいです。サポート役は親友の本所稚佳江さん(映画『プージェー』プロデューサー)。40年前に京都の川島テキスタイルスクールで隣に座ったのがご縁とのこと。原毛といえば、もちろん私も紡いだことがある。糸車を踏みながら少しずつ原毛を引き出して撚る。タイミングが難しい。ショール一枚分の織り糸を紡いで終わってしまった。フェルトを作ったのもずいぶん前。この場にいるのが、ちょっと恥ずかしいような後ろめたいような。でも、本出さんはそんな気持ちを大らかに吹き飛ばしてくれた。お話は、こんな言葉で始まった。「2025年、世界は大変だ。でも今この瞬間の『暮らし』が大切。羊は『暮らし』そのもの、『衣食住』。だから、スピニングをしましょう!」
◆挨拶のあと、前列に座る江本さんのジャケットに興味津々の本出さん。生地にほんの少し触れて「メリノの24マイクロンくらい。盛岡のホームスパンだと思う」という言葉に会場は大きくざわめいた。隣の山田和也さんのジャケットは、「30マイクロンくらいのチェビオット。たぶんイギリス製」。パタゴニア製のセーターを着てるのは長岡竜介さん。「コリデールの30〜33マイクロン。ナチュラルカラーだから在来種」。みなさん、お洒落だ! メリノ、チェビオット、コリデールは羊の種類。マイクロンとは糸の断面の直径の単位で、1マイクロンは1ミリの千分の一。蓄積された知識が滲み出る。「目で見てわからないことも手で触ればわかるんです」の言葉が素敵だ。人間の髪の毛は90マイクロンくらいだというからその繊細さがわかる。本出さんにどんどん引き込まれていく。
◆次は、目の前のフワフワの羊の毛の説明。「刈り取ったばかりの一頭分の羊の毛をフリースといいます」と、一番大きなジェイコブという種のフリースを広げる。ひとつながりのものという意味もあって、群れになってつながっているという使い方もあるとのこと。「ユニクロがフリースという言葉を使っちゃった。こんな普通名詞を商品名にしたらあかんやろ!」と本出さん。そうだそうだ! たてがみのある原種のフリースは犬くらいのサイズ。羊が家畜化されたのは一万年前。メソポタミアのあたりで始まったとのこと。ジェイコブは二千年前にはすでに存在していたそうだ。フェニキア人もバイキングも羊を船に乗せ大海へ乗り出した。陸の道は遊牧民が連れて歩いた。船に乗り大地を歩く羊を想像してみる。世界中に伝播し、それぞれの地域で品種改良が進んで、気候風土に合った在来種となっていった。日本には、珍獣というレベルで何度か来ているが、家畜としては定着しなかった。
◆羊はどんな恵みをもたらすのか。羊毛(ウール)から糸、フェルト(原毛を圧縮して作る不織布)が作れる。断熱材としても使われる。分解して堆肥になる。古着から毛をほぐして反毛(はんもう:リサイクルウール)にもなる。乳と肉。今回の参加者全員に「SPINNUTS」モンゴル特集号が配られたのだが、羊を屠る記事が見どころだと本出さん。夏は白食、冬は赤食。夏は乳を絞り、チーズやヨーグルトに加工して食べる。秋から冬には、歳をとった羊から一頭ずつ屠る。すぐに内臓を塩ゆでにして食べる。肉は、そぎ切りで紐状にしてゲルの中に干す。干し肉は湯で戻して肉うどんにして食べる。食べつなぐことのできる安心感。今度はアフリカの羊の写真。太い尾に入っているのは脂肪だ。この脂肪が欲しいのだ。脂尾羊という。ボンジリのような味とのこと。モンゴルでもみんな喜んで食べていた。毛をバーナーで焼き切って塩ゆで。そぎ切りにして、それを薪の火で直にちょっとあぶって油がパリッとするのが美味しいそうだ。モンゴルでは焼くことはない。胃袋の中に頭とか蹄とか野菜とかを入れて塩ゆでにすることもある。モンゴルの味付けは塩だけ。ジンギスカンという料理はありえない。
◆そして、毛皮。モンゴルの自然保護官が雪の中、寝袋だけで野宿している写真が映しだされた。シープスキンを内張りにしたデール(モンゴルの民族衣装)をかぶって、毛布を掛けている。マイナス60度だが羊の毛は凍らない。極寒でも生きていける。反対に、灼熱の砂漠でも羊毛は必要とされる。モロッコ、サハラ砂漠のトゥアレグ族が纏うのはウールの外套。陽射しから身体を守る。人の身体を守る保温性。自分の体温とほぼ同じ温度を保ってくれる。
◆そのほか、毛から採れる脂(ラノリン)は、化粧品や石鹸、ろうそくなどの原材料となる。衣食住、全部羊が与えてくれる。羊の歴史は人間の歴史と表裏一体。チンギス・ハーンが短期間にモンゴル帝国を作れたのも、羊を連れていたからだ。家畜とはライブストック(Livestock)。生きている在庫というそうだ。
◆羊への熱い思いに溢れた本出さんだが、「原毛屋」になった経緯が面白い。織物会社の龍村美術織物で秘書をしていた1983年、インド旅行に行く途中で、オーストラリア・シドニーに一か月滞在。羊を飼っているご夫婦と知り合う。妻は日本人の信子さん。フリースをポンと椅子の横において糸車で糸を紡いでいた。すごい衝撃。毛糸ってこんな風にできるんだ! 輝く美しい金の羊に見えた。この糸紡ぎとの出会いの日に「原毛屋」になると決める。本出さんは自分を信じて行動に迷いがない。帰国時のリュックの中には、もうフリースが3枚入っていたという。かっこいい。本出さんは話す。世界中、どの時代でも糸を作っていた。糸から自分の着ているものも作り出した。糸は世界の共通語だと思う。なのに、誰もがやっていたことが今は趣味の世界になってしまった。趣味の世界のスピニング・染織の方々には勉強家が多いのだ、と。そして、勉強家のひとりは本出さんである。
◆西洋で羊がいかに大切なものであったかがよくわかる絵が紹介された。ベルギーの都市ヘントの聖バーム大聖堂にある12枚で構成された祭壇画(1432年作)。血を流した羊は、人々の罪を贖うキリストの象徴。それを囲む天使、予言者、聖職者、アダムとイブ、聖歌隊、殉教者。羊は精神的なイエス・キリストの象徴であるという考え方。教会における祭壇画が織物の世界で展開されてタピストリー(緯糸で絵柄を表現する織物)となっていったという。タピストリーは宗教画でありメッセージのある絵物語。教会の祭壇画をタピストリーにすることがある。織物は軽くて壊れなくてたたんで持ち運べるから戦地に持っていける。野営しているテントの中でタピストリーを正面に置けば教会になる。聖域になる。織物は持ち運びやすいということが、日本の宝物にもつながっている。
◆どうして日本に大陸からたくさんの宝物がやってきたのか。中国や朝鮮からすると、日本は文化が劣っている後進国。属国として扱うために、文化や国力の違い、文明国であることを見せつけるために宝物を持ってきた。銅鐸や鏡、織物。軽くて壊れなくて持ち運べる織物は重宝された。日本各地で何枚も見つかっている。これは朝鮮通信使の本に記録してあったことだそうだ。運ばれてきた朝鮮毛綴(ちょうせんけつづれ)には風刺をきかせたデザインのものが多かったという。日本史の授業のようで面白い。大陸からの宝物が収められているのが奈良の正倉院。756年、聖武天皇の遺愛の品を収めるための蔵として建てられた。研究し、保存してきた保存課がある。年に一回、正倉院展の前に開封してチェックする。保存課に勤めていた本出さんの叔父さまは、一週間前から食を正し身を清め禊(みそぎ)をし、中に入られていたとのこと。
◆2011年、本出さんは正倉院の染織の宝物調査に参加する。京都在住のアメリカ人フェルト作家ジョリー・ジョンソンさんと大阪府立産業技術総合研究所の皮革の研究員、奥村章先生(故人)が仲間だ。調べたのは正倉院の花氈(かせん:花柄の毛氈)。毛氈(もうせん)というのはフェルトの敷物。真円に近い二つの立派な唐花文様。直径がほぼ1センチも狂っていない。花氈第一号は2.75m×1.39mの大きな敷物。神様が作ったのではないかと思うと本出さん。精密な花柄なので、陶器の技法である象嵌式で作られたとずっと紹介されてきた。また、素材は古品種のカシミヤ(カシミヤヤギの毛)ということになっていた。でも、カシミヤがフェルト化しないことは、趣味で紡ぎをしている勉強家のスピナーたちは経験値でよく知っている。ジョリーさん、奥村先生、本出さんは、そうではないだろうと意見が一致し、研究調査を始めた。フェルトは羊毛を何層か重ねて作るのだが、一層だけで作る薄いプレフェルトがある。このプレフェルトと無撚糸(撚りのかかっていない糸)を並べたり重ねたりして文様を作り出す方法を説明し、はめ込む技法の象嵌式ではないことを検証することができた。2013年の新しい紀要は、「花氈の素材は羊毛で技法はプレフェルト」と書き換えられたとのこと。すばらしい成果だ!
◆研究員としてわかったこと。宝物は最高の職人が作ったと思っていたが、フェルトがはがれている部分もあった。下手な人もいた。非常に親しみを覚えた。千年くらい前の人の息遣い。時間を超えた共感みたいなもの。性格まで想像できる。また、丹念に見ていくと、花弁一枚一枚から同じ呼吸を感じた。一人で作ったと思う。いろいろな宝物を見ると、何人で作ったのかがわかる。工房の規模や特徴もわかる。歪みやゴミのある雑な仕事も見えてくる。いろいろな面白さがある。そして、学者の先生たちがその前の資料を書き写しただけで、検証していなかったこともわかった。自分でやってみる、考えてみることがされないで、本に書いてあることやネットで得た情報だけをコピペして抽出していくと、次の時代に伝える情報が大きく変わっていく可能性があるのではないかと考えていると本出さんは話す。
◆日本での羊の歴史に話は続く。戦国時代、南蛮渡来の敷物で陣羽織を作るというのが大流行した。ものすごく派手な羊毛の敷物(フェルトや織物)で作る。軍服としても外套としても、雨風を凌ぎ体温を保つシェルターとして重宝された。陣羽織を鎧甲冑の上に着ると、かっこいい大将であるということを誇示できる。羊毛製品を一番欲しがったのは侍だった。8世紀頃から日本に入ってきていた毛氈は、江戸時代には80万枚輸入されたという。驚きの枚数だ。銅が大量に流出して幕府の財政を脅かす。たまりかねて、国産品を作ろうと考えた。1800年頃に第十一代将軍徳川家斉の案で巣鴨で羊を飼い、300頭まで増やしたが、1、2枚の羅紗(ラシャ:毛織物)しか織れなかった。江戸時代から明治時代にかけて、長崎、千葉県三里塚などでも試みるがうまくいかない。日本の風土に合わない品種だったこともあるが、一番の問題は羊も牧畜も知らない政府の役人たちの働きぶりだったようだ。明治政府は軍服官服を作るための羊毛が欲しかった。オーストラリアから輸入することにする。そこから、殖産興業として毛織物産業が盛んになっていく。日本の羊の歴史は政府主導。自国生産せず羊毛だけ消費してきた。
◆昭和になり、雨の降る地域でも飼えるコリデールを導入。第二次大戦後は衣料品不足を補うため、1945年からの10年間で100万頭まで増えた。しかし、昭和36年に羊毛が自由化となり、激減した。今、日本にいる羊は2万頭くらいだそうだ。200〜400頭を飼っている牧場もあるが、3〜4頭の羊を飼う自給自足の羊飼いもいる。糸を紡いでセーターにして、年間40〜50万円。糞を蒔いて土壌改良。季節の山菜、干し柿の出荷、お米と野菜を育てて生活している。世界的には本当に特殊。衣食住を全部賄い発展してきた西洋の羊文化と、百年あまりの歴史しかない日本の考え方の違いは大きい。もしかしたら、羊本来の考え方に、なぜか日本の若者が目覚めたのかもしれない。新規就労する若い人も増えているという。興味深いお話だ。羊こそが持続可能な生き方の考え方が集約されたものじゃないかな。食べ続けてきたから生きている家畜なのだ。
◆本出さんは2019年から「ジャパンウールプロジェクト」という活動を始めた。ここ20〜30年、日本の羊の毛はほとんどが放置されてきた。用途がなかった。それをなんとか利用しようと考えて、愛知県一宮市の毛織物工場、国島株式会社の社長伊藤核太郎さんと一緒に立ち上げた。質のいいジャケットが作れるくらいになってきている。日本の羊毛は主に中番手でイギリスの毛に非常に近く、ツイード用に適している。ブランケットや敷物にもいい。「できれば日本の羊の毛で地産地消につながるようなサプライチェーンがつなげるといいなと思っています」と本出さんの声は明るい。
◆ここからスピニングの実演。みんなが本出さんを取り囲む。厚紙で作った直径7センチくらいの円盤の真ん中に菜箸を通し、原毛をひっかけてひょいっと回すと、魔法のようにクルクル糸が紡がれていく。見ているだけで楽しい。回り続けるのが大切とのこと。毛の脂を取り除いて、虹色に染めた原毛が準備されていた。希望者に少しずつ分けてくださった。私自身の経験が甦って来る。手の中でフワフワの原毛が糸のようなものになったり、キュッと縮んで分厚いフェルトになったり。自分の目と手でその変化を感じたとき、ものすごく楽しかったこと嬉しかったこと。原毛は実家の押入れにあるはずだ。
◆羊をめぐる衣食住、文化や宗教の歴史、学術的調査。さらに本出さんの生きる姿勢がぐいぐい伝わってくる深くて濃いお話だった。羊についてこんなに考えたことはなかった。専門用語が多かったが、本出さんのやわらかい語り口に助けられ、理解することができた。たくさん学んで満ち足りた気持ち。不思議な幸福感に包まれる。本出さんに導かれて、いつのまにか「羊をめぐる暮らしと世界」のことを考えていた。[中畑朋子]
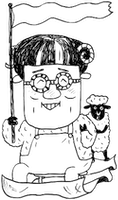
イラスト 長野亮之介
■まさか羊のおばちゃんの私にお声がかかるとは思ってもいませんでした。40年前から「青い地球一周河川行」の報告書に胸をときめかせ、モンゴル遊牧民の映画『プージェー』に衝撃を受け、一緒に旅する気分で『グレートジャーニー』にはまり、『西蔵漂泊』チベット潜入の登場人物や著者江本様に畏敬の念を抱き、綺羅星を見るように地平線会議の活動を遠くから見てきた私にとって、その星々が集まる会でまさか話をさせていただくなんて!
◆それでは自己紹介から。京都で原毛屋(ウールクラッサー・羊毛鑑定人)と出版社をしています、といっても一人です。原毛屋を始めたころ、父に「最近何をやってるんや?」と聞かれて、「手紡ぎ用の原毛を輸入して、趣味の染織しているスピナーに売ってる」と言うと、「…それどんな麦や?」と聞かれました。父だけでなく、そもそも誰にも理解できなかったと思います。毎回説明するのがめんどうで「SPINNUTS(スピナッツ・紡ぎに夢中)」という雑誌を始めました。それが出版社を始めるきっかけです。
◆そもそも糸紡ぎ、染織は女性の手芸、趣味ですから、認知されない=視界に入らない存在・ジャンルだと思います。「旦那さんのお金で、結構な趣味やねえ」というしらじらした視線をずっと感じています。でもほんの何百年、いえ地域によっては人間の衣食住を支える大切な手技であったはずです。
◆近年LGBTという言葉を聞くようになりましたが、差別されるステージにも上がっていないのが「手芸する女性」。経済社会では存在すら見えていないジャンルではないでしょうか。そんな私は2月21日当日、羊をめぐる衣食住——その世界と日本のことを偉そうに話しました。かなり恥ずかしかったです。でも今回何が一番言いたかったかと申しますと、その見えていない世界の中にこそ、大切なものがあるということが言いたかった。言わずにおれないこの気持ちを、どう伝えようか……。
◆現代の私たちの日常生活は、お金で衣服も食べ物も手に入れています。自分で作らなくても出来上がったセーターを着る=消費するだけですが、もともと人類は羊を育て、羊の世話をして、羊の毛刈りをして、毛を洗って、染めて、糸を紡いで、編んだり織ったり縫製して服にして、そしてようやく着ることができていたはずです。そういうことを知らずにすっ飛んで、現代はただただかっこいいという理由だけで、流行のファッションを追いかけて消費していることに、もやもやとしています。原毛屋になると決心した理由は「糸を紡ぐこと」は世界共通語だと思ったからでもあります。
◆しかし現実のウール業界は「ウールはチクチクする」という消費者のニーズにこたえ、細番手のメリノ羊やカシミヤばかり増やし、化学繊維の後追いをしています。一方太番手の羊毛の消費は少なくなり、ひいては在来種だけでなく主要品種でさえ維持が難しくなっています。羊の毛・ウールにしかできないことはあるのです。そして羊の恵みである肉と羊毛を消費し続けない限り、羊の品種を維持し、羊を生かし続けることはできないのです。
◆羊の家畜化は1万年前といわれています。羊はその肉と乳と毛から人の暮らしを支えてきました。羊は家畜です。家畜は英語でLivestockと言います。すなわち生きている在庫。人は羊さえ傍にいてくれたら生きていけると思ったでしょう。リアルからAIへ、世の中の価値観が大きく変わろうとしている現代、あえて経済という視界の外にある世界——羊と羊毛——を無駄なく使う取り組みの中に、持続可能な道が見えてくるのではないかと思っています。
◆最後に今回この機会をいただけましたこと幸甚でした。長野様のど真ん中を射抜く似顔絵とコメント。本所様の当日だけでない細やかなサポート。丸山様の丁寧な報告動画。なにより会の運営から通信発行と……皆様一丸となっての協力体制に驚きました。お一人お一人がプロの実力と惜しまぬ労力でこの会が成立し、かつ46年毎月続けられていることは驚愕です! まずは皆様へ心よりの御礼と、その一コマに登場できた幸せをお伝えしたいと思います。ありがとうございました。[本出ますみ]
|
|
|