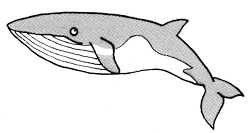
■「肩書をどうしようか迷うほど多彩な活動をされてきた方です」と紹介された白石ユリ子さん。とりあえずの肩書は、「ウーマンズフォーラム魚(WFF)」代表、「NPO海のくに・日本」理事長、「日本生活文化交流協会」創設者(会長)だが、いま力を入れているのは、後述する西アフリカでの活動だ。
◆白石ユリ子さんは、昭和8年12月に北海道で生れた。小6で終戦を迎え、思春期は混乱のなかだった。大学受験で上京するときは、旅館に泊めてもらうためにコメを背負って汽車に乗った。空襲がなかった北海道と比べ東京は酷かった。「新宿の三越や伊勢丹のあたりはグチャグチャ。西口は普通の人は行っちゃいけない『カスバ』です。だから、アフリカで仕事してても何ら気になりません。終戦時の日本の方がよっぽどひどかった」。
◆大学に入ると2年で学生結婚、すぐ子どもができた。夫は売れない画家で、卒業後、白石さんは4畳半で内職の日々となる。サラダ材料のジャガイモをふかし、洋服にボタンを縫い付け、デパートに卸す和菓子を作ってと多様な仕事を経験、「『内職の女王』と言われ、何でもトップでした」。
◆内職暮しが10年続いたころ、新聞広告で「主婦と生活社」の編集者募集を見て応募したら「明るい笑顔がよい」と採用に。世は五輪景気で出版の黄金時代、家計簿付き婦人雑誌が400万部も売れた。昭和43年前期のベストセラーは白石さん編集の手芸の本で、これで会社はビルが建ったと噂された。給料は破格で「少しお金持ちになった」そうだ。
◆「日本のために」本を出したいとの思いで、日本の伝統文化、生活文化を中心に企画をたてた。着物編集のセクションを作り、最後は着物辞典を出し「やりたいことは全部やって」1986年に退職。出版社にいたときにやり残した漁業を手掛けようと、日本の浜を行脚しはじめ、これまで3400か所を回った。全国を巡るうち白石さんは危機感を募らせていく。日本は世界で6番目に広い海に囲まれ、黒潮と親潮に恵まれて豊富な魚がいるのに、漁業も魚食文化も急激に衰退の一途をたどっている。海の国ニッポンはこれでいいのか!と「一人で腹を立て」、93年にWFFを立ち上げた。「『お国』がやらないんだったら私が」の心意気である。設立趣旨は「漁業者女性と消費者が一緒になって日本の食の未来を考える場をつくろう」。
◆白石さんと一心同体で活動をともにするのが、地平線会議ではおなじみの佐藤安紀子さん。97年12月の報告会で、「ニッポンの遠い海」と題してWFFでの活動を語っている。佐藤さんが白石さんを知ったのは出版社時代で、部下として働いていた。「とにかく、すごい上司でした。仕事にはとても厳しいけれど、何をしても判断が早いし、手早い」(佐藤さん)。
◆WFFは大車輪で動き出した。海から食卓にいたる関係者が一堂に会する「WFF全国シンポジウム」で政府に提言を行う一方、食卓の魚離れを食い止めようと、日本中の漁村と東京の消費者を結ぶ「浜のかあさんと語ろう会」を始める。2000年からはとくに子どもたちへの教育活動を強めていった。戦後急激に食文化が変わり、お母さんたちは出刃包丁を持たず一匹買いをしないから、子どもが魚の姿を見ない。「子どもが、魚を切り身の絵で描くというのはウソじゃないですからね」と白石さん。
◆小学校を訪ねては授業をさせてほしいと頼み、これまで東京の区立小1400校のうち800校で授業を行ってきた。「浜の母さん」の授業では、浜で獲れたばかりの新鮮な魚を、漁師の妻たちと生徒が一緒に料理しながら食べる。すると「浜に行ってみたい」との声があがり、漁村にホームステイする「海彦クラブ」を開始。さらに、離島を訪れて暮らしや環境、歴史を学ぶ「われは海の子」も発足。「やりたいことが出てくると、名前を変えてドンドン進めます」(白石さん)。次々にアイディアを形にしていった。
◆「お国」の惨状を救おうと、政治家や省庁にもしばしば政策提言をしてきたが、白石さんの憂国をよそに、現状は悪化の一途をたどっている。100万人いた漁師が今は13万人で高齢者ばかり。漁獲量は80年代の4分の1の300万トンに落ち込んでいる。水産物の輸入額は1兆8000億円(コロナ禍前)で輸出の3000億円と差し引き1兆5000億円の赤字。外に出て行くこのお金をなぜ日本の漁業の振興に使わないのか。「漁業を応援して魚を取ればいいと思うんだけど、このことがこの国にはどうしてもわからないようです。理由がわかりません」。ほとほと呆れたという表情で白石さんは言う。
◆WFFの活動が海外に広がるきっかけはクジラだった。白石さんの故郷、北海道の網走には捕鯨基地があってなじみがあり、戦後は毎日のように鯨を食べてきた。鯨肉は栄養にすぐれ、日本には1万年前からの豊かな鯨食文化がある。これを伝えなければと、白石さんは子どもたちに鯨を食べる機会をもうけ、絵本『クジラから世界がみえる』(06年)を作った。
◆1982年、IWC(国際捕鯨委員会)は商業捕鯨モラトリアムを可決、日本は調査捕鯨を行う時代に入っていた。商業捕鯨ができないのはおかしいと、白石さんはIWCに乗り込み、93年の京都会合から2018年のブラジル会合まで25年間、IWCの場で反捕鯨勢力と闘うことになる。IWC会合には多くの反捕鯨団体が押し寄せ、活発なキャンペーンを繰り広げるが、日本政府は何もしない。そこで日本から唯一参加のNGO、WFFが孤軍奮闘、政府に代わって表に立ち発信し続けた。
◆海の食料生産はサステナブルであり、漁業も捕鯨も日本の食料安全保障に必要不可欠なものだと白石さんは信じている。だから日本政府に頼まれなくても、手弁当で押しかけ応援しているのだ。
◆白石さんがIWCで重視したのは西アフリカ諸国。粘り強く日本の漁業、捕鯨についての立場を理解してもらい、多くの国が日本を支持し続けた。だが19年、日本はIWCを脱退、EEZ内に限定して大型鯨類の商業捕鯨を行っている。
◆鯨の話をしていた白石さん、ふと思いついて、「この会場のみなさんにおいしい鯨をごちそうしましょう」と言い出した。すぐに江本さんと握手し、「10月に、約束よ」で決まり。さすが、決断がはやい。
◆鯨がご縁で、白石さんはさらに遠くへと活動の場を広げる。IWCで懇意になった西アフリカ沿岸諸国から頼まれ、11年、漁村の女性のためのワークショップをはじめた。20年からはコートジボワールに通い、水産物を有効利用して、貧困にあえぐ漁村の女性たちの自立を支援するプロジェクトの指導に当たっている。
◆お金もお店もない女性たちは、魚を「借りて」路上に並べて売り、売り上げから借りた分を返して子どもを食べさせる、まさにその日暮らし。問題は、電気がなく魚の保存ができない、まだ食べられる部分が捨てられフードロスが多い、未加工で売るため売値が低いこと。白石さんは、日本伝統の魚のすり身に目をつけた。すり身は昔から、浜の母さんたちが、残った魚を無駄にせず、つみれやさつまあげにして利用してきた知恵の産物。煮沸した瓶に詰めれば3週間はもつ。さらに調理して付加価値をつければ、女性たちの収入源になる。
◆白石さんは、日本から大きなすり鉢を30個も現地に運び、すり身作りを実演。すり身でコロッケやハンバーグ、オムレツ、つみれ汁、たこ焼きなど様々な料理を作って試食会を開くと、その多彩さとおいしさに現地の人々は驚愕、「マダム・シライシは魔法使いだ」との声が上がったという。「すり身は、アフリカにとってはまったく新しい食べ方なんです。だから、とてもヒットしました」。白石さんのアイディアが現地にぴったりはまった。
◆すり身の研修プロジェクトは、50人が1週間ですり身づくりからすり身料理のマーケティングまでを実習する。ただ、事情は日本と違い過ぎた。まず、受講生の女性たちは交通費がないうえ、商売を休むとその日の食にも困るので、急遽日当を払うことに。識字率が1割と低く、名前も書けないので、朝8時から9時に無料で識字教室を開いた。また子どもを何人も連れてくるので、託児所を作り子どもにも食事を出すよう手配した。こうした出費はいつも白石さんの持ち出しになる。大変そうだが、白石さんは苦にならないらしい。「いろんなことが起きてるけど、全部計算済みだから。乗り越えるだけですよ」。
◆最後の勉強はマーケティング。まず5人のグループで、字の書ける人は字を、絵の描ける人は絵をと協力してポスターを作る。自分たちで作ったすり身のハンバーグやコロッケを持って街頭に出る。ポスターを見せ、魚は健康によいなどと説明しながらセールスするとすぐに完売、最後はいつも笑顔で喜び合うという。
◆研修の圧巻は修了式。たった1週間の授業なのだが立派な修了証書を手渡す。学校に行ったことも、社会に評価されたこともなかった女性たちは、修了証書を手に「生きててよかった」とうれし涙にくれる。修了生に抱きつかれる白石さんも、もらい泣きしてしまう。ある女性は「自分を誇れる証明書をもらったのは初めて。神棚に飾って一生の宝物にします。ママ(白石さんのこと)ありがとう」と感謝の気持ちを書いた。「こういうものを(生徒の)手元に置いてあげることでプロジェクトが続いていく」と白石さん。ママは女性たちの心をしっかりつかんでいる。
◆2021年に20人のリーダー研修から始まり、去年までで研修生は500人を超えた。経験を積んだ10人は、新人を教えられるまでになった。日本の外務省の支援で調理室や託児所のある「すり身センター」、「すり身加工場」が建設され、プロジェクトは国家的に注目される存在になってきた。昨年4月にはコートジボワール大統領から白石さんに農事功労勲章が授与されている。“SURIMI”という言葉が現地に定着しはじめ、社会が変化する兆しが見える。
◆白石さんは、年間100日前後はコートジボワールに滞在。この8月6日、11回目の現地訪問に出発した。今回は9月下旬まで滞在予定で、新しい施設、「女性と子どもの館(識字教育センター)」の開所式にも立ち会う。「これから女性たちのすり身レストランも開きたいし、やりたいことがいっぱいあるの。あと10年はがんばらなきゃ」。御年90歳のママの熱意とエネルギーは尽きない。
◆コートジボワールでの活動はすばらしいし応援したい。ただ、編集者時代から「日本のため」になりたいとの熱い思いで走ってきた白石さんが、いまなぜアフリカなのか。白石さんは現地から「受け取るものは彼女たちの成長ですよ。教えたことがみんな身について、それを利用して、もう嬉々としてやってるの。これ以上の喜びはありませんよ」という。佐藤さんになぜアフリカなのかを尋ねると「やりがいですね。現地がどんどん動いていくんですから」とのこと。
◆一方、「日本は、水産分野に限っては30年間、まったく動かなかった。WFFが別の視点から意見を言えば、聞かない、悪口を言われる、という世界です。漁業人口減、漁獲量減、子どもも大人も魚を食べなくなった。危機だからこそ果敢に挑戦すべきなのに、なかなか動こうとしません」と佐藤さんは残念そうに言う。
◆白石さんがうねりを起して作り変えていくアフリカの漁村の向こうに、この類まれな愛国者の片思いを受け止められない私たちの島国がかすんでいく。日本の凋落が止まない理由が見えてきた。[高世仁]
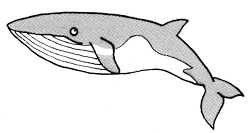
イラスト ねこ
■地平線会議の報告会へ出かけ旧知の方々、昔からおつきあいのあった皆さまにお目にかかったようで、まったく違和感なくお話をさせていただき本当に幸せでした。私のやってきたことは、私なりの冒険旅行です。すべて自分自身で考えて行動をするうちに、体中から熱い血が流れだして、さらに前へ進まずにはいられない。無謀といわれても、興味を持ったところから逃れられない、飛び込んでいかねばならないと突き進んでしまうのが私の生き方。座右の銘は「挑戦は人生の一部」であり、挑戦こそ人生だと信じて生きてきました。
◆思い返せば、子どものときから学生時代、今にいたるまでずっと同じ、ひとつの流れです。流れが緩やかなときもあれば急激なときもありますが、私の人生にはずっと「挑戦しなければ」という熱情が湧いています。戦前、戦後という日本の激動の時代に生を受け、挑戦せずにはいられない人やものごとに数多く出会えたことが、私に人生の味わいを教えてくれました。今日、8月10日はアフリカで夏のすり身ワークショップを始めるところ。3日前、アビジャンの空港に降り立ったとき、ああ帰ってきたんだと実感する自分がいて、そのことがしみじみとうれしく感じられました。
◆お話を聞いてくださったお一人、お一人にまたお会いしたいと「クジラを食べる会」を自分から提案してしまいました。皆さまにもう一度、お会いしたいと思っています。本当に楽しい一日で、今季一番の喜びでした。ありがとうございました。[白石ユリ子]
■「知らなかった、では済まされない」。30年前、白石ユリ子さんは日本の漁業の現状に対して、これは自分がやるべきテーマだと思い立ち、どうしたら皆を巻き込めるかと考えたとき、このフレーズを創出しました。世間が気づいていないことをいかに広く伝えるか。日本漁業の問題は、漁業界だけではなく消費者ひとりひとりにとっても食卓の問題、大切な食料の問題なのだ、という空気感を広く共有できないと解決できない、多く人に自分に関わることだと気づいてもらおうと考えた言葉でした。白石さんはいつも出会った問題、課題を世の中へ伝えるキャッチコピーで持てる能力全開にして取り組みます。そして「切り口を女性にしよう」。漁業界は当時、漁村も流通も行政も研究者もすべて男社会で、食卓側の顔がまったく見えなかったことから、漁村と首都圏の女性たちに声をかけてシンポジウムを開催。タイトルは「ウーマンズフォーラム魚」。それがそのまま、活動名になりました。シンポジウムのテーマは「お魚から地球が見える」。
◆この活動のスタート時は、本当にすさまじいものでした。漁業界という、それまでまったく関わりのなかった業界に対して、当初はジャーナリストとして切り込み、既存の媒体に書き続けたものの、書くだけではまったく何も変わらない。ならば自分でと「浜のかあさんと語ろう会」を開催したり情報誌を発行。漁業界を良くしたい、流通を変えたい、後継者が育つ漁村にしたい、末永く美味しい魚を食べ続けたい、海の環境を守りたいと考える人たちのネットワーク化をはかるために日本中を歩く歩く歩く。なんといっても日本の漁村は全国に6000か所あり多種多様。5キロ離れていれば魚の食べ方が違うというくらい、多様な漁業と魚食文化をもつ日本列島。それが維持され、日本中がその価値を理解することを願いながら、白石さんは漁業界にのめりこんでいきました。そして、漁業界だけでは解決できない、これは国民運動にしなければと考えて「ウーマンズフォーラム魚」、こどものころからの海と魚教育こそ国民が漁業を大切に考える原点となる、海が日本の将来を決めるとの信念から「NPO海のくに・日本」という活動母体をつくりました。
◆海は世界とつながっていることから、活動は世界へと広がり、いまはアフリカで年の半分近くを過ごしていますが、白石さんの原点は同じ、漁業と魚食文化をいかに良くするか、にあります。それは、魚という食料が人間にとって栄養面でも精神面でも大切であるという信念からですが、もう一つ、その土地、その社会における「海の人類学」がものすごく興味深いことも、ここまで走ってきた大きな動機になっていると思います。白石さんは、漁業界への挑戦をとおして、自ら気づかないうちに「海の人類学者」となり、魚をとおしてみえてきた社会の奥深さ、不思議さ、楽しさを記録したい、広く伝えたいと歩きつづけています。白石さんの地平線報告会を聞いて、ずっと側で見てきた私自身、学生時代に学んだ人類学を実地に体験してきた30年だったんだ、とあらためて思い至る3時間でした。[佐藤安紀子]
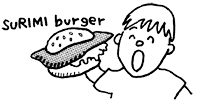

|
|
|