
■人類最古のメソポタミア文明を生んだ地。エデンの園があったとされるこの地は、ティグリス、ユーフラテスの二つの大河の大部分を従え中東アジアの要衝として栄えてきた。といえば聞こえはいいが多くの邦人にとってイラクから連想されるものは戦争、テロ、イスラム原理主義、石油……。こんなところが大半だろう。外務省渡航安全ホームページは赤く染め上げられたままだ。この国はトルコ、サウジアラビア、イランといった大国に挟まれている上に、イスラム教シーア派、スンニ派の主要な境界線でもある。国内の政情不安も相まって、アラブ世界の中で最もカオスな国の一つであるといえよう。そんなイラクには「アフワール」というさらなるカオス地帯が存在した。この二重のカオスにノンフィクション作家の高野秀行氏と地平線会議同人である山田高司氏は2018年以来3度にわたり調査に挑んだ。今回の報告会ではそんなカオスを切り開くカギとなった舟と布、この二つに絞ってイラク・アフワールの調査についてご報告いただいた。
◆誰もいかないところへ行き、誰もやったことのないことをし、それを面白おかしく書く。高野さんはそれをモットーにアマゾン、ミャンマー、ソマリアなどの辺境地帯に挑んできた。そんな高野さんの次なる興味を誘ったのがイラク・アフワールだった。アフワールというのはチグリス川とユーフラテス川合流点付近に存在するらしい大規模な湿地のことだ。そこでは現在もなお水の民(マアダン)が水牛を飼い、舟を使った生活を営んでいるという。そして、古来より湿地帯は戦争に負けたものや迫害されたマイノリティ、アウトローたちの逃げ場所であった。湿地では馬や戦車を使えず大軍を使って攻め込むことができないからだ。「水滸伝」の梁山泊さながら、と高野さんは表現している。このような湿地の歴史的背景もさることながら、自然地理学的にもイラクのような高温乾燥地帯に形成される湿地というのは世界でも他に例を見ない。「ここだ!」
しかし、である。フセイン政権崩壊以降、イラクを取り巻く政治的・治安的状況はあまりに悪い。ましてアフワールは、東京都の面積を上回るほど広大だが中に入ると村も集落もなく道もない。さらに葦が高く生い茂り視界を奪う。「何を目指したらよいのかわからない、このとりとめのなさに苦しめられた」と高野さんは振り返る。まさに二重のカオスである。どのように旅をすればいいのか? このカオスに切り込む一つのカギとなるのが船だった。
◆「いい舟や、ええ舟大工がおるんやなあ」。国内外多くの川を旅してきた山田高司氏(以下、『イラク水滸伝』に倣い山田隊長と表現させていただく)にアフワールの映像を見せた感想であった。舟大工という着眼点は高野氏の頭にはなかったが、かつて山田隊長の郷里・四万十川には川漁師のための舟を作る大工がいたそうだ。「軽トラは田舎のパスポート」という。地方の農林業従事者の相棒である軽トラならば特別警戒されずに現地に溶け込むことができる。アフワールでも軽トラに相当するもの=舟を使えば移動手段になるとともに現地民に馴染めるのではないか? 「まず目標ができたことが大事」と高野さんは言うが、渡りに舟ともいうべき山田隊長のヒントにより、舟づくりという目標を得てアフワールの調査に挑むこととなる。
◆初回のイラク訪問、アフワールに住むマンダ教徒の存在を知る。伝統的に職人業を生業としており舟大工もその一つだった。彼らを探せばよいのではないか? 最初のとっかかりを見つけることができた。早速舟大工の一人だ、という人物に当たり作業を見せてもらったが、なんとも雑すぎる作業の様子だったので別の人に当たることに。そこで湿地帯の中心地、「梁山泊」ともいえるチバーイーシュに向かうこととなった(湿地帯は東部・中部・南部の大きく3つに区分されチバーイーシュは中部に属する)。ここで舟大工を探すとともに現地のマアダンの生活ぶりを観察することができた。前述のようにマアダンは水牛を飼い生計を立てている。湿地で彼らは葦をつぶして浮島(チバーシェ)をつくり、葦で家を建て、葦を燃料として使い、葦を水牛の飼料として与え、まさにSDGsそのものといえる生活を営んでいた。一方で気づいたこともある。湿原の中でもチバーイーシュのような町にいる人は冷暖房完備の石造りの家でたいして日本人と変わらない生活を送っているということだ。そのすぐそばで水牛を飼って生活している人がいる……。このような湿地民(マアダン)の曖昧性はカオスそのもので一行を困惑させることになる。
◆さて、舟造りである。作ろうとしている舟は現地ではタラーデと呼ばれている。船首が三日月形にそりあがっているのが特徴で外側にはギール(石油由来の成分で日本でいうアスファルトのようなもの)が塗り付けられ隙間をカバーしている。現地では各氏族の長、シェイフ(族長)が乗る舟ということになっている(イラクは伝統的に氏族社会であるためシェイフは各地で多数見られる存在だ)。軽トラを作るつもりがリムジンになっていた、と高野さんは苦笑いする。このタラーデは五千年前の遺跡から出てきた舟の模型ともそっくりというかほとんど同じであり、それほど昔から外観を変えることなく引き継がれてきたという事実に驚嘆させられた。
◆今回お願いした大工は職人の町フワイルに住む舟大工さんでマンダ教徒ではなかったそう。マンダ教徒との婚姻をきっかけに舟大工の技術を学んだという極めて珍しいケースだという。今ではイラン製のモーターボートの流入もあって作り手はだいぶ減少しているようで、多くは家具屋や建具屋さんとして生計を立てているようだ(ちなみに手漕ぎ舟自体も減少しているそうだ)。タラーデの作製を交渉してみると驚いたことに2週間でできるという。900ドルで契約成立、かくして彼らのもとで作業が始まった。以下にその神をも恐れぬ舟造りの過程を記していく。
◆(1)材料 大きく分けて3種類の材木を用いている。1つ目はチャムと呼ばれるロシア産のエゾマツで舟底の縦板に使用している。2つ目は舳先と船尾に使うマレーシア産のジャーウィ(フタバガキ科)、ラワン材ともいい、これはチャムより固い。3つ目はシドレ、和名はキリストノイバラでナツメの一種だがこれはキリストがかぶせられた冠に使われたといわれる。乾燥に強く非常食として多くの家庭の庭で見られ、非常に丈夫で舟の肋骨に用いていた。これらの材木を電ノコで切断していく。ちなみに全工程を通して使った道具はわずか3種類(ノコ、カナヅチ、手斧)であり大工の祖父を持つ山田隊長を驚愕、というか困惑させた。「こんなものでできるのか??」
◆(2)船底の作成 早速木綿糸を地面に打ち込んだ釘にひっかけて張り巡らせて、楕円形を作っていく。これが船底の形でこの上に横板と縦板を置きはみ出した部分をノコで切り落としていく。「家を作ってるみたいだ」と高野さん。設計図やら図面といったものが存在しない。その辺に落ちている木版と比較しながらうーん、まあこんなもんかな、という具合に切断し、張り付けていく。釘の位置もざっくりメジャーで測るだけ。アーティストのようだが実際に測ってみるとだいぶ左右でずれていたりする。これで船底の基盤は完成、買い出し含めて4時間未満。「暑いから」といってこの日は作業終了だ。お昼は「鯉の円盤焼き」に舌鼓を打った。
◆(3)船底をカーブさせる 船底部を地面に固定し舳先と船尾を持ち上げ板で固定する。舳先は地面から50cmほどの高さだ。美しい三日月形の基板はこのような荒業で形成されていた。このアーティストたちはとにかくよくしゃべり、作業中でも口を閉じない。その相手をするのは雇った側となるため必然的に工場に居続けることとなった……。というか居ないと作業をやってくれる気がしないそうだ(笑)。
◆(4)側面部の形成 肋骨となる板を打ち付け、その外側に適当に側板を張り付けていく。とにかく適当に切って張り付ける。余っていれば切る。足りなければ付け足す。ギールを後で塗るからか隙間も気にしていないようだ。「ある意味合理的」と山田隊長は言う。働き方も非常に適当だ。「棟梁」は詩の談議にご執心であったり、「主任」はほとんど参加せずスマホをやたらいじっていたり、かと思えば狂ったように作業を開始したり(ただし1時間で飽きる)、親族と思しき人間がふらっとやってきて作業を手伝ったり……。各人がしたいときにしたい分だけ作業を進めるスタイルだ。1日の労働時間は4時間が最長だったという。ユーフラテスより続く古の文化の背景には働き方改革(笑)の比ではない超絶ホワイト労働環境があった。
◆(5)先端部の取り付け タラーデがタラーデたる所以である反り返った舳先部を形成するため、水に浸けてしならせておいたヤシの木を炙り、相変わらず適当に取り付けていく。彼らのこの作業スタイルを高野さんは「ブリコラージュ的」と表現している。「有り合わせの材料を使って自分で物を作ること」の意味で要するにその場しのぎの作業ということだ。タラーデのような舟づくりが五千年も引き継がれてきた背景にはブリコラージュによりわずか2週間で作れるよう簡易化された製造過程もあるのかもしれない。驚いたことに山田隊長は「もう自分でも作れる」とのこと!
◆(6)ギールを塗る いよいよ総仕上げだ。ギールは石油由来の生成物でアスファルトに相当するものだ。産油国イラクではその辺に転がっているらしいが今回は中部のヒートから取り寄せた良質のものを使ったそうだ。このギールを熱して砂を混ぜると餅状になり接着剤のようになる。これをうどんを練る棒のようなもので船体に塗り付けていく。この作業は煮えたぎるギールが熱すぎるため夜に行う。にぎやかな作業風景は何とも牧歌的で「南部の唄」の劇中のようだ。この上に泥を塗ってコーティングして遂に完成だ。風格のある姿がライトの中に浮かび上がった。
◆ここから舟旅までが長かった。隊長の病気、コロナ禍、治安の悪化でなかなかイラクへ行くことは叶わなかった。空白の2年を経て2022年、舟は廃墟と化したゲストハウスの中で泥に埋もれていた。何とか使えそうだがこの巨大な舟を川まで運ばねばならない。ましてゲストハウスの周囲は柵や土壁で覆われ文字通り障壁だらけだ。どうする?
◆もちろん、ブリコラージュだ。男たちは車を降りると脇目も振らずに舟に突進する。そして持ち上げようとする。重い。じゃあコロを使おう、コロはどうする? ペットボトルに水を入れたらどうだろうか、おいおいそこじゃあないぞ、さてどうやってこの柵を突破する? ……万事がそんな調子。みんな至極真剣な顔でやっているのがまた面白い。日本人からすれば違和感というか苛立ちを感じるのは当然かもしれない。まずは考えろよ、はじめから重機でも用意すればいいんだよ、動物じゃないんだから、と。その通りではある。しかしまずはやる、そして疑問と挫折から次の対応策を考える。この一大喜劇に人類の成長過程を見た気がした。ここイラクにはメソポタミアの発展の原点が今も残っているのだ。
◆高野さんが言う一大喜劇を経て、遂に舟は進水。山田隊長はこのまま沈むのではないかと思ったそう(笑)。男たちはお祭り騒ぎだ。歌い、踊り狂う。全然関係ないおっさんも一緒に踊る。楽しさとか喜びってこういうことだよな、とこの情景を見てなんとなく思った。アラブの民族服を纏い、舟に乗っている映像を見せてもらった。なるほど軽トラというにはほど遠い、リムジン、ひいては重さと扱いやすさを犠牲にして走るアメリカンバイクのような雄々しさをそこに見た。ギールをたっぷり塗って重量化しているため船底がひっかかれば何の手立てもなく立ち往生するだけだ。立派な先端部はあくまでシンボルで実用性は全くないという。山田隊長がいうことには「かっこいいから、五千年も続いたのではないか」。単純にして明解すぎる理由だが不思議に納得できる。人類の美的センスは変わらないのだ。かっこいいものはかっこいい!
◆アフワールを解明するためのもう一つのカギとなったのが布だ。一般にマーシュアラブ布と表現され、イラク・アフワール由来とされるこの布を(マーシュアラブとは英語で湿地のアラブ人のこと)コロナの空白期間に高野さんはたまたまインターネット上で目にしたとのこと。今回の報告会では特別に高野さんの所有物を持参いただき、じっくりと見物することができた(ちなみにこの布は長さ2〜3m、幅1〜1.5mとかなり巨大だ。高野さん、よくぞお持ちいただきました!)。
◆近くで見るとなるほど不思議な布だ。自由奔放なデザインが布の全面に緻密に描かれている。動植物や人間、建物といったかなり具象的、写実的なデザインもあれば「ナスカの地上絵のような」抽象的なデザインもある。さらにはアフワールには存在しない「人形」「バラ」「リンゴ」のようなものも描かれているのが特徴だという。イラク・アフワールのカオスを象徴しているかのように感じられた。
◆「ICチップのように緻密で作り手の脳内がそのまま表現されているよう」と高野さんはいう。技法自体も特殊らしく「二飛び二飛びの綾織り」で織られた毛織物の上に上記のデザインがすべて刺繍で施されている。イラク由来のこの布はほかの地域のものとは全く異なる特性を持つようだ。
◆なにより、中東の市場に出回っていることからイスラム圏由来のはずなのに具象的なデザインも多くイスラムの気配がない。さらに言えばアフワールの気配もない。「自分が見てきたアフワールのイメージと違いすぎる」と高野さんをさらなるカオスへ導くこととなる。画家・山口晃氏によれば「グランドデザインがありつつもその場のノリで作っている」とのこと。ここでもブリコラージュである。そしてこの情報化社会にあってこの布に関する情報が驚くほど少ない。自分たちはアフワールの核心を何も見ていないのではないか? 本当にアフワールのものなのか? 果たして今もこの布は作られているのか? 舟造りと並行してマーシュアラブ布の謎に挑むこととなった。
◆2022年、布を持参しイラクへの調査に赴く。現地語ではアザールと呼ばれるということがやっと判明。ユーフラテス川沿いのホドルという町でいまでも布を作っているセルマさんという女性にインタビューした。彼女が布づくりのグループを束ね、ワークショップも主催しているという(ちなみに彼女の作る布は高野さんのものよりも粗っぽく材質も異なっており、あくまで販売用のものだった)。この布は新婚の娘のために母親が作るものであったというが、なんと彼女が布づくりを始める前の1950年ごろにはすでにこの習慣はなくなりつつあったという。持参した布をセルマさんに見せたところその古さと質の高さに驚かれた。70〜90年前にホドルで作られたものではないか、ということだった。
◆ブリコラージュの塊のように見えるこの布だが実は図案があるという。例えば割ったリンゴ、川の波、人形のデザインなど大本は共通するものがあるのだ。ただしそこからのサイズやデフォルメは自由。「自由奔放で個性的なのに調和がとれている」鍵はここにあったのだ。
◆調査の過程で重要な証言を聴く。「アザールはもともとマンダ教徒とユダヤ人が作っていて後からムスリムが学んだ」という。さらに各地を訪ねていくと、アザールが作られているエリアとかつて湿地帯が広がっていたエリアがかぶるということに気付いた(開発が進む以前、イラクには現在のアフワールよりさらに広大なエリアに湿地が広がっていた)。つまり、かつての湿地帯の文化がこの布に残っているというのだ。面白い。さらにはシュメール人の遺跡のエリアともかぶるという! アザール、謎が深い。
◆こうしてアフワールの核心に気付く。「アザールの作り手は広い意味での湿地民である」ということだ。アザールには湿地内部には存在しないものも描かれている。つまり、アザールは水牛を飼い湿原内部で移動生活を送る「狭い意味での湿地民」(=マアダン、マーシュアラブ)ではなく、陸地に定住し湿原の内部と外部を行き来する「広い意味での湿地民」の手により作り上げられたのではないかということだった。この広義の湿地民にはマンダ教徒やユダヤ人、アウトローらも含まれる。「湿地の二重構造」と高野氏は表現する。謎に包まれたアザールこそがアフワールの文化を見事に反映していたのだった。
◆アザールについてこれですべてがわかったわけではなく、できればもう少し調査したいが、非常に高いハードルがあるとも高野さんは言う。70年以上前にすたれた文化である上に、作り手の多くは女性でイラク国内では接触が困難だ(イスラムが厳格化された現在のイラクではイラクでは女性は基本的によその男と顔を合わせてはいけない)。イラクでは半ばタブー視されているため、ユダヤ人ともなればなおさら話を聞くことは困難である。しかし、このアザールの調査がカオスに包まれたアフワールを理解する上で重要な一歩となることは間違いないだろう。
◆子供のころからアラブ世界というのはなんとなく冒険心をそそられるような場所だった。アラビアンナイト、魔法、砂漠……。血が沸いて肉が躍る大冒険、その源流がこのティグリス・ユーフラテス川流域にあるような気がした。
◆今回の報告会と書籍の拝読を通じて、久々に眠っていた童心が蘇ったような気がした。舟に乗り、マーシュアラブを探しアラブ世界を駆け回る構図、なんだか「船乗りシンドバッドの冒険」みたいだ。とにかく心躍る報告会だった。
◆大人的な目線で見ると、こういった人文系の調査報告を聴くこと自体が新鮮だった。自分は理系出身だが研究手法ははっきりしていた。データを取り、それを解析し考察していくという構図は内容はどうあれ大体決まっているのだがこのイラク・アフワールの調査ではすべて曖昧な状態からのスタートだ。目標さえ定まらない二重のカオス。その中から舟と布というカギを見つけ出し、現地民に溶け込みアフワールを解き明かしていく調査手法は純粋にすごい、というほかない。なにより自分にとってさほど馴染みのなかったアラブ・イスラム世界の文化や歴史を知るきっかけになった。
◆イラクの治安からして民間人が普通に旅をするにはほど遠い状況という。その世界を旅してきた二人の報告会、アラビアンナイトの登場人物が本から出てきた、そんな感じがした。ああ、旅に出たい!![竹内祥太 25才]
■足かけ6年かけて取材したイラクの巨大湿地帯アフワール。これほどまでに難しい標的は自分の30年以上の辺境キャリアでも初めてだった。なにしろイラクという国がカオスで、その中の湿地帯もカオスという「カオスの二重構造」。しかも辺境でありつつ、古代メソポタミアという人類最初の文明が生まれた場所でもある。政治、宗教、民族、氏族、歴史、文化、自然環境など考えるべき要素があまりに多く、かつ複雑なので、自分でも一体何をやればいいのかしばしば(というか大半の時間)途方に暮れていた。そして嫌というほど自分の無力さ、無能さを突きつけられた。
◆結局、多くの人の力を借りるしかなかった。私にアラビア語イラク方言を教えてくれ、最初の取材で通訳も務めてくれたハイダル君、イラク水滸伝の「頭領」ことネイチャー・イラクのジャーシム宋江、そしてなによりも支えになってくれたのが山田高司氏(通称・山田隊長)である。
◆山田隊長とは二十数年来の付き合いであり、私の辺境ノンフィクション作家人生において、唯一「師匠」と呼ぶべき人物である。今回のイラク行きは最初から取材(旅)が難航しそうだとわかっていたし、隊長とは「いつか一緒に大河を舟で旅しましょう!」と誓った仲だったので、当時郷里の四万十市にいた隊長を無理に東京へ引っ張り出し、三度に及ぶ取材行に同行してもらった。
◆現地に行けば、動画撮影に始まり、イラスト、GPSでの位置確認、取材ルートの研究、動植物や木材の同定、現地の自然環境アセスメントなど、私にできないことをなんでもかんでも隊長に頼んだ。我ながら頼みすぎだと思ったが、なんでもやれてしまうのが隊長の凄さである。
◆目を瞠ったのはイラストの上手さ。水牛飼いの人々の暮らしや古代宗教マンダ教の儀式、葦の浮島の作り方、鯉の円盤焼きや水牛の乳のクリーム「ゲーマル」の作り方など、写真だけではわかりにくいものを見事に描いてくれた。また旅や取材で出会う人々の似顔絵を即興で描き、地元の人たちの人気を得ていた。
◆隊長は口数こそ少ないものの、これまでの経験の深さから貫禄が滲み出ている。私が何か意見を言ってもみんなは笑うだけなのに、隊長が同じことを言えば、神妙な顔で「うん、わかった」とうなずくのだった。説得力がちがうらしい。「シェイフ・ヤマダ」なる呼び名が定着したのも不思議はない。シェイフとは族長のことだ。
◆今回の報告会も私だけならお笑い演芸大会の域を出ないところを、隊長の話で一気に持続可能な地球を真剣に考える場に変わった。虎の威を借りるという言葉があるが、今回の私は終始「シェイフ・ヤマダ」の威を借りていた気がしてならない。私に付き合うのはとんでもなく骨が折れたと思うが、この場をお借りして隊長に心から御礼申し上げたい。[高野秀行]

イラスト 山田高司
■足掛け5年に及ぶアフワール行のうち、イラク滞在は3か月弱、タラーデ(族長舟)の漂流譚は、わずか2時間で終わった。ホメロスの本家「オデッセイア」漂流譚は、足掛け10年。それをなぞらえたジョイスの「ユリシーズ」は24時間の出来事。高野秀行文豪は、今回のタラーデ漂流譚、たった2時間弱の航行のための紆余曲折を400ページの一大叙事詩に仕上げた。評判はすこぶるよく重版だという。
◆「あんた、てーしたもんだよ」。2017年夏、高野が四万十に訪ねてきて約束したのは、「アフワールを現地舟で探検する」だった。家族の大反対で3回断ったが、諸葛孔明より一つ多い四顧の礼で家族は折れてくれた(はずだった)。結果、たった2時間の漂流でも、高野は新刊の表紙用タラーデのいい写真を撮れて大満足。かたや、私は「一方通行の少年期の探検から相互交流の壮年期の探検へ」(余談3)を課題としてきた。
◆何かをアフワールにお還ししないと旅は終われない。手元に「イラク水滸伝」のために描き溜めたイラストがある。そこにタラーデを描き込むと、「失われたタラーデの旅」が浮き上がってきた。これまでも、そこの自然がある限り持続する暮らしのワザとチエを「永遠の瞬間」としてスケッチし、それらを合成した「悠久の風景」を描いて紙芝居やポスターにして置き土産にしてきた。今、イラク水滸伝・タラーデの旅36景を描いている。ポストカードにして、イラクの湿地保全活動の資金源に役立ててもらうつもりだ。
◆余談1 川下り練習で、日本の地方都市に高野と行くと、まず本屋に行き、「ああ、よかった高野秀行の本がありました」と安心していたけれど、もう大丈夫でないかな。
◆余談2 拙文の表題、20世紀2大傑作小説「失われた時を求めて」と「ユリシーズ」の題名だけ表題に借り合成しました。トルストイやドストエフスキーの名作長編と同じく、長すぎて饒舌で、読書は途中敗退。
◆余談3 「一方通行の少年期の探検から、相互交流の壮年期の探検へ」。『探検と冒険』(全8巻、朝日新聞社、本多勝一編集)の中のたった1ページ、SF作家小松左京のコラムに、このような内容の文章が、あったと記憶している。コロンブス、マゼラン、ドレークの大航海時代から、南極、北極、エヴェレストまで、近代の探検は国家や商社をスポンサーとし、成果を片方へ持ち帰るだけだった。小松氏は、これを「少年期の探検」として、これからの探検のあり方を「相互交流の壮年期の探検」としていた。アーサー・C・クラークの「幼年期の終わり」が下敷きにあると思われる。今回の高野のイラク水滸伝は、現地の人たちと共同作業の「壮年期の探検」といえなくもない。[山田高司]
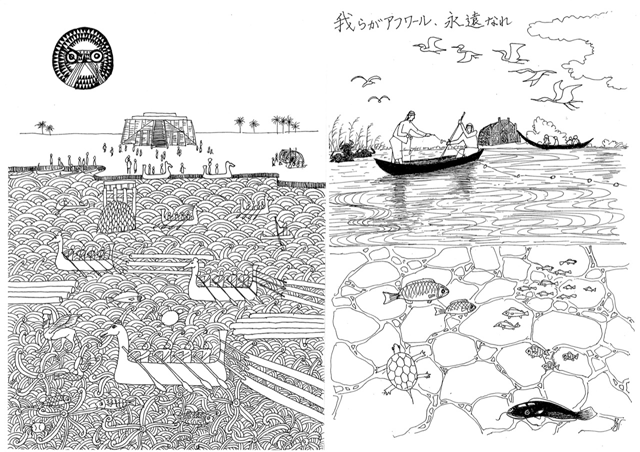
■先週末の報告会「アフワール漂泊譚」に参加させていただいた久保健一です。恥ずかしながら、地平線会議の報告会を聞いたのは初めてでしたが、江本さんとそのお仲間が長い時間をかけて築いてきた「ストック」の大きさを、スケールの大きな話の内容、裏方さんの運営の様子などからひしひしと感じることができました。
◆あらためて自己紹介をさせてください。岩手県岩手町生まれ。1991年に読売新聞に入社。ふり出しは金沢支局。国際部畑をあゆみ、2000〜2004年と2013〜2016年の2度にわたりカイロ支局。2008〜2011年にテヘラン支局。今年7月末、55才で読売を(定年)退職し、フリーライターになりました。
◆入社前後のころ、同期入社の仲間の間では、江本さんの「ゴルバン・ゴル計画」が大きな話題になっていて、「こんな壮大なプロジェクトにも参加できるのかな〜」と胸躍らせた記憶があります。また、国際部で内勤をしていた1990年代後半ころですが、外線からの江本さんの電話を受け、国際部の誰かに取り次いだことがありました。「話には聞いていたが、社外の事務所で仕事をしている記者が本当にいるんだ〜」とびっくりした記憶もあります。
◆時代は下り、数年前から、同郷(岩手県)の写真家・大村次郷さんが仕切っている「加藤九祚先生を囲む会」という集まりに参加しておりまして、その交わりの中で、江本さんが中心となったプロジェクト内容に関する書籍「チベットと日本の百年」を知って、読み、感銘を受けました。後半生を盛岡で過ごした西川一三や、私の父の故郷・岩手花巻ゆかりの多田等観のこともこの本で知りました。
◆地平線会議については、「囲む会」によく来られている丸山純さんや、岡村隆さんからも話をうかがい、今回は、知人でもある高野秀行さんが、私のフィールドでもあるイラクに関する新著に関連した報告会をするということを聞きつけ、おじゃますることにしました。
◆2021年3月3日付・朝日新聞夕刊の宮地ゆう記者の記事も改めて読み返してみましたが、地平線会議が続けてきた「日本人の冒険・探検体験の共有と記録」の意義の大きさを感じる次第です。
◇ ◇
◆山田高司さん、高野秀行さんの報告も、とても興味深く聞きました。僭越ながら、特に印象に残ったことについて感想を述べてみます。
◆【前半・舟のはなし】まず、舟(タラーデ)が「設計図に従って作るという我々の常識とは違う方法で作られている、という話に驚きました。高野さんが「ギール(アスファルト)を塗れば水漏れもないので、厳密に組み立てる必要はない。非常に荒っぽいがある意味、合理的」とコメントしていましたが、なるほどと思いました。確かに、イラクを含むアラブ圏でよく出くわす、アラブ人得意の「最後の帳尻合わせ」の一例なんだろうと感じました。事前の段取りを重視しすぎるきらいのある日本人には、学ぶべきものがあると思いました。
◆舟の設計図もなく、「作り方が言語化されていない」とも高野さんが言っていましたが、イスラムの聖典コーランに代表される口頭で伝えられるものが多かった社会を象徴していると思いました。それでも、「適当に調理しているように見えるが、食べてみるとおいしく出来上がるシェフのようだ」と表現していたように、時にハイレベルなものが生まれるのがアラブのすごいところです。
◆「湿地の民はおしゃべり」という話もありました。一般的にイラク人は、アラブ圏の中では「暗く、思索的」だと評されるのですが、マーシュ・アラブの民は、一般イラク人とはまた違って、明るい性格の人が多いのかな、とも思いました。質問すればよかったのですが、しそびれました。
◆【後半・布のはなし】高野さんが「イラク水滸伝」の中でも披露している「湿地民のイメージ図」に基づいて説明した、湿地帯「二重構成」仮説も知的関心を誘うものでした。現湿地帯にいるのは「狭義」の湿地民であり、「アザールの布を作っていた人々は、その外側にいた人たちだった、というものです。フセイン政権の弾圧対象だった湿地帯のイスラム教シーア派住民の中でも、水辺で暮らす「狭義」の湿地民は、「抵抗運動に加わるのではなく、もっと奥地に逃げてしまう人たち」(高野さん)であって、実際に抵抗するのは、「国家とのつながりを求める(外側の)湿地民たち」というのは、とても納得できる説だと思いました。
◆布作りの主な担い手が、「イラクにかつていたユダヤ人ではないか」というのも驚きました。1948年のイスラエル建国とその後のイラクの政治変動を契機に国を去っていったイラクのユダヤ人たちが残したものとして、今後注目されていく可能性もあるのではないでしょうか。高野さんも意欲を示していましたが、今後のイスラエルなどでの調査を心待ちにしたいと思います。[中東コラムニスト/カフェバグダッド 久保健一]
|
|
|